- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2413 芸術・芸能・映画 『教養として知っておきたい映画の世界』 コトブキツカサ著(日本実業出版社)
2025.08.17
『教養として知っておきたい映画の世界』コトブキツカサ著(日本実業出版社)を読みました。著者は映画パーソナリティ・エンタメ評論家。1973年11月16日生まれ。静岡県富士宮市出身。1993年、和光大学・芸術学科に進学するため上京。学業と並行して芸能事務所に所属し タレント活動を始める。2010年から映画を紹介する仕事を本格的に始め、テレビ、ラジオの出演や雑誌連載、国内外の映画祭の司会をはじめとする数々のメディアで活躍するほか、日本工学院にて「映画概論」の講師も経験。「映画パーソナリティ」として確固たる実績をあげています。年間映画鑑賞数は約500本。国内外の俳優にインタビューした人数は累計1000人以上。毎年、アカデミー賞の取材を現地ハリウッドにて行っているそうです。心理学を応用して編み出した「映画心理分析」(好きな映画でその人の心理を分析)や「映画処方箋」(その人の悩み事に合った映画を紹介)を行う「映画心理カウンセラー」の肩書きでも活動。
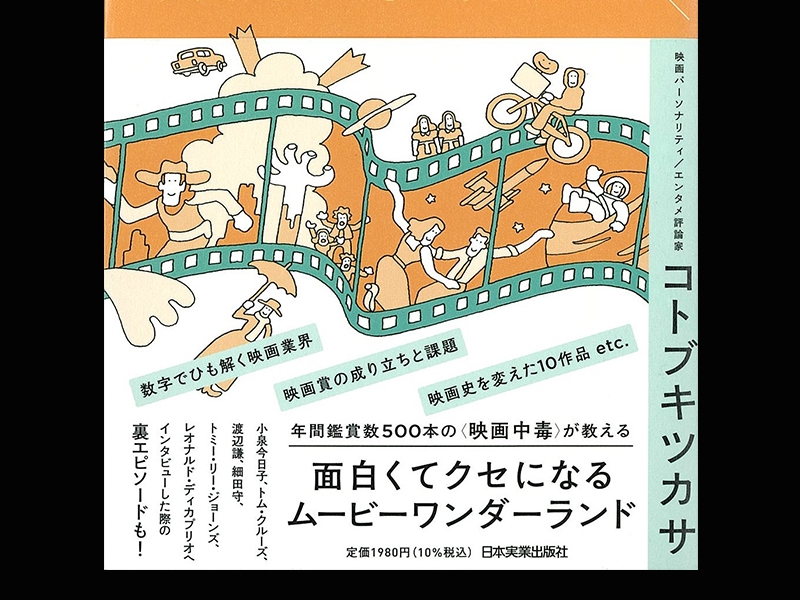 本書の帯
本書の帯
本書の帯には西部劇、ミュージカル、SFなどの映画フィルムのイラストとともに、「数字でひも解く映画業界」「映画賞の成り立ちと課題」「映画史を変えた10作品etc.」「年間鑑賞数500本の〈映画中毒〉が教える」「面白くてクセになるムービーワンダーランド」「小泉今日子、トム・クルーズ、渡辺謙、細田守、トミー・リー・ジョーンズ、レオナルド・ディカプリオへインタビューした際の裏エピソードも!」と書かれています。
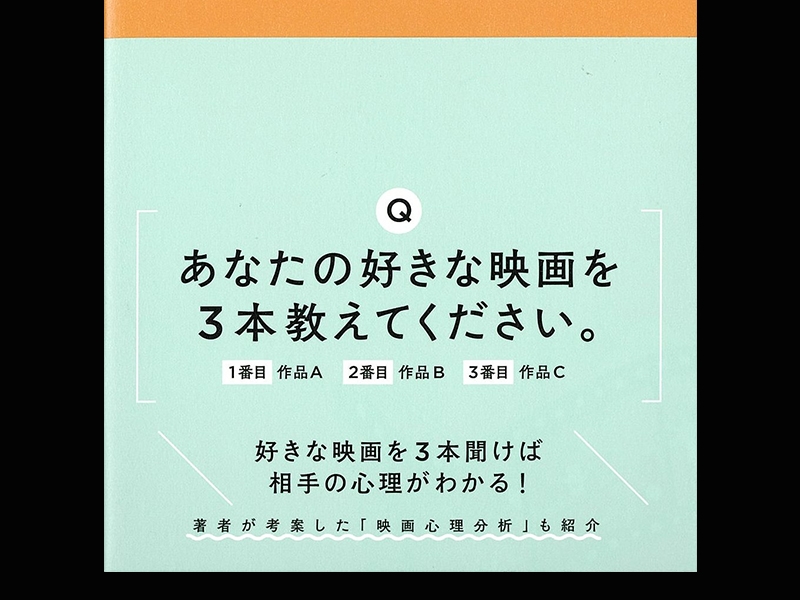 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には「あなたの好きな映画を3本教えてください。」「1番目:作品4」「2番目:作品B」「3番目:作品C」「好きな映画を3本聞けば 相手の真理がわかる!」「著者が考案した『映画心理分析』も紹介」と書かれています。
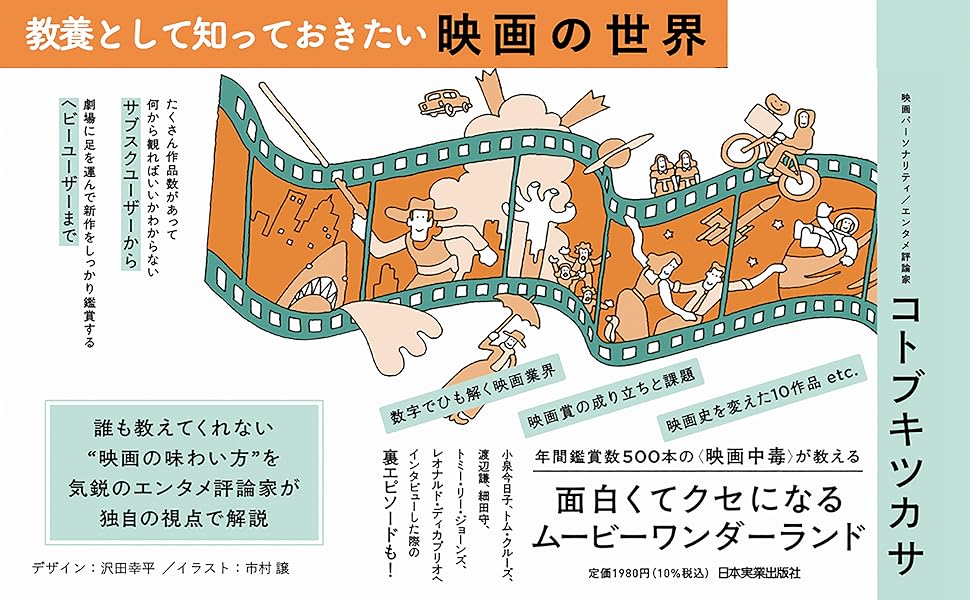 アマゾンより
アマゾンより
カバー前そでには「ようこそ映画中毒の世界へ!」として、「たくさん作品数があって何から観ればいいかわからないサブスクユーザーから」「劇場に足を運んで新作をしっかり鑑賞するヘビーユーザーまで」「誰も教えてくれない‟映画の味わい方“を気鋭のエンタメ評論家が独自の視点で解説」と書かれています。
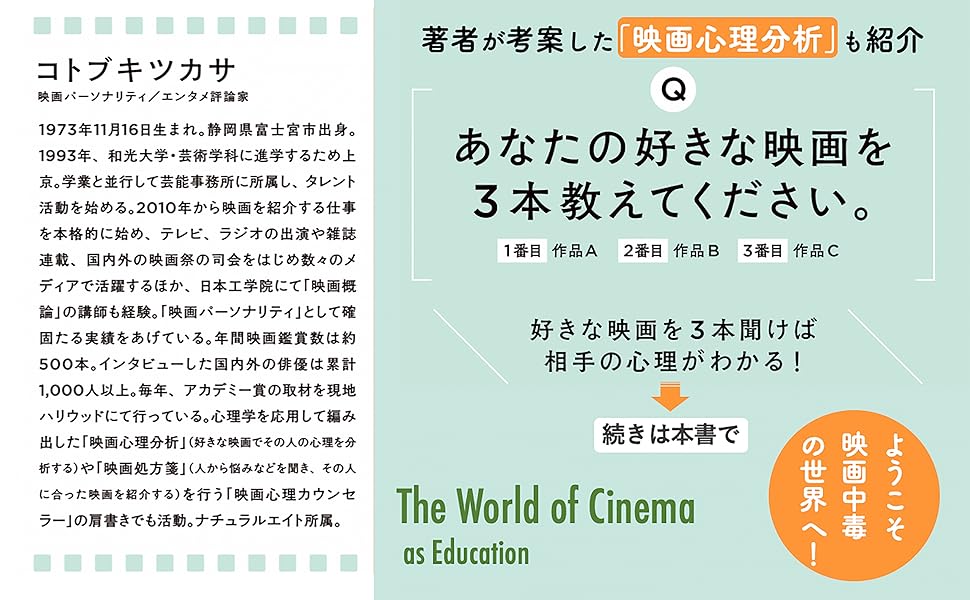
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
はじめに
「映画はエンターテインメントの中心なのか?」
第1章 商業映画の誕生と発展
第2章 映画業界の現状と課題
第3章 映画の歴史を変えた10作品
第4章 映画の世界の表と裏
第5章 映画のウィスプ
知っていると見方が変わる意外な真実
第6章 映画にまつわる個人的文化資源
付録 コトブキツカサの追憶
映画人との個人的エピソード
おわりに
「劇場の暗闇にいるからこそ感じる眩しさがある」
はじめに「映画はエンターテインメントの中心なのか?」の「●さまざまなコンテンツとの生き残り競争をしている映画業界」の冒頭を、著者は「1895年12月、フランス・パリのグラン・カフェで、リュミエール兄弟が初めて観客から入場料金を取って映画を上映しました。これが世界初の“映画興行”といわれています。その後、アメリカ・ハリウッドを中心に世界的発展と変化を繰り返し、約130年の時を経て現在に至ります。“キング・オブ・エンタメ”と呼ばれた映画業界は、変革期のただなかにいます。誰にとっても平等で有限な資源である「時間」を奪い合うために、さまざまな業界がしのぎを削り、多様なエンタメコンテンツを提供しています」と書きだしています。
昔は「劇場での映画鑑賞に費やされていた時間」が、スマートフォンで多彩な娯楽ジャンルを楽しむ時間にシフトしています。映画の鑑賞法も、amazon prime video、Netflix、Hulu、Disney+、U-NEXTなどの登場により、手軽にストリーミングで観られるようになりました。しかし、それは「映画を劇場で体験する」という、贅沢で特別な時間とは違った楽しみ方であるとして、著者は「“エンタメの飽食時代”といえる現在、映画業界はさまざまなコンテンツとの生き残りをかけた競争をしている真っ最中なのです」と述べます。
第1章「商業映画の誕生と発展」の「サイレント映画からトーキー映画への変革」の「●すべてを変えたトーキーの代表作『ジャズ・シンガー』」では、デイミアン・チャゼル監督作「バビロン」(2023)が取り上げられます。同作は1920年代以降のハリウッド黄金期を描いていますが、劇中で「ジャズ・シンガー」(1927)を観た青年マニー・トレス(ディエゴ・カルパ)が、サイレント映画のトップスターであるジャック・コンラッド(ブラッド・ピット)に電話をするシーンがあることが紹介されます。ジャックがマニーに「ジャズ・シンガー」の感想を電話越しで聞くと、彼は興奮しながら、「すべてが変わる!」と告げるのでした。
「時代とともに変化する映画界のムーブメント①」の「●製作者の個性豊かな世界観によって新たなジャンルが誕生していく」では、20世紀に入り、アメリカではショートフィルムを上映する小規模で庶民的なニッケルオデオンと呼ばれる映画館が話題となったことが紹介されます。ニッケルとは5セント硬貨、オデオンはギリシャ語で屋根付きの劇場のことです。著者は、「ニッケルオデオンで上映されていたショートフィルム文化をベースに、若い映像作家たちが新しい映画文化を求めて西海岸で活動をはじめ、それが後の映画産業の中心地であるハリウッドの誕生へとつながっていきます。1920年には、チャールズ・チャップリン、バスター・キートン、ハロルド・ロイドの世界三大喜劇王が制作に携わるコメディ映画というジャンルが確立されます」と述べています。
「●映像+音声による表現方法の広がりでジャンルがさらに多彩に」では、無声のサイレント映画から、音声を導入したトーキー映画に切り替わるタイミングで登場したのがトーキー・アニメーション映画であることが紹介。ミッキー・マウスとミニー・マウスのデビュー作ともいわれているディズニーの短編映画「蒸気船ウィリー」(1928)も、誕生間もないトーキー・アニメーションの歴史的代表作の1つです。映像が音声付きで再生される手法の登場により、表現方法の裾野は大きく広がり始めました。
1930年代は、映画産業の黄金期といわれる時代でした。フランスでは「巴里の屋根の下」(1930)のルネ・クレール、「女だけの都」(1935)のジャック・フェデー、「霧の波止場」(1938)のマルセル・カルネといった監督たちが、詩的リアリズムという映画運動によって、パリを舞台にする厭世的でロマンティックな作品で商業的成功を収め、フランス映画界を大いに盛り上げます。ここに挙げられた作品は、いずれもわたしの大好きな映画ばかりです。1930年代の主流はギャング映画やミュージカル映画です。1934年に公開されたフランク・キャプラ監督の「或る夜の出来事」がヒットしたことが後押しとなり、サイレント時代から続いたスラップスティック・コメディ(ドタバタ喜劇)からスクリューボール・コメディが人気となりました。スクリューボール・コメディとは、テンポのよい小粋な会話劇により、観客が予想できない展開が起こる映画の総称です。
「時代とともに変化する映画界のムーブメント②」の「●映画表現における既成概念を覆す新たな潮流の誕生」では、1950年代になると、黒澤明監督の「羅生門」(1950)が各国の映画賞で評価され話題となったことが紹介されます。ある事象に対して複数の視点を描く表現方法は、現在、世界の映画界共通語として羅生門エフェクトや羅生門スタイルと呼ばれています。また、時代的にレッドパージ(赤狩り)の影響が映画界にも押し寄せたことが紹介されます。共産主義に関与したことがある映画人が次々にハリウッドを追放されました。一方で、一般家庭へのテレビの普及が広まり、映画界は斜陽を迎えました。
第2章「映画業界の現状と課題」の「『脚本賞』と『脚色賞』の違いとは何か」の「●アメリカ・アカデミー賞は原作の有無で賞が分かれている」では、脚本賞 → オリジナルの物語(脚本)に与えられる、脚色賞 → 原作のある物語を映画化した脚本に与えられる。という違いが説明されます。これは、わたしも初めて知りました。「トップガン」(1986)は、原作となる小説や舞台はなく、ある雑誌の記事がきっかけで制作されました。ハリウッドの大物映画プロデューサーのジェリー・ブラッカイマーが、アメリカ海軍航空学校で訓練を受けているパイロットを取材した記事を読み、「次回作のヒントになるかもしれない」と直感でひらめいたことがきっかけだそうです。
その雑誌を、「フラッシュダンス」(1983)や「ビバリーヒルズ・コップ」(1984)で一緒に仕事をしていた同業者のドン・シンプソンに見せたところ、彼は中身を読むことなく、レイバンのサングラスをかけたパイロットが戦闘機の横に立つクールな雑誌のカバーを見ただけでヒットを予感。その場で雑誌の発売元に電話して、映画化の権利を買ったのでした。著者は、「アカデミー賞のカテゴリーでは、完成された物語を映画化の脚本にしたものだけが脚色ではなく、『トップガン』のように雑誌の記事からインスパイアされた脚本も「脚色」となります。ちなみに『トップガン マーヴェリック』では、この雑誌記事を書いたエフド・ヨナイの遺族から著作権侵害で映画会社のパラマウントが訴えられました。映画スタジオ側は『エフドが書いた記事はマーヴェリックとは関係なく、完全なオリジナルだ』と主張しています」と述べます。
「昨今の日本映画の課題①オリジナル脚本の減少」の「●原作ありきの映画が増えることの功罪」では、出版関係者によれば、マンガの連載が始まり評判がよいと、2~3話目には映画契約の話が出版社に持ち込まれるケースがあることが紹介されます。また、日本で最も有名な映画プロデューサーの1人に聞いた話では、自分が作りたかったり興味がある物語が頭に浮かんだら、その物語に近いマンガや小説がないか探すとか。「脚本をゼロから作り上げるより、固定ファンがついている原作のほうが全方位で映画化しやすいから」と同プロデューサーは説明。著者は、「その時の僕の心情を吐露すると、『明確に物語の構想が頭にあるのなら、オリジナル脚本の映画を目指せばいいのにな』と思ったものです」と述べます。本当に、そうですね!
「エンドロールが以前よりも長くなった理由」の「●フリーランスの俳優・スタッフが増えたことも影響している」では、最近エンドロールが長くなった理由の1つとして、労働組合(ユニオン)との契約が指摘されます。これはフリーランスの俳優・スタッフが増えたことや、ビデオやDVDとして作品が後世に残るようになったことも関係しているとして、著者は「クレジットは、過去にどんな作品に携わったかを証明するものにもなるため、映画業界を支える関係者が所属する各労働組合が、個人名の記載を主張するようになったのです。その結果、映画によってはケータリングのスタッフや清掃員の方々も記載されるようになっています」と述べます。これには驚きました。
「邦画界は監督より助監督のほうが年収がいい」の「●監督業の報酬額では副業が避けられない?」では、日本では、監督のほうがギャラが高いのに助監督のほうが年収がいいということを指摘します。日本の映画監督の作品1本の報酬は、制作費にもよりますが、平均すると300万~500万円といわれています。企画段階からさまざまな工程を経て作品が完成するまで数年かかるので、年収で換算すると厳しい数字になります。そのため、ミュージシャンのMV(ミュージックビデオ)や企業コマーシャルを撮影したり、教育機関で演劇や映像を教える講師業(ワークショップ)をしたり、雑誌コラムの原稿を執筆する文筆業などで生計を立てている映画監督は少なくないのです。
「●そもそも邦画は制作費が低く抑えられている」では、ハリウッドのビッグバジェット・ムービー(大作映画)は約1億ドル以上(約140億円以上。ここでは1ドル140円で換算します)の作品を指しますが、邦画は1億円未満がほとんどです。10億円超の映画は年間数本しか存在しないことが紹介されます。アメリカでは、学生映画でも100万ドル(約1億4000万円)の制作費が標準だとか。「インディーズの世界にはインディペンデント・スピリット賞があり、メジャー映画会社以外の会社が制作した作品を対象にしていますが、広告宣伝費などを除いた直接制作費2000万ドル以下(約28億円以下)の作品が基準になっています。アメリカでは28億円以下の制作費の作品がインディペンデント(自主制作)映画なのです」
第4章「映画の世界の表と裏」の「著名な映画賞・映画祭の成り立ち」の「●世界三大映画祭に含まれないアメリカ・アカデミー賞」では、世界三大映画祭とは、「カンヌ国際映画祭」「ベルリン国際映画祭」「ヴェネツィア国際映画祭」の3つを指し、アメリカの「アカデミー賞」は含まれていないことが紹介されます。著者は、「世界各国には歴史ある映画賞があり、その成り立ちは千差万別です。例えば、アメリカ・アカデミー賞は世界で最も華やかな映画賞であることは誰もが認めると思いますが、もともとはハリウッドで働くスタジオの重役や俳優や監督などが集まり、1年に1回、お互いの労をねぎらう晩餐会からスタートしました。三大映画祭より知名度があり、歴史もありますが、もともとは国内の映画産業に関わるものを対象にしたドメスティックな祭典なのです」と説明します。
ちなみに、アカデミー賞(アメリカ/毎年2~3月)は1929年設立。映画芸術科学アカデミー(AMPAS)会員の投票によって決定。会員の多くはハリウッド業界関係者。受賞者には裸の男性の立像「オスカー像」が贈呈されます。日本アカデミー賞(日本/毎年3~4月)は1978年にアメリカの映画芸術科学アカデミー(AMPAS)の許諾を得た上で、日本アカデミー賞協会により設立(「アカデミー賞」の名で表彰できるのはアメリカ・イギリス・日本だけ)。受賞者には、彫刻家・流政之氏が制作した全長3メートル20センチの巨大なモニュメント「映画神像」を小型化したトロフィーが進呈されます。実物の「映画神像」は現在、東京都有楽町マリオン、北海道札幌シネマフロンティア、福岡県T・ジョイ博多に設置。
「新しいルール造りが求められている世界の映画賞」の「●ハリウッドを震撼させたMe Too運動」では、ここ数年の映画賞の存在は過渡期にあり、改革が求められていることが紹介されます。アメリカ・アカデミー賞でいうと、2017年、ハリウッドを震撼させたのが、Me Too運動のきっかけともなったハーヴェイ・ワインスタインのセクシュアルハラスメント事件でした。映画プロダクション「ミラマックス」の設立者で、「オスカー請負人」とまでいわれていたハリウッドの大物映画プロデューサー、ハーヴェイ・ワインスタインが、長年にわたって多数の女性を暴行し、事件を口外しないよう隠蔽工作を行ってきたことを告発する記事が発表。この告発はアメリカ社会に衝撃を与え、性暴力および性的虐待を受けていた女性たちが声を上げる「#MeToo運動」と呼ばれる世界的社会現象に発展しました。
男性権力者による性犯罪が告発されるようになった傾向は「ワインスタイン効果」といわれるようになりました。セクシュアルハラスメント事件の他にも、特定の作品や個人の評価が高まるように、ロビー活動ばりの投票権を持つ会員に働きかける行動によって、オスカーの行方が左右されていることを非難する声も上がっています。アカデミー賞の主催団体、映画芸術科学アカデミー(AMPAS)の会員の高齢化や白人男性が多いことなど、構成比率についても問題視されてきました。著者は、「2015年のアカデミー賞では、俳優部門のノミネートが白人俳優で占拠されたため、『Oscars So White』(オスカーはとても白い=白人受賞者が多い)として、SNSを中心に、白すぎるオスカー(#Oscar So White)と批判するコメントが相次ぎました」と述べます。
「●水の流れを止めてはいけない」では、ゴールデングローブ賞も、選考委員が白人のみであることが問題視されたことが紹介されます。さらに、「ハムナプトラ」(1999)や「ザ・ホエール」(2022)で知られる俳優のブレンダン・フレイザーが、同賞を主催するハリウッド外国人記者協会の元会長フィリップ・パーク氏からセクハラ行為を受けたことを告白(ブレンダン・フレイザーはセクハラを受けたあと、心の病から俳優業を一時休止)しました。トム・クルーズは同協会への抗議の表明として、自身が獲得したゴールデングローブ賞のトロフィーを3本返還しています。わたしはトム・クルーズという俳優を人間的にリスペクトしているのですが、こういった行動も素晴らしいと思います。
「ハリウッドから始まったセクハラ撲滅運動」の「●セクハラ問題に対する糾弾の気運が世界に伝播」では、ワインスタインの悪行に関して、多くのハリウッド女優が過去に自分が受けた被害をインタビューで語ったことが紹介されます。例えば、グウィネス・パルトローはワインスタインに不適切な行為をされた後、当時パートナーだったブラッド・ピットにその旨を話し、ブラッド・ピットがワインスタイン本人に二度と同じことを繰り返すなと強く忠告したそうです。一方で、ニコール・キッドマンは、「当時、とても力のある人が夫(トム・クルーズ)だったおかげで、セクハラ被害を受けないで済んだ」と答えました。著者は、「ハーヴェイ・ワインスタインは裁判を受け、禁錮刑が確定しました。彼以外にも、ケビン・スペイシー、ウッディ・アレン、アーミー・ハマー、モーガン・フリーマン、ビル・マーレーなど、そうそうたる面々が過去のセクハラ行為などの疑いで、名指しで告訴されたり批判されました」と説明します。
「邦画界の今後の課題」の「●カウンターパートが存在しない日本」では、スティーブン・スピルバーグ、ジョージ・ルーカス、クエンティン・タランティーノ、ヴィム・ヴェンダース、ポン・ジュノなど、これまで著名な映画監督たちが日本の映画監督や作品に対するリスペクトを表明してきたことが紹介されます。著者は、「歴史を振り返れば、黒澤明、小津安二郎、成瀬巳喜男、今村昌平、大島渚、溝口健二、川島雄三、本多猪四郎、石井輝男、岡本喜八、深作欣二など、世界で評価されてきた日本人監督は多数います。さらに、北野武、宮崎駿、黒沢清、濱口竜介、是枝裕和、清水祟、塚本晋也など、現役のクリエーターとして作品を完成させて、世界で評価されている監督も大勢いるのです」と述べています。
「●希望の光となった『ゴジラ-1.0』の世界的ヒット」では、2023年から2024年にかけて、東宝の「ゴジラ-1.0」がアメリカで大ヒットしたことが紹介されます。山崎貴監督は監督として第96回アカデミー賞では邦画・アジア映画史上初の視覚効果賞を受賞。監督として視覚効果賞を受賞したのは「2001年宇宙の旅」(1968)のスタンリー・キューブリック以来、55年ぶり、史上2人目です。また、製作費20億円以下の予算で、全世界累計の興行収入は160億円を突破していることで、さらに世界の映画関係者を驚かせました。著者は、「ゴジラの第1作目が公開されたのが1954年。本作の大ヒットは、東宝がIP(知的財産)ビジネスの多様性を見せつけたといえます」と述べるのでした。
第5章「映画のウィスプ 知っていると見方が変わる意外な真実」の「麗しのサブリナ」(1954)では、「●撮影時にオードリーがNGを連発した理由」として、演技に関して完璧主義といわれていたオードリー・ヘプバーンが同作の撮影時はNGを連発したことが紹介されます。なぜ彼女はNGを連発したのかについて、「それには理由があります。じつはこの作品の脚本はとても難航していて、次のシーンの台本が現場に届いていないような状況で撮影をしていたそうです。そこで、長男ライナス役のハンフリー・ボガートがイライラしないように、わざとオードリーがNGを出して現場の雰囲気を和らげ、脚本が現場に届くまでの時間稼ぎをしたといいます。彼女の機転で無事撮影を終えた本作は、数々の映画賞に輝き、オードリーの代表作の1本となりました」と述ていべます。
「タイタニック」(1997)では、「●ジャックはディカプリオが演じる予定ではなかった」として、主人公であるジャックを演じたレオナルド・ディカプリオは、同作に出演したことでハリウッドのAクラスセレブとなりましたが、当初、ジャック役はスタジオ側が強く推薦していた俳優マシュー・マコノヒーが演じる予定で、先に起用が決まっていたローズ役のケイト・ウィンスレットもトーク番組で「相手はマシューだった」と語っていたことが紹介されます。ではなぜ主演が変更されたのかというと、ジェームズ・キャメロン監督が周りの反対を押し切り、レオナルド・ディカプリオを強引に推薦して決定したのでした。著者は、「キャメロン監督の強力な推しがなければ、今のディカプリオの地位はなかったかもしれません」と述べています。
「映画のウィスプ」の最後を飾るのは、一条真也の映画館「Mank マンク」で紹介した2020年のNETFLIX映画です。実在する新聞王のウィリアム・ランドルフ・ハーストをモデルに、大富豪の波乱に満ちた生涯を描いた、映画史に燦然と輝く不朽の名作「市民ケーン」(1941)の共同脚本家、ハーマン・J・マンキーウィッツの伝記映画です。アカデミーの会員たちからすれば、1930年代以降のハリウッドが舞台という点で、「自分たちの歴史だ」という意識が強く、大手スタジオからの意向や妨害に屈しないマンクに対してシンパシーを感じたのも納得ですあるとして、著者は「特筆すべきなのは、本作の脚本を最初に執筆したのが、ジャック・フィンチャー(脚本家・ジャーナリスト)であること。ジャックは本作の監督であるデヴィッド・フィンチャーの実の父親なのです。長い年月、作品化できなかった亡き父の遺稿を、息子であるデヴィッドが監督して世に知らしめたという、このサイドストーリーも会員たちの心に響いたのでしょう」と説明します。
第6章「映画にまつわる個人的文化資源」の「僕が『映画心理分析』を考案した理由と経緯」の「●映画心理分析をすると何がわかるのか」では、著者が開発した映画心理分析で見えてくることは、1本目に挙げる映画→「人にこう思われたい」という作品、2本目に挙げる映画→その人の「根底に流れるテーマ」の作品、3本目に挙げる映画→自身のキャラクターについて「バランスを取る」作品だそうです。著者は、「1本目は、『人にこう思われたい』という作品を挙げる傾向があります。本音と建前でいうと『建前』のようなもの、いわゆるペルソナ(自己の外的側面)。『私はこういう顔で生きております』という名刺のような映画です」と解説しています。
また、著者は「2本目は、その人の『根底に流れるテーマ』の作品を挙げる傾向があります。本音と建前でいうと『本音』、あるいは『潜在意識』のようなもので、『抑圧している陰の自分』が、その作品ににじみ出ています。3本目は、自身のキャラクターについて『バランスを取る』作品を挙げる傾向があります。本当の自分と世間に見せている自分のバランスを取るため、1本目と2本目の映画をほどよく中和させるような意味合いの作品を挙げています」と解説するのでした。面白いですね。
「映画音楽の重要性と北野映画にまつわるエピソード」の「●『好きな映画音楽を語る』=『好きな映画を語る』ことになることも」では、北野武監督の映画と音楽の逸話が紹介されます。1990年に公開された「稲村ジェーン」は、サザンオールスターの桑田佳祐が初監督した、鎌倉市稲村ヶ崎を舞台にあるサーファーのひと夏を描いた映画です。同作は、観客や評論家の評価は分かれたものの、興行的には成功しました。主題歌の「真夏の果実」、挿入歌の「希望の轍」「忘れられたBig Wave」も大絶賛されました。しかし、北野監督は自身が執筆する映画コラムで、「半分も観ないうちに逃げ出したくなった。こんなに長く感じた映画は初めてだね」と述べて、業界は騒然となったのです。
北野武が言いたかったのは、「音楽映画なのに邪魔な台詞がありすぎて音楽を殺している」ということだったのでしょう。この話が桑田佳祐の耳に入ると、彼の身内のパーティで、「たけしさんのことは尊敬しています。ただ、(この映画が)つまらないというのは感性が足りないから。たけしさんは若者の気持ちがわかっていない」と発言しましたその話を聞いた北野監督は翌1991年、久石譲氏を音楽監督として招き、サーファーが主人公、かつ、台詞がほとんどない「あの夏、いちばん静かな海。」をアンサームービー的に公開するに至ったのでした。著者は、「ちなみに、その後メディアで2人の確執が報道されましたが、年月を経て、現在はお互いをリスペクトしている旨の発言をしています」と解説しています。本書は、無類の映画好きで、映画人へのインタビュー経験も多い著者の蘊蓄を大いに楽しむことができました。すべての映画ファンに推薦したい好著です!