- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2416 読書論・読書術 『ややこしい本を読む技術』 吉岡友治著(草思社)
2025.09.01
『ややこしい本を読む技術』吉岡友治著(草思社)を読みました。読書論や読書法の類が好きで、これまで多くの関連書を読んできました。本書は異色の内容で面白かったです。著者は、宮城県仙台市生まれ。東京大学文学部社会学科卒、シカゴ大学大学院人文学科修士課程修了、比較文学・演劇理論専攻。竹内演劇研究所、駿台予備学校・代々木ゼミナール講師、大学講師などを経て、現在は、神田神保町VOCABOW office で、法科大学院・MBAの志望者、企業などに対する論理的文章の指導を行い、インターネット小論文添削講座「VOCABOW小論術」も主宰。著書多数。
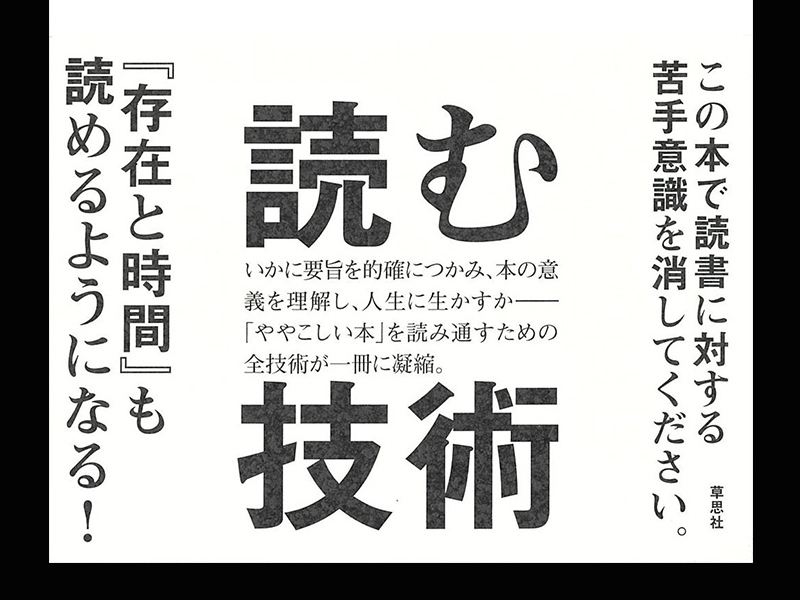 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、「いかに要旨を的確につかみ、本の意義を理解し、人生に生かすか――『ややこしい本』を読み通すための全技術が一冊に凝縮。」「この本で読書に対する苦手意識を消してください。」「『存在と時間』も読めるようになる!」と書かれています。帯の裏には「読むか読まないか、それが問題だ」と大書され、多くの名著のタイトルと著者名が並んでいます。
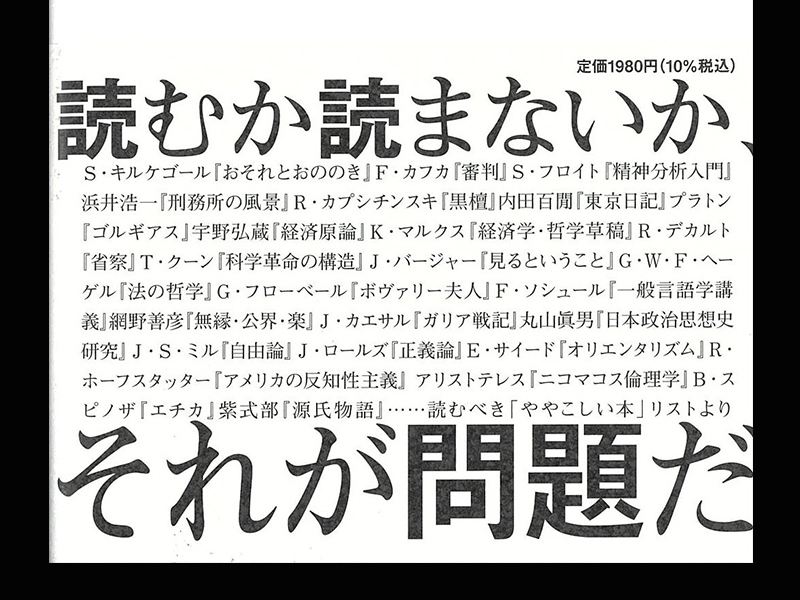 本書の帯の裏
本書の帯の裏
カバー前そでには、「この本では、心構えやルールを述べるだけではなく、それがどのように具体的な『読む』という行為に応用されるのか、さまざまな文章を使って検証しています。『ややこしい本』の作法に慣れて、その中で頭が活発に動く基盤を作ることができるはずです。(「はじめに」より)」と書かれています。
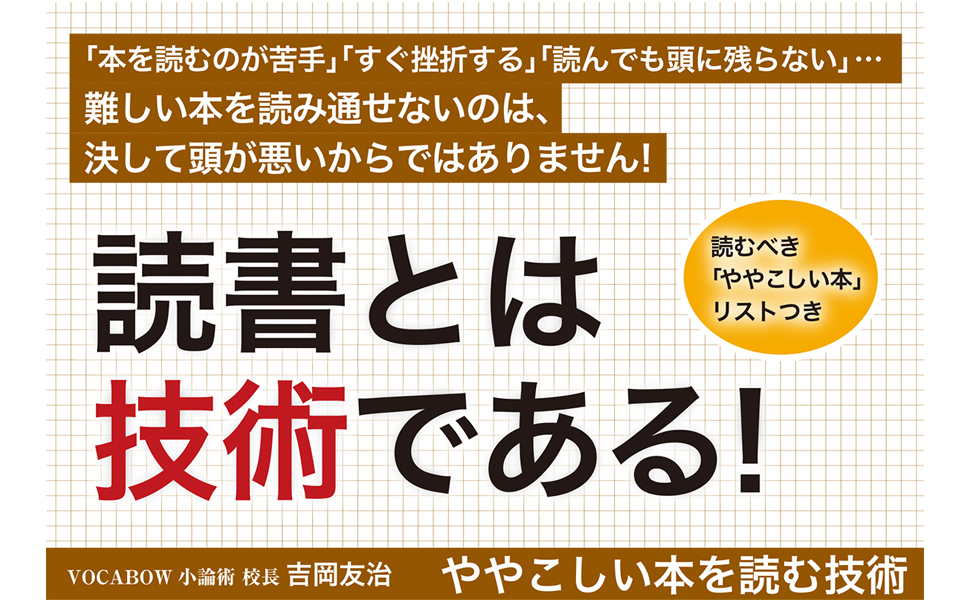 アマゾンより
アマゾンより
アマゾンの内容紹介には、こう書かれています。
「『本を読むのが苦手』『すぐ挫折する』『せっかく読んでも頭に残らない』『もっと難しい本を読みたいのに……』古典的な名著や難しそうな哲学書、自然科学書など……読んだほうがいいと思って買ったものの、最後まで読めなかったという人は案外多いのはないでしょうか? さらに言えば、『難しい本を読めないのは自分の頭が悪いから?』と間違った悩みを抱えている人もいるかもしれません。でも、難しい本を読み通せないのは、決して頭が悪いからではありません。では、なぜ読み通すのが困難なのか。実はこうした『ややこしい本』を読むには、読むための『読書技術』が必要なのです。『ややこしい本を読む』という行為は、楽しむことが第一の目的ではありません。つまり、本を夢中になって、ハラハラドキドキしながらのめりこんだりする従来型の読書法では、『ややこしい本』を読み通すことが困難だったのです」
続けて、アマゾンの内容紹介には書かれています。
「本書は、読書初心者にもわかりやすく、『ややこしい本』を読む『技術』をまとめたものです。どんな本を選べばいいかから始まり、どのようにして本の要旨を的確につかみ、本の意義を理解し、これからの人生に役立てていけばいいのか、までを1つひとつ丁寧に解説していきます。読み進めながら、『ややこしい本』の作法に慣れて、その中で頭が活発に動く基盤を作ることができるはずです。ぜひこの本で読書に対する苦手意識を払しょくしてください」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
第1部 読む前に準備する
①「読む」とはどういうことか?―ウォーミング・アップ
②「ややこしい本」のしくみ―読む前によく眺めよう
第2部 読みながらすべきこと
③問いはどこ?答えは何?―要旨をつかむ
④理屈はきっちりとたどる―根拠が分かる自分を作る
⑤証拠を出す―現実としっかり結びつくための材料
第3部 読み返しつつ考える
⑥ロジックを深める構造
⑦比較してテンションを探す
⑧別な本と比べる―比較・対比から新しい見方へ
第4部 ややこしい大著を読む
⑨ピケティの『21世紀の資本』を読んでみる
第5部 対話して世界を広げる
⑩みんなで話すと分かってくる―会読のすすめ
⑪文学はどう読むのか?―物語を豊かに読む
読むべき「ややこしい本」リスト
「あとがき」
「はじめに」の冒頭を、著者はこう書きだしています。
「『ややこしい本』とは何か? たぶん、読まなければと分かっているけど、何か読みにくくて、しばし積読(つんどく)状態になっているような本でしょう。因果なもので、我々は『~しなければ』と思うと、そこから全力で逃げたくなる癖があります。でも、『~しなければ』と感じているのもまた自分であり、逃げ出したところで、『読まなければ』という必要性が変わるわけではありません。後で『読んどきゃよかった』と後悔するにしても、『あんな本は別に読まなくてもよかったんだ。何の役にも立たない』と自己正当化するにしても、それでも心のどこかにひっかかりを感じてしまう」
「ややこしい本」を読むための戦略とは何か?
簡単に言うと「本と対話できる私を準備すること」だといいます。著者いわく、すべての人が「ややこしい本」を読めるわけではありません。「ややこしい本」はマラソンのようなものです。何のトレーニングもしないで、マラソンを3時間以下では走れないように、読むという作業は、いきなり参加しても完走はできません。混乱して途中棄権するか、救急搬送されてドクターストップになるか、のいずれかであるとして、著者は「少しずつトレーニングして、体力をつけて、自分のコンディションを整えて、それから挑戦する。読むことだって、そういう積み重ねの結果として可能になるのです」と述べています。
「世界の人口が、今何人で、これからどうなると予測されるか?」とか「日本のGDPの順位がどんどん下がって、どんな問題が生ずるか」といった情報や知識は、データを確認すればだいたい分かることで、ややこしくも何ともありません。著者は、「中学2年程度の読解力で足ります。新聞とかニュースは、そういうレベルです。でも『ややこしい本』とは、すでにある情報や知識を与えるだけではなく、既存の常識を揺さぶって、現在読んでいるその人に問いかけることで、その人が疑問を持ち、それをまた本に投げかけつつ、答えを求めつつ本からの挑戦を受けるという相互行為を要求する本です。その結果として、世界のより深い理解につながるのです」と述べます。
第1部「読む前に準備する」の「①『読む』とはどういうことか?―ウォーミング・アップ」の「理解するという快楽」では、そもそも、他人の考えを理解することは、人生における快楽につながるといいます。なぜなら、自分が今まで「こうだ!」と思い込んでいたことが覆され、新しい視点が開けるからです。著者は、「ものごとの捉え方が変わり、今までと世界の見え方も違ってくる。つまらないと前に感じたことでも、あらためて見てみると、新しい発見に気づく。新しいアイディアも湧くし、今までと違う行動や仕事の可能性も生まれてくる。それを積み重ねていけば、人生の方向さえ変わっていくかもしれません」と述べています。
著者は、同じことを漫然と繰り返すのではなく、新しい発見が次々に出てくるなら、生きることにも張り合いが出るし、刺激があって楽しいと述べます。逆に、理解が停滞して深まらないと、わたしたちは以前のパターンを踏襲するしかありません。そんな人生は面白くないし、退屈です。著者は、「相手を理解せず、自分が誰かも分からず、世界がどうなっているかも分からないとしたら、生きる価値はどんなに少なくなることか。だから、本を通して他者の考えを理解する行為は、自分の人生を楽しむための基本的な技法なのです」と述べています。つまり「ややこしい本」を読む意義とは、その場や時間を楽しくやり過ごすことにあるのではなく、むしろ、読むことで、世界を捉え直し、より面白がって生きることができるということなのです。読むことにともなう苦労は、その結果に至るスパイスにすぎないのです。
「この本で提示する読み方の基本」では、「ややこしい本」の内容を理解するには、読む側にとっても、ある程度の準備と成熟が必要になるといいます。たとえば、数学者高木貞治の『解析概論』は名著と言われていますが、それを小学生に与えたところで理解できませんし、そもそも「どう理解したらよいか?」と迷うことすらできません。ただ「ちっとも分からないなー!」とぶん投げるだけです。著者は、「『解析概論』を読むには、その前に読む側にも数学的な知識や経験が必要です。自分なりの考えをすでに持っているから、『え、ここはどうしてこうなるの?』と迷うこともできる。とすれば、迷うことだって、必ずしも時間の損失とは限りません。むしろ、迷えるということこそ、理解を進める助けになるし得るものもまた大きいのです」と述べています。
「②『ややこしい本』のしくみ―読む前によく眺めよう」の「自分の問題にするのが大事」では、「ややこしい本」は、謎=問いかけに答えるというしくみになっていると指摘します。その謎の提示を面白いと感じれば、それが本を読む原動力になるといいます。読むにつれて、その問いがどんどん大きくなって、寝ても覚めてもそのことを考え続ける、というようなことになったら理想的ですが、なかなかそうはいきません。著者は、「それでも、丁寧に読み続けていけば、しだいに、その問題が心の中で占める割合が大きくなる。そうしたらしめたもので、最後まで読み続けられる原動力が形成されたのです」と述べています。
第2部「読みながらすべきこと」の「⑤証拠を出す―現実としっかり結びつくための材料」の「理屈が現実と対応しているか」では、「説明」あるいは「言い換え」は、「風が吹けば桶屋が儲かる」と同じ構造をしています。つまり「風が吹けば、埃が舞い上がる。すると埃が目に入って、目の病気になる人が増える。だから、盲目の人も増える。盲人は三味線で生計を立てようとするので、三味線弾きが増える。三味線弾きが増えると三味線が売れる。三味線には、猫の皮が使われる。猫が捉えられて三味線に加工されるので、猫の数が減る。猫が減るとネズミが増える。ネズミが増えると桶をかじる。桶の修理依頼が増えて、桶屋が儲かる」。「風が吹く」という最初の事態を、次々に言い換えていくことで「桶屋が儲かる」までつなげていくのですが、著者は「『風が吹けば桶屋が儲かる』は、通常『一見もっともらしいが、実は信用ならない言い草』の意味で用いられます」と述べています。
「エビデンスから事実に迫る」では、「ややこしい本」は「風が吹けば桶屋が儲かる」と違って、著者の出したい結論に対して、証拠(エビデンス)を提出するといいます。理屈が現実と対応していることを示すことで、理屈と事実の両方から現実と結びつくことを表そうとするわけです。エビデンスとは、例やデータのことです。「風が吹けば桶屋が儲かる」も、理屈は合っているようでも、現実には、そういう出来事はほとんど起こらないから間違っています。でも「北京で蝶が羽ばたくと、ニューヨークでハリケーンが起こる」はどうか? こちらは「バタフライ効果」と呼ばれます。通常なら無視できる範囲の出来事が、やがて巨大な結果を生み出すことを意味しますが、「風が吹けば桶屋が儲かる」のようにバカにはされず、カオス理論では、その可能性が真面目に議論されています。著者は、「なぜ、片方は『バカバカしい』と言われ、他方は『あり得るかもしれない』となるのか? このギャップをつなぐのが証拠(エビデンス)です。多少なりとも証拠があれば、理屈のうえでの仮想を本当にあり得ることだと示すことができるのです」と述べます。
「エビデンスの効果は強力である」では、それでもエビデンスの効果は強力であるといいます。何よりも、エビデンスは現実と直接結びついているイメージがあるからです。だから、理屈を出さなくても、エビデンスの力だけで読む人を納得させることもできるのです。たとえば、心理学では「人間はこんな行動をする」ということを、実験で明らかにします。しかし、なぜ、そういう心理になるか、については理屈づけしないことも多いです。それでも「こういうものなんだ」と実験で明らかにすると、それだけで読者は納得させられます。ここで、著者は有名な「ミルグラム実験」を例に示します。これは「権威から許されれば、人間は止めどなく残酷になる」ことが示されたと言われる実験です。ある俳優が別室にある椅子に座り「犠牲者」の役を演じ、こちらの室内ではもう一人の俳優が研究者になって、集められた被験者に「犠牲者」に電気ショックを与えるよう求めます。
最初は、ためらっていた被験者たちも仕方なく電気ショックを与えるようになります。苦しむ姿は演技ですが、被験者は知りません。しだいに、より強い電気ショックを指示されますが、被験者はだんだん疑問を持たなくなり、ショックを与え続けます。最終的には、被験者の3分の2が、「犠牲者」が止めてくれと哀願しても電流を流し続け、さらに無反応になってもショックを与え続けたといいます。このミルグラム実験について、著者は「人間性の残酷さを垣間見せる怖ろしい実験ですが、なぜ、被験者たちがこんな行動を取るのかはとくに説明されておらず、『人間は残酷な面を持っている』ことがデータとして示されています。つまり理屈抜きで、事実だけで『人間とはこういうものだ』と示すわけです」と述べるのでした。
第3部「読み返しつつ考える」の「⑥ロジックを深める構造」では、著者は「映画を、あまり時間を置かないで二度見たことがあるでしょうか?」と読者に問います。著者によれば、二度見すると映画の時間感覚は明らかに変わってくるといいます。ストーリーは分かっているのでものごとがサクサク進み、あれよあれよという間に終わりになります。反面、初めに「面白い」と思ったところが、こけおどしに思えたり退屈だと思ったところに「あ、こんな工夫があったのか」と感心したり、「こうやって怖がらせたのか?」と技術的な工夫にも目が行く。関心の向く場所が変わってくるというのです。「距離を取って全体構造を見極める」では、これこそ「ややこしい本」が本来要求する読み方であるとして、著者は「受け身で『面白い』とか『面白くない』と消費するだけではなく、『面白い』なら『なぜ面白いのか?』と一歩進めて深く感じ、『面白くない』ならどこがどう問題なのか考える。ただハラハラドキドキするより、冷静になって本からちょっと距離を置いてしくみを眺める必要があるのです」と述べています。
のめり込むと、どうしても視野が狭くなります。「惚れてしまえば、あばたもえくぼ」というように、対象にのめり込みすぎると実像は見えません。著者は、「ほどよく距離を置いて、絵を鑑賞するようなつもりで見ればいいのです。そうすれば、線や色、構成などがよく見えてくる。同様に、『ややこしい本』も少し引いてみないと、全体の構造が見えてきません。文芸批評家小林秀雄によれば、フランスの詩人ボードレールは、画家のドラクロアの絵につい、「ドラクロアの絵を遠くから見てみるといい。何を描いているのか解らぬくらい離れて絵を見てみ給え。忽ちドラクロアの色彩の魔術というものが諸君の眼に明らかになるだろう。この場合諸君の眼に映じた純粋な色彩の魅力は、絵の主題の面白さとは全くその源泉を異にしたものであって、絵に近寄って見て、絵の主題が了解出来ても、主題はこの色彩の魅力に何物も加えず、又、この魅力から何ものをも奪う事が出来ぬ、と諸君は感ずるであろう。この主題と無関係な色彩の調和こそ、画家の思想の精髄なのである」と述べているそうです。
「何をどのように言っているか、能動的に分析する」では、文章でも同じことであり、小説でも二度目に読むときは、ストーリーよりも、むしろ、キャラクター、プロットの妙、情景描写の工夫などに目が行くことを指摘しています。著者は、「『源氏物語』だって、何回も読むうちに『私も夕顔のようになりたい!』という子どもっぽい願望は背景に退き、『キャラクター』の比較や『ストーリー』の構成など、『分析的な読書』に傾きます。『ややこしい本』の場合は、さらに、その傾向が強まる。『何を言っているか?』だけでなく、『どのように言っているか?』に興味が移ってくるわけです。この先どうなるか、とハラハラドキドキしていては、こういう『分析的な読書』はできません」と述べています。
「⑧別な本を比べる――比較・対比から新しい見方へ」の「同じ問いでも本が違えば答えはそれぞれ」では、「ややこしい本」を読むことは、単に難しい内容を理解すればいいのではないと指摘します。むしろ、先人が取り組んだ問題への取り組み方を身につけ、自分なりの解決を見出すことが目的だといいます。そのためには、あえて複数の教えに触れて、見方を相対化するべきだとして、著者は「大学入試の共通テスト『国語』でも、数年前から、複数の文章を比較読みする問題が出題されています。問題に対する一定の解決を学ぶだけでなく、いくつかの違った解決や考え方を比較することによって、問題をより深く捉える力を涵養しようとしています。単純で分かりやすい見方だけでなく、『反対の見方』『うがった見方』『中間的な見方』など並べてみると、『分かりやすい』と思っていた解決が、実は知識不足の結果にすぎなかったり、乱暴で一面的な解釈だったり、という事態に気づく。どちらかに決定することで対立を簡単にするのではなく、対立を含み込みつつ、さらに高度な観点にたどりつくことが可能になるのです」と述べています。
第4部「ややこしい大著を読む」の「⑥ピケティの『21世紀の資本』を読んでみる」では、たとえ名著であっても「ごもっとも!」と肯定するだけでは、読んだ意味はないといいます。むしろ、ここが問題でないか、ここはおかしいのではないか、と疑問が持てる方が「ややこしい本」を読んだ効能が出た、と言えるというのです。トマ・ピケティの『21世紀の資本』は難解なことで知られます。同書には「働いても資産の力にはかなわない」と書いてあるからと、暗号資産やFXへの投資を呼びかける輩も出てきているといいます。しかし、そういう読み方は「ヴォートラン」の21世紀版焼き直しでしかないし、もし「資産パラサイト」になることが唯一の上昇チャンスなら、今、資産形成しようと躍起になっている状況自体、もはや遅すぎることになりかねないといいます。著者は、「そういう曲解に陥らず、経済の容赦ない現実の挑戦を受けつつも、どういう社会を構想するのか、その問いを考えることがピケティを読む意味なのです」と述べるのでした。
第5部「対話して世界を広げる」の「⑩みんなで話すと分かってくる――会読のすすめ」の「読むことは対話をすること」では、「ややこしい本」を読むという作業は、過去にいた業者と対話することであるといいます。内容を語る方法も順序も、ほとんど読者との対話の形になっているとして、著者は「たとえば、理由は、読者が『なぜなの?』とツッコんでくるときの答えだし、『どういうことなの?』とか『証拠はあるの?』などという読者が抱くはずの疑問に対して、業者が説明したりデータを示したりするのが根拠の部分です。それどころか、あえて読者の提起しそうな反論を先回りして予想して、それとわざわざ対話しつつ、自説を強化したりすることすらあります。もちろん、読者からの反応をすべて本に書いてはおけないけれど、予想できる反応に対しては、あらかじめ答えを書いておいた方が『なるほど!』と思ってもらえる確率が高くなります」と述べていますが、これはブログ『あらゆる本が面白く読める方法』で紹介した拙著で提唱してことでもあり、非常に共感しました。
「ガイド役はいた方がいい」では、「ややこしい本」を読むときには誰かガイド役がいると便利だと指摘します。理解が困難なときに「こんなふうに読めばいいのでは?」と助け船を出してくれる存在です。大学のゼミナールなどで読むときは、だいたい、教師がそのガイド役をつとめてくれます。難読箇所になると「これは、こんな意味にもとれるよね」などとアドバイスしてくれる。すると、その先を読むのがぐっと楽になるわけです。著者は、「そもそも『ややこしい本』を読もうと思ったきっかけが『大学でのゼミ』だったということは少なくありません。まず自発的に読んでからゼミを受講するのが理想でしょうけど、たいていはそうはならない。自分で読もうとしても疑問ばかりが山積して途中で挫折する。悶々としたままゼミに出席するとやっと読み方のコツが分かり、もう一度読み直す。でも、それを次のゼミで発表すると『違うんじゃない?』と批判されてガッカリ……そんなことの繰り返しが通常ではないでしょうか? それでも、そんなことを続けているうちに、徐々に内容が身体にしみこんできて、文章が何を言おうとしているのか、見当がついてくる」と述べています。わたしは大学の卒論で三浦梅園の『価原』をテーマにしたことを思い出しました。非常に難解な本でしたが、ゼミの担当教官であった孫田良平先生が名ガイド役になっていただき、同書を読み進めていったのです。
「教えられなくても勝手に学ぶ」では、「読む」とは、結局自分で考える力をつけることが最終目的なので、教師は、必ずしも正確な情報を伝達しなくてよいといいます。「反面教師」という言葉にもある通り、極端なことを言えば、パワハラさえしなければ「悪い教師」だって役には立つ場面があるのというのです。有名な精神分析家であるジャック・ラカンも「無知ゆえに不適格である教授はいたためしがありません。人は知っている者の立場に立たされている間はつねに十分に知っているのです。誰かが教える者としての立場に立つ限り、その人が役に立たないということは決してありません」(『フロイト理論と精神分析技法における自我』(下)岩波書店)と言っているそうです。著者は、「つまり、教師とは学生自身が考えられる状況を作る役目を担っているのであり、知識の有無で教師になるわけではないのです」と述べます。
「メモや要約から発見につなげる」では、みんなで読むときは、その日の担当者や進行役がメモや要約(レジュメと言います)を作るといいとアドバイスします。著者が今でも覚えているのは、現在、某有名大学の法制史の教授をしている友人が、学生時代に作ってきたレジュメだそうです。マルクス『資本論』の価値と労働時間と労働強度の関係を立方体の形でまとめ、そこから剰余価値がどのように生み出されてくるか図示したものだったとか。理解の深さとともに、その作図の見事さにはうならされたそうです。読書会では、ときどき、そういうクリーン・ヒットが出てくるとして、著者は「自分の読み方がシェイプアップされて『やったー!』という感じがする。教師から指示されて気づくのと、自分たちで気づくのとでは全然喜びが違います。どんなささやかなものでも、何か新しい発見があると、その達成感でうれしくなるものなのです。いずれにしろ、『今、何を論じているか?』『どこに言及しているか?』を明確にし、出席者が共有できるためにも、まとめ=レジュメは必須です」と述べます。
「他人と語り時代と語る」では、「ややこしい本」は、著者と読者との対話だけではなく、むしろ、一緒に読む人との対話を通して時代や状況と対話するための道具でもあるといいます。とくに名著である「ややこしい本」は、そういう対話が何度でも繰り返されたいわくつきの書物であるとして、著者は「たとえば、ルネ・デカルトの『方法序説』はあまりにも有名ですが、その第6部は人間の身体を扱っており、内容は当時は最先端かもしれないが、現代科学では完全に否定され、『方法序説』を読むときは第6部をスルーすることが推奨されます。また、そのデカルトの記述の不完全性をめぐって、後年スピノザが徹底的に批判したりする。ただ、そんな紆余曲折を経つつもこの本が読み継がれているのは、そこに述べられた『方法的懐疑』などの発想が、今でも我々の発想や思考の有益なヒントになるからです」と述べます。
「だから読書はクリエイティヴである」では、「ややこしい本」の解釈は、決められた一定の意味しか持っていないわけではないといいます。むしろ、その意味は、時代や個人によって変わるし、新しい意味を帯びてくるというのです。たとえば、シェイクスピアの『リア王』の項では、自分の母親が、自分のアパートの浴槽で死亡しているのを見つけたというエピソードから始めていることを紹介し、著者は「つまり、この戯曲を昔のイングランドの国王の悲劇と捉えるのではなく、現代都市で生き延びる高齢者とそれを取り巻く人々に共通する問題だと受け取るわけです。このような読み方が妥当かどうかは別としても、主人公リアの怒りに満ちた奇矯な言動を、半分認知症が混じったような母親の言動と比較しながら『高齢者とのつきあい方』という視点から読むことで、自分の問題として捉えられるのは確かでしょう」と述べます。
シェイクスピアの『マクベス』では、演出家蜷川幸雄は時代設定を安土桃山時代に変え、大きな仏壇に見立てた舞台を作りました。その結果、舞台は、過去の亡霊たちがよみがえり、彼らの体験した残虐な歴史が再び物語られる場所となったのですが、著者は「その夢幻的な雰囲気は能にも通じ、マクベスの物語が日本の雰囲気の中によみがえる思いがしたものです。演出とは、既存の戯曲を読み替えて新しいイメージを創造する作業でしょう。古い作品に新しい解釈を試み、作品の多様性と魅力を増す。古典戯曲を演出するには、こういう「読み直し」が不可欠です。今まで行われていない読み直しであればあるほど、作品の独創性・創造性が際立つ。現代に即しつつ、誰もが知る作品からどんな未見の魅力を引き出すのか、演出家の仕事の醍醐味はそこにあります」と述べています。「ややこしい本」を読む作業も、その意味で演出家の仕事に似ているといいます。評価が定まった本の中に、時代に対応した新しい読み方を発見し、新しい意義を見つける。とすれば、読書とは、単なる受け身の作業ではなく、むしろクリエイティヴな作業になるはずだというのです。
「ややこしい本」の最初の部分は、著者がいろいろ「ほのめかし」を仕込んだり、先行研究との比較をしたりするので、極端に読みにくくなりやすいといいます。たとえば、哲学者マルティン・ハイデガーの『存在と時間』も、初めの100数10頁が過去の「時間論」、とくに、アリストテレスの議論の吟味に当てられています。アリストテレスの議論は、さらに彼に先行するプラトンやピタゴラスの説を前提にしています。これでは、ハイデガーを読む前に、アリストテレスを読まなくてはならず、アリストテレスを読むには、その前のプラトンやピタゴラスを読まなくてはなりません。いつになったら目的のハイデガー独自の見解にたどりつけるのやら……。こういう場合では、とくに複数で読むことのメリットが出てくるといいます。詳しい人にこの部分のまとめを頼めば、自分は途中で挫折して読めなくなっても、レジュメを眺めるだけで読んだ気になれますし、自分が担当で読んで理解できなかったとしても、誰かが秘蔵の知識を披露して突破口が開けます。こういう相互啓発が大事なのです。
「自発性を引き出す読み方」では、「本を読む」ことは徹底的に自発的な作業であると指摘します。自分が「なるほど!」と納得して、初めて先に進めます。その「理解」を各人が持ち寄って互いに吟味する。人によって読み方が違い、投げかける疑問もさまざまなので「ここをどう読むか?」「正しい読み方はどれか?」という解釈も変わってきます。他人の意見や解釈を聞いていて、その「なるほど!」感が得られるのなら、「読書会」のような集まりでアウトプットする価値は十分あるといいます。著者は、「こういうやり方は、1つのテキストに注釈をつける作業と似ているかもしれません。注釈とは、その一文あるいは一語がどのような意味を持っているか、を確定する作業ですが、同じテキストが注釈によって、まったく見え方が違ってくる。たとえば、イスラム教にスンニ派とシーア派という区別がありますが、両派の違いは、同じコーランという聖典の読み方が全然違うことにも現れています。コーランの注釈書は、一字一句に注がつき、その注釈の文章が、本文のまわりにとぐろを巻いて印刷されているのだとか。本をめぐって無数の言葉たちがうごめく様子が可視化できると思います」
「⑪文学はどう読むのか?――物語を豊かに読む」では、文学でも「ややこしい本」は確実に存在することが紹介されます。F・ドストエフスキーの作品など超絶に長いですし、そういう難解な物語や文学の好例でしょう。こういう本を読むときは、どうしたらいいか? 著者によれば、1つの方法は、わざとゆっくり読むことです。物語や小説は、どんなものでも、論理的文章より速く読めます。著者は、「ドストエフスキーの『罪と罰』や『カラマーゾフの兄弟』など相当長いのですが、最初はちょっと読むのに苦労しても、最終的には数日もあれば最後まで読めるつくりになっています。また、そういうスピード感を持って読まないと、面白くないという人もいるでしょう。私も、実はその一人です。ただ、ストーリーを理解するだけなら、そういう読み方でもいいかもしれませんが、それだと読み落とすところも多くなるのです」と述べています。
「ストーリーを追いかけるだけでいいのか?」では、大人になったら、たとえ物語でも、ストーリーを追いかける読み方だけでは飽き足りなくなることが指摘されます。なぜなら、小説や物語の魅力はストーリー展開だけではないと分かってくるからです。キャラクターの面白さや描写の妙、あるいは奇抜な比喩や語り方など、じっくり読むと感じられることがいろいろあるといいます。たとえば、ドストエフスキーの中編小説『地下室の手記』は、ストーリー的にはたいした起伏はありません。前半は、中年の男がグダグダと自分の部屋の中で悪態をついているところ、後半は、その男が、友人と飲みに行って煙たがられ、それから売春宿に行って冴えない女性と同衾するというだけの話です。著者は、「この作品の面白さは、圧倒的に前半の悪態にあります。あらゆるものに文句を言って軽蔑しまくる。果ては、悪態をつく自分も『バカだ!』と罵る。自分の言うことが結局自分自身を否定する言葉になっていて(俗に「ブーメラン」と言いますね)、この作品は、全体がブーメラン構造をしています。その語り口のしくみに気がつくと、この作品は俄然面白くなるのです」と述べます。なるほど!
「外国語で読む意外な効能」では、母語で書かれた作品を母語ではなく外国語で読むという方法が紹介されます。母語と比べて読むスピードは格段に落ちます。同じ箇所を何度も読まなければ意味が分からない場合もしばしばですが、そのために部分々々の感じはかえってくっきりと見えてくるといいます。著者は太宰の『人間失格』を英語で読んだことがあるそうですが、日本語で読んだときの陰鬱な感じがきれいさっぱりとなくなって、主人公の行動原理が、日本語より明確に、むしろ積極的に感じられるのに驚いたといいます。著者は、「『逃げる』行動にしても、英語で読むとなぜかアクティヴに感じられるのです。さらに、その印象について外国の友人と話すと『自分は、なぜ主人公に対してあんなに女性たちがやさしく接するのか、まったく理解できない』という反応が出てきました。自国語で読むと、主人公の惨めさにばかり注目して、彼を受け入れる女たちの行動に目が行っていなかったのです。ビックリしました」と述べています。わたしも日本文学の名作を英語で読みたくなりました。
「あとがき」では、本書を書くために、トマ・ピケティの本を完読する経験を得たのは幸運であったとして、著者は「あれほどのベストセラーになって、『ピケティを読む』などという解説本もあまた出ていたので、どんなに難解な本なのか、と身構えたのですが、実際読んでみると意外にも極めてシンプルな作りになっていて、『ややこしい本』の定石にピタリとはまっています。本来なら、解説本の必要もない明晰な書きぶりになっていることに感心しました。やはり『ややこし』くても、その背後にある文章作法は共通なのだ、という感を深くしました」と述べています。著者によれば、「ややこしい本」は、実は、まったくややこしくないといいます。ややこしいように見えても、その骨格は、きちんとした定式に則っているというのです。定式をきちんと理解して自分がどこを読んでいるか、さえ自覚すれば、「ややこしい本」の「ややこしさ」は軽減されて、その本の問題意識や解決法がより容易に直観されるしくみになっていると述べるのでした。本書は、わたしがこれまで漠然と思っていたことを言語化してくれた箇所が多々あり、とても多くの学びを得ることができました。