- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2427 メディア・IT 『生成AI時代の言語論』 大澤真幸/今井むつみ/秋田喜美/松尾豊著(左右社)
2025.10.27
『生成AI時代の言語論』大澤真幸/今井むつみ/秋田喜美/松尾豊著(左右社)を読みました。メインの著者である大澤真幸氏は、1958年長野県松本市生まれ。東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得満期退学。社会学博士。千葉大学文学部助教授、京都大学大学院人間・環境学研究科教授を歴任。『ナショナリズムの由来』で毎日出版文化賞、『自由という牢獄』で河合隼雄学芸賞を受賞。著書に『不可能性の時代』『〈自由〉の条件』『社会学史』『経済の起原』『資本主義の〈その先〉へ』など多数。共著に『ふしぎなキリスト教』『おどろきの中国』『げんきな日本論』などがある。現在、個人思想誌『大澤真幸 THINKING「O」』刊行中。
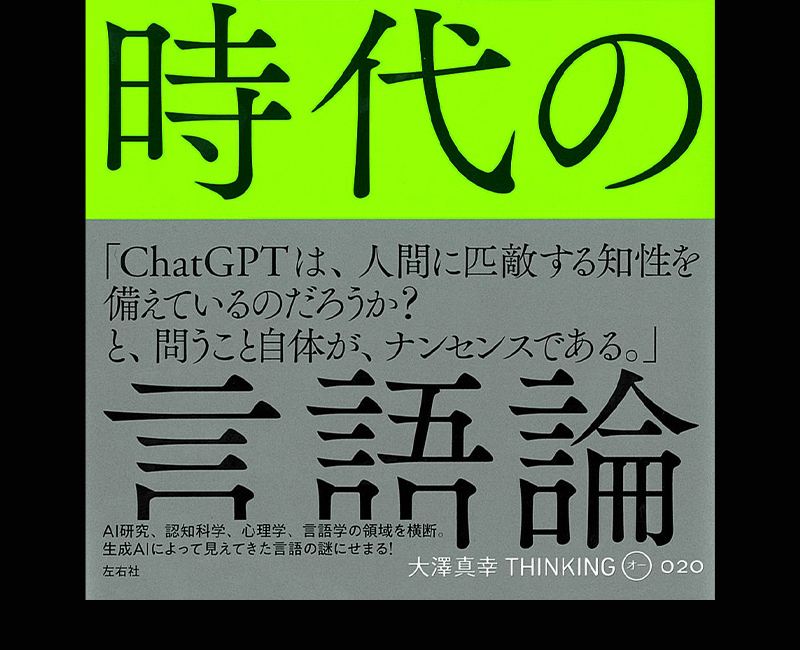 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、「ChatGPTは、人間に匹敵する知性を備えているのだろうか?と、問うこと自体が、ナンセンスである。」「AI研究、認知科学、心理学、言語学の領域を横断。生成AIによって見えてきた、人間の言語の謎にせまる」と書かれています。
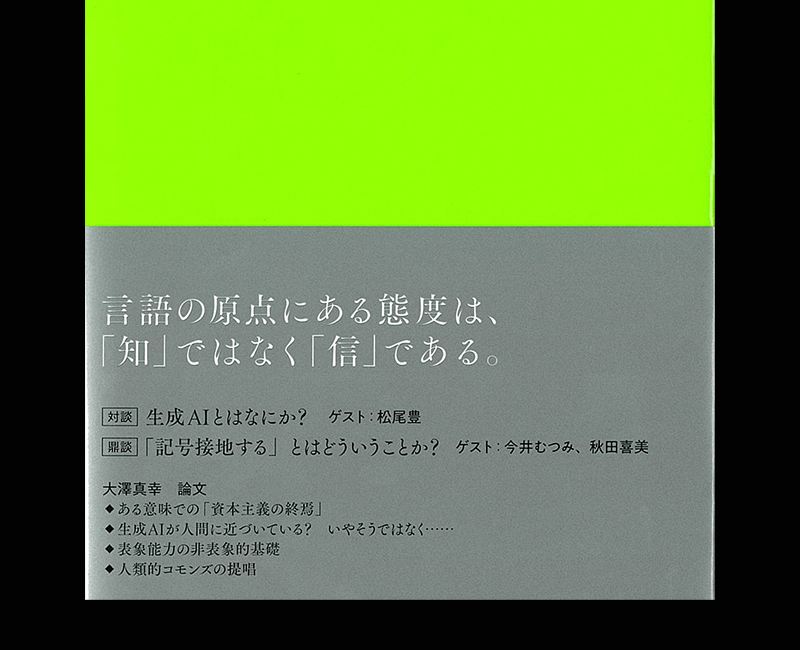 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏は「言語の原点にある態度は、『知』ではなく『信』である。」として、対談「生成AIとはなにか? ゲスト:松尾豊」、鼎談「『記号接地する』とはどういうことか? ゲスト:今井むつみ、秋田喜美」と書かれ、大澤真幸論文として、「ある意味での『資本主義の終焉』」「生成 が人間に近づいている? いやそうではなく」「表象能力の非表象的基礎」「人類的コモンズの提唱」の4本の論文のタイトルが並んでいます。
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「まえがき」
第Ⅰ部 対談・鼎談
対談 生成AIとはなにか?
松尾豊+大澤真幸
鼎談 「記号立地する」とはどういうことか?
AIから考える人間と言語の関係
今井むつみ+秋田喜美+大澤真幸
第Ⅱ部 論文――大澤真幸
小論 ある意味での「資本主義の終焉」
小論 生成AIが人間に近づいている?
いやそうではなく・・・・・・
論文 表象能力の非表象的基礎
記号接地はいかにして可能か
Ⅰ 記号接地問題
Ⅱ 言語による表象の2つの失敗
Ⅲ 言語と世界の適合方向
Ⅳ 共同注意の三角形
Ⅴ 音楽の作用
補論「オノマトペ」をめぐる覚書
論文 人類的コモンズの提唱 生成AIから考える
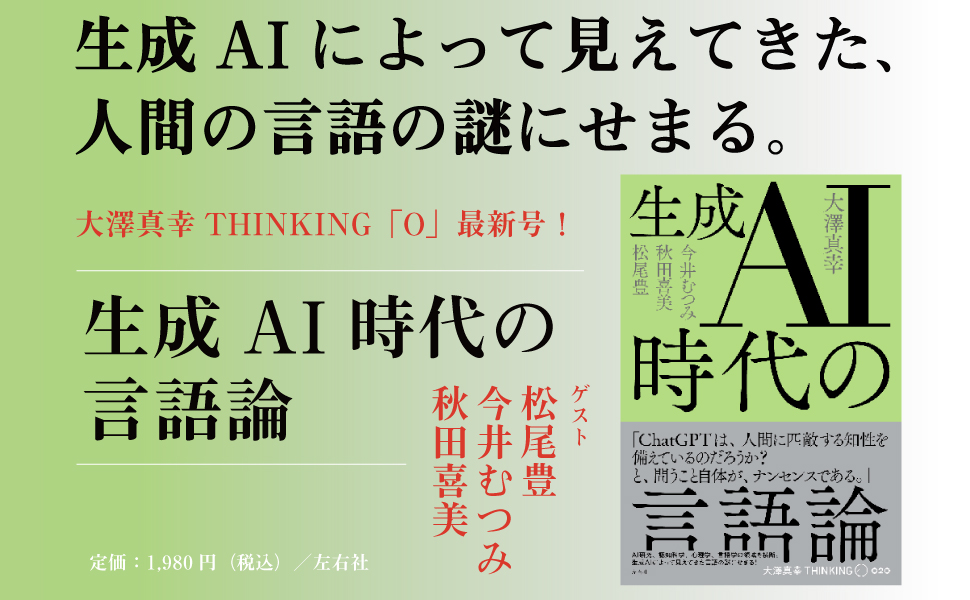 アマゾンより
アマゾンより
2024年刊行の本書の「まえがき」冒頭を、大澤氏は「昨年2023年は、大規模言語モデルに基づく生成AIが一般の人々の前に姿を現し、普及し始めた年として記憶されることだろう。もちろんその種の生成AIの代表が、ChatGPTである。人々は驚いた。このAIは、ほんとうに話しているように感じられる。何を尋ねても、そこそこ適切な答えが返ってくる。少なくとも、私の質問を理解しているかのような答えが返ってくる。私とAIの間でまともな会話が成り立っているような感じがする」と書きだしています。
大澤氏は、続けて「おそらく、一般の人々よりも前に、生成AIの開発者自身がもっと驚いたのではあるまいか。こんなにできるとは! これほどの成果は、開発者たちさえも予想していなかったに違いない。というのも、ChatGPTなどの生成AIの仕組みのことを思えば、この機械が、人間的な意味では思考していないこと、私たちと同じようには文を生成していないことは確実だからだ。生成AIがやっていることは、簡単に言えば、膨大な量のデータから単語のつながり方のパターンを見出し、統計的な観点からもっともらしい文をアウトプットすること、である」と述べます。
この資本主義の、資本主義ならざるシステムへの、すでに始まっている転換は、しかし、望ましい変化ではないと、大澤氏は言います。なぜなら、それは、資本主義の難点とされてきたこと、つまり不平等化や搾取をより過激なものに置き換えるような変化だからです。しかし、この変化を、柔道でいう「返し技」のように活用すれば逆に、これらの難点を克服した新しいシステムへと変動を促すこともできるのではないかとして、大澤氏は「その際、来るべき生成AIの国際的な管理ということが、この変動を引き起こす発火点のようなものになりうる」と述べるのでした。
第Ⅰ部「対談・鼎談」の「生成AIとはなにか?」をテーマにした大澤氏と松尾豊氏(東京大学工学系研究科教授)の対談では、松尾氏が「生成AIは、画像や言語、音声などを生成できるAIのことです。そのなかで、言語生成を行なうものが大規模言語モデル(LLM)です。これは従来の言語処理の性能を大きく超えたものです」と説明します。
松尾氏によれば、現在の大規模言語モデルは旧来と大きく2つの違いがあります。1つは、与えたテキストの次の単語を予測する学習をさせて、適切な単語を回答する能力を獲得させること。これは「ネクストワード・プリディクション Next Word Prediction」と呼ばれています。この過程で、文の背後にある文法構造や、単語の因果関係なども学習するので、この事前学習を行わせた後で翻訳や要約といった具体的なタスクをさせると精度が上がるのです。
もう1つは、トランスフォーマーという仕組みです。トランスフォーマーとは簡単にいうと、AIを動かすエンジンを作るための主たる技術です。従来よりも柔軟な処理が可能なアテンションという仕組みをたくさん使います。そしてトランスフォーマーを使ったモデルを、さきほどのネクストワード・プリディクションで訓練すると、さまざまなタスクに対して精度の高いAIができます。松尾氏は、「モデルが大きくなるほど、つまり、パラメータ数が大きくなれば精度が上がるのですが、GPT3やGPT4は非常に大きなパラメータのモデルを大量のデータで学習させることで精度が大きく向上しました。それを一般の人が使えるように対話用にチューニングしたものがChatGPTです」と述べます。
ChatGPTがここまで流行ったのは、開発したOpenAI社も意外だったのではないかと推測し、松尾氏は「対話という一般の人も使いやすいインターフェイスだったことが、要因の1つだと思います。またそれだけでなく、炎上しないように、ヒューマンフィードバックに基づく強化学習も徹底して行なっていて、差別的な発言や攻撃的なことを言わないようになっている。それもあって誰もが安心して使えるので、ここまで急激に広がったんじゃないかとも思いますね」と述べています。
「生成AIはフレーム問題を解決したか」では、大澤氏が「AIが有意味に何かを考えているということを認定できるためには、少なくとも2つの基本的な問題を克服できていなくてはならない、と私は考えています」と述べます。また、彼は「フレーム問題」を取り上げます。フレーム問題は、特定の課題だけを処理する知能には関係のないことで、さまざまな課題を処理するような汎用型の知能に対してだけ関係した問題です。無論、人間の知能は、そのような汎用型の知能のひとつです。汎用型の知能について、大澤氏は「それぞれの状況において、何かアクションを起こす際に、そのときどきの課題やタスクとの関係で有意味(レリヴァント)なことを、どちらでもよい(イレリヴァントな)ことから、十分に効率的に――たいていは一瞬のうちに――区別し、選択できなくてはなりません。ほとんど無数のことができるのに、今は、ある特定のことにだけ注意を向けなくてはならない。そんなことが、いかにして可能か、というのがフレーム問題です」と述べています。
「記号接地せずに現実世界を語れるか」では、もう1つの重要な問題が取り上げられます。それは、記号接地問題 symbol grounding problem です。わたしたちの言葉は意味をもっています。意味をもっているということは、言葉が、その言葉の外にある実在と結びついているということです。たとえば「いぬ」という言葉は、実在する犬という動物を指しています。もちろん、この場合の「実在」は、ユニコーンのような想像的な実在のような狭義の実在を超えたものも含みますから慎重にならなければなりませんが、いずれにせよ、言葉が何かを意味していると言えるのは、言葉という記号が、記号を超えた、あるいは記号以外の実在を指し示しているからです。記号接地問題とは、記号(言葉)を外部の実在とどのように結びつけるのか、という問題です。大沢氏は、「そこで伺いたいのは、人工知能はこの問題を解決できるのか、あるいは解決できているのか、ということです」と述べます。
「AIの導入でブルシット・ジョブが増える?」では、松尾氏が「一番の誤解は、いま人間が生産活動に寄与する意味のある仕事をたくさんしていると考えることです。これはまったくの誤解です。ほとんどの仕事は意味がないとまでは言わないですが、我々はもう物質的な豊さなどとは別の次元で仕事をしているはずです。普通に食っていくだけなら、何十年も前に人類全体が寝て暮らせるはず。そうならないのは、違うゲームを始めてしまっているからで、人間がそういう性質を持った生き物であるから」と述べます。松尾氏は、生成AIが進化することによって、生産と仕事は益々乖離してくると思うそうです。ですから、人の仕事はなくなることはないといいます。
「自由意志という幻想」では、大澤氏が「生成AIの活用についてポジティヴな側面だけでなく、ネガティヴな側面についても考えたいと思います。哲学者のニック・ボストロムはAIが発達すると、化学兵器を非常に効率的に、僅かな時間で発明できるようになると警告しています。松尾さんは社会的に警告しなければいけない問題として、たとえばどんな例を考えますか」と質問すると、松尾氏は「ある国がトップダウンにAIを軍事的に使ったときに何が起きるかといったことは、やはり考えるべき問題だと思っています。日本のAIは米中に比べて遅れていますが、グローバルな議論に加わっていかないと意味がないと思いますね。一方で、AIが発展して人間を襲うといった話はよくされますが、こちらはSFに近いです。100パーセントありえないとはいえないまでも、人間が悪用するほうが確率的には圧倒的に高いです」と答えています。
「AIの間接的支配」では、危険性についての興味深いニュースを大澤氏が語ります。2023年3月に、アメリカのNPO「生命の未来研究所」が「GPT4を超えるAIの開発を半年間停止すべき」ということを呼びかけた公開書簡を出しました。この書簡は実際には効力を発揮せず、開発が止まった様子もないのですが、大澤氏が注目したいのは、この書簡に署名した人たちでした。日本人で署名した人がいたかどうかはわからないものの、1000人以上の著名人や知識人が含まれています。たとえばイーロン・マスクも含まれていました。つまり、むしろ生成AIの開発を先導している人、そのために投資している人、少なくともそういう人たちと近いところにいる投資家や知識人が公開書簡の主な賛成者になっているといいます。
署名者の1人に、あの有名な歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリがいました。 ブログ『ホモ・デウス』で紹介した彼の著書では、バイオジェネティックなテクノロジーが発達すると、脳や神経系やDNAに変更を加えて、何かの能力を高めたり、属性を変更したりする、ヴァージョンアップした人間が登場することになるだろう、と指摘しています。大沢氏は、「ハラリは、このヴァージョンアップした人間を、「ホモ・デウス」と呼んだ。いままでの人間の格差はせいぜい資産の格差、富の格差、所有物における不平等でしたが、やがて、いわば生物としての属性における格差が生まれるだろう、ということです。
ホモ・デウスに自分自身や自分の子供を改造するには、巨額のお金がかかるでしょう。そうすると、ごく一部の富裕層はホモ・デウスとなり、貧困層はホモ・サピエンスのままい続けることになります。この図式を使うと、公開書簡を通じてAI開発にブレーキをかけようとしているのは、まさにホモ・デウスになりそうな人たち、ホモ・デウス予備軍であるとして、大澤氏は「彼らこそ、生成AIが普及し、その利用者が増えたときに、そこからの利益を得られる人たちです。彼らは、いくら生成AIが普及しても、失業の心配などまったくない。しかし、その彼ら、ホモ・デウス(の候補者)すらも、生成AIを恐れている」と述べています。
松尾氏は、「むしろ僕がこれから起こると思っている変化のうち興味があるのは、人間という存在が解体され、暗黙の前提としていたものがすべて覆ってしまうことです。それによって、人間の生き方や、社会のあり方を考え直さなくてはならなくなる」と述べます。一方、大澤氏が懸念しているのは、集合的な意思決定、つまり政治的意思決定を生成AIの判断に任せるようになったとき、どのようなことが起こるかということだといいます。そのような状態になると、AIが人間を支配しているのと同じ状態が出現するかもしれないとして、大澤氏は「事実、能力のない政治家が判断するよりも、AIが判断したほうが成功する確率が高くなることもありえます。国会答弁だってすでに、無能な閣僚ではなく生成AIが作成したほうが説得力がある……と言えるような状況になりつつあります」と述べています。
「コミュニケーションはどう変化する?」では、大澤氏が「ChatGPTとのコミュニュケーションは楽ですね。たとえば、生成AIに侮辱的なことを言ってもAIは傷つかない。それどころか、礼儀正しく返答してきます。こういうコミュニュケーションは人間側にとってはたいへん快適です。が、しかし同時に私は、コミュニュケーションの本質といいますか、コミュニケーションのまさにコミュニケーションたるゆえんに反しているようにも思います」と率直な感想を述べています。また、「日本のAI開発の未来」では、生成AIは、究極的に完全な共有物、人類的なコモンズのひとつにする必要があるとして、大澤氏は「いまでも、生成AIの使用法や運営の仕方については国際的なルールを決めようという動きがあるわけですけど、それ以上のことが、つまり生成AIなるもののこの人類社会における存在の仕方、何ものとして、誰のものとして存在しているのかということに関するルールや制度が必要です」と述べるのでした。
「『記号接地する』とはどういうことか?」「AIから考える人間と言語の関係」をテーマにした鼎談では、大澤氏が認知科学者の今井むつみ氏、認知・心理言語学者の秋田喜美氏の2人と語り合います。「人工知能は記号接地ができるのか」では、今井氏が「記号接地問題を解決するためにロボットは生まれたのだと思います。単なる処理だけでいいなら、CPUがあれば構わなかったはずです。でも、それだと記号接地問題は解決できない。だから、手足を付け、センサーを備えさせて、ロボットをつくったのでしょう。視覚、聴覚、触覚のセンサーさえあれば、それによって得た感覚をもとに記号と対象の対応づけができる。人間と同様の言語の習得も可能である、と。記号接地問題のブレイクスルーはそこから生まれるのではないかと、初期の開発者たちは考えたのではないでしょうか。現在も画像認識ができれば記号接地問題は解決できたことになるはずだと主張する人も少なくありません」と述べています。
「音楽家はなぜ記号接地できたのか?」では、人類の言語の起源には音楽が関係する可能性があることが指摘されているとして、秋田氏は「古来より音楽とは、儀式的に共同体のなかでつくられるものでした。その音楽には感情価、つまり、メロディーやリズムにアイコン的に付帯する何かしらの情動の質感が密接に結びついています。例えば、長調だったら楽しい感情、短調だったら少し暗い気分、という具合に音楽は聴く人の感情と連関するわけです。よく似たリチュアライゼーション(儀式化)は、オノマトペを起点とした言語進化論でも提案されています。場面場面で即興的に、その時々の音と調子で行なわれていたオノマトペ的発声が、共同体のなかで使われるうちに固定化していき、言語のもととなったという仮説です。さらに、先ほど話題になったように、感情価はオノマトペを捉えるうえでも重要な意味特徴です。つまり、感情とのアイコン的結びつきという点においても、共同体におけるリチュアライゼーションという点においても、音楽とオノマトペには共通点があると言っていいでしょう。アイコン性と感情価については、認知障害をもった音楽教師がなぜ音楽を口ずさむと記号接地できたのかを考えるうえでも、ヒントになりそうです」と語ります。
「言語の起源をめぐって」では、大澤氏が、認知考古学の領野を切り拓いた研究者にスティーヴン・ミズンを取り上げます。考古学というと骨や化石を対象とした、生活のマテリアルな側面に対する研究がこれまでは主流でしたが、彼は考古学的な証拠をもとに人間の心の進化について考えるユニークな研究を始めました。スティーヴン・ミズンには、『歌うネアンデルタール』という著書があります。大沢氏は、「言語の起源、言語がいつどのように生まれたのかについては、通説はありません。特に、ホモ・サピエンスより以前に出現した古い人類の種が、どのくらい言葉をもっていたのかについては、専門家の意見も分かれています」と述べています。
ネアンデルタール人やホモ・ハイデルベルゲンシスは、言語をまったく持たないか、持っていたとしてもきわめてプリミティヴなものだったのではないか、と考える専門家は多く、大澤氏もその説に説得力があると思っているといいます。ミズンは、この説に異を唱えたのではなく、この説に大胆な仮説を付け加えました。彼らは、歌でコミュニケートし、互いの間の連帯を感じていたのではないか、というわけです。大沢氏は、「言語以前の話をしているわけですから、歌詞付きの歌ではありませんが、歌詞などなくても歌えます。その歌は、ダンスとはっきりと区別されていなかったでしょう。ミズンは、言語の前に、歌・音楽があった、というわけです。言い換えれば、そのような歌から言語が発生したのだ、というのが彼の説です」と説明します。
今井氏が若い頃、ネイティヴ・アメリカンのアートを買い付けているアメリカ人の友人がいたそうです。彼女は、普通では入れない部族の儀式に入り込んで売買を行なっている人でした。彼女の案内で今井氏も一度、ホピ族の儀式にこっそり入れてもらったことがあったとか。今井氏は、「スカーフで顔を隠しながら、普段は見ることのできない儀式を覗かせてもらいました。驚かされたのは、彼らの声が、地の底からせりあがってくるように響きわたる、その光景です。まるで地面から声が生まれてくるように、儀式的な歌が歌われていました。メロディや韻律は確かにあるので音楽といえば音楽なのでしょうけど、どちらかといえば、地鳴りに近かったのを覚えています」と述べています。
今井氏が「確かに大澤さんがおっしゃったように、彼らはみんな1つになって踊っていました。歌いながら一体化していたわけです。あの行為こそ、コミュニティをつくるうえで非常に重要な営みなのでしょうね」と言うと、大澤氏は「音楽とは、考えてみると不思議なものです。何か生活に役立つかというと決してそうではない。しかし、原初の頃から人類にとって欠かすことができない営みの1つでした」と述べます。すると、今井氏は「音楽というと現代の私たちは音階あるいは歌詞のあるものを思い浮かべがちですが、必ずしもそうとは限らない。むしろ、太古の時代から奏でられてきたのは、あのとき私が耳にしたホピ族の儀式のような音楽だったわけです」と言うのでした。
ここで大澤氏は、ロビン・ダンバーという人類学者を取り上げます。「ダンバー数」の発明者として知られる彼は、霊長類の集団の規模は、大脳の新皮質の大きさと正の相関関係があるとして、後者から前者を導き出す公式を見出しました。よく知られているように、それによると、人間の集団の安定した規模は150人になります。このダンバー数についてはともかくとして、そのダンバーは、言語の音楽起源説に対してとても好意的な見解をもっています。そのうえで、彼は、音楽よりもさらに深く、言語の起源を遡っているとして、大澤氏は「歌が言語の前史だとして、その歌の前史は何か。それは、ダンバーの仮説では、『笑い』です」と述べます。
考えてみると、ヒト以外の動物はほとんど笑いません。チンパンジーなどの大型類人猿は稀に笑いますが、それはたいてい遊んでいるときで、遊ぶのは子どもだけですから、成熟した大型類人猿はほとんど笑いません。それに対して、わたしたち人間は絶えず笑っています。大沢氏は、「ネアンデルタール人のような旧人は、僕らのような言語を話さなかったとしても、歌ったかもしれないと言いましたが、それより前のたとえばホモ・エレクトゥスのような原人にとっては、その歌さえもハードルが高いと思いますが、しかし笑いならどうでしょう。彼らは笑ったかもしれない。笑いと言語は一見、かけ離れていると思われるかもしれませんが、間に原初的な音楽を入れてみると、連続性が見えてきます。歌やダンスの重要なところは、多数の個体が同期して、一緒に歌ったり、踊ったりできることです。笑いについてもそうです。私たちは一斉に笑う。笑いは、同調させる力があって、誰かが笑うと、意味がわからなくても人は笑ってしまいます。笑いは、原初の合唱ではないか、と思います」と述べるのでした。「笑い→歌や踊り→オノマトペ」には連続性があるのです。
「人間にとって言語の本質とは何か?」では、「ブートストラッピング・サイクル」が取り上げられます。ブートストラッピングというのは、靴(ブーツ)の履き口にあるつまみ(ストラップ)を自分でひっぱって、靴を履くことですが、そこから、自分の力で自分をより高めたり、よくしたりすること、その種の自己組織的なメカニズムを表現する比喩としてよく使われます。言語についての知識が雪だるま式に増殖し、どんどん成長していく過程が、ブートストラッピング・サイクルになっているのではないかというのが今井氏と秋田氏の仮説です。一番もとには、身体や現実に接地している言語知識があるわけですが、それがあれば、その知識が、自己増殖的・自己触発的に成長し、成熟した言語知識になっていくのではないか。大澤氏は、「このブートストラッピング・サイクルがどのように働くかを説明するにあたって、お二人は、パースの『アブダクション』の概念を導入されています。ここが非常に興味深いポイントです」と述べています。
チャールズ・サンダース・パースはアメリカ史上最も重要な哲学者ですが、彼の言ったことのなかでも特に重要で、今日でも継承し検討するに値するのが、アブダクションという推論の形式がある、というアイデアです。アブダクションとは、次のようなことです。まず推論とは、前提から結論を導くことですが、その推論の形式として、伝統的には2つがあると考えられていました。演繹と帰納です。演繹とは、一般的な規則から、特殊な実例を論理的に導き出すことで、帰納は、いくつもの事象を観察し、その共通性から一般規則を導き出す推論です。普通は、推論にはこの2つのタイプしかないと考えるわけですが、パースはこれらに加えて「アブダクション」という推論の形式がある、と主張しました。
アブダクションというのは、驚くようなこと、不可解な事象があったとき、ある仮説を置いてみる。その仮説を前提にして、その奇妙な事象が自然に説明できるならば、その仮説をとりあえず真と認めよう、ということだと説明し、大澤氏は「科学史上最も有名なアブダクションは、次のものです。りんごは地面に落ちる……けれども、月は落ちてこない。ふしぎなことですが、ここで、すべての物体の間に作用する万有引力なるものがあると仮定してみる。すると、りんごが木から落ちることも、月が地球の周りを公転することも統一的に説明することができます。これがアブダクションです」と述べます。
ヘレン・ケラーが手のひらで冷たい水を受けながら、もう片方の手にサリバン先生がwaterと綴りました。大澤氏は、「その瞬間、彼女が感じた驚きと歓び。このとき、彼女の経験には、単に、『水』というモノの名前を知った、ということにはとうてい還元できない、もっとも劇的な転換があったと思うんですね。僕らも、知らないモノの名前を教えてもらって、たとえば『これは、iPadというんだよ』などと教えてもらって、ひとつ知識が増えるというようなことがあるわけですが、ヘレン・ケラーがこのとき体験したことを、これと同じようなものだと考えたら、おおまちがいです。ヘレン・ケラーはこのとき、ひとつ新しい知識を増やした、ということではおそらくない。このとき、彼女にとっては、世界の見え方が、いや世界そのものが根本的に変容したのだと思う」と述べています。
世界そのものは根本的にどう変容したのか。「水」に限らず、すべてのモノには名前がある、そのような意味において、世界はカテゴライズされたものとして存在している、ということの発見です。それが存在しているということとそれが名前をもつということとは別のことではない。「名前をもつことにおいて存在する」というような様式で、世界のなかのすべての事物は存在している、ということをヘレン・ケラーは“water”の瞬間に発見したのだとして、大澤氏は「僕らは、気づいたときには、すでにヘレン・ケラーが発見したような様式でモノが存在している世界のなかにすでに入ってしまっているのでわかりませんが、彼女は、まさにそのような世界に入った瞬間をなまなましく体験したのでしょう」と述べるのでした。
「知っていることと、しんじること」では、大澤氏は、アブダクションの原型には、もしかしたら「信じる」という態度、心の構えがあると言えるのではないかと推測します。直接に知覚したり、感覚したりしてもいないものに関して、それを信じるという心のあり方は、人間に特有なものではないかというのです。また、信仰の問題について、大澤氏は「僕らが宗教的信仰とみなしている6つの特徴、アニミズムとか、シャーマニズムとか、死後の世界の存在とか、超越神とかの6つの特徴に関して、それらが現在の30個くらいの狩猟採集民にどのように分布しているかを調べた研究があって、それによると、最も広く、そして最も古くからあると推定される特徴は、アニミズムです。死後の世界についての観念はないところもあるし、道徳的な超越神はもっと稀です。アニミズムというのは、動物とか、そのほかの自然物に対しても、あたかも同種の他の個体(人間の仲間)に近いものとして接する態度ですから、広義の社会性のなかに含まれます。おそらく、アニミズム的な宗教は、ホモ・サピエンスの最も初期からあると思います」と述べています。
ある有名な社会学者が「宗教が社会現象なのではなくて、社会が宗教現象なのである」という言葉を残しています。宗教ということを最も広くとると、この洞察はまったく妥当だとして、大澤氏は「人間はわからないことがあると、大きな不安を感じる存在です。しかし、社会がある段階にまで成熟すると、自分が知らなくても誰かが知っていれば十分に安心できてしまう。そこに信仰的なコミットメントがあるわけであり、このことは、私たちの行動自体が、実は信仰の構造をもっていることを示しているのではないでしょうか。社会現象が宗教的だというのは、その意味でもとても正しい言葉だと私は思っております」と述べています。
ただ、このことは近代以前と近代以後で、分けて考えたほうがよいといいます。たとえば、近代以前の社会には、宇宙についての真理をすでに知っているとされる特権的な少数者がいました。神官とか、預言者とか、賢者とか、覚醒者とか、と言われる人たちです。ときには、その真理を知っている特権的な一者が、「神」というかたちで、人間から超越したところに幻想的に措定される場合もありました。大澤氏は、「ともあれ、そのような特権的な少数者が真理を知っているという想定があれば、一般の庶民、ほとんどの人は直接には真理を知らなくても、宇宙の秩序に対する信頼をもつことができ、安心して暮らすことができたわけです。しかし、近代科学以降は、状況が変わる。まず、真理にアクセスできる特権的な者などというものはいません。原理的には、誰もが真理にアクセスできる、というのが近代科学の大前提です。しかし、同時に、実際には、誰一人として最終的な真理を知らない、というのも近代科学の前提です」と述べます。
近代科学の説は、通説としてほとんど確実視されているものもふくめて、原理的に言えば、すべて仮説であって、「真理の候補」かもしれませんが、「真理」そのものではありません。大澤氏によれば、「真理」が、すでに特権的な少数者に知られているという状態(近代科学以前)から、「真理」に誰もがアクセスできるはずなのに、誰一人として到達できていないという状態(近代科学)へ。近代科学における真理は完全に証明されているのではなく――というか完全な証明などということは原理的にありえず――、非常に信憑性の高いアブダクションが重なっているだけだといいます。最終的な真理が知られていないという前提でも機能しているという点で、かつての宗教的信仰との大きな違いがあります。
第Ⅱ部「論文――大澤真幸」の小論「ある意味での『資本主義の終焉』」では、冒頭の「ChatGPTの登場」を、大澤氏は「生成AI、とりわけChatGPTの性能に、人々は驚愕し、そして恐怖すら覚えている。ChatGPTは、人間に匹敵する知性を備えているのだろうか? と、問うこと自体が、ナンセンスである。なぜなら、ChatGPTがやっていることと私たちの知性がやっていることは、まったく別のことだからだ。別のことをやっているのに、『答え(アウトプット)』はほぼ同じになるということは、もっと驚きではあるが、まずは、私たちが知性の働きと見なしているものとはかなり異なった操作に基づいていることは確認しておかねばならない。ChatGPTのベースにある大規模言語モデルとは、単語列より成るテクストがあったとき、そのテクストの『続き』を予測するものである。つまり、次にくる単語を予測することが、このモデルの課題である」と書きだしています。
「何が恐れられているのか」では、哲学者のニック・ボストロムが唱えてきたディストピアが取り上げられます。ボストロムは、近未来に、人間の知能をはるかに凌駕するAI、すなわちスーパーインテリジェンスが出現するかもしれず、このとき私たち人類は、滅亡リスクに直面するかもしれない、と述べていました。たとえば、今日ゴリラが絶滅せずに済んでいるのは、人間がゴリラを保護しているからだ。ゴリラの存在は、人間の「善意」に依存している。同様に、やがて、人類が生き延びられるとすれば、それは、スーパーインテリジェンスに善意があった場合だけだ、ということになるかもしれない。ハラリは、チンパンジーと人類との区別に相当する分裂が人間社会の内部に孕まれると主張していたわけですが、ボストロムのヴィジョンでは、同じタイプの区別が、スーパーインテリジェンスと人類との間に生まれるのです。
小論「生成AIが人間に近づいている? いやそうではなく……」の「個人の自由・自律性への脅威」では、すでに恐れられ心配されていることは、芸術作品の場合であることが示されます。あるアーティストが生成AIを使って作った画像を活用したとき、それは、このアーティストの作品なのか。どの程度までなら、そのアーティストの創造性に帰することができるのか。小説が、生成AIによって書かれたときにはどうなるのか。プロンプトを通じておおまかな設定を指定した人を、その小説の著者と認めてよいのか。そのような問題が提示されます。
大澤氏は、「このように、生成AIが、個人に帰せられてきた自由な思考、自由な判断、自由な意思決定ということに対して、脅威となる。生成AIは利用のされ方によっては、個人の自由と自律性を骨抜きにする。いや、それどころか生成AIは、個人の自由や自律性といった概念そのものの自明性を切り崩すポテンシャルをもつ。私たちの社会は、個人の自由や自律性を前提にし、それを倫理的にも望ましいことと見なして成り立っているので、このような生成AIの影響は、実に破壊的である。私はだから、生成AIは、個人の自由や自律性にとって危険な因子となりうるという主張は妥当だと考えるし、これに共感もする」と述べます。
「穏当な結論」では、そもそも、個人の行動や心の働きに帰せられている「自由」とか、「自律性」とかといった性質は、一種のフィクションであると述べられます。人間の行動や意思が因果関係から超越しているわけではありません。もっとも、「それらは幻想なのだから除去することができる、除去すべきである」というわけではないとして、大澤氏は「それらは、私たちがそこから逃れられないし、逃れるべきでもないフィクションだ。『自由』や『自律性』は、カントが言うところの超越論的仮象である。普通の仮象は、理性によって取り除くことができる。しかし理性がどうしても必要とする仮象、理性がまさに理性的であるために前提にせざるをえない仮象がある。そうした仮象をカントは『超越論的仮象』と呼んだ。人間の一人ひとりが自由に意思決定し、自律的に行動しうると仮定しない限り、何が正しいか、何が善いことなのか、ということを考えること自体が無意味になってしまう」と述べています。
生成AIは、私企業である巨大プラットフォーマーの管理下にあります。わたしたち利用者は、生成AIがどのようなアルゴリズムに従っているのか、どのようにチューニングされているのか、どんなバイアスがかけられているのか、まったく知りません。利用者は、私企業の利益にかなうように、少なくともその私企業に不利益にならないように、AIの回答を通じて誘導されているかもしれないのです。この問題に対しては、次のように対応することが究極の解決策であろうとして、大澤氏は「地球上の何億人もが使用する生成AIと結びついた巨大デジタルプラットフォームは、人類レベルのコモンズ(共有物)とすべきである。それは、コモンズにふさわしいかたちで管理・運営されなくてはならない。つまり、人類のレベルでの民主主義的な管理・運営に委ねられなくてはならない」と述べるのでした。大胆かつ的確な提言であると思います。
「生成AIが人間に近づく? その逆だとしたら?」では、生成AIというものが、人間の人間たる条件のどの部分に、どのように作用しているのかを正確に見究める必要があるということが述べられます。そして、生成AIが普及したとしてもなお、人間が、その生の有意味性を保ちうるとしたら、それはどのような場合なのか、考えておく必要があるといいます。生成AIが与えるさまざまな利便性への代償として、生きることの意味、生きることの充実の最も根幹的な部分が失われないようにしなくてはならないとして、大澤氏は「私たちは、生成AIの能力が人間の言語能力や認知能力の水準に達しているかということをたえず気にしている。しかし実際には、私たちの方が、自分の言語についての経験を、むしろ生成AIの方に適合させようとしている。生成AIが人間に近づいてきているのではなく、人間の方が生成AIに近づこうとしているのだ。それは、言語をめぐる体験の核心部にあった宝物を、自分から放棄することに等しい」と述べるのでした。
論文「表象能力の非表象的基礎 記号接地はいかにして可能か」のⅠ「記号接地問題」では、記号接地問題は、もともと、認知科学の領域で提唱されたことが紹介されます。とりわけ人工知能AIに関する考察においてでした。スティーヴン・ハルナッドが、1990年の論文で、AIは実際には何ごとも理解してはいないということの証明の枢要な部分として、記号接地問題を定式化し、AIはこの問題を解決できていない、と論じました。AIは記号を操作する。デジタル化した記号を、です。つまり、AIは記号を記号に関係づけ、記号を別の記号に置き換えていきます。しかし、その記号はどこまで行っても、あるいはどこまで遡っても、外的な対象とは結びついてはいません。この状態を、ハルナッドは、「記号から記号へのメリーゴーランド」と表現したのです。
Ⅴ「音楽の作用」の3「音楽の進化的価値」では、音楽や歌は、一緒に歌い、音を鳴らし合う者たちの間の連帯感、絆を高める効果があるということが指摘されます。これが進化にとって価値があったと推測されるわけです。大澤氏は、「われわれは現在、一人でも音楽を聴いたり、歌ったり、楽器を奏でたりするが、本来は、一緒に歌ったり、奏でたりするのが音楽の原点であっただろう。最初の音楽は、ダンスと未分化だったに違いない。そして、ヒトの進化の歴史の中で、音楽・歌は、言語よりも先に出現しただろう。諸説あるが、言語は、現生人類(ホモ・サピエンス)とともに出現したと考えるのが妥当であろう」と述べています。
ホモ・サピエンスの祖先ではありませんが、その「いとこ」にあたるネアンデルタール人は、いくつかの間接的な証拠から判断して、「言語」をもちませんでした。少なくとも、われわれから見て言語と見なしうるようなコミュニケーションの手段を、ネアンデルタール人はもたなかったと推測されますが、大澤氏は「ネアンデルタール人も一種の音楽を――もちろん言語を使わない音楽を――もっていたと見なすことはできます。音楽は、おそらく、ネアンデルタール人とホモ・サピエンスの共通の祖先――ホモ・ハイデルベルゲンシス――あたりで出現したのではあるまいか」と述べます。
大澤氏の考える進化のストーリーは以下の通りです。
「(ホモ・サピエンスの出現に先立つ)人類の進化のある段階において、直接の血縁関係を超えた他個体との、意図的・積極的な協働が――生存と繁殖にとって――重要な価値をもつようになった、と考えられる。たとえば、育児における協働が必要になったのではないか。つまり直接の親以外の者が、育児に参加する必要が出てきたのではないか。さらに、おそらくより重要だったのは、採食行動における協働である。もちろん、彼らは狩猟採集民だが、たとえば生きた動物の狩猟に関して、意図的な協働がいかに効率をあげるかは、すぐにわかる。そのとき、必ずしも強い血縁関係のない個体たちの間の絆を強化し、互いの間の信頼関係を構築・維持するための戦略として発達したのが、一緒に音楽すること、一緒に歌い、踊ることだったと考えられる」
音楽を聴いたり、歌ったりすると、脳内の報酬系が活性化します。そしてエンドルフィンが分泌されます。この事実をどう解釈すればよいのでしょうか。毛づくろいをされているとき、エンドルフィンが分泌されることがわかっています。エンドルフィンが分泌されると、他個体への「共感」や「思いやり」のようなものが高まることが知られています。音楽は、他個体の身体に直接に触れることなくエンドルフィンの分泌を促しています。大澤氏は、「この事実は、音楽が、社会的グルーミングを代替する戦略として進化してきた、という仮説を支持する傍証のひとつである」と述べます。
論文「人類的コモンズの提唱 生成AIから考える」の2「資本主義はすでに終わり始めている?」では、ギリシャの元経済相でもある経済学者ヤニス・ヴァルファキスが現在の経済システムを「テクノ封建主義」と呼んでいることが紹介されます。ヴァルファキスによると、2008年(リーマンショック)以降、決定的な変化がありました。中心的なプレイヤーは、インターネットを舞台に巨大な収益をあげている資本です。とりわけGAFAMに代表されるプラットフォーマーの利潤の獲得の方法は、資本主義のやり方ではなく、(もともと資本主義がそれに取って替わってきたはずの)封建制のやり方になっています。つまり、彼らは資本家というよりもむしろ、封建領主になっている。これがヴァルファキスの診断の中心的なポイントです。
大澤氏は、「封建制というからには、荘園――つまり領主の私有地――があるわけだが、それは何か? アマゾンやフェイスブックといったデジタルなプラットフォームが、荘園にあたる。巨大なプラットフォームは、インターネットのデジタル空間の中にある、封建領主の領地にあたる」と説明します。プラットフォーマーの「荘園」にはどうして価値があるのかを考えてみるとよいでしょう。とてつもない数の商売人たちが、それを使わせて欲しいと願うほどにこの荘園には価値があります。どうしてなのか。この荘園の価値を高めるためにせっせと働いてくれる、「農奴」がいるのです。賃金労働者ではなく、農奴です。この仕組みが、封建主義的だとする根拠はここにある。領主が賃金をまったく払わないのに、荘園の価値を高めるためにただ働きをする農奴が、地球上に何億人もいるのです。
農奴とは誰のことか? 大澤氏は「農奴とは、プラットフォーマーが提供するサービスを利用している『我々』のことである。我々は毎日、プラットフォームを使って、検索したり、テクストや写真をアップしたり、買い物をしたりしている。このとき我々は、気前のよいプラットフォーマーにタダでサービスを提供してもらっている気でいる。しかし、この『無料の利用』こそ、ほんとうは、我々の未払い労働そのものである。X(旧ツイッター)で呟いたり、グーグルで検索したり、アマゾンで買い物したりすると、我々は、自分の個人情報を残す等、プラットフォーマーのストック――彼らの『荘園』であるところのプラットフォーム――の価値を高めるのに貢献している。我々は『ありがたい』とまで思いつつ、無料でサービスを利用しているつもりだが、これこそ、農奴の労働であり、我々の方こそ、無報酬で、領主のために働いていたのだ。今、グローバル経済に活力を与えているのは、インターネットのプラットフォーマーたちである。彼らは、その利益を、市場からではなく、デジタルな荘園から得ている。とすれば、それはもはや資本主義ではなく、一種の封建主義である。ヴァルファキスはこのように認定する」と説明しています。
3「封建主義化、それとも……」では、トマ・ピケティが設立した世界不平等研究所(World Inequality Lab.)なるシンクタンクが紹介されます。この研究所が2022年に発表した World Inequality Report 2022 によると、1995年から2021年までに蓄積された全地球の富の38%を、上位1%の富裕層が独占しました。つまり、この4半世紀の間に人類があらたに蓄積してきた富の4割近くが、グローバルな所得順位で上位1%の人のものになったのです。大澤氏は、「これほど法外な格差は、どんな理屈によっても正当化されない。資本主義の美点とされている業績主義は、この格差を正当化しないだろう(上位1%の人が、全地球の人口の40%近くの人の労働の合計に匹敵するほど偉大なことを為し遂げたとは誰も思うまい)。何かが根本的にまちがっているのだ」と述べます。
デジタルな荘園を特定のプラットフォーマーのものと見なすことは正当化できるでしょうか? 大澤氏は、「絶対にできない。プラットフォームを成り立たせている中核の技術は、いうまでもなくインターネットである。とするならば、デジタルな荘園は、人類の集合的知性の産物であって、特定の個人や法人の所有に帰してはならないモノである。それは、本源的にコモンズ(共有物)、人類の全体に属するコモンズだ。人類のモノを、特定の個人や企業が所有し、しかも封建制のやり方で利益を得たらどうなるか。とてつもない格差が生ずるに決まっている」と述べます。
そして、最後に大澤氏は「資本主義は終わりつつある。ただし、それは、封建主義へと向けて終わりつつあるのだ。資本主義の中心に封建制の原理を組み込むことは、資本主義の中で我々が苦しんできたこと、つまり経済的な不平等や搾取を、よりいっそう過酷なものとして再現することを意味している。我々がなすべきことは、この封建主義へと向かう趨勢を活用して、人類的なコモンズを構築することである。資本主義を封建主義へと向けて終わらせるのではなく、コミュニズムへと向けて終わらせよう」と述べるのでした。「コミュニズム」という言葉は気になりますが、大澤氏によるAIを人類的コモンズとする提唱には基本的に賛成です。本書を読んで、AIのみならず、これからの社会の在り方についても大きな学びを得ました。