- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2025.12.06
『葬式仏教』薄井秀夫著(産経新聞出版)を読みました。「死者と対話する日本人」というサブタイトルが付いています。著者は、株式会社寺院デザイン代表取締役。昭和41年、群馬県生まれ。東北大学文学部(宗教学)卒業。中外日報社、鎌倉新書を経て、平成19年にお寺の運営コンサルティング会社である株式会社寺院デザインを設立。檀家や地域に求められるお寺にするため、活動の再構築のサポートを行っています。著書に、『葬祭業界で働く』(ぺりかん社)、『10年後のお寺をデザインする』『人の集まるお寺のつくり方』『寺院墓地と永代供養墓をどう運営するか』『どこが違うの? お仏壇』(以上、鎌倉新書)など。
 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「布施や戒名への違和感の正体」「『教え』に興味がない日本人が仏教で葬儀をするのはなぜか?」「死者を想う気持ちとすれ違うお寺との関係をひも解く」と書かれています。
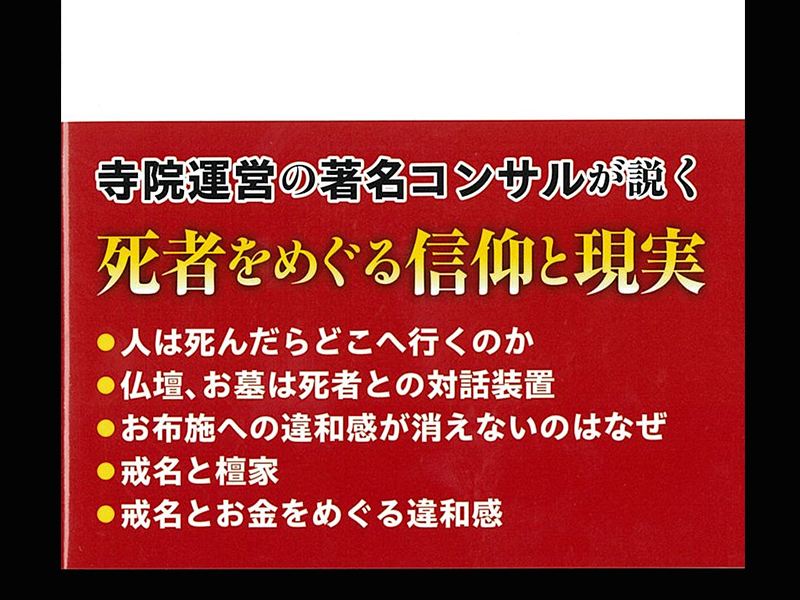 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には「寺院運営の著名コンサルが説く死者をめぐる信仰と現実」として、以下のように書かれています。
●人は死んだらどこへ行くのか?
●仏壇、お墓は死者との対話装置
●お布施への違和感が消えないのはなぜ
●戒名と檀家
●戒名とお金をめぐる違和感
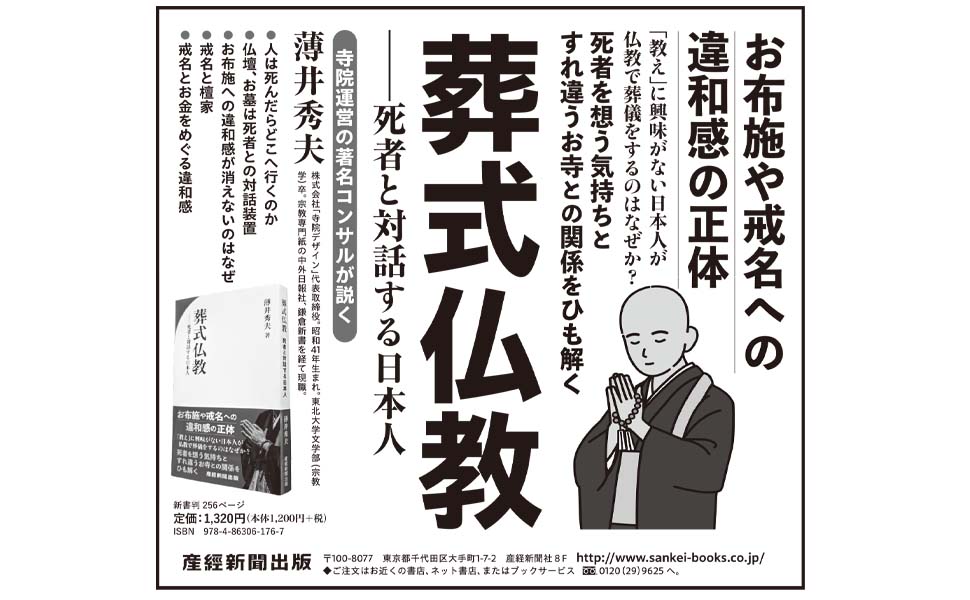 アマゾンより
アマゾンより
アマゾンの内容紹介には、以下のように書かれています。
「葬式仏教とは、葬送が活動の中心となっている日本特有の仏教だ。 なぜ日本人は『教え』に興味がないのに、仏教で葬儀を行うのか。日本人の死者を想う気持ちと、すれ違うお寺の関係をひもとく。お布施・戒名・檀家など制度や金額に釈然としない人たちが急増し、仏教離れが止まらない現代に“葬式仏教の光と影”をあぶりだす!」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
第1章 人は死んだらどこへ行くのか?
第2章 葬式仏教という宗教
第3章 死者と対話する装置
―仏壇とお墓
第4章 社会問題化するお布施
第5章 なぜお布施への違和感が
なくならないのか
第6章 戒名と檀家
葬式仏教の未来―むすびにかえて
日本仏教の主要宗派
「あとがき」
「はじめに」では、葬式仏教という言葉は日本の仏教を揶揄して使われがちであると指摘します。「本来、教えを説くべき仏教が、それをせずに、葬式ばかりしている」というわけです。著者は、「ほかの国に、こんな仏教はない。葬式仏教というのは実にヘンテコリンな仏教なのだ。しかし日本における葬式仏教の歴史は長い。室町時代の後半に生まれ、これまで500年以上にわたって日本人に信仰され続けてきた。そして現代でも、葬式といえば仏教である。お墓で、仏壇で、みな当たり前のように手を合わせている。葬式仏教は、批判されながらも、圧倒的な支持を得ているのだ」と述べています。信仰は単なる思想ではなく、人の営みであるといいます。そこには「大切な家族があの世でも安らかであって欲しい」という切なる想いが込められているのです。著者は、「葬式仏教は、日本人が生活のなかで信仰してきた、紛れもない宗教なのだ」と喝破するのでした。
第1章「人は死んだらどこへ行くのか?」の「[1]なぜ死者のことを[ホトケさん]と呼ぶのか」では、「多義的なホトケ」として、民俗学者の柳田国男は、「死者を無差別に皆ホトケというようになったのは、本来はホトキという器物に食饌を入れて祀る霊ということ」(『先祖の話』)と言っていることが紹介されます。つまり、死者にお供えする器の名前の「ホトキ」が変化して、死者の霊を「ホトケ」と呼ぶようになったと説明しているわけです。著者は、「ただ柳田は、この考えを想像説であると言っていて、どうも確信があるわけではないようである。ちなみに、仏陀(悟りを開いた人)のことを『ホトケ』と言うようになったのは、日本に仏教が入ってきたとき、『ブッダ』を『浮屠』と音訳し、それが変化したものとされている」と述べます。
「死んだらホトケの説得力」では、仏教の教義は、言葉や論理を駆使して、人が安らぎを得るための方法を説いていることが指摘されます。それは2000年以上にわたって発展してきた仏教の叡智です。ただ、深い教えになればなるほど、一般生活者にとっては難解になってしまい、誰もが理解できるものではなくなってしまいました。一方、仏教は民間信仰レベルで先祖供養という信仰を発展させ、死者の安らぎを祈り、死者に見守ってもらう信仰を深めてきました。「死んだらホトケ」という考え方には、そうした信仰が集約されているとして、著者は「ホトケという言葉が、仏(如来)や仏陀を意味すると同時に死者を意味することで、『死者が安らぎを得られる(仏陀になる)』『死者に見守ってもらえる(仏に見守ってもらえる)』という確信を象徴的に語ることになる。死者と仏、仏陀というそれぞれの意味の境界を浸食し、混乱させ、渾然一体とさせることで、死者があの世で安らかに暮らしており、私たちを見守ってくれる存在であることを印象づけるのだ」と述べます。
「[2]仏教は『千の風になって』が嫌い」では、「万葉の時代から続く素朴な感覚」として、秋川雅史が歌った大ヒット曲「千の風になって」について、「そこ(お墓)に私はいません」という歌詞に共感した人が、お墓参りをしないかというと、そうではないといいます。著者は、「『千の風になって』を聴いているときは、その歌詞に感動し、お墓の前に行くと、そこに大切な家族の存在を意識して手を合わせる。信仰はそういう曖昧さを持っている。人の心や信仰は、理屈では割り切れないのである。『千の風になって』の歌が多くの人に受け入れられたのは、現代人の信仰が浅くなったからでもなく、死生観が貧困だからでもない。むしろ、日本人の根っこにある感性に訴えかけるものがあったからではないだろうか」と述べるのでした。
「[3]魂はどこへ行った?」では、「宗派ごとにあの世は異なる」として、原始仏教では修行を重ねて悟りに近づくことが重要視されましたが、大乗仏教ではむしろ厳しい修行がなくとも悟りに近づけることが強調されることが指摘されます。要するに、「誰もが救われる」というのが大乗仏教なのです。日本に伝わった仏教は、さらに独特の展開をするようになります。特に法然が専修念仏を説いて以降、“専修”、つまりたくさんの教えや修行のなかからひとつを選んで、そこに専心するということが仏教界の主流になっていったことが述べられます。
法然以前の仏教は、厳しい戒律と多種多様な教えを包括した宗教でしたが、法然はそれを単純化し、誰にでもわかりやすい仏教を説きました。日本人にとっては、このシンプルな教えが馴染みやすかったようで、その後の日本仏教は法然の考えた“専修/単純化”の流れを進んでいきます。法然の専修念仏の流れを汲んだ親鸞も同様であり、禅を強調した道元、題目を強調した日蓮もみんな専修の道を歩んでいるとして、著者は「実は日本の仏教にさまざまな宗派があるのは、専修が大きな役割を果たしている。念仏にしても、禅にしても、題目にしても、どれかひとつだけを強調するため、別のものを強調するグループと相容れないのである」と述べています。
少なくとも近代以前の日本人は、「西の方角に極楽浄土が本当にある」と信じていたといいます。それは必ずしも、わたしたちが住んでいる世界と同じように“物質的な実体を持つ世界”ということではありません。仏さまの世界であり、この世界とは次元の異なる世界です。著者は、「この物質的な世界とは異なるという意味で、霊的な世界と言ってもいいだろう。そして、そうした世界が本当に西の方角に存在していると考えていた日本人は、決して少なくなかったはずである。ちなみに、法華経の霊山浄土は極楽浄土とはちょっと事情が異なり、実際にインドにある霊鷲山のことで、現在はチャタ山と呼ばれている。お釈迦さまが法華経を説いた地であり、インド仏跡ツアーなどで行くことができる」と述べます。
「統計調査が語る現代人のあの世観」では、日本人は世界でもまれに見るほど先祖の魂の力を信じている国民なのであることが指摘されます。考えてみれば、仏壇のある家では、そこにご飯やお茶、お菓子などを供えるのが一般的です。故人の好きだったものを供えるのは、そこに故人の魂がいるという前提があるからと言えます。災害のときに位牌を持って逃げる人も多いといいます。多くの日本人は、位牌を単なるモノではなく、そこに魂が宿っていると考えているからでしょう。著者は、「このように日本人の生活のなかには、無意識に“魂の存在”が前提となっている行動が少なくない。今後も科学は魂の存在を認めることはないだろう。先に述べたように、仏教もどちらかというと魂の存在を認めない傾向がある。科学も仏教も、魂否定論者なのである。にもかかわらず、現代の日本人は魂を信じている。魂に慣れ親しみ、先祖に手を合わせることの大好きな国民なのだ」と述べるのでした。
「[4]葬儀というドラマ」では、著者は「実は流れがわかると、葬儀はおもしろい儀式なのである(「おもしろい」というのも不謹慎であるが……)。お葬式の流れは、あたかも演劇のようなストーリーになっている。1時間足らずのあいだに、とてもドラマティックな展開が詰め込まれているのだ」と述べます。葬儀の流れは宗派によって異なりますが、著者は浄土宗と曹洞宗の葬儀について触れます。ちなみに浄土宗の葬儀は、序分(仏さまをお迎えする部分)、正宗分(仏さまの教えをお聞きし、死者を送る部分)、流通分(感謝して、仏さまをお送りする部分)の三部構成になっています。著者は、「この三つの構成を見るだけでも、葬儀がドラマのような展開をする儀式であることがわかるだろう」と述べています。
曹洞宗の葬儀の流れを紹介した後、著者は「通夜も含めた儀式全体が、あたかも演劇のようになっているところがわかるであろう。葬儀は、故人を無事あの世に送るための壮大なドラマでもあるのだ。参列者がこのストーリーを理解できれば、儀式に没入することができ、故人をあの世に送るドラマを象徴的に体験できるはずである」と述べます。ところが現実は、葬儀を退屈に感じている人は多いようです。本来、葬儀は退屈であるはずがありません。故人を送る真剣な儀式ですし葬儀自体が壮大なドラマになっているからです。これについて、著者は「退屈に感じるのは、ただ『わけもわからず』、座らされているからである。『わけも知らされず』と言ったほうがいいかもしれない。本当はドラマティックで、心を揺さぶられる儀式なのに、私たちは何も知らされず、ただただ終わるのを我慢して待っているだけなのだ」と述べるのでした。
「野辺送りの時代」では、現代は葬儀のなかで引導(死者が悟りを得られるよう法語を唱えること)を渡していますが、もともとは野辺送りで墓地まで行って、埋葬するときに引導を渡していたことが紹介されます。現代は土葬ではないため、葬儀会場での儀式のなかで「迷わずあの世に行くように」と棺に火をつける手振りを行い、象徴的に火葬するところで引導を渡すことになっています。野辺送りは、戦後にだんだんと行われなくなっていきましたが、著者は「地域の結びつきが弱まっていったため、葬列を組むことが難しくなったのが理由のひとつである。お葬式の会場が自宅でなく、葬祭ホールになったことも大きい」と述べます。火葬が一般的になり、土葬をしなくなってきたことも、葬列を組む意味を希薄にしました。土葬の場合は、葬儀後すぐに埋葬するため墓地へ向かわなければなりませんが、火葬の場合は葬儀当日に埋葬する必要はありません。著者は、「実は、野辺送りが行われていた時代は、葬儀のメインイベントは葬列を組んで歩くことにあった。家族・親族がみんな一緒に故人とともに墓地へ向かい、近隣の人はそれを見送るという風景は、日本人の葬送の原風景だったのである」と述べています。
現代社会においては、家族葬や1日葬が増えるなど“葬送のあり方”が激変しており、問題視されることが多いです。しかし、わたしたちが標準的と思っている葬儀自体が、ひと昔前の葬儀をかなり省略してできあがったものなのだと指摘する著者は、「残念なことに、参列者のことをあまり重視せずに省略してしまったため、葬式の意味をわかりにくくしたうえ、参列者をただの傍観者にしてしまった。野辺送りがなくなった理由は、火葬の普及に加え、地域社会と家族制度の変質が大きい。葬送が省略の道をたどってきた理由も、地域社会と家族制度の変質である。葬送の省略は時代の必然であり、やむを得ない。しかし、もう少し気の利いた省略の仕方もあったのではないかと個人的には感じている」と述べるのでした。
「[5]日本人はあの世をどう考えていたか」の「柳田国男が感じていた仏教人と人々のズレ」では、日本人の死生観と仏教の教義とのあいだにズレがあることが指摘されます。そもそも日本人の多くは、仏教の教えに帰依して仏教徒になったわけではありません。むしろ仏教側が日本人の民間信仰的な死生観を取り込んで、日本人を仏教徒にしていったのです。著者は、「おそらく室町時代や江戸時代には、民間信仰的なものも、なんの疑問もなく仏教として受け入れられていたと思われる。当時の僧侶らは、何が本来の仏教かなどということには興味がなかったのだ。関心があるのは、どうすれば人々の不安を取りのぞいてあげることができるかということだった。そのためには教義にもとづくものなのかどうかは、どうでもよかったのである」と述べています。
著者いわく、日本の仏教徒は教義的な死生観のなかには生きていません。日本人の死生観を考えるのに、仏教の教義をベースにするのはあまり意味がなく、あくまでも当事者は信仰者であるといいます。死の当事者は故人であり、遺族であるとして、著者は「魂とあの世の問題も、教義にもとづいて論じるのはあまり意味がない。一度、仏教の教義を離れて、民俗学的な視点で考えることが必要だろう」と述べます。実は、柳田は“仏教の教義と現実に生きている人の死生観とのズレ”についてかなり手厳しい批判を繰り返しており、「死んで『ほとけ』などと呼ばれることを、迷惑に思ったものは昔から多いはずである。日本人の志としては、たとえ肉体は朽ちて跡なくなってしまおうとも、なおこの国土との縁は絶たず、毎年日を定めて子孫の家と行き通い、幼い者の段々に世に出て行く様子を見たいと思っていたろうに、最後は成仏であり、出て来るのは心得違いでもあるかのごとく、しきりに遠いところへ送り付けようとする態度を僧たちが示したのは、あまりにも1つの民族の感情に反した話だった。それだからまた言葉は何となっておろうとも、その趣旨はまだちっとも徹底していないのである」などと述べています。
故人は家族の近くで見守っていたいのに、仏教はそうすることは間違いだと言って、遠くに送ってしまおうとする。日本人の感覚にあわない話で、それゆえ「故人を浄土に送る」という考えは、いまだに人々に広まらないと柳田は考えているのです。柳田は「判りきったことだが、信仰は理論でない」「眼前我々と共に活きている人々が、最も多くかつ最も普通に、死後をいかに想像しまた感じつつあるのかというのが、知っておかねばならぬ事実」とも述べています。著者は、「柳田のスタンスは、あくまでも信仰者の視点である。信仰している当人が、死後の世界をどう考えているかということなのだ」と述べるのでした。
「『古事記』と『万葉集』の時代」では、ほとんどの日本人は、死者の魂は、あるときは「どこか近く」で、あるときは「あの世」から見守ってくれていると信じていることが指摘されます。また、仏壇の前で手を合わせるときは「仏壇」に、お墓の前で手を合わせるときは「お墓」にいるとも思っています。著者は、「よくよく考えると矛盾しているのだが、感覚的に疑問を持つことはない。魂がいる場所は『あれもこれも』なのである。魂は、生きている私たちが『いる』と思ったところにいる。今も昔も、日本人はそう考えているのであろう」と述べています。
「[6]信仰の構造――教えと祈り」では、「佛教は葬送や祈願を語らない」として、日本の仏教徒は、文化庁の統計によると約8324万人である(『宗教年鑑』令和4年版)ことが紹介されます。日本の人口は約1億2454万人(令和5年8月)なので、日本人の約67%が仏教徒ということになります。日本消費者協会の調査によると、89.4%の人が仏式で葬儀をあげている(『「葬儀についてのアンケート調査」報告書』令和4年3月/一般財団法人日本消費者協会)のも現実です。ただ、おそらくお釈迦さまや祖師方の教えに帰依している人はそのうち1%にも満たないのではないだろうかとして、著者は「そもそも、教えの内容がどんなものなのかを知っている人すら、少ないのが現実である。それに対して、葬送や祈願を仏教と見なさない人も多い。なぜなら、お釈迦さまも祖師方も、葬送や祈願について何も語っていないからだ。仏教は、お釈迦さまや祖師方が説いた教えであり、葬送や祈願は本来の仏教にはないものという解釈である」と述べています。
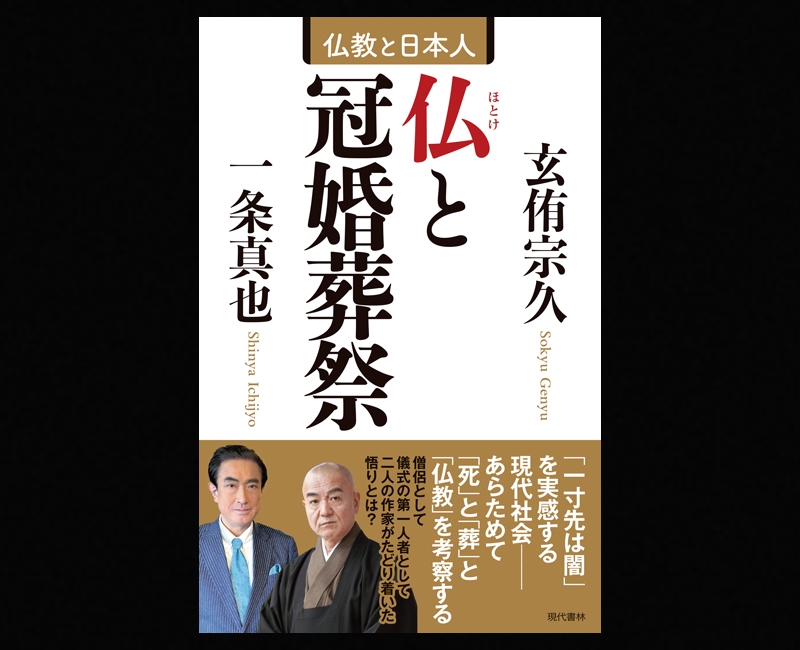 『仏と冠婚葬祭』(現代書林)
『仏と冠婚葬祭』(現代書林)
「教えと祈りの二重構造」では、一般生活者にとって、仏教とは“葬送”であり“祈願”であることが指摘されます。葬送を通して「あの世での安らぎ」を祈り、祈願を通して「この世での安らぎを祈る」のが、現実の仏教であるというのです。著者は、「もちろん、教えが不要と言っているのではない。葬送や祈願という実践の根底にあるのが教えという理論なのだ。教えと祈りは、理論と実践という構造をなしている。人々の救いをめざす教えが基本にあるからこそ、仏教は葬送や祈願で人々を救おうとするのである。信仰は教えだけで成り立っているわけではない。祈りという要素が加わることで、合理性を超えたものが生まれ、信仰になっていく」と述べます。
第2章「葬式仏教という宗教」の「[1]葬式仏教は仏教を堕落させた犯人なのか?」では、「葬式仏教犯人説の検証」として、葬式仏教という言葉には、仏教のあり方を揶揄するニュアンスが含まれていることが多いことが指摘されます。「葬式ばかりやっていて、教えを説かない仏教」「葬式で金儲けばかりしている仏教」というニュアンスであす。現代の仏教に対して、不満を持つ人は多いです。特に「お布施」「戒名」「檀家制度」については、社会とのあいだに大きなズレを生じており、常に批判の対象となっています。そしてその批判のほとんどが葬式仏教に関わるものです。そのため、よく耳にするのが「日本の仏教は、葬式仏教になって堕落した」という話です。著者は、「仏教が教えを説くことは大切ではあるが、そこに期待をしている日本人は少ない。仏教に期待しているのは、何よりも弔いであるということだ。見方によっては、葬式仏教は日本で最も求められている宗教だとも言える」と述べています。
「仏教の制度疲労」では、葬式仏教の問題点としてあげられるものには、お布施・戒名・檀家制度などがあることが紹介されます。お布施の問題は「僧侶が金額を言ってくれない」「高額のお布施を強要された」といったもの、戒名の問題は「お布施の金額で戒名のランクが変わる」といったもの、檀家制度の問題は「お寺との関係性が不平等である」「一方的で強制的なものが多い」「檀家を簡単には辞めることができない」といったものです。これらの問題について、著者は「仏教がきちんとしたお布施や檀家制度の仕組みを提供できていないということである。たとえばお布施は、お寺や僧侶に対してお金を納めるための仕組みである」と述べます。もともとお布施は、地域社会がある程度の基準を暗黙のうちに定め、それにもとづいて個々が金額を決めてお寺に納めていました。
僧侶は「お布施はお気持ちでけっこうです」と言いますが、現実は地域のバランス、個々の家の事情、お寺への配慮などを総合して、地域がお布施の金額を決めていたのです。著者は、「戦後何十年かのあいだに地域社会が変質するなかで、こうした“地域知”が働かなくなってきた。“地域知”による調整機能が効かなくなっているのに、誰も補おうとしない。そんな状況で、『お布施はお気持ちでけっこうです』と言われても途方に暮れてしまう。以前はスムーズだったお布施の仕組みがうまくいかなくなっているのは、ここに理由があるのだ」と述べ、さらに「お布施・戒名・檀家制度のあり方は、変えてはいけない普遍的なものではない。仏教が社会と関わるなかで生まれたものなので、社会とのズレが生じるようになったのならば、修正して変えていけばいい。いや、むしろ変えていくべきである」と述べるのでした。まったく同感です。
「葬送が仏教を民衆に広めた」では、現在の日本には約7万5000のお寺があることが紹介されます。その9割近くが、室町時代の後半、応仁の乱以降から江戸時代の初めまでの約200年のあいだに建立されているといいます。特に地方の農村・山村・漁村にある小規模寺院は、ほぼすべてこの時代のものといっても過言ではないそうです。著者は、「たった200年のあいだに、お寺は少なめに見積もっても5倍以上になり、数でいえば約6万のお寺が増えた。しかも、この時期に建立されたお寺は、村の寺であり、街の寺であり、庶民の寺である。立派な伽藍があるわけでもなく、立派な仏像があるわけでもない、ごく普通のお寺である」と述べています。
なぜ、お寺が増えたのでしょうか。それは、当時の社会に惣村が生まれたことが大きいといいます。惣村とは自治をもった村のことで、荘園制度が崩れて人々が自分たちで地域社会をつくっていこうとして生まれたといわれます。惣村は水利配分、道路の設置、境界紛争の解決などを行うようになり、祭祀にも関わるようになりました。ただそれまでの庶民には、お寺を建立する経済力はありませんでした。お寺は武士や貴族などの権力者にしか建立することができなかったのです。しかし惣村が生まれることによって、庶民でも村で暮らす何十軒という家がお金を出しあえば建立できるようになりました。ただし、それまでの仏教が、葬送に対してあまり積極的でなかったのも事実です。僧侶は、中央の貴族や武士、あるいは地方の有力者に、教えを説いたり、祈祷をしたりというのが活動の中心でした。
当時、死は穢れなので、僧侶は関わるべきでないという考えがあったほどです。ところが室町時代の後半以降から、僧侶たちは「死んでもあの世での安心が得られる」と説き、死者の葬送を行うようになります。著者は、「仏教が庶民の葬送に関わるようになっていくのだ。葬式仏教はこうして誕生したのである」と述べます。応仁の乱から戦国時代にかけての社会不安の時代に、一般の人たちが浄土という考え方に魅力を感じたのは想像に難くないとして、著者は「惣村が生まれ、仏教が葬送に関わるようになる。2つが同時に起きたことで、ニーズが高まり、仏教は一気に広まったのである。室町時代の後半に急速にお寺が増えたのは、そこに理由がある。つまり日本の仏教は、葬式仏教として広がったのである。当時の僧侶らが、死の不安に寄り添ったからこそ、葬式仏教が生まれたのだ」と述べるのでした。
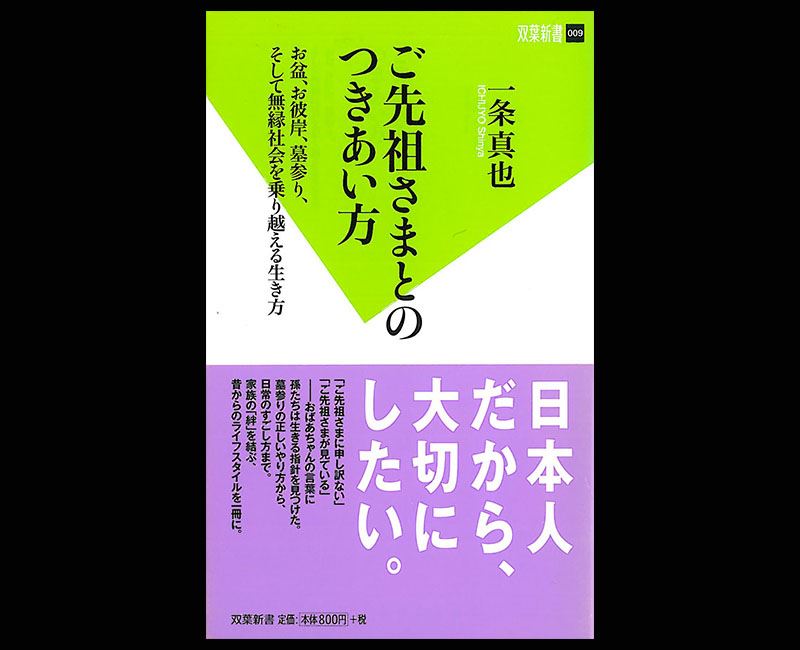 『ご先祖さまとのつきあい方』
『ご先祖さまとのつきあい方』
(双葉新書)
「死者と生者がお互いを思いやる世界観」では、わたしたち日本人の宗教的情操は、教義的な仏教よりも、葬式仏教に大きな影響を受けていることが指摘されます。死者とつながる信仰から、わたしたちは心の安らぎを得るとともに、たくさんのことを学んできたのです。著者は、「仏壇に向かって亡くなった家族と対話するときの安らぎ。いただきものはまず仏壇に供えようとする謙虚な気持ち。成績表を供えることで、祖父母や先祖に見守られていると感じるようになる子どもたち。法事で親類が集まって、一族の絆を感じる瞬間。故人を想いながらお墓の前で手を合わせるときの追憶と感謝。通夜や葬式で、故人のあの世での安らぎを祈りながら、たくさんの友人・知人と悲しみを共有すること。もちろん、どれも仏教の教義にはないものだ」と述べます。
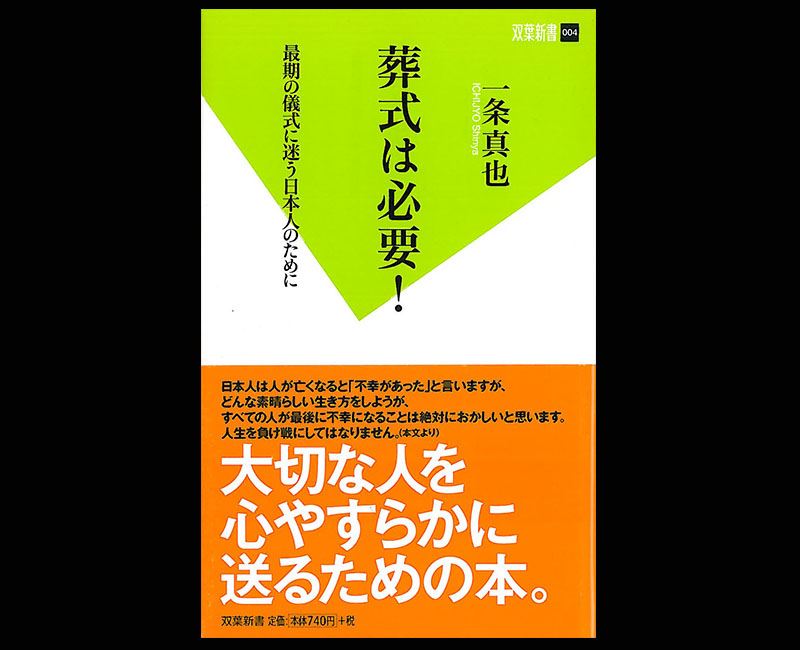 『葬式は必要!』(双葉新書)
『葬式は必要!』(双葉新書)
続けて、著者は「それでも葬式仏教は、死者への優しさに満ちた、とても美しい信仰だと思う。死者と生者がお互いに思いやる世界のなかに私たちは生きている。そして普通の日本人にとっては、これこそが仏教なのだ。日本人は何百年ものあいだ死者を想い、死者とともに生活してきた。そして現代のように科学合理主義が支配する社会になっても、故人をあの世に送りとどけるために葬式が行われ続けている。葬式仏教は日本人にとって、とても大切な財産であることを忘れてはならないと思う」と述べるのでした。この著者の考えは、わたしのそれとまったく同じであることを告白しておきます。
「[2]僧侶が弔いに関わってはいけない時代」の「ある僧侶の話――母を亡くした娘と僧侶」では、鎌倉時代初期に活躍した鴨長明の『発心集』という仏教説話の中の1つが紹介されています。あるとき京都に住む僧侶が、思うところがあって、坂本にある日吉神社に百日詣をしました。80日目を過ぎて、お参りから帰る途中、家の前で人目をはばかることなく泣いている娘と出会いました。訊くと、その朝に娘の母親が亡くなったのですが、神社に仕える村ゆえに死の穢れのことを考えると、葬式も出せないというのです。娘の話を聞いた僧侶は「本当に困っているのだな」と切なくなり、ともに涙を流したといいます。そして、日が暮れてから闇夜にまぎれて亡骸を丁重に弔ったのでした。
「勇気を振り絞って死に関わる」では、この『発心集』の話から、鎌倉時代に死の穢れが、いかに怖れられていたかということを確認します。特に国に認められた正式な僧侶(官僧)は、死の穢れに触れた場合、30日間の精進潔斎をしなければならなかったうえ、穢れが他人に感染するのを防ぐために家の中に籠っていなかればならなかったのです。著者は「僧侶が弔いに関わろうと決心するまでには、そうとうな葛藤があったはずである。社会的な掟と慈悲の心のあいだで、気持ちは揺れ動いたに違いない。それでも僧侶は、娘の母親を弔おうと決心した。これが、葬式仏教の誕生であろう。おそらく、たくさんの名もなき僧侶たちが同じような場面に出くわし、同じような決心をした。人を救いたいという気持ち、そして慈悲の気持ちが、弔いの行為を生んだに違いない」と述べるのでした。
「[3]教義では説明できないお盆という行事」の「仏教ではお盆をどう考えるか」では、お盆は『盂蘭盆経』の物語がもとになって始まった行事で、餓鬼道に落ちた家族を救うため、お供えをするようになったということが紹介されます。著者は、「お盆法要のときの法話で、この物語を聞いたことがある人は多いと思う。お寺の檀家になっている人であれば、一度くらいは聞いているはずだ。ところがこの物語は、聞いていて据わりの悪さを感じてしまう。亡くなった家族が餓鬼道に落ちていることを前提にしているからである。餓鬼道に落ちていないのであれば、そもそもお盆の供養は必要ない。大切な故人が餓鬼道に落ちているという設定なのが、なんとも釈然としないのだ」と述べています。
『盂蘭盆経』は中国でつくられたお経であり、偽経という位置づけがされています。仏教界でも、正式なお経ではないと考える人は多いです。そうなると、お盆の教義的な裏づけそのものがなくなってしまうとして、著者は「理屈のうえでは、お盆は実に仏教と相性の悪い行事なのだ。しかし、現実には何百年にもわたって、お盆は仏教の行事として親しまれている。日本仏教の最大の行事といっても過言ではないだろう。これを成立させているのは、伝統的でエスタブリッシュな仏教の背後にある“もうひとつの仏教”の存在であろう。見えない宗教だが、むしろこちらの信仰のほうが多くの人たちに親しまれている。それこそが葬式仏教なのである」と述べます。
「見えない宗教」では、日本の仏教徒が信仰しているのは葬式仏教であることが強調されます。その信仰の中身は「亡くなった家族を供養することで、あの世で安らかで過ごしてもらうことができる」「亡くなった家族が、あの世から私たちを見守ってくれる」というシンプルなものです。この教えは教義的な仏教には存在せず、そのため葬式仏教は“堕落した仏教”ととらえられがちです。また葬式仏教という宗教は、カタチとしては存在していないとして、著者は「本山もお寺も教団もないし、お経もない。もちろん宗教法人もない。それでも信仰としては、圧倒的多数派である。宗派の教えを信仰している人よりも、祈りを通じて死者と語りあうことを信じている人のほうが多い。組織化された宗教としては存在していないが、信仰としてのみ存在している。まさに『見えない宗教』と言えるだろう」と述べるのでした。
「葬式仏教は語るに値しない」では、日本の仏教には宗派があり、本山があり、たくさんの信者(檀家、門徒)がいることが指摘されます。そして実際にそれらを支えているのは、宗派の教えではなく、「見えない宗教」としての葬式仏教の信仰です。日本の仏教の信仰を考えるうえで、葬式仏教の存在を無視することはできません。お釈迦さまや宗祖たちの教えをいくら語っても、一般生活者の信仰は何も見えてこないからです。現代の仏教には、さまざまな矛盾が存在しています。特にお布施・戒名・檀家制度などにおいては、仏教と一般生活者のあいだに大きなズレが生じています。現代において、仏教の存在感は絶望的なほどなくなりつつあるとして、著者は「それは、葬式仏教的なものを無理矢理エスタブリッシュな仏教の枠組みに入れようとする姿勢にも問題があるのではないだろうか。知的であろうとするあまり、純粋であろうとするあまり、一般の人たちの気持ちが見えなくなってきていることに原因はないだろうか。仏教の未来のためにも、死者への祈りを大切にする葬式仏教を再評価することが必要ではないかと思う」と述べています。
「日本人が無宗教だと考えられている理由」では、そもそも宗教という言葉は日本語にはなかったことが指摘されます。明治時代初期にドイツ語の訳語として生まれた言葉なのです。当然ながら、ドイツ語が指す宗教はキリスト教を前提としています。新たに入ってきたキリスト教と比べると、当時の知識人たちにとっては、日本で信仰されている仏教が前時代的なものに見えたとして、著者は「欧米のキリスト教徒がきちんと教えを理解し、それを生活のなかで実践しているのに対し、日本の仏教徒は教義をほとんど知らず、死者への祈りと現世利益の祈りばかりに明け暮れているように見えたのだ。宗教という訳語は、そんな時代背景のなかで生まれたのである」と述べています。
しかし、実際はキリスト教も決して合理的で近代的なところばかりではありません。たとえば、カトリックの国では聖母マリアを信仰する人は多いですが、それはキリスト教の教義にはない信仰であり、キリスト教以前の地母神信仰の名残が見られるといわれています。キリスト教も、伝播した国々で、それぞれさまざまな民間信仰の影響を受けているのです。ただ、明治時代初期に来日した欧米人は知識人階級が多く、民間信仰について語ることはありませんでした。当然、宣教師が民間信仰について語ることもありません。渡欧した日本人も文化を学ぶことが目的であり、民間信仰には興味がありませんでした。著者は、「当時の日本人は、欧米における民衆レベルのキリスト教徒がどんな信仰を持っていたのかを知るよしもなかったのである。宗教という言葉を日本語に翻訳する過程で、そうしたキリスト教の教義にはない素朴な祈りが剝ぎ取られてしまったのだ」と述べるのでした。
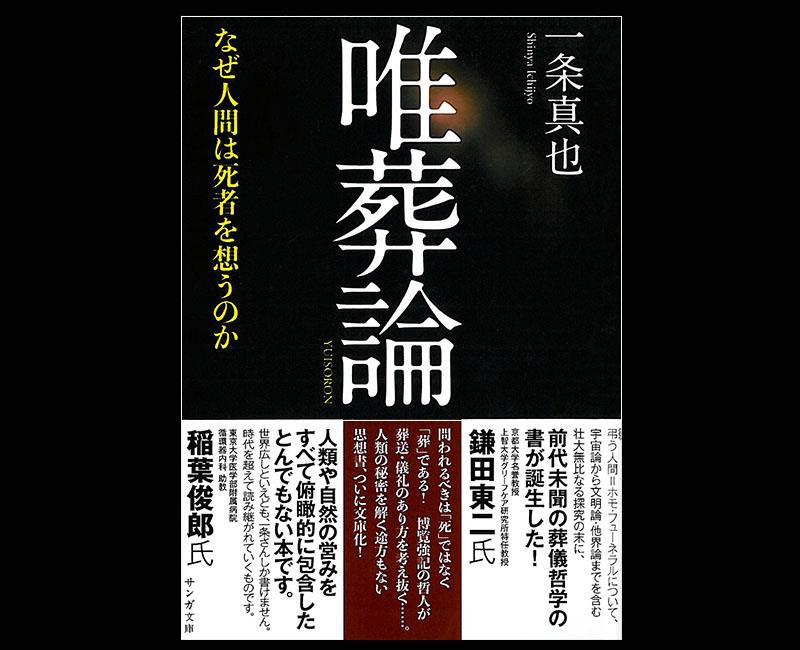 『唯葬論』(サンガ文庫)
『唯葬論』(サンガ文庫)
「[4]死者との対話がもたらすもの」の「日本の仏教とは何を信じているのか?」では、著者が「素朴で感覚的な信仰のなかにこそ、豊かな宗教世界は存在している。なにより日本の仏教徒に最も親しまれてきた信仰は、死者供養である。教えにもとづく信仰を持っている人は、今も昔も少数派に過ぎない。仏教の教えをもとに日本人の死生観を語るのには無理があるのだ」と喝破しています。「亡くなった故人が私たちを見守ってくれるという信仰」では、供養は「生者が死者の安らぎを祈る」という一方通行ではなく、「死者からも生者の安らぎを祈る」という信仰を含んでいると指摘します。「亡くなった家族が、私たちを見守ってくれる」という信仰です。
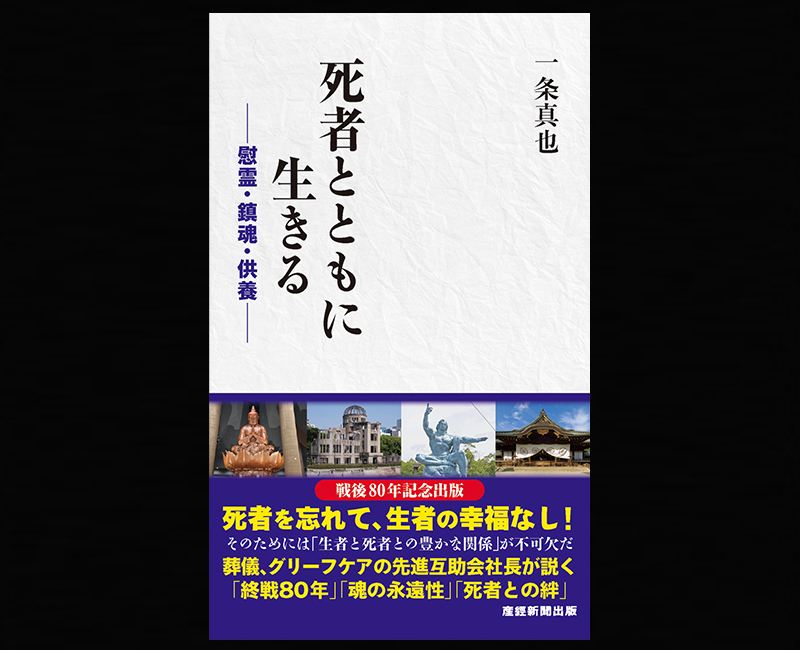 『死者とともに生きる』(産経新聞出版)
『死者とともに生きる』(産経新聞出版)
生者が死者の安らぎを祈り、死者が私たち生者の安らぎを祈る。生者と死者の祈りが双方向に絡みあっていくのです。もうひとつ、人は「大切な人があの世で苦しんでいないか」と心配になるものですが、それは自分自身の死に直面しても同様です。自分自身もいつかは死を迎えます。当然のことながら、他人の死以上に自分の死は不安です。著者は、「自分という存在がなくなってしまうのではないか、あるいは死んだら苦しい思いをするんじゃないかと。ところが、供養という信仰は、自分が死んでも誰かが供養してくれることを想定している。自分の供養で先に死んだ人の安らぎを実現できるのなら、自分自身も誰かに供養してもらえさえすれば、死後の安らぎを保証されるということなのだ」と述べます。
 『供養には意味がある』(産経新聞出版)
『供養には意味がある』(産経新聞出版)
「死者との対話がもたらすもの」では、供養という信仰は死者の安らぎを祈る信仰であり、死者が生者の安らぎを祈ってくれる信仰であると述べられます。この信仰の根幹には、死者との対話があります。人は死んでも何かしら人格的な存在が残り(これを多くの人は「霊」「魂」などと呼ぶ)、変わらぬ関係、変わらぬ愛情、変わらぬ友情が続き、対話をすることができるとして、著者は「私たちは大切な人が死んでも、その人とつながっていたいのだ。それゆえ、お墓や仏壇の前で死者と対話を続けているのである。こうした日本の仏教徒の死生観は、素朴だがとても豊かだと思う。私たちは供養という行為を通して死者とつながり、あの世ともつながっている。供養は、死者と生者がお互いにいたわりあう優しい信仰である。死者の安らぎとこの世の私たちの幸せを、葬式仏教は私たちに約束してくれるのだ」と述べるのでした。これは拙著『供養には意味がある』(産経新聞出版)で訴えた内容と同じです。
 『図解でわかる!ブッダの考え方』
『図解でわかる!ブッダの考え方』
(中経の文庫)
「[5]非言語が伝えるもの」の「葬式をする仏教は『あるべからざるもの』なのか」では、僧侶の中でも、「仏教は本来、教えが中心であるべき」という意識は強い。自分たちが関わっている葬送中心の仏教は、“仮の姿”だと考えている僧侶もいることが紹介されます。僧侶の資格を取るには、大学で仏教を学んで、本山などの研修機関で修行をすることを条件としている宗派が多いです。そこでは教えと修行が中心であり、葬送について学ぶ機会はほとんどありません。ところが、若い僧侶が資格を取ったあとに実家のお寺に戻ると、現実の活動はほとんどが葬送に関わることです。そこで現実を受けとめることができないと、「これは本当の仏教ではない、仮の姿なんだ」と自分に言い聞かせるしかないのです。しかし、“葬式仏教”は“教えの仏教”に比べて圧倒的な支持を得ているのが現実です。
「葬式仏教の宗教世界」では、葬式仏教にもちゃんとした教えや死生観があり、言語とは異なる形式で人々に伝えられていることを忘れてはならないといいます。現代人は、言語化されているものがすべてだと考える傾向が強いですが、宗教には儀礼というものがあり、時間や空間を通して伝えられている事柄も多いのです著者は、「儀礼といっても、本堂で行われるような法要だけではない。お墓や仏壇へのお参りなど日常的な宗教行為も儀礼であり、そこには葬式仏教の豊かな死生観が非言語で表現されている。生者が死者を供養することで、死者はあの世で安らぎを得られる。死者もあの世から私たち生きている者の安穏を祈ってくれる。“相互に幸せや安らぎを祈りあう信仰”である。その死者を供養する場がお寺であり、お墓であり、仏壇である」と述べています。
著者いわく、葬式仏教は言語ではなく、儀式や習慣で伝えられる宗教なのです。理念よりも、感覚で伝えられる宗教と言ってもいいでしょう。現代人は言語化されたものにとらわれ過ぎているため、こうした感覚的なものを程度が低いと考える傾向が強いですが、非言語で語られる葬式仏教の教えには、日本人が長い年月をかけて積み重ねてきた智慧がこめられていのです。葬式仏教という宗教が、教えとして語られないにもかかわらず、多くの人に信仰されているのは、ここに理由があるのではないかとして、著者は「日本人の生活のなかでは、言語で語られる理念的な仏教よりも、非言語で語られる葬式仏教のほうが、圧倒的に存在感があるのも事実である。そして、この信仰もまた、仏教なのだ」と述べるのでした。この考えは、わたしが説く「宗遊」に近いと思います。
第3章「死者と対話する装置――仏壇とお墓」の「[2]システムとしてのお墓の限界――「守る人」の存在が不安定に」の「非定住時代のお墓」では、かつての日本は農業に携わっている人口が多く、定住型の社会であったことが紹介されます。特に地方では、何代にもわたって同じ家に住み続けるのが当たり前でした。ところが、第一次産業に従事する人が減り、会社勤めをする人が増えてくると、同じ場所に住み続けることが当たり前ではなくなってきます。また、子どものうちは親と同居していても、大人になると家を出ていき、別に暮らす人も多くなります。つまり、一生同じ場所に定住するという文化がなくなってきます。一方、お墓はずっと1カ所にあるのが当たり前。お墓はいまだに定住文化のなかにあるのです。
 わが家の墓の前で
わが家の墓の前で
日本はもともと農耕をベースにした定住型社会であり、今なおその影響が強いです。お墓を大切にするのは、農耕社会の特徴でもあります。同じ場所に住み続け、先祖が開拓した田畑を耕して暮らすというのは、お墓を守りやすい状況を生み出していたのです。一方、遊牧民などの非定住型社会では、あまりお墓にこだわらない民族が多いです。遺骨を埋葬してもそこに石碑のような“しるし”は建てません。そもそも同じ場所に住み続けることがないので、どこかにお墓をつくっても、その場所を離れたらお墓参りができないのです。著者は、「弔いを大切にする文化はあるものの、遺骨やお墓にはこだわらないのである。お墓を建てても、定期的に墓参りを行うことは物理的に不可能だからだ」と述べます。伝統的なお墓は、現代のような非定住型の社会にはだんだんとあわなくなってきています。
 わが実家の仏壇
わが実家の仏壇
「[3]仏壇――死者とともに暮らすという文化」の「廃れつつある仏壇」では、仏壇という文化は、少しずつではありますが、廃れていっていると言わざるを得ないと述べられます。仏壇を置く家が減った理由としてまず挙げられるのが、住宅事情です。特に新しく建てた住宅には和室がないケースが多く、仏壇を置きにくい原因となっています。また、マンション住まいだったり、一戸建てに住んでいても小規模だったりして、仏壇を置くスペースそのものがないという場合も少なくありません。住環境が、仏壇を置くのを許さないということです。
 仏壇開眼供養のようす
仏壇開眼供養のようす
もうひとつの理由は、3世代同居がなくなりつつあることです。仏壇を守る役割は、家族のなかで年齢の高い人が担うのが一般的です。祖父母、息子夫婦、孫が一緒に暮らす家であれば、祖父もしくは祖母が仏壇を守っていました。次の世代は、それを見ながら仏壇に馴染みつつ、仏壇に手を合わせることの大切さを学んできました。ところが、核家族化が進むと、祖父母の家と、その息子夫婦と孫の家は別々となり、若い世代の家には仏壇がなくなります。つまり、仏壇のない家が生まれるということです。それを何世代か繰り返すことで、仏壇がないのが当たり前になっていくのです。
 わが家の仏壇の前で
わが家の仏壇の前で
「仏壇の衰退は何をもたらすか?」では、近年、仏壇を持つ家が減っている理由として、住宅事情や核家族化が大きく影響していると指摘されます。しかし、仏教自身が積極的に死者供養を説かなくなっている現状も、仏壇の衰退に大きく影響しているのではないかとして、著者は「仏壇の存在感がなくなっていくことは、日々の信仰生活の衰退を意味する。そして、死者とともに暮らす文化の衰退を意味する。仏壇は、私たちと死者をつなぐ依り代であり、私たちと死者をつなぐ装置だからである」と述べています。
 「サンデー毎日」2018年2月18号
「サンデー毎日」2018年2月18号
仏壇がどの家にもあった時代、日本人は常に死者が家のなかにいることを意識し、死者が安らかであることを祈り、死者が見守ってくれることを願って生きてきました。日々に仏壇と接することで、死者への優しさに満ちた信仰を育んできたのです。これも時代の流れかもしれませんが、日本人は大切なものを、またひとつ失いつつあるような気がするという著者は、「お墓と仏壇は、日本人が信仰を育んでいくうえで、とても大きな役割を果たしてきた。それはどんなお経よりも、どんな法話よりも、大きな役割を果たしてきた」と述べるのでした。
第6章「戒名と檀家」の「[1]戒名とお金をめぐる違和感――あの世にも身分制度はあるのか?」の「死んだ人につける名前?」では、世間では、戒名に対して良い印象がないことが指摘されます。「お寺に戒名をつけてもらったら、高額の戒名料を請求された」「いい戒名をつけてもらったら、そのあとのお布施も高額になってしまった」などの噂を一度くらいは聞いたことがあるだろうとして、著者は「噂の真偽はわからないが、多くの人が違和感を覚えているのは確かだ。そうしたことから、『自分が死んでも戒名はいらない』と考える人もいる」と述べています。
有名人では、吉田茂首相の側近を務めた実業家の白洲次郎が「葬式無用 戒名不要」と遺言に記したところ、妻の白洲正子がその遺志を汲んで、葬式を行わず、戒名をつけることもしませんでした。また、戒名を僧侶につけてもらわず、自分でつけるという人もいるようです。こちらも有名人では落語家の立川談志が、生前に自分で「立川雲黒斎家元勝手居士」との戒名をつけたといいます。談志は落語家らしく戒名でもユーモアをきかせたのですが、この戒名が災いして、遺族がお墓を買おうとしたところお寺に断られてしまい、納骨まで1年以上かかったそうです。
「遅ればせながら、死んでから仏教徒に」では、戒名に言及しています。戒名をひと言でいうと、仏教徒になるにあたってつけられる名前です。それゆえ本来は生きているうちにつけるものとされています。ですから僧侶は全員、戒名を持っています。それがなぜ死んでからつけられるかというと、ほとんどの日本人が正式に仏教徒になる儀式を行っていないからです。カトリックの場合、入信するときに洗礼という儀式が行われ、洗礼名(クリスチャンネーム)が与えられます。
それとほぼ同じ意味合いであるが、仏教の場合は仏教徒になるときに授戒という儀式が行われ、戒名が与えられます。もちろん生きているうちに仏教徒になる場合です。しかし現実は、9割近くの日本人が仏教で葬式をあげているのにもかかわらず、生前にこの授戒を受けて戒名を持っている人はほとんどいません。そのため仏教徒として葬式をあげるために、遅ればせながら亡くなったときに授戒をして、戒名をあたえるのです。仏教の教義上、無事あの世に送り届けるのに必要な段取りということなのです。
「葬式仏教の未来――むすびにかえて」では、現代の仏教をとりまく環境は決して明るいものではないことが明かされます。直葬や1日葬、墓じまいの増加、年忌法要の省略など、さまざまな問題が表面化しています。著者はその原因のひとつに、「供養したいという素朴で純粋な人の想いを、思想的な仏教が抑圧している」ということがあるのではないかと思っているそうです。現代の仏教は理詰めの説明が多く、とても窮屈です。そもそも話が難しくて、聞く気も起きてきません。ほとんどの人は、仏教は自分の生活とは関係のないものと感じるようになっているのです。
 「産経新聞」2025年6月23日号
「産経新聞」2025年6月23日号
葬式仏教は、500年以上にわたって日本人に信仰されてきた宗教です。死者と生者がお互いを想いあうとても優しい信仰です。このまま葬式仏教を衰退させていくのは、あまりにも惜しい気がするとして、著者は「そのためにも、仏教と人々とのズレはなくしていくべきだと思う。そしてズレをなくしていくための責任は、仏教側にあるのだ」と述べるのでした。本書は、現代日本の仏教と葬儀を知るうえで最高のテキストであるといえます。本書を初めて知ったのは、戦後80年の「沖縄慰霊の日」となる6月23日の「産経新聞」朝刊に、芥川賞作家で臨済宗福聚寺住職の玄侑宗久先生との対談本『仏と冠婚葬祭』、および、大阪大学名誉教授・中国哲学者の加地伸行先生との対談本『論語と冠婚葬祭』、京都大学名誉教授で宗教哲学者の故・鎌田東二先生との対談本『古事記と冠婚葬祭』の書籍広告が掲載したときです。現代書林から刊行された「宗教と日本人」三部作ですが、このとき、お隣で本書の書籍広告が掲載されていたのです。わたしの本もたくさん出していただいている産経新聞出版さんが版元で、不思議な御縁を感じた次第です。
