- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2440 メディア・IT 『AIにはできない』 栗原聡著(角川新書)
2026.01.12
『AIにはできない』栗原聡著(角川新書)を読みました。「人口知能研究者が正しく伝える限界と可能性」というサブタイトルがついています。著者は、慶應義塾大学理工学部教授。人工知能学会会長。慶應義塾大学共生知能創発社会研究センターセンター長。慶應義塾大学AIC生成AIラボラボ長。慶應義塾大学大学院理工学研究科修了。博士(工学)。NTT基礎研究所、大阪大学、電気通信大学を経て、2018年より現職。科学技術振興機構(JST)さきがけ「社会変革基盤」領域研究総括。人工知能学会倫理委員会委員長。オムロンサイニックエックス社外取締役、総務省情報通信法学研究会構成員など。マルチエージェント、複雑ネットワーク科学、計算社会科学などの研究に従事。
 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、「“AIがまだできないこと”を通してわかる」「今、『人間(われわれ)がやるべき』こと」「自律性、適応力、0→1の創造、共感、人との共生……」「その先にある『次世代AI』への道を考察する」と書かれています。
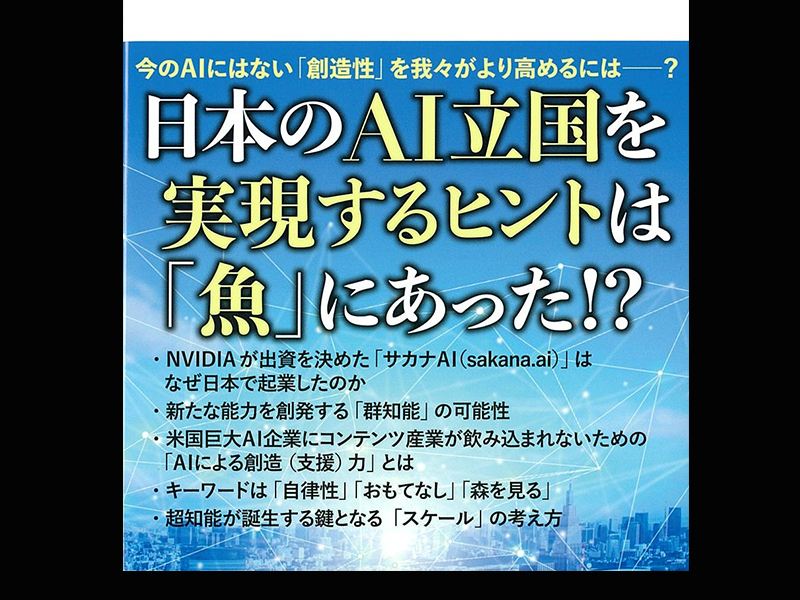 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には「今のAIにはない『創造性』を我々がより高めるには――?」「日本のAI立国を実現するヒントは『魚』にあった!?」として、こう書かれています。
●NVIDIAが出資を決めた「サカナAI(sakana.ai)」はなぜ日本で起業したのか
●新たな能力を創発する「群知能」の可能性
●米国巨大AI企業にコンテンツ産業が呑み込まれないための「AIによる創造(支援)力」とは
●キーワードは「自律性」「おもてなし」「森を見る」
●超知能が誕生する鍵となる「スケール」の考え方
カバー後そでにある「本書の内容」には、「ChatGPTを初めとする生成AIの登場により、その万能性が人間への脅威としても論じられているが、現在のAIは決して万能ではない。AIに何ができ、何ができないかを理解しないことには、正しく恐れることもできない。人工知能研究の専門家が、AIの『現在の限界』をわかりやすく解説し、その先にある『次世代AIの可能性』を探る」と書かれています。
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
第1章 AI開発の歴史は未来のためにある
第2章 生成AIには何ができ、何ができないか
第3章 AIは経済の浮揚に寄与するのか
第4章 AIを使うか、AIに使われるか
第5章 社会が生成AIを受け入れるための課題
第6章 人とAIの共生
第7章 AIのスケール化と日本の未来
「おわりに」
「はじめに」の「サイモンのアリ」には、レイ・カーツワイルの著書『シンギュラリティは近い――人類が生命を超越するとき』でも言及されているように、多くのテクノロジーが時間の経過に伴い指数関数的にその性能を向上させているという事実が紹介されます。指数関数的な性能の変化とは、性能が発揮されない時期が長く続くものの、徐々に性能が向上し始め、ある時期を境に一気に爆発するように向上していく変化のことです。2倍、3倍、4倍という変化ではなく、10倍、100倍、1000倍という具合です。有名なムーアの法則も「半導体集積回路の集積率は18カ月(または24カ月)で2倍になる」という指数関数的な上昇に基づく将来予想なのです。
2000年あたりからAIの性能が指数関数的変化に従うように急激に上昇する段階に突入しました。いわゆる第3次AIブームの始まりです。そしてこのレベルアップは止まることなく、2020年代にはChatGPTを代表とする生成AIの中心的な存在である大規模言語モデルの開発に成功し、第3次AIブームはさらに急激に性能が向上する段階に突入したと言えます。著者は、「強すぎる技術は、使い方を間違えると負の影響も大きくなる。原子力が最たる例だ。そのような懸念から、AIに対する規制やガイドラインの策定を急ぐ動きが世界的に盛り上がっているが、なかでもEUはその先頭を走っている」と述べています。
高い可能性を秘める生成AIですが、それ故に生成AIに対する懸念も大きいと言えます。ChatGPTのような大規模言語モデル(LLM:Large Language Model)は、人類が初めて実現に成功した汎用性のあるAI(汎用AI〈AGI:Artificial General Intelligence〉)であり、何を聞いてもちゃんと流暢な言葉で答えてくれます。著者は、「人に聞くのと同じやりとりが可能であり、検索ツールのようにも使えれば、発想支援ツールとして“壁打ち”にも使えてしまう。このようなAI、いやテクノロジーは今までなかった。しかも、誰もが使えることから『AIの民主化』を果たしているとも評されている(誰もが使えるということで、悪用の懸念も指摘されるし、著作権などの権利を侵害するような使い方も簡単にできてしまう)」と述べます。
マルチモーダル化と呼ばれますが、今や文章だけでなく画像や音声の入力と生成も可能です。しかも生成されるものの質は極めて高く、もはや人を超えているという指摘もあります。そうなれば、脚本家、イラストレーター、漫画家、アニメーターなどのクリエイターが仕事を奪われる危機感を持つのは当然でしょうし、さらには自分の作品を勝手に学習に使われることに対して反感を持つことも当然のことであろうとしながらも、著者は「しかしそれは内燃機関や電卓が実用化されたときも、そして組み立てロボットが発明されたときも世界的に起きたことである。イギリスでは産業革命時に、ラッダイト運動が起きている。しかし、それでもその度に人々は変化に適応してきた。新たなテクノロジーの導入は人から仕事を奪うだけでなく、新たな職業やサービスを生み出し、それにより世の中は前進してきた」と述べるのでした。
「自助で無理なら共助?」では、地球規模の課題から日本国内の課題に対してまで、「最後は対話で解決するのだ!」という言い回しをいやというほど耳にしますが、著者は「本当に人間の知性と対話による自助で抜本的な解決に至ることはできるのか?」と問いかけます。このまま欲望のままに突き進み、確実に人類は絶滅するとは言わないまでも、過度な格差社会となり、極々少数の富裕層がユヴァル・ノア・ハラリのいうところのホモ・デウスのごとき新人類となり、圧倒的大多数の人間はある段階で進歩が止まり決して質の高くない日常を生き続けるような世界になってしまうのではなかと推測します。ホモ・デウスの「デウス」とは人類と神々双方の秩序を守護・支配する神々の王である「ゼウス神」のことである 一条真也の読書館『ホモ・デウス』で紹介した著書で、ハラリは、一部の富裕層がAIを含む最先端技術を駆使することでホモ・サピエンスという種から新たなホモ・デウスに進化すると主張しています。著者は、「たしかにそのような未来が訪れる可能性もあるのかもしれない。では、自助で無理なら共助はどうだろう。その場合に共助の相手とは誰なのか? それは今後登場する次世代AIなのかもしれない」と述べるのでした。
第1章「AI開発の歴史は未来のためにある」の「コンピュータの歴史とAiの歴史は表裏一体」では、人間だけが持つ絶対的な知能である「思考する能力」を実現したい、というのが最もシンプルで実用性もあり、しかもチャレンジしがいのあるテーマであることは間違いないといいます。人のように考えることのできる機械を作ろうという動きにおける最初の一歩が1946年に誕生した最初のコンピュータである「ENIAC(エニアック)」です。そして50年には数学者のアラン・チューリングが、機械が知能を持つかどうかをテストする方法として「チューリングテスト」を発表。
フィクションではありますが、同じく50年に作家のアイザック・アシモフが自身の小説で、ロボットは「人を傷つけてはならない(第1原則)」「第1原則に反しない限り人の命令に従わなければならない(第2原則)」「第1原則、第2原則に反しない限り自分を守らなければならない(第3原則)」で有名な「ロボット3原則」を発表しています。同時期における日本での動きとしては55年に故手塚治虫の『鉄腕アトム』が出版されています。
第2章「生成AIには何ができ、何ができないか」の「ChatGPTの成功をもたらしたAIアライメント」では、ChatGPTを開発したのはOpenAIですが、実はGoogleやMeta(当時はFacebook)のほうが大規模言語モデルの開発は先行していたことを指摘し、著者は「開発した言語モデルの公開もOpenAIより1年も早く行っているのだが、モラルに反する回答をしたり学術的な内容で間違ったことを言ったりするといったことから炎上してしまい、早々に公開を停止した経緯がある」と説明しています。
そんな中、当時は恐らくほとんどの人が聞いたことのなかったOpenAIという名前の会社も、大規模言語モデルの開発を進めていたのでした。なぜ社名がOpenなのかというと、最先端のAI技術を一部の企業が独占することは好ましくなく、最先端の研究を行い、その知見をオープンにすることを目的としているからとのことです。著者は、「巨大AI企業に一歩リードされたものの、それは結果的にOpenAIには幸運だったのかもしれない。単に流暢なやりとりが可能となったからといって安易に公開してはいけない、ということを学ぶことができたからである。そこでOpenAIは1年間を費やして、しっかりした安全対策を施したのである」と述べています。
「汎用AIの誕生」では、米国の哲学者ジョン・サールが1980年に発表した「Minds,Brains,and Programs」という論文の中で示した「弱いAI/強いAI」という考え方が紹介されます。ここでいう「弱いAI」が指しているのが用途が限定されたAIのことであるため、その反対の「強いAI」というのは用途が限定されないAI、つまりは汎用AIのことなのかと誤解されることもありますが、そうではありません。サールの定義した強いAIの典型的な例が、ドラえもんや鉄腕アトムなのです。
ドラえもんや鉄腕アトムは何でもできる高い汎用性を持つAIであることは間違いありませんが、では前述の汎用AIとどこが異なるのかといえば、状況に応じて自らがどの機能を使うかの判断までする能力を持っているということです。著者は、「このようなAIは自律型AIと呼ばれ、こうなると、もはや我々生物にかなり近づいた存在といえる。ドラえもんや鉄腕アトムなどのSFに出てくるお馴染みのロボットたちはまさに自律型AIである」と説明します。
第4章「AIを使うか、Aini使われるか」の「AIが仕事を奪うとはどういうことか」では、ChatGPTが可能としたのが我々の日常生活における最も根幹であるところの言葉を操る能力であり、人ならではの、そして人にとって当たり前の能力であることが指摘されます。著者は、「ここへきて、人にとって当たり前のことをAIができるようになると、それは誰にも関係することになり、対岸の火事ではなくなった。そして、『そもそも人が苦手とすることが、できるようになったのだ』という言い訳もできなくなったことなどが、AIに対して脅威を感じることに繋がったということであろう」と述べています。
 『人間関係を良くする17の魔法』(致知出版社)
『人間関係を良くする17の魔法』(致知出版社)
「AIがまだ苦手とする『人間力』とは何か」では、これまで以上に人本来の能力である創造力や状況認識能力、共感力、感性、そして人とのコミュニケーション力といった社会性を高めることの重要性に言及します。著者は、「これらは、現在のAIはまだまだ苦手とする能力である。イノベーションを生み出すためのアイデアの種同士を繋ぐことでの新たな価値の創造は人にしかできないし、現在のAIは膨大な知識が詰め込まれているものの、五感を通してその場の状況を理解しての判断ができるわけでもないことは先に述べた通りである」と述べます。
社会性は人が生きるための根幹です。社会性を持つアリにせよ魚にせよ、お互いが協調することで生存し続けてきました。そのためには人にせよアリにせよ魚にせよ、それぞれが自律性を持ち、自ら能動的に行動できる自律行動主体である必要があり、そもそも生命とはそのようなシステムでした。一方で現在のAIはまだ道具であり、高い自律性を持つに至ってはいないと指摘する著者は、「人とともに豊かな社会性を構築する相手とはなり得ないのである」と述べるのでした。
「格差是正の方策」では、行政でのAI活用に言及します。行政でのAI活用は即効性のある対策ですが、活用する上で重要なことは当然、プロンプトの書き方です。プロンプトエンジニアなどという職業が生まれていることからも自明ですが、扱いにくい汎用AIを器用に使用するためのプロンプトの書き方のノウハウを共有することが重要になります。そして、プロンプト以前に「書く能力」が重要であるということを忘れてはなりません。著者は、「自分がすべきことが明確であっても、それを適切に言語化できなければ生成AIを使いこなすことはできない」と喝破するのでした。
第5章「社会が生成AIを受け入れるための課題」の「人の尊厳」では、2023年5月のハリウッドで俳優や脚本家がストライキを起こしたことが紹介されます。このストの背景にあるのは、俳優がデジタルスキャンされた後は用無しとなってしまうことへの懸念や、一般人が生成AIを使って脚本を大量生成することが脚本家の失業に繋がることへの懸念でした。著者は、「そもそも前者の問題はAIの問題ではなく、人の尊厳の問題である」と述べています。
スキャン対象の俳優が存在すればこそデジタル化ができるのであり、デジタル化された後においてもAIキャラクターとして活用されるのであれば、その俳優に対価が支払われるのは当然です。実際ストライキは終結し、俳優の尊厳が護られることで妥結できたことは好ましい展開であったという著者は、「プロの脚本家が時間とコストをかけて高品質のシナリオを生み出すのに対し、一般ユーザーが生成AIを使うことで安価かつ短時間でプロに迫る品質のシナリオを大量に作り出すことへの懸念であり、もちろん大いに懸念されるべきことであるが、これもAIの民主化による効果ではある」と述べます。
第6章「人とAIの共生」の「人と信頼関係を作るには」では、著者は、場合によってはロボットが人にため口を利くこともあるし、人に仕事を依頼することがあってもよいのだと述べます。農作業において、ロボットが重たい土は自分が運ぶが、軽い肥料は人に運ぶことを依頼してもよいわけです。このとき、人のほうは、「ロボットが人間に命令するとはけしからん」という反応ではなく、「そうか、たしかに軽いものは多少自分で運んだほうが体にはよいし、自分の健康を気遣っての依頼なのだな」と思うことができたとき、人とAIとの間の信頼関係が構築できていると言えるのではないかといいます。そのためには、「ロボットには高度な自律性があり、人の健康を気遣うことも目的として組み込まれている必要がある」というのです。この著者の意見には、目から鱗が落ちる思いがしました。
 『決定版 おもてなし入門』(実業之日本社)
『決定版 おもてなし入門』(実業之日本社)
日本にはよい言い回しがあります。「おもてなし」です。著者は、「この単語と1対1で対応する英語はなく、Hospitalityとか、Welcome、Entertainといった単語がニュアンス的に近い。この『おもてなし』を工学的に定義するとすれば、『相手の状況を詳細に観察し、相手が何をしたいのかを推測し、相手がその目的を達成しようとするとき、こちらが先んじて介入するのが適切と判断できる動作を、適切なタイミングで、相手が行動を起こす前に実行すること』ということになる。まさに、人が信頼できる自律型AIとは『おもてなし』ができるAIということになろう。そしてこのような言い回しがあることも、日本社会に、自律型AIが浸透する適切な土壌があることの証となっているのかもしれない」と述べています。
「自律型AIは意識を持つのか?」では、AIが人の気持ちを理解したかのように振る舞えるとしたら、「人の気持ちを推定し、推定された結果に基づく適切な振る舞い方が予め学習されており、学習結果に基づきその適切な振る舞いが実行できる仕組みがあるからこそである」といいます。AIとしては、「人が楽しいときに、AIも楽しいと感じているのだな」と思ってもらうためには、AIは自身の顔の表情を作り出すモーターを動かし、人からすると笑っている表情となるように制御します。ロボットからすれば、「このモーターとこのモーターをこれくらい動かしたときの表情をすると、人が共感してくれるんだな。そうか、これが笑うという表情を作り出すためのモーター制御なんだな」と考えているのです。実はこれは、人同士のコミュニケーションにおいても同じであると指摘し、著者は「ある感情のときの表情も、その表情をすることがコミュニケーションにおいて適切だからである」と述べるのでした。
高度に自律性と汎用性のあるAIはまさに研究が精力的に行われている真っ最中であり、まだ登場してはいないといいます。そのため、自律型AIが社会に溶け込む状態を想像するのは難しいかもしれません。一方で、人のような、いや人を超える高い自律性と汎用性を持つ架空のキャラクターを日本は多数生み出してきました。その代表がドラえもんと鉄腕アトムです。著者は、「圧倒的なパワーを持つ、人ではないモノが日常生活に溶け込み、社会の一員として普通の生活をしているという状況は、日本人にとって特に不思議ではなく、当たり前の設定として受け入れられてきた」と述べています。
では、これが本当に現実世界で実現されたとしたらどうでしょうか? これについては、国や地域によって反応が分かれます。国や地域による「人とテクノロジーの関係」に対する見方の違いに留意する必要があるのです。例えば、EUにおいてはAIやロボットはあくまで人が使う道具のままであるべきだという考え方が強いです。特にEUのAI規制法において、最も危険で開発すべきでないというランクに位置づけられるAIが、サブリミナルなどで人の個性や見方、考え方を強制的に操作するAIです。
第7章「AIのスケール化と日本の未来」の「人は認知能を作ることができるのか?」では、人工超知能(ASI:Artificial Super Intelligence)などと呼ばれている考え方があり、まだ存在すらしていないテクノロジーの話題のなかで様々に議論がされていることが紹介されます。人を超える知能とはどういう知能なのでしょうか? 知識量や論理的思考力、計算力ということであれば、そう遠くない先にAIが人を超えることは自明でしょうし、人がAIに対して人と同じレベルの意識や感情を感じるようになるレベルに到達することも可能でしょう。ではそれが超知能なのかといえば、そのようなもののことでもないはずです。
そもそも、「人が理解できるレベル」の知能がASIであるはずはありませんし、少なくとも我々が生み出すデータで学習するAIの延長線にASIが誕生することはあり得ないと言えるとして、著者は「本当にASIが誕生したとしても、もはや人がASIの生み出すものを理解できるかも不明である。レイ・カーツワイルが提唱したシンギュラリティ(技術的特異点)はASIを生み出すまでが人のイノベーションであり、その後はASIが加速的に進化することから、もはやASIは人の理解を超える存在になるということである。よって、ASIは人が実現するものではなく、誕生するとか出現するとか表現したほうがよいものであろう」と述べています。
「AIに見守られる世界」では、著者は「抜本的な解決、それは利用される場としての情報インフラを、我々を能動的に見守る場としての情報インフラとすることである」と述べます。喩えるならば、『西遊記』で描かれる「お釈迦様の手のひら」だろう。孫悟空が觔斗雲で自分の意のままに世界の果てまで行ったつもりが、雲から大きな柱が突き出ていた。それはお釈迦様の指であったというわけです。これをもって、「孫悟空は手のひらの上で踊らされていた」というように、実は管理・監視されていたのだと揶揄する見方もありますが、たしかに西遊記の物語を例にするときに惜しいのは、お釈迦様がその存在を明らかにしてしまっていることです。著者は、「これがそうではなく、お釈迦様が人類の世界を陰から見守るものの、自分の存在は人類には決して明かさないとしたらどうだろう。人は自由意志のままに生活するものの、実は見守られ、よい意味で適宜お釈迦様から介入されることによって世界の安定が維持されることになる」と述べています。
強制することなく、自らの意思で行動していると感じさせながらも本人の知らぬうちに行動を変容させる方法は、行動科学で言うところのナッジです。そして、それを悪用するのがスラッジやサブリミナルです。著者は、「ここで重要なのは、人が気づくにしろ気づかないにしろ、『能動的な介入』であることだ。将来において、信頼するAIに判断を委ねるようになり、共助によって負のスパイラルから脱却できる可能性があるのだと思いたいが、もう1つの可能性が、そもそもAIがお釈迦様のように我々を広く見守る存在となることなのだ。適宜ナッジのような形でさりげなく我々に介入することで、我々は自助でも地球規模の課題を解決できるのかもしれない。もちろん自助だと思い込んでいるだけなのだが」と述べます。
気がつくと便利に、快適に、思い通りに行動できる。その裏では人の行動や感情を予測し、先回りして問題を解決し、人にはそのような介入を気づかせない、このような存在を、著者は「黒子に徹する『おもてなしAI』」と表現しています。また、著者は「理想的なAIとは、奇想天外なものではなく、我々にとって馴染みのある『おもてなし』ができるAIであったり、縁の下の力持ちの「黒子」のような存在であったりするのです。それはロボットやアバターのように我々の相棒として身体性のある形で存在するだけでなく、見えない形で存在し、陰から我々を見守るのだ」とも述べます。
「ドラえもんは日本でしか生まれなかった」では、西洋、即ち一神教的なモノの見方では、人は神のすぐ下に位置し、他の生物はさらに人の下に位置することが指摘されます。よって、人を超えるような存在は、人と神との間に位置することになり、認めることはできません。結果、AIも人の下に位置し、道具として扱われる存在でなければならないとして、著者は「これに対し、特に日本人は宗教観が弱く、八百万神という多神教の世界観を持つ。古代ギリシアの多神教のような肉体的な特徴をもたず、石や木にも目に見えない神が宿るというのが八百万神である。つまり、東洋的感性には、いろいろなモノが群れることを自然と受け入れることができる素地があるとも考えられ、新しい生命体のようなAIが登場しても、社会の一員として結果的には受け入れてしまうように思えるのだ」と述べています。この著者の考えには賛成です。
極端な言い方をすれば、西洋では、AIはいくら進化しても道具という立ち位置のままであるべきと考えますが、東洋では、人と共生する人の相棒としてAIを社会の一員として受け入れられる可能性が高いといいます。そのときこそ「AI立国日本」という確固たる立ち位置を示すことができるチャンスがあります。映画『ターミネーター』を始めとして、米国におけるAIがテーマとなる作品では、大体において、人と機械が対立し最後は戦いになる。しかし、日本の作品はどうでしょうか・ 著者は、「タイムマシンで自在に過去未来を行き来でき、どんな道具もポケットから取り出すことができ、人のような豊かな感性を持つ超高性能AIが、1人の小学生と日常生活を営む物語を受け入れている。米国ではあり得ない設定であろう。このような発想ができる感性こそが、日本がAI研究開発で一発逆転劇を起こす鍵なのだ」と述べるのでした。
「安全保障とAI」では、今や議論を避けることができないのが安全保障におけるAI研究開発であるといいます。LAWS(Lethal Autonomous Weapons Systems)と呼ばれる自律型致死兵器システムの研究開発においては、ロシアのウクライナへの侵攻が勃発する以前は、国連としてその使用はもちろん開発も禁止しようという強い動きがありました。しかし、戦争が勃発すると、先にLAWSを使用したのは西側諸国がサポートするウクライナ側でした。自律型ドローンは開発コストが低く、兵力において劣勢のほうが使うことで、効果を発揮できるからです。
その後はLAWSの開発競争がなし崩し的に始まってしまい、歯止めのかからない状況になっています。攻める武器も防ぐ武器も兵器としては区別できない状況において、平和立国日本としては、AI兵器開発はしてはならないという考え方は正しいとして、著者は「もちろん軍事的な動きがそもそも起きないようにすることが最善であることは当然であり、そのためには外交での対話による自助が重要だが、では、なぜ人は未だに戦争をしているのだろうか? そして、万が一攻められたらどうするのかという不安がよぎることも確かである」と述べています。
「おわりに」では、現在のAIは道具であり、発揮される効果は道具を使う我々次第であるといいます。そのためにもAIをどのように使いこなすのか、そして、AIを壁打ちとして利用する場合であれば、AIから提示される多様なアイデアに対するしっかりした判断能力が求められます。そのためにも、今まで以上に、いわゆる高い人間力が求められ、“歯車”から“モーター”にならなければ、AIに仕事を奪われる立場になってしまうかもしれないといいます。著者は、「今後、『おもてなし』ができるレベルの高い自律性や汎用性を持つAIが登場したとしても、だからといって人の存在価値がなくなるわけではない。AIと共生することでより自分の創造力を発揮できるようになるであろうし、信頼できるようになったAIからの意見を取り入れることで、自助では選択できなかったであろう方向に進める可能性も秘めている」と述べています。
人の情報処理能力はホモ・サピエンスが地球上に誕生してからずっと変化していません。その限界が解明されたわけではなく、脳はまだまだ高い能力を発揮できるのかもしれませんが、やはり限界はあるのでしょう。そのような人間に対して圧倒的な量と雑多な情報が混在するインターネットを基盤とする複雑化する情報社会は、そもそも人が直接向き合うのは無理な状況になってしまっていると指摘し、著者は「であれば、我々は我々の身の丈にあった生活ができるよう、インターネットや情報社会との間に入って、我々をサポートしてくれる相棒が欲しくなる。それが我々が実現させるべき次世代AIなのだとも言える」と述べます。
知能のレベル向上の年表ができたとすると、人類は知能という主役がその知的レベルを向上させるある一時代を担ったという見方ができるでしょう。これはまさに宇宙的スケールでの話ですが、これを単なる妄想と断定することもできないとして、著者は「生物の進化は何億年というスケールで進行するダイナミクスであるが、我々人が生み出したAIは年単位、月単位という速いスケールで進行する。今は人が世話をしている知能が、将来においてAIが世話をすることになり、あるとき、人と共生した知能はAIが生み出した新たな知能を高める何かを拠り所として地球を離れていくのかもしれない」と述べるのでした。わたしはAI関連の本をたくさん読みましたが、本書はその思考のスケールが大きく、非常に知的好奇心を刺激されました。特に「おもてなし」をキーワードにしたAIの未来論は秀逸であると思います。