- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.0404 民俗学・人類学 『贈答の日本文化』 伊藤幹治著(筑摩選書)
2011.08.05
『贈答の日本文化』伊藤幹治著(筑摩選書)を読みました。
本書のテーマである「贈答」は、日本の儀礼文化の核となるものです。
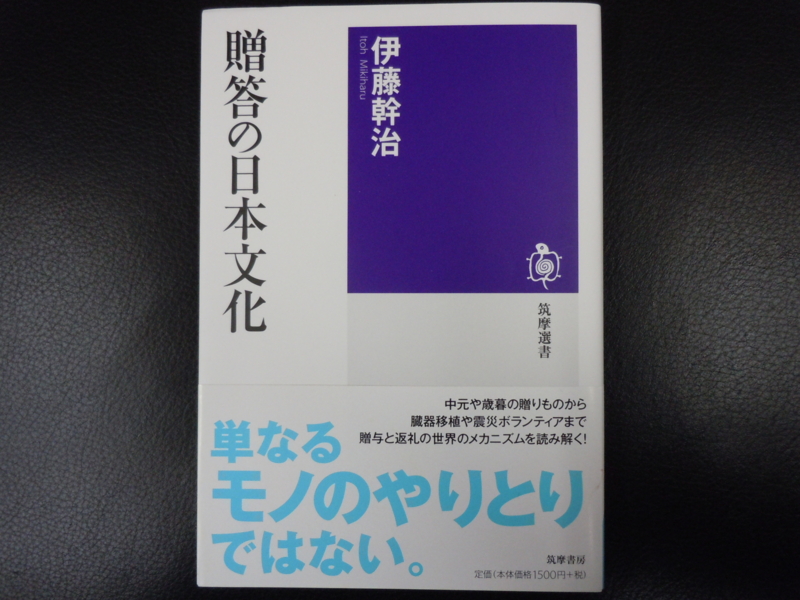
贈与と返礼のメカニズム
著者は國學院出身の民俗学者で、国立民族学博物館教授、成城大学教授、成城大学民俗学研究所所長などを歴任し、現在は国立民族学博物館の名誉教授です。
また、柳田國男全集編集委員を務め、第1回澁澤賞・第18回南方熊楠賞を受賞しています。著書も多いですが、その中の『宴と日本文化』(中公新書)という名著を、わたしは『遊びの神話』(PHP文庫)で取り上げたことがあります。
本書『贈答の日本文化』では、人類学者モースの『贈与論』などの成果を踏まえて、「贈与」「交換」「互酬性」といったキーワードを手がかりに、日本文化における贈答の世界のメカニズムを読み解いています。
本書の目次構成は、以下のようになっています。
序章 贈答の世界を解読するために
1:現代日本の贈答
2:共通文化と民俗文化
3:贈与/交換/互酬性
第1章 贈答の過去と現在
第1節 世相からみた贈答
1:贈答と生活改善運動
2:贈答の両義性
第2節 農村の贈答
1:年中行事のなかの贈与と返礼
2:通過儀礼のなかの贈与と返礼
第3節 都市の贈答
1:贈答の3つの型―連続・受容・創出
2:交換論からみた都市の贈答
第2章 贈答の仕組み
第1節 民族誌からみた互酬性
1:贈与と交換の民族誌
2:互酬性の再検討
第2節 互酬性の原理
1:返礼の期待と返礼の義務
2:恩と義理の概念
第3章 贈答の諸相
第1節 贈答の持続と変化
1:象徴的返礼としてのオウツリ
2:仕掛けられた交換―バレンタインデーとホワイトデー
3:交換財としての食物
第2節 贈答の文化装置
1:均衡原理と競合原理
2:記憶装置としての祝儀帳と不祝儀帳
3:贈与と返礼の調整装置
第4章 贈答と宗教的世界
第1節 アニミズム的汎神論の世界
1:小さな神がみとの交流
2:神への贈与
第2節 共存の論理と救済の論理
1:現世志向と来世志向
2:無償の贈与としての喜捨
終章 贈答と現代社会
1:現代日本の公的贈与
2:贈与の論理と贈答の論理
「あとがき」
本書の冒頭で、著者は「贈答とは単なるモノのやりとりではない。特定の機会に贈りものをやりとりする儀礼的行為である。毎年、中元や歳暮の季節が訪れると、贈答品が全国各地を頻繁に往き来する。子どもの誕生、結婚、葬式などの改まったハレの日、あるいは病気、地震や洪水などの自然災害、旅行、転居、新築などの折にも、見舞いやお祝いといってはモノが贈られ、お返しがされる。この国の人びとは、毎年こうした贈りもののやりとりを繰り返している」と述べています。
日本人における贈答の習慣は、すでに中世後期の武家社会に成立していたそうです。
伊勢貞親という室町幕府の要人が『伊勢貞親教訓』という書物に、「他家より人の物くれたらんには、相当の贈るほどの返しをすべし」とあるのです。贈りものを貰ったら、それに見合うだけのお返しをしなければならないということですね。
当時の武家社会では、「均等交換」が行われていたわけです。こうした贈答の習慣は、中世後期以降、いろいろと変化を繰り返しながらも、近世・近代を経て現代にいたります。現代日本においては、さまざまな贈答が行われています。
まずは、中元や歳暮、結婚式や葬式のときの贈りものとお返し。そして、クリスマスやバレンタインデーやホワイトデーなどの贈りもののやりとり。さらには、社会のグローバル化やボーダレス化にともなって寄付行為、ボランティア運動、臓器移植、開発援助なども広い意味での贈りものにあたるでしょう。
日本の贈答文化には、明治維新のとき、大きな変化がありました。明治維新以降、東アジアの後進国であった日本は、国民国家の形成をめざしました。そのため、欧米先進諸国の政治、経済、法律などの諸制度の導入に努めたのです。そして、国民国家の基礎を固めるために、この国に平準化された共通文化を創出しようとしていました。著者は、次のように書いています。
「政治エリートたちが最初に着手したのは共通文化の枠組みづくりであった。ひとつは、1868(明治元)年から開始され、神話、儀礼、象徴などを操作して制定された国民祝祭日の制度化である。いまひとつは、1872(明治5)年12月の太陽暦の採用である。もひとつは、1876(明治9)年に制定された日曜休日制である。
いずれも、この国に平準化された共通文化を創出するための制度上の枠組みであった。その過程で、正月(元日)、春秋の彼岸(春分の日、秋分の日)、5月の節句(こどもの日)などの、近代以前から全国各地で伝承されてきた民俗文化は、共通文化のなかに徐々に統合されることになった」
共通文化を創出する試みとしては、「共通言語」としての国語の創出と普及、神社制度の改革による国家神道の創出と普及なども挙げられます。それらの規範文化が、敗戦によって挫折したことは言うまでもありません。
一方、明治30年代に東京大神宮(日比谷大神宮)で最初に挙行され、急速に全国に普及していった「神前結婚式」などは民俗文化であると言えます。
共通文化の創出というのは、為政者による日本の儀礼文化の破壊という一面があると言えるでしょう。儀礼文化破壊の危機は、明治期だけでなく終後にも訪れました。
戦後、国民生活の合理化を促進するために、いわゆる政府主導の生活改善運動が展開されたことがあります。全国の自治体の協力を得て、婚礼の簡素化や香典の廃止などが推進されました。その結果、冠婚葬祭の慣習および贈答習俗の一部に変化が生じました。
しかし、民俗学者の田中宣一などは、香典返しの撤廃、香典の低額一律化などに一定の効果をあげた地域もあったが、逆に冠婚葬祭の簡素化が一時的な現象にすぎなかったり、あるいはまったく実施されなかったりしたところが多かったと報告しています。
なぜ、生活改善運動は思ったほどの効果を上げなかったのか。その理由について、著者は次のように述べています。
「生活改善運動を促進した為政者側が、贈答とよばれる贈りもののやりとりが近代以前からながいあいだ、日本社会に根をおろしている返礼の期待と返礼の義務という、人間社会に普遍的な互酬性の原理に根ざした慣行であることを十分に認識していなかったからであろう。互酬性の原理には、国家権力がいかに介入しようとしても容易にほろびを生じないしたたかさがある」
まさに、贈答という行為は人間にとって地域を超えた普遍性を持っていたのです。人間とは「贈答するヒトである」と言えるかもしれません。日本人の贈答といえば、誰しも中元・歳暮を思い浮かべるでしょう。もちろん、その他にも贈答の機会はあります。著者は、次のように述べています。
「日本の中元と歳暮は、欧米のクリスマス・プレゼントと同じように、近代以前から伝承されている贈答の機会である。それに対して、家族の誕生日、クリスマス、結婚記念日は、近代以降に欧米から受容された贈与の機会である。このように欧米から文化要素を受容することによって、日本社会の伝統的な贈答の世界は変化をとげてきたが、1970年代以降、欧米から再び父の日(6月第3日曜日)、母の日(5月第2日曜日)、バレンタインデー(2月14日)という、あたらしい贈与の日が導入されることになった」
バレンタインデーは欧米を中心に世界共通ですが、日本人はまことにユニークな新しい贈与の日を作り出しました。ホワイトデーです。このホワイトデーについて、著者は次のように述べています。
「ホワイトデーとよばれるお返しの日は、近年のグローバル化とローカル化が相互に影響しあって生まれたグローカリズムを表象している。現代日本社会には、こうしたグローカリズムがいろいろ認められるが、ここではバレンタインデーとホワイトデーが、後述する返礼の期待と返礼の義務という、人間社会に普遍的にみられる互酬性の原理を巧みに操作して創案されていることを指摘しておこう。
ホワイトデーの創出によって、現代日本社会には3つの型の贈答が共存することになった。ひとつは、近代以前から伝承されてきた中元、歳暮などの連続型である。いまひとつは、近代以降に欧米から受容された家族の誕生日、クリスマス、結婚記念日などの受容型である。もうひとつは、1970年代以降、特定企業によって仕掛けられたバレンタインデーとホワイトデーという創出型である」
さらに著者は、こうした3つの型は、この国の歴史過程にみられる文化の連続性、可変性、創出性という、日本文化の3つの属性を反映していると分析しています。ホワイトデーをきわめて日本的な贈答文化と見る著者は、次のように述べます。
「バレンタインデーの『贈与』という欧米の慣習を受容するにあたって、日本の企業がホワイトデーと名づけた贈与に対する『返礼』の日をあらたに設けたのは、オウツリやオタメという象徴的返礼が示唆しているように、日本人の社会規範のなかに、中世後期以降贈与には返礼が欠かせないとする『贈答の論理』がひそんでいることに着目したからであろう」
欧米でも新しい贈与の日の創出は試みられているようで、著者は次のように述べます。
「欧米社会では、贈りものとしての商品が活発にやりとりされるクリスマスの季節は、1年のなかでも最大の贈与の機会である。J・デーヴィスの『贈与と英国経済』(1972年)によると、英国では1970年ごろ、挨拶状、化粧品、花などの業界の代表者が、特定日促進委員会を組織して10月第2日曜日を『祖母の日』とする運動を展開したことがあったという。父の日や母の日のほかに、あたらしい贈与の日を創出して贈りものをする機会を拡大し、消費をうながそうとしたのである」
ちなみに、フランスでは3月第1日曜日が「祖母の日」として定着しています。著者は日本の贈答文化の特徴として食物の交換をあげ、次のように述べています。
「食物の『贈答交換』がたびたびおこなわれるのは、多くはハレの日である。彼岸のボタ餅などのように、先方にあるのがわかっていても贈る。また、一定の日に一定の親方に餅などを贈呈し、むこうからもやはり贈っているところがある。日本のように食物を贈りあう例は文明国ではめずらしい。他には見られぬところである。これはいわゆるカワリモノの作法で、変わった品物の交換を意味する。古風はこわれているが、機会があるたびにそれが願われるのである。これを一概に国民性といってしまうことには警戒を要するが、特殊なものは一緒に食わねば―共同飲食をせねばならぬと思う特殊な気持ちからすることであって、それがいまも残っているのである」
さらに、日本人の贈答文化の核心に迫っていく著者は、次のように述べます。
「日本社会には、近代以前から誕生祝い、結婚式、葬式などに、親戚、友人、知人からモノや金銭が贈られる慣習が制度化している。その際、贈り手の名前、贈られた品物とその数量、あるいは金銭の額が記録される。その記録は一般に祝儀帳、不祝儀帳とよばれ、贈与と返礼のメカニズムをあきらかにする有力な手がかりのひとつになっている」
日本人の贈答文化を知る上で、本書に紹介されている社会心理学者のH・モーズバッハのエピソードが非常に印象的でした。1981(昭和56)年3月、国立民族学博物館の特別研究「日本社会における贈答の数量統計的研究」の一環として、同館でおこなわれた国際シンポジウム「日本人の贈答」(Gift-exchange among the Japanese)で発表した「西欧人からみた日本人の贈答風俗」(1984年)のなかで、モーズバッハは次のようなことを述べています。
「1968(昭和43)年にわたしと妻が京都で2人の学生と出会ったときのことである。歓談したのち、町で軽い食事をいっしょにしようと彼らをさそった。わたしたちは知りあったばかりであったし、高いものをたべるつもりはなかった。しかしちょうど正月であったため、ほとんどのレストランが休業していたので、あちらこちらさがし歩き、やっとのことで非常に高級そうな『すきやき』の店をさがしあてた。心づもりのないときにしては、あきらかに贅沢な店だったので、いくぶんためらいをかんじた。けれども、選択の余地はなかった。案の定、勘定書きはたいへん高かった。知りあって間もない友人である2人の学生もそのことに気づいていた。わたしと妻が東京にもどってから、つぎの週に、その2人の学生から小包をうけとった。なかには、美しく高級そうな七宝焼の壺がはいっていた。その壺を鑑定家のところにもっていくと、およその値段がわかった。おどろいたことに、それは4人分のすきやきの値段にほぼ等しかった。そして、2人が相応の返礼をすることによって、義理をはたしたのだ、ということもわかった」
このエピソードを知ったわたしは、日本人として大変嬉しく思いました。
さて、日本人の贈与におけるキーワードとして、「現世利益」があります。わたしたち日本人は、何らかの「ご利益」を期待して、神社や寺の賽銭箱にお金を入れたり、もっと多額の寄付をしたりします。このような行為について、著者は次のように述べています。
「現世利益は仏教用語である。近世以降、日本社会で現世利益という思想が民衆のあいだにひろく受け入れられ、その内容は多岐にわたっている。家内安全、無病息災、大願成就、病気平癒、子孫繁栄、商売繁盛、五穀豊饒、工事安全、航海安全、厄除け開運、学業成就、入試合格、恋愛成就などがある。そこに、この世における人びとのさまざまな世俗的願望が盛り込まれている」
そして著者は、日本人の「現世利益」志向の背景にアニミズムの存在を見ており、次のように述べています。
「アニミズム的汎神論の世界に住む小さな神がみのなかに、耳神や腰神などの病気を治してくれる神がみが多く創出されているのは、病気平癒を願う人びとの現世利益の思想とまったく無縁ではあるまい。彼らにとって大事なのは、キリスト教が根をおろしているヨーロッパの人びとのように、『あの世』(彼岸)における救済ではない。『この世』で共存する小さな神がみから授かるご利益である。アニミズム的汎神論の世界は、このように人びとの世俗的願望にもとづいて神がみが創出され、神がみもまた、人びとの世俗的願望に直接応えてくれると信じられることによって存続してきたが、その背後には人びとの『この世』を重視する思想がひそんでいる」
「現世利益」を仏教用語であると言いましたが、それはあくまで日本仏教の用語です。ブッダが開いた原始仏教においては「喜捨」というキーワードがあります。「喜捨」とは、富めるものが貧しいものに自分の財を与える「無償の贈与」のことですね。
また、ユダヤ教やキリスト教にも「無償の贈与」という考え方があります。『旧約聖書』には、貧しい人、旅人、孤児、寡婦のために、畑を刈り残して、落ちた穂や実、置き忘れた束などをそのままにして置くことが説かれているのです。こういったことを踏まえて、著者は次のように述べます。
「このような宗教的風土を考えると、神がみと人びとの直接互酬性を基調とする日本社会では、キリスト教社会のように神と人の間接互酬性にもとづいた救済観や喜捨という無償の贈与の思想が根づくのはなかなかむずかしいのではなかろうか。それにしても、世俗的価値を容認し、これを正当化しているために、日本の宗教は解決しなければならない問題をいろいろかかえ込んでいる」
現在、贈与はグローバル化社会を迎えて、じつに多彩な広がりを見せています。
D・チールは「贈与行動の社会的次元」(1986年)の中で、贈与を私的贈与と公的贈与に分けています。そして、私的贈与を持続的関係をもつ個人間の贈与、公的贈与を集団への寄付もしくは寄与というかたちをとる贈与と規定しています。
毎年、年末の贈答の季節に行われる「歳末たすけあい」「海外たすけあい」、あるいはUNICEF(国際連合児童基金)の活動などが公的贈与です。ボランティア活動、献血、臓器移植、開発援助などは、いずれも公的贈与ということになります。
これらは、いずれも不特定多数の「見知らぬ人びと」に対する寄与もしくは寄付です。これを贈与論の文脈でとらえると、ボランティア活動は「労働贈与」、献血は「血液贈与」、臓器移植は「臓器贈与」と言い換えることができると著者は述べます。
本書を読んで「面白いな」と思ったのは、献血のエピソードです。東京都赤十字血液センターでは、血液を安定して確保するために、これまで牛乳、清涼飲料、ハンバーガー券、菓子などを献血者に提供していたそうです。それが、最近では「献血離れ」に歯止めをかけるために、若者や女性向けにタロット占い、専門家によるネイルカラー、マッサージなどのサービスをはじめているというのです。
これには非常に驚きましたが、贈りもの(血液)を貰ったら手ぶらで返してはならないという「交換規則」が日本人の間には共有されていることを痛感しました。
現在、日本の贈答文化、ひいては儀礼文化は大きな曲がり角に来ています。そのことを、著者は次のように述べています。
「近世以降、ながいあいだ日本社会に定着していた香典と香典返しにも変化の兆しがみられるようになった。一部の人びとのあいだで、弔問者に直接、香典返しをおこなわずに、死者が生前世話になった病院その他の公共機関に、香典の全額もしくは一部を寄付するという慣習が生まれていることである。このことは、香典と香典返しが『私的交換』(贈答)から『公的贈与』寄付)に転換しつつあることを示唆しているとみてよかろう。
こうした変化とは別に、近ごろ日本社会にも普遍的な社会規範に根ざした見返りを求めない公的贈与がみられるようになった。恵まれない子どもたちに贈りものをする『タイガーマスク現象』とよばれる匿名の贈与が、そのひとつである」
著者は、「無縁社会」などと呼ばれる現代日本社会の問題点も視野に入れます。そして、本書の最後で次のように述べています。
「現代日本社会は現在、解決しなければならない問題をいろいろかかえている。見知らぬ人びとがたがいに絆で結ばれ、たがいに助けあう社会的連帯の問題などはそのひとつであろう。都市ではかつて血縁、地縁によって支えられていた人びとの絆がうしなわれ、孤独で不安定な生活を強いられているからである。ここに取りあげた見返りを期待しない普遍的な社会規範にもとづく公的贈与などは、こうした問題を解決するためのひとつの糸口になろう」
わたしは血縁、地縁の再生を試みながら、新しい「有縁社会」づくりをめざしていますが、著者のいう「見返りを期待しない普遍的な社会規範にもとづく公的贈与」というものが今後重要になってくるだろうと思いました。
本書の内容は、文化人類学(民族学)と民俗学という、2つの学問的領域にまたがっていますが、もともとは1つの根から生まれた兄弟であり、姉妹です。
人類における「互酬性」というものがいかに普遍的であるかに注目しながら、日本の贈答の仕組みを明らかにする本書は、これからの有縁社会のあり方にも多くのヒントを与えてくれる名著であると思いました。