- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2332 宗教・精神世界 『中途半端もありがたい 玄侑宗久対談集』 (東京書籍)
2024.06.06
『中途半端もありがたい 玄侑宗久対談集』(東京書籍)をご紹介します。ブログ「玄侑宗久先生との対談」で紹介したように、わたしは5月29日に玄侑氏と対談させていただきましたが、その予習として2012年に刊行された本書を読みました。面白く、かつ学びの多い一冊でした。
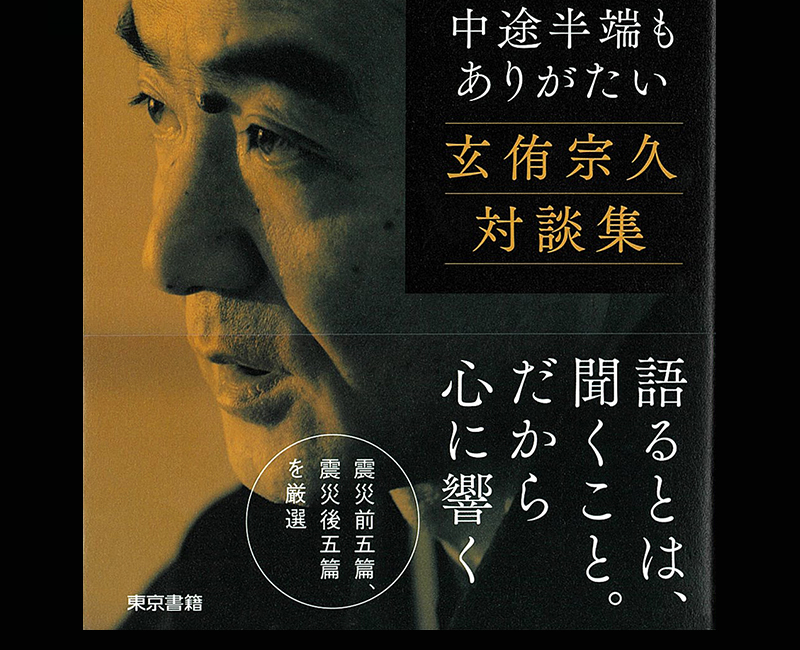 本書の帯
本書の帯
カバー表紙には玄侑氏の顔写真が使われ、帯には「語るとは、聞くこと。だから心に響く」「震災前5篇、震災後5篇を厳選」と書かれています。また帯の裏には、「いずれも斯界の第一人者。私としては講義を受ける気分だが、それでは対談にならないので半端な言葉を差し挟む。(中略)大震災の前後で自分がどう変わったのかは、読み返してもよくわからない。それは読者の判断に任せ、私としてはこの刺激的な人々の話がすべていつでも読み返せる形になったことを独り歓んでおこう。――まえがきより」と書かれています。
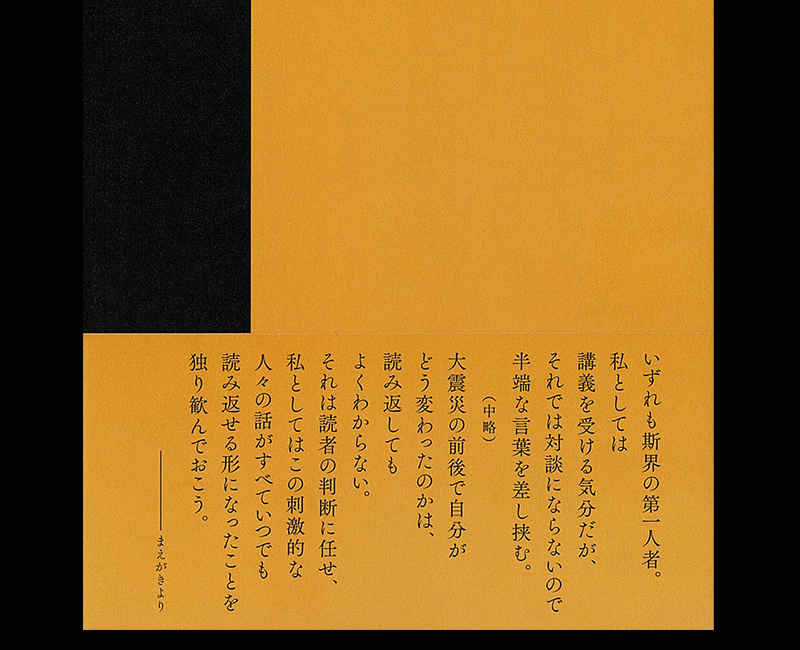
本書の「目次」は以下の通りです。
「中途半端もありがたい」
木田元 回り道の人生
辰巳芳子 父性と母性
五木寛之 老いを愉しむ
養老孟司 日本人の心の古層
片田珠美 個性病を超えて
山田太一 心の復興
中沢新一 無常からの再出発
佐藤優 福島と沖縄
日野原重明 足るを知る
山折哲雄 原発作業員に祈りを
 対談する玄侑氏
対談する玄侑氏
「中途半端もありがたい」の冒頭には、いきなり以下のように書かれていて、わたしは衝撃を受けました。
「対談とは、どだい中途半端なものである。たいていは出版社(あるいはクライアント)の企画意図に左右されるし、相手のかたが長年かけて蓄積してこられたことがそう簡単にわかるはずもない。対談準備というのもむずかしいもので、準備しすぎると面白くなくなってしまう。事前にその著書などを読みすぎると、相手の言葉が新鮮に感じられず、そうなるとこちらも新奇な発想ができなくなる。かといって、何の準備もしなければまっとうな反応もできないから、相手のテンションを下げてしまい、結局は自分も面白くなくなってしまう」
 これを読んで当惑しました
これを読んで当惑しました
これを読んで、わたしは当惑しました。なぜなら、わたしは対談相手のことをきちんと予習するのが礼儀だと思っていますので、今回も玄侑氏の著書を(再読も含めて)固め読みし、しっかり準備していたからです。でも、「対談とは、どだい中途半端なもの」と言われれば、その通りだなとも思います。それならどうすればいいのでしょうか。著者によれば、「やはり中途半端がいい」そうです。「ある程度は相手のことを学んだものの、まだまだそれはアウトラインにすぎず、言ってみれば過去のことにすぎない。きっと自分との対面では、これまで知らなかった側面も出してくださるに違いない……。そのような、不安と期待とある種の信頼感を中途半端に抱きつつ臨んだとき、たいてい対談はうまくいく」と述べています。
 対談は中途半端がいい!
対談は中途半端がいい!
相手が話している時とき、無意識ではあっても自分の次の言葉が準備されています。それが意識的になってしまうと、あるところから相手の言葉は聞かなくなります。じつはそのほうがテンポはいいのですが、自分の中に大きな化学変化は起こりにくくなります。しかし逆に、その場で相手の言葉に100パーセント聞き入ってしまうと、ぐずぐずした反応しかできなくなります。著者は、「面白いやりとりというのは、本当に虚心にはなってしまわず、ある程度の思い込みを保つことで可能になるのではないだろうか」と問いかけ、最後は「人生も結局はあらゆる外部世界との対談のようなものではないだろうか。ならば人生も、慣れた習慣と新たな創造との中途半端な混合体であることこそ望ましい。習慣という安らぎと創造による躍動は、じつは相互補完的な関係なのだ」と述べるのでした。
「回り道の人生」では、哲学者の木田元氏と対談します。
木田氏は「ソクラテス以前のギリシャ人の考え方にしても、『古事記』にしても、ケルト神話にしても、自然というのは生きて生成するものだという、かなりアニミスティックな自然観ですよね」と語りますが、玄侑氏は「そこから輪廻という考え方が生まれるには、何かがさらに加わったのだと思います。埋葬で考えると、火葬をした人々というのは、インドとゲルマンの古い人々しかいないんですね。あれは、遺体の中にあった魂が何か別のものに入る、という輪廻の考え方があって初めてできると思うんです。単なる抜け殻だと思うためには、輪廻転生という考え方がかなり裏付けになっているわけです」と述べています。日本仏教が渡ってきた頃、中国では大論争の挙げ句に輪廻は否定されているんです。輪廻を認めると、自分の先祖の中に豚や牛もいることになる。それは耐えられないというので、輪廻だけを外して仏教は日本にくるんです。そうすると死後の保証がないままに火葬することになりますから、奈良の元興寺で初めて火葬が執り行なわれたときには、まるでオウム真理教を取り囲むような騒ぎになったんです。
やがて浄土思想というのが出てきてその問題は解決しますが、それまでは火葬というのはやはり残酷に見えるわけです。玄侑氏は、「輪廻観というのがはっきりあってこそ焼けると思うんですよ。それがゲルマンの古葬でも行なわれていたということは、やはりそこにも輪廻観があったんだと思うんです」と述べます。すると、木田氏は「ギリシャでもピタゴラス教団は明らかに輪廻思想を持っていました。ピタゴラス教団のもとはオルフェウス教らしいですね。だからオルフェウス教にもピタゴラス教団にも、それを受け継いだプラトンにも輪廻思想というのがあったのです。ただそこでは、肉体は魂にとっては牢獄みたいなもので、そこから抜け出すことが魂の浄化につながっていくという考え方をしていました」と述べるのでした。
「死を意識した戦争体験」では、木田氏が敗戦間際の昭和20年4月に江田島の海軍兵学校に入ったことが紹介されます。実際に海軍兵学校に入って驚いたのが、成績によって卒業後の生存期間まで決まるということだったそうです。以下の会話が展開されています。
玄侑 あぁ、成績が悪いと危険なところに配属されるんですね。
木田 一番は海軍省に入り、二番は戦艦に乗り、順位が下がるにつれてだんだん条件が悪くなっていくんです。航空隊には入るのはまだいいほうで、さらに下がっていくと潜水艦に乗ったり。あの頃、回天というのがあったでしょう。
玄侑 人間魚雷ですね。
木田 それより下が陸戦隊。これは敵の戦車が上陸してくると、爆雷を抱え込んで体当たりをして阻止するんです。つまり、成績順に分隊での席次が決まり、成績によって卒業後どれくらい生きられるかが決まってくるんです。
玄侑 それはすごい話ですよね。
木田氏によれば、その成績は、数学ができるかどうかでほぼ決まったそうです。ところが、入学後まもなく数学の宿題が出て、木田氏が1題やる間に隣の同級生は20題全部解いたそうです。それを見て、木田氏は「これはまずいところに来たなと思いました。ですから、戦争が終わったときには心底ホッとしましたよ。ちなみにその隣の同級生は、後に日立製作所の会長になりましたが」と述べています。また、当時はいまのように、引きこもりだとか鬱だとかはありませんでした。そのことについて、玄侑氏は、「ほとんどの精神疾患は、戦争のような極限状態になると治ってしまうと聞いたことがあります。それは皆が同じ目に遭っているからということがあるのかもしれませんし、外圧がかかると内面に生ずる反発力のようなものによって元気になるという面もあるのかもしれません」と述べています。
「人生に回り道はない」では、玄侑氏が「私もさんざん回り道をした挙げ句に思うことは、回り道なんてないということですね。結局自分にとっては真っ直ぐだったんですよ」と述べています。孔子的な人生観からすると、而立、不惑、知命というのは一本道です。孔子が30歳で政治思想をいろんな若者に教えていくということを始めて、40歳で惑わなかった、50歳にしてそれが自分の天命だと悟った。これは本当に一本道であると指摘し、玄侑氏は「あらかじめ決めた目標の遂行を重視するその考え方からすると、確かに多くの人は回り道をしてきているんですけれども、老荘はもうちょっと違う見方をします。老荘の行動原理というのは『やむを得ず』なんです。やむを得ずしたことのみが『至れり』、素晴らしいんだと。逆に、やむを得ずでないことは皆人為と見なすんですよ」と述べるのでした。
「人間は死に臨む存在か」では、サルトルはハイデガーの「死に臨む存在」という概念に疑問を呈して、「死というのは理解したり、それに態度決定したりしながら生きることができるようなものではない死というのは突然、理不尽に襲いかかってきて、人生のすべてを無意味にしてしまう出来事なのだ」と言っていることが紹介されます。メルロ=ポンティもこれに同意しています。木田氏は、「僕も死についての考え方では、どうもハイデガーよりもサルトルやメルロ=ポンティのほうに共感を覚えますね。『葉隠』の「武士道と云うは死ぬことと見つけたり」みたいなハイデガーの考えは、ちょっと理解できないんです。プラトンなんかも『パイドン』を書く頃になると、ピタゴラス教団で輪廻思想を学んできて、魂は不死で、それを肉体から浄化することが哲学の仕事だと説き始めます。哲学することは死ぬことの練習をしているようなものだ、死ぬことのエクササイズだなんて言い出すのです。しかし僕は孔子の言う『いまだ生を知らず。いずくんぞ死を知らんや』のほうがよくわかる気がするんです」と述べるのでした。
「父性と母性」では、料理家で随筆家の辰巳芳子氏と対談します。
「三つの心」では、道元禅師は「人は三つの心を持たなければいけない」というふうに言ったことが紹介されます。ひとつめが「喜心」、喜ぶ心。二つめが「老心」、親が子どもを慈悲深く見つめるように見る心。三つめが「大心」で、玄侑氏は「大きな心というのは、おもしろいんですけど、『春声にひかれて春沢に遊ばず、秋色を見るといえども更に秋心なし』という表現があります。昼の、たとえば鳥の鳴き声とかを聞いて心躍る気持ちがあっても、だからといって春の沢まで出ていってはしゃぎ回ったりはしない。秋の景色に寂しさを感じても、心の中まで寂しくなったりはしない。ある部分では感覚を研ぎ澄ませなきゃいけないけれども、ある部分では非常に気にしなくならなきゃいけないというところがあって、その辺のかねあいなのかなと思いますね」と述べています。
玄侑氏によれば、「自分」という言葉は「自然の分身」という言葉を短縮したといいます。西欧的な自己というものは完全に自然から独立しています。辰巳氏は、「環境の問題に取り組んでいるかたが、共存とか、共生とおっしゃいますが、根のところは、仏教的な自然観を持たないと、どこまで行っても小手先の共存、共生になるような気がします」と述べます。また、玄侑氏が「1970年代くらいから、男の子に『男の子らしくしなさい』ということが言えなくなったみたいです。それを言うことは差別だみたいな情けない風潮がずっと続いているわけです。でも、雄と生まれたからには、一人前の雄になる以外に大人になる方法はないわけですよ。そこをやっぱり深めないといけないと思います」と述べるのでした。
「老いを愉しむ」では、作家の五木寛之氏と対談します。
「お坊さんは長寿」では、五木氏が「お坊さんは総じて長寿でしょう。日本人の職業別平均寿命だといちばん長生きなんだ。昔、井上ひさしさんが書いていたけど、小説家より歌人のほうが、寿命が短い。歌人より俳人のほうが短い。要するに表現形式が短いほど寿命も短くなるという説。お坊さんは、大蔵経みたいな長いお経を読むから長生きするんですよ(笑)」と言えば、玄侑氏は「ものを考えることは、命の元気という面から考えれば、かなり抑圧的に働くと思うんです。考えないで覚醒しているという状態が坐禅だし、お経を唱えても同じ状態に入ることができる。長生きの秘訣と言うと変ですが、考えない時間を持つことがいいんだと思いますね」と語っています。
「『鬱』には力がある」では、東洋の豊かさは、「おもう」にいろいろな種類があることではないかと、玄侑氏が指摘します。西洋の「おもう」はthinkやconsiderという、いわば「考える」です。五木氏が「訳すと『思惟』ですよね。理性的、知性的」と言えば、玄侑氏は「はい。しかし東洋では、記憶については『憶う』、思考するには『思う』、ここまでは理性です。それから想像の『想う』は瞑想の入り口です。さらに『懐』という字の『懐う』は、全体はつかむという感じです。『懐』は『いだく』とも読みますから、完全に瞑想的な知だと思うんです。『おもう』に4種類の使い方があるのが、すごく豊かだと思うんですね」と述べます。すると、五木氏が「僕は最近、『鬱』が大事ではないかと考えているんです。鬱を薬で退治するというのは、西洋的な間違った考え方であって、鬱を抱いて生きるということを主張しています。鬱は本来、鬱蒼たる樹林とか、鬱勃たる野心とか、鬱然たる大家とか、力のある表現ですからね。病気のように言うのはおかしい」と述べるのでした。
また、五木氏は「僕は、ため息をつくことを推奨しているんです。韓国では『恨息』と書きますね。大きなため息をつくことで、人間は何ともいえない悲しみを乗り越えていく。本居宣長が『石上私淑言』で、悲しみは悲しむことで乗り越えるんだと言っています。人は生きていれば悲しいことに出会う。悲しみを内側に隠していると、生涯その悲しみと同居しなければいけない。だから、悲しいときは悲しいと呟き、人に語り、歌にもうたえ、そうすることで、悲しみを客体化して乗り越えていくことができるんだ、と。カラオケで演歌をうたっている人は、歌に託して別れや淋しさをうたっているんですよ。だから、あれはいいことなんです。演歌はなるべく、寂しい、しょぼいメロディで、切ない歌詞がいい。前向きな演歌なんて意味がない。『おれは河原の枯れすすき』なんてのがいちばんいいんですよ」とも語ります。それを聴いた玄侑氏は、「お経と同じ効果があるでしょうね。『思い』から一時解放される」と述べるのでした。
「笑いは道に近し」では、以下の会話が展開されます。
玄侑 植物でも動物でも、どこを見れば年齢がわかるというのがありますよね。木なら年輪があるし、鯉なら鱗の付け根の線の数とか。でも、花弁には年齢は刻まれないんです。それで思い出したのは、「咲く」という字は「わらう」と読みますよね。笑うと歳は関係なくなるのかな、と。
五木 なるほど、年々歳々花相似たり、というのはまさにそうなんですね。歳々年々人同じからず、と続くけど、「笑い」に年齢はない。
玄侑 老子も「笑いは道ちかし」と言っていますしね。
五木 まさにアンチエイジングそのものです。
「日本人の心の古層」では、解剖学者の養老孟司氏と対談します。
「日本人はなぜ『般若心経』が好きか?」では、養老氏が「玄侑さんは『現代語訳 般若心経』を出されていますけど『般若心経』があんなに流行るのはなぜでしょうね」と問います。すると、玄侑氏は「日蓮宗と浄土真宗以外はだいたい読みますので宗派色が強くないし、本文262文字(最後の4文字は経題)という適当な長さのお経なので、これから入るというかたは多いですね。それに『般若心経』はこう読まなきゃというのがない。意味を学ぶ人もいれば、お唱えすればいいという人もいる。原理を振りかざさず、どんなあり方も認めてしまうんですね。でも実は『般若心経』ほど内容のむずかしいお経はあまりないんですよ」と答えています。
「日本人は無宗教か」では、養老氏が「精神科では病気の原因を本人の内側に求めます。精神分析の医者は話をさせて自分のほうに向かって吐き出させる」と言えば、玄侑氏は「仏教の場合は、拝むことで、外側に憑いていればそれがなくなると思うし、内側でもお経が効いたと解釈できるんです。儀式の持っている力は説明しきれません」と言います。養老氏は、「それがどういう社会的な形を取るかは時代によっても違うけれど、精神状態というのは昔といまでかなり違っていた可能性がありますから、神の啓示をうけて天理教を開いた中山みきなどは、本当に宗教体験をしているんでしょう」と述べます。また「穢れ」について、玄侑氏は「『穢れ』は神道のものだと言いますけど、万葉仮名では「気枯れる」「気離れる」と書きました。全体とつなげていたのが『気』ですから、間に何かが詰まれば枯れてしまう。だから祓って清める、そうすると全体と通じて穢れが去ると考えたのでしょう。これは道教の影響だと思いますが、平安時代のお坊さんは、『死は穢れだ』と誰も弔いを引き受けなかった。鎌倉時代末期になって、真言律宗や禅宗のお坊さんたちが、自分たちは穢れないからやろうじゃないかということになった。そして日本の仏教はどんどん無原則化していくんです」と述べるのでした。
「日本人は一神教化しているか」では、以下の会話が展開されます。
養老 丸山眞男は『歴史意識の古層』で、『古事記』『日本書紀』で最も多く使われている語は「なる(生る)」だと言っている。「なる」というのは草木が豊かに茂る風土だからこそ生まれる日本人の根本なんですね。
玄侑 「成仏」も仏に「なる」ですからね。
養老 「なる」には「実る」という意味もありますし、日本人は「この先どうなります?」なんてすぐ訊く(笑)。「なりゆき」という言葉にも「なる」が根本にありますね。
玄侑 植物の生成力も背景にはあるんでしょうね。またいまでも日本語には言霊がある感じがしますね。擬音語や擬態語が日本語は多いでしょう。「ぴちゃぴちゃ」「しっとり」「こりごり」なんて英訳できませんよ。でも日本人同士だとその言葉だけで感覚の底まで通じますからね。「ぎゃーてい、ぎゃーてい」というマントラも、そういう力を持った音でしょう。
人は感覚から入って脳の中で概念化すると指摘する養老氏は、「たとえばリンゴとナシがあったとき、具体的にはひとつひとつ別なものです。でもそれをリンゴとかナシとかしてまとめる。その次に果物という総称を与える。さらにどんどん階層的に概念化していく。そうすると最後はひとつにならざるを得ない。宇宙全体を一個の概念で構成することが可能です。それが唯一絶対神の起源です。都市化すると一神教化するんです。モーゼがエジプトを脱出してイスラエルで興したユダヤ教も、派生したキリスト教も、イスラム教も都市の宗教ですから」と述べています。玄侑氏が「仏教では概念でまとめきれないものが儀式にありますね」と言うと、養老氏は「東大寺のお水取りは面白かったなあ。寒い中、一晩中見ていたんです。あとで、お坊さんに『なぜお水取りをするんですか』と訊いたら、『昔からやっているからで、私たちにもよくわかりません』って(笑)」と述べます。玄侑氏が「理屈をつければ、若水を汲んでくることで命が甦るということでしょうけど、概念化したものを儀式によって脱ぐという意味もあるんでしょうね」と言えば、養老氏は「儀式は根本的に感覚から抜け出せないものですから、儀式によって感覚世界を限定してしまおうというわけです。教会の中に人を集めて牧師が説教するのも、周りの状況を決めてしまえば、感覚もある程度一定になるんですね」と述べるのでした。これは非常に興味深い指摘だと思います。
「日本人独特の宗教感覚」では、以下の会話が展開されます。
養老 日本文化の歴史を語ろうとするとき、やはり宗教は外せません。歴史を見ると、仏教は文化を支えてきたと言える。でも仏教のことは歴史書に書かれていないことも多く、なかなか意識化しにくい。
玄侑 歴史を宗教抜きで書いてしまいたいという欲求がどこかにあったのでしょうね。また、お坊さんが語られずにきたということもありますね。
養老 宗教を入れると客観的でなくなるということでしょうけど、客観的な歴史なんてありませんからね。江戸時代、三代将軍の家光が沢庵和尚に帰依して、沢庵が政事に関する相談役を務めていたことも、歴史の表舞台にはあまり書かれていません。
玄侑 家康時代の天海僧正や儒学者の林羅山も幕府のブレーンとして活躍していましたね。歴史的な文書もお坊さんが書いていることが多いんですよ。最近では「教育勅語」も原文は臨済宗の老師が書いたと言われています。
「お守りやお札は道教」では、玄侑氏は「お守りやお礼はもともと道教のものですし、我々がやっている三拝を三回繰り返す『三拝九拝』も道教の作法です。また『三種の神器』の『神器』という言葉もそうです。道教では鏡と剣の『二種の神器』だったんですが、神道は勾玉を加えて三種にした。日本の神道が三種になったのは仏教の三宝の影響だと考えられています。まったく混沌としていますね」と語っています。一方の養老氏は、「旧制高校の教育は、社会的判断は『儒教』。個人の判断は『道教』、哲学的抽象的思考は『仏教』となっていました」と述べます。また、七福神の神様もいろいろ混じっていると指摘し、玄侑氏は「七福神は16世紀から17世紀はじめに臨済宗の僧によってつくられたと言われています。弁財天、大黒天、毘沙門天はインドから、寿老人、福禄寿は中国の道教、恵比寿は日本、布袋は中国の実在した臨済宗の僧です。道教から二人も入っているんですよ」と述べるのでした。
「祈りによって得られるもの」では、養老氏が「僕がときどき思うのは、近代人がいちばん忘れがちなのは祈りじゃないかと。お祈り抜きの宗教はないでしょう。イスラム教などはしょっちゅうお祈りしている」と言います。それに対して、玄侑氏は「あれだけ祈りが身体化していると何も考えない状態になれますね。目を閉じただけでは頭の中が空っぽにならないので、動作を加えたほうが祈りになりやすいんでしょう。先日うちのお寺でやった『大般若経』の転読も、経本を翻転するとき気をゆるめると崩れてしまいますから、目も手も、そして耳もフル回転しないとできません。だから余計なことを考える余地がない。あれがおそらく『空』だと思います。『空』になった状態の身体から自然に発するのが、もしかすると祈りかもしれません」と述べます。
面白いことに、数学上のゼロは、西洋で長い間タブーだったことが指摘されます。理論的にものを考えようとすると、ゼロがあると矛盾が起こってくるからだとして、養老氏は「インド数学がアラビアに入ってアラビア数字になりますが、古代ギリシアのピタゴラス学派はゼロをタブー視しています。はじめて無限の概念を、ゼロを含めて考え始めたのは、ルネッサンス以降でした。ゼロというのは、『数はないが、数字のひとつ』です。仏教の『無』は、ゼロの『数はない』というほうの意味です。『空』は幾何学的な位置はあるけど中身がない。でも代数でいうとゼロ。ないほうから言うと『無』ですから、ゼロのところで『無』と『空』が背中合わせになっていて、相互補完しているわけです」と述べるのでした。
「個性病を超えて」では、精神科医の片田珠美氏と対談します。
「人間はもともと超多重人格的存在」では、解離性同一障害について言及されます。解離性同一障害をテーマにした『阿修羅』という小説を書いた玄侑氏は、「解離は、たとえば戦争が始まるとなくなると言われます。挙国一致で皆が一丸とならなければいけない時代には、本人も解離している場合じゃないというわけでしょう。時代性という意味で、いま何が解離を起こさせているかとか考えると、私は根本的には個性教育だと思うんです。いまの人たちは『私ってこういう人です』という言い方を幼い頃からしますね。そうした早い時期からの自己規定を学校の先生も求めている。確固としたアイデンティティを人間関係に未熟な幼時から求めるのは、あまり適切とは言えないし、そもそも本来の日本人的なあり方ではないと思うんです。解離性同一性障害が出てきた背景には、パーソナリティーを個性として捉えるという考え方が付け焼き刃で押し付けられていることが、非常に大きいのではないでしょうか」と述べています。
それに対して、精神科医である片田氏は「解離性同一性障害はアメリカで1980年代から爆発的に増えましたが、90年代後半になると徐々に減っていきます。カナダの哲学者イアン・ハッキングは『束の間の心の病』と呼んでおり、極めて特殊な歴史的・地理的条件の下で生まれ、発展し、やがて消えていく精神疾患の典型だと言っています。アメリカにも、この『疾患単位』の信憑性自体に疑問を投げかける精神科医たちがいます。治療者があまり意識せずに行なった暗示――誘導尋問とまでは言えませんが――の効果と、患者の側の信じやすい性格、あるいは真似をする傾向の混ざり合った『想像の産物』ではないのかと。私もどちらかというと、その意見に近いです」と述べます。また、アメリカの精神科医ハリー・スタック・サリヴァンは「状況の数だけ自己がある」と言っていますが、人間というのは、いろいろな人に対してさまざまな人格を見せながら、その場その場で身過ぎ世過ぎをしている、「超多重人格」とも言えると指摘しています。
「自己増殖する神、変幻自在な人間」では、「超多重人格」といえば、まさに日本の神々がそうだと指摘されます。八百万の神々の大本にいる神産巣日神は、いくらでも自己増殖します。玄侑氏は、「それと同じ発想が仏教にもあって、観音さまは33に変化し、それを仏教では優れた能力と捉えるのですが、その典型とも言える千手観音を西洋に持っていけば、たぶん化け物のように受け止められるに違いないと思うんです」と述べます。それに対して、片田氏は「ヨーロッパでは『悪魔憑き』、わが国でも『狐憑き』と呼ばれる、一種のトランス状態は昔から観察され、記述されてきました。また、祭りとか宴、あるいは宗教儀式などの際に、場合によってはアルコールや薬物を用いて、人工的にトランス状態をつくり出し、人格の抑圧された部分を解放するようなことも行なわれていました。こういうのが、ガス抜きになっていたわけですね」と述べています。
西洋の伝統的な考え方には、まとまりを持った良い人格というものが想定されているといいます。それが乱れてしまうのは外側から何かが憑いたと捉える場合が多かったようだとして、玄侑氏は「イギリスの心霊学が発達した背景にも、それがあると思われますが、背後霊とか地縛霊とか因縁霊といった霊を外からくっつけることで現状の不思議さを説明しようとする。しかし東洋では、仏教でも六道の変化と言って、地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天という人間性の変化を想定していて、さらに、その上に、声聞・縁覚・菩薩・仏がくるのですが、合わせて十界の変化を前提にしているわけです。このように、変化を前提にしていれば、大概の出来事は受容できてしまう。しかし、基にソリッド(堅固)なものを想定していると、外づけで語るといった工夫がいる。それがうまくいかないときに、統合できなくなったり、解離が起こってしまうのかなという気がするんですけれども」と述べています。
片田氏は、「いまの教育が個性を重視していることも一因ですが、怪我をさせないようにしていることも問題だと思います。その辺に石ころがあったら、親があらかじめ取り除いてやって、子どもが躓かないようにする。いまは、挫折や失敗といった『対象喪失』にできるだけ直面させない、怪我をさせないように極力配慮しますから、子どもの側も、失敗をしたり、ヘタを打ったりすることを怖がるわけです」と語ります。玄侑氏が「フロンティアスピリットがなさすぎじゃないですか」と言えば、片田氏は「ないですね。我々の若いときは、外国に行きたがったものですが、いまどきの若者は外国に行くことにもあまり積極的ではないようです。見たこともない所に行って危ない目に遭うのも嫌、恥をかくのも嫌、そんなお金があったら将来に備えて貯金したいという子が多いみたいですよ」と答えます。すると、玄侑氏は「極端なのは、子どもを産んだ後のことを考えると大変だから産まないでおこうという選択。産んでもいつかその子が自殺するかもしれないと思えば、最大の安全策は産まないことでしょう、そこまで行ってますよね」と述べるのでした。
「死と向き合う、生と向き合う」では、死後の世界の問題が取り上げられます。玄侑氏が「死後の世界はどうなっているかと訊かれても、われわれ禅宗では『わからん』と答えるんです。それじゃああんまりだというので極楽浄土を提案した人々もいるわけですが、これは未来がわからなくて不安な人々を、こうすれば必ず極楽浄土に往生できますよという言い方で救済しようとする考え方です。でも本来はわからんでしょう」と言えば、片田氏は「そこをうかがいたかったのですが、本来の仏教は、死後の世界はわからないという立場を取られますか?」と質問します。玄侑氏は、「そうです。『死んだらどうなるんですか』とお釈迦さまが訊かれて、『無記』と誌されています。答えないんです。『十難無記』というのは、お釈迦さまが答えなかった10の質問ですが、その中のひとつです。死後の世界についてお釈迦さまは、『なんだおまえ、結局わからないんじゃないか』と馬鹿にされても、けっして答えなかったと言われています」と答えています。
片田氏は、「私は自らの臨床経験から、死というのは、心臓が停止する瞬間に訪れる物理的なものだと思っています。でもそれを受け入れられない人のために極楽浄土という概念をつくりだした人たちが、仏教者の中にいたわけですよね」と言います。それを受けて、玄侑氏は「そういうことですね。ただ光に包まれるというイメージは、単なる概念というより、かなり体験に由来するものだとは思います」と語ります。それに対して、玄侑氏は「キリスト教も、最初は裁きの宗教であったものが、後に救済の宗教と言われるようになります。パウロの出現で、『愛』が強調されることで変わるんですが、『死』は宗教の大いなる契機ではあると思います。でもそれがメインと言いきれない宗教もありますね。仏教のメインテーマは、苦からの脱却です。その苦のひとつとして死があるわけです」と述べています。
「人格は多くの他者によってつくられる」では、片田氏が「敵か味方に二分してしか世界を捉えられない思考形態を『パラノイア的思考形態』と言いますが、パラノイア思考の人はとにかく世界を敵と味方に分けて、敵が自分に害を加えてくるという被害妄想を抱きやすいため、敵と思われる他者に対して非常に攻撃的になります。いまのいじめとかモンスターペアレントとかクレーマーとかは、非常に他責的です。とにかく他の人のせいにして責める。そういうふうな人が増えている気がします」と述べています。また、「自ら罰を受けようとする無意識の衝動では、対象喪失が解離を引き起こす重要な要因のひとつになりうることが指摘されます。片田氏は、「アメリカで多重人格障害の患者が増え始めたのは1970年代初めですけど、そのきっかけになったのが1973年に出版された『失われた私』という伝記の出版です。『16の別の人格に取り憑かれたある女性の驚くべき真実の伝記』として宣伝されたのですが、この伝記が出てから多重人格障害が爆発的に増えていったんです」と述べます。
「精神医学だけで心を掴めるのか」では、玄侑氏が「精神医学の歴史はまだ浅いですよね。今後まだまだ変わるだろうという気はします。第一、病名が次々に変わっていますから」と述べます。片田氏が「解離性同一性障害も、かつては多重人格障害と呼ばれていました」と言うと、玄侑氏が「躁うつ病ともいまは言わなくて、双極性障害ですよね。病名がどんどん変わるということは、まだ解釈が変化する可能性はありますよね。心は本当に掴みきれない……」と述べます。すると、片田氏は「心を精神医学だけで掴めるのかという問題もあります。だから精神科医はしばしば文学とか哲学、仏教などに興味を示します」と述べます。
続いて、霊能者が話題になります。
玄侑志賀「我々から見ると、精神科医のかたと、江原啓之さんのような霊能者は対極にいると思います。精神科医が、こうした問題をすべてその人の内部の問題として見ているのに対して、霊能者は、ほとんど外部から何かが憑いていると見る。我々はその中間にいて、どっちもあるんじゃないのって思っているんです(笑)」と言えば、片田氏も「霊能者は、悪いものを外部に追いやっている、いわば外在化しているわけですね。しかし、悪いものはすべて外にあるから、それを消滅すればいいという考え方は危険だと思うんです。精神科医は、脳や心、体も含めて、患者さんの内部の問題として理解しようとしている、つまり『内なる悪』を捉えようとしているので、たしかに対極にいますね」と述べています。
「赤面恐怖と『にらめっこ』」では、人格障害について言及されます。玄侑氏は、「人格障害は英語でパーソナリティー・ディスオーダーと言いますが、何だかおかしな英語です。これは何かあらかじめオーダー(秩序)があると考えているわけですから、そう考えると、これはやっぱり人間にスタンダード(標準とか基準)があると想定している国の病だなって思うんです」と述べています。片田氏は、「アメリカでのスタンダードを想定しているんですよ。いま話題になっている社会不安障害は、アメリカでとても多くて、だいたい10人に1人が罹っていると言われているんです。かつては『内気』とか『赤面恐怖』とか言われた人たちのことですが、日本にもいっぱいいましたよね。だけどアメリカは、キャリアアップしていくために、常に自己をアピールし、高く売り込まなければならない国です。そういう社会では社会不安障害と診断されるような人がどうしても増えるわけですが、この人たちにもSSRIという新しいタイプの抗うつ薬を投与して、バリバリやりなさいとハッパをかけるわけです」と述べます。
それを聴いた玄侑氏は、「だいたい日本人はそれこそ内気にかけては世界一みたいなもんで、民俗学者の柳田國男が書いているんですが、日本人が内気を解消するために、全国的に展開した方法がある、と。それは『にらめっこ』だと言うんです。『ダルマさん、ダルマさん、にらめっこしましょ……』のあの遊びです。彼らは、にらめっこは子どもの頃からやることで、人間関係をスムーズにつくれるようになるという隠れた目的をしっかり含ませた遊びなんだというわけですよ」と述べます。片田氏が「それは素晴らしい」と感銘を受けると、玄侑氏は「にらめっこって結局は、笑いに解消するでしょう。非常に面白い人間関係の技術を無意識に学べる遊びだったんじゃないですかね。だから、もっとにらめっこすればいいんですよ」と述べます。それを聴いた片田氏は、「笑いに解消できるって、とても大事なことで、先ほどの生老病死ではないですが、やはり人生は辛いこと、切ないことのほうが多いですからね。でも面白がるというか、笑い飛ばすことって、大事ですね。関西にはその伝統があるから、『おもろい』ことが何よりも大事なわけです」と述べるのでした。
「底の浅い父性を振りかざす母親たち」では、昔は母子密着から引き離すような村の掟があったことが指摘されます。ある年齢になったら半強制的に一定期間皆で集団生活を送らせるようなしきたりがありました。玄侑氏が「宗教の世界でも荒行をするとか。この行をやったら一人前と認めるとかね」と言えば、片田氏は「いまはそうした大人になるための通過儀礼がなくなっていますから、いつまでも母の欲望を引きずっている。引きこもりの男の子たちを見ていると、『お母さんから離れていくような不実なことを僕はしないよ』というメッセージを送り続けているような、あくまでも母の欲望に忠実、みたいなところがありますね」と述べています。
仏教において母親は慈悲の象徴です。慈悲というのは異物を取り込むものだとして、玄侑氏は「母親は胎盤があるために、血液型の違う異物を育てることができる。敵に餌をやっているようなもので、こんなすごいことはないでしょう。最初の慈悲のモデルは明らかに母親だったと思うんですよ。そういう異物を取り込めるというモデルを、人格形成の中で考えていかなければいけないという気がします」と述べます。仏教では、不幸の根源は「私」というものだと認識しています。「私の都合に合わない」という感覚が「苦」となる。だから、「私」の輪郭を弱めたり、「私」の都合を解く訓練こそ必要なのです。ところが、いまの教育は、「私」をどんどん強固にして、戦って勝てる「私」にしようとすると指摘し、玄侑氏は「ヨーロッパは歴史的にその方向だったと思いますけど、日本は違うんじゃないかという気がするんです。どうやらいまの日本人は、外来の個性病に罹っているように思えてならないんです」と述べるのでした。
「心の復興」では、シナリオライターの山田太一氏と対談します。玄侑氏は、「日本人の幸せっていうのは、限定されたことにどう『仕合わせ』ていくか。あるいは、もう与えられていることをどう寿ぐかというところにあるんじゃないでしょうか。さらに言うなら、西洋的な自己が持ち込まれたことが、自殺を増やすきっかけにもなったような気がするんです。『自己実現しなさい』と言われても、その自己が見えないと、ものすごい苦しみが生れますから」と語っています。山田氏は、「だからこそ僕は、人間の限界、哀しみを知ることが大事だと思います」と述べます。昔は「苦労自慢」というのがありました。「私のほうが苦労した」という人が出てきて、苦労した人ほど偉い、みんなで敬意を表するという感覚があった。山田氏は、「あれはとても質のいい価値観だったと思うんです」と述べます。
玄侑氏も、「被災者のかたももっと苦労自慢をしていいんでしょうね。ただ、まだあんまりみなさん口には出しません。もう少し時間が経たないとむずかしい気がします」と述べています。そんな中で、「とにかく笑顔で頑張れ」みたいなことを言われると、泣けないまま負のエネルギーがこもっていく可能性がある。それを芸術などに転化する人もいるでしょうが、大部分の人にとってはやっぱり毒物として作用するとして、玄侑氏は「だからもうちょっと外に出せる環境も必要ですね」と述べます。また、山田氏は「『メメント・モリ』とよく言いますけれど、確かに死を思うことは大切です。根本的な体験を突きつけられると、いままでのくだらない悩みが無化されて、いちばん大事なものが見えてくる。でも、それだけでずっと生きたら、人間は非常につまらない存在になります。ですから、悲劇や苦労の中で啓示された真理だけで生きていくのもまずいんじゃないかと、僕は思うんです」と述べるのでした。
「どこまで曖昧さに耐えていけるか」では、「全能感」の話題が出た後に、玄侑氏が「仏教っていろんな仏像をつくりましたよね。もともとはお釈迦様が持っていた能力を、薬師如来や文殊菩薩や弥勒菩薩などに分担させていった。その背景には、全能感を否定したいっていうのがあると思うんですよね。一方で、比叡山から各宗派が下りていって、鎌倉新仏教ができていきますけれども、あれも同じ流れだと思うんですよ。あまりにも総合的な天台仏教に対して、『南無阿弥陀仏だけでいい』『南無妙法蓮華経だけでいい』、あるいは『坐禅だけでいい』とか、限定していきました。八百万の神という基本ソフトがあって、仏教もそのソフトの上で稼働したということかもしれませんが、そういった価値の並列化がきわめて日本的な気がします」と述べるのでした。
「無常からの再出発」では、思想家・人類学者の中沢新一氏と対談します。
「無常との共生」では、玄侑氏が子どもの頃、テレビがうちに初めてきたときに、最初に映ったのが「ブーフーウー」だったことが明かされます。『三匹の子ぶた』ですね。ブーは木の家をつくった。フーはわらの家だった。ウーがレンガの家をつくって、ウーが一番賢いねという話でした。玄侑氏は「でも、ウーのレンガの家は日本じゃ賢くないだろうと思うんですよ」と言います。中沢氏が「蒸し暑いしね」と言うと、玄侑氏は「そうそう。日本なら木の家のブーが賢い。それなのに、あんな話を無批判に流していたのは、その後の原発関係のアニメ、『鉄腕アトム』とか『サイボーグ009』とか、『8マン』に通じる流れだったと思うんです。この主人公たちのエネルギーはすべて原子力ですからね。やっぱり逆らえない流れというか、日本はみんなの気持ちを無意識にそっちのほうに持っていっていたところがあります」と述べます。すると、中沢氏は「僕らはまさにその世代ですものね。子どものときからの刷り込みは『鉄腕アトム』から始まって、原子力の平和利用という言葉をすんなり受け入れた科学少年でした」と述べるのでした。
中国の諸子百家の中では、国を認めないと言ったのは老子だけだという玄侑氏は、「一番小さい単位として邑があり、それがいくつか合わさって、県になったり郡になったりしますが、春秋戦国時代になると、その上に国が発生します。その国を、老子は認めなかった。荘子もそれに近いんですが、積極的には反対を示さなかった。おそらくかかわりたくもなかったのでしょう。しかしそれ以外の諸子百家は、国は基本的に肯定したうえで、仕官しようとしているわけなんですね」と述べています。「相互扶助のある社会へ」では、老子や先住民の考え方を近代化すると、アナーキズムの考え方になってくることが指摘されます。とくにクロポトキンの発想に近くなります。クロポトキンは地理学者で、シベリアの先住民の社会のつくり方を研究して、相互扶助という人間関係がいちばん重要だと考えました。クロポトキンについて、中沢氏は「国家ができると、この相互扶助を破壊してしまう。この破壊を彼は大変憎んで、アナーキズム思想に発展させていくのです」と述べています。
また、中沢氏は「クロポトキンの書いたものを読んでみると、老子やブッダや先住民が考えていたことと同じことを、近代的に言い換えているのがわかります。国家を相対化しながら、地域で相互扶助が及ぶ程度の範囲の人間共同体をつくっていくという考え方です。今回の大震災で、日本人ははじめて自分たちの未来をどうしたらいいかと真剣に考えるようになりましたが、地域の生き方について、そういう考え方も参考になるかと思います」とも述べています。それを聴いた玄侑氏は「相互扶助というと抽象的な感じがするんですが、要は顔が見えるということですよね」と述べます。ちなみに、「相互扶助」という抽象を具象化したものが「互助会」です。ブログ『相互扶助論』で紹介したクロポトキンの著書の名がありました。互助会のコンセプトである「相互扶助」について書かれた古典的名著で、拙著『ハートフル・ソサエティ』『隣人の時代』『心ゆたかな社会』でも同書を紹介・引用しています。
「二宮尊徳と宮沢賢治」では、中沢氏は「今回、福島のことをいろいろ勉強し始めて、ことに相馬とか双葉町のあたりが気になったのですが、あのあたりは江戸時代の末期に二宮尊徳が仕法と呼ばれている農業改革をやったところなのですね。共同体のつくり方、農業技術の改良やイノベーション、そうした面で先進的な地帯でした」と述べています。玄侑氏が「そうです。いわゆる農村復興策としての『報徳仕法』ですね。『一圓融合』の思想なども仏教の縁起の考え方を背景にして、素晴らしいです」と言うと、中沢氏は「二宮尊徳のお弟子が相馬藩の武士で、非常に頑張った。ある意味で、相馬は日本農業のトップランナーだったところですね」と述べます。すると、玄侑氏は「ええ。尊徳翁の娘婿が富田高慶で、相馬の仕法を支えます」と述べるのでした。
「一から出直す、生まれ直す」では、以下の会話が展開されます。
中沢 東北のほうはよく、羽山というところで生まれ変わりの儀式をやりますね。
玄侑 この世とあの世の「はざかい」だから「はやま」。字は「端山」とか「麓山」とか、いろいろですけどね。
中沢 それが大変おもしろい儀式で、小屋の中にこもって水垢離をとってみたり、いろんな豊作の儀式を続ける。最終日の真夜中から朝にかけて、奥の院の神様のところへ入っていくんです。そのときは、全員がわらじに履き替えて、雪の中を行く。
玄侑 白装束でしょう。
中沢 ええ、白装束です。脇に大きな国道が通っていて、シャーッ、シャーッと、車が走っていく、その下を白装束でわらじ履いて、変な一団がものも言わずに歩いていく。ものすごくシュールな光景でした(笑)。奥の院へ行くと、神がかりをする人がいて、来年はどういう作物、作付けがあるかを占う。ビューッと車が走っている脇で、何千年も前からの山の神のお祭りが進行している。
中沢氏は、「東北の文化そのものが、死や再生のことをとても大切にしている。それに夏には死霊が戻ってくる。死者と生きている人間が一緒になるという、このふたつが東北の文化の重要なところでしょうね」と述べています。また、「仙台の七夕祭りは、死者の霊を呼ぶためのものだ」と、玄侑氏がTV番組の中で発言していたことに触れると、玄侑氏は「旧暦では7月15日がお盆だったわけですね。江戸時代になって、それが13、14、15の3日間に拡張されますが、7月7日が七夕で、ちょうどお盆の1週間前なんですよ。たまたま中国から星まつりが輸入されて、これが日本ではお盆のプレ行事になった。お盆に帰ってくる先祖を迎えるための目印に、七夕には竹を立てる習慣になっていくんです。星への願いごとを短冊に書きますけど、あれは星じゃなくて、先祖の神々なんです。日本では亡くなった人はまず先祖と呼ばれますね。しかし50年もたつとそれが祖霊神になり、そこから役割に応じていろんな神の名前で降りてくる。だから、先祖と神とがひとつながりなんですね。陸前高田に動く七夕という行事がありますが、あれはまさに死者を迎えるためのものですよね」と述べています。拙著『リメンバー・フェス』(オリーブの木)で、わたしは死者を迎える祭りのことを「リメンバー・フェス」と名付けましたが、七夕も リメンバー・フェスだったのです!
東北には環状列石があります。環状列石はお墓ですから、あそこに死者を共同で祀っています。遠くのいろんな村から人が集まってきて、数日間にわたってあそこでお祭りをやりました。中沢氏は、「死者を呼び戻して、死者と一緒になって生きている人間がお祭りをすることを、あの環状列石でやった。東北では縄文時代からある風習で、夏のお祭りの伝統はそこから始まっているようでしょう」と述べています。玄侑氏は、「環状列石があるところと集落のあいだにはたいてい川があったりしますね。中国から『三途の川』が伝えられる以前から、日本でも川が『こちら』と『あちら』を隔てていた」と述べます。中沢氏が「西馬音内とかの盆踊りなどでは、踊る人が顔を隠して、覆面して踊っているでしょう。踊っている人が死者だということなのでしょうね」と言うと、玄侑氏は「ええ、そうだと思います。そんなふうに生まれ直しの文化も色濃く残っていますし、世間では取り返しがつかないと言いますが、東北では取り返しがつくんです」と述べるのでした。
「福島と沖縄」では、元外務省情報分析官で作家の佐藤優氏と対談しています。「ふたりは親戚!?」では、冒頭から、佐藤氏のひいおばあさんが三春にある臨済宗妙心寺派のお寺の娘であったことが明かされ、なんと玄侑氏と佐藤氏が親戚であったことが判明します。この世は有縁社会であることを再確認するような出来事でした。「自衛隊の新しい意味」では、東日本大震災後の被災地で必死の救助活動を行った自衛隊が新しい意味を持ったということが話題になります。岩波書店の『世界』の編集長も同意見であると紹介した佐藤氏は、「『世界』は反戦平和、9条断固擁護という編集方針を取っていますが、被災地を回っていて、自衛隊に関する印象が完全に変わったと言うのです。道ひとつ聞いても丁寧だし、遺体の処理をきちんとやってくれる、と」と述べています。
佐藤氏の発言を聴いた玄侑氏は、「本当です。埋葬作業もできず、供養もグリーフケアもできない被災地の環境で、自衛隊の人たちがずらりと並んで一糸乱れず敬礼するというのが、ひとつの葬送儀礼になりました。それを見て、みんな合掌して涙を流したんですね」と述べます。佐藤氏は「おそらく、警察予備隊ができるときの発想だった郷土防衛隊みたいな要素ですね。ある意味では自衛隊には、下から出てくる要素と、上から出てくる要素と両方あります。この下からの要素が、今回非常に可視化されたのではないでしょうか」と言うのですが、玄侑氏が「結局、日本の自衛隊にとってメインの仕事は災害復旧でしょう。これまでひとりも殺していないし、人を生かす、救うことにずっと徹してきたのが、ここにきて『私たちの自衛隊』になったように感じます」と述べるのでした。
「足るを知る」では、聖路加国際病院の理事長を務めた故日野原重明氏と対談しています。「『方丈記』を読み返す」では、日野原氏が「以前、玄侑さんの『復興の知恵と力は寺や神社に宿る』という記事を読んだら、お祭りの存在が非常に大きな意味を持っていると書かれてありました。お寺や神社にはお祭りが溶け込んでいて、大きな心の癒しがあるんじゃないかという感じを私も持っています」と述べます。すると、玄侑氏は「日本人は身分や地位などに関係なく、同じお祭りに皆が参加します。こういう民族はほかにないと思いますね」と述べます。また、玄侑氏は「私は日本人ほど自然災害に遭い続けてきた民族も少ないと思うのですが、そのひとつの文化的な成果といえるのが『懐かしむ』だと思っています」と述べています。「懐かし」という言葉は、万葉集では「夏樫」と書いてあります。つまり中国の漢字には「懐かしい」という意味の字がないのです。いまの「りっしんべん」の「懐」という字には、もともとそういう意味はありません。
さらに、「懐かしむ」のが日本人の特性だったという玄侑氏は、「『面影』を懐かしむわけですよね。中国などの場合は王朝が変わると、以前の王朝の物すべて壊したり焼いたりしますから、懐かしまない人々のように思えます。だから文字もなかったんでしょうね。もともと『水に流す』など、忘れようとする習性が日本人にはあると思いますが、それでも忘れられないから『もののあわれ』という美学が結晶したのではないでしょうか。『もののあわれ』の『もの』は、あらゆるいのちのことです。鳥獣虫魚、植物、あらゆるいのちはぜんぶつながっている。そのつながりのことを『もの』と言ってるように思います」と述べるのでした。
「原発作業員に祈りを」では、宗教学者の山折哲雄氏と対談しています。「『無常』という行動規範」では、「無常」というのは日本人の場合は行動の規範にまでなったのだと指摘し、玄侑氏は「上田閑照先生は『日本人がおじぎをするのは寂滅現前である。それまでの過去をそこでいったん死滅させ、新たな自己を立ち上げる、敷居の前でそれまでの自分をいったん殺すのだ』とおっしゃっていますが、無常な事柄あまりにも多かったために、日本人はそういう挨拶を身につけたのではないか。つまり、『無常』を行動化して過去を引きずらない方向を選び取ってきたわけですが、それは、禅の目指す方向なんです」と述べています。
それに対して、本居宣長が「もののあはれ」ということを言いました。「世の中のこと、あるいは人の情けというのがわからないと、『もののあはれ』はわからない」という言い方からしても、忘れようと思っても忘れられないことが背景にあるのだとして、玄侑氏は「一に返ろう、一から出直そう、という文化を日本人は持っていると思いますが、そうは言っても忘れられないこともある。それがひとつの美学、『もののあはれ』として結晶されたのかな、などと思ったりしていました」と述べています。それに対して、山折氏は「『無常』というと、仏教であったり、禅であったり、そういう連想が働きます。そのとおりだと思いますが、最近、私は『無常』は仏教以前、もしかすると宗教以前、つまり、宇宙の摂理、自然の本質的なあり方そのもののことを言うのではないのかな、というように思ってきました」と述べるのでした。本書『中途半端もありがたい』は今から12年も前に刊行された本ではありますが、その内容はまったく古くなっていませんでした。人間にとって普遍性のあるテーマを語り合っているからこそ、長く読み継がれる対談本となった気がします。