- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.0291 文芸研究 『もういちど村上春樹にご用心』 内田樹著(ARTES)
2011.03.11
『もういちど村上春樹にご用心』内田樹著(ARTES)を読みました。
2007年に刊行された『村上春樹にご用心』の続編かと思ったら、そうではなく「改訂新版」でした。わたしは『村上春樹にご用心』を読んでいましたので、すでに読んだ文章がほとんどでしたが、初出のものを含めて、あらためて面白く読めました。
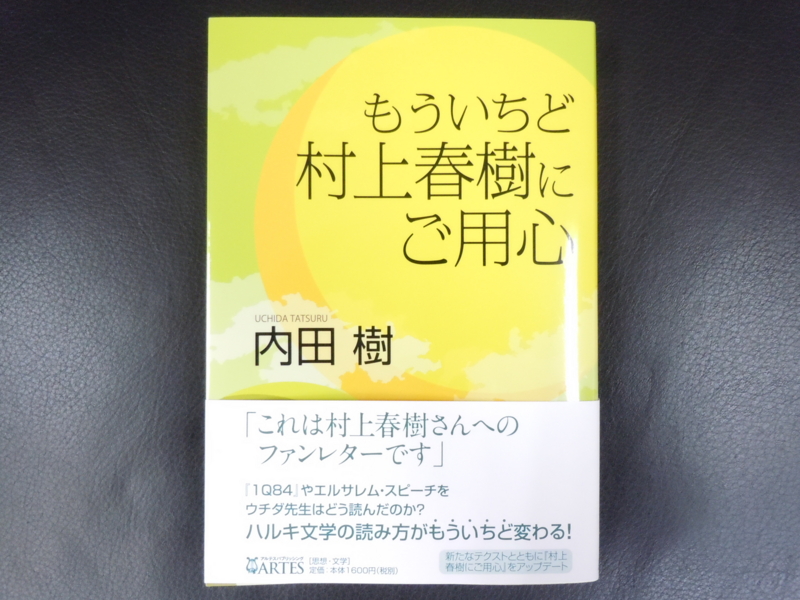
ハルキ文学の読み方がもういちど変わる!
本書の構成は以下のようになっています。
「新版の読者のみなさんへ」
「はじめに―村上春樹の太古的な物語性について」
①初心者のための 村上春樹の「ここが読みどころ」
②『1Q84』とエルサレム・スピーチを読む
③村上春樹の世界性
【特別対談】柴田元幸×内田樹「村上春樹はからだで読む」
④翻訳家・村上春樹
⑤うなぎと倍音
⑥雪かきくん、世界を救う
「旧版のあとがき」
「新版のあとがき」
著者が当代一の「村上春樹読み」であることは衆目の一致するところだと思います。
その凄みは、最初の「はじめに―村上春樹の太古的な物語性について」で、いきなり開示されます。
著者は、最新刊『1Q84』をはじめとした村上作品が世界中の読者に読まれていることについて、村上作品が決して「前衛的」でも「反文学」でもなく、ほとんど古典的な「世界文学」の系統に位置づけられると指摘したうえで、次のように述べます。
「村上作品は、あらゆる文化圏の人々の琴線に触れる『原型的な物語』を語っています。初期の『羊をめぐる冒険』から『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』、『アフターダーク』、『ねじまき鳥クロニクル』、『海辺のカフカ』を経て『1Q84』まで、変わることなく、ひとつのプリミティヴな物語の構造が反復されていると僕は思っています」
その「プリミティヴな物語」とは、どういう物語なのでしょうか。著者は続けます。
「それは、ごく平凡な主人公の日常に不意に『邪悪なもの』が闖入してきて、愛するものを損なうが、非力で卑小な存在である主人公が全力を尽くして、その侵入を食い止め、『邪悪なもの』を押し戻し、世界に一時的な均衡を回復するという物語です」
それは、ほとんど古典的な「ビルドゥングスロマン」と同じなのです。
わたしは、芋づる式読書としての「DNAリーディング」というものを提唱していますが、村上作品には過去のさまざまな名作のDNAが流れていることを感じます。
村上春樹は、もちろん、すぐれた物語の製造者です。しかし、その物語は独創的というよりも先達たちの強い影響のもとに書かれているのです。
当然ながら著者もそのことに気づいており、次のように述べています。
「『羊をめぐる冒険』で村上春樹は世界文学の正系のポジションを発見しました。物語的鉱脈と言ってもいい。『羊』は直接的にはレイモンド・チャンドラーの『ロング・グッドバイ』の村上春樹的リメイクです。そしてその『ロング・グッドバイ』はスコット・フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』をリメイクしている。これは村上春樹自身が『ロング・グッドバイ』の訳者解説で詳細に種明かしをしています」
しかし、それだけではありません。村上作品のDNAのルーツは、さらに遡ることができるのです。さらに著者は述べます。
「実は『ギャツビー』にも先行作品があります。アラン・フルニエの『ル・グラン・モール』です。これは近代のアメリカ文学とフランス文学の両方をそこそこ読んでいる読者であれば、タイトルを見ただけで想像がつくことです。
フィッツジェラルドがパリに滞在しているときに、フルニエのこの小説がちょうどベストセラーになっていました。フィッツジェラルドは少なくともそのタイトルとプロットの大筋については知っていたはずです。そして、もちろん、『ル・グラン・モール』にも、それが下敷きにした先行作品がある(はずです。フルニエの専門家がいたらお訊きしたいところです)。どれも、ある種の『弱さ』ゆえに、坂を転げ落ちるように破壊する非現実的に魅力的な青年の相貌を、傍観者である語り手が物語るという構造になっています」
「日の下に新しきものなし」という言葉がありますが、すべての文学作品には先行する作品があり、究極的には「原型的な物語」に行き着くのでしょう。
村上春樹がそれを自覚的に書いたと思われる最初の作品が『羊をめぐる冒険』です。著書は、次のように述べています。
「『羊』において村上春樹はそのような根源的な志向を刻み込まれた青春小説の正系の水脈にしっかりと杭を打ち込みました。それからは、その水脈から滔々と言葉が湧き出てきた。そういうことだと思います。ですから、村上春樹が後にチャンドラーとフィッツジェラルドを自ら訳したのは、『羊』の先行作品に対する敬意の表明であると同時に、自作がその系譜を継ぐ作品であるということの堂々たる宣言だったと思います」
まったくその通りだろうと、わたしも思います。
村上春樹は自身のDNA、すなわちタテ糸というものを大切にする作家なのです。
そして、それを発見し、自覚することによって、言葉というものは豊かに湧いてくるものなのかもしれません。エルサレム賞のスピーチでは仏壇に祈りを捧げる父親のエピソードが出てきましたが、自身の先祖に対して限りない敬意を払うという姿勢は村上春樹の小説にも共通しているのですね。
著者は、「はじめに」の終わりを次のようにまとめています。
「村上文学は『邪悪なものをめぐる神話』であり、『青年の生長譚』であり、かつ『血族と因果の物語』でもある。このあまりに古典的な、ほとんど太古的な『物語』特性ゆえに、村上文学は世界文学としての要件を満たすことになった、というのが僕の仮説です」
「ノーベル文学賞に最も近い作家」とされている村上春樹は、日本人にも一番愛されている作家です。つまり「国民作家」です。
これまで「国民作家」といえば、古くは夏目漱石にはじまり、昭和になってからは三島由紀夫や司馬遼太郎などの名前が浮かびます。
三島と司馬といえば、昭和を代表する日本文学の巨人ですが、二人の仲は良好なものではありませんでした。
昭和46年11月26日に三島が割腹自決した翌日、司馬は「毎日新聞」の「異常な三島事件に接して」という記事で次のように述べています。
「新聞に報ぜられるところでは、われわれ大衆は自衛隊員をふくめて、きわめて健康であることに、われわれみずからに感謝したい。三島氏の演説をきいていた現場自衛隊員は、三島氏に憤慨してヤジをとばし、楯の会の人をこづきまわそうとしたといったように、この密室の政治論は大衆の政治感覚の前にはみごとに無力であった。このことはさまざまの不満がわれわれにあるとはいえ、日本社会の健康さと堅牢さをみごとにあらわすものであろう」
これは、あまりにも辛らつな言葉です。
生前の三島由紀夫は司馬遼太郎の文学をまったく認めていませんでした。単なる大衆文学の人気作家ぐらいにしか思っていなかったようです。
もしかすると、事件後に辛らつなコメントを発した司馬遼太郎の心の中には純文学のスーパースターであった三島由紀夫への暗い想念があったのかもしれません。
このように水と油のような関係であった三島と司馬ですが、面白いことに、村上春樹の中にはこの2人のDNAも流れているようなのです。
著者はまず、「村上春樹と三島由紀夫はちょっと似ているところがある。それは二人とも説明がすごくうまいことです」と述べています。
『村上春樹の隣には三島由紀夫がいつもいる。』佐藤幹夫著(PHP新書)という本があるくらい、もともと村上春樹は三島由紀夫の文学的DNAを受け継いでいる作家だと言われています。しかし、内田樹氏は、三島由紀夫だけではなく、司馬遼太郎の面影も村上春樹の中に見つけてしまうのです。内田氏は、司馬遼太郎という人が「フェアネス」ということにすごくこだわる人であり、一面的にものを見ることを嫌ったと述べます。
そして、彼を「できるだけ多様な証言を採り上げて、日本近代史の『ビッグ・ピクチャー』を描き、さらに一歩進んで、近代日本を作り上げる過程で非業の死を遂げた人々の『鎮魂』という作業を手堅く続けてきた作家」と評した後で、次のように述べます。
「よく知られているように、その司馬遼太郎はノモンハン事件のことを書こうとして準備していました。手に入る限りの資料を集めていたけれど、ついに書けなかった。その理由について、司馬遼太郎は『ノモンハン事件にかかわった軍人たちの中で、自分が感情移入できる人物が一人も見出せなかった』からだと書いています。共感できる人物が一人もいない歴史的事件については後世に至ってもそれを物語る人がいない。それゆえ、軍事的にはほとんど無意味な草原を奪い合って死んだ兵士たちについて、誰も物語的には鎮魂していない。ですから、『ねじまき鳥クロニクル』でノモンハン事件が出てきたときには、胸を衝かれました。そうか、司馬遼太郎の跡を継ぐのは、村上春樹だったのか、と」
わたしは、この文章を読んだとき、軽いめまいを覚えました。そして、わたしも「そうか、司馬遼太郎の跡を継ぐのは、村上春樹だったのか」とつぶやきました。
三島由紀夫のDNAを受け継ぎ、司馬遼太郎の跡を継ぐ・・・。
これは、もう日本史上最強の作家と言えるでしょう。
わたしたちは、ものすごいモンスター作家の作品を同時代で読んでいるのです!
これほどのモンスター作家が日本人だけのものであるはずがありません。
実際、村上春樹はノーベル文学賞の候補に何度もなっていますし、いずれ必ず受章するでしょう。著書の内田氏も、新聞社から依頼されて何度も村上春樹の「ノーベル賞受賞予定稿」を書いているそうです。
とにかく村上春樹は万人が認める「世界作家」なのです。一方、わが国の中高年の男性に圧倒的な人気を誇る司馬遼太郎は「国民作家」と言えるでしょう。
司馬遼太郎は、どうして「国民作家」にとどまり、「世界作家」にはなれなかったのでしょうか。そこを問題視する著者は、次のように述べます。
「検索すればすぐ知れるが、村上春樹の翻訳はさまざまな言語で数百冊のものがただちに購入できる。フランスの地方都市の書店でも、村上春樹のペーパーバックは何冊でも手に入った」
ところが、以下のように司馬遼太郎の外国語訳を読むことはきわめて困難です。
「Amazonで現在入手できる英訳は3点しかない(『最後の将軍』、『韃靼疾風録』、『空海の風景』)。『竜馬が行く』も『坂の上の雲』も『世に棲む日々』も『燃えよ剣』も外国語では読めないのである」
まさに「意外」の一言ですが、著者は述べます。
「外国の学者が日本的心性について知りたいと思ったら、司馬遼太郎を読むのが捷径だと私は思うが、その道は閉ざされているわけである(むろん、藤沢周平や池波正太郎も英語訳は存在しない。ついでに言えば、吉行淳之介も島尾敏雄も安岡章太郎も小島信夫も英語では読めない。埴谷雄高も谷川雁も平岡正明も村上一郎も吉本隆明も英訳はない)」
その事実を知ったとき、アメリカやヨーロッパはもちろん、ロシア、東欧、インドネシア、中国など世界中の読者に読まれている村上春樹の物凄さが改めて思い知らされます。
なぜ、村上春樹はここまでの「世界性」を獲得したのか。
著者は、それは彼の小説に「激しく欠けていた」ものが単に80~90年代の日本というローカルな場に固有の欠如だったからではないからだといいます。それは、「はるかに広汎な私たちの生きている世界全体に欠けているもの」だったからであるというのです。
では、この世界に生きるわたしたちが「共に欠いているもの」とは何でしょうか。著者は、次のように述べます。
「それは『存在しないもの』であるにもかかわらず私たち生者のふるまいや判断のひとつひとつに深く強くかかわってくるもの、端的に言えば『死者たちの切迫』という欠性的なリアリティである」
著者いわく、生者が生者にかかわる仕方は世界中で違います。しかし、死者が「存在するのとは別の仕方で」生者にかかわる仕方は世界のどこでも同じだというのです。
著者は、「『激しく欠けているもの』について」という村上文学の本質を衝くエッセイの最後に次のように書いています。
「村上春樹はその小説の最初から最後まで、死者が欠性的な仕方で生者の生き方を支配することについて、ただそれだけを書き続けてきた。それ以外の主題を選んだことがないという過剰なまでの節度(というものがあるのだ)が村上文学の純度を高め、それが彼の文学の世界性を担保している」
わたしも、明らかに村上文学とは「死者と生者との交流」が最大のテーマであると思います。拙著『ご先祖さまとのつきあい方』(双葉新書)の「生命の輪は廻る~あとがきに代えて」にも書きましたが、もともと村上春樹の文学には、つねに死の影が漂っています。彼の作品にはおびただしい「死」が、そして多くの「死者」が出てくるのです。
著者も、「およそ文学の世界で歴史的名声を博したものの過半は『死者から受ける影響』を扱っている。文学史はあまり語りたがらないが、これはほんとうのことである」と述べ、村上春樹のほぼ全作品が「幽霊」話であると指摘しています。
もっとも村上作品には「幽霊が出る」場合と「人間が消える」場合と二種類ありますが、これは機能的には同じことであるというのです。このような「幽霊」文学を作り続けてゆく村上春樹の心には、おそらく「死者との共生」という意識が強くあるのでしょう。
その「死者との共生」のために存在する文化装置として、葬儀や墓といったものがあります。今は亡き愛する人を忘れないように、世界中の人々は葬儀や墓を大切にしているのです。しかし現在の日本では、「葬式は、要らない」とか「墓は、造らない」といった暴論が横行しています。また、「無縁社会」とか「孤族」といったネガティブなキーワードが流行し、果ては「孤独死」を肯定するという輩まで出てきました。
このような社会の流れに対して、わたしは一貫して異議を唱えてきました。
そして、『葬式は必要!』、『ご先祖さまとのつきあい方』(ともに双葉新書)を書き、今月には新刊『隣人の時代』(三五館)を上梓します。
いつも思うのですが、何かを「要らない」という主張を展開するのは簡単ですが、その反対に何かを「必要!」と説得するのは難しいものです。
揚げ足を取ってヤジを飛ばすことは、応援演説することよりもはるかに楽なのです。
でも、どうしても世の中に必要なものなら、たとえ、難しかろうが、不利であろうが、やはり「必要!」と言い続けなければなりません。
そんなわけで、わたしは孤独を感じることがけっこうあるのですが、本書の「新版のあとがき」に紹介されている村上春樹の言葉を読み、非常に感動しました。
それは、2010年に刊行された村上春樹のインタビュー集『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです』(文藝春秋)に出てくる次のような言葉でした。
「ネガティブなことを言ったり書いたりしているのは、簡単だし一見頭がよさそうに見える。実際、今のマスメディアでもてはやされているのは、それに適した頭のよさだったりする傾向があるけれど、僕はやっぱり、そろそろ新しい価値観を作るべき時期だと思うんです。それも、偉そうなものじゃなく、ありきたりのもので作っていく時期が。お惣菜のすすめじゃないけれど、冷蔵庫をのぞいてそこにあった材料で、何かおいしいものを作ってしまう。(・・・・・)とにかく冷蔵庫にあるものでなんとかする。これからはそういう時代だと思うし、僕もそういうことをやっていきたいという気がしているんです」
わたしは、この村上春樹の発言に本当に感動し、「自分のやっていることは間違っていない」と勇気が湧いてきました。こんなに1人の人間の「こころ」に影響を与えられるなんて、「やっぱり、すごい作家だなあ!」と痛感した次第です。
著者も、この文章にはいたく感激したようですが、その理由を次のように書いています。
「有限の資源から引き出しうる最高のパフォーマンスを追及するという村上さんの構えについて、僕は『ブリコルール』というレヴィ=ストロースの術後を借りて何度か論じています。でも、『冷蔵庫』というような同じ比喩が出てくると、なんだかうれしくなってしまいますね」
「ブリコルール」とは、「ブリコラージュ」を行う人のことです。「ブリコラージュ」は「器用仕事」とも訳されますが、「寄せ集めて自分で作る」といった意味です。
そして、「ブリコルール」とは、ブリコラージュの職人に他なりません。
じつは、わたしも常々、ブリコルールでありたいと願っています。
わたしが提唱する「平成心学」は「何でもあり」や「いいとこ取り」を旨としますが、これは明らかにブリコラージュの精神に通じていると思っています。
そのブリコラージュの精神で、わたしは『葬式は必要!』、『ご先祖さまとのつきあい方』、そして『隣人の時代』を書きました。
死者と生者が交流できるために、無縁社会を乗り越えるために、日本人が幸福になるために、いろんな考え方や具体的方法などを寄せ集めてみました。
『隣人の時代』が刊行されたら島田裕巳氏にお送りしようと決めていましたが、内田樹氏、そして村上春樹氏にもぜひお送りしたいと思います。