- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.0188 SF・ミステリー 『虐殺器官』 伊藤計劃著(ハヤカワ文庫)
2010.10.02
「ベストSF2007」第1位、第1回PLAYBOYミステリー大賞(国内部門)第1位、そして「ゼロ年代ベストSF」第1位に選ばれた作品で、「現代における罪と罰」を描いていると高い評価を得ています。著者は、昨年3月20日に34歳の若さで亡くなっています。
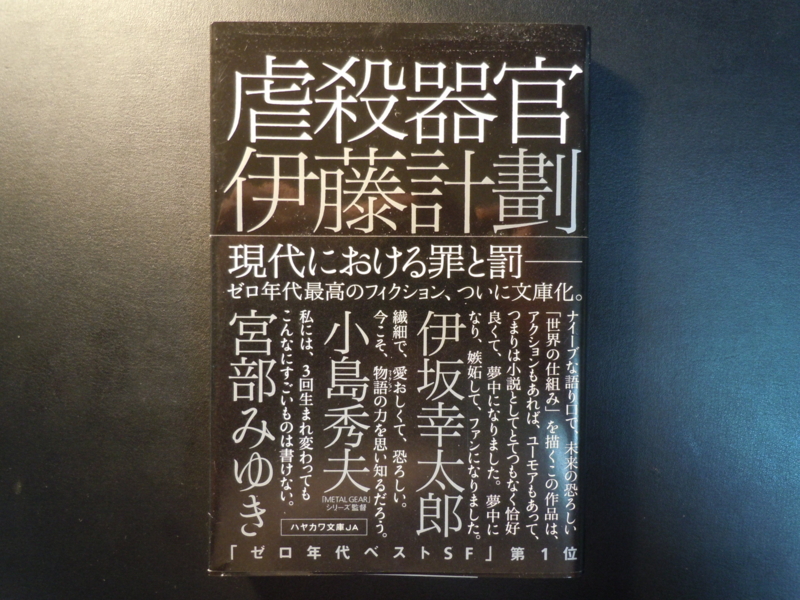
究極の哲学小説
物語は、大量虐殺を誘発する、謎の器官をめぐるものです。9・11以降、”テロとの戦い”は転機を迎え、アメリカをはじめとする先進諸国は徹底的な管理体制に移行してテロを一掃します。
その一方で、後進諸国では内戦や大規模虐殺が急増していました。そして、サラエボは核爆発によってクレーターとなります。米国情報軍大尉クラヴィス・シェパードは、世界を混乱に陥れている「虐殺器官」の鍵を握るジョン・ポールという謎の男を追ってチェコへと向かいます。
とにかく多くの人々が本書を絶賛し、帯には次の3人がメッセージを寄せています。
「ナイーブな語り口で、未来の恐ろしい『世界の仕組み』を描くこの作品は、アクションもあれば、ユーモアもあって、つまりは小説としてとてつもなく恰好良くて、夢中になりました。夢中になり、嫉妬して、ファンになりました」伊坂幸太郎(作家)
「繊細で、愛おしくて、恐ろしい。今こそ、物語(フィクション)の力を思い知るだろう」小島秀夫(「METAL GEAR」シリーズ監督)
「私には、3回生まれ変わっても、こんなにすごいものは書けない」宮部みゆき(作家)
というわけで、ものすごく期待して読みはじめたわけですが、まるでアニメやゲームのような世界観、戦争というテーマ、バタ臭い名前の登場人物、こなれていない硬質の文体。正直言って、どれもが、わたしの趣味には合いませんでした。特に、「METAL GEAR」シリーズの影響を強く感じます。
それもそのはず、著者は「METAL GEAR SOLID~GUNS OF THE PATRIOTS」のノベライゼーションを書き、それをとても誇りにしていたそうです。わたしは、「METAL GEAR」のようなステルスゲームの世界は嫌いなのです。でも、わたしは、あらゆる本を面白く読む男であります。集中して注意深く読み進むと、ストーリーはともかく、随所に興味深い記述がありました。本書は、小説としてよりも哲学エッセイのようなスタンスで読むと面白く読めることに気づきました。いわば「哲学小説」です。たとえば、次のような箇所にそれを強く感じます。
「心の健康を保つためには、深く考えないのがいちばんだし、そのためにはシンプルなイデオロギーに主体を明け渡すのがラクチンだ。
倫理の崖っぷちに立たせられたら、疑問符などかなぐり捨てろ。
内なる無神経を啓発しろ。世界一鈍感な男になれ。
正しいから正しいというトートロジーを受けいれろ」(25頁)
「現実が人それぞれであるように、歴史もまた人それぞれだろう。だから、状況はこうだ、と言ってしまえる歴史など、どの紛争にもありはしない。
ユダヤ人虐殺はなかった、人類は月へ着陸していなかった、エルビスは生きている。
その種の与太話がときおり盛んに議論されるのは、歴史というものが本質的な意味で存在しないことの証左に他ならない。湾岸戦争は起こらなかった、とものすごいことを言ったのは、ポストモダンの聖人であるところのボードリヤールだったっけ」(43-44頁)
「戦争遂行業務。
とても不思議なことばだ。ある種の人々は嫌悪感すら抱くかもしれない―平和活動家や、リベラルの人々は。ぼくはその言葉に今まで想像したこともなかった未来を予感して、不謹慎にもわくわくしてしまった。ぼくはいつもことばに敏感に反応しすぎる。
ピザ屋がピザを作るように、害虫駆除員がゴキブリを駆除するように、戦争もまたある立場からは、民族のアイデンティティーを賭けた戦いでも、奉じた神々への殉教でもなく、単なる業務にすぎないのだ、とDIAの話を聴きながら、ぼくは考える。業務であるから、予算を立てることもできるし、計画することもでき、業者に発注することもできる。戦争はもはや国が振るう暴力から、発注し委託されるものに成り果てた」(86-87頁)
「百万単位の死(メガデス)を思考するための文学。
聖書の黙示録を戦略戦術レベルに落としこむためには、ことばの技巧(アート)が要請された。そのやりくちはいまやすっかり定番となって、おかげでぼくらはそうした官僚的な言葉の裏にある、家族を失った子供や穴だらけにされた死体を、いちいち思い浮かべずに済んでいる」(87頁)
「ハイテク機器と規模の拡大、あとは単純に人件費の増大によって、近代の戦争のコストは極端に膨れ上がった。戦争をやっても単純にいえば儲からないのです。それでどんなに石油の利権が確保できても、ね。では、それでもアメリカが戦争をしているのはなぜか。世界各地で、民間業者の手まで借りて火消しに走り回っているのはなぜか。正義の押しつけ、という人もいますが、コストを払っている以上、わたしはそれを、戦争をコミュニケーションとした啓蒙であると思っています」(179-180頁)
「罪悪感の対象が死んでしまうということは、いつか償うことができる、という希望を剥奪されることだ。殺人が最も忌まわしい罪であるのは、償うことができないからだ。お前を赦す、というそのことばを受け取ることが、絶対的に不可能になってしまうからだ。
死者は誰も赦すことができない」(187頁)
「ぼくはそれについて考える。魂がある、と考えることにどんな意味があるかを。魂がある。肉体を離れた人間の崇高な中枢がある、と考えたほうが、ぼくが見殺しにしてきた多くの子供たちや、手にかけてきた多くの独裁者やごろつき、そうしたものの命を奪ったという罪を軽減できる――そうした魂がしかるべき生を営むことのできる、天国とか地獄とかいうオルタナティヴな世界を想定すれば。
なんだ、宗教の最低の利用法じゃないか。ぼくはぜんぜん無神論者なんかじゃない。そのことに、いま気がついた」(206頁)
「見たことも遭遇したことも交戦したこともない敵の野蛮さ、人非人語りは戦場の定番だが、同様に幽霊話や怪談の類も戦場には欠かせない。幽霊戦艦に幽霊潜水艦、リトアニアの森をうろつくドイツ兵の亡霊。そしてここにもやっぱり幽霊はいて、夜の森に群なして歩む虐殺の被害者たち、ヒンドウー・インディアに殺されたモスレムや仏教徒の村人たちを見たという怪談が、何年にもわたって語り継がれ、ここに詰める兵士たちを怖れさせている。
死が隣り合わせの戦場で、なぜ兵士たちは幽霊を怖れるのだろうか。
頭上の機雷や圧潰の恐怖に怯えながら海中を征く、Uボートの乗組員たちが怖れる幽霊潜水艦。膠着した戦線の夜に現れて同胞を死へといざなう幽霊兵士。死がどれだけ近くにあろうとも、人は幽霊を怖れることができる。どうしようもなく現実だけが横たわる戦場にあっても、フィクション――いや、この場合『妄想』と言ったほうが近いのかもしれない――は人間の実存を脅かすことができるのだ」(302頁)
「仕事だから。十九世紀の夜明けからこのかた、仕事だから仕方がないという言葉が虫も殺さぬ凡庸な人間たちから、どれだけの残虐さを引き出すことに成功したか、きみは知っているのかね。仕事だから、ナチはユダヤ人をガス室に送れた。仕事だから、東ドイツの国境警備隊は西への脱走者を射殺することができた。仕事だから、仕事だから。兵士や親衛隊である必要はない。すべての仕事は、人間の良心を麻痺させるために存在するんだよ。資本主義を生み出したのは、仕事に打ちこみ貯蓄を良しとするプロテスタンティズムだ。つまり、仕事とは宗教なのだよ。信仰の度合において、そこに明確な違いはない。そのことにみんな薄々気がついてはいるようだがね。誰もそれを直視したくない」(310頁)
「殺人や強奪や強姦が、生存のためのニーズから発生したものだとすれば、他人を思いやり、他人を愛し、他人のために自分を犠牲にすることもまた、進化のニーズによって生まれたものだ。われわれのなかには、それなりに生存の必要性によって発生したはいいが、競合し合っている感情のモジュールがいくつかあるんだよ。そして、そのなかにはいまではすっかりいらなくなってしまったが、まだしつこく残っている機能もある。食料が乏しい時代には、甘いものを好むという脳の機能モジュールは栄養摂取の指標づけの上で大きく役に立ったろう。しかしいま、食料が溢れる社会においては、その嗜好性はダイエットの敵と言われる」(364頁)
「世界はたぶん、よくなっているのだろう。たまにカオスにとらわれて、後退することもあるけれど、長い目で見れば、相対主義者が言うような、人間の文明はその時々の独立した価値観に支配され、それぞれの時代はいいも悪いもない、というような状態では決してない。文明は、良心は、殺したり犯したり盗んだり裏切ったりする本能と争いながらも、それでもより他愛的に、より利他的になるよう進んでいるのだろう。
だが、まだ充分にぼくらは道徳的ではない。まだ完全に倫理的ではない。
ぼくらはまだまだ、いろいろなものに目をつむることができる」(382頁)
これらの言葉が並ぶ本書は、まるで21世紀の賢者の名言集の観さえあります。「哲学小説」という表現も理解していただけるのではないでしょうか。本書は著者のデビュー作で、2007年に発表されました。
なんと、著者は弱冠32歳で本書を書いたことになります。参考文献は明示されていませんが、「解説」を書いた翻訳家の大森望氏が次のような書名を挙げています。それによれば、ダニエル・C・デネット『解明される意識』『自由は進化する』、スティーブン・ピンカー『言語を生みだす本能』『人間の本性を考える』『心の仕組み』、マイケル・S・ガザニガ『脳のなかの倫理』、マーティン・デイリー&マーゴ・ウィルソン『人が人を殺すとき』などがテキストとして使われたようです。これらの本の多くは、わたしも『ハートフル・ソサエティ』(三五館)を2004年に書いたときに、参考資料として読みました。
しかし、SF作家・伊藤計劃は、該博な知識をもて遊ぶ単なる博覧強記ではありません。伊藤計劃の最大の特徴とは、「ひたすら、いま現在の人間と世界が抱えている問題を描こうとしたことだろう」と、大森氏は述べています。
あるオンラインSF誌のインタビューで、著者はSFを「社会とテクノロジーのダイナミックスを扱う唯一の小説ジャンル」と認識していたと語っています。また、「わたしはおそらく、これからも地上や『いま、ここ』に縛り付けられたままなんだろうなあ、と思います。・・・・・ひたすら今現在の人間のことしか考えていない」と書いています。
「今現在の人間のことしか考えていない」というのは、わたしが想像するに、「今現在の人間を幸福にするにはどうすべきか」ということではないでしょうか。その意味で、ほとんど同じ参考文献をもとに書かれた『虐殺器官』と『ハートフル・ソサエティ』の2冊は類書と呼べるかもしれません。大森氏は、次のように述べています。
「近未来に託して現在の問題を描くのはSFの得意技だが、たしかにそれをここまでテクニカルかつ繊細にやってのけた日本SFは珍しい。『虐殺器官』の世界では、テロ、新自由主義経済、グローバリズム、民間軍事会社、環境破壊、貧困など、いま、ここにある問題が恐ろしく冷徹に分析される」
それにしても、本書『虐殺器官』には、全篇に死体が登場し、「死」の匂いが立ち込めています。これは著者が病魔に犯されながら本書を書いたことも影響しているでしょう。
2001年の夏に最初の癌が右足に見つかり、著者は入院中の病室で9・11の第一報を聞いたそうです。2005年6月、左右の肺に転移が見つかり、7月に肺の一部を切除しました。その当時のmixi日記で、自らの病状を次のように語っています。
〈デビューする(予定はないが)前に身体が文学者と化してきた伊藤。喀血と足萎えといえばクラッシックかつハードコアな文学戦士のブランドである〉
〈体からすこうしずつパーツが取り除かれてゆくこの人生を、わたくし「逆『どろろ』状態」と呼ぶことにしました。体を取り戻してゆくあの漫画の逆ルートだからです。天国の手塚先生、見てますか〉
ここには、まだ痛々しいながらもユーモアさえ感じられますが、死の直前には悲痛感が満ちてきます。著者は、閲覧者を友人に限定した2007年2月7日のmixi日記に「以下は、自分がどこまで弱い人間かという記録である」との但し書きをつけた上で、次のように赤裸々に記しています。
〈尿も出ず、排便も出来ず、いま私はベッドの上で縛りつけられている/死ぬということを自分がまるで受け入れていなかったということに愕然としながら〉
〈これから死ぬ自分を受け入れるにはどうしたらいいのだろうか。/だれか、助けになる方法を知っていたら教えて欲しい〉
その方法のひとつとは、著者自身が本書『虐殺器官』の206ページに書いた「宗教の最低の利用法」に他ならないと、わたしは思うのですが。しかし迫り来る死に直面する恐怖を正直に告白する著者の姿に、言葉もありません。ここまで赤裸々な「死の恐怖」の告白は、正岡子規の『病床六尺』以来ではないかとさえ思います。子規にしろ、著者にしろ、その卓越した文才とともに、「もっと生きて、もっと書きたい」という生への強い意志があったのでしょう。実際、著者は最初に右足を失ったとき、「両足がなくなってもいいから、僕はあと二十年、三十年生きたい。書きたいことがまだいっぱいある」と母親に語ったそうです。
その年の3月20日、伊藤計劃はついに力尽きます。彼の母親によれば、死のだいぶ前から食事も水もあまり摂れない状態だったそうです。でも、死の当日の夕食には大好物のカレーが出ました。著者は、「少し食べてみる」と言って、スプーンに10杯ぐらい食べたとか。それから1時間ほどして、床ずれを防ぐために姿勢を変えたとたん、すーっと意識がなくなり、そのまま帰らぬ人になったそうです。
著者の母は、2009年7月の星雲賞授賞式に故人にかわって登壇したとき、伊藤計劃の最後の模様を語った後、次のように述べました。
「お腹が空いたまま逝ったら、三途の川も渡れなかったんじゃないかと思いますが、最後にカレーを食べたので、今帰ってこないところをみますと、なんとか向こうにたどりついてるんじゃないかと思います。応援してくださった皆様、おつきあいしてくださった皆様、本を読んでくださった皆様、ほんとうにありがとうございました」
わたしは、このご母堂の挨拶を読んで、涙が出ました。そして、伊坂幸太郎に「とてつもなく恰好良くて」と言わしめた前衛的な作品を書いた著者の回想に「三途の川」という古典的な言葉が出てきて、なんだか安堵しました。著者の死の恐怖を救ったものは、おそらく子規と同様に母の存在だったと思います。
最後に、哲学を「死の学び」と表現したのはソクラテスですが、その意味でも、戦場を舞台に死を極限まで考察した本書は、究極の「哲学小説」であると確信します。
不世出の天才SF作家・伊藤計劃よ、安らかに眠れ!