- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.0112 哲学・思想・科学 『なぜ、脳は神を創ったのか?』 苫米地英人著(フォレスト新書)
2010.07.11
『なぜ、脳は神を創ったのか?』苫米地英人著(フォレスト新書)を読みました。
著者は、ご存知、ベストセラーを連発する脳機能学者です。本書は、アマゾンの「哲学・倫理・思想のベストセラー」で現在、1位を独走中の本です。
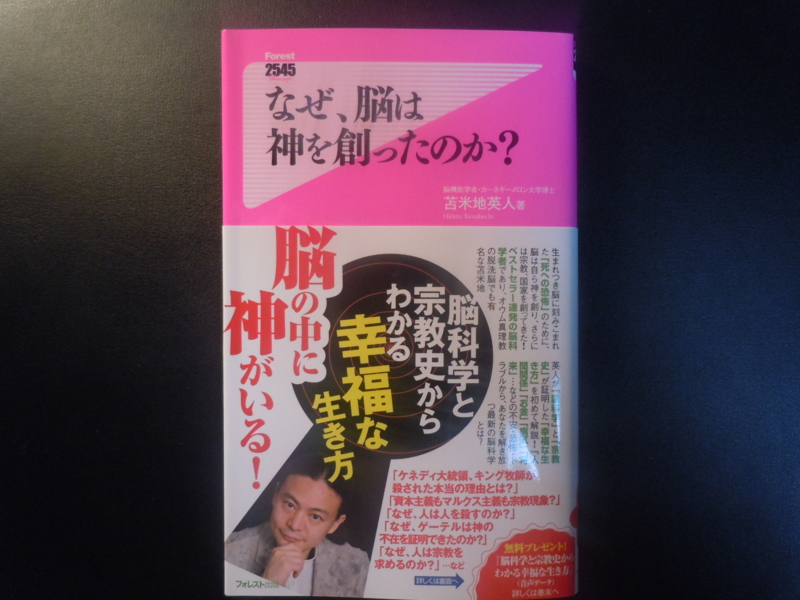
脳の中に神がいる!
フォレスト出版から『最短で一流のビジネスマンになる!ドラッカー思考』を刊行したとき、同社の編集者に薦められて、著者の本を固め読みしました。中でも、『洗脳原論』(春秋社)と『スピリチュアリズム』(にんげん社)が非常に面白かったです。
著者は、オウム真理教信者の脱洗脳や、国松警察庁長官狙撃事件で実行犯とされる元巡査長の狙撃当日の記憶の回復などに関わり、脱洗脳のエキスパートとしてオウム事件の捜査に関わってきたそうです。一部で「マッド・サイエンティスト」とか「トンデモ脳機能学者」などと呼ばれているようですが、わたしは本物の天才ではないかと思うぐらい頭脳明晰な人だと思っています。まあ、ときどき、その発言に違和感をおぼえることも事実ですが。(笑)
本書では、「神」の問題にダイレクトに迫っています。
「なぜ、人はスピリチュアルにハマるのか?」
「なぜ、人は宗教を信じるのか?」
「なぜ、人は占いが好きなのか?」
「なぜ、脳は神を創造したのか?」
などの問題を認知科学、脳科学、分析哲学から紐解くという内容になっています。
著者によれば、ゲーデルとチャイティンの功績によって、「神の不在」は数学的、哲学的に証明されました。それでも人間が信仰心を抱くのはなぜか。著者は、その理由を主に3つ挙げています。
第1に、自分が不完全な情報システムであるということを、誰もが何かをきっかけにして自覚するため。人は、大変な災厄に見舞われたり、最愛の人を死に別れたりしたとき、自分の無力さを痛感します。未来の出来事を知ることができない人間とは、どんなに努力しても部分情報しか得られないことに「気づく」のです。すると、すべての人ではないにせよ、人間には完全情報を求める心が芽生えます。著者は、次のように述べています。
「絶対神のような神をつくりあげてきた思想の始まりは、このような完全情報に対する憧憬や畏怖の念といえます。自分が部分情報にすぎないという思いが、逆に、完全情報があるに違いないという考えに結びつきます」
その完全情報を求める心が信仰の念を強め、それに近づくために人間はさまざまな儀式や祭祀を生み出してきたというのです。
人間が信仰心を抱く第2の理由は、シャーマニズムに見られるような信仰心の醸成だそうです。シャーマニズムは、邪馬台国の卑弥呼に代表される巫女や祈祷師の能力によって成立つ信仰で、世界中に見られます。
著者は、シャーマニズムについて、「自然崇拝、精霊崇拝というアニミズムをともなうケースがほとんどであると同時に、その基本を祖先崇拝においています」と定義した上で、「集団に属する人々は、自分たちにはどうにもできない問題を解決してくれる存在として、巫女や祈祷師を崇めるようになります。そして、シャーマンに備わった特殊な能力が、祖先を敬うという人々の情動と合わさって、ひとつの宗教システムになってゆくのです」と述べています。
シャーマニズムにおいても、部分情報しか得ることができない人間が完全情報を求めようとするメカニズムが働いています。完全情報としての神の概念がはっきりとした輪郭を持つにつれ、人々の信仰心は強化されてゆくのです。
そして、人間が信仰心を抱く第3の理由は、死の恐怖だといいます。これは、わたしも大いに同感で、『ロマンティック・デス』(幻冬舎文庫)や『ハートフル・ソサエティ』『法則の法則』(ともに、三五館)をはじめとした多くの著書で、「死の恐怖」が哲学・芸術・宗教を誕生させたと述べています。本書の著者も次のように述べています。
「死の恐怖は、ほとんどの生物のなかに情報として書き込まれており、死を恐れない生物はありません。死の不安のない生物がいたとしたら、それは大喜びで死に絶えて、とっくの昔に絶滅しているのです」
逆に言えば、絶滅せずに進化し、現代まで生き残っている人類は、よほど死を恐れている種であるということです。著者によれば、「死の恐怖」は脳の大脳辺縁系などに刻まれている根源的な恐怖であり、それをやわらげるためには、何らかの「ストーリー」が必要になってきます。そのストーリーこそは、部分情報としての人間にとっての完全情報たる「死後の世界」あるいは「神の世界」の側からのストーリーテリングなのです。著者は言います。
「宗教の教義が持つストーリーはいずれも、こうしたストーリーテリングに当てはまります。そして、それが一番上手な人が教祖として、人々の信仰の対象に据えられることになります」
こうして生まれた人間の信仰心は、完全情報である「神」とコミュニケーションを目的とする社会システムとして発展していくというのです。
本書には、神秘的な逸話を持つ人物の正体をさぐる興味深い考察もあります。
たとえば、宮本武蔵の正体は、催眠術師ではなかったかといいます。剣豪というと、剣のみで優劣を競う世界であるかのように思います。でも、織田信長の時代から江戸幕府が打ち立てられて戦国時代が終了するまでの時代を追うと、剣豪たちの多くは剣術と同時に妖術を使ったことを示す断片的資料がたくさん残っているというのです。著者は、次のように述べます。
「その昔の戦国時代には、剣術が強い人が権力を握りました。古武道の成り立ちから見ても、剣が強かった人たちが瞬間催眠に秀でていた可能性は高いと思えます。
その意味では、織田信長も、徳川家康も、催眠術師であった可能性は残されているわけです。要するに、信仰から生じる権力も、社会に君臨する権力も、その根っこにあるのは、大きく催眠術師に分類することのできるような『技』であたっといえるのではないでしょうか」
さらに、著者はあの「ブッダ」こと釈迦の正体についても、次のように述べます。
「あくまで私見ですが、現代風にいえば、釈迦は天才的なヨガ行者もしくは気功師だったのではないかと考えられます。病気をどんどん治してしまうわけです。それは、オカルトでもなんでもありません。
釈迦を信じた人は、病気が治って当然です。たとえ、あまり信じてもらえなかったとしても、釈迦がその人の内部表現の書き換えにたけていれば、病気は治ってしまうのです。当時はバラモン教の時代ですから、人々は、超人として、釈迦というバラモンの1人を拝んだのであり、そのラディカルな思想に共感したのではなかったかと考えられます」
さて本書で、著者は次のような思い切ったことをズバリと言います。
「宗教は、本質的にはこの21世紀には不要なものです。
ところが、世界はいまだに暗黒時代であり、とくに日本は、いまなお平安時代の闇が支配しているようなものです。そのため、国家の繁栄や世界の経済システムの維持発展というありもしない価値のために、人々は争い、人間不信は広がり、権力者による収奪はつづき、戦争も絶えません。
私には釈迦が『はやく宗教を必要としないところまで大人になれよ。2500年もの間、お前たちは何をやってきたのだ』と促しているようにも思えます」
これは、さすがに異論を唱えたいところですね。わたしは、戦争が根絶されて人類社会が平和になったとしても、宗教は人類にとって必要なものだと考えます。それは、わたしが完全情報の世界の実在を信じているからかもしれません。たとえ、どんなに平和で豊かな社会になっても、人々は「神」を必要とするように思うのですが。
プロフィールを見ると、著者は天台宗ハワイ別院国際部長であり、チベット仏教カギュー&ゲルク派傳法大阿闍梨だとのこと。なんだか凄そうでもあり、よくわからない気もする肩書きですが、とりあえず仏教者、つまりは宗教者なわけです。宗教者である著者が「宗教は、この21世紀には不要」と主張するところが本書の良くも悪くも面白いところでしょう。
わたしは、この21世紀には新しい宗教が必要だと思っています。でも、それは「宗教」とは呼ばれないかもしれません。わたしは、それを「宗遊」と呼んでいます。
宗教の「宗」という文字は「もとのもと」という意味で、私たち人間が言語で表現できるレベルを超えた世界です。いわば、宇宙の真理のようなものです。その「もとのもと」を具体的な言語とし、慣習として継承して人々に伝えることが「教え」です。だとすれば、明確な言語体系として固まっていない「もとのもと」の表現もありうるはずで、それが「遊び」なのです。
音楽やダンスなどの「遊び」は最も原始的な「もとのもと」の表現であり、人間をハートフルにさせる大きな仕掛けとなります。もはや何かを人間の心に訴えるとき、「教え」だけでプレゼンテーションを行なう時代ではないと思います。
幸福、愛、平和といった抽象的なメッセージを伝えようとしても、今までは「教え」だけだったので説教臭くなって人々に受け入れられないという面がありました。そういった抽象的な情報は、言語としての「教え」よりも、非言語としての「遊び」の方が五感を刺激して、効果的に心に届きやすいのです。
人間が心の底からメッセージを受け取るのは、肉体というメディアを通過させた「体感」によってでしょう。情報と記号が氾濫する現代においては特にそのことが言えます。
じつは、「宗遊」とは「葬儀」の同義語でもあります。「遊び」についての不朽の名著『ホモ・ルーデンス』を書いたイタリアの文化史家ヨハン・ホイジンガは、「遊びは文化よりも古い」と述べました。
わたしは、『ロマンティツク・デス』の中で「葬儀は遊びよりも古い」と書きました。実際、世界史を見ても、相撲・競馬・そしてオリンピックなどの来歴の古い「遊び」の起源はいずれも葬儀と深い関係があります。そもそも、約10万年前にネアンデルタール人が死者を埋葬した瞬間、サルがヒトになったとも言われ、葬儀とは人間の精神的営みにおけるビッグバンであり、人類の存在基盤そのものなのです。古代の日本では、天皇の葬儀にたずさわる人々を「遊部(あそびべ)」と呼んでいました。「葬儀」と「遊び」のつながりをこれほど明らかにする言葉はありません。
本書の著者も言うように、21世紀は「宗教」の時代ではありません。21世紀は「宗遊」の時代です。わたしは、そう確信しています。「宗遊」とは、「死」を見つめ、心を純化する営みとしての哲学・芸術・宗教が統合された大いなる精神の世界です。そして、それは葬送儀礼そのものでもあります。「宗遊」が真に実現されるとき、日本人はもはや、人が死んでも「不幸」とは呼ばないでしょう。