- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.0088 死生観 『メメント・モリ』 藤原新也著(三五館)
2010.06.05
藤原新也さんにお会いしたのを契機に、『メメント・モリ』(三五館)を再読しました。25年にわたって読み継がれてきた「生」と「死」の聖典が21世紀エディションとして蘇りました。これまで愛読されてきた情報センター出版局版にはなかった新しい写真が22点、コピーが21点加えられています。
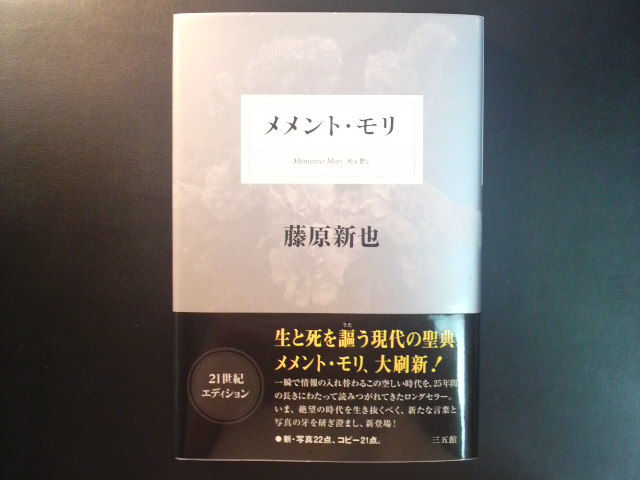
201006042245000
生と死を謳う現代の聖典
最初に、この本を読んだのは、たしか大学生の終わり頃でした。ものすごい衝撃を受けました。なにしろ、インドで撮影したという人間の死体が写っているのです。それも、人間の死体が犬に食われている写真まである。しかも、「ニンゲンは犬に食われるほど自由だ。」というコピーがついているのです! もう、ぶっ飛びました。
本書を開くと、最初のページに、「ちょっとそこのあんた、顔がないですよ」とあります。そこから、いちいち読む者の心に揺さぶりをかけるようなインパクトの強い言葉が並んだ序文がスタートします。
「いのち、が見えない。」
「死ぬことも見えない。」
「今のあべこべ社会は、生も死もそれが本物であればあるだけ、
人々の目の前から連れ去られ、消える。」
「街にも家にもテレビにも新聞にも机の上にもポケットの中にもニセモノの生死がいっぱいだ。」
「死は生の水準器のようなもの。」
「死は生のアリバイである。」
そして、この後、「メメント・モリ」という言葉が初めて登場し、著者は述べます。
「この言葉は、ペストが蔓延り、生が刹那、享楽的になった中世末期のヨーロッパで盛んに使われたラテン語の宗教用語である。その言葉の傘の下には、わたしのこれまでの生と死に関するささやかな経験と実感がある。」
序文を通過して、読み進むと、見たこともないような圧倒的な写真たちが次々に目に飛び込んできます。キラキラとひかる夜の海、天国にも地獄にも見えるオレンジ色の世界、祭りの日の聖地に転がる人間の死体、燃やされる人間の死体、カラスにつつかれる人間の死体・・・。
ふと、羊のような動物の死体に花輪が手向けてある写真に目がとまりました。人間以外の「いのち」にも礼が尽くされている場面は感動的でした。羊の足には蹄(ヒズメ)があります。そうです、口蹄疫にかかって殺処分された宮崎の牛たちと同じです。殺された無数の牛たちは、もちろん花など捧げられず、人間から食べられることもなく、ただ殺されました。その処分の光景など、わたしたちの目からまったく隠されています。
人間の死体も動物の死体も隠されている日本。人間の死体も動物の死体も晒されているインド。どちらが自然に近いかは一目瞭然でありましょう。

この世か、あの世か。
フランスの箴言家ラ・ロシュフーコーは「太陽と死は直視できない」と言いました。たしかに自分の死、1人称の死は絶対に見ることができませんが、3人称の死をこれでもかとばかりに見せてくれる本、それが本書です。そして、写真の素晴らしさは言うに及ばず、それらに添えられたコピーの数々はまた素晴らしい。
「死の瞬間が、命の標準時。」
「死体の灰には階級制度がない。」
「死とは、死を賭して周りの者を導く、人生最期の授業。」
「死人と女には花が似合います。」
「水はバイブルである。」
「火はアナキズムである。」
「赤子は黙って人権宣言。」
「眠りは、成仏のための、日々の錬磨のようなもの。」
「母の記憶は、子供の記憶。」
「父の記憶は、青年の記憶。」
「歩みつづけると、女は子供を孕むことがあります。
歩みつづけると、男は自分の名前を忘れることがあります。」
「極楽とは、苦と苦の間に一瞬垣間見えるもの。」
そう、著者のコピーは箴言そのもの。藤原新也は現代日本のラ・ロシュフーコーなのです!

あまねく照らすもの
わたしの魂を強く揺さぶったコピーが3つあります。
「太陽があれば国家は不要。」
「月の明りで手相を見た。生命線がくっきり見えた。」
「ひとはみな、あまねく照らされている。」
ラ・ロシュフーコーの箴言の通りに、太陽と死はともに直視できません。それに加え、太陽と死はともに、人間に対して「最大の平等」を与えてくれるものです。太陽はあらゆる地上の存在に対して平等です。それゆえ、太陽光線は世界中の人々に等しく降り注ぎます。
わが社の社名はサンレーですが、万人に対して平等に冠婚葬祭を提供させていただきたいという願いを込めて、太陽光線(SUNRAY)という意味を持っています。
「死」も平等です。「生」は平等ではありません。生まれつき健康な人、ハンディキャップを持つ人、裕福な人、貧しい人・・・・・「生」とは差別に満ち満ちています。しかし、どんな人にも「死」だけは平等に訪れます。ですから、上の3つのコピーは、太陽光を冠した社名の会社を経営し、月を基軸とした平等な葬送を志しているわたしにとって、涙が出るくらいに共感できるものなのです。
しかも、「ひとはみな、あまねく照らされている。」が添えられている写真は、雲の間からチラリと姿を見せている天体が太陽なのか満月なのか、よくわからないのです。それは、まるで天国か地獄かよくわからない写真のようです。
わたしは、藤原新也という写真家が天才であることの最大の証明は、天国にも地獄にも見える、太陽にも月にも見える、そんな世にも不思議な陰陽一体の作品を生み出したことにあると思います。それは、もう、天使も悪魔も超越した、光も闇も包みこんだ存在。そう、限りなく神そのものに近い世界ではないでしょうか。

死後の世界はイメージ・アート
本書のラストに登場する写真が、わたしは大好きです。一言でいえば、絵に描いたような楽園。青い空、白い雲、赤い花、緑の芝生・・・・・。この写真以上に楽園をイメージさせる写真は、なかなか撮れないでしょう。いわば、「完璧な写真」としか表現できません。
こんな美しい写真を毎日ながめて、死後の世界をイメージすると良いかもしれませんね。わたしは、「死後の世界」とは一種のイメージ・アートだと考えています。
臨死体験者の報告を聞いても、亡くなった人は、「死んだら、こんな世界に行くのだ」という生前のイメージ通りの世界に行くのではないかと思います。だから、キリスト教徒は天国に行くし、仏教徒は浄土へ行く。この楽園をいつも想い続けている人は、この楽園へ行く。
他の写真に添えられたものですが、「死のとき、闇にさまようか 光に満ちるか 心がそれを選びとる」というコピーが、本書にも出てきます。「死後の世界」とは、心が選びとった世界、心が編集したイメージなのです。
わたしは、本書の写真を展示した「メメント・モリ・ミュージアム」のを夢見てしまいます。そこを訪れた者は、自然と死を想い、知らない間に死が怖くなくなるようなミュージアム。そんな空間が、できれば著者の故郷である門司港に誕生すれば素敵だと思います。
それにしても、本書は贅沢な本です。この過剰な写真に過剰なコピー。こんな過剰な本が他にあるでしょうか。これほど心が乱され、これほど心が休まる本が他にあるでしょうか。こんな凄い本が他にあるでしょうか。