- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2339 評伝・自伝 『俺は100歳まで生きると決めた』 加山雄三著(新潮新書)
2024.07.29
『俺は100歳まで生きると決めた』加山雄三著(新潮新書)を読みました。「まだやりたいことがある。だから若大将は生きる。」というサブタイトルがついています。著者は、1937年(昭和12年)生まれ。歌手、俳優、作曲家。慶應義塾大学法学部卒業。「君といつまでも」などヒット曲多数。主演映画に「若大将」シリーズなど。2021年度の文化功労者に選出されています。
 本書の帯
本書の帯
本書のカバー表紙にはエレキギターを持った著者の全身写真が使われ、下部には「年齢を重ねて再びチャンスを摑み、命の危機も乗り越えた、最高の幸福論」とあります。
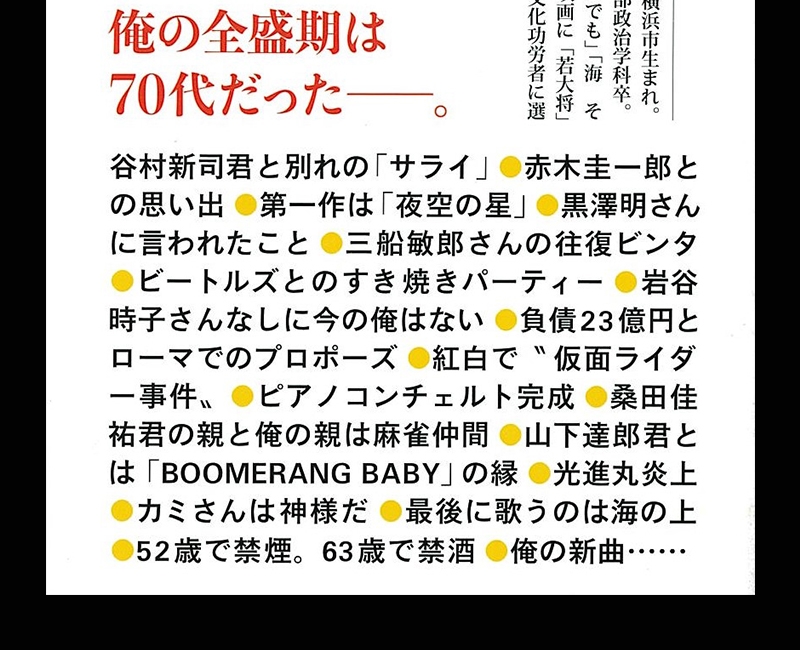 本書の帯の裏
本書の帯の裏
カバー裏表紙の下部には、「俺の全盛期は70代だった――。」として、「谷村新司君と別れの「サライ」●赤木圭一郎との思い出●第一作は「夜空の星」●黒澤明さんに言われたこと●三船敏郎さんの往復ビンタ●ビートルズとのすき焼きパーティー●岩谷時子さんなしに今の俺はない●負債23億円とローマでのプロポーズ●紅白で“仮面ライダー事件”●ピアノコンチェルト完成●桑田佳祐君の親と俺の親は麻雀仲間●山下達郎君とは「BOOMERANG BABY」の縁●光進丸炎上●カミさんは神様だ●最後に歌うのは海の上●52歳で禁煙。63歳で禁酒●俺の新曲……」と書かれています。
また、カバー前そでには「2022年末のNHK紅白歌合戦出演を最後にコンサート活動から引退した加山雄三は、ある決意をする。『俺は100歳まで生きる』と。新たな音楽活動に挑戦して本人が『攻めに転じた』という70代から愛船の火災と病に見舞われた80代、そして未来を見据えた余生まで。自身を育んだ茅ヶ崎の海や強い絆で結ばれた友たちに思いを馳せながら、永遠の若大将が語る幸福論!」と書かれています。
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
第一章 輝かしき俺の70代
第二章 茅ヶ崎の海が俺を育てた
第三章 俺の芸能生活、山あり谷あり
第四章 80代、まだまだ青春
第五章 今の俺、これからの俺
「おわりに」
「はじめに」で、著者は「日本では、75歳以上を後期高齢者というらしいね。70になったら、まあまあ老人ということだよ。でも、ふり返ると、俺の全盛期は70代だったんじゃないかな。コンサートで歌ったり、テレビ番組であちこち歩き回ったり。70代は毎日充実していたからね。その延長線上に、今の80代の元気な暮らしがある」と書いています。
第一章「輝かしき俺の70代」の「俺の音楽のルーツはベートーヴェン」では、東日本大震災の直後に東北の被災地をまわり、歌ってあらためて気づいたことがあるとして、著者は「俺の歌の多くは、ギター1本だけでもちゃんと伝えることができるんだ。バンドメンバーを何人も連れていかなくてもやれる。なぜなのか――。メロディがシンプルなんだよ。手前味噌になるけれどさ。聴いた人たちが気持ちよくなるようなコード進行でできているんだ。ほとんどの曲は、歌を通して俺の気持ちを伝えることができた。あのときは、親父に感謝したね。俺の音楽のルーツ、作曲のもとになっているのは、親父の部屋の棚のレコードだったから。うちの親父はクラシックが大好きでね。たくさんレコードを持っていた。そのなかでもよく聴いていたのが、バッハ、ベートーヴェン、ブラームスの“3B”だよ。この3人は特別で、ほかのレコードとは別の棚に収納されていた」と述べています。
3Bのなかで著者が一番好きだったのは、ベートーヴェンだそうです。スケールが大きくて、物語性があって、メロディがシンプルだとして、著者は「ピアノ協奏曲第5番の『皇帝』も、年の瀬になるとあちこちのホールで演奏される協奏曲第9番の合唱も、ドラマティックでわかりやすいメロディだろ。だから、一度聴いたら覚えてしまう。口ずさめる。それを思うと、ベートーヴェンの影響を受けた音楽家はたくさんいた。たとえば、永六輔さんが作詞、中村八大さんが作曲で坂本九ちゃんが歌った『上を向いて歩こう』からはベートーヴェンのピアノ協奏曲第5番の『皇帝』の影響を感じるだろ? 何度もピアノで弾いているうちにメロディが脳に記憶されて、それが作曲のときにアウトプットされてきたのかもしれない」と述べます。
第二章「茅ヶ崎の海が俺を育てた」の「いやだったフリチン」では、著者の幼少時代の家は茅ケ崎駅と相模湾を結ぶ道の途中にあったことが紹介されます。かつては「上原謙通り」、今は「雄三通り」という名称になっている道沿いです。著者は、「夏は毎日海で遊んだ。楽しくてしかたがなかった。でも、1つものすごくいやなことがあってさ。親父の方針で、夏は外でも全裸にさせられていたんだ。フリチンだよ。親父は太陽の光を全身で浴びたほうが身体にいいと思ったんだろうな。他の人はみんな海水パンツをはいているのに、俺だけフリチン。恥ずかしいなんてもんじゃなかったね。尻に砂はつくしさ。すごい不満だった。しかたがないから、海藻をひろってさ。腰に巻いて前を隠していた。今でも写真が残っているよ」と述べています。
「目の前で消えた命」では、戦時中はよく死体に出くわしたことが紹介されます。ある朝、著者が浜を散歩させていた犬が足を止めました。人の死体が打ち上げられていたのです。著者は、「死んだ人をそのまま放置しておくわけにはいかないだろ。脚を持って浜に引き上げようとした。すると、皮がずるっと剝けてね。骨がむき出しになった。水をふくんでブヨブヨになっていてさ。ものすごい臭いがした。俺はあわてて砂に両手を突っ込んでこすり合わせた。でも、臭いはとれなかった。俺、水死体と出くわす体験が多くてさ。いつもカガワさんという駐在さんに連絡をしていたんだ。『カガワさん、大変だ』『どうした?』『また死体が上がってる』あとはカガワさんに引き継ぐんだ。俺は家に駆けこんで、風呂場で石鹸でゴシゴシ手を洗うんだけど、死体の臭いはなかなかとれなくて、おふくろによく叱られていた」と述べます。また、「多感な時期に死んだ人をたくさん見ると、人生観が変わると思うな。運命というかさ。自然や戦争のような大きな流れには人は逆らえない。かなわないと知る。それを思うと、今の俺は生かされているというかさ。守れられている気もするよ」とも述べています。
「峰岸慎一の説得で俳優に」では、俳優になろうという著者の夢を父親の上原謙が反対したというエピソードが紹介されます。著者は、「俺の俳優志望を親父が反対するのには理由があった。ずっと経ってから知ったんだけどね。すでに、俺の映画会社入りの話があったらしい。松竹からオファーが来ていたんだな。でも、親父は断っていた。俺には言わなかったけどね。だから、松竹にも頼みづらい。ほかの映画会社に俺を入れれば松竹に申し訳ない。そんな事情があったんだな。そうしているうちに東宝の大プロデューサー、藤本真澄さんが俺を欲しがってくれた。そんないきさつで、東宝に入ることになった。そのあたりも本人である俺の知らないところで決まっていったんだけどね。複雑な気持ちはあったけれど、考えてみたらね、ずっと親父の恩恵をたくさん受けている。ありがたいと思っているよ」と述べています。
第三章「俺の芸能生活、山あり谷あり」の「若大将と青大将」では、1960年に東宝に入ったことが紹介されます。給料は5万円でした。電車に乗って成城にある東宝撮影所に通いました。著者は、入社した年に三船敏郎主演の『男対男』でデビューして、『独立愚連隊西へ』で主演。このときに決めた芸名が「加山雄三」でした。この芸名について、著者は「うちのおばあちゃんが占い師に相談してくれてさ。その占い師が10個くらい字画のいい名前を考えてくれた。そのなかから選んだんだ。『“加”は加賀百万石から。“山”は日本一の富士山から。“雄”は英雄から。“三”は東宝の創業者の小林一三から』」と述べます。
第1作の『大学の若大将』(1961年)では水泳、2作目の『銀座の若大将』(1962年)では拳闘、3作目の『日本一の若大将』(1962年)ではマラソンをやりました。これで3作。でも、3つでは終わりませんでした。若大将シリーズはヒットしたのです。全部で18本作られました。若大将は著者で、ライバルの青大将は田中邦衛が演じました。ヒロインは星由里子でしたが、途中から酒井和歌子に替わりました。ザ・ランチャーズを結成したのもこの若大将シリーズがきっかけでした。著者は、「映画の中で俺はスポーツもやったけれど、歌ったり演奏したりもしたよ。青大将役の田中邦衛さんは、俺よりも5つ年上。最初に会ったときはびっくりしたよ。20代であの風貌だったからね。ところが撮影がスタートすると、素晴らしいんだ。なんともいえない味がある。邦衛さんのような俳優と一緒にやらせてもらえて、ありがたかったな。青大将がいたからこそ若大将がいた。今もそう思っているよ」
若大将シリーズが18本も続いたのは邦衛さんのおかげだという著者は、「俳優としての俺のキャリアで、あの人と出会えたのは大きな財産だったな。若大将シリーズの後、邦衛さんは『北の国から』で主演して、あのドラマはたくさん賞を獲っただろ。長く続いて、間違いなく日本のドラマ史の名作の1つになった。俺は自分のことのようにうれしかった。邦衛さんは評価されるべき、素晴らしい人だと思っていたからね」と述べています。
「黒澤明さんに言われた『テレビに殺されるなよ』」では、日本映画の二大巨匠である小津安二郎監督と黒澤明監督の思い出が綴られています。小津監督はずっと茅ケ崎に住んでいました。著者の父である俳優・上原謙と仲がよかったから、よく著者の家に遊びに来て酒を飲んでいたそうです。でも上原は下戸だったので、小津監督だけ酔っ払って、いつもなにを言っているかわからなくなりました。よれよれで帰っていったそうです。
黒澤作品では、著者は『椿三十郎』(1962年)と『赤ひげ』(1965年)の2作に出演しました。どちらも主演は三船敏郎でした。著者は、黒澤監督から「台詞は覚えなくていいぞ 」といつも言われていたそうです。著者が「監督、覚えなくちゃ出てこないですよ」と言ったという著者は、「もっともな反論だろ。黒澤さんの言うことが、あのころの俺には理解できなかった。『思えば出てくるんだよ』黒澤さんは言う。もはや禅問答だ。大監督が言うんだから、そんなもんかな、と思いながらも台詞は覚えていった」と述べています。
東宝撮影所がある成城の街で、著者は黒澤監督とすれ違ったことがあったそうです。そのとき、「おい、加山!」と呼び止められました。著者が「はい!」と言って立ち止まると、忠告されました。「テレビに殺されるなよ」「はい!」。それだけのやりとりで、黒澤監督はにっこりと笑って歩いていったそうです。『椿三十郎』や『赤ひげ』を撮影している頃は、若大将シリーズが大人気でした。それでテレビ番組によく呼ばれ、若大将シリーズでは歌もやっていました。歌謡番組にも出演しました。著者は、「黒澤さんは、テレビタレントの色が付き過ぎると役者としてよくないと言ってくれたんだろうな。愛情を感じた。忘れられない出来事だよ」と述べます。
「幸せだなあ」では、音楽制作において著者がもっとも脂が乗っていたのは1965年かもしれないといいます。次々とレコーディングしました。「君といつまでも」「夜空の星」「ブラック・サンド・ビーチ」「お嫁においで」「旅人よ」……。いくらでも曲ができました。「君といつまでも」はトータルで350万枚も売れました。インストゥルメンタルのロック「ブラック・サンド・ビーチ」はベンチャーズも気に入ってカバーしてくれました。こうした曲の中で歌詞のある作品のほとんどを岩谷時子が詞を書いています。
映画『エレキの若大将』の中で歌って大ヒットした「君といつまでも」は、間奏部で台詞がりますが、最初はなかったそうです。大阪の毎日放送にあったレコーディングのスタジオで生まれたといいます。著者は、「スタジオに入って、俺はまず既に録音されていたオケ(歌の入っていない演奏だけの録音)を聴いて感激した。作曲家で編曲家の森岡賢一郎さんがアレンジしてくれたあの曲のオケを聴いたら、素晴らしくてさ。俺、もう、うれしくてさ。思わず言ったんだよ。『幸せだなあー」』感激して本心が言葉になったんだ。それを岩谷さんやディレクターが反応した。『今の加山さんの言葉を入れましょう』そう言って、間奏部の台詞になったんだ」と述べています。
「負債23億円とローマでのプロポーズ」では、著者は「人生は山があれば谷もある。1970年に俺は想像もしていなかった状況で大借金を背負うことになった。茅ケ崎の湘南海岸沿いでおじが経営していたパシフィックホテル(パシフィックホテル茅ケ崎)が倒産したんだ。おじは行方がわからなくなって、書類上共同経営者になっていた俺に借金がまわってきた。負債は23億円。今の価値なら、50億円以上になる計算だ」と述べます。著者の最大のピンチのときに救いになってくれたは夫人でした。当時はまだ結婚していませんでしたが、著者が莫大な借金を背負っても、メディアに悪く書かれても、まったく態度を変えなかったそうです。「大丈夫?」と一度だけ聞かれましたが、「大丈夫だよ。俺、頑張るからさ」と言うと、「よかった」と言われたそうです。著者は、「借金についてはその程度の会話しかしなかったと思う。カミさんは10代で父親を失っていて、ずっと強く生きてきた。肝が据わっているんだな」と述べるのでした。
「紅白で“仮面ライダー事件”」では、あの有名な事件に言及しています。著者は紅白で7年連続で歌い、1986年からは3年続けて白組のキャプテンをやりましが、「その1986年のとき、俺は失敗しちまった。これは有名な話だけどさ。あの年が初出場で、白組のトップバッターで歌った少年隊の曲『仮面舞踏会』を『仮面ライダー』って紹介してしまったんだ。『白組のトップバッターは少年隊。おい、張り切っていこうぜ! 紅白初出場。少年隊。「仮面ライダー」です』堂々と言った」と述べています。1986年の紅白には小林旭が出場しており、司会を務める著者のそばに来て「違うだろ。仮面ライダーじゃない。『仮面舞踏会』だろ」と教えたそうです。
「ありがとう。バイバイ」では、1991年11月に著者が企画した父親の誕生会が紹介されています。親戚を40人くらい集めて、近所の馴染みの寿司屋の大将に来てもらって、大騒ぎしたそうです。上原謙は、大将が握った寿司を3人前くらいぺろりと食べていたとか。そのときに、著者が父親のために作曲したピアノコンチェルトを聴かせましたが、「親父は大よろこびさ。『お父さんは、第2楽章が好きだ』そう言ってくれた。第2楽章はスローなんだ。静かで気持ちのいいテンポになっている。当時は成城の家で一緒に暮らしていた。親父の部屋は離れで、ご機嫌で寝床に帰っていった。俺が見送ってね。部屋に入った親父は扉をしめた。でも、すぐにまた開けたんだ。どうしたのかと思ったら、幸せそうな顔で言ったんだよ。『ありがとう。バイバイ』息子の俺に頭を下げた。それが生きている親父の顔を見た最後になった」と述べます。
翌朝、婦人を連れて船で海に出た著者のもとにお手伝いさんから電話があり、「大旦那様が亡くなられました!」と告げられました。驚いて、葉山マリーナに船をつけて、家に向かいました。死因は急性心不全で、バスタブのなかで命が尽きていたそうです。82歳でした。著者は、「親父の最期、いい顔してたよ。苦しまなかったんだなと思った。安心したよ。いい旅立ちだったんだな。理想的な最期だよ。長患いすることはなく、介護もされず、前夜はみんなに祝ってもらって、ピアノコンチェルトの完成版を聴いて、馴染みの寿司をたらふく食べて、息子に『バイバイ』と言って翌朝コロリと逝った。俺が目指しているピンピンコロリだ。いや、パーフェクトだから、完全ピンコロだな」と述べています。
第四章「80代、まだまだ青春」の「桑田佳祐君、達郎君夫妻主催の80歳パーティー」では、著者は「山あり谷ありの芸能生活を経て、大借金や税金は10年で返済し、60代、70代はけっこう頑張ってきた。そして、俺の80代はブルーノート東京でのバースデー・パーティーからスタートした。桑田佳祐・原由子夫妻と、山下達郎・竹内まりや夫妻が、俺の誕生日を祝ってくれたんだ。あのときは子どもたちがおいしいものをご馳走してくれるっていうから、カミさんと一緒に腹をすかせて出かけていった」「桑田君、原坊(原由子)、達郎君、まりやちゃん、星野源君や歌手・水谷千重子として友近ちゃんもいた。桑田君や達郎君が『夜空の星』とか『蒼い星くず』、星野源君が『お嫁においで』を演奏してくれた。この日のために、みんな2日間もリハーサルをしてくれたらしい。最後は俺が『マイ・ウェイ』を歌った。いい夜だったな」と述べています。素晴らしい交友関係であり、著者がいかに後輩たちから慕われているかがわかりますね。
「桑田君の親と俺の親は麻雀仲間」では、著者と桑田佳祐とは実は長い付き合いになることが明かされます。桑田の父親はかつてパシフィックホテルの従業員で、ボウリング場で働いていたそうです。桑田もよくプレイしていたとか。だから、桑田佳祐はボウリングがうまく、一時期はプロボウラーになりたかったといいます。著者は、「サザンオールスターズや桑田君の曲の歌詞にもボウリングがよく出てくるだろ。その桑田君の父親とうちの親父は麻雀仲間だったんだ。よく打っていた。そんな関係だから、俺も桑田君がよちよち歩きのときから知っている。パシフィックホテルのプールで幼かったころの桑田君が遊んでいて、プールに落ちそうになるのを抱き上げたのが、彼と俺との出会いだ」と述べます。
「達郎君とは『BOOMERANG BABY』の縁」では、山下達郎が『COZY』というアルバムで、著者の曲である「BOOMERANG BABY」をカバーしていることが紹介されます。また、達郎夫人である竹内まりやを著者は光進丸に乗せたことがあるそうです。著者は、「さだまさし君や谷村新司君たち、ヤンチャーズのメンバーも、桑田君や達郎君も、俺とは世代が違う。彼らのような自分より若い人たちと一緒に歌ったり、演奏したりすると、感化されるよ。元気になるし、前向きになる。たくさんのことを与えてもらえる。いくつになっても、若い人たちといるべきだと思うな」と述べています。
また、坂本九の「上を向いて歩こう」は、コード進行にベートーヴェンの「皇帝」の影響を感じるという著者ですが、「そういう俺の『君といつまでも』もジャズのスタンダード・ナンバー『オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリート』をモチーフにつくっている。誰だって誰かの影響を受けて今があるんだよ。俺だって、ベートーヴェンやショパンの影響も受けているからね。長くミュージシャンをやっていると、1つや2つかは誰かの曲と似てしまう。好きな音楽は何度も聴いてインプットしているから、身体に染み込んでいて、自然とアウトプットしてしまう。それは、オレはリスペクトの1つのかたちだととらえている」と述べています。
「最後に歌うのは海の上」では、最後の紅白で、著者は「海 その愛」を歌ったことが紹介されます。著者が最初山をイメージしてつくったメロディに、岩谷時子が海の歌詞をつけてくれた曲です。 間奏のときに、著者は「音楽とともに歩んできて幸せいっぱいです! 本当にありがとうございます」と語りました。著者は、「2022年の大晦日で、コンサート歌手としての加山雄三は幕を下ろした。作曲家としては、今までに作った作品は539曲だ。親父はクラシック音楽のレコードを集めて聴くマニアだった。おふくろは流行歌のファンだった。それが俺のなかで混ざって、加山雄三特有の個性になったような気もする」と述べています。
第五章「今の俺、これからの俺」の「朝ご飯が夫婦の絆を強くする」では、特定の宗教を信仰していないことを明かして、著者は「だから、空に感謝する。自分たちをこの世に生んでくれた親父、おふくろ、じいさん、ばあさんにお礼を言う。お祈りを終えたら、おいしい朝ご飯だ。同じ食事を同じテーブルで、同じようにおいしいと思えるのは、とても大切だよな。幸せなことだ」と述べ、「自然には逆らっちゃいけない。謙虚にならなくちゃ、生きていかれない。台風が近づくと、海にものすごく大きな波が立つ。そんなものに人間はかなわない。よけいなことを考えなくなる。なにが起きても、じたばたしてもしかたがないという考えになっていくんだよ」と述べるのでした。
そして、最後に著者は「実際に溺れかけた人も何人も見てきた。戦争中には浜に打ち上げられた死体をいくつも引き上げてきた。その都度、交番のカガワさんに電話して来てもらったけれどね。泣いたってわめいたって、自然にはかなわない。運命にはかなわない。そう考えざるを得なくなった。俺たちの上には、手の届かない神の領域があるんだ。ずいぶん前に茅ケ崎を離れて、今は東京の街中で暮らしているけれど、子どものころに身体にしみた考え方はずっと変わらない。今は運命に逆らわないようにしながら、100歳を目指している」と述べるのでした。人間の寿命というのは天のみぞ知るものであり、「100歳まで生きると決めた」などというのは不遜な気がしますが、天下の若大将が言うのなら「仕方ねえなぁ!」とも思います。どうか、著者には少しでも長生きしていただきたいです。