- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2024.08.11
『偽史の帝国』藤巻一保著(アルタープレス)を読みました。「〝天皇の日本〟はいかにして創られたか」というサブタイトルがついています。著者は1952年北海道生まれ。作家・宗教研究家。中央大学文学部卒。雑誌・書籍編集者を経たのち、宗教を軸とした歴史・思想・文化に関する著述活動を行っています。東洋の神秘思想、近代新宗教におけるカルト的教義と運動に関する著作を数多く手がけています。本書は、宗教研究家である著者が、「天皇制」の根幹となった「明治以降、国民に浸透した日本史」の正体を明らかにする一冊です。歴史・宗教に関する幅広い知見、膨大な資料の裏付けによる、特に宗教史の面からの深く詳細な考察は、日本史関連の書籍に今までなかった”衝撃的な”内容となっています。近年類書の多い、「歴史修正主義」関連書籍の決定版といえるものとなっています。
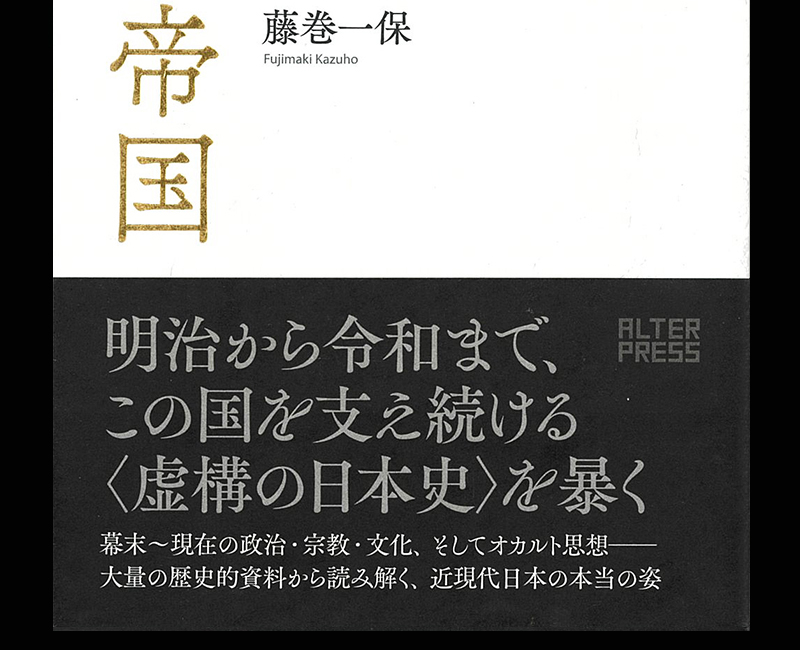 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「明治から令和まで、この国を支え続ける〈虚構の日本史〉を暴く」「幕末~現在の政治・宗教・文化、そしてオカルト思想――大量の歴史的資料から読み解く、近現代日本の本当の姿」と書かれています。帯の裏には、「近代日本人は、日本をどのような国だと思い込もうとしたのか。また、その思い込みは、日本をどこに連れていったのか」(本文より)と書かれています。
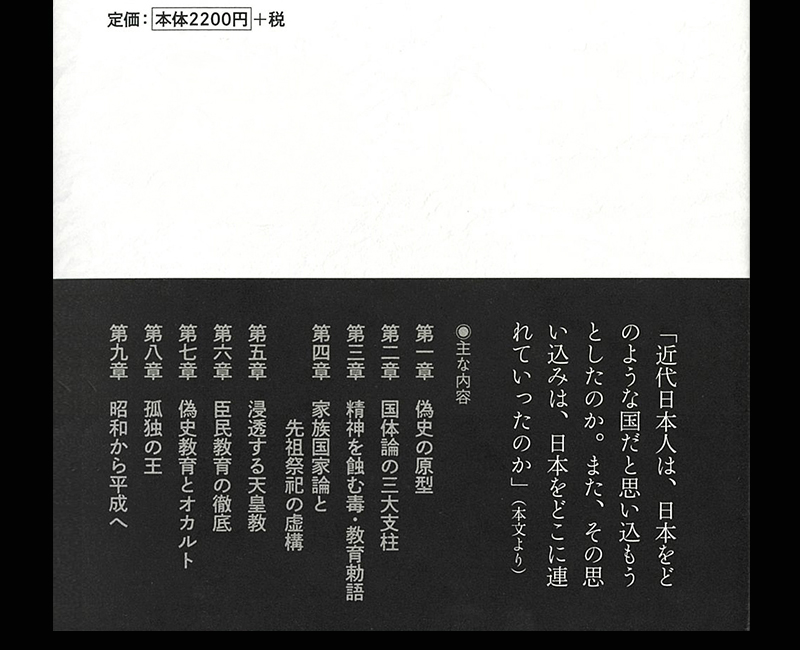 本書の帯の裏
本書の帯の裏
アマゾンの内容紹介には、以下のように書かれています。
「明治期、新たな統治体制を構築しようとした日本政府は、天皇を中心に据えた『偽の歴史(偽史)』を創作した。今なお日本の歴史に決定的な影響を与え続けるこの空想的な『偽史』は、いかにして出来上がり、浸透し、肥大していったのか 本書は、『国体論』『教育勅語』『家族国家論』などのキーワードを軸に、政治・文化・宗教、そしてオカルト思想に至る大量の歴史的資料をひもとき、『偽史』、そして近代日本の赤裸々な姿を明らかにする」と書かれています。
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
第一章 偽史の原型
第二章 国体論の三大支柱
第三章 精神を蝕む毒・教育勅語
第四章 家族国家論と先祖祭祀の虚構
第五章 浸透する天皇教
第六章 臣民教育の徹底
第七章 偽史教育とオカルト
第八章 孤独の王
第九章 昭和から平成へ
「蛇足として」
「はじめに」では、日本以外の国々の国体(国柄)は、その地に生きる人間がつくってきたものだと指導者層は言うとして、著者は「政治も、文化も、宗教も、多様な民族性も、みなその地に暮らす人々が地理的条件や歴史文化を通じてつくりあげてきた『人為』による構築物だが、日本だけはそうではない。日本は神がつくりだした『神為』の国であり、神の直系子孫である天皇の祖先が永遠の統治権と文化の種を授かって降臨し、天界の神とひとつになって惟神に治めてきた、地上に類例のない特別な国だと支配層は国民に教育しつづけた。日本は『神の国』であり『天皇の国』――これがこの国の指導者層のいう国体の中身なのである」と述べています。国体論には、それを支えるためにつくりだされた3本の太い柱があるといいます。大日本帝国憲法、教育勅語、国家神道です。著者によれば、この三大支柱は、幕末から明治中期までの国民教化の助走期間を経て、人々の意識の中に深く植えつけられ、偽史にもとづくまったく新しい「伝統」が、国の始まりからつづく不変の伝統と位置づけられました。
第一章「偽史の原型」の「妄想の始まり」では、偽史とは、実際にあった事柄や実在した人物、実際に起こった事件などの「史実」にもとづかない、創作された歴史を指すことが告げられます。歴史の解釈は多様ですから、その見方や史実の評価、解釈の違いなどによってさまざまな史観が成立します。けれどもどのような史観であれ、史実をベースに考えを組み立てるという研究の作法は同じです。同じ作法によって導き出されているからこそ、異なった立場同士の議論が成立し、理解が進んでいきます。けれども偽史は史実をベースとしないと指摘し、著者は「神話伝説や信仰から生み出された『物語』に、歴史のほうを従属させる。『こうでなければならない』という偽史制作者側の思い込みと都合が、自分たちには具合の悪い『事実はこうだった』を力でねじ伏せ、人々を『こうだったはずだ』の世界観や、『こうでなければならない』国家像、国民像へと引きずっていく」と述べています。
日本はなぜ「天皇の国」なのか。その理由として、明治以降の国家はこの天壌無窮の神勅を挙げてきました。天の主宰神である天照大神が、地上の主君として自分の孫を下界に送りこみ、彼に対して永遠に「治せ」と命じた。だから日本は、いかなる時代であっても天孫族の血を引く天皇によって治められなければならない国なのであり、天皇の統治と天皇の国の繁栄は、天地のつづくかぎり永遠に継続する(天壌無窮)としたのです。天の主宰神から「治せ」と命じられてはじまった“歴史”をもつ国は、日本以外のどこにも存在しません。
そこで文部省は、日本が「流転の世界に不易の道を知らしめ、漂える国家・民族に不動の依拠を与えて、国家・民族を基体とする一大家族世界を肇造する使命と実力とを有する」地上で唯一の国なのだと主張したのです。「一大家族世界を肇造する」とは、ばらばらになっている諸国・諸民族をひとつにまとめて救済し、平和な一大家族の世界を創出するということ。日本国と日本国民には、この「世界救済の歴史的使命」があるのです。だから国民は、おのれのもてるすべてを天皇と国に捧げ、聖なる使命達成のために働かねばならないというロジックは、戦時中、さかんに唱えつづけられた「八紘一宇」(全世界を一つ屋根の下に治めるの意)を言い換えたものにほかなりません。
「ルーツとしての国学」では、日本を「神国」とする意識は、外国や他民族との比較から生まれてくることが指摘されます。他国と比べ、我が国はこんなにすぐれているという意識が神国意識を生み出すのですが、日本の場合はその「すぐれている」根拠として、天の主宰神である天照大神の直系子孫が王として君臨してきたとする神話が利用されてきました。日本は神々が創造・守護し、天神直系の神裔(神の子孫)によって治められている特別な国だという意識が、長い歴史をつうじて支配層のうちで育まれてきたのです。
明治以降、さかんに唱えられるようになった神国思想のルーツとされるのは、天皇家がふたつに割れて王権を争った南北朝時代の南朝方公卿、北畠親房の『神皇正統記』です。その冒頭――「大日本は神国也、天祖[国常立尊ないし天御中主神]始めて基を開き、日神[天照大神]永く統を伝え給う。我国のみとの事あり、異朝にはその類なし、この故に神国と云う也」という文章は、江戸時代の国学者の命題となり、尊皇攘夷を掲げて倒幕に動いた維新の志士たちの思想的バックボーンとなりました。国学の源流となった思想界の巨人・本居宣長は、日本を「天照大御神の御本国、大御神の直系である皇統のしろしめす御国」と位置づけ、いかなる国も日本を尊び、「君主国とあがめ臣下となって服従」しなければならないと説いています。なぜなら日本は、「万の国の本、よろずの国の宗として存在している御国」だからです。
日本を大宗国とする思想は、「宣長没後の門人」を自称し、明治維新に絶大な影響を及ぼした平田篤胤に受け継がれました。篤胤によれば、万国を開いた「神代の尊い神々」は、みなまず日本に出現しました。だから日本こそが「神の御本国」にほかならないのです。日本と外国では、そもそもの国の成り立ちが違います。諸外国は、イザナギ・イザナミが海をかき回して大八洲国を生んだときの余波で、「潮の沫の凝り固まって成った」土地です。しかもその開拓は、両神の国生みからずっと後の時代に、大国主神と少彦名神が行いました。だから外国は「末つ国の枝葉の国」であり、枝葉の国であるがゆえに、日本の古伝(宣長のいう「まことの道」)が歪んだり誤った形で伝わっているのです。
「天皇万国総帝説」では、国学の巨人である本居宣長や平田篤胤は、いうまでもなく天皇を尊崇していたことが示されます。けれどもその尊崇はまだ比較的穏やかなもので、徳川将軍家による統治も、神々には深い考えがあってそのようにしているのだと肯定していました。ところが明治維新をはさむ前後になると、徳川政権の正統性はおおいに揺らぎ、天皇とそが唯一絶対の統治権者であり、日本のみならず世界を治めるべきだとする主張がなされるようになりました。その代表に、篤胤の門下の大国隆正がいます。明治維新は王政復古、神武創業への復帰という大方針のもとに行われましたが、この方針を岩倉具視に献策したのが、公家の西園寺家末流の出身で真言僧から還俗していた玉松操で、玉松の国学上の師にあたるのが大国隆正でした。
大国は天皇を世界の「総王」として、徳川将軍家の上に置きました。著書『文武虚実論提要』の2年後に成った『直毘霊補註』でも、「天皇のみが真天子であり、支那の国王は堯や舜をはじめ、みな偽天子」だと述べ、同年の『本学挙要』においても諸外国は「世界の総主」である天皇に「朝貢」し、「天皇の臣下としてわが朝廷の官爵を受ける」べきだと唱えています。大国のこの主張を「天皇万国総帝説」といいます。天皇はなぜ世界の総主・総帝なのか。大国の主張の根拠も、宣長と同じく天壌無窮の神勅に置かれているのです。
大国は、本居のいう「天照大神の本国」たる日本以外の海外諸国も、ナギ・ナミ両神が創り出したものだと断言しました。国生みの際、不具の子として生まれ、海に流されたと『古事記』に伝えられる「ヒルコ」こそが、諸外国のルーツだというのです。著者は、「こうして、本来は日本を指していた『葦原の千五百秋の瑞穂の国』は、ヒルコの領域――海外全域にまで拡大され、地球全土を意味するものとなった。昭和になって軍部と政官界が熱心に唱えだした『八紘一宇』の八紘(全世界)が、すでに明治維新の時点で、ヒルコの拡大解釈を介して偽史に取りとまれていることを、大国の文章は証している」と述べます。
大国のこれらの思想は、特に珍しいものではないといいます。尊王論で知られた水戸学の会沢正志斎は、吉田松陰ら勤王論者に絶大な影響を与えた幕末の思想的指導者の一人ですが、彼もまた「神国日本は……日の神の御子孫たる天皇が世々皇位につきたもうて永久にかわることのない国柄である。本来おのずからに世界の頭首の地位に君臨し、天皇の御威徳の及ぶところは遠近にかかわりなかるべきものである」と、同様の主張をなしています。著者は、「自分たちの国、自分たち民族や文化を高みにおいて、他の国家や民族を低級視し、自分たちに従べきものとする思想を、エスノセントリズム(自民族中心主義)という。江戸後期から幕末にかけて、国学者はこのエスノセントリズムを猛烈に肥大させていった」と述べます。
欧米諸外国からの現実的な脅威とはまだ縁遠かった本居宣長や平田篤胤のエスノセントリズムは、おもにインドの仏教や中国の儒教など、アジアの外来思想や文化に向けられていました。ところが外国船が押し寄せ、かつて見たこともない欧米列強の巨大文明と対峙せざるをえなくなった幕末になると、対象は一気に世界規模に広がりました。その結果、天皇が神から授けられた特別な権威の及ぶべき範囲も世界規模に拡大され、「葦原の千五百秋の瑞穂の国」が、日本から世界へとバージョンアップされたのです。
「岩倉具視の国体思想」では、岩倉具視が「国体」と「政体」をはっきり区分けしていることが紹介されます。岩倉にとっての「国体」とは、天祖がイザナギ・イザナミに命じてこの国土を創造させ、その地に天孫を降臨させて永遠に統治させることを定めて以来の、不変不動の国の在りようと理解されています。著者は、「『皇統一系』が神定めに定められた特別な国柄ということだ。一方、『政体』とは、皇統一系の国体のもとで運営される政治のありようをいう。トップの天皇は未来永劫にわたって不動だが、その下の政権は、時代の状況に応じて変化していく。不変不動の国体のもと、政体が状況に応じて変化していくのであって、政体が国体を左右することはありえない。日本という国は、必ず国体あっての政体でなければならないと岩倉は主張した。この観念が、以後の国家思想の骨格となり、今日にいたるまで影響力を保持しつづけるナショナリズムの根本思想となるのである」と述べています。
維新前の岩倉は、「天孫神聖清浄の神州」である日本に対し、諸外国は「醜虜犬羊糞土の域」だと蔑んでいました。諸外国を「末つ国の枝葉の国」と見下すエスノセントリズムの典型的な視線が、ここに認められます。けれども明治4年から6年にかけて欧米諸国を視察し、そのあまりにも豊かで強大な文明に激しいカルチャーショックを受けたのち、岩倉は「外国の富強強大なるは我が皇国の比に非ず」と率直に認識を改め、いま最も重視し、急いで施策を打たなければならないのは「外国交際」だと主張するようになったといいます。
政府は急ピッチで欧化政策を進めました。その結果、出現した極端な西欧文化模倣の一時期(明治10年代末~20年代初頭)を鹿鳴館時代といいます。政府高官らは競って西欧の文化をとりいれ、洋装で着飾って、舞踏会や演奏会などを催しました。著者は、「こうした時代の空気のなかで、欧化主義に反撥し、強く日本回帰を求める国粋主義が、明治の中頃から勃興する。時を同じくして発布されたのが、天皇の絶対的な権限と権威を法制化した大日本帝国憲法(明治22年)、および国民教育の指針となる教育勅語(同23年)だった」と述べるのでした。
「国体論をめぐる論争と福澤諭吉」では、福澤諭吉も開明的な意見を表明していたことが紹介されます。保守論者は、『古事記』や『日本書紀』の神代記などを根拠に、天皇の主権はわが国はじまって以来の伝統であると位置付け、「今の日本国民が帝室[皇室]を奉戴する[君主としていただく]ことは、あたかも唯その旧恩に報ずる義務」のように主張していますが、そうした意見は「維新前の古勤皇の臭気を帯び」た旧説にすぎないといいます。今日帝室が最重視されている理由は、天皇が「人心収攬[人の心をとらえる]の中心となりて、以て社会の安寧を維持」しているからだというのです。
政府が人民統治のために創作したイデオロギーを、福澤は「偽」とし、「侫」と断じて一刀両断します。「聖明の天子」とは、たとえば天下万民のために暴君を倒して新たな王朝を開いた殷の湯王や周の武王、民家の竈から煙が上がらないのを見て生活の苦しさを察し、3年間租税を免除したと伝えられる仁徳天皇らのような王を指すのですが、これらの王を挙げたうえで、福澤はそれらの伝承をきっぱりと否定するのです。著書は、「福澤は、一方では天皇家の長大な歴史と伝統を敬い、また国民の求心力の中心という役割を肯定はした。神憑り的な虚構まみれの天皇信仰を否定したのである」と述べます。
「植木枝盛の神武天皇賊王論」では、言論を厳しく抑圧するための法律がすでに明治の時点でつくりだされていることが指摘されます。世間で最もよく知られている不敬罪も、明治15年に施行されました。天皇・三后・皇太子・皇陵に対する不敬は3月以上5年以下の重禁固と罪金、皇族への不敬は2月以上4年以下の重禁固と罪金が定められ、しかもこの罪に関しては「公然性」という要件が除かれました。こっそり不敬の言葉を日記に書きつけただけでも、見つかれば犯罪となります。つまり不敬罪は、国民の内心にまで土足で踏みこんで処罰できる法律として登場したのであるとして、著者は「これらの法律や活動の絶対的な基軸となったのは、『万世一系の国体』『国体あっての人民』という明治維新以来、着々と進められてきた国体イデオロギーにほかならない。このイデオロギーの、いわばエンジンとなったのが帝国憲法であり、教育勅語であり、国家神道なのである」と述べるのでした。
第二章「国体論の三大支柱」の「国体論の支柱としての憲法」では、明治憲法は、為政者が国民に定着させなければならないと考えていた天皇の絶対性や神聖不可侵性を巧みに法文化しましたが、そこでイメージ付けされた天皇像は、あくまで国民向けの表看板であって、実態ではないことが指摘されます。天皇の実態は、“薩長幕府”によって担がれた神輿の扉の奥に祀りこまれた、国民からは絶対にのぞくことのできない秘密の御神体にほかならないとして、著者は「その人は、生きて現実を動かす統治権者ではない。この神輿を担ぎ回って国民に天皇信仰を強制し、実際に国政を担ったのは、伊藤ら明治国家の創作者たちなのである。久野収と鶴見俊輔がその共著で天皇制国家を『みごとな芸術作品』と呼んだとおり、伊藤はこの仕事をほとんど完璧に成し遂げた。しかしこの『作品』は、あまりにもみごとにできすぎた。伊藤らがうまくやりすぎたといってもよい。あまりにもうまくやりすぎたがために、天皇信仰そのものが為政者のコントロールから離れて、幽鬼のように一人歩きするにいたるからである」と述べています。
「神道と祭政一致」では、明治以降、国家の管理と保護のもと国教的な性格を与えられ、天皇信仰の中軸をになった神社神道を「国家神道」ということが紹介されます。国家神道という呼称そのものは、政府や神道サイドが自称したものではありません。戦後GHQ(連合国最高司令官総司令部)が使った「ステート・シントウ」の訳語として一般化したものですが、その性格はまさしく「国家の神道」に合致しているといいます。著者は、「明治の神道には、国家神道とは別に国家から公認を受けた神道十三派があり、教派神道と総称されているが、教派神道の天皇崇拝や祭祀は、それぞれの教団の信仰や教義にもとづく私的なもので、国家が公的な天皇崇拝・祭祀と位置づけて強力にバックアップした国家神道とは異なる。国家神道は、国家権力が長い歴史をもつ神社神道を天皇信仰のイデオロギー一色によって再編し、祭祀を整備し、神社役員の人事権まで掌握したうえで新たにつくりだした、明治生まれの神道なのである」と述べます。
祭政一致は宗教と政治が未分化だった古代世界で広くおこなわれていた政治形態で、古王国時代のエジプト、シュメール、古代ギリシアなど数多くの地域で類似信仰が認められます。政治と祭祀が未分化の古代社会にあっては、共同体の首長がしばしば神の名において祭祀と政治の両権能を握ったからです。日本でも、邪馬台国の女王・卑弥呼のケースに明らかなように、祭政一致による国の運営が行われてきたことは確実で、オオキミと呼ばれた時代の天皇家も、日本各地の豪族と同様、古代的な祭一致の政治形態を取っていたらしいことは、記紀神話や考古学の知見などから窺うことができます。ただし、維新後に唱えられるようになった祭政一致は、古代世界で行われていた史実としての祭政一致ではないとして、著者は「当時の国学者や神道家らが“妄想”したのは、天孫降臨の時点から高天原の神々によって定められた、他に代替のきかない、万世一系の天孫の血筋にのみ課せられている、世界で唯一無二の、惟神(神とともに為される神そのもののおこない)によるマツリゴト(祭事であり同時に政事)――という意味だ。彼らが自分たちの神道を『かんながらの道』や『惟神神道』と呼んだ理由もここにある」と述べます。
「国教化に突き進む神社神道」では、明治の祭政一致論は、他国・他民族を劣等視するエスノセントリズムと一体化した国学・神道思想から生じたことが指摘されます。そのため、神道以外の宗教は、皇国本然の姿を損ねる不正で異質な、また神智ではなく人智によってこねあげられたさかしらな教えと見なされ、排斥の対象となりました。その代表として糾弾されたのが、本居宣長や平田篤胤らが口を極めて批判し、否定した仏教で、まっさきに神社から追い出されました。他にも諸宗や民間呪術信仰などが混淆して生まれた修験道、密教系の習合神道、日蓮系の法華神道、密教から理論を借りて創作された吉田神道、陰陽道、天社土御門神道、民間巫覡などが次々整理や粛正の対象となりました。
寺社に関する法令は、明治初年から矢継ぎ早に連発されています。初年だけを見ても、3月13日に「祭政一致の制に復し、天下の諸神社を神祇官に所属せしむ」ことが布告され、その月のうちに「切支丹邪宗門」に対する禁制や、神仏分離令が発令されました。4月から閏4月にかけては、神社の神々につけられていた菩薩号が廃され、古代から神社や神社系列寺院の管理を担ってきた別当・社僧に対する還俗命令も発せられました。注目されるのは神職の葬式だとして、著者は「それまで僧侶に委ねられてきた神職やその家族等の葬儀は、以後、すべて神葬式(神道による葬儀)に改めよという達しが、元年閏4月19日、新設まもない神祇事務局から出されている」と述べます。
政府は神道に突出した優位性を与えるための諸政策を、矢継ぎばやに推進していきました。その極めつけが、明治4年5月14日の太政官布告第234号です。天皇の祖神を祀る伊勢神宮をすべての神社の頂点として、神社界全体のヒエラルキーを確定し、全神社を国家の管理下に置くための施策で、この布告により全国神社の社格が定められました。著者は、「この施策により、全神社は官社と諸社に二分された。『官』すなわち国家が管理する『社』である官社は、神祇官が祀る官幣社と、地方官が祀る国幣社の総称で、それぞれ大・中・小の社格に分類整理され、ともに神祇官の管領下に置かれた。官社のうちの官幣社には、祈年祭・新嘗祭・例祭ごとに皇室から神への供物(幣帛)が供進され、国幣社に対しても祈年祭と新嘗祭ごとに皇室から幣帛供進されたが、例祭には国庫から幣帛料供進される点が異なった。国家に帰属する官社が皇室や国庫から幣帛や幣帛料を受け、神祇官の管理のもとに祭祀がおこなわれるということは、その祭祀が国家の祭祀であることを示している。この制度によって、神社神道は事実上、日本の国教となったのである」と述べるのでした。
寺の最大利権は葬儀や年忌法要など「死穢」にかかわる法事ですが、政府はこれについてもメスを入れようとしました。明治元年に、神職家の葬式は仏式ではなく神道式の神葬式にせよという布達が出ましたが、5年になるとさらに徹底した指示が出されました。「従来、神官は葬儀には関係しないことになっていたが、これからは氏子などから神葬祭の依頼を受けたときは、神官が喪主を助けて葬儀を取り扱うようにせよ」と命じたのです。著者は、「皇室の神道も神社神道も、古代から一貫して死を忌避してきた。人間や動物の死体には穢れが発生するとみなして、穢れが清まるまでの一定期間は、公の場所に顔を出し、他者と交わったり仕事などをしてはならないと規制してきた。この伝統的なルールを、政府は自分たちの都合のために、いともたやすく否定したのである」と述べます。ただし、この神葬祭取扱は、明治15年に再び禁止となります。
「信教の自由と神社非宗教論」では、明治政府は、「『天皇教』ともいうべき国家的イデオロギーそのものを信仰内容とする『新たな宗教』」、すなわち国策によって新たにつくりだされた明治生まれの神道に、一律的に国民を取りこむことをめざしたことが指摘されます。神道が年を追うごとに国教化されていく状況に対する危機感から、島地黙雷ら仏教者は「信教の自由」と「政教分離」の論陣を張って対抗しました。何を信仰するかはあくまで個人の自由に任すべきで、国家が権力にものをいわせて強制すべきものではないと主張し、神道を国家の紐付きにしている政教一致の体制を改めて、神道を政治から切り離すべきだと主張したのです。著者は、「この主張は、仏教者のみならず一部の知識人やジャーナリズムのあいだでも支持され、木戸孝允を始めとする政府首脳の一部まで、認識を共有したというから、無視できない世論が形成されていったとみてよい」と述べています。
神社神道は、先祖に対して子孫が行ってきた、また当然行うべき祭祀儀礼であって、信仰の有無とはいっさい関係がありません。著者は、「先祖がいたから子孫が存在する。信仰の有無で先祖がいたりいなかったりするものではない。阿弥陀仏を信仰しようがキリストを信仰しようが、いかなる信仰者であろうとも先祖は存在し、祖神が存在する。その先祖・祖神に対する「忠孝」の表現が神社神道の祭祀なのであり、これは日本がはじまったときから皇祖神によって定められた忠孝の道そのものだ。だから宗旨のいかんにかかわらず、日本人は必ず神道を踏みおこなわねばならない――明治国家はこんな理屈を立てて、国民に神社神道の受け入れと奉祀、つまりは国民こぞっての天皇信仰を強制した。これこそが国家神道の狙いだったのである」と述べます。
「祭祀と宗教の分離」では、「大日本帝国憲法」「国家神道」という国体論の2本の柱が確立した翌23年、国体論を支えるもう1本の柱である「教育勅語」が渙発されたことが紹介されます。著者は、「日本を、天皇による天皇のための国家と位置づけた帝国憲法が公布され、非宗教という立場から国民の宗教心を事実上支配する地位についた国家神道が確立し、臣民道そのものといってよい忠孝道を規定した教育勅語が渙発されたことにより、偽史の骨格を形成する国体の三本柱が、ここに完全に出そろったのである」と述べるのでした。
第三章「精神を蝕む毒・教育勅語」の「教育勅語批判と礼賛」の冒頭には、「国体の3本柱は、前章で述べた大日本帝国憲法、教育勅語、国家神道の三者だが、社会的な影響力という点で最も大きな働きをしたのは教育勅語だ」と書かれています。大国・清を倒したという事実は、日本人をすっかり舞いあがらせました。民衆は、この戦勝によって世界に比類のない日本国体の偉大さが世界に示されたと受け止めました。また、マスコミが書きたてる日本兵の忠勇無比の働きは、まさしく教育勅語が教えている「義勇公に奉じ、以て天壌無窮の皇運を扶翼」するものと理解され、絶賛されました。著者は、「教育勅語は、いまや日本人の無上の規範へと価値を高めていったのである」と述べています。
「勅語の宣伝者たち」では、長年月にわたる教育・洗脳の成果で、天皇にかかわることがらや言葉に、ただちに国民を思考停止の“金縛り”にしてしまう強い力が宿ったと指摘します。「天皇」という金縛りは社会全体にかけられ、その象徴が、御真影であり教育勅語だったというのです。著者は、「役人や御用学者らが『方便』『御守』としてことあるごとに駆使した言葉は、ほかにもある。官制イデオロギーそのものである皇国、国体、家族国家、伊勢神宮、天壌無窮の神勅、八紘一宇などの言説は、いずれも同様の方便・御守として権力者側がたくみに利用し続けました。
これらの言説を誹謗中傷すれば、ただちに不敬罪をはじめとする弾圧のための諸法令が発動された。単一民族、単一文化(日本文化の源流は天皇家で天皇家の文化の源流は高天原)、単一祖先(日本国民はすべて天皇家の分家)、単一言語(神由来の特別な“言霊”言語)など単一性を強調した術語も、その列に加えて考えてよいだろう。いずれも史的・科学的根拠をもたない完全なフィクションだが、戦前まではしばしば事実として強調された」と述べるのでした。
第四章「家族国家論と先祖祭祀の虚構」の「家族国家論という虚構」では、天皇家を日本国の本家、すべての国民を天皇家の分家とし、日本は創始の時点から「一大家族国家」だったとする官制のフィクションを「家族国家論」ということが紹介されます。明治の旧民法は、戸主への権力集中を制度化し、祖先の資産と祭祀は戸主(イエの統率者)のみが相続し、戸主権は長男が単独相続するものと規定しました。戸主にすべてを受け継ぐ権利を与えたのです。戸主には、ほかにも数々の権利が与えられました。家族員の住まいを指定する権利や、家族員の婚姻・養子縁組に対する同意権も戸主の専権とし、戸主の同意なしで婚姻や養子縁組をおこなった場合の離籍権(イエから排除する権利)も戸主に帰属させました。
現在の憲法は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると定めていますが、旧民法時代の婚姻は「イエとイエとの契約」であって、「個人と個人の契約」ではありません。戸主の同意なしに婚姻が成立しないのはそのためです。婚姻とは、新婦が「婚家のルール(これは歴代戸主のルールと同義語だ)に従属します、婚家の祖霊に仕えます」と誓う一種の奴隷契約にほかならないと指摘し、著者は「無償の労働奉仕や妊娠・出産は嫁の絶対的な義務と見なされ、強制される。にもかかわらず、彼女は法律的には『無能力者』で、なんらの権利も持たない。貞操義務を課せられているのも妻だけだ。妻の浮気は姦通罪となるが、夫の浮気は刑法の対象にはならない。財力等が許せば、夫は妾を複数もってもなんら問題ない」と述べます。
このように、明治民法は男(夫・戸主)の権利を最大限に広げる一方、女(妻・家族員)の権利を極限まで限定しました。彼女たちは、夫とイエに奉仕し、子を生むための道具にほかなりませんでした。田畑や牛馬と同じように、何よりもまず「生産性」が求められたのです。他方、男の権利のほとんどは、戸主に集中されました。イエにおける絶対権者である戸主は、イエというミニマム国家における“小さな天皇”であり、戸主に従属するイエの構成員(妻子や兄弟姉妹や使用人など)は、労働力などを提供して戸主に奉仕し、イエ存続のために働く、ミニマム国家における最小単位の“臣民”にほかならなかったのです。
明治以来、天皇と国民を固く結びつけようと腐心してきた政府は、イエ制度においても、忠孝論を最大限に活用しました。その理屈によれば、戸主とそれ以外の家族員は、戸主に対する家族員の「孝」によって結ばれており、同時にすべての戸主は、日本国民の“総本家”である天皇と、「忠」によって結ばれています。本家であり全国民の親である天皇は、分家であり自分の赤子である国民(戸主とその家族員全体)を慈しみ、彼らの忠に応えて恵みを施す。同じように、各イエの戸主は、家族員の自分に対する孝に応えて、扶養その他の恵みを施します。著者は、「これが太古以来の変わらぬ家族国家・日本の伝統であり、諸外国では決して見ることのできない、世界に冠たる日本の国体そのものだ――こんな不気味なフィクションが、明治以降くりかえし語られつづけ、今日にいたってもなお一部でその復活が執拗に求められている“伝統的”な家族像の中身なのである」と述べます。
「国家神道と家族国家論」では、家族国家論は明治政府が生みだした新たな国教――国家神道にとっても、まことに好都合な理論として活用されたことが指摘されます。著者は、「神道家をはじめとするウルトラナショナリストらは、忠孝の精神が、あたかもDNAのように親から子へとうけつがれると主張した。この遺伝的継承を過去に遡っていくと、ついには天孫ニニギ尊とともに高天原から地に降り、さまざまな氏族の祖神となったお伴の神々へと行きつく。それら天津神や、天孫に帰服した土着の国津神から伝えられつづけてきた忠孝“伝統”を、氏族らが具体的な祭儀として表現したものが、神社神道における氏神祭祀であり、各イエにおける祖先祭祀だと位置づけたのである」と述べています。
「先祖祭祀のルーツをめぐる虚構」では、人類が死者に対する祭祀を行いはじめた理由のひとつに、死者の蘇りや祟り、死者がもたらすかもしれない自然災害、さまざまな不幸などに対する原始的な恐怖感情があったことが指摘されます。死者の国を、血や膿や腐敗などで穢れ、まがまがしい悪鬼邪霊がうごめいている恐ろしい場所とする観念は、イザナギが黄泉国の妻イザナミを訪ねて逃げ帰ったとする『古事記』の一シーンに明瞭に描かれているとおりであり、考古学の方面でも遺体の手足を折り曲げて葬る屈葬墓の研究などで、早くから指摘されてきたというのです。著者は、「神への祭祀の背景のひとつに『祟る神』への恐怖があったことは、疑う余地がない。なにより官撰史書等に見られる数多くの記事が、それを証明している。天照大神を『祟る神』と見なした記録も、現に存在している。ところが家族国家論のなかでは、こうした不都合な事実は黙殺され、あるいは改変された」と述べます。
「天皇家の先祖祭祀」では、たとえやんごとなき天皇や皇族であっても、亡くなれば死穢を帯びるし、触れれば穢れに感染する――明治維新で天皇像の全面的な書き換えがおこなわれる以前、死という万人平等の局面では、天皇も庶人も同じだったとして、著者は「ともに死穢を帯び、仏の救済を必要としている亡者の一人であることに変わりはなかった。だから朝廷では、あたりまえのように成仏を祈念しての供養や年忌法要、各種の法事がおこなわれていたし、天皇の寝所の隣には、守護仏である観世音菩薩が祀られてきた。それが平安時代からつづく宮中の伝統だった」と述べています。
朝廷の祭祀を掌る神道は、穢れを徹底的に遠ざけてきました。そのため死穢にかかわる祭祀に神道はタッチしないのが大原則であり、死の穢れに感染した者は、神社への参拝も神事への参加もできず、30日間の謹慎というのが『延喜式』の定めでした。この触穢の思想があったからこそ、死穢と接触する宗教儀礼の主要な部分はすべて仏教が受けもち、一部を陰陽道がになう体制が守られてきたのです。天皇家の葬儀が山陵への土葬による神葬から、火葬を用いる仏式に変わり、ついには墓そのものまで寺院の管理となったのもそのためでした。
「明治政府がつくりだした新たな伝統」では、山陵を神宮に準じるものとして扱うことに言及します。これは山陵の被葬者を、仏教式の供養が必要な「ホトケ」ではなく、伊勢神宮の皇祖神と同じような「カミ」として遇するということです。それは同時に、山陵を、全国民がこぞって崇敬し、忠義を尽くさねばならない「生き通しの神の鎮まる神社」の一種へと新生させることを意味します。著者は、「これこそが『神国日本』の正しい姿であり、『神武創業』の祭政一致時代に復古する明治の聖代にふさわしい――明治政府はこの方針に基づいて宗教・教育政策を強力に推進し、伝統の根本的な統廃合を断行した。このときから、過去の天皇霊は、ホトケではなくカミとして、国民の前に立ち現れることとなった」と述べます。
そもそも明治という新時代が生まれた時点で、わが国には天皇家の宗教施設の頂点をなすと考えられている「宮中三殿」そのものがありませんでした。天照大神の形代(神霊の代替物とされる象徴物で、それ自体に霊異が宿ると考えられた)とされる神鏡のレプリカを祀る「賢所」だけは、古代から宮中に存在しました。しかし、歴代天皇霊を祀る「皇霊殿」と、天皇家の守護神である宮中八神および天地やおよろずの神々を祀る「神殿」は存在せず、この三者が宮中三殿として揃ったのは明治5年のことなのです。他方、歴代天皇の霊牌(位牌)や念持仏などを祀る仏教にもとづく宮中施設は、平安時代の光孝天皇(在位884~887年)のときから清涼殿内に設けられ、近世まで絶えることなく受け継がれてきました。「御黒戸」(黒戸御殿)と呼ばれる持仏堂がそれです。
御黒戸は、常には女官が管理したが、天皇自身がなかに入って念仏を唱えたり、天皇の命に依って加持祈禱などの修法が行われました。称光天皇や後土御門天皇のように、御黒戸で崩御した天皇もいます。歴代天皇の霊牌のほか、彼らが守護仏として信仰してきた念持仏も御黒戸に祀られており、歴代天皇によってそれらが拝まれ、供養されてきたという事実は、明治になって書き改められる以前の天皇の死後の姿が、「カミ」ではなく「ホトケ」と見なされていたことを何より雄弁に物語っています。
明治の開始とともに、山陵に鎮まる歴代天皇霊は「ホトケ」から「カミ」へと姿を変えた。山陵を舞台とする国家祭祀や、天皇による山陵親拝も、新たに開始された。國學院大學教授の武田秀章は、この新しい事態の意味を、「神武創業を存立の根拠とした維新政府にとって、山陵・皇霊への祭祀は、いわば政権存立の根幹にかかわる国家祭祀だったのであり、それは天皇の山陵行幸・宮中への皇霊鎮祭という前代未聞の新儀を実現するまでに進展したのである。(傍点は引用者)」と、的確に表現しています。
家族国家論は「国家と家という異質の制度」を「天皇と民衆の先祖を媒介することによって接合」したものにほかなりません。民衆が長い歴史の中で培ってきた多様な宗教観を、政府が強権によって取り払い、明治生まれの“天皇教”に合致するように平準化した「官制の先祖崇拝」――それこそが明治新制の家族国家論なのであるといいます。著者は、「この思想によって、親や先祖への『孝』と、天皇への『忠』はひとつに縒り合わせられた。天皇と国家にひたすら忠誠を尽くすことを求めるために編み出された、明治生まれのこの壮大なフィクションは、日清・日露戦争の勝利によって、大衆層に深々と根をおろすこととなる」と述べるのでした。
第六章「臣民教育の徹底」の「『国体の本義』の発行」では、忠孝一本、忠君愛国、家族国家、祖孫一体など、明治から国家が営々と積みあげてきた偽史のピースを網羅し、猛然と進められている日本ファシズム化の正統性を謳いあげた「家畜の忠誠心」の集大成ともいうべきプロパガンダ本を文部省が出版したのは、昭和12年5月のことだと紹介。書名を『国体の本義』といいます。『国体の本義』の配布にあたり、文部省はこの本を小学校の修身、国史、地理、国語などの授業に活用するよう指示し、中等学校、高等学校、専門学校に対しても、国体にかかわる授業では本書の趣旨をしっかり教えるようにと通達しました。著者は、「洗脳の対象は、学童や生徒だけではなかった。教える側の教師に対しても、『国体の本義』精神の徹底が図られた。昭和7年、文部省は左翼思想の排除、国体明徴、日本精神の植えつけを目的として、道府県に直轄の国民精神文化講習所を設置していた」と述べています。
『国体の本義』の講習の対象は全国の教職員のほか、青少年団指導者、青年訓練所職員らもふくまれており、「銃後の戦士」たる青少年を育てるにふさわしい忠君愛国精神に燃える指導者の涵養が狙いでしたが、この講習所における主要テキストとしても、『国体の本義』が用いられたのです。さらに巧妙な策も講じられました。本書が全国の高等学校、専門学校、大学予科、各府県の師範学校の入学試験、文部省中等教員試験検定、各府県小学校教員試験検定の試験問題として出題されるようになったため、入試や検定試験にかかわるすべての者は、好むと好まざるとにかかわらず、本書を学ばざるをえなくなったのです。著者は、「この“洗脳テキスト”とあわせ文部省は『国体の本義解説叢書』を矢継ぎばやに刊行し、教育勅語のときと同様、商機に便乗した御用学者と出版人による解説本が次々と刊行された。国民に徹底した『家畜の忠誠心』を求める『国体の本義』は、たちまち時代の思潮となり、かつてないほどに強く国民の心を縛る方向へと進んだのである」と述べるのでした。
第七章「偽史教育とオカルト」では、「八紘一宇」に言及します。八紘一宇とは、世界をひとつ屋根の下に治めるという神武天皇の詔を指します。八紘は、本来は神武が征服しようとした日本全体のことをさした言葉と考えるのが自然ですが、明治以降の国家主義の進展とともに、八紘は日本ではなく世界の意味に変わり、全世界をひとつ屋根の下に治めることと主張されるようになりました。「国是となった八紘一宇」では、八紘一宇が政府の公式見解となったのは第二次近衛内閣による「基本国策要綱」(昭和15年)からだと紹介します。同要綱は大東亜新秩序の建設を謳っていますが、その中で政府は「皇国の国是は八紘を一宇とする肇国の大精神に基」づくと明記しました。ここにいたるまでも唱えつづけられてはきましたが、大東亜戦争直前の昭和15年以降、八紘一宇は国家によって確定された施政方針、すなわち「国是」となったのです。
八紘一宇の第一段階としてさかんに唱えられた「大東亜共栄圏」も、第二次近衛内閣の松岡洋右外相が昭和15年に記者らの前で語ってから、広く用いられるようになった言葉です。その理屈は、「八紘一宇の世界一家体制」を建設するのが日本の使命だというところにあるとして、著者は「家族国家論は、ほんらい日本における君民の関係をしっかりと固定するために創作されたものであり、一部のエキセントリックな狂信者を除けば、海外までふくむものではなかった。ところが昭和の軍閥政治は、それを世界規模に拡大した。八紘一宇と忠孝一本論を国民に徹底して刷りこむための仕掛けは、昭和12年8月の第一次近衛内閣による『国民精神総動員実施要綱』によって、すでに公に実現されている」と述べます。
「『竹内文書』と『神日本運動』」では、官製偽史が民間に及ぼした影響には甚大なものがあったと指摘します。その典型として、官製偽史を極限までエスカレートさせた弁護士・中里義美による「神日本運動」が取り上げられます。中里は政界や軍部など国家の支配層に数々のパイプをもっており、小磯国昭とも親密な関係にありました。昭和10年代の狂信的な精神情況を濃縮した運動体が、中里の創設にかかる神乃日本社なのです。中里によれば、天皇は日本に限定されたローカルな王ではなく、世界天皇なのだから、その赤子である日本人には、全世界を天皇信仰に導く使命があるといいます。その使命の具体的な内容が、「世界の廃藩置県」です。世界の指導者に土地と人民を奉還させ(廃藩)、天皇が改めて世界統治の体制を定める(置県)という意味で、つまりは八紘一宇にほかなりません。
『日本書紀』に伝えられる天壌無窮の神勅を、国家は神代の「歴史的事象」と位置づけ、国体の根拠としてきました。けれども中国やエジプトなど日本よりはるかに古い歴史と文化伝統をもつ国とくらべるとき、『古事記』や『日本書紀』は成立があまりにも新しく、なおかつそこに記されている神武紀元以来の歴史そのものが、世界の親国と称するにはあまりにも短くみすぼらしいとして、著者は「神が最初の国として創造したはずの日本が、そんなに短い歴史の国、みすぼらしい文化の国であるはずはない――この思い込みがエスカレートし、ついに記紀は日本のほんとうの歴史を覆い隠すために編まれた偽物の史書だと、彼らは見なすにいたった」と述べます。
中黒が真実の歴史を伝えるものだと力説する「諸古文献乃至古蹟」とは、『竹内文献』『富士宮下文書』『ウエツフミ』などの偽書類や、「国史に目覚めたる憂国の士」らによって「発見」されつつある太古日本の祭祀遺跡、神代の神宝、日本のピラミッド遺跡、朝鮮におけるスサノオの古蹟(曾尸茂梨)、世界各地で発見されている数々の未解読文字(『竹内文献』はそれらの文字を記紀以前の歴代天皇によって創作された「神代文字」だとする)などを指すといいます。
「天皇のふたつの顔」では、国家はなぜ左翼ではなく右翼に属する彼らを監視したのかが考察されます。異様なまでに高揚した天皇絶対主義がエスカレートすれば、記紀を正史とし、記紀神話を国体の軸としてつくりあげられた偽史国家体制そのものの変革や否定の運動と結びつく可能性があったからであるとして、著者は「伊藤博文らが創造した明治国家においては、天皇はたしかに政治的権力と精神的権威をあわせ絶対者として祭られてきた。けれどもそれは、あくまで一般国民に向けた表向きの天皇の権力・権威であって、実際には天皇がみずからの意思により自由に権力を行使することなど、まったくできない仕組がつくられていた」と述べています。
天皇の実質的権力を、補弼機関の担当者が「ほとんど全面的に分割し、代行するシステム」は、けれども昭和にいたって大きなほころびをみせはじめました。著者は、「社会が抱える数々の巨大な矛盾、絶望的なまでに進行している政治や経済などの行き詰まりを一挙に解消する解決法として、それまで天皇と臣民のあいだを遮断し、数々の権益を享受しつづけてきた補弼勢力とそのパトロンである財閥を一掃し、『天皇親政』を実現しなければならないとする過激思想が、軍部の中堅将校や革新右翼を中心に急速に広まっていき、その実現をはかるための国家革新運動、昭和維新運動が展開されていったからである」と述べます。
「ただ刺せ、ただ衝け……」では、革新将校や、彼らと手を結んだ民間右翼の多くは、自分たち自身が「たてまえ」を「たてまえ」ではなく「歴史の真実」とみなす天皇教信奉者の側に属していたと指摘します。そのため天皇抜きの革新は、最初から考察の埒外にありました。そうであればこそ彼らは、天皇を、形式ではなく現実の絶対君主とせよ、天皇親政を実現せよと叫んだのです。著者は、「この主張は、必然的に『申しあわせ』によって天皇親政を巧みにコントロールしてきた元老や政府内閣の顕官たち、また彼らと結託して巨利を貪ってきた財閥などの打倒へと向かい、天皇に制限をかけている憲法の廃止や、党利党略に明け暮れる政党政治の廃絶要求へと向かった。こうして、青年将校や民間右翼らによる昭和前期のテロの時代の幕が開ける」と述べるのでした。
第八章「孤独の王」の「天皇位という神輿」では、天皇は国家の方針に対して最終的な承認をおこなう形式上の「最高機関」ではありましたが、終戦直前の「聖断」などごく一部の例外を除けば、みずから決定し、実行を命ずることのできる最高実権者ではなかったことが指摘されます。著者は、「神輿に担がれたシンボルとして生きるという生き方は、天皇家の伝統といってよい。神輿の争奪戦は、過去から連綿とつづいてきた。古い担ぎ手が斃され、新たな担ぎ手が表舞台に出てくるというのが『天皇の国』の歴史の大半で、皇居の外が神輿の争奪戦でいかに騒然となっていようとも、神輿そのものはおおむね安泰だった。鎌倉倒幕に動いた後鳥羽天皇や、室町倒幕に動いた後醍醐天皇のように、神輿から飛び出してその手に実権をにぎろうとした天皇は、まったく例外的な存在だった」と述べています。
武家政権の最後の担ぎ手となったのが徳川家康です。家康は、天皇家を京都御所という事実上の座敷牢に封じこめ、文化的な権威と多少の権力、小大名程度のわずかな食禄(禁裏御料、当初は1万石でのちに3万石になった)を与えて、政治にはいっさい関わらせない体制をつくりました。著者は、「天皇家は、時代が進むにつれてこの暮らしに次第になじんでいき、安住するまでになりました。
明治になり、新たな担ぎ手である薩長幕府の不動のエースとなった伊藤博文は、表向きはいっさいの権力を天皇に集中させるとともに、天皇家を日本一の大財閥に仕立てあげ、政治的には政府を筆頭とする補弼機関が国家全体を動かすという秀逸なシステムをつくりあげた。形態こそ前代とは異なっているが、天皇が神輿のなかの御神体であることに変わりはなかった」と述べます。
「人間宣言と日本国憲法の意味」では、天皇現人神説は、もともと天皇自身が否定し、一部の狂信者および刷りとみが容易な児童以外の国民にも信じられていなかった「たてまえ」だから、否定して問題はないといいます。しかし、「相互の信頼と敬愛」という「虚構」だけは、どうしても守られなければならないという著者は、「そのようなものはなかったということになると、天皇と国民とをつなぐイデオロギーがなくなり、天皇制の根拠そのものが消えてしまう。そうなったら、共産革命という、当時の日本人がもっとも恐れていた事態も、現実味を帯びてくる。実際、敗戦後に復権した共産党は天皇制廃止を強く訴えており、共産主義思想を指導の軸にすえた労働争議も各地で頻発していた」と述べています。
「天皇の国・日本」を護るためには、天皇と国民のあいだには、伝統的に「終始相互の信頼と敬愛」という「紐帯」があったというフィクションは、絶対に欠かすことのできない国体護持の最後のキモだったといってよいとして、著者は「GHQは、日本統治に天皇の権威を利用するという方針を堅持していた。だから、軍国主義にかかわるものは次々廃止しても、天皇と国民の『相互の信頼と敬愛』という『虚構』にはタッチせず、積極的に利用した。GHQのこの方針は、国体護持のために無条件降伏を受け入れた昭和天皇にとっても、天皇を利用することで権力を保持してきた補弼機関にとっても、じつに好都合だった。三者の思惑はそれぞれ異なっていたが、天皇の『人間宣言』は、無条件降伏後も国体が護持されねばならないというコンセンサスの、みごとな合致点となっていたのである」と述べるのでした。
第九章「昭和から平成へ」の「至尊に煩累を及ぼしたてまつらざる事」では、戦後、政府が国をあげて押し進めたのは、戦争責任を軍部、とりわけ陸軍に全面的に押しつけ、天皇は終始平和主義者だったというイメージを広めるとともに、天皇と国体を護ることだったと指摘します。その作業は、敗戦後ただちに重臣や政府、軍部のあいだで着手されています。著者は、「ここでいう『天皇』とは、昭和天皇個人だけを意味するのではない。天皇個人を守ることによって、『天皇位という神輿』を護ることこそが至上命題なのだ。「昭和から平成へ」では、沖縄訪問もふくめて、昭和天皇がやり残した「つとめ」を、明仁天皇は、強い意思をもってやり通したことが指摘されます。代替わりして2年目の平成2年(1990)5月、韓国の盧泰愚大統領が訪日しました。韓国側は日韓併合する新天皇の謝罪を求めていましたが、自民党からの強い反対を受けた当時の海部俊樹首相が天皇の謝罪にストップをかけ、自分が代わって謝罪すると申し出ました。
晩餐会当日、天皇は謝罪の言葉こそ口にしなかったが、「貴国の人々が味わわれた苦しみを思い、痛惜の念を禁じえない」という表現で、併合時代に触れたのでした。2年後の平成4年(1992)には、国内右派の反対を押し切り、近代天皇で最初の訪中天皇となりました。このときも、天皇は「わが国が中国国民に対し、多大の苦難を与えた不幸な一時期がありました。これは私の深く悲しみとするところであります」と思いを口にし、翌5年から、かつての戦地を慰霊して廻る「旅」をスタートさせました。最初に選ばれた旅の行き先は沖縄でした。著者は、「まず訪れなければならない場所は、沖縄以外にはありえなかった。皇太子時代に訪れたときは、牛乳瓶や火焔瓶を投げつけられた。それでも皇太子時代に5回の沖縄訪問を行い、即位後も6回訪問した」と述べるのでした。
 皇産霊神社の瀬津禰宜と
皇産霊神社の瀬津禰宜と
じつは、本書を國學院大學の大学院で神道を学んだ皇産霊神社の瀬津隆彦禰宜にも読んでもらったのですが、「本書全体の感想」として、「国家神道論に関しましては、従前の国家神道の議論の枠から出るものではなく、現状での国家神道論の概説書と捉えることはできるかと存じます。そのため内容そのものに目新しさは感じられません。一方でタイトルである“偽史の帝国”や“不気味なフィクション”・“洗脳”・“天皇教”などの記憶にのこりやすい言葉でレッテルを貼ることで、ある種の印象操作をしているような文言に違和感を覚えました。著者のライターという立場を考慮すれば、購買欲を惹起する文章を書かねばならないというやむを得ない部分もあるかと思いますが、神道に関する議論の中でも殊更に慎重さが求められる当該分野におきましては、あまり適当な姿勢ではないように感じました」と述べています。
