- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2014.03.26
『0葬―あっさり死ぬ』島田裕巳著(集英社)を読みました。
わたしはNPO法人・葬送の自由をすすめる会が発行する「そうそう」3号のインタビュー取材を受けました。同会の現会長は『葬式は、要らない』を書いた島田裕巳氏、つまり本書『0葬』の著者です。
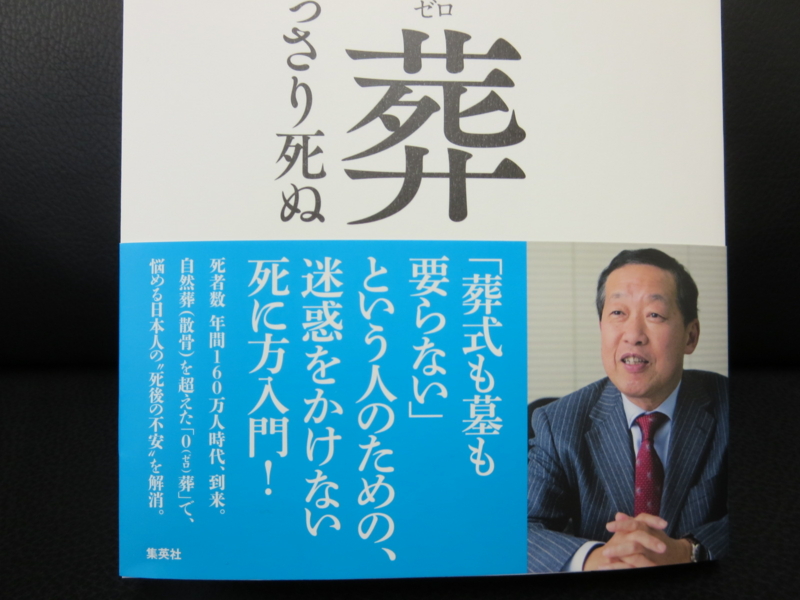 著者の写真が掲載された本書の帯
著者の写真が掲載された本書の帯
本書の帯には著者の写真とともに、「『葬式も墓も要らない』という人のための、迷惑をかけない死に方入門!」「死者数 年間160万人時代、到来。自然葬(散骨)を超えた『0(ゼロ)葬』で、悩める日本人の”死後の不安”を解消」と書かれています。わたしは「散骨」と呼ばれる海洋葬や樹木葬などには大いに賛成していますので、著者の新しい活動を好意的に受け止めています。そもそも「葬送の自由」といった時点で「葬式は、要らない」とは考えていないことは明白であると思ったからです。しかしながら、本書に書かれている「0葬」とは自然葬(散骨)を超えた内容とのこと。それがどのようなものなのか。わたしは期待と不安を胸に本書を読み始めました。そして、読了後は少しの共感と大きな違和感の両方がわたしの胸に残りました。
本書の目次構成は、以下のようになっています。
「はじめに」
第1章 人を葬ることは相当に面倒である
第2章 なぜ葬儀や墓はこんなにも厄介になったのか
第3章 生老病死につけこむ資本の論理
第4章 死者が増えるから葬儀で儲けようとする
人々が次々とあらわれる
第5章 世間体を気にするがゆえに
資本の論理につけこまれる
第6章 仏教式の葬儀は本当に必要なのか
第7章 マイ自然葬、そして究極の0葬へ
第8章 人は死ねばゴミになる
「はじめに」の冒頭に、著者は次のように書いています。
「死者とともに生きる必要は、もうない。
少し前まで、私たちは死者とともに生きてきた。
というのも、死者は私たちと同居していたからである。
もちろん、今でも死者とともに生きている人たちはいる。けれども、しだいに多くの人たちは、死者と同居し、死者とともに生きることを望まなくなってきた」
いきなりショッキングというか、わたしには違和感が炸裂する文章ですが、著者は現代人の生活空間に死者が同居していないことを次のように説明します。
「襖もなく、長押もない都会の家では、高いところに写真を飾っておくスペースもない。かといって、海外の家庭で行なわれているように、飾り棚やチェストの上に写真立てに納められた写真を飾っておく慣習も、それほど広まってはいない。仏壇を置かなければ、都会の家には死者が生きる場所はない」
著者は「死者が住む場所があるとすれば、それは唯一、墓である」という言葉を紹介した後で、次のように述べています。
「一度墓に入ってしまえば、死者は家に戻ってくることはない。家に仏壇がなければ、死者は家に戻るすべを持たない。生者と死者は分離された。生者の生きる世界と死者の生きる世界は、ほとんど交わらなくなった」
著者によれば、「死者の存在感は重い」そうです。「そこには、ただ位牌や写真があるだけなのに、死者には物語がつきまとい、その分、同じ家で生活している人間にのしかかってくる」といいます。
そして「スープのさめない距離」という言葉を持ち出し、次のように述べます。
「死者がスープのさめない距離にいたとしたら、それは鬱陶しい。多くの人がそう感じることだろう。車に乗ってドライブに出かける距離くらいは、離れていてほしい。近くに墓を求めないのは、単に経済的なことだけが理由になっているわけではない。物理的に、ある程度の距離が求められているのだ」
さらに、著者は以下のように述べています。
「私たちはこれまで、人を葬るということにあまりにも強い関心を持ちすぎてきたのではないだろうか。それに精力を傾けすぎてきたのではないだろうか。
それこそが日本の文化であり、死者を丁重に葬ることは日本人の精神にかなってきたと言われてきた。だが、社会は大きく変わり、死のあり方そのものが根本的に変容してきたことから考えれば、従来の方法は意味をなさない。
極端な言い方をすれば、もう人を葬り、弔う必要はなくなっている。
遺体を処理すればそれでいい。そんな時代が訪れている」
人間には遺体という「からだ」だけでなく、「たましい」があります。また、遺された人々には「こころ」があります。著者のこの物言いには、死者の「たましい」と遺族の「こころ」に対する視点がまったく抜け落ちています。
第1章「人を葬ることは相当に面倒である」では、「葬儀をする生物は人間だけ」という項を設け、著者は次のように述べます。
「人類以外の生物は、哺乳類であったとしても、仲間が死んだとき、それを葬ったりはしない。葬式をしないのはもちろん、遺体処理さえしない。それは、人類に近いとされる猿でも同じだ。猿には知性の萌芽があるようにも見えるし、実際、実験でその点は証明されている。だが、猿は仲間の遺体処理さえしないのだ。
その点では、仲間を葬るという行為が、私たちが人類の一員であることの証とも言える。人類である限り、葬儀を営むのは当たり前のことである。現代人もまた、その伝統を引き継いでいる」
また、中江兆民を葬儀無用論者の先駆者として、著者は述べます。
「兆民は1887年(明治20年)にはじめて葬儀無用論を唱えたが、1901年(明治34年)には喉頭癌の宣告を受け、その後に著した『一年有半』や『続一年有半』では、『霊魂の不滅や神などといった存在は観念的なものにすぎない』と唯物思想を唱えた。葬儀無用論は、そうした兆民の思想から導かれるものである。遺言には「おれには葬式など不必要だ。死んだらすぐに火葬場におくって荼毘にしろ」ということばを残した。その遺言にしたがって、遺体は解剖され、墓碑も建てられなかった。彼の葬式無用論は、実践されたわけである」
しかし、ここで歴史は思わぬ展開を見せます。これを「歴史の皮肉」と表現する著者は、次のように書いています。
「生前に兆民と親交のあった板垣退助や大石正巳といった自由民権家が、兆民を偲ぶために青山会葬場(現在の青山葬儀所)で、宗教上の儀式にとらわれない『告別式』なるものを開いている。実はこれが、今日一般化した告別式のはじまりとされている。つまり、葬儀無用論を唱えた人物を偲ぶ会から、告別式というスタイルが生まれたわけである」
もう1人、著者は葬儀無用論者として夏目漱石の名前を挙げていますが、実際には漱石の葬儀は盛大に営まれました。その様子を弟子の1人であった芥川龍之介が『葬儀記』に書いています。
葬儀無用論といえば、著者はかつて『葬式は、要らない』において、ブッダの葬式観に触れました。ブッダは決して霊魂や死後の世界のことは語らず、この世の正しい真理にめざめて、一日も早く仏に到達することを仏教の目的にし、葬儀というものを否定したというのです。いわば、仏教の開祖であるブッダ自身を「世界最初の葬儀無用論者」として位置づけたわけですね。

たしかにブッダは、弟子の1人から、「如来の遺骸はどのようにしたらいいのでしょうか」と尋ねられたときに、「おまえたちは、如来の遺骸をどうするかなどについては心配しなくてもよいから、真理のために、たゆまず努力してほしい。在家信者たちが、如来の遺骸を供養してくれたのだろうから」と答えています。自身の死に関しては、「世は無常であり、生まれて死なない者はいない。今のわたしの身が朽ちた車のようにこわれるのも、この無常の道理を身をもって示すのである。いたずらに悲しんではならない。仏の本質は肉体ではない。わたしの亡き後は、わたしの説き遺した法がおまえたちの師である」と語っています。
しかしながら、ブッダに葬式を禁じられた弟子の出家者たちも、自分自身の父母の死の場合は特別だったようですし、ほかならぬブッダ自身、父の浄飯王や、育ての母であった大愛道の死の場合は、自らが棺をかついだという記述が経典に残っています。それは葬儀というものが、単に死者に対する追善や供養といった死者自身にとっての意味だけでなく、死者に対する追慕や感謝、尊敬の念を表現するという、生き残った者にとってのセレモニーだからです。
そして、弟子たちに葬儀の重要性を説かなかったとされているブッダ自身の葬儀は、盛大に執り行われました。葬儀は遺言によりマルラ人の信者たちの手によって行われました。7日間の荘厳な供養の儀式のあと、丁重に火葬に付したといいます。ブッダは、決して葬式を軽んじてはいなかったはずです。もし軽んじていたとしたら、その弟子たちが7日間にもわたる荘厳な供養などを行うはずがありません。なぜならそれは完全に師の教えに反してしまうことになるからです。
それともマルラ人たちは本当にブッダの教えに反してまで、荘厳な葬儀を行ったのでしょうか。教えに従うにせよ、背いたにせよ、マルラ人たちは偉大な師との別れを惜しみ、手厚く弔いたいという気持ちを強く持ちました。
いずれにせよ、著者が葬儀無用論者の代表として白羽の矢を立てたブッダも中江兆民も夏目漱石も、本人たちの意思(?)に反して、盛大な葬儀が行われたわけです。しかし、盛大な葬儀というものを徹底的に否定する著者は、時代は「家族葬で当たり前。直葬でもかまわない」という方向に向かっていると言います。
その背景には、日本の葬儀費用の高さがあるというのです。『葬式は、要らない』の帯には「平均費用231万円は、ダントツの世界一!」と書かれていました。本書『0葬』で著者は述べます。
「残念ながら、世界の葬儀費用を比較した資料はほとんどない。少し古いものだが、葬祭業者のサン・ライフが1990年代前半に行なった調査では、アメリカが44万4000円、イギリスが12万3000円、ドイツが19万8000円で、韓国が37万3000円という結果が出ていた」
「日本の葬儀費用、231万円」というのは、2007年に財団法人日本消費者協会が行なった調査のもので、そこには葬儀社への支払いの他、飲食の経費や寺への布施、香典返しの費用が含まれている。また、正確には遺族がこの費用を全額負担するわけではない。参列者が香典を持ってくるからだ」
じつは、この点を、わたしは一環して批判してきました。「香典」というファクターを無視して、諸外国と日本の葬儀費用を単純に比較することはフェアでないばかりか、一種の情報操作にほかならないからです。「SOGI」編集長である碑文谷創氏もこの点を批判されていたと記憶しています。しかし、本書『0葬』では「日本の葬儀費用、231万円」に対する言い訳が述べられています。このように事実をきちんと認めて訂正する行為は大切ですね。
本書で興味深かったのは、第2章「なぜ葬儀や墓はこんなにも厄介になったのか」の中で「葬式組」について触れている箇所です。著者は、かつては「葬式組」が葬送のすべてを取り仕切ったとして、以下のように述べます。
「死者が出た場合、土葬するために墓穴を掘る必要がある。その役割を担うのが、村のなかにある『葬式組』である。葬式組は葬儀万端を取りしきってくれる組織でもあり、遺族はこの葬式組にすべてを任せることができた。
葬式組は、村社会に特有の組織である。葬式組の世話になった遺族は、次の機会には、つまり別の家に死者が出たときには、自分が葬式組に加わり、葬儀を取りしきったり、さまざまな手伝いに参加しなければならない。つまり、葬式組は相互扶助の組織なのである」
葬儀を行う相互扶助の組織といえば、戦後、冠婚葬祭互助会が誕生しました。互助会の誕生と発展によって、各地から「葬式組」は急速に消えていきました。
著者はまた、第3章「生老病死につけこむ資本の論理において、葬儀を行う組織としての企業の存在に注目し、「一時は、企業が葬式組の機能を果たしていた。それも、企業とそこで働く社員とのあいだの関係が密接だったからである。終身雇用、年功序列、企業内組合を特徴とする、いわゆる『日本的経営』を実践する企業では、そうした傾向が強かった」と述べています。
しかし、戦後の日本人は「葬式組」でも「企業」でもなく、葬儀を出す場合は互助会や葬儀社に依存するようになりました。その傾向は地方よりも都市で進んでいるわけですが、地方の方にもそれを促進する要因があるとして、著者は次のように述べます。
「現在、地方の方がはるかに車社会の様相を呈している。地域の交通機関が発達していないために、車を使うしかないからである。全国でもっとも自動車の普及率が低いのが東京で、60パーセントにしかならない。区部に限ると、50パーセント近くに落ち込む。大阪でも70パーセント程度だが、反対に95パーセントを超えている県が20近くある」
第4章「死者が増えるから葬儀で儲けようとする人々が次々とあらわれる」では、「今、墓に対する需要が急増している」として、以下のように「樹木墓地」というものが紹介されています。
「最近、都営霊園では『樹林墓地』が設けられるようになった。樹林墓地は表面が芝生になっていて、コブシやヤマボウシ、モミジなどが植えられている。そして、遺骨を布製の袋に入れてその下に保管する。都営小平霊園では約830平方メートルの敷地を用意し、そこにはおよそ1万700人が葬られることになっている。料金は、遺骨の場合一体が13万4000円で、粉にすれば4万4000円で済む。2012年夏の募集では、500体分の枠に対して、16倍を超える応募があったというから大人気である」
この「樹木墓地」は、今後の日本人の葬送にとって大きな意味を持つものです。ある意味で、無縁社会や老人漂流社会を乗り越える可能性を持っているのですが、わが社でも「鎮魂の森プロジェクト」を立上げており、今秋から福岡県田川郡でスタートする予定です。
本年6月6日、わたしは仏教連合会が主催する講演会に招聘されています。この場で、あらゆる仏教宗派の僧侶の方々の前で講演をさせていただきます。
2010年1月に、日本人の「こころ」に暗雲を漂わす2つの言葉が生れました。「無縁社会」と「葬式は、要らない」です。前者はNHKスペシャルのタイトルで、後者は幻冬舎新書の書名ですが、わたしは両者は同じ意味だと思います。このような言葉が生れてきた背景には、日本仏教の制度疲労があると思います。何の制度かというと、いろいろあるのですが、最も大きなものは檀家制度でしょう。身寄りのない高齢者、親類縁者のない血縁なき人々が急増して、それこそ檀家という制度が意味を成さなくなってきています。
わたしは冠婚葬祭業者として「日本仏教のイノベーション」あるいは「日本仏教の再生」のお手伝いをさせていただきたいと願っています。
「そもそも、仏教は葬儀と結びついていなかった」と唱える著者は、第6章「仏教式の葬儀は本当に必要なのか」において、日本に最初に伝えられた仏教の宗派である「南都六宗」について以下のように述べています。
「南都六宗は奈良時代に栄えた6つの仏教宗派の総称で、法相宗、三論宗、華厳宗、律宗などからなり、寺としては、法隆寺、東大寺、興福寺、薬師寺などが挙げられる。現在、こうした寺を訪れる人は多いいが、それはそれぞれの寺の建物や塔、あるいはそこに安置された仏像を拝むためである。
こうした寺には、墓地がない。だから、そこに所属する僧侶たちは葬儀をあげることはない。墓地がないために、墓でつながった檀家もいない。
しかも、それぞれの寺の僧侶が亡くなったときには、その寺で葬儀をあげることはない。僧侶の家が所属している宗派で葬儀を行ない、墓もそうした寺院に関係する墓地にある。つまり、南都六宗は葬式をしない宗派なのである。それは、この時代にはまだ仏教と葬儀とが結びついていなかったことを意味する」
それでは、どうして日本仏教は葬儀と深く関わるようになったのか。著者は、「葬式仏教」への決定的要因について以下のように述べています。
「日本の仏教が葬式仏教への道を歩む上で決定的な要因となったのが、1つは浄土教信仰の浸透であり、もう1つが禅宗による葬儀の開拓である。
浄土教信仰は、死後に西方極楽浄土に生まれ変わることを目指すもので、インドの輪廻転生の考え方からすれば、あり得ないものである。
ところが、中国では不老不死への憧れや神仙の考え方があり、死後は西方極楽浄土に生まれ変わりたいという信仰が生まれた。浄土教信仰の起源は中国にあり、それが日本に伝わったわけである。その点で重要な役割を果たしたのが、唐に渡った後、第3代の天台座主になる円仁である。円仁は唐から多くのものをもたらしたが、そのなかに『念仏行』も含まれていた」
そして、禅宗が日本人の葬儀を開拓していった状況が述べられています。
「ある意味意外なことだが、仏教式の葬儀の方法を編み出したのは禅宗であり、そのなかの曹洞宗であった。禅宗がなぜ葬儀の方法を編み出すことになったのか、教えのレベルで考えると理解が難しい。
曹洞宗の宗祖は道元である。道元は比叡山で学び、唐にも渡ったが、その後福井に永平寺を開き、そこを禅の修行のための根本道場とした。
永平寺に入った雲水たちは、早朝から夜まで一日中厳しい修行を続け、悟りを目指した。そこからしても、曹洞宗から仏教式の葬儀が生まれるはずはない。
しかし、雲水が修行に専念するためには、それを支える経済基盤が必要である。修行に明け暮れていれば、他に収入を得ることはできない。それは道場の崩壊にも結びつく。そのとき、禅寺の経済基盤を確立するために動いたのが、曹洞宗では道元とともに二大宗祖とされる螢山紹瑾であった。彼は中国の禅宗に伝わる『禅苑清規』という書物をもとに、修行途中で亡くなった雲水の葬儀の方法を俗人の葬儀に応用する道を開いた。
これによって、日本に独自な仏教式の葬儀が確立された。これは、しだいに同じ禅宗の臨済宗だけではなく、天台宗、真言宗、さらには浄土宗にも広がった」
この禅宗による葬儀の開拓のくだりは、もちろんわたしは知っていました。でも、これほど整理してわかりやすく説明している文章を読んだのは初めてです。わたしは、著述家としての著者の筆力に脱帽しました。著者は、仏教と葬儀の関係について、さらに次のように述べています。
「先祖を供養するという考えかたは、もともと仏教にはなかった。仏教は、その開祖である釈迦が出家したように元来は家を否定するものであり、むしろ家を離れ、世俗の世界から離脱することを奨励する宗教であった。
ところが、これも中国を経てのことだが、仏教のなかに祖先を重視する儒教の教えが入り込み、祖先崇拝の観念が浸透していった。
位牌という習俗も、もとはといえば儒教の信仰にもとづいている。儒教では『孝』が強調され、親や祖先を敬うことが奨励される。それが、祖先崇拝の信仰を確立することに結びついたのである。こうして、江戸時代において、死者を葬るための信仰を構成する要素がすべて出そろい、それが組み合わされて葬式仏教という1つのシステムが構築されることになった」
このような歩みを経て、仏教式の葬儀は、「しきたり」として民衆の間に受け継がれることになりました。故人に特定の信仰でもない限り、日本人のほとんどは仏式葬儀を行ってきたのです。もちろん、無宗教式の葬儀も存在しましたが、けっして根づくことはありませんでした。著者は、次のように述べています。
「よく言われるのは、無宗教式の葬儀では間が持たないということである。仏教式の葬儀では、導師となった僧侶の読経を背景にして参列者は焼香した。ところが、無宗教式では読経がない。故人の好きだった音楽を流しても、それはすぐに終わってしまい、読経の代わりにはならないというのである。
それに、仏教式の葬儀では、死者がどういった世界に赴くのか、それを語るストーリーがある。死者は法要をくり返すなかで世俗の世界から解き放たれ、やがては西方極楽浄土に往生できるという物語である。神道式やキリスト教式にもそれはあるが、無宗教式にはあの世へ向かうストーリーが根本的に欠けている」

親しい人間が死去する。その人が消えていくことによる、これからの不安。残された人は、このような不安を抱えて数日間を過ごさなければなりません。心が動揺していて矛盾を抱えているとき、この心に儀式のようなきちんとまとまった「かたち」を与えないと、人間の心にはいつまでたっても不安や執着が残るのです。この不安や執着は、残された人の精神を壊しかねない、非常に危険な力を持っています。この危険な時期を乗り越えるためには、動揺して不安を抱え込んでいる心に、ひとつの「かたち」を与えることが求められます。まさに、葬儀というものを行う最大の意味はここにあります。
では、この儀式という「かたち」はどのようにできているのでしょうか。それは、「ドラマ」や「演劇」にとても似ています。死別によって動揺している人間の心を安定させるためには、死者がこの世から離れていくことをくっきりとしたドラマにして見せなければなりません。ドラマによって「かたち」が与えられると、心はその「かたち」に収まっていきます。すると、どんな悲しいことでも乗り越えていけるのです。それは、いわば「物語」の力だと言えるでしょう。わたしたちは、毎日のように受け入れがたい現実と向き合います。そのとき、物語の力を借りて、自分の心のかたちに合わせて現実を転換しているのかもしれません。
つまり、物語というものがあれば、人間の心はある程度は安定するのです。逆に、どんな物語にも収まらないような不安を抱えていると、心はいつもぐらぐらと揺れ動いて、愛する人の死をいつまでも引きずっていかなければなりません。
仏教などの宗教は、大きな物語だと言えるでしょう。「人間が宗教に頼るのは、安心して死にたいからだ」と断言する人もいますが、たしかに強い信仰心の持ち主にとって、死の不安は小さいでしょう。なかには、宗教を迷信として嫌う人もいます。でも面白いのは、そういった人に限って、幽霊話などを信じるケースが多いことです。

これまで日本仏教は「葬式仏教」などと揶揄されながらも、日本人の宗教的欲求をしっかりと満たしてきました。でも、「葬式は、要らない」という言葉に象徴されるように、その存在基盤は大きく揺らいでいます。今こそ、日本仏教は変わる必要があるのではないでしょうか。
この読書館でも紹介した『アップデートする仏教』には、「仏教3.0」という考え方が示されていました。「仏教3.0」は制度疲労を迎えた日本仏教を再生させることであり、それがそのまま「アップデート」ということになります。でも、仏教に必要なものは「アップデート」とともに「初期設定」でもあります。
わたしが『図解でわかる!ブッダの考え方』(中経の文庫)にも書いたように、仏教の「初期設定」とは開祖であるブッダの考え方にほかなりません。そのブッダの考え方に最も近い上座部仏教(テーラワーダ仏教)、すなわち「仏教2.0」の存在も無視することはできません。ヘーゲルの弁証法にならえば、「仏教1.0」としての現存の日本仏教とともに「仏教2.0」の上座部仏教も取り入れれば、正・反・合で「仏教3.0」が誕生するのかもしれません。それが日本人の精神生活のベースとなれば、葬儀や墓の問題も新たな展開を見せ、無縁社会をも乗り越える道筋が見えてくるような気がします。
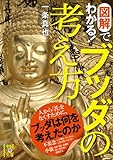
そして、わたしは「仏教3.0」だけでなく「冠婚葬祭3.0」についても考えるべき時期が来ていると思います。制度疲労を迎えているのは、けっして日本仏教だけではないのです。パネル・ディスカッション「儀式文化創造シンポジウム」で、わたしはパネリストとして儀式のイノベーションの必要性を訴えました。いま、七五三も成人式も結婚式も、そして葬儀も大きな曲がり角に来ています。現状の冠婚葬祭が日本人のニーズに合っていない部分もあり、またニーズに合わせすぎて初期設定から大きく逸脱し、「縁」や「絆」を強化し、不安定な「こころ」を安定させる儀式としての機能を果たしていない部分もあります。
いま、儀式文化の初期設定に戻りつつ、アップデートの実現が求められているのではないでしょうか。そう、「冠婚葬祭3.0」の誕生が待たれているのです。たとえば、わが社が提案する「禮鐘の儀」などもその1つだと思います。
その「冠婚葬祭」、それも「葬祭」の現状について、著者は述べています。
「これはあまり知られていないことだが、地域によって火葬した後に遺族が持ち帰る遺骨の量は異なる。基本的には、東日本と西日本で違う。
東日本では、遺骨をすべて持ち帰る『全骨収骨(拾骨)』で、その分骨壺はかなり大きい。それに対して西日本では、『部分収骨』で、全体の3分の1、あるいは4分の1程度しか持ち帰らない。残りは火葬場で処分される。したがって、骨壺も東日本と比べるとかなり小さい。ここでいう東日本と西日本は、基本的に糸魚川静岡構造線で分かれる」
このあたりにも「アップデート」が必要な気がしますね。「葬祭アップデート」として、誰しも「自然葬」を思い浮かべるでしょう。著者は、「自然葬」について次のように述べています。
「自然葬ということばは、現在ではもっぱら、海や山に細かく砕いた遺骨を撒く行為をさすが、土葬もまた遺体を自然に還すということでは自然葬としてとらえることができる。あるいは、チベットなどで行なわれている鳥葬も自然葬に含めることができるだろう。高原で遺体を切り刻み、鳥が食べやすくして、肉を食わせるやり方で、鳥はハゲタカである。インドでは、ガンジス川に遺体を流す水葬が行なわれており、これも自然葬に含めて考えることができる。こうした自然葬と比較して、火葬した遺骨を骨壺に納め、それを墓に埋葬するやり方は、遺骨が自然に還らないという点で『不自然葬』だとも言える」
この「不自然葬」という言葉には説得力がありますし、わたしも共感しました。
「自然葬」以上に「不自然葬」を否定したのが「0葬」です。第7章「マイ自然葬、そして究極の0葬へ」において、著者は「0葬」について以下のように述べます。
「土葬では、遺体を墓地に葬ったところで一応の区切りがつく。なかには詣り墓を造って、そこで供養を行なう家もあるが、誰もがそうしなければならないというわけではない。基本は、埋めたら終わりである。
火葬の場合にも、火葬した時点で終わりにしたらどうだろうか。
遺骨の処理は火葬場に任せ、それを引き取らないのである。
これは、土葬し終えた状態と同じになる。それが、0葬である」

この「0葬」というネーミングですが、映画化されたベストセラー小説『永遠の0』を彷彿とさせて、なかなかキャッチーではありますね。でも、「永遠のO」と「0葬」では、わたしは「0」の意味がまったく違います。『「永遠の0」と日本人』の書評にも書いたように、「永遠の0」は仏教でいう「空」にも等しく無限の時間と空間を指しているように思います。けっして「無」ではありません。「無」ではなく「空」です。人間の魂が永遠に生き続けられる絶対の時空です。一方で、「0葬」というのは「無葬」という意味です。「空」と「無」は違います。「0葬」には巨大な虚無感が漂っています。
著者は、さらに「0葬」の意義を説きます。
「0葬に移行することで、私たちは墓の重荷から完全に解放される。墓を造る必要も墓を守っていく必要もなくなるからだ。ゆえに、遺族に負担がかからない。
私たちは必ずしも墓が必要だと思うから、それを造っているわけではない。遺骨が残ることでそれを葬る場所を必要としているから、という面が強いのだ。だからこそ、『千の風になって』という歌が流行ると、それを葬儀や納骨のときに歌う人が増えたのだ。この歌の歌詞は「故人が『私はお墓に眠ってなんかはいない』と訴える」というのが趣旨である。この歌が2007年年間売り上げ約113万枚の大ヒットという形で支持されたように、皆、墓に故人がいるとは考えていない。千の風になって、もっと自由になった、あるいはなりたいと考えているのだ」
ここまでは、わたしもある程度共感しました。しかし、著者は続いて以下のように述べています。
「残された人間が故人を思い出すのは、故人がした善行を通してではなく、反対に迷惑になったことを通してだったりする。死後に忘れられないためには、生前、周囲に数限りない迷惑をかけておいた方がいいのかもしれない。
それでも、人が死ねば、やがてその存在は忘れられていく。何年もその存在が、多くの人に記憶されている人はほとんどいない。だったら、あっさりと消えてしまった方がいい。まさに『立つ鳥跡を濁さず』である。
これから遺体処理の方法が開発され、最後には灰どころか何も残らない形がとれるようになるかもしれない。それこそが究極の0葬である」
この文章には、わたしは大きな違和感を覚えます。「どうして、ここまで人間の人生というものに価値を置かないのだろう」と不思議に思うと同時に、一連のオウム真理教事件でのバッシングによって著者が相当なニヒリズムに陥っていることが理解できました。

著者の言い分ではまるで人間の最期は「ゴミ」ということになります。実際、本書の最終章に当たる第8章のタイトルは「人は死ねばゴミになる」です。「ミスター検察」と呼ばれた故・伊藤栄樹氏の著書のタイトルでもあります。
ここまで日本人の葬送儀礼や先祖供養を徹底的に否定するのは、なぜか。著者は「私たちは死者のことを、あるいは死後のことを気にかけすぎてきた。それによって、死者は私たちの身近にいて、生きている者の行く末を見守っているという感覚を得てきた」と述べていますが、これは日本民俗学の開拓者である柳田國男が、太平洋戦争が終った翌年に刊行した『先祖の話』で展開した考え方です。

どうやら著者には柳田國男に対しての批判的視点があるようで、次のように述べています。
「柳田は『仏教嫌い』で有名だったが、それは彼が強く影響を受けた国学の考え方でもあった。民俗学は日本の民俗社会にある慣習や儀礼について研究する学問だが、そうしたものが成立する上で仏教の影響を受けていないとするのが柳田の主張であり、彼は自らのそうした試みを『新国学』と呼んでいた。
したがって、死後に西方極楽浄土へ往生するという仏教の考え方を否定し、死者はそんな遠い場所に旅立つのではなく、亡くなった後も残された家族の近くにいて、その生活を見守っていると主張した。先祖は、春には田の神となって耕作を助け、収穫が終わると山の神となって近くの山へ戻っていくというのである」
さらに著者は、柳田國男の祖先崇拝についての見方について、「民俗社会の慣習や儀礼が仏教の影響をまったく受けていないとする柳田の主張には無理があり、それは証明されなかったものの、祖先が田の神になり、山の神になるという柳田のとらえ方は、現実に存在する信仰と合致したため、広く受け入れられた。そこから、日本人の信仰の核には祖先崇拝があるという見方が一般化した」と述べています。
2013年11月、宮内庁は、天皇皇后の葬儀が行われた場合、従来の土葬ではなく、火葬で行なうことを決定したと発表しました。陵墓についても、昭和天皇などのものより小さくし、皇后陵と隣り合わせにするそうです。これは天皇家の「葬祭アップデート」にほかなりませんが、日本人全体にとっての「葬祭アップデート」も切実な問題となっています。故人が生きた証を無にしてしまうという「0葬」には納得できませんが、日本の葬送儀礼がこのままで良いとも思いません。日本人の「こころの未来」を拓くような葬儀や墓の在り方について、わたしは今後も考え続け、かつ実践していきたいです。
