- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2014.05.07
本書『魂をデザインする』は1992年6月10日に上梓した本です。サブタイトルは「葬儀とは何か」ですが、「一条真也対談集」として、10人の先生方とわたしの対談が収められています。
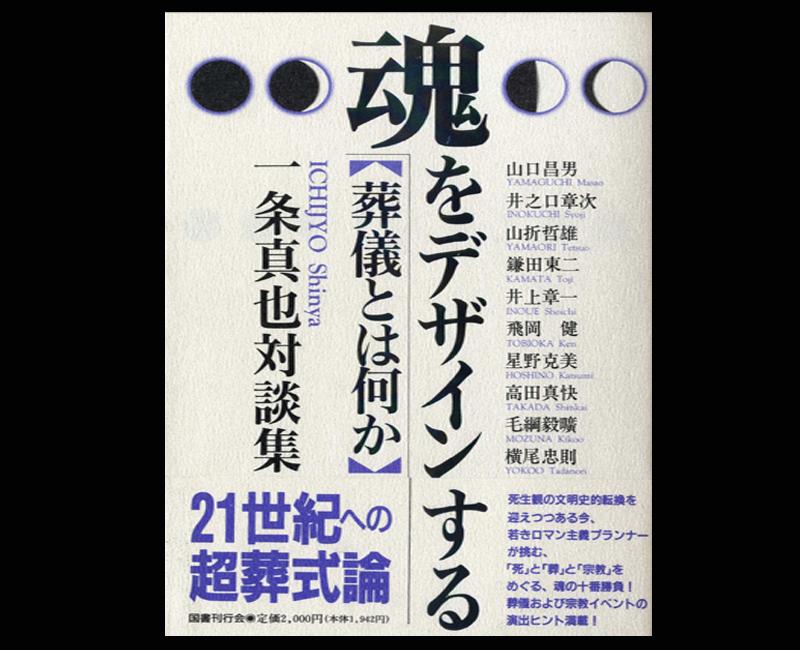 『魂をデザインする』(1992年6月10日刊行)
『魂をデザインする』(1992年6月10日刊行)
帯には「21世紀への超葬式論」とのキャッチコピーに続いて、「死生観の文明史的転換を迎えつつある今、若きロマン主義プランナーが挑む、『死』と『葬』と『宗教』をめぐる、魂の十番勝負! 葬儀および宗教イベントの演出ヒント満載!」と書かれています。
「魂の十番勝負」で当時28歳だったわたしが胸を借りた相手は、山口昌男(文化人類学者)、井之口章次(民俗学者)、山折哲雄(宗教学者)、鎌田東二(宗教哲学者)、井上章一(文化史家)、飛岡健(現代人間科学研究所所長)、星野克美(マーケティング学者)、高田真快(江戸川不動尊唐泉寺住職)、毛綱毅曠(建築家)、横尾忠則(画家)という錚々たる面々でした。今から考えても超豪華メンバーですが、当時のわたしが社長を務めていたハートピア計画が「葬儀研究レポート」という報告書を親会社のサンレーに対して作成することになり、これらの方々と小生の対談が企画されたのです。
他にも、梅原猛、吉本隆明、栗本慎一郎、松岡正剛、荒俣宏、中沢新一、浜野安宏、谷口正和といった方々が対談相手の候補として挙がっていましたが、諸々の理由で実現しませんでした。ただし荒俣宏氏だけは、版元である国書刊行会のラインで最後まで有力候補でした。同社の佐藤今朝夫社長も尽力して下さったのですが、当時の荒俣氏は住所不定というか、なかなか連絡が取れず、とうとう対談の日程的リミットに間に合わなかったのです。あれは、返す返すも残念でしたね。稀代の「博覧強記」として知られる荒俣氏とガチンコで「葬儀」について語り合いたかったです!
『魂をデザインする』という本は非常にマニアックな内容だと自分では思っていたのですが、一条本の熱心な読者の中には本書を最高傑作と思っておられる方が少なくないようです。つい最近も、このたび一緒に仕事をすることになったアート系出版社の女性編集者が高校生時代に本書を読み、その影響で「死生観」に興味を抱くようになったと告白してくれました。まさか女子高生が「葬儀」をテーマとした対談集を読んでいたとはまったくの想定外でしたので、それを聞いたときは大変驚きました。
また、「ベスト50レビュアー」こと不識庵さんは、「一条本」すなわち、わたしの本をすべて読了されたばかりか秀逸な書評を書いてくれています。彼はアマゾンに「一条本」のレビューを書いた後、しばらくして自身のブログである「不識庵の面影」に記事をアップしてくれます。そのブログ記事「魂をデザインする―葬儀とは何か(一条真也対談集)」の中で、彼は「甲乙付け難い一条本の中で、私がもっとも愛してやまない一冊。それが、この『魂をデザインする―葬儀とは何か』なのです」と書かれています。
また、続けて不識庵さんは、「言葉は、人の人生をも変えうる力を持っています。この言葉との出会いは読書であることも多いのですが、やはり人との出逢い、邂逅によってもたらされた時、魂を揺さぶるような化学反応を引き起こすように感じます。謦咳に接する、という言葉がありますが、まさに本書は一条真也氏にとって、とてつもなく大きな意味合いを持った『記念碑』といえる存在ではないでしょうか」とも述べています。たしかに、本書は若いわたしが謦咳に接し続けた記録とも言えます。
本書の目次構成は、以下のようになっています。
1.葬儀という舞台空間 山口昌男
死と誕生=宇宙的なサイクルの中の行為
葬儀のダイナミズム=非日常的舞台空間の演出
聴覚=イメージの増幅装置
葬儀の二面性=親密な空間と社交の場
2.葬儀の民俗学 井之口章次
日本人の霊魂観=祖霊信仰と仏教の相互変質
葬儀の習俗=五葬とそのバリエーション
修験道=独自のスタイルを残す山岳仏教
墓=合理主義化と個人主義化の進行
3.世界の他界と葬儀 山折哲雄
葬儀=社会的な死の確認の行事
霊の行き先=土俗的な想像世界と霊界ブランド
骨=霊肉二元論の上に立つ第3の要素
葬儀の新機軸=遺骨信仰からの発想
ベナレスの明るさ=ガンジス河の浄化力
近代=霊魂を実感できない視覚の時代
死後のイメージ=翁から神への軌跡
4.神道的宇宙と葬儀 鎌田東二
神道における死=”穢れ”あるいは魂の帰還
葬儀の発生=他界認知の始まり
先祖供養=魂の循環に連なる者たちへの慈しみ
琴=神の言葉を語る聖なる道具
警蹕=神が伝え行きかう音の橋
メディアとしての月=宇宙の中の地球を映す鏡
5.葬儀のスタイル 井上章一
霊柩車=民俗習慣に対する行政上の対抗策
死の隠蔽化傾向=葬儀のスペクタクル化の限界
葬儀の多様性=簡素化と個別化の両立
老人ケア=葬儀業者の新しい役割
既成教団=近代が生み出した不安を放置
6.葬儀の芸術世界 飛岡健
豊かさの時代=葬儀の精神的側面がクローズアップ
宗教ブーム=物質的満足の果てに行きつく憧れ
聖なる闇=精神が死と直面する空間
音楽=神へと接近する窓口
荘厳なる儀式=社会の精神性を高める契機
7.「死」と「葬」のマーケティング 星野克美
死の記号論=死の多義性へ
死にがい=死生合一への希求
臨死=近代末への限りない接近
死の様式=オカルティズムの逆流と儀式の励起
臨界=文化の聖痕としての生死のあわい
霊園=精神の遊泳空間
8.仏教と葬儀の今日的課題 高田真快
同行2人=死者とともに歩き、生きる旅路
共存=生者のあわいに生きる死者
霊=供養する心に表れる共感
現象としての死=生死の区別はない
1本のワラ=死の恐怖にもがいて
ガンの克服=観念の行がガンを解毒し、浄化した
奇跡=信ずるものは実在する
仏教の改革=世襲制がガン
9.極楽演出の空間術 毛綱毅曠
風水のポリセミー=文化の露出
中有としての近代=ハイテクは異界を創造しうるか
神聖空間=ハードとソフトをつなぐテクノロジーを
光・水=自然とのインターフェイス
光と音と香=死者への供物
10.アストラル界と宇宙的現実 横尾忠則
滝=水が輪廻を運ぶ
魂の体験=原意識がインスピレーションの母
夢=死のシミュレーション
幽体離脱=実存の逸脱としてのアストラル体
UFO=見者としての宇宙人
反進化論=変異こそが現実
覚醒する夢=メディアとしての夢
死への回帰=死の世界が現実であり、生は死者の夢にすぎない
 カバーを外すと、月の満ち欠けをイメージした装丁が・・・・・・
カバーを外すと、月の満ち欠けをイメージした装丁が・・・・・・
いま、『魂をデザインする』を読み返してみると、たしかに「これは、すごい本だ!」と自分でも思いました。読者の知的好奇心を刺激しながら、熱気のようなものも放っている。そして、「葬儀」という重いテーマが軽やかに自由に語られているように感じました。それぞれの先生方との対話はいずれも忘れえぬ青春の思い出であり、大いなる学びでした。ここでは、10人の先生方の発言で、特にわたしの印象に残っている言葉を紹介したいと思います。最後に、わたし自身の発言もご紹介いたします。
問題は、死者儀礼において、すべての人間がひとつの感情を共有するわけにはいかないということです。一方には死者と魂を共有するような、非常に親密な関係がある。葬儀のコアの部分で、そういう親密な空間の演出をもう少し考えてもいいと思う。しかし、それだけでは、葬儀は成り立たないでしょう。神道の祭祀でいえば、コアとしての神事がある一方、これに対する直会(なおらい)の部分があって、みんながパッと騒ぐ。で、行列がその間をつなぐというようなところがある。葬儀においても、この2つの側面が併存するのは自然なことではないでしょうか。(山口昌男)
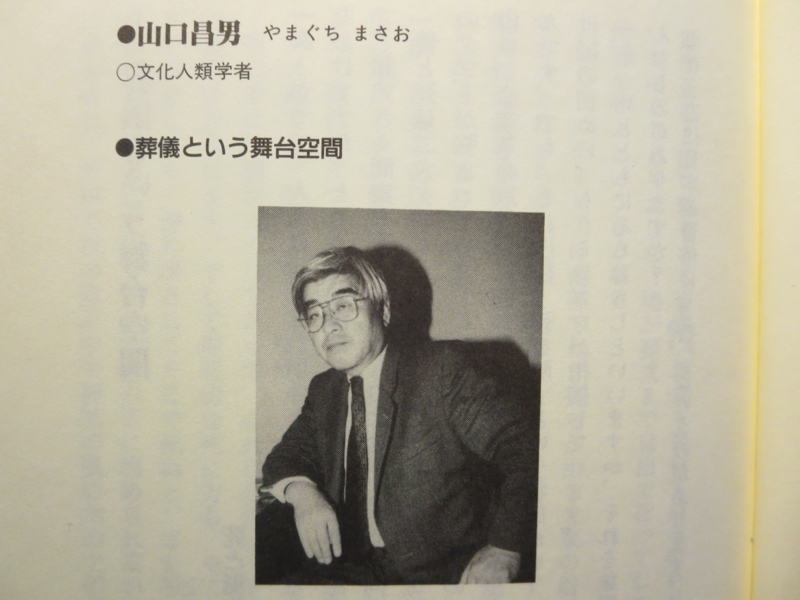 山口昌男氏
山口昌男氏
葬祭会館の建設に反対する人だって、自宅で葬式をする人たちばかりではないでしょうに。困ったものですね。しかし、私が30年前に葬式の本を書いたときに、「葬」という字には「死」という文字が入っているから良くないと、柳田國男先生から言われまして、『仏教以前』という題に変えたことがあります。ところが、15年前に『日本の葬式』という本を出したときには、もうそんなことをいう人は誰もいなくなりましたよ。
いまはもう、そんなタブーも世間からなくなったとばかり思っていました。みんなお墓をほしがっていますし、どんなお墓にしようかとなどという話は、家族の中で平気で話されている。葬祭会館の問題にしても、いずれは変わりますよ。
(井之口章次)
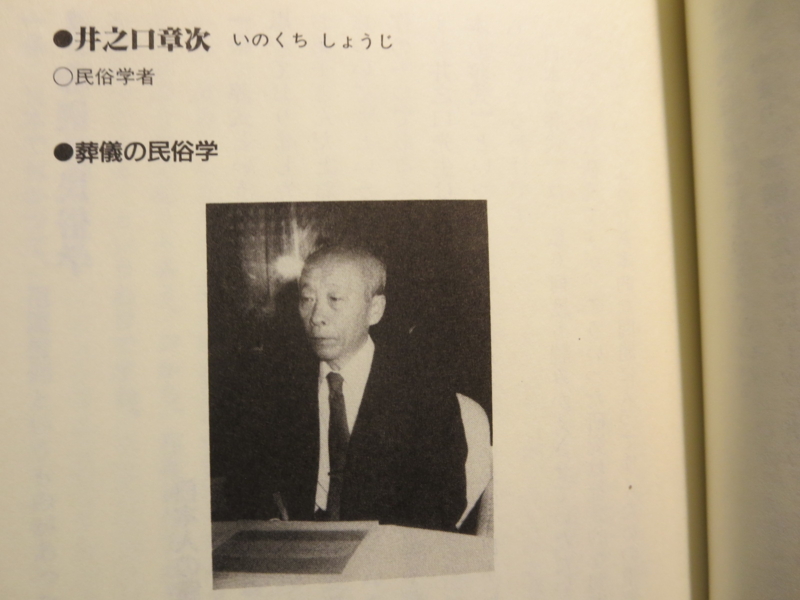 井之口章次氏
井之口章次氏
葬儀にとって大事な要素が3つあると思うのです。まず1つが、荘厳なる儀礼の空間。次に遺族たちのグリーフワークとしての悲しみの空間。そして、一般参列者にとっての意味は、むしろ社交だと考えたほうがいいと思うのです。遺族とともに悲しむといたって、それは言葉だけの話。参列者の最大の関心は社交ですよ。だからその儀礼空間、グリーフワークの空間、そして社交空間がはっきりと対象化されて構成されれば、葬儀がもう少しメリハリのきいたものになるかもしれないし、全体が暗いだけのものではなくなるのではないでしょうか。
(山折哲雄)
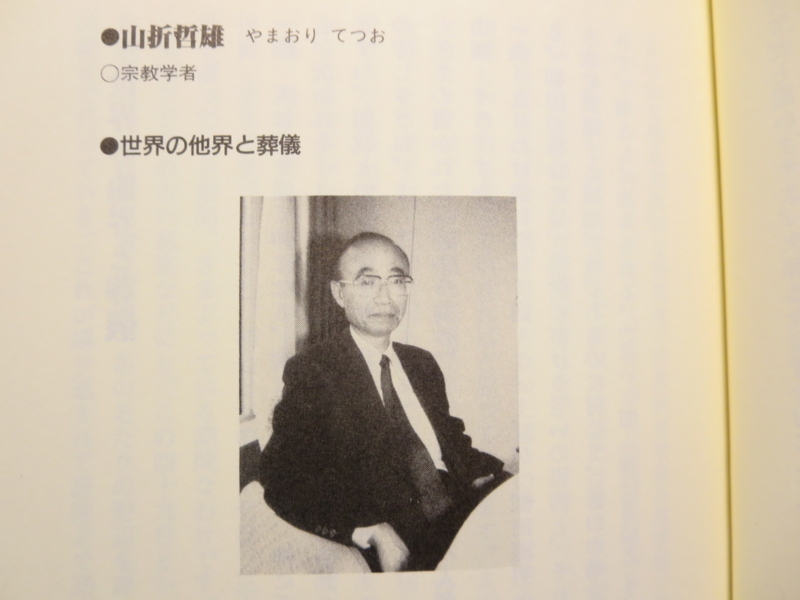 山折哲雄氏
山折哲雄氏
わたしはお墓を月につくったらいいと思っています。
まずは地球上の全人類、すべての生命を慰霊する記念碑のようなものを全宗教一致で建てる。地球生命を見守る慰霊塔です。まあ、これは日本的なローカルな発想ですが、先祖の魂は近くの山から子孫たちの人生を見守ってくれている、というのがありますよね。それならば、地球を一番よく見ることができる宇宙空間、月から人類を見守る、という設定があってもいい。(鎌田東二)
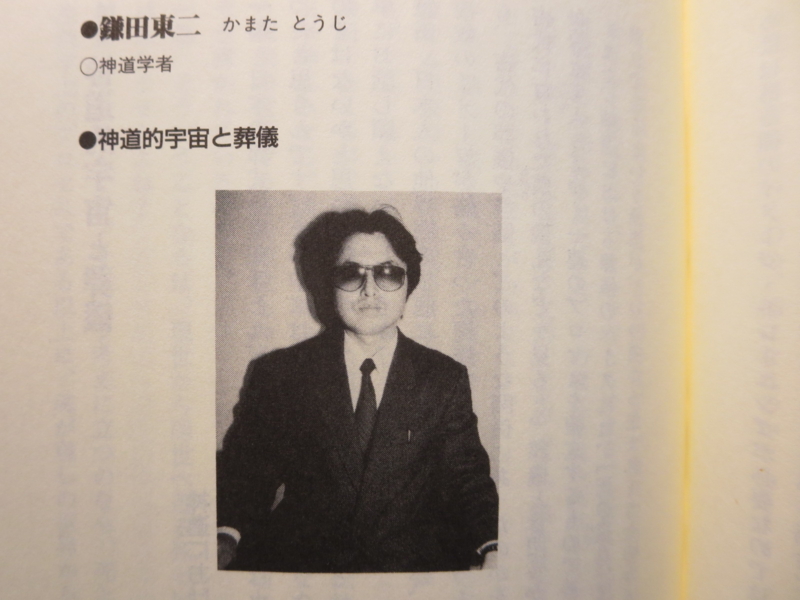 鎌田東二氏
鎌田東二氏
私はね、個人的に葬式は簡素でいいと思っているんです。いまでもインドへ行きますと壮大な葬式がありまして、配り物もすごい。あれほどではないにしても、明治時代の葬列というのも似たようなものだったのではないかと考えているのです。つまり、ごく一部の金持ちが盛大な葬式を出して、貧しいも者に恵むという感じがあるのです。けれど、民主的な社会というのは、こうした恵むというお金持ちの優越感みたいなものを消してきた。それはそれで、いいことだったのです。(井上章一)
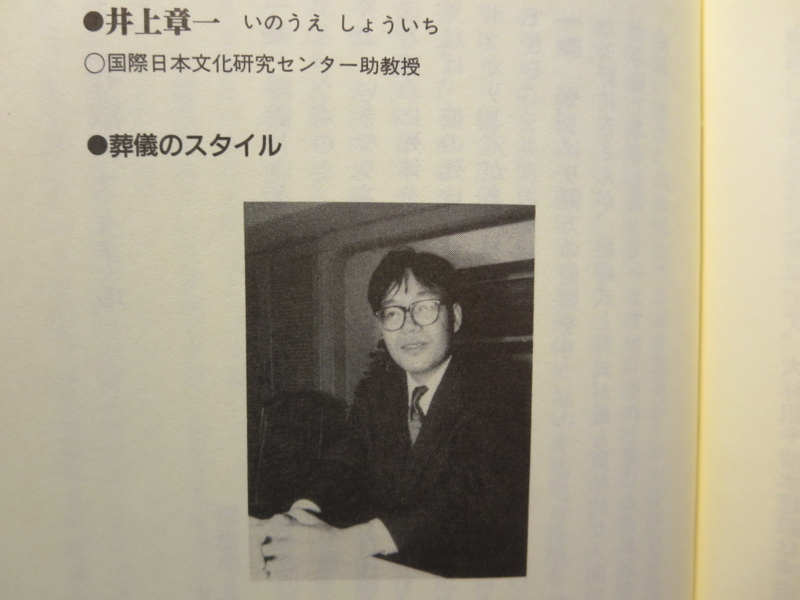 井上章一氏
井上章一氏
死というものは、基本的に暗くていいのです。その暗さが神聖さや荘厳さにつながればいいのです。ベートーベンの「葬送行進曲」だって厳かなものじゃあないですか。やはりそのように演出効果を考えているんですよ。ただしね、暗さはいいけれども陰気はいけません。陰気の中には神聖さも荘厳さもありません。そうではなく、黄泉の世に続く闇の世界、その徹底した暗さの中で、人間の精神が死との直面を体験する。そのほうが、葬儀としての価値があるのではないかと思いますね。(飛岡健)
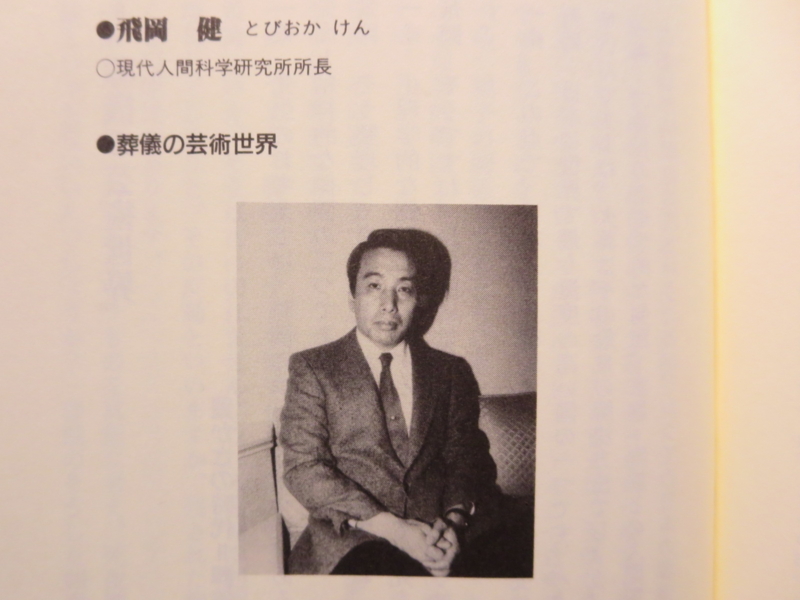 飛岡健氏
飛岡健氏
たとえば、ヨーロッパでは教会が、日本ではお寺が死の問題の処理をしてきているでしょう。でも、それはまさに葬儀という、それも表層的意味としての葬儀を司っているにすぎないですから。死の問題、死を迎えること、死を考えることまではフォローできていない。死を考えるのが人間なんですね。人間が死を考えはじめた、その表れが実は葬儀だったわけですけれどもね。だから、「臨死」カルチャーセンターとしての葬祭会館で死を考えたり、死を研究したり、新しい次元で死の文化を生み出したり、生活に取り組んだりすることができれば、素晴らしいですね。人間である限り、死の問題を避けて通ることはできないんですよ。
(星野克美)
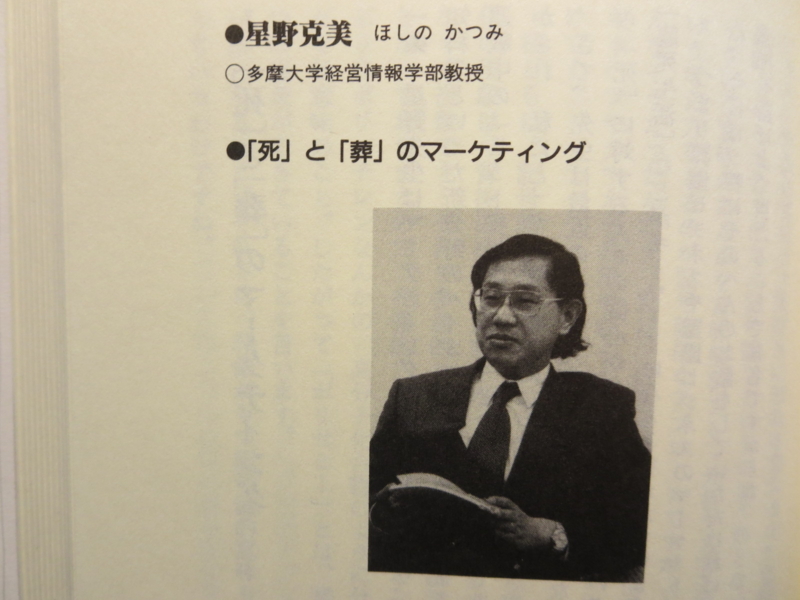 星野克美氏
星野克美氏
やはり葬儀というものの上に立って、仏教も成り立っていくんじゃないでしょうかね。葬儀をやっておりさえすれば、寺もやっていけるわけですからね。それから檀家制度という一番くだらないものができまして、そのために坊主がこの檀家はわしのもの、寺もわしのものというふうになってきましたから、葬式仏教だと言われても仕方がないんじゃないでしょうかね。(高田真快)
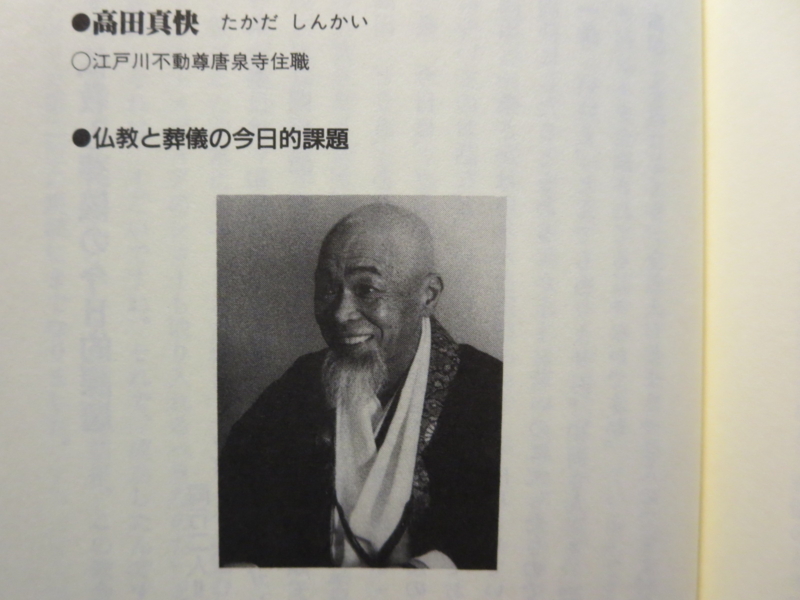 高田真快氏
高田真快氏
空間演出の究極は、最後に残っている匂いだとか光だとか、そういうものですよね。デザインでつくっている空間というのは、生者のためであって、あとの音だとか光だとか匂いというのは、やっぱり死者に贈るものだと思いますね。
物質からだんだん魂に移行していく。バイブレーションが変わっていくんだ。そのうちに黙っていても、その中に、違う次元にいるなっていう、デザインをしなきゃいかんよね。いまの葬祭場のデザイン見たら、モダンデザインなんですよね。これなんか一見きれいだけれどね、きれいなだけで、全然幻想性もなければ神秘的でもない・・・・・・。(毛綱毅曠)
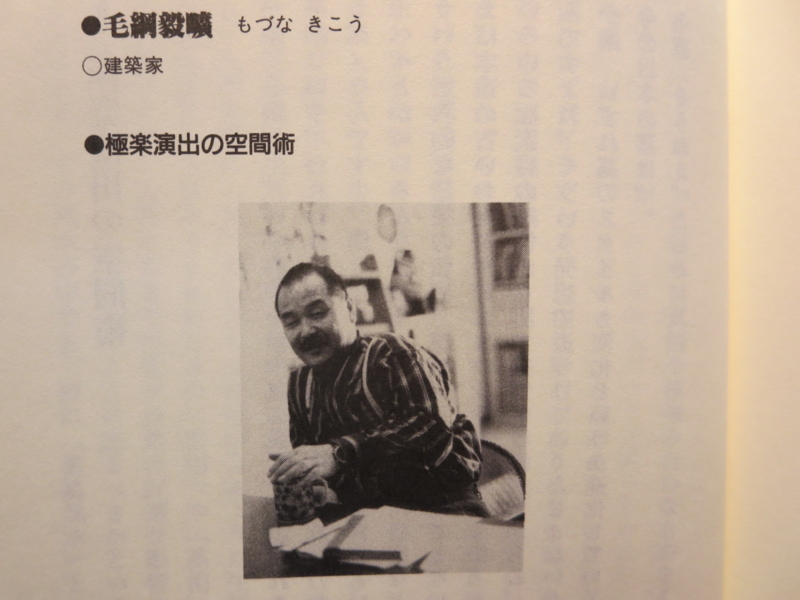 毛綱毅曠氏
毛綱毅曠氏
われわれは死ぬために生きているんじゃなくて、死後の世界も存在しているということを認識すれば、こちらの生の世界に対する認識の仕方とか、生き方とかそういったものに大きく影響してくるし、そうすると今の社会的、文化的状況だって大きく変わると思うんです。だから今までの文明というのは、そういう死後の世界とかそういうものを認めた上で成り立っている文明ではないでしょう。一部、そういう文明もありますけどもね。まず、それが大きく変わるでしょうね。霊的なものを認めてないということを前提にしたいわゆる近代主義というのはもともと非合理なものを排除してしまって、論理的、言語的なものだけを知性として受け入れている。だから、われわれはその恩恵をこうむったり、その被害を受けたりしているわけだけれども、そのへんのところがいま、大きいテーマになっているし、一条さんがやろうとしていらっしゃる事業とかにも関わってくると思うんですよね。(横尾忠則)
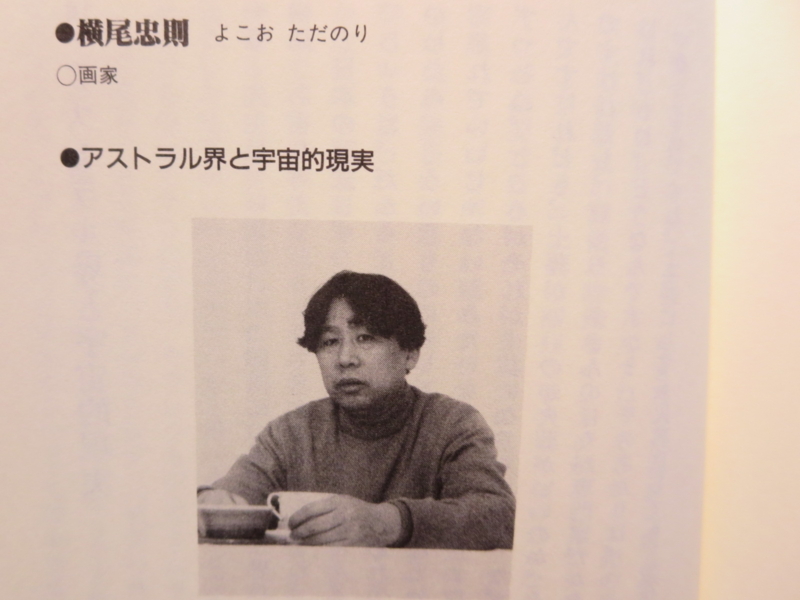 横尾忠則氏
横尾忠則氏
私は、いつの時代も人々の死生観というのは、その社会の文化の核をなしてきたと思うんです。死について考えることは、人間や世界や宇宙や神について考えることでもありますからね。そこから、哲学、芸術、宗教などが生まれてきて、文化を形成していくわけです。
(一条真也)
 当時のわたしは28歳でした
当時のわたしは28歳でした
こうやって先生方の発言を読み返してみると、横尾先生が「そのへんのところがいま、大きいテーマになっているし、一条さんがやろうとしていらっしゃる事業とかにも関わってくると思うんですよね」などと言われていることに新鮮な驚きをおぼえました。あの大芸術家がわたしの事業について気にかけて下さっていたなんて、よく考えたら大変なことです。横尾先生以外にも、みなさん、今後の葬儀文化についてじつにさまざまな具体的提案をして下さいました。それは、サンレー や紫雲閣 の事業発展を願っておられるわけでは別にないと思います。また、葬祭業界の発展を願っているわけでもないでしょう。それは、きっと「日本人が幸せに旅立てる良き葬儀を実現してほしい」という願いをわたしに託されたのではないでしょうか。
『魂をデザインする』は『ロマンティック・デス~月と死のセレモニー』(国書刊行会)の後に同じ版元から刊行されましたが、10の対談の時期は『ロマンティック・デス』の刊行時期と前後しています。前半の山口昌男、井之口章次、山折哲雄、鎌田東二、井上章一、飛岡健の各氏は1990年の11月から12月にかけて、後半の星野克美、高田真快、毛綱毅曠、横尾忠則の各氏は92年の1月に、それぞれ対談させていただきました。
この約1年間は、日本人の死生観が大きな転換期を迎えた時期と重なっていたように思います。すなわち、脳死問題にはじまって、安楽死、尊厳死、臨死体験など、人間の死が社会的に大きな関心を集め、さまざまな議論がなされました。また、日本最大の宗教団体である創価学会が僧侶のいない友人葬をスタートさせ、海洋散骨をはじめとする自然葬、関西の葬祭会館で話題になったハイテク葬、わたしが『ロマンティック・デス』で言及した宇宙葬や月面葬もマスコミなどでよく取り上げられました。まさに、それら一連の現象は、現代人の死生観が根底から大きく揺らぎはじめたことの現れではないかと思いました。
 本書の対談で鎌田東二先生と出会いました
本書の対談で鎌田東二先生と出会いました
10人の対談者の中で、わたしの人生に最大の影響を与えたのは、現在は義兄弟となった鎌田東二先生です。くだんの不識庵さんは、本書の書評ブログで次のように述べています。
「ラディカルな宗教学者・鎌田東二氏と若きロマン主義プランナーとの運命的な出会い。勿論、火薬庫の爆発は、引火という外的な誘因によるものですが、どの程度の爆発になるのかは、引火の方法とタイミング、火薬の質と量によって異なるのです。”運命的な出会い”が運命的なる所以。私がイチオシの一条本がこの『魂をデザインする』である理由もここにあります。
『ロマンティック・デス』は、いわば満月の夜のベスビアス・スターマイン。この対談をきっかけとして、もたらされたハートフルなビックバンこそ、一大事件だったのです。この「一大事件」が現在も一条氏の精神的な支柱となっているのではないでしょうか。その証拠に『ハートフル・ソサエティ』、『隣人の時代』など、ハートフル・ランドでは様々な魅力を持った花火が毎年上がり続けています。その意味で、この『アンソロジー』のような対談本の価値は、私にとっても計り知れないものがあります」
「あとがき」では、わたしは次のように述べています。
「すべての対談を終えてみて確認したことは、葬儀に対する考え方は『死生観』につながり、それが『人生観』や『世界観』、ついには『宇宙観』にまで広がっていくということである。先生方は、最初は葬儀というテーマで語りはじめられたけれども、最後はその思想の全貌を垣間見せてくれた。葬儀というテーマは、思想や生き様をのぞく窓なのかもしれない。これほど、人間の心を広角度で見渡すことのできる窓も他にないと思う。私にとって、10の対談はかけがえのない知的冒険の旅であった」
 まさに「魂」の十番勝負でした
まさに「魂」の十番勝負でした
日本人の死生観が大きく変わりはじめた1992年の時点で、いま行われている葬儀について検証し、未来の葬儀像を描いておくことは、将来の日本人の死生観や精神生活のためにも重要な意味を持つ。そのように確信して、わたしは本書を上梓しました。
最後に、もしも本書の続編として『魂をデザインする PART2』を刊行するとしたら、今ならどういったメンバーと対談したいか。考えるだけなら自由なので、正直な思いを述べさせていただくと、やはり荒俣宏氏とは対談させていただきたいですね。他には、美輪明宏、北野武、角川春樹、村上春樹、よしもとばなな、桑田佳祐、茂木健一郎、佐藤優の各氏、そして最後に島田裕巳氏と対談したい。それぞれの方々に「あなたは、どういう葬儀をお望みですか?」と問うてみたい。これが、現在の率直な気持ちです。
