- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2353 マーケティング・イノベーション | 経済・経営 『日本企業はなぜ「強み」を捨てるのか』 岩尾俊平著(光文社新書)
2024.09.08
『日本企業はなぜ「強み」を捨てるのか』岩尾俊平著(光文社新書)を紹介します。増補改訂版『日本“式”経営の逆襲』というサブタイトルがついています。著者は、慶應義塾大学商学部准教授。平成元年佐賀県生まれ。東京大学大学院経済学研究科マネジメント専攻博士課程修了。東京大学史上初の博士(経営学)を授与され、2022年より現職。組織学会評議員、日本生産管理学会理事を歴任。第73回義塾賞、第36回組織学会高宮賞、第37回組織学会高宮賞、第22回日本生産管理学会賞、第4回表現者賞等受賞。主な著書に『13歳からの経営の教科書』(KADOKAWA)、『日本“式”経営の逆襲』(日本経済新聞出版)、『イノベーションを生む“改善”』(有斐閣)など。
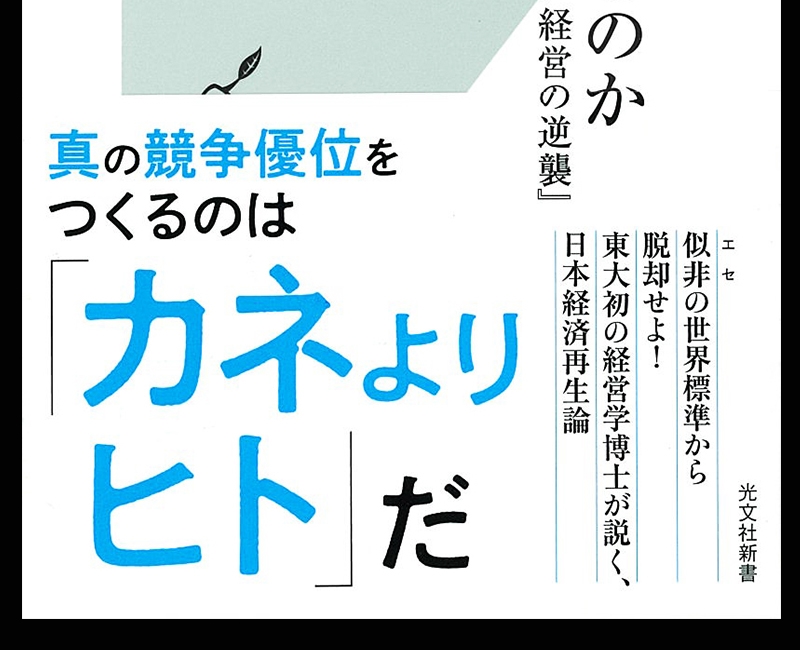 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、「真の競争優位をつくるのは『カネよりヒト』だ」「似非の世界標準から脱却せよ! 東大初の経営学博士が説く、日本経済再生論」と書かれています。また、カバー前そでには、「かつての日本企業が抱いていた「お金より人が大事」という考え方は決して理想主義ではなく、実利に適ったものであり、それこそがビジネスを繫栄に導く強みであった。しかし、日本企業はいつしか人より金に走り、アメリカ式の経営を表層的に真似し、低生産性と低賃金の低空飛行に陥った。どうすれば、この『負のスパイラル』を抜け出せるのか? 東大史上初の経営学博士にして平成生まれの慶大准教授が放つ、渾身の日本企業再生論」と書かれています。
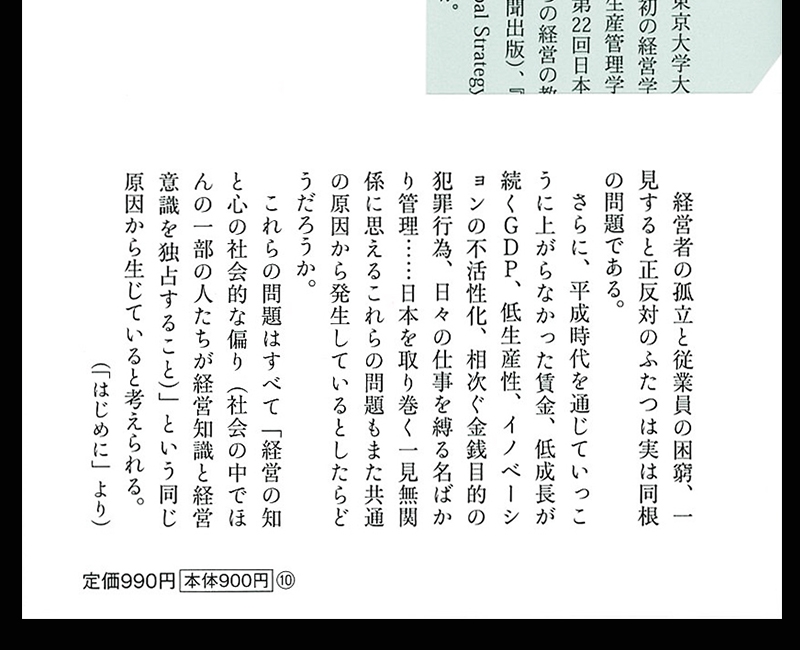 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、以下のように書かれています。
「経営者の孤立と従業員の困窮、一見すると正反対のふたつは実は同根の問題である。さらに、平成時代を通じていっこうに上がらなかった賃金、低成長が続くGDP、低生産性、イノベーションの不活性化、相次ぐ金銭目的の犯罪行為、日々の仕事を縛る名ばかりの管理……日本を取り巻く一見無関係に思えるこれらの問題もまた共通の原因から発生しているとしたらどうだろうか。これらの問題はすべて『経営の知と心の社会的な偏り(社会の中でほんの一部の人たちが経営知識と経営意識を独占すること)』という同じ原因から生じていると考えられる。(「はじめに」より)」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに:日本が失った経営」
序章 日本の経営をめぐる悲観論は正しいのか
第1章 逆輸入される日本の経営
第2章 実践一辺倒の日本、コンセプト化のアメリカ
第3章 経営技術をめぐるグローバル競争時代を生き抜くために
第4章 長年にわたる日本企業の強みもメイド・イン・アメリカに?
第5章 最新シミュレーションで日本の経営技術をよみがえらせる
第6章 コンセプト化とグローバル競争の先にある未来
「増補改訂版へのあとがき」
「参考文献」
「はじめに:日本が失った経営」の「『ヒト優位の経営』と『カネ優位の経営』」では、著者は「経営の知と心が一部の人に独占されてしまうからこそ、経営人材ではない多くの人の賃金は上がらず、経営発想が生れないためにGDPも低成長にとどまり、イノベーション実現のために協力し合えず、価値創造から金銭を得る方法が分からずに犯罪に手を染める人が増え、他者の力を引き出す経営ではなく他者を監視する名ばかり管理がはびこる」と指摘します。これに対して、過去の日本式経営は、少なくとも理念型・理想型としては、「すべての人が価値創造の主役」と考えて、この「経営の知と心の社会的な偏り」をなくす試みだったといいます。
過去の日本の経営においては、名実ともに価値創造の主役はカネではなくヒトだった時期があると指摘し、著者は「その背景にあったのは、昭和という『インフレ下の経営』である。ここで、インフレとは、相対的にカネの価値が下がりヒトやモノの価値が上がることを指す。反対に、デフレとは相対的にカネの価値が上がり、ヒトやモノの価値が下がることを指す。振り返ってみれば、平成の経営は、デフレという、カネ優位の時代におけるヒト軽視の経営だったのである」と述べています。
「『ヒトよりカネ』の似非世界標準経営からの脱却」では、その後の日本には「ヒトよりもカネが大事」な似非世界標準経営が広まったことが指摘されます。現代の日本では、コーポレート・ガバナンスの仮面のもとに、カネを守るためにヒトにムダな書類を作らせ、ムダな時間を使わせ、ムダな監視をするといった、経営とはいえない「名ばかり管理」が横行していると指摘し、著者は「成長のために真に必要なコーポレート・ガバナンスの理念を曲解した管理が蔓延っているのである。反対にアメリカをはじめとする海外では、たとえば『心理的安全性』や『ティール組織』等の議論にみるように、ヒトを大事にする経営への志向が強まっているにもかかわらず、である。その意味で、日本において流行するアメリカ式経営は『似非』世界標準、『似非』アメリカ式経営に過ぎない」と述べます。
日本の主流派が「カネよりヒト」から「ヒトよりカネ」の経営に変わったことで、経営者にとっての従業員は「同じ経営人材として経営者と一緒に価値を付加にする仲間」ではなくなりました。経営知識と経営意識が共有されていないから、経営者と従業員が仲間ではなくなるとして、著者は「こうして経営者は孤立し、従業員は仲間として尊重されずに困窮する。『経営を一緒に考えられる仲間がいない』と嘆く経営者も、『経営者が自分を尊重してくれない』と悩む従業員も、どちらも経営知識と経営意識の組織内での偏りによって生まれているのである。今こそ、日本に住むすべての企業人は、『日本式経営の自己破壊・逆輸入』の弊害を認識すべきだ。なぜなら、日本式経営の自己破壊・逆輸入は、『強みを捨て、弱みを取り入れる』という完全な愚行であり、日本企業の存続を危うくするからだ」と述べるのでした。
序章「日本の経営をめぐる悲観論は正しいのか」の冒頭を、著者は「世界的な企業家たちが、過去から現在にいたるまで、日本の経営に注目し続けている。たとえばあのアマゾンの創業者で、いまや世界有数の大富豪でもあるジェフ・ベゾスは、日本の経営から現在でも多くを学んでいると公言している。そんな主張に触れると、この本を手に取っていただいた方の多くは『そんなバカな』という反応をされるだろう。なぜなら昨今よく聞く言説とは真逆の主張だからだ。そんなわけないだろう、日本の経営は世界と比べて遅れているのだから、というのである」と書きだしています。
その反対に、アメリカと日本の関係を長期観察してきた実務家や一部の研究者など、ごく少数の方々からは「世界的な企業家が日本の経営に注目しているなんて、そんなあたりまえのことを、何をいまさら」という反応があるかもしれないとしながらも、著者は「だが、流行りの言説に騙されず、現状をきちんと認識しないと、日本企業にとってきわめて現実的なデメリットがある。流行に右往左往することで企業経営の土台が危うくなる、あるいは本来得られた利益を逃す。これは、企業経営者、リーダー、従業員、コンサルタントなど日本に住むすべての人にとって不幸をもたらすだろう」と述べています。
第1章「逆輸入される日本の経営」の「『両利きの経営』ブームの源流はどこに」では、近年、両利きの経営という概念が流行していることが紹介されます。2019年にはチャールズ・オライリー教授とマイケル・タッシュマン教授による『両利きの経営』(東洋経済新報社)の日本語訳が出版され、話題を呼びました。ここで「両利き」とはAmbidexterityの日本語訳であり、両利きとか二刀流などとも訳すことができます。では経営におけるAmbidexterityとは何と何の二刀流かといえば、それは既存の技術や知識などの活用(深化・深耕)と探索であるとされます。つまり、既存のビジネスでしっかりと稼ぐことと、新しいビジネスを始めたりイノベーションを引き起こしたりすることとを両立する経営という意味だといいます。
「ユーザー・イノベーション、フリー・イノベーションと現場の知恵」では、ユーザー・イノベーションが取り上げられます。これは、企業内の研究者や開発者ではなく、その製品の利用者に新製品開発を一部任せることによってイノベーションを創出するという、経営コンセプトのことです。たとえば、マウンテンバイクというアイデアは、山登りや山下りを自転車でおこなう特殊な趣味の集団から生まれたとされます。このように、消費者の中には「自分で製品を作ってでも自分が持つ問題を解決したい」という人たちが存在します。しかも、消費者は大抵の場合、なんらかの職業についていたり何かを学んでいる学生だったりするのです。著者は、「つまり、いってしまえば消費者は多分野の専門家でもあるというわけだ。そんな消費者の発想や知識を利用して製品開発しようというのがユーザー・イノベーションである」と説明します。
ユーザー・イノベーションを少し違った視点からみてみると、日本企業はある意味では半世紀前からこの分野のトップランナーでした。著者は、日本企業において「ユーザーがイノベーションの主な担い手になってきた」ところがあると指摘し、それは小集団活動と全社的品質管理(TQC)であるといいます。小集団活動やTQCというのは、製造設備の使用者である作業者が主体となって、製造品質を向上させるためのアイデアを提案することを指します。製造設備のユーザーがその設備そのものや、設備の新しい使い方に関してアイデアを出すのです。そのためにQC(品質管理)サークルといわれるチームが組織されます。そのチームにおいてみられるのは、アイデアを提案すること自体で作業者が満足し、作業者が課業後に相互に協力し、そうして提案されたアイデアが職場で拡散していくというプロセスです。著者は、「ほとんどデジャブのようである。そう、まさしくQCサークルはユーザー・イノベーションなのである」と述べるのでした。
「リーン・スタートアップとリーン思考」では、著者は以下のように述べます。
「究極の話、材料の買掛金支払期間よりも顧客からの売掛金回収期間のほうが短ければ、実は運転資金は0円でもいい。そんな会社があるだろうか。実はあるのである。完璧ではないがそれに限りなく近い企業はある。それは、グーグルなどの情報通信産業に属する企業群である。これらの企業は毎日のように売上が上がってくるが、支払いの中心は人件費や開発費用であり、たいていは支払いまでには猶予がある。現代のスタートアップ、特にインターネットを主戦場とするスタートアップには、リーン・スタートアップの考え方が非常によく適用できる。トヨタ生産方式の究極の形はグーグルなのである」
第2章「実践一辺倒の日本、コンセプト化のアメリカ」の「知識創造理論、QRコード、コールドチェーンという希望」では、QRコードが取り上げられます。QRコードは、もともとトヨタ自動車の一次サプライヤーであったデンソーによって開発されました。そもそもは、トヨタ自動車から送られてくる「カンバン」を読み取るためのものとして研究されたのがQRコードの始まりです。カンバンとは、完成品在庫・中間在庫の量をコントロールするために、生産指示書としての機能を持たせた札のことです。トヨタ生産方式とは、「必要なときに、必要なものを、必要なだけ」生産する経営技術の体系です。そして、トヨタ生産方式の最終段階として「早く作りすぎない」ように、カンバンの数だけ生産させるようにしたのです。
「第2章への補足:日本式経営の強みを活かしてイノベーション創出へ」では、「日本式経営の強みは、イノベーション創出の必要性が叫ばれる今こそ再認識すべきである」と訴えます。トランジスタラジオ、カラオケ、胃カメラ、インスタントラーメン、新幹線、ウォークマン、家庭用ゲーム機……日本はあらゆる分野に革新をもたらしたイノベーション大国だったとして、著者は「日本がイノベーションを生み出せなくなったのは、むしろ中途半端に似非アメリカ式経営を取り入れた時期以降である」と述べます。こうした日本式経営の強みは、①経営教育により経営成果が得られやすくなる、②何事も他人の協力を得なければ実現できない、という2つの仮定から、簡単な計算によって驚くべき結論が得られるといいます。すなわち、「経営成果は、経営教育が普及している人数乗で、向上していく」という結論です。
また、価値創造の民主化においては、仕事を楽しく作り変えることと生産性を上げることが両立できうるし、実際にそれらを両立させる人材が産官学のリーダーとして尊敬されることになるといいます。価値創造の民主化がただの理想ではなく現実になりうる理由があり、それは「資源は有限でも価値創造は無限だ」ということです。著者は、「人類は有史以来、数百倍を優に超えるほどの経済発展を遂げた(こうした試算の1つにマディソン推計がある)。だが、その間に、地球の質量は隕石と太陽光の分くらいしか増えていない。それどころか、人工衛星の打ち上げ等によって、地球の質量は減っているかもしれない」と述べています。
資源を組み換えて、人間にとっての価値を創り出すことで、経済発展が生み出されてきたのです。そして、価値創造の余地が無限であるならば、価値を奪い合う必要はなくなります。この場合、価値は協働して創り出すものに変わるからです。そのためには、価値創造に貢献すべく経営意識と経営知識が多くの人に共有されている必要があるとして、著者は「このように、価値創造は無限に可能だと気付くことが、価値創造の民主化の前提条件なのである」と述べるのでした。
第6章「コンセプト化とグローバル競争の先にある未来」の「おわりに:日本式経営は『これから』だ」の冒頭を、著者は「日本の経営は過去の一時期、世界を席巻した。しかし現在では、こうした過去を知る者は少なくなってきた。そして、日本の経営がすべてダメだといわんばかりの悲観論・自虐が蔓延したのである。そうした中で、もともと日本企業の経営技術に根差していたコンセプトがアメリカ経由で世界中に広まり、日本に逆輸入されるといった状況が生みだされてしまった。本書はこうした状況を『経営技術の逆輸入』と呼んだ。こうした逆輸入状況によって、日本の産官学が『強みを捨て、弱みを海外から取り入れる』という失敗をおかす可能性もあった」と書きだしています。
日本がこうした状況に陥ったのは、第一に、根拠なき悲観論や自虐的自己評価によって、アメリカ発コンセプトを適切に評価できないことにありました。第二に、これまで日本企業や日本社会は、文脈に深く依存した緊密なコミュニケーションを強みにしてきたため、逆にいえば文脈に依存しない、誰にでも伝わるコミュニケーションを苦手としてきたことも、こうした状況をまねいた一因といえるとして、著者は「より具体的には、抽象化・論理モデル化と、それを前提にした議論とを苦手にしてきたのである」と述べます。そして第三に、そもそもアメリカがコンセプト発信のプラットフォームをおさえてしまっているという理由もあると指摘します。
「増補改訂版へのあとがき」では、著者の提案する「価値創造の民主化」という解決策は地味だが実行可能性があるとして、「すべての人が『人間こそが価値創造の主役であり、価値創造の障害となる対立を解消し続けるのが経営だ』という考えを持とう。すべての人が名実ともに価値創造の主役になろう。そのための経営教育が全国どこでも無償で受けられるようにしよう。それだけである」と訴えます。最初は「人間こそが価値創造の主役であり、価値創造の障害となる対立を解消し続けるのが経営だ」というただの信念でよいといいます。その信念の結果として、すべての人に開かれた経営教育が家庭・学校・職場でおこなわれて実際に価値創造力が向上すれば、実績が信念を強化するというのです。
こうして信念と実績が互いに強化しあう循環が起これば、ヒトを大事にすることや、金融商品や土地ではなくヒトに投資することが実際に利益を生むようになるとして、著者は「そうなれば、『ヒトよりカネ』の風潮から『カネよりヒト』への転換が合理的となる。しかも、令和における(昭和と同様の)インフレ下の経営は、間違いなく追い風になるだろう。これこそが、単なる懐古主義ではない、真の意味での『日本式経営の逆襲』への第一歩である」と述べるのでした。
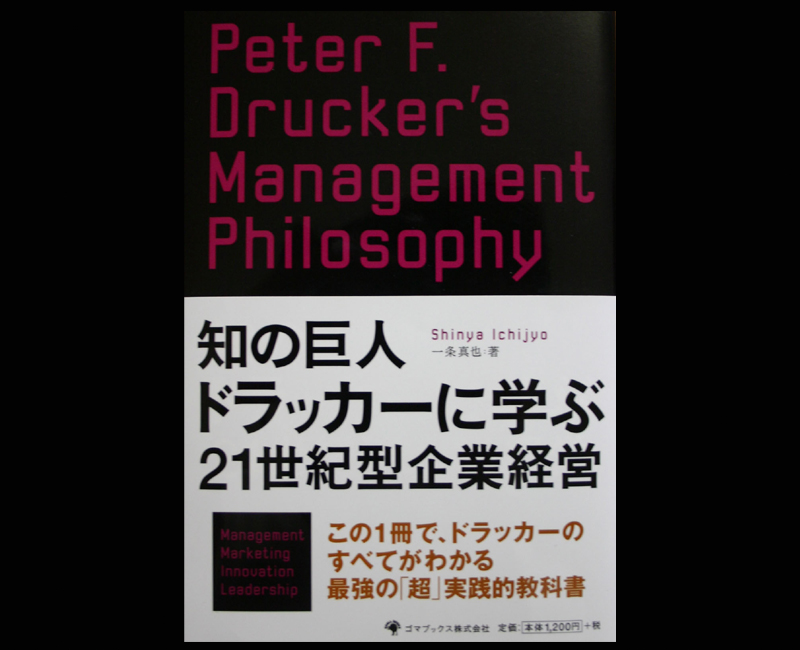 『知の巨人ドラッカーに学ぶ21世紀型企業経営』(ゴマブックス)
『知の巨人ドラッカーに学ぶ21世紀型企業経営』(ゴマブックス)
わたしも経営者の端くれですが、本書には共感する部分が多々ありました。著者の岩尾氏は「東大史上初の経営学博士にして平成生まれの慶大准教授」ということで非常に優秀な方ですが、経営学者ピーター・ドラッカーの影響を強く感じました。拙著『知の巨人ドラッカーに学ぶ21世紀型企業経営』(ゴマブックス)では、「人が主役」こそドラッカー経営論の根幹であると訴えましたが、本書『日本企業はなぜ「強み」を捨てるのか』にも「人が主役」の思想を強く感じました。各章の最期にいちいち「補足」が入るという論文調の記述方法はちょっと硬かったですが、久々にドラッカー理論の香りを嗅げて嬉しかったです。なお、著者は「本書の内容は自由に要約・紹介していただいて構わない。書影や各ページの画像、図表などについても、筆者は著作権を一切主張しない。もし本書がすこしでも現状に対する動揺を引き起こしたとしたら、それをSNS、チャット、ブログ等で周囲にも伝えていただけると、これ以上なく幸甚である」と書いていますが、素晴らしいことです。ひたすら著作権を主張する売文屋などではなく、岩尾俊兵氏には「日本式経営を蘇らせたい」という高い志があるのだと思います。