- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2024.09.09
『わたしの知る花』町田そのこ著(中央公論新社)を読みました。著者から献本されたサイン本を汚すのが怖くて、新たに購入した本を読みました。しみじみと感動し、心が温かくなりました。著者は、現代日本を代表する人気作家です。映画化もされた一条真也の読書館『52ヘルツのクジラたち』で紹介した名作で本屋大賞を受賞。その他、一条真也の読書館『ぎょらん』や『夜明けのはざま』で紹介した葬儀小説の大傑作をはじめ多くのベストセラーがあります。
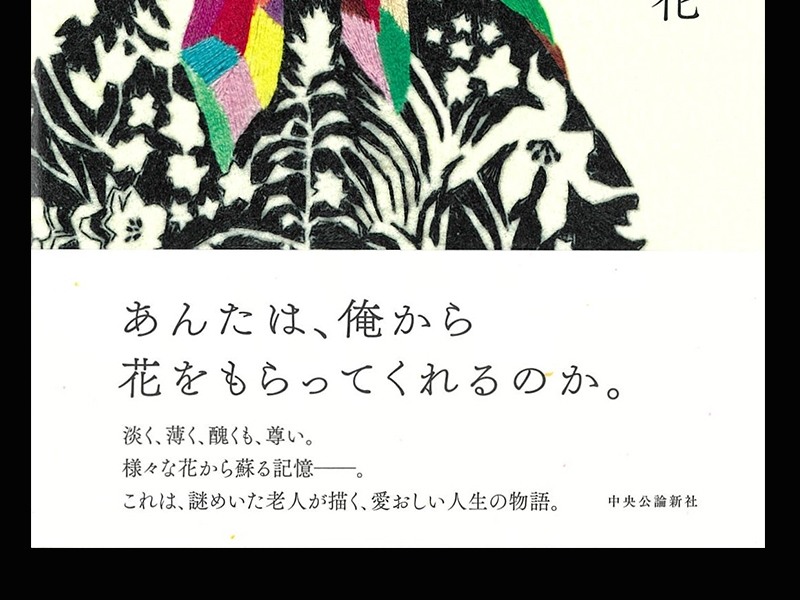 本書の帯
本書の帯
本書のカバーには宮城高子氏の「マルチクロス」「私も南口」が装画として使われ、帯には「あんたは、俺から花をもらってくれるのか。」「淡く、薄く、醜くも、尊い。様々な花から蘇る記憶―。これは、謎めいた老人が描く、愛おしい人生の物語。」と書かれています。
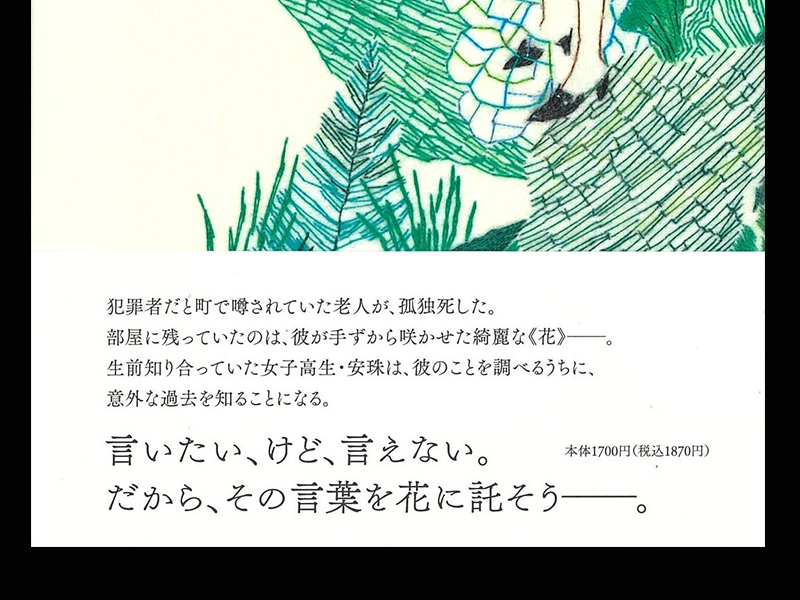 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、「犯罪者だと町で噂されていた老人が、孤独死した。部屋に残っていたのは、彼が手ずから咲かせた綺麗な“花”―。生前知り合っていた女子高生・安珠は、彼のことを調べるうちに、意外な過去を知ることになる。」「言いたい、けど言えない。だから、その言葉を花に託そう――。」と書かれています。
本書の「目次」は、以下の通りです。
一章 ひまわりを花束にして
二章 クロッカスの女
三章 不器用なクレマチス
四章 木槿は甘い
五章 ひまわりを、君に
エピローグ
正直に言うならば、最近のわたしは小説を読む余裕などはありませんでした。もうすぐ89歳になる父の容態がおもわしくなく、毎日かなりの時間を実家で父の側にいるからです。わたしの趣味といえば読書と映画鑑賞が代表的ですが、どちらも最近は時間を取ることができません。映画館で約2時間連絡を断つこともできないので、映画を観ていません。本も、仕事の資料などは読みますが、小説を読む時間的余裕と心の「ゆとり」がないのが現状です。
 『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)
『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)
それでも、わたしは本書『わたしの知る花』をたまらなく読みたくなりました。じつは、拙著『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)がPHP文庫化されることになり、その解説を町田そのこ氏が書いて下さることになったのです。PHPの担当者から送られてきた町田氏の解説文を読んだとき、わたしは非常に感動しました。そして、「町田そのこさんという方は、なんて優しいんだろう」としみじみと思いました。すると、町田氏の書かれた小説が無性に読みたくなってきたのです。父が寝ているときや、夜遅く自宅に戻って自分の時間を持てたとき、本書『わたしの知る花』を少しづつ読みました。ようやく読み終えたとき、ここのところ疲れ気味だったわたしの「こころ」に温かいミルクのような滋養が与えられたような気がしました。
本書を読んで、まず感じたのが著者の筆力の凄さです。『愛する人を亡くした人へ』の文庫解説も素晴らしい名文でしたが、著者は小説家なので、その才能と本領は小説でこそ最大限に発揮されるはずです。『わたしの知る花』を読んで、著者の豊かな表現力に唸りました。たとえば、一章「ひまわりを花束にして」では、女子高生の安珠が公園で絵を描いている老人と出会った描写に「しゃがみこんでいたおじいさんがあたしを見上げてくる。口の周りに、そり残しの髭がちらほらあるのが見えた。白髪交じりの短い髭は、冬の庭みたいだった。今は七月の半ばで、すでに夏本番って感じなのに、セミは大合唱してんのに、からだに冬を持っている感じがした。」(P.12)という文章があります。この「冬の庭」という言語感覚には衝撃を受け、「すごい!」と思いました。
また、三章「不器用なクレマチス」では、安珠の幼馴染の奏斗がある老人に「自分が男だっていう確信が持てない」という悩みを告白するとき、「心がとても、あやふやで弱くて、自信を持てないんです。そんなだから、好きな子にも、好きって堂々と言えない。まるで自分が、輪郭のない灰色の塊みたいだ」(P.164)と語ります。この「冬の庭」とか「輪郭のない灰色の塊」といった表現力の高さには「やっぱり、プロの小説家は違うなあ!」と感心しました。奏斗から秘密を告白された老人が過去を思い出す場面の「すごく居心地が悪かった。スナックの女といい仲になりそうだと自慢した相手が愛妻家だと知ったときと同じような、嫌な感覚だった」(P.172)という一文は、思わず笑ってしまいました。うまいこと言いますね~。
『わたしを知る花』には、ミステリーの要素もあるのですが、基本的にはグリーフケアの物語でした。そう、「愛する人を亡くした人」の物語だったのです。ある登場人物にとってとてもかけがえのない大切な人が不幸な事件で亡くなります。その人物は、続いたはずの故人の命や夢を描き続け、追い求めてゆくという、切なくも哀しい物語でした。わたしは、「ああ、この物語を書いた町田そのこさんに『愛する人を亡くした人へ』の解説をお願いして本当に良かった」と心の底から思いました。葬儀という仕事にも関わってきた著者には、死者への想いや温かいまなざしというものが備わっているように感じます。そうでなければ、『ぎょらん』や『夜明けのはざま』などの名作が生まれるはずはありませんね。
さて、本書には、いくつかのキーワードがあると感じました。「家族」と「生きてきた意味」と「縁」と「愛」と「花束」です。まず、「家族」ですが、広告会社に就職したばかりの美園という女性の母親は家族依存症というか、配偶者や子どもに異常なまでに関わろうとします。それは一見、優しく、家族のことを深く愛しているがゆえなのですが、「一人の時間」を大切にしたい美園には負担となっていました。二章「クロッカスの女」には、美園の以下のように書かれています。
子どものころから、集団行動が得意じゃなかった。休み時間はみんなでドッジボールをするよりひとりで本を読んでいたかったし、休日に家族でショッピングに行くよりもひとりで映画を観ていたかった。
決してひとが嫌いなわけじゃないし、社交性に大きく欠けるわけでもないと思う。友達も家族も私なりに好きだし、大事にしてきたつもりだ。学校でも会社でも、できうる限りコミュニケーションをとってきた。ただ、長時間誰かと一緒にいると、だんだんと疲れてきてしまう。私は、自分のためだけの時間がないとだめなのだ。もちろん、誰しもがひとりでふっと息を吐く時間が必要だろう。私は、その時間がひとより長くないといけない人間なのだ。
だから、『常に、一緒に』を求めてくる母とは合わなかった。(『わたしの知る花』P.90~91)
美園の母・紫里は、夫に対しても過干渉でした。毎日のコールは必須で、飲み会は1時間ごとに家に電話。バレンタインデーに貰ったチョコから旅行のお土産まで、ひとから貰ったものは逐一細かい報告を求めました。美園が就職した会社の入社式の日、父は家を出ていきました。母は半狂乱になりました。美園の視点でこう書かれています。
それから一ヶ月後、父から『離婚した』と電話がかかってきた。憔悴した声で『パパの我が儘で、ごめん』と言われて、私は考えた末に『ひとりの時間って、必要だもんね』と返した。父は一拍の呼吸のあと『分かってて、結婚したのにな』と乾いた声で笑った。誰かと一緒の時間を過ごして一緒に年を取るのは当然のことだと思ってた。ぼくの両親も、祖父母たちもそうやって生きてきた。だからぼくもそうすべきだとは分かってる。しあわせじゃなかったわけじゃない。君たちと過ごした時間は尊いし、家族の情だってある。でも、もうひとりでいたいんだ。誰かといる息苦しさに耐えきれずに死を選ぶくらいなら、離れようと思ったんだ。
死、と口にしたとき、父の声が震えた。だから私は、それは正しいよ、と言った。死ぬくらい辛いのなら、それでいいと思う。辛かっただろうに、私が社会人になるまで待っていてくれてありがとう。
紛れもない本心だった。私だって、同じようなものだから。(『わたしの知る花』P.94~95)
この美園と父が求めた「ひとりの時間」、そして「誰かといる息苦しさ」というのは多くの現代人が感じているのではないでしょうか。わたし自身が「ひとりの時間がひとより長くないといけない人間」だと自覚しているので、この文章は心に沁みました。しかし、夫に去られた紫里は、近所人の紹介で訪問介護の仕事に就きます。そして、そこでさまざまな出会いがあり、「働きがい」や「生きがい」も感じていくのですが、病に冒されて亡くなります。母を亡くして初めて母の孤独を知り、母についてもっと知りたいと思った美園に、母から介護を受けていた香恵という女性は「いいこと教えてあげる。私が七十五年生きてきて導き出したことなんだけどね、まっすぐに生きてきたひとは、いつか愛される。まっすぐに誰かを求めたひとは、いつかまっすぐに求められる。背中を、追ってくれるひとが現れる。あなたはこれから、まっすぐに生きたお母さんの背中を追うんでしょう。お母さんとの時間を芯として、お母さんを追う。それで、いいのよ。そういうものなの」(P.137)と語りかけるのでした。
次のキーワードは「生きてきた意味」です。ふつう、人間をはじめとした生物の「生きる意味」とは、子孫を残すだと考える人は多いでしょう。美園やその父は家族である母を疎ましく感じましたが、家族を作りたくて必死になっている人々も存在します。いわゆる不妊治療を受けている夫婦などが最たる例でしょう。四章「木槿は甘い」には、結婚から4年後に不妊治療を受けた風太郎と奈々枝という夫婦が登場します。産婦人科の検査の結果、夫の方に問題がありました。風太郎は精子の数が少なく、また、その運動率が40%未満――軽度の乏精子症かつ精子無力症であるとの診断でした。それからの風太郎は必死であらゆる努力を重ねましたが、1年半後についに心が折れます。ある日、奈々枝に「子どものいない人生を選ばせてくれ」と頭をさげたのです。「頑張ってきたつもりだ。でも、これ以上はもう耐えられそうにないんだ。それに、自然に子どもが授かれないというのなら、自然に反して子を持つべきじゃないってことだと思うんだよ。だから、どうかおれの我が儘を許してほしい」と言いながら、声を殺して泣く夫を前に奈々枝は「分かった」と頷くしかありませんでした。しかし、彼女はこう考えるのです。
あのとき、『ふたりきりで生きる人生』を選ぶことに少しの動揺もなかったとは言わない。むしろ、はっきりと絶望を覚えていた。一年半の間に、わたしの中には『子どものいる人生』の想像が膨らんでいた。女の子だったら、男の子だったら。迎える季節はいつ? 里帰りをするの? それともふたりで頑張ってみる? まち中で見かける親子連れの姿に自分たちを重ね、わたしだったらこうする、でもあのひとみたいな感じもいいかも、なんてしょっちゅう考えた。それらが全部、無に帰した。
(『わたしの知る花』P.200)
奈々枝と風太郎は、子どもをつくること以外に「生きてきた意味」を求めます。ヨガのインストラクターである奈々枝は自分のスタジオを持つことに、風太郎は作家になって作品を残そうとします。また彼は、自身が経営するアパートの住人である葛城平という老人が遺したノートに記された絵物語をSNSで公開しようとします。アパートの一室で亡くなった平という老人は、自分の遺品はすべて処分してほしい」と言っていました。それで奈々枝が平の作品をSNSで公開することは「故人の気持ちをあんまりにも冒瀆していない?」と言って反対します。すると、風太郎は「じゃあ、君は! 彼がちゃんと生きて、紡ぎ続けた成果を無にするのか!?」と怒鳴り、「彼は、絵を描き物語を紡いで生きてきた。ずっとひとりきりで生き、ぼくたちふたりだけにひっそり見送られて、名を記した墓もない。彼があんなに必死に積み重ねてきた痕跡は、誰も知らないままだ。ぼくにはそんなの、嫌だ。ひとは何か残せるって、信じたいんだ!」と叫ぶのでした。
ここで「墓」という単語が出てきましたが、わたしは著書を上梓するたびに「また生前に墓を1つ建てたな」という思いがします。その意味では、著作物を発表するという行為は「生きてきた意味」となるのかもしれません。でも、平のことを知るために夫婦を訪ねてきた安珠によって、奈々枝は「何かさ、わたしたちって『残す』ことに必死になっていたんじゃないかなって思うんだ。でも今日、安珠ちゃんのおかげで、違うって気付けたような気がしてる」「波乱の人生をひとり生きた彼は『何も残さなかった』ではなく『大事なものを残した』。そして彼はきっと『残そう』という気持ちで生きていなかった」(P.233)と語ります。それを聴いた風太郎も、「残ったか残っていないかなんて、自分で決められるもんじゃないんだよね、きっと」(同)と言うのでした。これは、100冊を超える著書を残したわたしの胸に響いた言葉でした。わたしも「残そう」と思って本を書いたことは一度もないからです。「墓を建てたな」というのは、あくまで結果であり、目的ではありません。このことは、すでに立派な墓をいくつも建ててこられた著者の想いでもあるでしょう。
次のキーワードは「血縁」です。
ネタバレにならないように注意しながら書くと、この物語には「あの人物と、この人物は血縁関係にあったのか!」という驚愕の事実が隠されています。その事実は最後に明かされるのですが、非常に感動的なラストが用意されています。血縁は「縁」の1つですが、現代社会では希薄化しているとされます。現代社会は「無縁社会」などと呼ばれますが、この世に無縁の人などいません。どんな人だって、必ず血縁や地縁があります。そして、多くの人は学校や職場や趣味などでその他にもさまざまな縁を得ていきます。この世には、最初から多くの「縁」で満ちているのです。ただ、それに多くの人々は気づかないだけなのです。ちなみに、「縁」という目に見えないものを実体化して見えるようにするものこそ冠婚葬祭だと思います。
ただ、人と人が「縁」を結ぶにはタイミングというものがあります。夫婦になる場合なら、なおさらです。本書の五章「ひまわりを、君に」では、ある男女の登場人物が互いに惹かれ合いながらも、タイミングが合わなかったがゆえに、何度抱き合っても、自分たちの関係が分からず、「最良の恋人になれたタイミングも、よき友人になれたタイミングも、清い思い出を分かち合う旧友になれるタイミングすら、あったはずだった。でもこのタイミングでの関係は、何と形容していいのか分からなかった。正しいのか、正しくないのかさえも。ただ、抱き合うわたしたちの間に、甘く心安らぐ言葉が交わされたことは一度もなかった」(P.322~323)と書かれています。
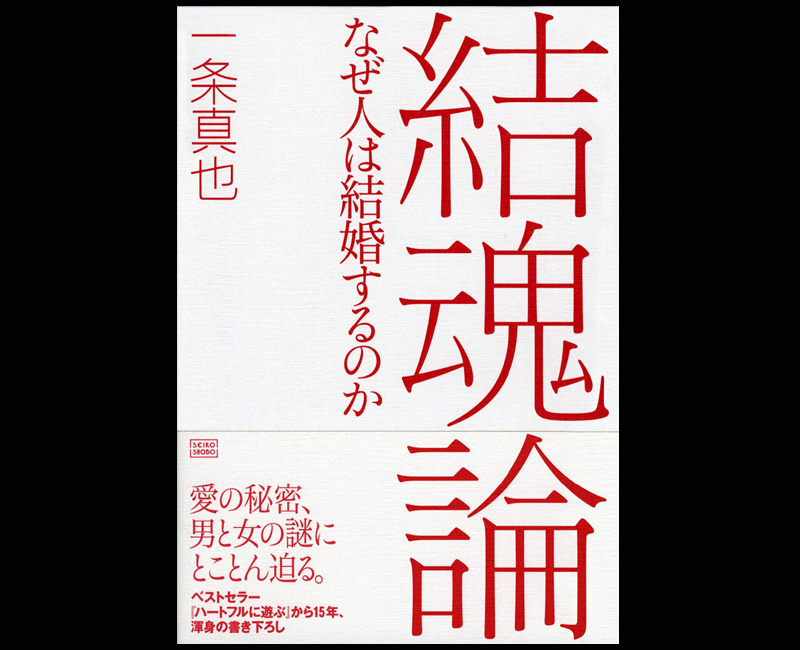 『結魂論〜なぜ人は結婚するのか』(成甲書房)
『結魂論〜なぜ人は結婚するのか』(成甲書房)
拙著『結魂論〜なぜ人は結婚するのか』(成甲書房)に、わたしは「宇宙の歴史が138億年、生命の歴史でも35億年だとされているので、人類の10万年という歴史は長いようにも思えますが、1人の人間が100歳まで生きたとしても千代かかるわけで、やはり途方もない時間の長さです。ましてや宇宙は時間的にも空間的にも人間の想像できるレベルをすでに超えてしまっています。その宇宙の中で、『そもそも、わたしは存在しなかったではないか』という仮定は簡単に考えられます」と書き、「何億年か前の地殻変動のときに日本列島そのものが海底に沈んでいたら」とか、「先祖が関ヶ原の戦いで死に、当家の家系がそこで絶えていたら」とか、「祖父が父の生まれる前に、タイタニック号に乗って沈没事故に遭い、溺死していたら」などの例を挙げました。その最もポピュラーな可能性は「父と母が別の相手と結婚していたら」です。そうなれば、当然ながら、わたしはこの世に存在していません。
 わが両親の結婚写真
わが両親の結婚写真
1961年(昭和36年)5月20日に東京は赤坂のホテル・ニュージャパンで両親は結婚しました。ちなみに、わたしたち夫婦は1989年5月20日に結婚しましたので、両親の結婚からちょうど28年後。結婚記念日は同じです。じつは、わたしはそのことをまったく知りませんでした。このたび、『佐久間進のすべて』という父のムックを作って初めて気づいたのです。不思議な縁を感じました。結婚してから63年の時間が経過しても、両親はとても仲が良いです。闘病中の父はすっかり弱ってしまいましたが、毎日のように母と握手をしています。父は、そのたびに「あんたは、いい顔をしてる」とか「あんたのおかげで、ここまで来れた。本当に、ありがとう」と言います。すると母は、「長生きしてね。ひとりになったら寂しいよ」と言うのです。なんだか泣けてきます。この両親が出会い、愛し合わなかったら私自身が存在していないわけですから、感謝の気持ちでいっぱいです。
そして、「愛」というキーワードが出てきます。ブログ「両親を想って『愛の讃歌』を歌う」で紹介したように、先日のパリ五輪の開会式のフィナーレで、セリーヌ・ディオンがエッフェル塔の上から歌った「愛の讃歌」には非常に感動しました。NBCテレビで開会式のコメンテーターを務めていたケリー・クラークソンはセリーヌ・ディオンを「声のアスリート」と呼びましたが、わたしはまさに「平和の女神」のようだと思いました。「平和」といえば、『わたしの知る花』には「平等」という理想から「平」と名付けられた男性が登場しますが、平は「平等」だけでなく「平和」の平でもあります。セリーヌ・ディオンが「愛の讃歌」を歌う姿は、エッフェル塔の上から、白く光り輝く平和の女神が「人類よ、戦争を止めなさい。そして、愛し合いなさい!」と訴えているようでした。そう、愛とは恋愛から夫婦愛へ、夫婦愛から家族愛へ、家族愛から隣人愛へ、そして人類愛へと進化するのです。ちなみに、父は「人類愛に奉仕する」ということを訴え続けてきました。冠婚葬祭業者としての究極の理想と言えます。
 『花をたのしむ』(現代書林)
『花をたのしむ』(現代書林)
「愛」は目に見えませんが、さまざまな方法で見える化することはできます。その最良の方法が最後のキーワードである「花束」を贈ることではないでしょうか。誰でも恋人には花を贈りたいものであり、恋愛にとって花束は必須のアイテムです。でも、花束を贈る対象は恋人だけではありません。拙著『花をたのしむ』(現代書林)の序文「魂のごちそう、心の万能薬」で、わたしは「職場でのコミュニケーションがうまくいかずに悩んでいる人もいるでしょう。離婚を考えている人もいるでしょう。親の介護をしている人もいるでしょう。わたしたちは、すべてつながっているのです。わたしたち人間は一人では生きていけません。重要なのは『人間』ではなく、『人間関係』なのです」と書きました。誰かに花束をプレゼントすることが、なぜこれほど人間関係を良くするのかという秘密がここにあるように思います。イエスやムハンマドは「愛」を説き、孔子は「仁」を説き、ブッダは「慈悲」を説きましたが、それらすべては他者に対する「思いやり」ということ。最近の言葉でいえば「コンパッション」です。誕生日で、快気祝いで、送別会で、贈られる花束とは「思いやり」そのものなのです。
 町田そのこ氏に花束を贈呈しました
町田そのこ氏に花束を贈呈しました
『わたしの知る花』は、まさに花束の物語でもあります。ひまわりの花束をはじめ、クロッカス・クレマチス・木槿(むくげ)・ポピー・ガーベラといった花束たちが登場します。花束は、「愛」や「思いやり」とともに「感謝」も見える化してくれます。ブログ「町田そのこ氏と対談しました」で紹介した今年5月13日のサンレーグループの全国葬祭責任者会議では、特別対談として町田氏とわたしのトークショーが行われましたが、最後にわたしから町田氏に花束贈呈をしました。わたしが「『ぎょらん』や『夜明けのはざま』を書いていただき、多くの方々が葬儀の大切さを知りました。映画『おくりびと』の原案となった『納棺夫日記』を書かれた青木新門氏もお亡くなりになられましたが、町田そのこさんという希望の光を得ました。また、『ぎょらん』と『夜明けのはざま』は、わが社の社員に深い感動と勇気と仕事への誇りを与えていただきました。本当にありがたかったです。心からの感謝を込めて」と言って花束をお渡ししました。
 花束を持った町田そのこ氏と
花束を持った町田そのこ氏と
それから約4ヵ月後、わたしはまた町田氏に花束をお贈りしたいと思います。『愛する人を亡くした人へ』の素晴らしい文庫解説を書いていただいた感謝の気持ちとしてですが、本書『わたしの知る花』で感動を与えていただいた感謝も込められてます。この素晴らしい作品を読んで、わたしは読書とは「こころの花」を咲かせる行為なのではないかと思いました。本というメディアは書き手が種を宿して、読み手がそれを育てる。種から芽が出て葉となり、そしてゆっくり花を咲かせるように……。わたしの感謝の気持ちを込めて贈る花束は、ひまわりを選びました。町田そのこさんは喜んでくれるでしょうか?
 著者に贈った花束
著者に贈った花束
