- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2024.10.22
『世界と比べてわかる日本の貧困のリアル』石井光太著(PHP文庫)を読みました。著者は、1977年東京都生まれ。作家。世界の物乞いや障害者を追った『物乞う仏陀』(文藝春秋)でデビュー。主な著書に、『絶対貧困』『浮浪児1945ー』『「鬼畜」の家』『43回の殺意』『こどもホスピスの奇跡』(以上、新潮文庫)、『ルポ 誰が国語力を殺すのか』(文藝春秋)、『本当の貧困の話をしよう』(文春文庫)、さらにはブログ『遺体』、ブログ『祈りの現場』、ブログ『無縁老人』で紹介した本があります。海外ルポをはじめとして貧困、医療、戦争、文化などをテーマに執筆してきました。
 本書のカバー表紙の下部
本書のカバー表紙の下部
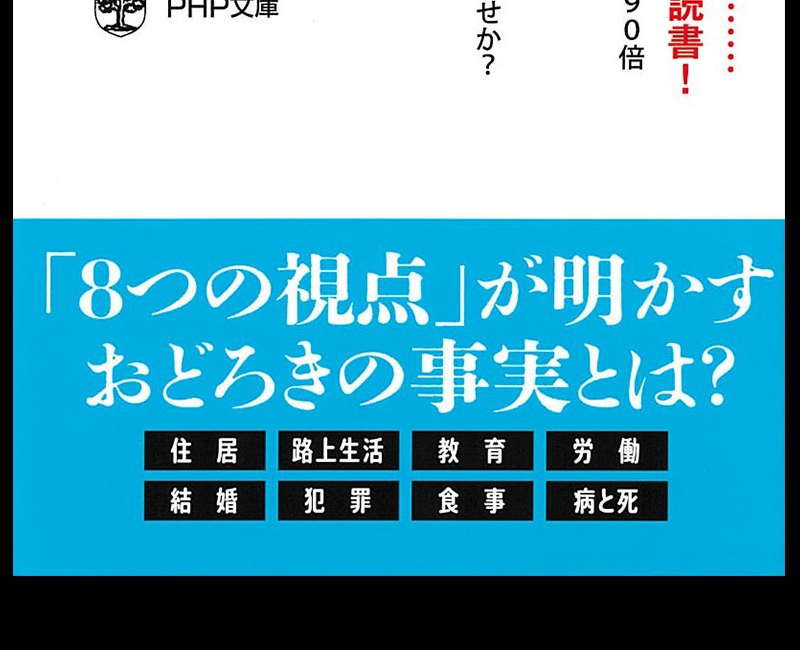
本書のカバー表紙の下部には、「データが明かす『見えない貧困』の真実」「■日本人の6人に1人が『貧困層』」「■世界で7億人超が『絶対的貧困』」と書かれています。カバー前そでには、「日本は先進国中ワースと4位の貧困国」「危険だが『希望はある』途上国の生活……」「この国の『幸せのかたち』お問い直す」と書かれています。
カバー裏表紙には「希望とは何か、貧しさとは何か……豊かさの真実を知るための必読書!」として、「▼日本の児童虐待相談件数は39年で約190倍」「▼途上国における『二重の排除』」「▼日本でなぜ餓死者が出るのか」「▼途上国の『貧困ビジネス』の実態」「▼シロとクロに分断された社会は本当に幸せか?」と書かれ、下部には「『8つの視点』が明かす おどろきの事実とは?」「住居」「路上生活」「教育」「労働」「結婚」「犯罪」「食事」「病と死」と書かれています。
 アマゾンより
アマゾンより
アマゾン「内容紹介」には、「◆日本人の6人に1人は貧困層、世界で7億人超が絶対的貧困……」「◇世界と日本のデータが明かす『見えない貧困』の真実とは?」「◆読めば、この国の『幸せのかたち』が見えてくる!」「世界第3位のGDPを誇る日本。しかし実際には、『先進国中ワースト4位の貧困国』であると聞けば、驚くだろうか。その理由は、日本の貧困は、いわゆる途上国の貧困とされる、『絶対的貧困』とはまったく形態が異なる『相対的貧困』だから。貧困という言葉は同じでも、絶対的貧困と相対的貧困は、その性質が大きく異なる。本書では、途上国の絶対的貧困と、日本の相対的貧困を、8つの視点から比較することで、現代社会における『本当の貧しさとは何か』を考える。読めば、貧しさとは何か、希望とは何か、豊かさとは何か――その片鱗が見えてくる一冊」と書かれています。
 アマゾンより
アマゾンより
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
第一章 住居
コミュニティー化するスラム、
孤立化する生活保護世帯
第二章 路上生活
家族と暮らす路上生活者
切り離されるホームレス
第三章 教育
話し合う術をもたない社会、
貧しさを自覚させられる社会
第四章 労働
危険だが希望のある生活
保障はあるが希望のない生活
第五章 結婚
子どもによって救われるか、破滅するか
第六章 犯罪
生きるための必要悪か、
刑務所で人間らしく暮らすか
第七章 食事
階層化された食物、
アルコールへの依存
第八章 病と死
コミュニティーによる弔い、
行政による埋葬
「あとがき」
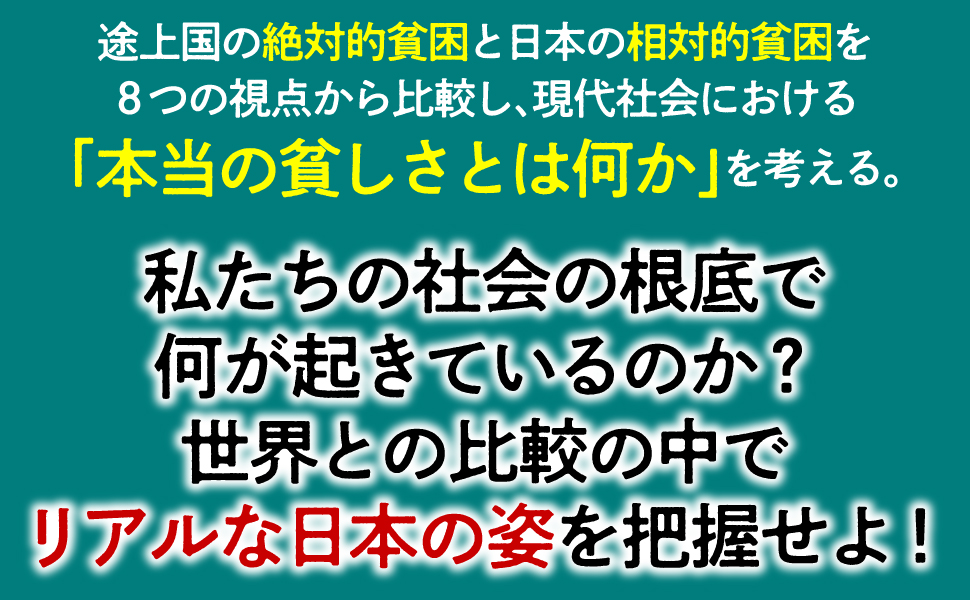 アマゾンより
アマゾンより
第一章「住居」の「(途上国)過密状態のスラムでの暮らし」には、生活環境の二大要素は、住居と人間関係であることが指摘されています。しっかりした住居に暮らしている人は災害や感染症から身を守れるし、家族や地域のコミュニティーとの関係が良好な人は他者と協力し合って困難を乗り越えることができるとして、著者は「生活が成り立つには、この両輪が機能する必要がある。しかし、貧困はそうした生活環境に悪影響をもたらし、住居や人間関係を劣悪なものにする。ただし、途上国なのか先進国なのかによって、貧困が及ぼす影響はまるで異なるものになる。まったく別の貧困問題として表出するのだ」と述べます。
スラムとは、不法占拠によってつくられた居住地のことを示します。地方で農業や漁業をしていた人たちは、災害や病気や借金などで暮らしていけなくなった時、仕事を求めて都市にやってきます。しかし、彼らはお金がないのでマンションなど住居を借りることができません。そこで、町外れの空いている土地を見つけ、無許可で「バラック」と呼ばれる小屋を建てて暮らすのです。このバラックがたくさん集まって居住区となったところがスラムです。著者は、「スラムの住民たちが従事するのは、肉体労働、工場労働、運搬業、清掃業といった低賃金の仕事だ。スラム内に仕事はあまりないので、先に述べたようにダウンタウンに働きに行くのが一般的だ。収入は1日働いて数百円といったところで、生きていくのに精いっぱいの金額しか得られない」と述べます。
「(日本)福祉制度による孤立」では、戦後間もない頃をふり返れば日本にも貧しい人たちの同質性の高いコミュニティーは存在したことが指摘されます。「朝鮮人部落」と呼ばれた被差別地区などです。朝鮮半島出身の人たちが身を寄せ合って集まり、差別や貧困から協力して身を守っていたのです。町によっては、沖縄や奄美大島からの移住者が集まる地区などもありました。同じ文化的背景を持った人が助け合って暮らすコミュニティーという意味では、途上国のスラムのそれと類似しているといえるだろうとしながらも、著者は「だが、現代の都市では、そうしたコミュニティーはほとんど消え失せたといっても過言ではない。原因は、経済の発展に伴って、町の構造や人間関係のあり方が変わっていったからだ」と述べます。
日本の生活困窮者たちがコミュニティーの代わりに手に入れたのが、国の福祉制度でした。人と人とのつながりに頼って生きるのではなく、国が提供する生活保護だとか、児童手当だとか、介護保険制度といった制度に依存するようになったのです。著者は、「たとえば、昔の貧困地域では近隣住民たちが協力して子育てをしたり、お年寄りの介護をしたりしていた。それが今では国の保育サービスや介護サービスが取って代わっている。あるいは、かつて家に食べ物がなければ、近隣住民に米を借りたり、差し入れをもらったりしていた。「困った時はお互い様」と言って、持ちつ持たれつの関係が築かれていた。今はそれがなくなり、人々は食べ物がなくなれば隣人ではなく、自治体のフードバンクや生活扶助に頼っている」と述べています。
かつてあったコミュニティーの相互扶助システムは、公的支援に移行しました。人々が公的支援に乗り換えたのは、利便性の高さゆえでした。コミュニティーの相互扶助システムには、お互いの距離が近くなる分、多くのしがらみが発生し、時にそれは息苦しさを伴うものだったとして、著者は「人々は公的支援によって、そこからの脱却を図ったのだ。ところが、それは優れた面ばかりではなかった。人と人との濃厚なネットワークを失ったことで、生活困窮者たちは『孤立・孤独』の問題に直面することになったのである。現在、日本社会で起きている貧困問題を思い浮かべてほしい。結婚できずに独身で生きていく若者、アパートの密室で行われるDVや虐待、8050問題、独居老人の孤独死……。これらの根底には、孤立と孤独という共通点がある」と述べます。
途上国の人々や昔の日本人はわずらわしい人間関係の中で助け合いのネットワークを築いていたのに対し、今の日本人は制度に依存することによって孤立し、孤独に陥っていると指摘する著者は、「日本の貧困支援の現場では、度々こうした問題点が指摘され、孤立・孤独の予防の必要性が説かれてきた。そこでよく提案されるのが、地域コミュニティーを新たに結成させたり、既存のそれに生活困窮者を参加させようという解決策だ。だが、それは簡単なことではない。生活困窮者がコミュニティーに参加する時の壁は大きく2つある」といいます。1つ目が、低所得で苦しむ人々が抱えているパーソナリティーの問題です。2つ目として挙げられるのが、彼らが貧困ゆえに抱えている劣等感です。著者は、「日本では、低所得であることは劣っているとか、恥だとかいう意識が強い。これは社会に渦巻く自己責任の考え方が大きいだろう。彼らに能力がなかったり、努力しなかったりしたから、困窮していると決めつけられがちなのだ」と述べるのでした。
第二章「路上生活」の「(日本)ホームレスが直面する五重の排除」では、日本ではすべての人は「健康で文化的な最低限度の生活」が営めるという建前があり、数多の福祉制度が用意されていると指摘されます。ここでいう最低限度の生活の基準が、生活保護といえます。社会活動家の湯浅誠氏は、著書『反貧困』で、人間がホームレスのような境遇に落ちる背景として、以下の「五重の排除」を挙げています。
1.教育課程からの排除:教育を受けられないことで社会的な地位を得られない。
2.企業福祉からの排除:職を得られなかったり、得ても十分な給与をもらえない。
3.家族福祉からの排除:困窮したときに頼ることのできる家族がいない。
4.公的福祉からの排除:生活保護、障害年金等の公的福祉を受けられない。
5.自分自身からの排除:社会復帰に対する希望を抱くことができない。
湯浅氏によれば、社会には人間が貧困の底に転落しないように1~5のセーフティーネットがあるといいます。通常はこのうち、どれか1つに引っかかれば最低限の生活を営むことができますが、すべてから排除された時、人は最低限度より下の生活を余儀なくされるのです。「(途上国)途上国における二重の排除」では、途上国のセーフティーネットは「家族福祉」と「自分自身」の2つしか存在しないことが指摘されています。率直にいえば、スラムの人々は、いつ自分が社会からドロップアウトしてもおかしくないという不安を抱えているのです。
著者は、途上国の人々は「日頃からコミュニティー内の結束を高め、助け合うことによって、いざ自分が逆の立場になった時に手を差し伸べてもらえるようにしているのだ」と述べます。また、「(日本)いったん落ちると這い上がれない」では、2022年度の厚生労働省による「ホームレスの実態に関する全国調査(概数調査)」によれば、日本には3448人のホームレスがいるとされていることが紹介されます。20年前の2万5000人と比べると、今は支援団体の数も増え、統計上のホームレスの数は6分の1近くまで減っています。
「(途上国)家族みんなで暮らす路上生活者」では、都市の経済は、何万人、何十万人といった路上生活者によって支えられている実態があることが指摘されます。彼らが荷物運び、清掃、皿洗い、建設業、廃品回収といった3K(「危険」「汚い」「きつい」)の仕事をするから町は成り立っています。それを理解しているので、無暗に排除しようとは考えないのです。スラムでは住民たちが相互扶助を目的としたコミュニティーを形成しています。これと同じことが、路上生活をする人々の間にも見られるとか。
路上での生活には、スラムより多くのリスクが潜んでいます。道端に家具を置いていれば盗まれかねませんし、子供たちがはしゃいで走り回っていれば交通事故に遭いかねません。夜に年頃の女性たちだけでいれば、犯罪者や変質者に目をつけられることもあります。著者は、「彼らはそうした危険から身を守るためにコミュニティーをつくる。大体、3~5くらいの家族で一緒に暮らし、代わる代わる荷物を見守ったり、子供の世話をしたりするのだ。仕事を融通し合う、食費を分担する、高齢者の介護をするといったことも行う」と述べるのでした。
第四章「労働」の「(途上国)もし仕事を失ったとしたら」では、途上国のスラムなどでは、人々が職を失った時、コミュニティーの相互扶助システムが機能するということが指摘されています。しかし、コミュニティーに入っていなかったり、何かしらの事情で相互扶助システムが機能しなかったりすれば、彼らは自力で命をつないでいくしかありません。著者は、「そんな彼らが生き延びる手段の1つが経済難民になること、つまり他国へ『出稼ぎ』に行くことである。自国より豊かな国へ移り、そこで働くことで生活の糧を得るのだ」と述べています。
第五章「結婚」の「(日本)貧困から抜け出す手段か、生活レベルの低下か」では、途上国では結婚は将来の生活を安定させるための手段となっている一方で、日本の若者は結婚に対して逆のイメージを抱きがちだと指摘しています。著者は、「日本人は、憲法や制度によって最低限度の生活を保障されている。そのため、途上国のように結婚をセーフティーネットと捉える意識がなく、逆に『結婚をしたら生活レベルが落ちてしまう』と否定的に考えるのだ」と述べています。確かに、日本で著しい非婚化、少子化の大きな原因であると、わたしも思います。
「(途上国)路上生活者にとっての家族」では、路上生活をしていれば、変質者に襲われるとか、人身売買のブローカーに捕まるとか、酔っ払いにからまれるといったことが起こりやすいことが指摘されます。著者は、「親としては、そんな環境で娘をいつまでも1人にさせておきたくない。だから、早い段階で信頼できる男性を見つけてきて、結婚させようとするのだ。つまり、結婚が子供の身の安全を守るための手段になっているのである。これは治安の悪い国で行われる児童婚についても同じことがいえる」と述べています。これは一体、どういうことでしょうか?
犯罪が横行しているような社会では、年頃の子供が1人でフラフラと歩いていれば、どんな犯罪に巻き込まれるかわからりません。子供の方も教養がないのでだまされやすかったりします。それゆえ、早いうちに結婚をさせることによって、リスクをできるだけ減らそうとするのです。著者は、「先進国の人たちの中には、児童婚を一概に悪と捉えて批判する人がいる。しかし、親や国家が若者を守れない状況にあっては、早婚は逆に子供の安全を保障するものとなっている。社会の状況によって結婚の持つ意味もだいぶ違ってくるのである」と述べます。
第六章「犯罪」の「(日本)社会の成熟が生み出す『完全な黒』と『完全な白』」では、日本においては終戦直後の混乱の中で、テキヤの存在が一定の役割を担っていたことが指摘されます。しかし、戦争から数年が経つと、警察は本来の権力を取り戻すようになっていきました。すると警察はテキヤに治安維持を任せる必要がなくなり、彼らを市場から締め出すようになりました。著者は、「これまで必要悪ということで見逃してきた闇市やテキヤを排除し、合法的な市場を作り上げていったのだ。最終的には、テキヤは表の世界から居場所を奪われ、地下活動によって存続を図らなければならなくなる。警察はそんな組織を『暴力団』としてさらに弾圧していく。現在、俗にテキヤ系とされている暴力団の一部はその生き残りだ。ここからわかるのは、社会の状況によって犯罪組織が『必要悪』と見なされるか、『完全悪』と見なされるかが分かれるということだ」と述べています。
第七章「食事」の「(途上国)稼いだお金の大半が食事代に」では、日本にいると食糧危機を肌で感じることは少ないかもしれないとしながら、著者は「WFP(国連世界食糧計画)によれば、現在の世界の飢餓人口は8億2800万人に上っており、毎日3万人の子供たちが飢餓によって命を落としている。ここで『飢餓』について考えてみたい。国連やNGOの報告書では度々この言葉を見かけるが、食事をとれずに餓死寸前に追いつめられている状態だけでなく、極端に栄養が偏った状態も含まれる。つまり、栄養が摂取できていない栄養失調と、栄養に偏りができている栄養不良の両方を示すのだ」と述べています。
「(日本)栄養価の高い炊き出し」では、世界でも日本食は安くて美味しいと評判であるとして、著者は「格差という視点から見た場合、日本では階層によって食べる料理がまったく違うということはあまりない。もちろん、日本にもアワビ、マツタケ、伊勢海老、松阪牛といった高級食材はある。だが高所得者だからといって毎日それらを食べているわけではないし、低所得層の人々だって毎日食パンの耳やカップ麺だけを食べているわけではない。そう、日本における食の特徴は、階層ごとに厳密に分かれているのではなく、料理自体は同じものを食べていることだ。具体的にいえば、高所得者だって牛丼やたこ焼きやソバを食べるし、低所得者だって寿司やステーキを食べる。よほどのことがない限り、たこ焼きを食べたことのない富裕層はいないだろうし、寿司を食べたことのない貧困層もいないはずだ」と述べます。
「(途上国)貧困フードの危険性」では、絶対的貧困層の人々の食事は、栄養計算された料理ではないことが指摘されます。胃を膨らますためにライスやパンだけを食べていれば栄養は偏りますし、ぶっかけメシや揚げた魚の頭などの貧困フードの中には人体に有害なものが含まれていることもあります。貧困層の子供たちの最大の死因は、「肺炎」と「下痢」となっていると指摘する著者は、「免疫力の低下によって、不衛生な環境の中で感染症にかり、肺炎や下痢といった症状で簡単に命を落としてしまっているのである。国連もこうしたことに懸念を示しており、5歳までに亡くなる子供の3人に1人が栄養不足が原因と指摘している。逆にいえば、栄養をとれていれば、ここまで子供の死亡率が高くなることはなかったはずなのだ」と述べるのでした。
第八章「病と死」の「(途上国)『死体乞食』で最期を迎える」では、著者は「いつか人間は死を迎える。それはすべての人間が等しく受け入れなければならない運命だ。しかし、その人が亡くなった後に、どのように遺体が処理されるかは平等ではない。その人の経済力によって、埋葬の仕方に違いが出るのだ。途上国のスラムや路上で闘病している人がいれば、家族やコミュニティーの人たちが看病をする。そして、その人が死去すれば、家族やコミュニティーの人たちが死後の始末を行うことになる。どの国であっても、遺体を埋葬するには多少なりとも費用が発生するものだ。火葬する場合は、薪代、棺代、埋葬代などがかかる。土葬の場合にも、遺体の搬送、お清め、穴掘りなどにチップが必要だ。絶対的貧困層の人たちにとって、これらの費用は大きな負担だ」と述べています。
ネパールでは、薪を使って火葬をしようとすれば数万円かかり、廃タイヤを使用する安価な火葬でも数千円は必要です。あるいは、パキスタンの公営墓地で土葬をしようとしたら、墓地までの搬送費や、穴掘り担当者への謝礼として数千円はかかります。よくインドでは薪代のない貧しい人たちはガンジス川に焼かずに捨てるといったことが語られるとして、著者は「たしかに私自身、ガンジス川で焼かれずに浮かんでいる遺体を目にしたことは何度もある。しかし、全体的にはそうしたことはごく稀だ。家族など周りの人たちは、亡くなった人の尊厳を守り、できるだけ丁寧に葬ろうとする。故人や家族に貯金がなかった場合は、親戚や友人からカンパを募るとか、知人に金を借りるなどして自分たちができる範囲の葬儀を行う」と述べます。
世間の人たちに慈悲を乞うことで埋葬代を集める人々が世界には存在するのです。なぜ、金に困っているはずの路上生活者までもがやってきて、寄付をしてくれたのか。関係者はその理由を著者に「路上に暮らしている人は、みんな明日は我が身だと思っている。事故や病気でいつ死ぬかわからないからね。だから、彼らは同じような境遇の人たちが困っていれば、少しでもできることをしておくんだ。そうすれば、いざ自分が死んだ時に、周りの人たちが援助してくれるからね」と説明したそうです。途上国の相互扶助システムの根底にあるのは、自分がつらい状況に陥った時に助けてほしいという気持ちです。それがあるからこそ、彼らは多少の無理をしてでも他人に手を差し伸べようとするのです。
「(日本)豊かな国でどう死ぬか」では、低所得の人たちは仕事をしていても、雇用形態や勤務形態から孤立しているケースが少なくないことが指摘されます。家で急死しても、それを確かめる人がいないのです。それゆえ、発見が遅れることになります。もう1つ、目を向けなければならないのが、身寄りのない生活困窮者の埋葬についてです。著者は、「一般的に、日本で独居やホームレスの人が亡くなれば、自治体が親族に連絡をして事情を話し、遺体の引き取りを依頼する。親族が承諾すれば、彼らが自腹を切って葬儀から埋葬までを執り行う。ところが、自治体から連絡を受けた親族の方が、遺体の引き取りを拒否することがある」と述べています。
親族が遺体の引き取りを拒否するのは、生前に故人との関係が悪かったり、経済的に引き取る余裕がなかったりするケースが大半です。著者は、「こうなると、自治体自らその遺体の処理をしなければならなくなる。この際、自治体は契約している地元の葬儀会社に業務を委託するが、1人当たりの予算は決まっている。地域によって差があり、1、2級地(東京23区などの大きな町)なら大人が20万1000円、小人が16万800円、3級地(地方の小さな町や村)だと大人が17万5900円、子供が14万700円となっている。業者はこの金額ですべてを行わなければならない。だが、現実的にはこの金額で葬儀から火葬、そして納骨までを行うのは難しい」と説明します。
「おわりに」では、日本は、児童虐待、教育格差、不登校、人工妊娠中絶、家庭内暴力、孤独死など貧困とかかわる多様な課題を抱えていると指摘します。それらの大半は、人がコミュニティーから切り離され、制度に依存することによって、孤立するところからはじまっているといえるだろうとして、著者は「物理的な貧しさからは脱却したはずなのに、精神的な貧しさの中で悲劇が起きているのだ」と述べます。このことを思う時、著者は1つの言葉を思い出すといいます。今から40年ほど前に日本を訪れたマザー・テレサが、バブル経済に浮かれている日本人に投げかけた以下の言葉です。この言葉は、「日本という国が抱えている問題の核心をついているといえる」と、著者は述べるのでした。
飢えとは食物がない、ということではありません。愛に飢えるのも、飢えです。老人や身体障害者や精神障害者やたくさんの人が誰からも愛されないでいます。この人たちは、愛に飢えています。このような飢えはあなたの家庭にもあるかもしれません。家庭に老人がいるかもしれません。病人がいるかもしれません。この人たちにほほえみかけたり、一杯の水をあげたり、いっしょに座ってしばらく話をしたりすることで、あなたは神への愛を示すことができるのです。日本のような豊かな国にも、このような飢えを感じている人がたくさんいます。人間の愛とはどんなものか忘れてしまった人たちがたくさんいます。誰も愛してくれる人がいないからです。ですから、さっそく実行しましょう。愛の喜びを周囲の人々にあげるように。まず家庭で、それから隣近所の人々へ。
(中井俊已『マザー・テレサ愛の花束』PHP文庫)
