- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2371 プロレス・格闘技・武道 『Gスピリッツ選集 第一巻 昭和・新日本篇』 Gスピリッツ編(辰巳出版)
2024.12.10
『Gスピリッツ選集 第一巻 昭和・新日本篇』Gスピリッツ編(辰巳出版)を読みました。『ゴング』の遺伝子をもつ雑誌『Gスピリッツ』に連載されたプロレス関係者のインタビュー記事を集めた本です。昭和プロレスに関しては知り尽くした感もありましたが、本書を読んで、新たな新事実をたくさん知ることができました。
 本書の帯
本書の帯
表紙カバーには猪木と坂口の黄金タッグが並んだ「新日本プロレス ビッグ・ファイトシリーズ」(1973年4月20日・蔵前国技館)のポスター写真が使われ、「〈証言〉坂口征二 藤波辰爾 北沢幹久 柴田勝久 永源遥 新間寿 大塚直樹 櫻井康雄 舟橋慶一」と書かれています。帯には、「誰もが熱狂した金曜夜8時の格闘ロマン」「永遠に色あせないプロレスがここにある」と書かれています。帯の裏には、「プロレス専門誌『Gスピリッツ』に掲載された貴重な証言をテーマ別に再編集した待望の選集第1弾」と書かれています。
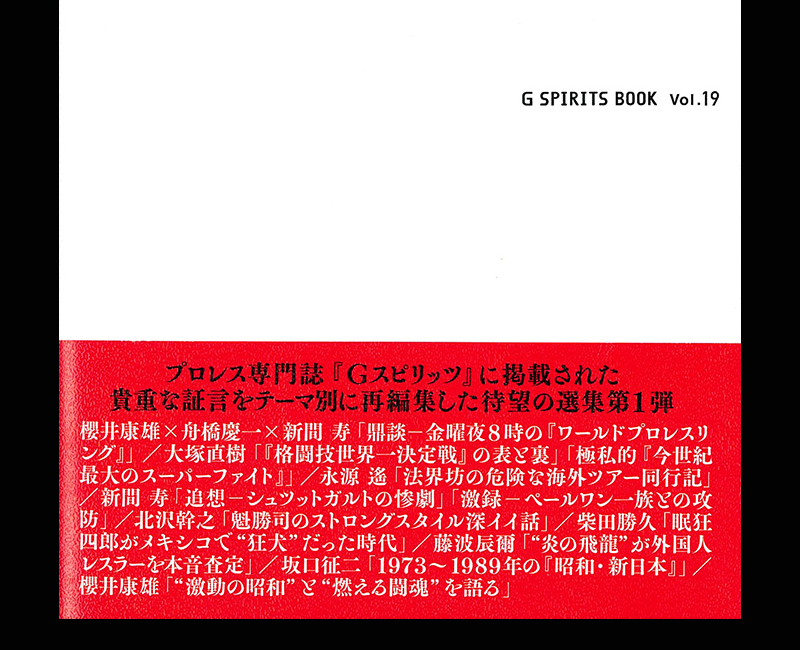 本書の帯の裏
本書の帯の裏
アマゾンの内容紹介には、こう書かれています。
「Gスピリッツ(タツミムック)に掲載された貴重な証言をテーマ別に再編集した待望のアンソロジー! 第一巻は『昭和・新日本篇』と題して、大きなムーブメントを巻き起こした『格闘技世界一決定戦』はもちろんのこと、ハプニングの連続だった海外遠征、全日本プロレスとの企業戦争、そして絶対的なエースだった“燃える闘魂”アントニオ猪木の思い出などをレスラー、フロント、マスコミが濃密に回顧。貴重な写真も満載なので、あの熱かった時代を今一度、本書でご堪能あれ!」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
[鼎談―闘魂実況コンビ×過激な仕掛け人]
金曜夜8時の『ワールドプロレスリング』
■櫻井康雄×舟橋慶一×新間寿
[昭和・新日本プロレスの格闘ロマン]
『格闘技世界一決定戦』の表と裏
■大塚直樹 元新日本プロレス営業部長
極私的『今世紀最大のスーパーファイト』
■大塚直樹 元新日本プロレス営業部長
法界坊の危険な海外ツアー同行記
■永源 遙
追想―シュツットガルトの惨劇
■新間寿 元新日本プロレス営業本部長
激録―ペールワン一族との攻防
■新間寿 元新日本プロレス営業本部長
[旗揚げメンバーの回想]
魁勝司のストロングスタイル深イイ話
■北沢幹之
眠狂四郎がメキシコで〝狂犬〟だった時代
■柴田勝久
追悼―柴田勝久1943~2010
“炎の飛龍”が外国人レスラーを本音査定
■藤波辰爾
[副社長兼ブッカーの回想]
1973~1989年の「昭和・新日本」
■坂口征二
[元東京スポーツ編集局長の回想]
〝激動の昭和〟と〝燃える闘魂〟を語る
■櫻井康雄 元『ワールドプロレスリング』解説者
「プロフィール一覧」
「Gスピリッツ初出一覧」
2012年3月刊行の『Gスピリッツ』23号に掲載された「金曜夜8時の『ワールドプロレスリング』」では、元テレビ朝日アナウンサーで「ワールドプロレリング」を実況した舟橋慶一が、当時の新日本プロレス中継の時間が30分であることに触れ、「今、中継が30分ということは試合がダイジェストでしょ。それは野球でホームランのシーンばかり見せられるのと一緒ですよ。そこに至るまでの流れがわからないと面白さは半減しますよね。僕は一番いい時代に実況していたと、つくづく思いますね。猪木さんはテレビをものすごく有効に使った人で、カメラに向くアングルなんか最高でしたよ。我々には言わないけど、卍固めにしても必ずテレビカメラを意識してやっていたはずだから。なおかつ観客の歓声も全部聴こえているし、相手との間合いも計算して、瞬時に今、自分は何をするべきかを判断できる人でしたね」と語っています。
2015年6月刊行の36号に掲載された「法界坊の危険な海外ツアー同行記」では、アントニオ猪木の海外遠征に何度も付き添い、多くの異種格闘技戦のセコンドを務めた永源遥が、1980年2月27日に蔵前国技館で行われたアントニオ猪木vsウィリー・ウィリアムスの一戦について、「俺は常に飛び込める体勢でいたし、ラウンドが終了するたびに猪木さんが安全になる位置に立っていましたよ。でも、あれはどっちがいい悪いじゃなくて、緊張感のある試合だったね。空手側のエキサイトぶりは確かに異常だったけど、考えようによっては気持ちが純粋なんだと思いますよ、異種格闘技戦をやっていたころは、熱い時代でしたね。みんなが純粋だったんですよ」と語っています。インタビューアーの「その熱い時代に、猪木さんは最前線で戦っていたんですよ」と言うと、永源は「たとえ控室でゴロッと横になっていても、いろいろ考えていたと思いますよ。何だかんだ言っても、猪木さんは大したもんだねえ。自分に自信がなければできませんよ」と語るのでした。
2008年6月刊行の7号に掲載された「追想―シュツットガルトの惨劇」では、“過激な仕掛け人”と呼ばれた元新日本プロレス営業本部長の新間寿が、“地獄の墓堀人”ことローラン・ボックが猪木へ挑戦したときのことを語ります。未知の男からの挑戦表明に、新間は親しいスポーツ紙の記者に調査を依頼。その記者から受けた報告は、「ボックはろうあ者で、レスリングに集中できるから物凄く強い」というものでした。新間は、「ちょうどニューネッシーが話題になっていた頃なんだけど、世の中にはまだまだ知られていない生物がいるんだなというのと同じように、世界には我々が知らない格闘技があって、とてつもない力を持った選手がいるんじゃないかと思ったね。逆にボックとしたら、モハメド・アリと戦った“東洋の神秘”である猪木さんを呼んだらヨーロッパでセンセーショナルなニュースになるということだったんだろうけど」と述懐しています。ニューネッシーというのは、77年4月にニュージーランドオキで引き揚げられた首長竜に似た謎の巨大腐乱死体です。そんなUMA(未確認生物)とボックが同一視されていたとは面白いですね。考えてみれば、当時のテレビ朝日はかの「川口浩探検隊」シリーズを放映中でした。猪木の「格闘技世界一決定戦」も「川口浩探検隊」と同じような濃いファンタジーだったのかもしれません。
そのボックから招聘されたヨーロッパ・ツアーでは、11月23日のオランダ・ロッテルダム大会で思わぬハプニングが起きました。1964年東京五輪の柔道無差別級金メダリストとして鳴り物入りでプロレスに転向し、全日本プロレスに上がって話題を集めたアントン・ヘーシンクが出場する予定でしたが、なんとドタキャン。猪木との一騎打ちが現地で大々的に宣伝されていましたが、当日になって会場に現れなかったのです。これに怒った1972年ミュンヘン五輪の柔道無差別級金メダリストのウィレム・ルスカが「同じオランダの柔道家として俺が代わりに猪木とやってやる」と名乗りをあげて事なきを得ました。このヘーシンクのドタキャン劇の裏には、複雑な事情があったようです。
新間寿は、「たぶん、ヘーシンクは馬場さんと連絡を取ったと思うんだよ。それで日本テレビから、“何でそんなところに出るんだ!”とストップがかかったんじゃないかな。ヘーシンクは出るつもりだったと思うよ。結構、いいギャラを提示したというから」「それとツアーに入る前に、ちょっとした事件があったんだよ。主催者側から“試合に火が点くようなことを喋ってくれ”と言われていたらしいんだけど、そうしたらヘーシンクが“プロレスは約束事がある。真の実力の問題ではない”というようなことを言い出したんで、ルスカが怒ってね。“自分がしてきたことをあたかもショーまがいなものだと言ったヘーシンクは、先輩でも許せない。このツアーまがいなものに参加するなら、俺が相手をして1分で倒してやる!”となっちゃったらしいのよ。そんなこともドタキャンの一因だったかもしれないね」と語っています。
インタビューの最後に、アリ戦やルスカ戦をはじめ多くの異種格闘技戦を手掛けてきた新間寿は、「韓国でパク・ソンナンと戦い、パキスタンでペールワンと戦い、西ドイツでボックと戦った。いつでも、どこでも、誰とでも戦うという姿勢を貫いてきたのが新日本プロレスであり、それを率いていたのがアントニオ猪木ですよ。だから今、アントニオ猪木という人間を一番必要としているのは誰かと言ったら、我々、プロレスを愛する人間全員なんだ。コミッショナーでも何でもいいから、あの人に“俺がプロレスの礎を創るんだ”という精神を今こそもってほしいね!」と熱く語るのでした。
2008年4月刊行の6号および2011年3月刊行の19号に掲載された「魁勝司のストロングスタイル深イイ話」では、日本プロレスから新日本プロレスまで常に猪木と行動を共にした北沢幹之が、「北沢さんが妃プロに入門して、最初に猪木さんに会われた時の印象というのは?」という質問に対して、「猪木さんは自分より1歳下なんですよ。自分は年下のもんには絶対に負けたくないという気持ちを強く持っていたんですけど、これがまた猪木さんは凄い身体をしているし、その当時から強かったんです。道場の中で猪木さんは殴り合いでもグラウンドでも、あらゆる面で強かったですよ。一緒に練習をやった人は、わかると思うんですけどね。サブミッションだけじゃなく、アマチュアレスリングも強かったです、ズバ抜けて」と語っています。ちなみに、北沢という選手は、ラッシャー木村、マサ齋藤、山本小鉄、木戸修、藤波辰爾、佐山聡といった錚々たるプロレスラーたちのデビュー戦の相手を務めた実力者です。
「具体的にその頃のスパーリングというのは、どんな感じだったんですか?」というインタビュアーの質問に対しては、北沢は「その頃は打撃も有りでした。拳を顔面に入れたりはしなかったですけど、最初は組まないで張り手でバンバン殴り合ったりとか。で、そこから捕まえて倒して極めるというのをやっていましたね。自分はボクシングも好きだったんで、よくボクシングの選手とスパーリングをやっていましたよ。力道山先生に“ボクサーなんかヘッドロックだけで極めろ”なんて言われながらね(笑)。聞いた話だと、今はヘッドロックでちゃんと極めることができないレスラーってゴロゴロいるみたいですよ」と答えます。続けて、インタビュアーが「道場で、そういう他流試合用の練習もされていたんですよ」と言うと、北沢は「やってました。自分は今でも孟んですけど、猪木さんの弟子で良かったなと。怖いものがなくなりましたから。何かを覚えたりする時は、厳しいところの方がいいですよ」と語るのでした。
北沢といえば、カール・ゴッチとも交流がありましたが、「67年11月に東プロが崩壊して日プロへ戻ることになるわけですが、同年11月にカール・ゴッチさんが呼ばれた理由というのは、何だったんですか?」という質問に対して、北沢は「猪木さんを潰すために呼んだんでしょ、日プロが。後で聞いた話ですけど、そうみたいですよ。他にもゴリラ・モンスーンというガチンコの強い選手がいたんですけど、それを猪木さんにぶつけるとか言って。猪木さんは、“いつでもやってやるよ!”と強気で言っていましたけどね。でも、ゴッチさんが来たら、すぐに猪木さんと仲良くなったんです、練習の好きなもん同志というのは、やっぱり合いますよね」と語るのでした。その後、新日本プロレスは旗揚げ戦で猪木vsゴッチ戦を行うなど、グッチとは密な関係にありましたが、80年代に入って徐々に疎遠になっていきます、84年になってゴッチはシン日本を離れて旧UWFに協力するようになりますが、これは金銭的な問題だったとか。ゴッチの娘婿のミスター空中がかなりの金額を要求してきたようで、結局そんなに払えないということで決裂したそうです。
カール・ゴッチはいわゆる裏技の達人でもありました。ルー・テーズと違って、決まらないと目を突いたり、アゴを殴ったり、脊髄に肘を落としたり、口や肛門に指を入れたりとか非常に悪いことをしてきたそうです。その裏技も猪木にしっかりと受け継がれたといいます。「猪木さんも試合で一線を越えることがありますよね。天龍源一郎は、試合中に指を曲げられて脱臼したそうですが」というインタビュアーの発言に対して、北沢は「あの人は、そういうの平気です。そうじゃないと、本当に強くはならないですよ。上まで行かないですね。自分なんかはそれができないから、中途半端で終わったんです。ただ、猪木さんが偉いなと思うのは練習の時は相手をケガさせませんでした。よく先輩で極めると話さないでギューやる人がいたけど、絶対そういうことはやらなかったですよ。あれは自信がないから、やるんだと思います。それに猪木さんは後輩をイジメることもなかったし」と語っています。
2012年3月に刊行された23号に掲載された「“炎の飛龍”が外国人レスラーを本音査定」では、藤波辰爾が「以前、藤波さんは“大きい選手の中ではアンドレ・ザ・ジャイアントが一番戦安かった”と言っていましたよね」というインタビュアーの発言に対して、「アンドレも俺と試合をするのが凄く楽しみだったみたいね。だから、敢えて俺に似つかわしくないことをやらせようとしたし。あれだけ身体が違うと、まともに勝負ができなんだけど、彼も日本での俺のポジションを知っているからチャンスをくれようとするのよ。アンドレが一番やりやすかったというのは、彼の巧さだろうね。俺は後ろに回る、けっていく、たまには組んでいくんだけど、それが不釣り合いじゃないというか試合がスイングするんだよね。アンドレは運動神経もいいし、物凄く勘がいい。俺とは逆に自分より大きい相手とやることはないでしょ。常に自分よりも小さい相手を闘うわけだから、自分の出せる技、自分の受けられる技がわかってるし、相手を見ながら試合を組み立てていくの。俺はアンドレをボデイスラムで投げてるからね。確か日本人でアンドレを投げたのは、猪木さんと俺と長州(力)だけじゃないかな。彼はよほどじゃないと、ボディスラムなんかやらせないから」と語っています。
次に藤波は、ブルーザー・ブロディについて語ります。「実際に試合をされてみて戦いやすい相手でしたか?という質問に対して、藤波は「やりづらかったね。ブロディという選手は気が短いように見えて、自分の頭の中で試合が組み立てられているから突発的な動きがないんだよ。ハンセンなんか突発的な動きばっかりじゃない? 新日本は日本人選手もそういうタイプだから、合わせやすいというか」と答えます。「臨機応変に戦う選手にとっては、ハンセンタイプの方がやりやすいということですか?」という質問には、「うん、ブロディの場合はハンセンみたいなムチャな動きをしないんだよ。自分の“型”や“間”をきっちろ持っているから、こっちが変則的な動きをすると俺の方が浮いちゃうんです。だから、ブロディは新日本のガイジンにはない間を持っていたよね。ハンセン、ホーガン、アンドレは、ゆったりした中にも新日本流の突発的な動きをしたりする。それは猪木さんのレスリングから影響を受けているんだろうね。ブロディはやっぱりオーソドックスな全日本タイプで、1つの枠があって、そこからハミ出た動きがないんですよ。マニュアルの動きというか、“プロレスとは、こういうものなんだよ”という教科書があるかのような動きなんだよね」と語ります。
「ブロディよりもディック・マードックの方が格上意識を見せつけると指摘する選手も多いんですが、藤波さんとしてはどう思いますか?」という質問に対しては、藤波は「マードックは自分で試合を組み立てていくから、認めていない選手が相手だと試合時間をもたさないんですよ。俺は物凄くやりやすかった。自分の仕掛けに反応して来る相手の時だと、マードックは何分でもプロレスをエンジョイしていたね。俺も真夏の炎天下で30分、40分…こっちはもう脱水状態になっちゃって(苦笑)。やりやすかったというよりも、彼はプロレスの教科書みたいな存在だったよ。ああいうタイプの選手がいないから、今の選手はプロレスを覚えないんじゃないかな。間であったり、技であったり、寝てよし、立ってよし。攻めも受けもね。彼とやった時は、自然に身体が動くんだよね。俺の仕掛けに瞬時に反応してくるし、オレもマードックの仕掛けに自然に反応して。あれで相手をオチョクらなかったら、最高の選手なんだけどね(笑)。実力もあるから、UWFが業務提携で新日本に来た時、危険視されていた前田日明を相手に一番試合運びが巧かったもの。あの前田でさえ、マードックにはコントロールされちゃって何もできなかったから。それでいて、ちゃんと試合では前田の良さも出ていたんだよね」と語っています。
2013年12月刊行の30号および2015年6月刊行の36号に掲載された「1973~1989年の『昭和・新日本』」では、新日本プロレス最強のナンバー2として猪木を支え続けた坂口征二に対して「86年になってUWF勢が戻ってきたはいいものの、坂口さんはマッチメークに神経を使っていた印象があります」というインタビュアーが言います。すると、坂口は「いやあ、あいつらはロープには飛ばないしいよ。星野さんなんかは試合が終わった後に、“何を考えてんだ、この野郎!”って控室に殴り込んだりとかな(笑)。そうやってギクシャクしていたけど…やっぱりみんなプロだから、何だかんだと言いながら手を合わせてやってたよ。越中なんかは、よくやられてたよな。でも、一番の問題はUWFが来ても、お客さんが全然入らなかったんだよ、毎日、何百人とか冷えた偉大だったよね。それで例の水俣の事件があるんだよ(笑)」と語っています。
水俣の事件とは、UWF勢が参戦してきて1年後、87年1月23日に新日本とUWFの選手が親睦のために宴会をして、熊本県水俣市の旅館を破壊してしまったという伝説の事件です。このとき、坂口は前田日明と武藤敬司の2人を座らせて「いいから飲め!」と一升瓶で焼酎を飲ませたそうです。前田にはずっと本物の焼酎を飲ませていましたが、武藤には途中から水を注いだといいます。すると、前田が途中でそれに気付いて激怒しました。坂口は、「“いいから飲め、この野郎!”“やるのか、この野郎!”、“ちゃんこを片付けろ!”と今度は俺と前田が揉めちゃって(苦笑)。それを見ていた武藤が怒って、前田と外に出て殴り合ったんだよ。最後は俺が前田をビール瓶で殴ったのかな? まあ、オレもよく憶えていないんだけど(苦笑)。あとは髙田がフルチンで歩いてた(笑)。船木は相変わらず泣き上戸で泣くしよ。3階のトイレはげろが詰まって、噴水みたいになったり(笑)」と回想します。「最後の最後は、どうなったんですか?」との問いには、坂口は「確か俺と猪木さん、荒川なんかで2~3時まで飲んでたよ(笑)。メチャクチャな宴会だったけど、次の日になったら、みんなケロッとしていてね。武藤はお客さんに見せられないぐらい顔が腫れていたから、試合で怪我をしたことにして欠場にしたけどよ(苦笑)。まあ、そんなことがあってから、みんなの心が少しは通じるようになったというのかな」と語るのでした。
2010年9月に刊行されたSPECIAL EDITION『アントニオ猪木』および2011年6月に刊行された『Gスピリッツ』20号に掲載された「“激動の昭和”と“燃える闘魂”を語る」では、東京スポーツの元編集局長で元『ワールドプロレスリング』解説者の櫻井康雄が登場します。猪木の新弟子時代について、「その時代をリアルタイムで知らない世代としては力道山に靴べらで殴られたとか、そういうイメージしかないんですが、実際はどうだったんですか?」という質問に対して、櫻井は「確かに、力道山は猪木に対して特に厳しかったですよ。というのは、やっぱり将来性を見込んでいたんでしょう。逆にジャイアント馬場には全然厳しくない。力道山は“あいつは、あれでいいんだ”と言っていましたね。言い方は悪いけど、“あれは見世物だから”と。ハッキリ、力道山は僕らにそう言いましたよ。その頃、力道山が一番厳しく鍛えていたのは猪木と大木金太郎。だから、トレーニングの時には目を皿のようにして2人を見ていました。試合では決して派手なパフォーマンスは許さないし、本格的な関節の取り合いをさせてね。ジムでも、そういう練習をさせていましたから」と答えています。当時、猪木にアマレスのテクニックは吉原功が、関節技は高専柔道出身の大坪清隆が教えていました。
多くの猪木の試合を観戦してきた櫻井康雄ですが、猪木のベストバウトとして、1975年12月11日に蔵前国技館でのビル・ロビンソン戦を挙げます。「名勝負として語り継がれている試合ですが、猪木さん自身はロビンソン戦に関して、あまり良く言いませんよね。ロビンソンはプライドが高いので譲らないところがありますし、猪木さんが技術面で押されるシーンも見受けられましたから」というインタビュアーの発言に対して、櫻井は「でも、ロビンソンは猪木を凄く評価していましたよ。猪木とすれば、本当はロビンソンをずっと使いたかったわけ。でも、馬場も持っていかれちゃって」と言います。「猪木さんのライバルとして、本当に相応しい相手でしたよね」という発言に対しては、櫻井は「僕は今でも思う。あの後、せめて1年、少なくとも3回はロビンソンと対決できたでしょ。そうしたら、2人はもっといい勝負をやっていたんじゃないかって」と言います。さらに「もしそうなったら、若い選手たちもああいうスタイルの試合を目指すようになって、その後の日本マット界の流れも多少は変わっていたかもしれないですよね」という発言に対しては、「うん、変わったと思う。だけど、猪木vsロビンソンは1試合だけだったから、今でも人の口に上るというのもあるけどね。あれは猪木の生涯の名勝負のうちに入ると僕は思いますよ」と語るのでした。
櫻井康雄が所属していた東京スポーツ新聞社は、1979年8月26日に「プロレス夢のオールスター戦」を日本武道館で開催し、メインイベントのタッグマッチでは馬場と猪木のBI砲が復活しました。これについて、櫻井は「8・26に僕が撃ち込んだ理由というのはね、これはプロレスのロマンなんですよ。東スポが主催した73年の『世界最強タッグ戦』にしてもそうですしね。うすでに全盛期を過ぎてはいたけれども、伝説のルー・テーズとカール・ゴッチが組んで猪木と坂口とぶつかる。そこにロマンやストーリーがあるじゃないですか。東スポが仲介に入った74年の猪木vs小林戦だって同じなんです。力道山vs木村以来、20年ぶりの日本人トップ同士の対決、事実上の日本選手権ということで朝刊スポーツ紙も大々的に取り上げたわけですよ。でも、今は何をやろうともプロレスは社会的な話題にならない。ロマンチシズムというものが今のプロレスには求められないんですよね。だから、人々の心に響かないんです」と語っています。彼は「東スポロマン」という言葉も使っており、UFOにしても河童にしてもロマンであり、そういうものが今のプロレスには感じられないといいます。そして、「僕から言わせれば、ロマンのないものは大衆ウケしないんですよ」と喝破するのでした。
「最後に改めて櫻井さんから見たアントニオ猪木とは?」というインタビュアーの質問に対して、櫻井は「僕はプロレスは文化だと思っているんですよね。要するに、人間の魂に影響を与えるものが文化だと。そういう意味では“昭和のプロレス”というのは、ひとつの文化であるというのが僕の持論なんです。これは堂々と胸を張って言えるね。やっぱり力道山と猪木のプロレスで、どれだけの人々が魂を揺さぶられて影響を受けたのか。これはまさに文化なんですよ。その担い手となったのは力道山からアントニオ猪木。悪いんだけど、僕は馬場じゃないと思う。人々に影響を与えたのは猪木だったと思うし、猪木にカリスマ性があるというのもそこだよね。じゃあ、力道山と猪木のどちらが“ミスター昭和プロレス”かと言ったら、僕は猪木だと思います」と言い切ります。力道山が活躍したのは9年間ですが、その後、昭和が終わるまで猪木はずっとミスタープロレスでした。そして、猪木のプロレスは人々に刺激や影響を与え、見る者の心を揺さぶってきたのです。それにしても、文化とは「人間の魂に影響を与えるもの」という櫻井康雄の指摘には非常に共感し、感銘を受けました。わたしは「冠婚葬祭こそは文化の中の文化」であると思っているのですが、ぜひ、人間の魂に影響を与える儀式の提供を心掛けていきたいです。