- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2025.04.10
『ネット怪談の民俗学』廣田龍平著(ハヤカワ新書)を読みました。著者は、1983年生まれ。法政大学ほか非常勤講師。専攻は文化人類学、民俗学。一条真也の読書館『妖怪の誕生』で紹介した著書があります。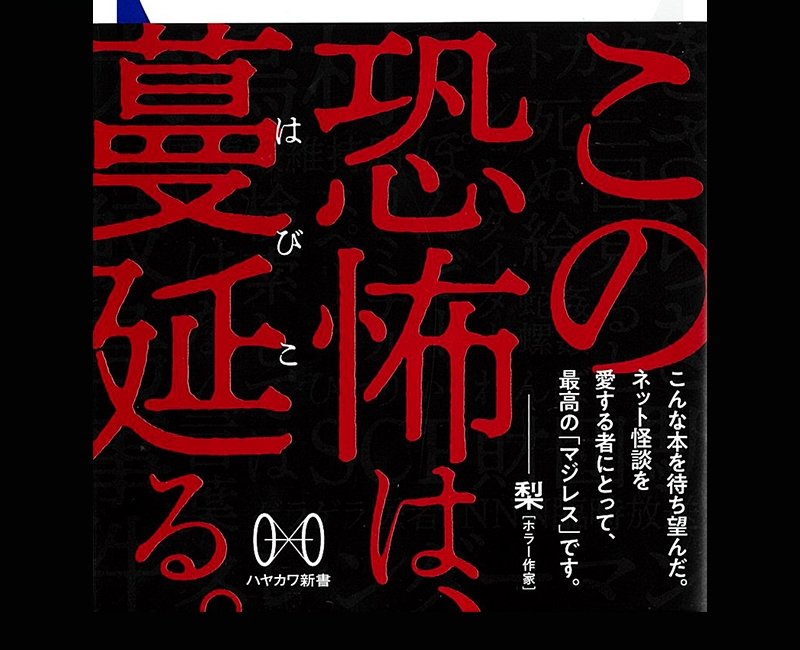 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、「この恐怖は蔓延(はびこ)る」と大書され、「こんな本を待ち望んだ。ネット怪談を愛する者にとって、最高の『マジレス』です。――梨(ホラー作家)」と書かれています。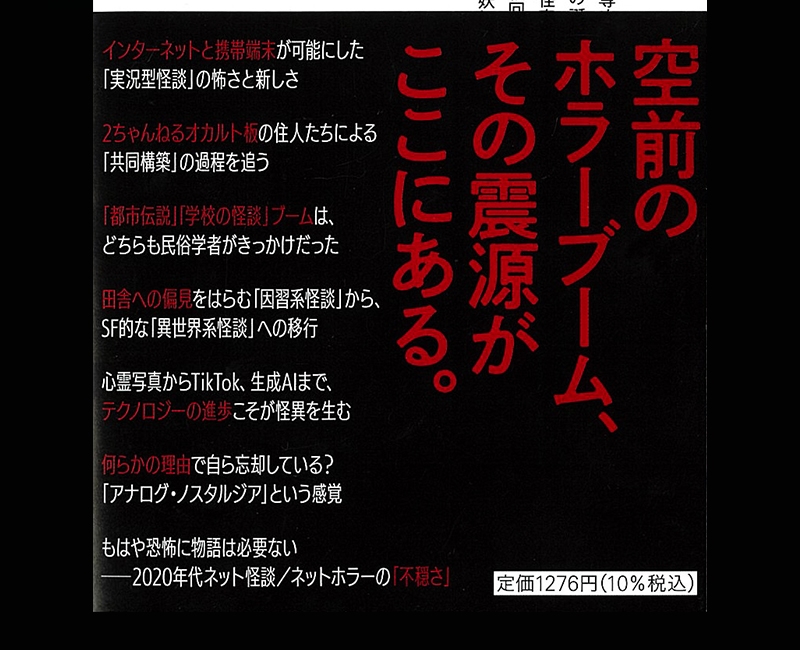 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には「空前のホラーブーム、その震源がここにある」と大書され、「インターネットと携帯端末が可能にした『実況型怪談』の怖さと新しさ」「2ちゃんねるオカルト板の住人たちによる『共同構築』の過程を追う「『都市伝説』『学校の怪談』ブームは、どちらも民俗学者がきっかけだった「田舎への偏見をはらむ『因習系怪談』から、SF的な『異世界系怪談』への移行」「心霊写真からTikTok、生成AIまで、テクノロジーの進歩こそが怪異を生む」「何らかの理由で自ら忘却している?『アナログ・ノスタルジア』という感覚」「もはや恐怖に物語は必要ない――2020年代ネット怪談/ネットホラーの『不穏さ』」と書かれています。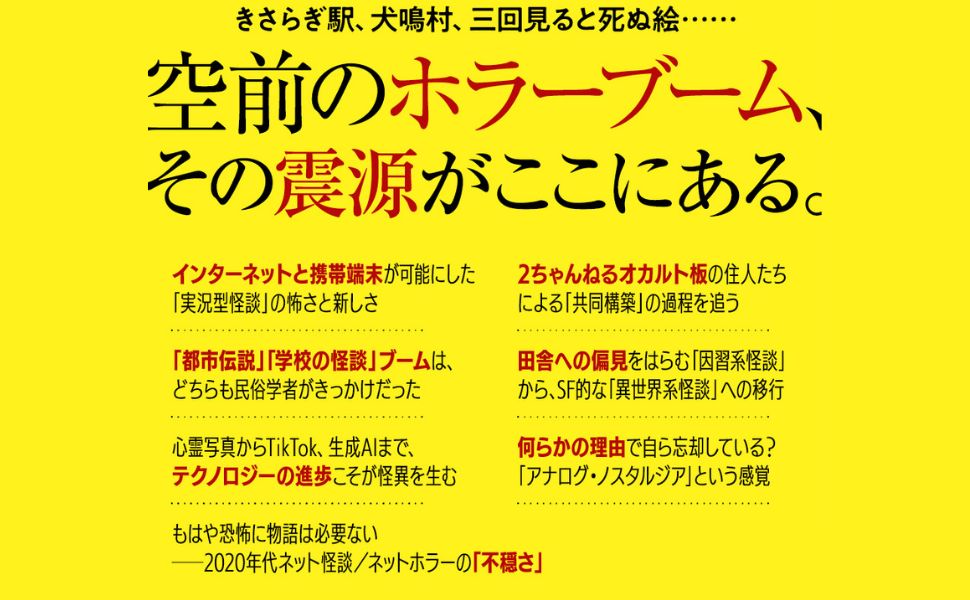 アマゾンより
アマゾンより
カバー前そでには、こう書かれています。
「『きさらぎ駅』『くねくね』『三回見ると死ぬ絵』『ひとりかくれんぼ』『リミナルスペース』など、インターネット上で生まれ、匿名掲示板の住人やSNSユーザーを震え上がらせてきた怪異の数々。本書はそれらネット怪談を『民俗(民間伝承)』の一種としてとらえ、その生態系を描き出す。不特定多数の参加者による『共同構築』、テクノロジーの進歩とともに変容する『オステンション(やってみた)』行為、私たちの世界と断絶した『異世界』への想像力……。恐怖という原始の感情、その最新形がここにある」と書かれています。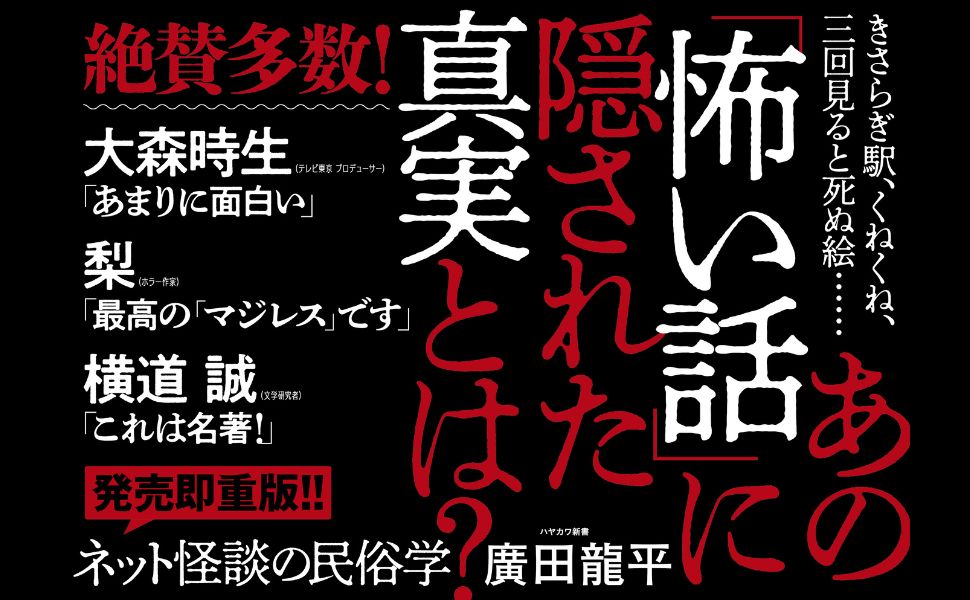 アマゾンより
アマゾンより
以下のコメントがアマゾンに寄せられています。
「現代の教養新書はこうあるべき。正直、やられた!と思いました」――中山永基(岩波新書編集長)
「ネット怪談をこれ以上なく学術的に語る。そんなこと可能なんや!という本です」――三宅香帆(『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』著者)
「あまりに面白い。これもしかして全国民必携の本では⁉」――大森時生(「行方不明展」プロデューサー)
「こんな本を待ち望んだ。ネット怪談を愛する者にとって、最高の「マジレス」です」――梨(ホラー作家)
「これは名著!」――横道誠(文学研究者)
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「まえがき」
第1章 ネット怪談と民俗学
第2章 共同構築の過程を追う
第3章 異世界に行く方法
第4章 ネット怪談の生態系
―掲示板文化の変遷と再媒介化
第5章 目で見る恐怖―画像怪談と動画配信
第6章 アナログとAI
―二〇二〇年代のネット怪談
「あとがき」
「注」「参考文献」「怪談索引」
「まえがき」の冒頭を、著者は「私たちは誰もが、一度ならず『怖い話』を見聞きしたことがあるだろう。本で読んだことがあるかもしれないし、テレビや映画館で見たことがあるかもしれない。子どものころ、大人に聞かされたことがあるかもしれない。日本にかぎらず、人類社会の多くは何らかのかたちで、オバケが出てきたり怪奇的なことが起きたりする『怖い話』を語り継いでいる。おそらく、その起源は先史時代にまでさかのぼれるだろう。ところで21世紀、『怖い話』がもっとも多く生まれているところはどこだろうか? 誰も数えたわけではないから正確な答えがあるわけではないが、有力な候補の1つが、実は『インターネット上』である」と書きだしています。
本書の大きな目的は、1990年代末から2020年代前半までのおよそ四半世紀にわたって、日本のネット怪談の大まかな見取り図を提示することであるとして、著者は「ネット怪談を取り上げた本や論文は少なくないが、その多くは特定のジャンルや話に集中している(「きさらぎ駅」や「コトリバコ」など)。それに対して本書は、いろいろなジャンルやメディアに目を配ることによって、今後、日本のネット怪談を語るにあたっての土台になることを目指している。そのため本書では、インターネット上での展開のみならず、商業化されたものや、国外に拡散されたものまで視野に入れる。また、現在の日本のネット怪談に関係するかぎりで、国外(主として英語圏)のネット怪談も見てみたい」と述べています。
第1章「ネット怪談と民俗学」の「民俗学とはどのような学問か」では、菊地暁が『民俗学入門』(2022)のなかで、民俗学は「『普通の人々』の『日々の暮らし』が、なぜ現在の姿に至ったのか、その来歴の解明を目的とした学問である」と定義したことが紹介されます。この目的のために使われるのは、日常生活の歴史を体現したわたしたち自身です。また、島村恭則は『みんなの民俗学』(2020)において、人々(「民」)を『対啓蒙主義的、対覇権主義的、対普遍主義的、対主流的、対中心的』な『ヴァナキュラー』(「俗」)の観点から研究する学問が民俗学であるとしました。
菊地と島村の両者に共通しているのは、ある社会の文化や歴史を知ろうとするとき真っ先に挙げられる有名人物や重大事件、芸術作品、政治制度といったものや、それらを調べるとき重要だと見なされる文献資料・公的記録だけを見ていくと掬い取ることのできない多くの人々の実践を、みずからの足元から見つめていこうとする態度です。たとえば地元の祭りや踊り、親戚の範囲、民家の構造、手作りの農具、季節ごとの行事、近所での貸し借り、葬式の出し方、明日の天気を知る方法、女性の仕事など……日本の民俗学者は、こうしたことを1世紀ほど前から地道に研究してきました。
本書に関わる範囲でもう1つ、民俗学の研究対象として適切なところがあるとすれば、それは、「公的・制度的・商業的な認可を受け、大量販売や大規模な収益を見込んでつくられることがほとんどない」点であるとして、著者は「権利を主張できる特定の作者がいるのではなく、誰が作りだしたのか知られていなかったりコミュニティとして所有していたりするものを民俗学は研究しているのである(それ以外のものをまったく研究しないというわけではないが)。本書の、共同で構築されるものとしての怪談という捉え方はこの点に基づいている」と述べています。
「画像から生まれる――スレンダーマン」では、インターネット文化の全般的な特徴として、地縁や血縁に縛られない、世界各地から参加できる――などを指摘することができると述べます。スレンダーマンはきさらぎ駅とは違い、特定の作者に帰属できる創作物として――日本語で言うなら「ネタ」として――投稿されたものであるとして、著者は「ただ、作者のサージは最初のころから構築の方向を制御しておらず、私たちが得ることのできる情報の大半は、むしろ彼以外によって共同構築されたものである。サージは、いわば0から1にした人物であるが、1から10にしたのはインターネット上の無数の人々だった」と述べています。
「スレンダーマン」のような創作ホラージャンルを、英語圏では、クリーピーパスタ(creepypasta)と言います。コピペ(copy&paste)をもじったコピーパスタ(copypasta)に、さらに「気味の悪い」を意味するクリーピー(creepy)を組み合わせた造語です。言葉自体は2000年代半ばに生まれたようですが初出は分かっていません。クリーピーパスタは、意図的に作者への帰属を曖昧にして、本当なのか虚構なのか分からないものとして楽しまれました。しかし、専門家のヴィヴィアン・アシモスが「その物語は虚構として合理的に理解されることもあるだろうが、作者と切り離されているので、現実世界の都市伝説として生を得ることもできる」と言うように、実話だと真に受ける人も出てくることがあるのです。
クリーピーパスタが創作であることが明示されなかった結果として、傷害事件が生じてしまったこともある。2014年5月31日、アメリカ合衆国ウィスコンシン州のウォーキショーという町で、二人の少女が、スレンダーマンに忠誠を誓うため、別の友人を刃物でめった刺しにする事件が発生した(被害者は幸いにも命を取り留めた)。あまりにも作り込まれた創作は、かえって現実性を強めてしまう。スレンダーマンを構築した人々は、ある意味で、うまくやりすぎてしまったのである。
「アメリカ民俗学の『伝説』概念」では、アメリカ民俗学における「伝説」とは、「異常だったり、奇妙だったり、説明がつかなかったり、予想できなかったものだったり、脅威を感じたりする出来事」を語ったものであることが紹介されます。著者は、「その出来事は、現実世界のどこかで、現実にいる人々が体験したものとされる――このぐらいの定義ならば日本の『怪談』にも応用できるだろう。しかしそれだけではない。伝説研究にとって重要なのは、終わりと始まりが決まっている昔話とは異なり、伝説は完結していないという点である」と述べています。
ネット怪談と同じように、従来の伝説もまた、一般的には未完成のうえ、断片的な話があちこちに散らばったままなので、それを聞いた人々は、伝説の内容が本当かどうか考察してみたり、不十分なところをつなぎ合わせてみたり、話し合ったりするとして、著者は「このようにして伝説は肉付けされていき、徐々に体系的な物語群としてまとめられたり、逆に地域や時代によって多くのバリエーションが生れたりする。伝説は、単に語られる物語などではなく、それにかかわる人々の行動のなかで構築されつづけるものでもある」と述べます。
アメリカ民俗学では、視聴覚メディアによる表象のほかにも伝説の表現方法があることが論じられています。それが「オステンション」(ostension)です。もともと記号論の用語ですが(「直示」と訳される)、伝説研究においては、すでにあるテキストで言われていることを試してみたり、再現してみたり、とにかく身をもって示してみる行為のことを指します。古いネットスラングで言うならば「○○してみた」「やってみた」というやつであると説明し、著者は「日本でよく知られたものとしては、女子トイレの3番目の扉を叩いて花子さんを呼び出してみるとか、五十音図に硬貨を置いてこっくりさん占いをしてみるなどの行為を挙げることができる」と述べます。
アメリカ民俗学では、クリーピーパスタをはじめとするネット怪談がホラー文化との関係で論じられることが多いのですが、対照的に日本民俗学がホラーという題目で何かを論じることはめったにありません。Jホラーやフォークホラー(folk horror)さえもろくに取り上げてきませんでした。著者は、「これは、ホラーが創作のジャンルであるのに対して、日本民俗学における妖怪や怪談の研究は、たどっていくと民俗社会の信仰を探るために始まったものなので、現代における創作された恐怖の楽しみ方がほとんど眼中に入っていなかったからだろう」と述べています。
「平成令和怪談略史」の「「うわさ――都市伝説、学校の怪談」では、1988年、アメリカの民俗学者ヤン・ハロルド・ブルンヴァンの著書『消えるヒッチハイカー』の日本語訳が出版された(原書は1981年)ことが紹介されます。アメリカの都市伝説を題材にした民俗学書です。タイトルの「消えるヒッチハイカー」は、自動車を運転していた人がヒッチハイクをしている若者を乗せたところ、一度も停車していないのにいつの間にかその若者が消えていたというもので、同じパターンの話が無数に記録されています。ブルンヴァンのこの本が日本語に訳されたことで、「都市伝説」という言葉が日本でも広く知られるようになりました。こうした話は、従来の日本民俗学では「世間話」に分類されていたのだが、それらを新しいジャンルにひとまとめにしたのが、80年代終わりの「都市伝説」概念の大きな意義であるといいます。
第2章「共同構築の過程を追う」では、ネット怪談は民俗学的には伝説の一種であることが指摘されます。伝説は、ある人物が一通り話して終わり、それで完成するようなものではありません。むしろそれに続いて、他の人々が内容を検証したり、現場に行って確認してみたり、語り継いでいくなかで他の伝説との関連性が発見されたり、正確な情報に改められたり、イラストや音声が付加されたり、学者が原典版を発表したりと、多くの人々が関わるなかで、どんどん変わっていきます。ネット怪談もこれとまったく同じであるとして、著者は「最初に掲示板に書き込まれてそれで終わりというわけではなく、短い期間のあいだに次々と変転していき、そして忘れ去られることもあれば、現在まで根強く語り継がれて(コピペされつづけて)いることもある。要約されて本や論文に掲載されることもあれば、漫画化・映画化により大幅に換骨奪胎されることもある」と述べています。
そんな中でもネット怪談が面白いのは、ものにもよりますが、発端となった出来事が報告されてから現在定着している形態になるまでの共同構築の過程をかなりの程度細かく観察できることです。その時間的な範囲はさまざまで、前章のきさらぎ駅のように数分ごとにレスが蓄積されていくものもあれば、もう少し間隔を空けてまとまった続報が投稿されるものもあり、さらに最初の話が数年後に改変されて話題を集めることもあります。著者は、「実は、ネット怪談といえば誰でも知っているコトリバコやくねくねなども、最初から完成された怪談が投稿されたというよりは、時間をかけて徐々に私たちが今知っているような形になっている」と述べます。
「2000年代初頭までの状況」では、インターネット上のウェブサイト利用が一般に普及する1990年代半ばまでの状況が説明されます。パソコン通信の電子掲示板やネットニュース(不特定多数が参加できるテキスト投稿システム)、メーリングリスト、IRC(チャットの一種)などで怪談が流通していました。アメリカでは都市伝説や恐怖体験がネットニュースに投稿されていたようですが、日本語のネットニュースの記録を検索してみても、ほとんど見つかりません。「心霊スポットから怪村へ」では、怪村情報が乱立するなかでも注目されたのは、青森県にあるという杉沢村と、福岡県にあるという犬鳴村であったことが紹介されます。どちらも公的な地名としては存在せず、1990年代初頭から地元の若者のあいだでは評判でしたが、紙媒体ではほぼ知られていませんでした。それが今では一条真也の映画館「犬鳴村」で紹介した2020年公開の日本映画のように劇場公開される映画の題材にまでなったのは、間違いなくインターネット上で拡散したからだといいます。
杉沢村は、かつて集落まるごと皆殺しにされた場所で、入り口には鳥居があり、惨劇の現場では今なお死者の霊たちがさまよっているというものです。それに対して犬鳴村は、犬鳴峠(実在する地名)近くに、国家権力の通用しない反社会的な集落があるというものです。どちらも行政によって地図から抹消され、存在しないことになっているという、陰謀論的な説明がされることがあります。著者は、「道に迷うなどして村にたどり着いてしまうと、死者に憑依されたり村人に攻撃されたりするなどろくなことが起きず、場合によってはそのまま帰ってこられないこともあるという」と説明しています。
怪村は、中世から知られている隠れ里のように、あるはずなのに行くことができないところに1つの特徴があります。通常の心霊スポットならば、自分も恐怖体験を味わおうとオステンションを実践することはそれほど難しくありません。行けばいいからです。だが怪村の場合、そもそも場所が分からないので、文献・ウェブ調査や地元の人々からの情報提供、周辺の探索など、行きつくまでの謎解き要素が大部分を占めています。そうしたものは、現地に行った人だけが特別な関わりの深さを持てる旧来の心霊スポットと違い、世界中の誰もがネットを利用できるかぎりで同じぐらい深く探索できるという点で、場所という制約から解放されていました。
「ネット怪談と田舎と民俗学」では、怪談・オカルト研究家の吉田悠軌は、コトリバコこそが2000年代後半に続々と登場した「集落に隠された因習と謎についての恐怖譚」(つまり民俗学的要素を持つもの。名前だけ挙げると「八尺様」や「リョウメンスクナ」、「ヤマノケ」、「逆さの樵面」など)という方向性を決定づけたと主張していることを紹介します。2010年代に入ると、長く語り継がれる新しい話は出てこなくなります。それに対して、2020年代に入ってもネット怪談と言えば典型的に挙げられるのがコトリバコや八尺様などであることからも分かるように、2000年代後半に生まれた因習系ネット怪談は、20年近く経ってもなお根強い人気があります。
犬鳴村やコトリバコをはじめとして、古典的なネット怪談のいくつかが、「辺鄙な田舎」や「山の奥深く」に対する差別的認識によって読者にとってのリアリティを帯びることになったという点を無視することはできないと指摘し、著者は「都市部から遠く離れたところ(あるいは「未開」社会)には、現代文明の常識が通用しない、遅れた観念や非人道的な風習(「因習」や「迷信」などと表記される)を守る固陋な人々がおり、異常な出来事が、さも当然であるかのように生じている――という差別的偏見は、戦後日本に限っても、60年代の『秘境』ブームから70年代の横溝正史ブーム、2010年代後半の『フォークホラー』ジャンルの浸透や『因習村』概念の誕生にいたるまで、連綿と続いている」と述べています。
因習村のジャンル概念はまだ固まっていませんが、辺鄙な土地に、近代的とは思えないおぞましい風習(因習)が隠されており、都会から来た人々がそれに巻き込まれるというパターンを踏むものが多いです。近年の映画では一条真也の映画館「ミッドサマー」で紹介した2019年のアメリカ・スウェーデン合作映画、一条真也の映画館「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」で紹介した2023年のアニメ、一条真也の映画館「変な家」で紹介した2024年の日本映画などが挙げられ、またネット怪談ではやばい集落や犬鳴村などがそれに近いと指摘しつつ、著者は「ただ、これらのホラーやネット怪談においては、危険なのは前近代から続く風習というより、近代的ではない風習を現代も続けている(場合によってはわざわざ創出している)集団それ自体である点に注意が必要である」とも述べています。
日本のホラー界隈でも、フォークホラーの広まりに連なるように、田舎を危険なものとして描くことが流行っているようです。これに対しては、2020年に「近年、田舎を田舎というだけで何が起こっても許される装置として乱暴に描いてしまう応募作が多い」という批評がなされています。この問題意識を引き継いで、小説家の澤村伊智はそうした作品について「『結局それって田舎をバカにしてんじゃないの?』という。感度が高い人ほど、たとえば横溝映画が全盛期だった70年代とは違って、異文化を恐怖の対象として扱う作品を無邪気に楽しんではいられないという意識を持ち始めている」と指摘しています。
このような視点から犬鳴村を研究した鳥飼かおるは、犬鳴峠やその近辺をめぐるさまざまな否定的イメージをいくつも取り出しています。たとえば筑豊炭鉱の過酷な労働から逃げてきた人々の場所としての山中や、より広い意味で山に住む人々(「サンカ」「山人」など)への偏見などです。後者については、戦前の柳田國男らの民俗学が、山の人々を「文明社会の私たち」と対比させながら分析していたことも、鳥飼は指摘しています。著者は、「そもそも田舎の『遅れた』民俗を誰よりも綿密に調査して世間に公表してきたのは民俗学者たちであったし、都会の『進んだ』人々は民俗学の研究成果によって風習や物語を知ることができた」と述べます。
あるいは民俗学者自身が、場合によっては「遅れた」民俗の近代化に取り組むこともありました。それ自体は田舎の人々の生活改善を目指した運動だったのですが、彼らの仕事は、現代社会とは相容れない民俗の存在を、そういう枠組みのなかで紹介するものともなったのです。日本民俗学のはじまりとも言われる『遠野物語』(1910)の序文で、かつて柳田は「願はくは之を語りて平地人を戦慄せしめよ」と言い放ち、さまざまな伝説・怪談を都会の人々に向けて再話しました。著者は、「しかし、スクリーンの手前という安全圏にいる21世紀の平地人は、すでに『戦慄』をエンターテイメントとして楽しむことに慣れきってしまっている」と述べるのでした。
「台湾の『赤い封筒』と因習系の衰退?」では、民俗学者の及川祥平は心霊スポットに出没する幽霊について、「人は[……]すでに亡い家族や友人が血まみれでフロントガラスに落ちてきたり、四つん這いで追いかけてきたりすることを望むだろうか」と問いかけていることが紹介されます。著者は、「死者をことさらに醜悪で手に負えない、人間的な対話のできないものに仕立て上げるのは、当の死者とは無関係に恐怖を消費する人々でしかない。親しかった人々にとって、その死者が生前どのような存在だったのか、死後どのような存在であってほしいのかを私たちがイメージする余地が失われてしまっているのである」と述べています。
台湾の「赤い封筒」というネット怪談における「田舎」は、もはや日本のどこかではなく、国外の、しかしかつて日本が植民地化していたぐらいには関係の深い近隣地域でした。著者は、「そうした地域の一部で、珍しいとは言え確かに受け入れられ実践されていた民俗文化を、単にネット上で見かけた非合理的で前近代的な因習として無批判に怖がり楽しむことは、私たちの他者への偏見を増幅することはあれ、補正するものではないだろう。とはいえ、ふたたび及川の議論を参照するならば、民俗学は人々のネガティヴな実践を分析して提示することはあっても、要不要を判断するものではない。それは、民俗学の研究成果も横目にみながら『生活者自身』が答えを導くものなのである」と述べています。
2010年代に入って、コトリバコなどの因習系怪談が新たに生み出されづらくなったことは、そうした「答え」の1つだろうという著者は、「少なくとも投稿者(報告者/作者)やクリエイターは、先述のホラー批評にあるように、地方や病気、障害、宗教などへの差別や偏見をプロットに組み込む作品を徐々に避けていっているように見える」と述べ、さらに「恐怖の根源には自分とは違うもの、自分の知らないものへの漠然とした不安や警戒があるとはよく言われることである。だが、そうした不安や警戒が、現実に存在する具体的な人々・集団や、それをモデルにした登場人物に直接向けられる怪談やホラー作品の体験談あるいは新作は、今後、ゆるやかに減っていくのではないかと思われる」と述べるのでした。
第3章「異世界に行く方法」の「異界と異世界」では、ネット怪談における代表的な異界といえば犬鳴村や杉沢村であることが指摘。著者は、「それらは私たちの世界のどこかにあることが何となくイメージできる。犬鳴村は犬鳴峠の近くにあるし、杉沢村は青森市のどこかにある。そうした異界は日常世界と地理的連続性があると言うことができる」と述べます。他界(死後の世界)は、前近代の日本では地下や海の向こう、天上など、やはり地理的に連続したところにあるとされていましたし、少なくとも「死んだら行くところ」という点で日常世界と不可分の関係にあり、この世と役割を分担しています。こうした諸々の異界をあわせて、広い意味での「私たちの世界」が成立しているといいます。それに対して異世界は、「他界も含めた私たちの世界とは無関係なところ」と定義できるとして、著者は「たとえばきさらぎ駅では、この駅のある地域を地理的にイメージすることはできない」と述べます。
「マンデラ効果」では、並行世界を想定する奇妙な体験談としてマンデラ効果(the Mandela effect)が紹介されます。これはもともと、南アフリカの政治家ネルソン・マンデラ(1918~2013)が、1980年代の反アパルトヘイト闘争のなかで死んでいたはずという記憶を持った人々が多くいるという現象にちなんで名づけられたものです。個人的な問題でないとすれば、それは単なる記憶違いではなく、何らかの理由で過去が改変されるという現象が生じているのではないかと考えた超常現象研究家フィオナ・プルームが2010年に命名。英語圏では2015年になって一気に知名度が高まり、日本でも2016年ごろからTwitterやオカルト板、オカルト系サイトなどで徐々に知られていきました。
怪談/ホラーといえるかどうかは難しいですが、都市伝説扱いされているものとして、未来人ジョン・タイター(John Titor)も並行世界に触れています。タイターなる人物(原音に近いのは「ティター」)は2036年からやってきたという触れ込みで2000年末から英語圏の電子掲示板に未来のことを投稿し、大きな話題になりました。このとき、時間旅行にまつわるタイムパラドックスを解決するためにタイターは並行世界の存在を示唆したとされています。この人物については、日本では最初に都市伝説サイト「医学都市伝説」が2004年11月に懐疑的に取り上げ、その後、オカルト雑誌『ムー』2005年12月号で南山宏が記事にしたことでオカルト板などに広まっていきました。英語圏のネット発の都市伝説がこれほどの規模で日本で話題になったのは、クリーピーパスタ以前ではジョン・タイターが際立っています。
「21世紀の怪談としての異世界系」では、異世界系怪談はくねくねやコトリバコなどの田舎にまつわる怪談とは性質を大きく異にすることが指摘。伝統的な超自然の概念(幽霊、神仏、祟り、怨念、呪術、他界など)では説明できないことばかりなのです。2020年代に入っても、代表的なネット怪談といえば因習に関するものというイメージが強いですが、実際には、むしろ謎の超技術や宇宙の知られざる物理的構造といったものがひそかに体験されていることを前提としたものも目立つといいます。著者は、「いわば、謎解きに焦点を当てるミステリ(因習系怪談)ではなく、新たな知識を生み出すサイエンス(・フィクション)が焦点になっているのである」と述べています。
他方で、おそらくその分、伝統的な(伝統的っぽい)知識があれば少なくとも雰囲気だけは楽しめる因習系ほどには一般化していないのだろうとして、著者は「時期的に見ると、2000年代半ばを頂点とする因習系怪談に対して、異世界系怪談は2000年代後半から2010年代にかけて、マンデラ効果などのグローバルな話題にも関連しながら語られるようになっている」と述べています。また、実在する人物や集団への差別や偏見を助長しかねない因習系が徐々に避けられるようになっていった動向のなかには、「異世界系のひそかな進展も含まれているのではないかと思われる」とも述べます。
「異世界に行ってみる」では、異世界系で考察と並んで関心が持たれているのは、実際に異世界に行くことが試みられるオステンション行為であることが紹介されます。「学校の怪談」などではすでに特定の行動をすることによって異世界に飛ばされてしまうといううわさが数多く知られていました。しかし、異世界はよく分からない恐ろしいところなのだから、そうした行動は禁忌でした。また、深夜の学校のように、そもそも立ち入れない場所で実施しなければならないものも多かったのです。それに対してネット怪談に顕著なのは、異世界に行ってしまうからそうした行為が禁止されるのではなく、異世界に行けるからそうした行為が楽しまれるという逆転現象でした。なかでも有名なのが「飽きた」と「異世界に行く方法」の2つです。
「現実感のありか」では、わたしたちの世界も異世界も、実は機械によってつくりだされた仮想空間だという説を紹介します。それならば、本来はスクリーン上でしか現れないはずの文字化けが印刷物や音声言語に現れても説明がつくというわけですが、こうしたイメージは映画「マトリックス」(1999年)や、哲学者ニック・ボストロムの提唱するシミュレーション仮説(この世界は、高次の存在によるコンピュータ・シミュレーションだというもの)によって、21世紀初頭、世界的に知れ渡ることになったと説明しています。現在では、ヘッドマウントディスプレイなどデバイスの高度化によって、わたしたち自身が相当にリアルなシミュレーション世界の住人になることさえできるといいます。また、2ちゃんねるの匿名性は、個人の体験談のみならず共同体に関わる物語であっても投稿しやすく(創作しやすく)するものでもあり、物語の拡散と変化を推し進めるものでもあり、さらにアーカイブとして機能するものでもあったことが指摘されます。
第4章「ネット怪談の生態系――掲示板文化の変遷と再媒介化」の「まとめ動画と再媒介化」では、あるメディアを別のメディアで表象(再現)することを、メディア論の用語で「再媒介化」(remediation)と呼ぶことが紹介。再媒介化は、自分たちがメディアを通してものを認識していることに気づかせる「複媒介性」(hypermediacy)と、じかに見ているという感覚を与える「無媒介性」(immediacy)の両方を働かせます。まとめブログや動画による再媒介化は、「まとめ」というジャンル自体が複媒介性を強調するとともに、オカルト板にありがちな参加者らの反応を抹消することによりオリジナルを復元しようとする点で無媒介性を志向してもいるといいます。それは共同構築性を見えなくすることにより、完成された作品として提示することでもあるのです。
「ネット怪談の衰退――『あるある』化とホラー志向」では、2020年代に入ると、投稿サイトに発表されたホラー作品の一部は書籍化されたり映画化されたりするほど注目を集めるようになったとして、著者は「カクヨムならば芦花公園『ほねがらみ』(2019年公開→2021年出版)や背筋『近畿地方のある場所について』(2023年公開→同年出版)、オモコロならば雨穴『変な家』(2020年公開→2024年映画化)などである。インターネット発の怖い話自体は生産され、受容されている。ただ、その重心はネット怪談からネットホラーへと移っていっているのが現状である。さらに創作ではない怪談のほうも、2010年代以降、ライブや配信、書籍といったかたちで商業化しうることが認識されてきた」と説明しています。
「インターネットを、日本を越える」の「日本の商業メディア」では、1990年代には盛んに目新しい怪談(都市伝説と学校の怪談)を集めていたライターや民俗学者たちは、ネット怪談の急速な展開についていくことができなかったと指摘します。インターネットに流通する怪談をまとめて紹介した本のなかでも古いのはオカルトライターである山口敏太郎の『本当にいる 日本の「現代妖怪」図鑑』(2007)あたりだろうという著者は、「同書の『サイパーゴースト』という章では、30ページにわたってインターネットにまつわる怪異が紹介され、本書で取り上げたものとしてはくねくね、ニンゲン、杉沢村、犬鳴村などが掲載されている。総称には『ネット流布話』という用語が使われている。他方で、オカルト板や洒落怖スレが一大発信地であることには触れられていない」と述べます。
2017年1月には、Twitter上で活躍していた朝里樹(アカウントは@asazato4)が、私家版ながらも379ページにおよぶ『日本現代怪異事典』という書籍を出しました。同書は戦後日本に伝わる都市伝説や学校の怪談、そしてネット怪談などを1000項目ほど解説したもので、妖怪・怪談好きの間では大きな話題となりました。さらに、この本を入手した国文学者・サブカル研究者の伊藤慎吾が出版社に紹介したことにより、私家版を増補したものが2018年1月に出版され、こちらもベストセラーになりました。著者は、「『日本現代怪異事典』は在野の愛好家である朝里が編集したものだが、今では(ネット怪談に限らず)研究者も必ず参照する重要文献となっている」と述べています。
「話者としてのインターネット老人会」では、民俗学者がフィールドワークをするとき、高齢者(いわゆる「古老」)を話者として優先する傾向にあるのは、一度失われると取り返しのつかない記憶を少しでも早く記録するためでもあることが指摘されます。他方で、すでに記録が残されていても、アーカイブ(まとめブログ)に保存されなければ、いわば死蔵状態に陥ります。するとやはり、「古老」への聞き取りが重要になってくるとして、著者は「『インターネット老人会』と自虐的に呼ばれる人々の記憶は、ネット怪談のみならず、民俗学にとってもインターネット文化研究にとっても、きわめて貴重なものなのである」と述べるのでした。
第5章「目で見る恐怖――画像怪談と動画配信」では、口承のほかに「書承」という伝わり方もあることが指摘されます。書かれたものを利用するやり方です。その媒体には、本や雑誌だけではなく、プライベートな場でやりとりされる手紙や日記なども含まれます。ただし、書承によって伝わるのは文字だけとは限りません。たとえば日本では、江戸時代に木版印刷が普及し、無数の怪談集が刊行されましたが、その多くには場面を描いた挿絵が含まれていました。出版物による書承は地域や時代を超えて同じ文章を大量に複製することを可能にしただけではなはなく、視覚的なイメージを広めていくこともできたのです。19世紀における写真の出現はイメージのあり方を大きく変えました。写真は感光することで機械的に生み出される複写だから、何にもまして主観の入らない客観的なものだと見なされたのです。著者は、「19世紀後半に心霊写真が流行したのも死後の存在を示す客観的証拠として写真が利用されたからだった」と述べます。
超常的なものについて言えば、単純に「事物がかつてそこにあったということを決して否定できない」という思想家ロラン・バルトの指摘を利用しているとも言えるとして、著者は「私たちがイメージする心霊写真の多くはぼやけており、写真の『写し取る』機能を十全に果たしていないように見えるが、それでも主観とは無関係に『客観的にあった』ということの証拠としては機能しているのである。霊的なものではないが、ネッシーや雪男などの未確認動物の存在が曖昧な写真によって広まっていることも押さえておくべきである。はっきりとは見えないが確かに何かがいるという性質は、ネット怪談における画像や動画にも受け継がれている」と述べています。
第6章「アナログとAI――2020年代のネット怪談」の「古い映像、記憶に残る映像」では、「ファウンドフッテージ」(found footage)が取り上げられます。これは、直訳すると「発見された映像の断片」という意味で、何らかの理由で行方不明だった(あるいは存在が知られていなかった)映像が見つかり、再生してみると、撮影者たちに恐ろしいことが起きていたことが分かるという設定のものが多いです。フィクション作品に形式的な現実感を持たせるための技法として、21世紀に入ると多用されるようになりました。なかでも、1999年に公開された映画「ブレア・ウィッチ・プロジェクト」に連なるホラー映像作品のジャンルが中心を占めています。The Backrooms(Found Footage)も、タイトルどおり、このジャンルの作品です。
また、「アナログホラー」や「モキュメンタリ―」も取り上げられています。「アナログホラー」(analog horror)は、基本的にはデジタル映像が一般的になる前の時代(おおよそ1990年代半ばまで)に記録されたという設定のアナログ画質の映像のなかに、どこか不穏だったり、異常なことが起きていることを示唆する情報が入っていたりするデジタル作品を指します。「モキュメンタリー」(mocumentary)は「フェイクドキュメンタリー」(fakedocumentary)とも言い、ドキュメンタリー映像の形式を模した創作です。いずれのジャンルも、再媒介化の2つの側面――複媒介性と無媒介性――を存分に利用しています。
フィクションとして分析するならば明らかに複媒介性を主張していますが、ファウンドフッテージなら「自分が作ったものではない」、モキュメンタリーなら「写されているのが現実である」、アナログホラーなら「デジタル的な加工編集が難しい」とする認識にも寄りかかっているため、映し出されるものは無媒介性を同時に強調。そのため、こうしたジャンルの作品は成功すればするほど、視聴者に「これは事実なのだろうか?」という思いを抱かせると指摘し、著者は「視聴者によっては本当に起こったことではないかと受け取り、たとえ初出のメディアではネットホラーとして受容されていたとしても、再媒介化(転載や切り取り動画など)が繰り返されることにより、ネット怪談に変質してしまうこともある。こうした再媒介化がほとんど誰によっても可能になっているインターネットでは、そうした変化はよく見られるものである」と述べます。
「異世界からの実況配信」では、画像としてのバックルームやリミナルスペースに共通するのは、不穏さのほかに「夢で見たことがある」や「子どものころ行ったことがある」「行ったことがないのに懐かしさがある気がする」といったコメントが多く投稿されていることであるといいます。著者は、「ノスタルジアを感じるが、しかし過去の現実に符合しないという奇妙な感覚だ。リミナルスペースが流行る前の2012年にはすでにこのような感覚に対して『アネモイア』(anemoia)という新語が作られており、リミナルスペース系の画像に対してこの語がハッシュタグに使われることもある」と述べています。
「不穏さ」では、著者は「誰かが主導的な立ち位置にいるわけではない共同構築は、たとえば当初のスレを全体として見るならば一貫した何かを構築するわけではないかもしれないが、まとめサイトやまとめ動画などへの再媒介化によって視聴者は、それらを一貫したナラティヴ(物語)として受け取ることができる。他方でマノヴィッチの言うように、私たちはそれらをバラバラなまま受容することもできる。全体としてのつながりを求めず、1つ1つの投稿に恐怖や不穏さを感じることもできる」と述べています。
わたしたちの身の回りで起きる(ことがあるかもしれない)怪奇現象もまた、ナラティヴを備えるほどに具体的で因果性があってまとまった出来事ではないものが多いとして、著者は「自室で変な音がしたり、ふとおかしなものが見えたり、風景にどことなく違和感を覚えたり、何となくぞっとしたり、悪寒を感じたり、鳥肌が立ったり、冷や汗をかいたりすることはあっても、たいして気にせずに忘れてしまうかもしれない。こうした感覚的で曖味な不穏さは、データベースが優位となる構造のインターネットにおいてこそ、逆説的ではあるが明確な対象として共同構築されるのである」と述べるのでした。この文章を読んで、わたしは一条真也の映画館「SKINAMARINK/スキナマリンク」で紹介した世にも不穏なホラー映画を連想しました。本書は、ネット怪談や民俗学に限らず、ホラー映画の最前線を考える上でも非常に多くの示唆を与えてくれました。
