- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2392 オカルト・陰謀 | ホラー・ファンタジー 『現代の怪異あるいは怪異の現代』 及川祥平編著(アーツアンドクラフツ)
2025.04.11
『現代の怪異あるいは怪異の現代』及川祥平編著(アーツアンドクラフツ)を読みました。「現代怪異研究小論集」というサブタイトルがついています。編著者は1983年、北海道生まれ。成城大学文芸学部准教授。博士(文学)。専門は民俗学。主な著作に『偉人崇拝の民俗学』(勉誠出版)、『民俗学の思考法』(共編著、慶應義塾大学出版会)、一条真也の読書館『心霊スポット考』で紹介した本があります。同書は素晴らしい名著です。
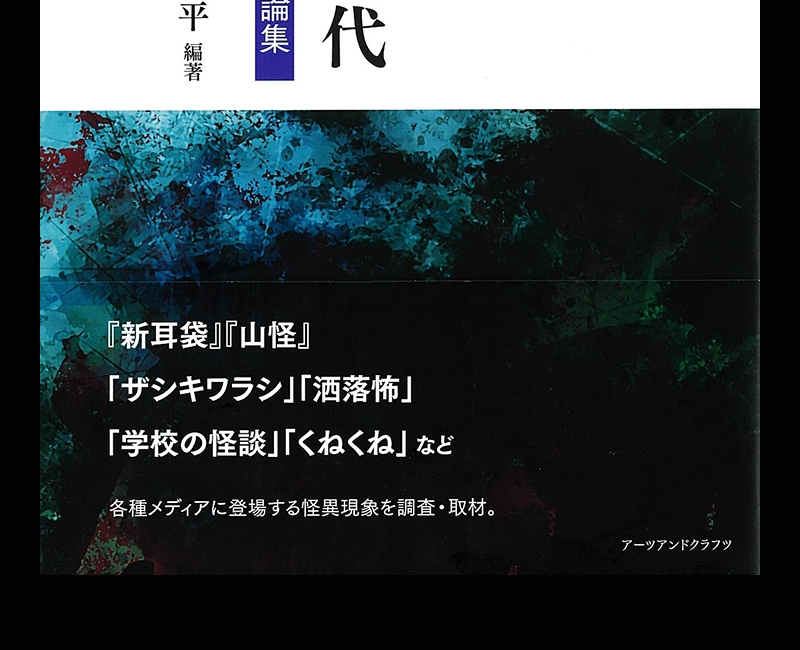 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、「『新耳袋』『山怪』『ザシキワラシ』『洒落怖』『学校の怪談』『くねくね』など各種メディアに登場する怪異現象を調査・取材」と書かれています。
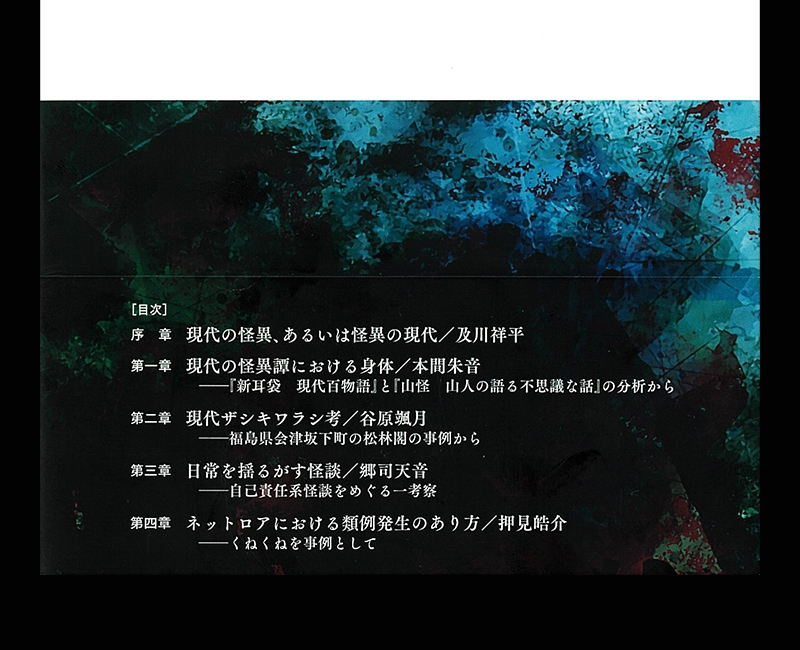 本書の帯の裏
本書の帯の裏
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
序 章 「現代」の「怪異」、あるいは「怪異」の「現代」/及川祥平
第一章 現代の怪異譚における身体――『新耳袋百物語』と『山怪 山人の語る不思議な話』の分析から/本間朱音
第二章 現代ザシキワラシ考――福島県会津坂下町の松林閣の事例から/谷原颯月
第三章 日常を揺るがす怪談――自己責任系怪談をめぐる一考察/郷司天音
第四章 ネットロアにおける類例発生のあり方――くねくねを事例として/押見皓介「執筆者一覧」
及川祥平氏は、序章「『現代』の『怪異』、あるいは『怪異』の『現代』」の「はじめに」を「本書には、現代の怪異に民俗学の立場から接近しようと試みる、4本の文章をおさめている。いずれも、筆者が成城大学および同大学院で指導を担当した卒業論文および修士論文の一部を大幅にブラッシュアップしたものである」と書きだしています。及川氏の担当ゼミナールは民俗信仰論・現代民族論を称しています。民俗信仰論とは、日々の暮らしのなかにある宗教文化の研究を意味しています。民俗信仰は、民俗学が生活と宗の接点を問う際に使用してきた概念であり、いわゆる民間信仰や民俗宗教、またはヴァナキュラー宗教などの言葉と指示する対象はおおよそ重なります。
一方の現代民俗論は、現代社会の日常や諸課題に民俗学の立場からアプローチすることを意味させています。及川氏のゼミでは、「現在を知るための史学」という民俗学の特質をふまえながら、同時代の社会・文化、暮らしや出来事を考えるように促しているそうです。及川氏は、「在籍するゼミ生はそれぞれ民俗信仰論ないし現代民俗論的なテーマを自ら定めて卒業研究に取り組んでいくわけだが、両研究領域にまたがるような卒論・修論も少なくない。現代社会の霊や神、怪異・妖怪をめぐる文化に、同時代の世相との関係をからめながら取り組もうとする者が多い。本書には、そのような学生たちの研究成果のなかから、近似した関心に基づくものを集めることにした」と述べています。
「一.なぜ現代か」では、「現代」の意味が説明されます。「現代」は、自明の「対象」ではないといいます。むしろ、それは「目的」や「問い」への名づけであるといったほうが適切かもしれないとして、及川氏は「筆者には、自分が生きるこの時代がよくわからない。だからこそ、民俗学という思考の方法によって、世の中のことを調べ、考えようとしている。また、そのような「私」のことも、実はよくわからない。なにかを感じ、想ったとして、どうしてそのように感じ、想わなければならないのか。また、どうしてこのように生きなければならないのか。現代の民俗学はそのような、この時代のこの社会に生活者として生きる『私』の疑問に、ささやかな回答を見出していくための学問であると思っている」と述べます。
「怪異」とはなにか。それは怪しむべき事物、不思議な事物に与えられる総称です。本書でいう怪異は目的ではないといいます。むしろ、素材でだというのです。または、認識の焦点であるといいます。つまり、怪異という素材をからめることで見えてくる「現代」がある、というのが及川氏の考えであるとして、「なんらかの出来事が、なんらかのかたちで怪しまれたとき、それは怪異それ自体のことのみならず、それが怪異であり得る状況やなにかを怪しむ主体を照射している。または、私たちはなんらかの状況なり脈絡に拘束されながら、出来事を怪しんだり不思議がったり、ときには怖がったりしているともいえる。そのような状況なり脈絡が私たちを拘束するあり方こそが、筆者の目的であり、怪異はそれを考えるための(もちろん、極めて魅力的な)題材でしかないわけである」と述べます。
及川氏は、「怪異」を論じる専攻研究を概観します。民俗学におけるこの方面の先行研究としては、古いものでは今野圓輔の昭和32年(1957)の『怪談――民俗学の立場から』や池田彌三郎の昭和49年(1974)の『日本の幽霊』などがただちに挙げられます。
今野も池田も、民間信仰や説話の世界をふまえつつ、彼らの同時代の怪異・妖怪に論及していました。今野、「人間社会が変遷し、人の心や知識や環境が変わるにしたがって、それらの反映としての妖怪社会は、当然に人間社会とその変遷過程を同じくしている。かれらもまた、人間生活とまったく同様の時代により、環境によって変遷し、消長のあることが明白に立証される」と述べています。
実は柳田國男の妖怪研究にも、多分に同時代への意識がみられました。河童やザシキワラシなどの怪異が登場する『遠野物語』には、「要するに此書は現在の事実なり」と記されているのです。及川氏は、「つまり、おとぎ話ではないのだと、柳田は述べている。もちろん、怪異が実在するということを述べているわけではない。便宜上、怪異を前近代的なるものに比定するなら、柳田の意図は、近代日本における近代性の偏在、また同時に近代社会に前近代が偏在するという事実を、近代人たる読者に心づかせることにあったといえる」と述べるのでした。
「二.怪異に歴史をみる」では、「現代」の怪異を問題とするとき、それは今風の新趣向のみが関心の対象になるわけではないということを確認します。古典に確認できる話の趣向が、道具立てをのみ変えながら語りなおされていくあり方は、ひとつの変遷の問題である。日本でも有名なタクシー幽霊の怪談が、アメリカではヒッチハイカーの怪談になることはもはや周知の事実です。その一方、この怪談は日本でも近代には人力車の怪談でした。そして、池田彌三郎の示すように、同道した人物が死者であり、送り届けた先でその人物が死者であったことを体験者が知るという話は『今昔物語』にすでにみえます。
また、細部の相違はあるものの東日本大震災の被災地の怪談として今日も再生産されています。道具立てや状況の今日性が重要な留意点であることはもちろんですが、同型の話が変質しつつ時間を越えていくあり方も、この方面の興味深い問題です。そして、前近代社会において語られ得た怪異譚が、今日の社会においては見いだせないという事実もまた、ひとつの時代の志向を表していると指摘し、及川氏は「狐狸の類の活躍する怪異譚は現代においても語られ得る。しかし、その語られるあり方は、かつての社会におけるそれとは異質である。その相違が微細なものであれ、そこに私たちの『今』とそこに至る『過去』を照射する手がかりを探ることが、『現代』の『怪異』に歴史を見る醍醐味といえるだろう」と述べるのでした。
「三.怪異を表象する」では、「怪談を語ること」への注目が、民俗学と研究対象との関係を検証する意味をもつことに触れています。及川氏は、「怪異譚には、または怪談には、民俗学の研究成果が流入している。または、怪異譚を愛好する人びと、怪談のプレイヤーを自認する人びとは、必ずしもアカデミックな手順はふまないまでも、対象について『考察』を重ねる。研究者の発する言説と非アカデミックな探究者の言説は、一般向けの書籍やウェブサイトの情報のなかで、またはそれらの摂取を通して、綯い交ぜになりながら流通し、怪異のかたち/怪異譚のかたちを方向づけている。現代の子どもたちと語らう機会をもつと、話題が妖怪に及ぶことがある。漫画・アニメ・映画・ゲーム等で妖怪は人気のコンテンツだからであり、彼らの妖怪の知識量は相当なものである」と述べています。
現代の子どもたちの妖怪知識には、当然のことながら民俗学の研究成果が流れ込み、それと同等程度に近世の創作妖怪やアニメや漫画の情報が流入し、ひとつの像を形成しています。これは最近の子どもたちに特有の現象ではないといいます。子どものころに筆者が作成した自前の妖怪図鑑を先日引っ張り出してきたところ、個々の項目執筆に際して参照された情報源はやはり似たようなものであったとして、及川氏は「研究者もまた社会の情報伝達のネットワークのなかにおり、かつ、情報生産者として独特の役割を果たしている。先行研究の書き手たちは、怪異をめぐる言説空間のなかに、意識するにせよしないにせよ、あらかじめ参加している」と述べます。
それは及川氏も同様であるといいます。つまり、それはどこかの誰かの文化として無責任に記述すべきものであるよりは、無数の語り手・聞き手、書き手・読み手と筆者も含めた「私たち」の問題として再考される余地があるとして、及川氏は「民俗調査の場における話者の語りに、民俗学的な知識の還流がみられることは、早くから民俗学者の注意を引いてきたが、怪異を探究する私たちは、やはり、この怪異をめぐる世相に影響を及ぼすアクターであることは自覚されて良い。怪異を通してこそ手を取り合える。『私たち』というものがあるという意味において、それは学問が直面した困難な状況を指し示すものではない。民俗学は『私たち』をこそ、問うものともいえるからである」と述べるのでした。
2022年に成城大学を卒業した本間朱音氏は、第一章「現代の怪異譚における身体――『新耳袋百物語』と『山怪 山人の語る不思議な話』の分析から」の「一.先行研究の整理と問題の所在」で、現代の怪異譚を身体に注目して分析しています。そこで主要な分析対象とするのは木原浩勝・中山市朗の『新耳袋 現代百物語』(以下『新耳袋』シリーズ)です。『新耳袋』はすでに怪談実話・実話怪談への関心のもと、飯倉義之、伊藤龍平らによって注目されているとして、本間氏は「怪談実話・実話怪談は1990年前後に黎明期を迎え、1998年頃から拡大していった新しいジャンルの怪談であり、怪異についての説明がなく、内容に『オチ』がないことが特徴といえる。『実話』であるがゆえに因果や起承転結がなく、怪異合理的に説明することが不可能なのである」と述べています。
「五.『新耳袋 現代百物語』と『山怪 山人が語る不思議な話』」の「(1)『山怪』の概要と集計結果」では、『新耳袋』との比較対象として『山怪 山人が語る不思議な話』(以下『山怪』)を取り上げています。『山怪』は写真家・作家として活動する田中康弘が山関係・狩猟関係の現場を四半世紀以上にわたって歩く中で得られた不思議な話205話を全3巻にまとめた怪異譚です。「(3)現代怪異譚としての『新耳袋 現代百物語』の性格」では、『山径』における怪異を大きく6パターンに分類しています。「火の玉」「光の玉」「謎の光」の怪異、怪音や声の怪異、空間に作用し体験者を惑わせる怪異、神隠しのような怪異、動物の姿をした怪異、人型の怪異である。
本間氏によれば、怪異のあり方が似通っているのは、『怪』の事例における体験者が、狩猟関係者、山の周辺の集落に住む人に絞られていたためかもしれないと推測します。どの怪異についても背後には狐や狸などの動物が潜んでいることも指摘します。つまり、『山怪』に登場する怪異は、『新耳袋』の「狐狸妖怪を見たという話」として分類されるようなものが大半を占めていたと言えます。それに対し、『新耳袋』では、体験者の属性は多様であり、怪異のあり方や怪異との接触のあり方も非常に多様であったとして、本間氏は「もちろん人型の怪異、人間の身体部位を持つ怪異が圧倒的に多く現れるが、その怪異の様子も全身、欠損、個別の部位のみなど様々である。そして『山怪』において、怪異が体験される場が山やその周辺に限られていたのに対し、『新耳袋』では家、学校、会社など幅広く、現代の生活圏内で日常に近い状態であったことも特徴であると言える」と述べます。
『新耳袋』や『山怪』のような現代怪異識においては、怪異との直接的な身体接触だけではなく、「目で見ること」が怪異と交流するために非常に重要な行為となっていると指摘する本間氏は、「怪異を目で見る、つまり視覚で捉えることができなければ、その存在に気づくことができない場合さえある。しかし、『新耳袋』と『山怪』で語られる体験は、視覚優位であるという点では共通しているが、その怪異と体験者の関係のあり方は大きく異なる。『山怪』では『火の玉』『光の玉』などの現象や、狐、狸などの動物の怪異が中心であり、身体への接触が少なく、視線の交錯がないという点で、体験者が一方的に怪異を感知するという関係にあった。また人型の怪異に遭遇したとしても、それは動物が起こした『現象』として解釈される。これらの特徴から、『山怪』は不思議で不可解な現象の「観測」の物語であったと言える」と述べています。
一方、『新耳袋』には人間の姿をした怪異が多く現れ、体験者とは身体の接触や視線の交錯を通して、双方向的な位置関係にありました。またその身体には、生きている人間に近い身体観が反映されていました。『新耳袋』は、生きている人間の延長線上として捉えられる怪異が引き起こす、「交流」の物語であったと総括できるとして、本間氏は「『山怪』では怪音のみの怪異が多くあったのに対し、『新耳袋』では視覚と聴覚に同時に作用する怪異が多くみられた。仮に怪音が聞こえた場合でも、そのあとに怪異の姿を目撃するなど、聴覚に加えて視覚で怪異を捉えているのである。『新耳袋』も『山怪』も、各種の感覚のなかでも視覚が優位であったが、『新耳袋』はより顕著に視覚優位の時代が刻印された怪異譚集であるといえる」と述べるのでした。本書『現代の怪異あるいは怪異の現代』で最も興味深かったのは及川祥平氏の論文ですが、次に興味深かったのが大学を卒業したばかりの本間朱音氏のそれでした。優秀な若い研究者の出現で「怪異」研究はますます面白くなりそうです!