- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2014.08.26
『火山列島の思想』益田勝実著(ちくま学芸文庫)を読みました。
著者は、1923年に山口県下関市に生まれた国文学者です。東京大学文学部卒業、同大学大学院修士課程修了、長く法政大学教授を務めました。1989年に退職し、2010年に亡くなっています。説話研究や民俗学の視点を導入した研究で知られ、日本人の精神的古層を明らかにしました。
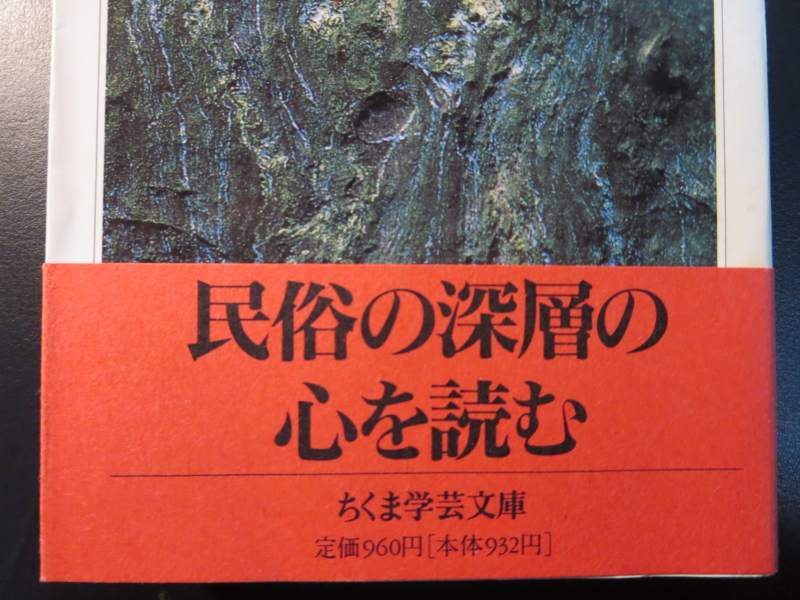 「民俗の深層の心を読む」と書かれた帯
「民俗の深層の心を読む」と書かれた帯
本書の帯には「民俗の深層の心を読む」と書かれています。また、カバー裏には以下のような内容紹介があります。
「日本人の心の原像とは何か? われわれの祖先たちはいかなる意識をもってこの火山列島に生き、またそれはどのようにわれわれの心に刻みこまれているのだろうか? 原始の日本人の呪術的想像力、そして古代的社会機構によるその変容のプロセスに、徹底した実証、渾身の学問的想像力で迫る、日本古代文学研究史上の記念碑的作品」
先日わたしは「現代の賢人」である上智大学名誉教授の渡部昇一先生と対談する機会に恵まれましたが、そこで「カミ文明圏」という興味深いお話しを伺いました。それ以来、わたしは「日本人の心」の原型としての「和」に強い関心を抱いています。本書を読んだのも「和」についてもっと知りたいと思ったからでした。「和」については、いずれ一書にまとめてみたいと考えています。
この『火山列島の思想』は、「バク転神道ソングライター」こと鎌田東二先生の愛読書だそうです。2012年9月23日の「朝日新聞」朝刊でも、「古事記1300年 鎌田東二さんが選ぶ本」として、同書が紹介されています。同年は『古事記』編纂1300年、『方丈記』著述800年、法然没後800年、親鸞没後750年という節目の年に当たり、鎌田先生いわく「日本の宗教や文化の総括と未来につなぐ力と知恵が問われている年」でした。
日本「古典」として第一に挙げられる古事記は、本居宣長の『古事記伝』以来、じつに多様な研究書が刊行されてきましたが、鎌田先生は改めて取り上げてみたい研究書として本書の名を挙げ、次のように述べています。
「この本を手にした学生の時、ワクワクした。『火山列島』のこの国にどのような『思想』が展開していったのか。『原始の日本人の呪術的想像力』を、古事記の創世神話や出雲神話や英雄伝説の内側に潜行して、その『呪術的想像力』のイメージと論理をたぐりよせる力ワザに目を瞠(みは)った。とりわけ、本のメーンタイトルともなった論考は、『日本的固有神の性格』という副題で、『オオナモチ』と呼ばれた『大国主神(おおくにぬしのかみ)』を、『大穴持の神として、この火山列島の各処に、時を異にして出現するであろう神々の共有名』で『火山の国に固有の神』と見てとるが、『3・11』後の日本社会の中での古事記や日本の神の問題を考える際、避けて通ることのできない視点であろう」
本書の目次は、以下のような構成になっています。
黎明 ―原始的想像力の日本的構造―
幻視 ―原始的想像力のゆくえ―
火山列島の思想 ―日本的固有神の性格―
廃王伝説 ―日本的権力の一源流―
王と子 ―古代専制の重み―
鄙に放たれた貴族
心の極北 ―尋ねびと皇子・童子のこと―
日知りの裔の物語 ―『源氏物語』の発端の構造―
フダラク渡りの人々
偽悪の伝統
飢えたる戦士 ―現実と文学的把握―
「あとがき」
「新装版あとがき」
「文庫版解説」(鈴木日出男)
「黎明 ―原始的想像力の日本的構造―」の冒頭には、「黎明の異変」として以下のように書かれています。
「原始社会における日本人の想像力の状況は、今日からはにわかに推測することができない。それは、ことさらに揣摩臆測を事とするものでなければ、あげつらう勇気を持ちえぬほど、確かな手がかりの少ない、茫々たるそのかみのことである。しかし、すべてが湮滅しさり、埋没しはてたかに見える原始の日本人の想像法が、ずっと後々まで強力に生き続けて、日本人の想像のひとつの鋳型の役割を果たしていることもあり、生き続けてきていると、かえってその古さに気づかないから、奇妙なものである。わたしたち日本人の脳裏では、実に永い間、闇の夜と太陽の輝く朝との境に、なにか特別な、くっきりした変り目の一刻があった。異変が起きるのは、いつもその夜と朝のはざま、夜明けの頃でなければならなかった」
「幻視 ―原始的想像力のゆくえ―」では、天理教の開祖である中山ミキの「おふでさき」などに触れながら、以下のように述べています。
「このような強烈な民間における神話のエネルギーの蘇りに対して、明治新政府の側が内部に保有しているのは、平田鉄胤らの国学者たちが頑固に保持してきた記紀の解釈でしかない。国粋主義の排外的・保守的狂信はあっても、かれら平田派の国学思想が、本居宣長当時の、既成の儒教思想・仏教思想から人間を解き放つ解放性を持ちえていなかったことは、いうまでもない。政府は肇国神話と紛らわしい『口記』の内容を嫌ったのであろうが、実はそれとともに、この中に籠る恐るべきエネルギーにあてられてしまったのだ、とわたしは考える。まともに、これに対抗できるエネルギーは、廃仏毀釈・国教樹立の大失敗を演じた後では、吹きまくる西欧思想の新風に圧倒されつづけの、明治の国学者たちの『古事記』の講釈の中には、もうどこにもなかったであろう。天理教が『口記』のためにも弾圧を受けたのは、その点から考えれば当然ともいえる。弾圧し、人々の眼から遠ざけずにおけるようなものではなかった」
そして、本書のタイトルにもなっている「火山列島の思想 ―日本的固有神の性格―」の冒頭には、以下のように書かれています。
「日本の神々がどこから来たかは、日本人がどこから来たかの問題である。そういう比較神話学的な問題の立て方に対して、わたしは片手落ちのようなものを感じている。同時に、この日本でしか生まれなかった神々、この列島生えぬきの神々のことも重視すべきではないか」
今や神道研究の第一人者である鎌田東二先生に大きな影響を与えたという「火山神オオナモチ」の論考は、以下のように述べられています。
「結局、火山神は、山容の神格化オオナモチから、噴火の神格化ヒの男神、ヒの女神、さらにその神の火への懼れ心から把握する神の姿オオモノイミへの、広い幅の中で仰がれ敬われていたわけである。火山神を重要視しなければならないのは、単に日本が火山列島であるからだけではない。神の不常在性、祭る者の忌みを重視しすぎて、神の客体化が弱い点など、信仰に現われた民族性が、火山神に集約してみられるからである。逆に言えば、火山神の少しもかかわり合わないところで、そういう民族性ができていったとは、どうしても考えにくいのである」
また、著者は「出雲の英雄神」としてのオオナモチにも思いを馳せます。著者は8世紀という後代の大隅のオオナモチの神によって、はるか前代の出雲のオオナモチの性格を突きとめようとする、倒立立証法を用いているわけですが、以下のように述べます。
「日本人の物の考え方が歴史社会の発展の中でどんどんと移り変りながら、一方、そういう新しい変動にさらされていないところには、ずっと後代まで古い形のものが残存する、後代によって逆に前代のもののそのまた祖型を考えうる、という倒立立証法が、この国の歴史の検討に有効な武器であることをもっともよく示したのは、柳田国男の樹立した日本民俗学であった。あのようなすぐれた方法が実験の中で磨かれていくためには、歴史の中でただ1回的惹き起こされた事件を、常住不断にうちつづいてきた常民の生活の中の事実よりも重視する、文献史学に対する懐疑と批判が大きな力となっている」
さらに続けて、著者は次のように述べています。
「不断に繰り返される事の中には、次々と新しいものが生まれつつ、古いものも死に絶えないでいろいろな形で生きながらえていく。古いということと、新しいということとが、断絶の契機においてのみ、古くあり、新しくあるようなものではないのである。大きな広がりと厚みを持って歴史は進展していく。日本民俗学のこうした方法は、対象の選択と把握にもおよび、日本の火山列島としての性格、火山列島での日本人の暮らしという面にもおよぶべきであった。しかし、そうならなかった。火山の脅威や火山灰地帯の生活の苦悩を、学問の対象にひき据えなかった」
本年5月27日、高円宮家の次女である典子さまと、出雲大社の神職である千家国麿さんとの婚約が内定しました。千家は代々、出雲大社の神事を司る「出雲国造」という役職を務めてきた家柄です。『古事記』『日本書紀』にある高天原から大国主神(オオナモチ)の下に遣わされた神「天穂日命(あめのほひのみこと)」を祖とします。その天穂日命は、天照大神の次男です。天照大神は天皇家を初めとする皇室の先祖としても知られています。つまり、典子さまと千家さんは、はるか昔の先祖を同じくするカップルなのです。
皇室のルーツである大和朝廷と古代出雲のについて、著者は述べます。
「古代の出雲と大和朝廷の関係は、他の諸国と中央政府の関係とたいそう違いがある。たとえば、出雲では国造が新たに任じられる時(もちろん、世襲であるが)、いま『国造さん』と呼ばれている千家・北島家の先祖たちは、上京して任命式に臨み、帰国すると1年間潔斎して出京、天皇に『出雲国造神賀詞』を奏し、ふたたび帰って、潔斎1年、ふたたび上京して貢献物を出し、同じ賀詞を奏する。捧げるのは、68個の玉、金銀装の太刀1ふり、鏡1面、倭文織り2端、月毛の馬1頭、鵠2羽、50荷の進物で、しかも、その時には、180数社の出雲国内の大小の神社の祝部が全部随行しなければならない」
そして、刺激的な論考である「火山列島の思想 ―日本的固有神の性格―」の最後に、著者は次のように述べています。
「神の出生も、その名の由来も忘れることができる。人間社会の生産力の発展、自然との対抗力の増大が、それを可能にした。しかし、その忘却の過程において、人々は、生みつけられた土地の神の制圧下にその精神形成のコースを規制されてきた。火山神は忘れられても、日本の火山活動が活潑であった時代に、マグマの教えた思想、マグマの教えた生き方は、驚くほど鞏固にこの列島に残っていったらしいのである」
「廃王伝説 ―日本的権力の一源流―」では、「月狂い」のわたしが心惹かれてやまないツキヨミが登場します。著者は、次のように述べます。
<・・・・・・ツキヨミ、・・・・・・万葉時代には、月のことがツキヨミだった。だから、月夜見なんて字で書くが、ほんとうは≪月の山≫という名じゃな。アフリカにある山のようだ。・・・・・・すると、この山は西側の村に顔を向けていた山だな。西の方の人が永年望み見てきた山だ。・・・・・・>
<ツキヨミは月、月読尊の山か。死んだ妻イザナミを慕って黄泉国へ行ったイザナキが、追われて逃げ帰り、海へ入ってみそぎする。その時、左の眼を洗うと、アマテラスが生まれ、右の眼を洗うと、ツキヨミが生まれた。
・・・・・・だが、ほんとうは、ツキヨミは月神そのものなんかじゃないはずだ。ヨミは「鯖を読むな」の「読む」で数えることのはず。月を数える神――神じゃない月齢視測者だ。月を祭る人のことじゃないか。ひとりじゃない、・・・・・・一族だろう。>
さらに、謎に満ちたツキヨミについて、著者は次のように書いています。
「この地上のあちこちに、ヒジリ(日知り)という太陽視測者や、モノシリ(霊知り)という霊力察知者たちが、ツキヨミ(月視測者)などとともにいた太古の日本。かれらはそれぞれに地方の司祭者で権力を持っていた。大和でヒジリと呼ばれた者たちの末裔=天皇家がいまも神聖視されているように、それは小規模なそれぞれの神聖家族だったに違いない」
本書全体の中で、わたしが一番心を動かされたのは、このくだりでした。さらに著者は、「聖家族の技能」として以下のように述べています。
「<神>と<神を祭る者>が融合、もしくは混乱して、神の権威を鎧った<神を祭る者>が天空へ上げられて<神>となっていく。ツキヨミはそういうものだ。信州諏訪の上社の大祝の家が神と呼ばれているのは周知のことだか、各地にいる神さん・大神さんは、実は神代さんという苗字の人と同じ性質の人々なのであろう。神の憑代となる人、神を招き下す人――神代とありのままに呼ばれる人々もあれば、権威に包まれて神とか大神とか呼ばれる人々もある」
日本民俗学にも精通した著者は、以下のように柳田國男と折口信夫という二大巨人の神に対するイメージの違いにも言及しています。
「日本の神の祖型を、<祖霊>とみる柳田国男と、<来訪するまれびと(ストレンジャー)>とみる折口信夫―あの深く尊敬し、いとおしみ合った師弟は、晩年になって、おたがいの神についてイメージをぶっつけ合ってみて、その根深い違いに驚いたのだった(柳田国男・折口信夫対談「日本人の神と霊魂の観念そのほか」『民族学研究』14の2、1949年)。片や死霊に、片や生身の人間にと、ふたりの巨匠の神の祖型の見つけ方の違いもさることながら、同時に、このふたりの民俗学的方法が、思わず知らず飛び越えてしまったものについても、わたしは考えこまざるをえない。神は誰れにとってもの神とはかぎらない。そして、祭る者の祭る技能の優劣が祭られる神の優劣をも決していくような、人対神の問題として、日本の神を考える必要が広汎にあるのではなかろうか。神の問題を祭る人間の方から考えていき、そこから、それぞれの神の個性をも、だんだんと突きとめていくべきではないのか。わたしはそう考えるようになっている」
「神」の問題を考えるならば、「祭」の問題が切っても切り離せません。著者は、「祭」について以下のように述べています。
「祭そのものは、くらやみ祭が、御神幸を人々に見せないために神輿の通路の灯火をすべて消すことを求めて、『くらやみ』祭と呼ばれるように、厳格な秘密性を持っている。元来は、ごく少数の事に携わる者以外は、屋内に忌み籠っていなければならない性格のものであった。長門・住吉神社(下関市)の神職が和布刈神社(北九州市門司区)に出向いて行なう旧の大晦日の夜の和布刈神事の折は、関門海峡の両岸の住民は、用便のためにさえも一歩も外に出ないことになっていた。隙間から海中のわかめを刈る神事の火をのぞき見することも固く禁じられており、戦前までは厳重に守りつづけられていた。そして、日本の神祭りの大衆の参加を拒むそのような性格、<神の独占>は淵源するところが遥かでもあった」
ここに登場する和布刈神事の舞台は、ブログ「和布刈神社」で紹介しました。鎌田先生と一緒に訪れたのですが、このとき先生は本書のこの記述を連想されたのでしょうか。
本書に収録された最後の論考である「飢えたる戦士 ―現実と文学的把握―」では、『平家物語』が論じられます。「フィクションとリアリティ」として、著者は次のように述べています。
「巨視的にみて、『平家物語』は、古代から中世への歴史的大転換期を生きた人の、自分たちの生きた時代に向かっての歴史的把握の試みであった。それを貫くものが、古代的世界の没落への惜しみない悲傷であり、その中に横たわっているものが、中世的な新しい人間群像と新しい人間関係に対する鮮烈な驚嘆であることが、この語りものを特色づけている。この物語のことを考えようとすれば、なによりも、大きな歴史の力を感受しての強い抒情と、歴史を構成する人間的事実に対する深い関心とが、作者をゆさぶり、作者の物語る意欲を搔き立てている点に、眼を注がなければなるまい。語りものとしての『平家物語』の成立に関する研究は、歳月を追って細密化し、複雑になりつつあるが、この点を逸することが出来ない」
本書で取り上げられているテーマはじつに幅広く、興味は尽きません。「文庫版解説」で、国文学者の鈴木日出男氏が次のように書いています。
「益田氏の関心はやがて、壱岐や沖縄の月の信仰の問題へと広がっていく。壱岐の神話では、神としての月を祭る者がツキヨミと呼ばれる壱岐県主であり、しかもその祭る者の氏族の職能神としてツキヨミの神が想定されていた。同じように沖縄では、月を祭るのがツキシロと呼ばれる第一尚家、その氏族の職能神がツキシロの神。神とその神を祭る者との間には厳然たる関係があり、しかもその中間に、祭る者の神格化が介在していて、彼らは神の子であることを僭称しながら本来の神を祭る。それが<祭る技術>である。益田氏は、このような図式を想定した」
火山神オオナモチも、『平家物語』も興味深いテーマですが、やはり最も興味を引かれたのはツキヨミの神に代表される月信仰の話でした。
