- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2025.06.28
この Ⅰ・Ⅱ 巻合計で70000字を超える、わが人生最大の書評を、謹んで著者の御霊に捧げさせていただきます。『日本人の死生観 Ⅰ 霊性の思想史』鎌田東二著(作品社)を読みました。日本人の「いのち」は死後どこへ行くのか。汎神論と習合思想の土壌に醸成された独自の世界像を『記紀』『万葉』から探る「たましい」の精神史です。日本思想史に燦然と輝く宗教哲学者である著者が遺作として発表した本であり、心して読みました。著者は、1951年、徳島県生まれ。京都大学名誉教授であり、わが‟魂の義兄”でした。その魂の兄は、5月30日18時25分、ご自宅で奥様に見守られながら、その偉大な生涯を閉じました。享年74。故人はステージ4のがん患者でありながら、八面六臂の大活躍をされました。宗教哲学、日本民俗学、国学、神智学、スピリチュアリズム、スピリチュアルケア、グリーフケア、そしてアート…「こころ」と「たましい」に関わる、あらゆるジャンルを自由自在に駆け巡った精神世界の巨星が墜ちました。まだまだ日本にとっても、わたしにとっても、必要な方でありました。
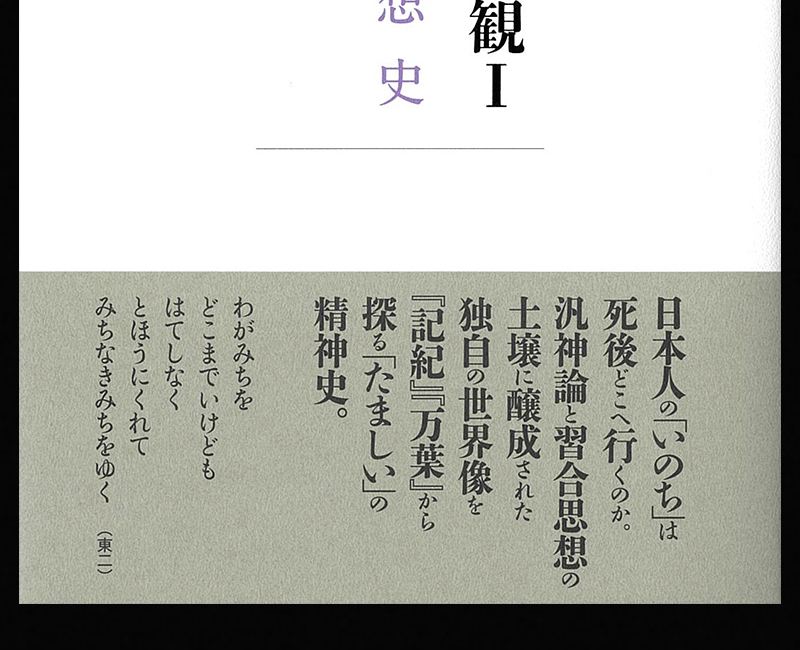 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、「日本人の『いのち』は死後どこへ行くのか。汎神論と習合思想の土壌に醸成された 独自の世界像を『記紀』『万葉』から探る『たましい』の 精神史。」「わがみちを どこまでいけども はてしなく とほうにくれて みちなきみちをゆく(東二)」と書かれています。
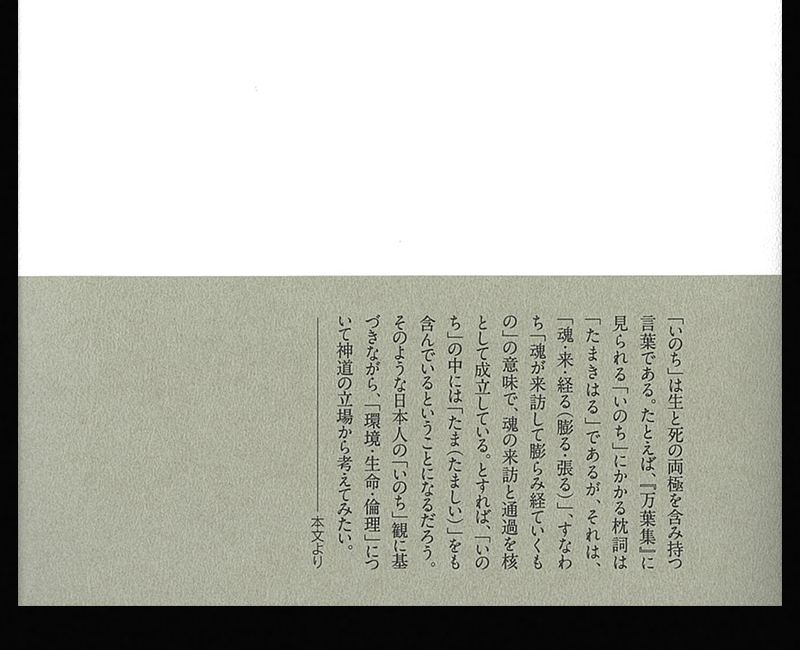 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、以下のように書かれています。
「『いのち』は生と死の両極を含み持つ言葉である。たとえば、『万葉集』に見られる『いのち』にかかる枕詞は『たまきはる』であるが、それは、『魂・来・経る(膨る・張る)』、すなわち『魂が来訪して膨らみ経ていくもの』の意味で、魂の来訪と通過を核として成立している。とすれば、『いのち』の中には『たま(たましい)』をも含んでいるということになるだろう。そのような日本人の『いのち』観に基づきながら、『環境・生命・倫理』について神道の立場から考えてみたい。(本文より)」

本書の「目次」は、以下の通りです。
序章 安部公房と三島由紀夫の比較から始める
第一章 「霊」あるいは「霊性」の宗教思想史
第二章 うたといのりと聖地の死生観
第三章 いのちをめぐる東西の自然理解と死生観
―環境・生命・倫理~神道の立場から
第四章 モノと霊性
―ものづくりからもののあれはまで
終章 言霊と神道
―草木言語から人間言語・地域言語への射程
「初出一覧」
「参考文献」
「あとがき――出雲系死生観」
「補記 出雲魂ルネサンス」
仮面の告白 (新潮文庫)
仮面の告白 (新潮文庫)
作者:三島 由紀夫
新潮社
Amazon
序章「安部公房と三島由紀夫の比較から始める」の「1、安部公房と三島由紀夫の『日常』と『非日常』の交錯と変容」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。
「安部公房の世界は『日常の中の非日常』である。ありえないことがさもありえるかのごとく自然に生起して知らず知らず不測の事態に立ち至る。誰にでも起こりそうな非常事態の襲来。それが安部公房の世界だ。それに対して、三島由紀夫の世界は『非日常の中の非日常』である。ありえないことがありえないように不自然に生起していかにもドラマティックに展開する。出生時の記憶を持つ主人公を描いた『仮面の告白』、然り。二・二六事件の青年将校や特攻隊員の「霊の声」を描いた『英霊の聲』、然り。20歳で死んで輪廻転生し続ける主人公を描いた『豊饒の海』四部作、然り。普通ならありえないことが次々と生起してくるその非日常世界の非日常性」
「2、明治と昭和の戦争世代論」では、安政5年生まれの井上円了(1858―1919、哲学者・東洋大学創設者)の提唱した「明治第二世代」論を基に、明治期に活動した人々の世代的課題について言及しています。まず、「明治第一世代」とは、維新の大業を成し遂げた最後の世代で、嘉永年間(1848―1854)までの間に生まれた人です。この世代は、新政府軍の長府藩(長州藩の支藩)報国隊に加わり戊辰戦争を戦った乃木希典(1849―1912、陸軍大将・学習院院長・乃木神社祭神)や反政府軍の会津藩白虎隊に関わった山川健次郎(1854―1931、物理学者・東京帝国大学総長・京都帝国大学総長・九州帝国大学初代総長)らがそうであるように、戊辰戦争や会津戦争や北越戦争に参戦した最後の世代です。つまり、勝利した新政府軍側であろうが、敗戦した反政府軍側であろうが、10代の終わりか20歳頃に「明治維新」を実体験した世代です。激動の時代に生まれたのが「明治第一世代」なのです。
続く「明治第二世代」は、安政元年(1854)から文久年間(1861―1864)に生まれた人で、実質的に、日本人として最初期の哲学や薬学や病理学や地球物理学や民権思想やキリスト教神学を担っていった人が多いです。日本の学術・思想の勃興期のリーダーたちといえます。井上哲次郎(哲学者・東京帝国大学文科大学学長・日本人初の東京帝国大学の哲学教授)、海老名弾正(牧師・思想家・熊本英学校創立者)、植村正久(牧師・神学者)、元良勇次郎(東京帝国大学文科大学の初代心理学教授)、坪内逍遥(小説家・劇作家・翻訳家・早稲田大学教授)、嘉納治五郎(柔道家・講道館創設者・東京高等師範学校校長・旧制五高校長)、内村鑑三(キリスト教思想家)、森鴎外(陸軍軍医総監・小説家)、新渡戸稲造(農政学者・教育者・東京帝国大学教授)、岡倉天心(思想家・東京美術学校校長)、徳富蘇峰(思想家・『国民新聞』主宰)、清沢満之(真宗大谷派僧侶・宗教哲学者)、二葉亭四迷(小説家)、伊藤左千夫(歌人・小説家)、津田梅子(教育者・津田塾大学創立者)などで、井上円了はこの「明治第二世代」です。
そして「明治第三世代」は、幕末の慶應元年(1865)以降の生まれで、日本独自の独創的な思想や文学を展開していった改革者たちです。江戸時代最後の慶應3年(1867)生まれの南方熊楠や夏目漱石や正岡子規、また明治3年(1870)生まれの西田幾多郎や鈴木大拙、さらには明治4年(1871)生まれの出口王仁三郎、明治8年(1875)生まれの柳田國男を挙げることができます。これら「明治第一世代」「明治第二世代」「明治第三世代」にはそれぞれの時代と世代の課題や役割や特色があったといえます。そしてその世代差は大きかったともいえます。それは、政権や体制が劇的に転換する戦争を体験しているかどうかの違いです。
この明治という日本近代において、誰が、なぜ、文学を推進したのかを考えると、その多くが敗残者(挫折者)であったと、著者は指摘します。官軍と賊軍(旧幕臣)の区別でいえば、賊軍側に立つ者が文学の道に進んだわけです。徳川体制から明治体制に転換する際の敗者が世界と心の裏を覗き込み、その苦悩を描いたとして、著者は「薩長など新政府軍側は勝者として表舞台の政治・経済を牽引・運営する。それに対して、文化・教育・芸術・宗教(キリスト教などは特に)に関わる者は、旧幕臣を含む敗者や下級士族や没落士族の子弟が多かった。近代化から外れた者と文学や芸術や宗教との関係は根深いものがある。おそらくそれは『古事記』や『平家物語』の時代からそうであっただろう。『古事記』とは新体制の『新事』に対する『古事』であろうから」と述べています。
こうした「明治世代」論を1つの指標として、著者は「昭和世代」論を考えてみます。つまり、戦争前と戦争後とに大きく区分し、その戦争に関わる世代の年齢差から世代の特質や課題を見て取るという指標です。しかし、ここで考えておかなければならない重要な点は、戊辰戦争や明治維新が国内戦であり、そこでは勝者も敗者も共に日本人でしたが、昭和の戦争は国外戦、すなわち日中戦争と太平洋戦争という国外戦であり、日本国家および全日本人が「無条件降伏(ポツダム宣言受諾)」という「敗戦」を体験したという大きな違いです。著者は、「つまり、昭和の戦争には勝者はどこにもおらず、敗者しかいないという違い」に注目します。その違いを踏まえて、「昭和世代」を考えてみると、大きく、「大正生まれ」と「昭和一ケタ世代」と敗戦(一般には「終戦」という)前の「昭和二ケタ世代」と「戦後世代」の4世代の違いを想定することができるといいます。
この観点から、著者は以下の文学者や思想家を挙げます。
①大正末期世代:安岡章太郎(1920〈大正9〉―2013)、加藤清(1921〈大正10〉―2013)、司馬遼太郎(1923〈大正12〉―1996)、遠藤周作(1923―1996)、安部公房(1924〈大正13〉―1993)、三島由紀夫(1925〈大正14〉―1970)、梅原猛(1925―2019)・海野和三郎(1925―2023)
②昭和ヒトケタ世代:河合隼雄(1928〈昭和3〉―2007)・土方巽(1928―1986)・澁澤龍彦(1928―1987)、加賀乙彦(1929〈昭和4〉―2023)、開高健(1930〈昭和5〉―1989)、小松左京(1931〈昭和6〉―2011)・高橋和巳(1931―1971)・山折哲雄(1931―)、高橋たか子(1932〈昭和七〉―2013)・石原慎太郎(1932―2022)・五木寛之(1932―)
③昭和二ケタ世代:大江健三郎(1935〈昭和10〉―2023)・美輪明宏(1935―)・寺山修司(1935―1983)など。
このような世代論を踏まえて、著者は「昭和20年(1945)の敗戦時に20歳前後の大学生であった遠藤周作や安部公房や三島由紀夫や梅原猛らが戦争と日本国ないし日本文化に対して持つそれぞれの思いの深さと複雑さを、その後の彼らの活動の中から垣間見ることができる」と述べています。『豊饒の海』全巻に登場する唯一の人物であり狂言回し役の判事である本多繁邦は、「輪廻転生」する主人公の「審神者」ですが、最後の最後に、「神」も「美」も松枝清顕も飯沼勲も月光姫もすべてを見失ってしまうとして、著者は「それは唯識哲学とニヒリズムとアナーキズムを三島美学のレトルトの中で変容・消滅させる錬金術のワザである。実際、三島由紀夫は、この最後の原稿を書き上げた1970年(昭和45)11月25日の朝、原稿を編集者に託した後、自衛隊市ヶ谷駐屯地に向かい、楯の会会員と共に東部総監室に押し入って自決したのである」と述べます。
三島由紀夫は『豊饒の海』第一巻『春の雪』の最後に、この作品は「『浜松中納言物語』を典拠とした夢と転生の物語」と注記しています。著者は、「三島由紀夫は生命尊重と基本的人権を最優先する現代の人間観や社会通念に抗して、あえて反時代的な悲劇的物語を『仮設』するために『輪廻転生』の思想に依拠し、その作品の完結直後に「七生報国」と染め抜いた鉢巻を締めて自決したのである。この三島由紀夫の周到さを嗤うことはできない。その三島由紀夫が、『日本文学小史』の中で、民俗学を『奥底にあるものをつかみ出す』学問として徹底的に批判したのは実に興味深い」と述べています。
『仮面の告白』の作者である三島由紀夫は、表面の奥底にある「仮設」される「深層」や「真相」や「真実」というものの噓くささと仮構性を見抜きました。そのような近代的思考の基底にある「思考方法」に疑義を表明し激しい批判と拒絶を示したのです。形あるものをそのまま受け取らず、常に“裏”や“奥底”を探り当てずにはいられない“剥ぎ取る”思考に三島は思考の頽廃と下品と虚無を感じ取ったのです。「私はかつて民俗学を愛したが、徐々にこれから遠ざかつた。そこにいひしれぬ不気味な不健全なものを嗅ぎ取つたからである」と三島は言いますが、著者は「この『いひしれぬ不気味な不健全なもの』とは、『奥底』とか『無意識』とか“内面”を『つかみ出す』思考と意図であり、いかにもそれらしい“真実”なるものである」と述べます。
さらに、著者は以下のように述べています。
「私たちはこの三島由紀夫の『奥底にあるものをつかみ出す』思考に対する批判の先行形態として、『ツァラトゥストラかく語りき』の中のニーチェの背後世界論批判を想起する。ニーチェは、この現実世界の奥や内や裏や背後に天国や霊魂の世界などを想定する思想を『背後世界論』と呼び、それを『奴隷の思想』として徹底批判した。西洋思想を支えた二本柱であるキリスト教もプラトン哲学も共に二元論的な『背後世界論』で、それがルサンチマンに満ちた弱者の思想であると拒絶した」
この点ではニーチェ主義者であった三島由紀夫は、「私には無意識はない」と豪語し、深層構造を掘り下げる営みを同様に「奴隷の思考」と拒絶しました。そして三島は「奥底」や「深層」ではなく、表面の「フォルム=形」に執心しました。『文化防衛論』の中で三島は、「文化は、ものとしての帰結を持つにしても、その生きた態様においては、ものではなく、又、発現以前の無形の国民精神でもなく、一つの形(フォルム)であり、国民精神が透かし見られる一種透明な結晶体」であると述べています。著者は、「考えてみれば、三島由紀夫の讃美した『天皇』も『武士道』も彼の死にざまである割腹自決もみな、『形』(あるいは「型」)の文化であったといえる。三島はこの『形=フォルム』の中に民族の精神性の結晶、『国民精神が透かし見られる一種透明な結晶体』を見て取ったのである」と述べます。
三島は『英霊の聲』の冒頭で、神道の祭りを「顕斎」と「幽斎」に分けて説明しています。「顕斎」とは、賀茂神社の葵祭とか八坂神社の祇園祭とかの神前に神饌をお供えして斎主が祝詞を奏上し宮司以下参列者が玉串奉奠して拝礼して神事の後で神人共食儀礼の直会をする通常の祭りの形態をいいます。対して「幽斎」とは「帰神の会」が行っている「帰神の法」の実修を含むシャーマニスティックな修法・儀礼で、「霊を以て霊に対する法」、伝統的に「神懸り」と呼ばれるシャーマニスティックな儀礼です。著者は、「三島由紀夫の『英霊の聲』は、鎮魂の芸能である能がそうであるように、『怨霊の聲』を取り次ぐ語りであった」と喝破します。
特攻隊の霊は確かにひとたびは「英霊」として祀られはしましたが、しかし「英霊」とは名ばかりで、それを支える「国体」も信仰実体も消滅しました。だから「英霊」は戦後日本の虚偽体制の中で「怨霊」化するほかないのです。その「怨霊」の崇りの言挙げとして『英霊の聲』は記されているのです。だからこそ三島は執拗に「などてすめろぎは人間となりたまひし」と呪詛的言挙げを繰り返したのです。著者は、「それは、日本人にとって、神とは何か、霊魂とは何か、祈りとは何か、祭りとは何か、神社とは何かと問いかける日本文化論でもあった」と述べます。
三島由紀夫が『英霊の聲』を発表した1966年(昭和41年)の2月1日、三島と阿部公房の対談が「二十世紀の文学」と題して『文藝』2月号に掲載されましたが、その中で三島は「自分が非常に自由だという観念は、伝統から得るほかないのだよ。僕がどんなことをやってもだよ、どんなに西洋かぶれをして、どんなに破廉恥な行動をしてもだね、結局、おれが死ぬときはだね、最高理念をね、秘伝をだれかから授かって死ぬだろう」と語っています。この三島の発言について、著者は「おそらくこの頃『英霊の聲』を構想していた三島由紀夫は、『死ぬとき』に授かる『最高理念』や『秘伝』を夢見、そこに日本文化の神髄を見ようとしていた」と述べています。
日本の「伝統」には方法がなく、方法論がありません。ただしかし、「結晶体」だけはあります。それは基本的に主体とか自己実現とか成長という「個人」的な過程とは異なります。「個」ではなく、“道”ともいうべき「伝承すべき至上理念」があって、そこに向かって伸び育っていって「最高度に達したとき」に何かを「つかむ」のです。だが、そこで終わります。だから、「結晶体」は残るのです。だが、それがある方法論に従って伝授されるというものではありません。そのような「伝統」が日本の「伝統」ですが、三島は、「結局、日本の伝統というものの観念は中世に出来た」と指摘します。著者は、「それは古代からあったものではない、というのが三島の『伝統』論であり、日本文化論である」と述べるのでした。
「補記 梅原猛の三島由紀夫論」では、梅原猛と三島由紀夫は大正14年(1925)の同年生まれ、同学年の同級生となることが紹介されます。梅原猛は二つの三島由紀夫論を書きました。1つは、『百人一語』(朝日新聞出版、1993年)の中の短い三島由紀夫論で、梅原猛が山背大兄王、小野小町、南方熊楠、種田山頭火、曾我蕭白、川端康成、湯川秀樹など100人の著述や残された言葉の中から「一語」を選びそれにコメントしたもので、1990年から1992年にかけて毎週掲載された『朝日新聞』の記事をまとめて単行本にしたものの中にあります。そこで、梅原猛は三島由紀夫の数ある小説の中で一番好きなのが『海と夕焼』という短編で、その「いくら祈つても分れなかつた夕映えの海の不思議」を問題にしています。梅原は「この短編は、三島由紀夫という詩人の最も根源的な内面の秘密を語るもの」と洞察した。そして、「三島由紀夫は『奇蹟』なしには人生を生きるに耐え得ない人間であった」と論評し次のように締めくくっています。、
その背後には、おそらくは彼の不幸な幼児体験があろう。不幸な幼児体験を持った人間は、夢、あるいは奇蹟なしに人生を生きることが出来ない。彼にとって文学、あるいは詩は、そういう奇蹟を現出する魔法の杖であったが、彼は作品の上だけでなく、現実にもこのような奇蹟の実現を夢見たのである。そして戦後の啓蒙的合理主義に導かれた高度経済成長時代が来て、人々が全く奇蹟の足音を感じなくなると、彼はますます懐かしく奇蹟への強い希望に生きていた戦争の時代、特にあの純粋な『天皇信仰』に生きた特攻隊のことを想起したのである。そして彼はその奇蹟の希望を再現しようとして、まことに滑稽と思われる壮絶な死を遂げたのである。
私は生前には彼の日本観を厳しく批判したが、今は私と同年のこの「天才」に、強い同情を感じている。
(『百人一語』P.293)
著者によれば、梅原猛は、三島由紀夫の「弱さ」「孤独」「役者」的ふるまい、「愛と死の原点」について指摘していますが、もっとも興味深く予言的な指摘は、三島の代表作『金閣寺』と遺作『豊饒の海』四部作を論じた「三島と南北」の最後に書かれた「もとより、近代人三島が生れ変りの話をそのまま信じていたとは思われないが、作品においても、行動においても、生れ変りの説に、三島は自己を賭けていたと私は思う。松枝清顕の生れ変りが次々現われたように、三島由紀夫の生れ変りが次々に現われるということが、死に際しての、彼の強い願望であったと思われる。三島由紀夫の生れ変りは、やがて次々と現われて、日本の政治や文学の世界を悩まし続けるような不吉な予感が、私にはするのである」という文章です。
著者は、「梅原猛の『三島由紀夫の生れ変り』の『予言』を、オウム真理教事件の首謀者で絞首刑となった麻原彰晃(松本智津夫)や神戸連続児童殺傷事件を起こした酒鬼薔薇聖斗(少年A)を含めるとすると、『芸術新潮』昭和52年(1977)5月号に記されたその『予言』は、ほぼ半世紀を経た今日、底知れぬ不気味なメッセージを我々と社会(世界)に突き付けている」と述べるのでした。
第一章「『霊』あるいは『霊性』の宗教思想史」の「2、樹木のメタファーと問題意識」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。
「身体を一本の樹木にたとえるならば、心は樹木の中を流れる樹液である。そして霊は樹木に穿たれた、例えばトトロが棲んでいるような空洞、すなわち孔である。樹液である心は根を通して大地から水を吸い上げ、養分を幹や枝葉に送り込む。それに対して、樹木に穿たれた空洞=孔は大地とも天空ともつながり、同時にそれをも突き抜け、樹液とは異なる回路で洞内に風を送り、気を送り、想いを送る。その時、霊としての空洞=孔は異次元へと開かれた回路(チャンネル)となる。霊と心と身体との関係を、まずはそのようにイメージしておこう。『霊』とは何かという問いは、換言すると、この世界とはどのような存在なのか、どのような存在世界の構造になっているのか、その中で、生命や人間はいかなる存在性と位置を占めているのかという問いとなる。それを内実=内包から問うか、外延から問うかという違いはあっても、いつしかこの二つの問いの方向は必ずや交差する」
20世紀の流れを人間に即して概括すれば、まず20世紀とは人間理性への懐疑から始まり、身体=深層的自己への注目に至り、ついには霊あるいは霊性・スピリチュアリティへの回帰が起こっているように見えます。著者は、「理性(精神)への懐疑と身体=深層的自己への注視は、マルクス、ニーチェ、フロイトという3人の無神論的反ヘーゲリアンによってもっとも過激に主張された。この3人は20世紀思想を誘導した思想的預言者であった。だが皮肉なことに、ヘーゲルが『霊=Geist』を語りすぎたあまり、彼らは多かれ少なかれ『霊=Geist』の存在を否定した。それを人類史的幻想ないし執着として思想破壊した。にもかかわらず、20世紀を過ぎ21世紀に入った昨今、『霊ブーム』、『スピリチュアル・ブーム』だといわれる」と述べています。
高度経済成長を終え、バブルがはじけた後、1995年に阪神淡路大震災とオウム真理教事件が起こりました。その2つの出来事は破壊と混迷と不安の時代の始まりの象徴であったという著者は、「これによって、当時の精神世界ないしスピリチュアル系に大きなダメージがあった。そして1998年以降、自殺者数は3万人を超えた。その数は交通事故の3倍以上の数であり、中でも中高年の男性の自殺が増えている。その後、2001年に9・11同時多発テロ事件が起きた。また2003年には離婚件数が30万組を突破。毎年80万組が結婚して、約30万組が離婚する。(2023年の婚姻件数は約47万組、離婚件数は18万組)ここには安定した社会秩序への信頼と安らぎはない。そのような不安の高まる中で、空洞としての孔が開き始める。人々は空虚な穴ではなく、つながりの回路としての孔を求めている。それを、この世の関係性と因果律で説明し尽くすことのできない異次元回路の孔の物語によって心の空虚を埋める。スピリチュアル・ブームといわれる現象の底にはこのような霊・スピリチュアリティという孔への希求があるのではないか」と述べるのでした。
「3、縄文の霊性と木と貝」では、日本、より具体的には日本列島における死生観の歴史を考える時、旧石器時代と新石器時代の霊についての思想性や死生観を考察してみる必要があるといいます。大局的に言えば、日本列島に独自の文化形態が生まれたのは縄文時代で、その期間は草創期から晩期まで1万年以上の長期に及びます。そこで考えなければならないのは、縄文遺跡から出土した巨木や渦巻き模様や動物の描かれた土器などの文様の意味するものです。ここで、著者は青森市で発掘調査された三内丸山遺跡に注目します。三内丸山遺跡は2000年に、国特別史跡に指定されましたが、人々を驚嘆させたのは、直径と深さが約2メートルの柱穴を掘り、柱を立てて造った大型掘立柱建物跡でした。そこに直径約1メートル、高さ約20メートルと推定される6本のクリの巨木が間隔4・2メートルおきに立っていたことがわかったのです。そしてそれは約35センチの長さの単位でできていたといいます。
この6本柱の長方形の建造物が何であるかについて、縄文考古学者の小林達雄は、日の出や日の入りに関係する宗教的施設だと解釈していますが、未だ定説といえるものはありません。小林は、縄文時代に大きな生活革命がなしとげられたと考え、それを「縄文革命」と総括し、具体的方針を「縄文姿勢方針」としています。そこにおいて、遊動的生活様式から定住的なムラを営む大転換が起こり、技術革新、社会文化革新が進んだとします。それによって、ムラの中に住居や食物の貯蔵穴や倉庫やゴミ捨て場や公共的な広場や共同墓地が造られ、人工性を強め、人間の住むムラと周囲の自然=ハラとの対立的関係が生まれたというのです。しかしその対立関係は、決して自然を征服の対象とするような敵対関係でなく、むしろ自然の秩序から距離を置くことで自然との揺るぎない新しい関係構築に向かう転換だったと捉えるのです。すなわち、自然=ハラはヒト―ムラにとっての倉料庫や資材庫となり「共存共栄の場」となったとするのです。
もう1つの縄文遺跡、能登半島先端部にあって富山湾に面した石川県の真脇遺跡にも驚くべき出土品があります。ここには、紀元前6000年頃の縄文前期初頭から紀元前1000年頃の縄文晩期終末までの約5000年間の長期定住の遺品があり、そのため「縄文文化の宝庫」と呼ばれています。特に、数百頭のイルカ骨と巨大環状木柱列が有名です。後者の縄文晩期の巨大な10本のクリの半割材を環状に立て並べた環状巨大木柱列は、じつに壮観です。この巨大環状柱列も三内丸山遺跡の大型掘立柱と同様すべてクリ材で、樹皮をはがして半割にしてあり、柱を円形に配列して立てる時に弧の方を内側、半割面を外側へ向けていますが、著者は「実に興味深いデザインである。この環状柱列は能管の作り方である八ツ割返し竹製法を思い起こさせる」と述べています。
八ツ割竹製法や「喉」によって編み出された能管の奇妙な音は、縄文遺跡から出土する「石笛」と呼ばれる自然に穴の開いた石(一部は人工的に孔を開けている)が生み出す音と酷似しています。作曲家の広瀬量平や哲学者の上山春平は、能管の音の原型はこの石笛であると指摘していますが、著者もその説に賛成だといいます。それでは、なぜこのような不思議な音が生み出されたのか。著者は、「それは、間違いなく、音によって異次元回路を生み出すためだと思う。つまり、霊的世界との交信のためにこのような音が繰り返し必要とされたのだ。それは超音波的な、複雑微妙な倍音を持つ力強い響きである。この音によって縄文の人々はたましいの回路を確保した。夢幻能の多くは死者の霊を呼び出し、その思いを存分に語らせ、それによって鎮撫するかたちをとるが、そのような死者との霊的交感の時空を招き寄せる音響を必要としたために、石笛の音が能管という日本独自の笛に引き継がれたのではないだろうか」と述べます。
「霊」という観点から日本の宗教文化を捉える際に、縄文時代の霊性的感覚と死生観の考察を抜きにすることはできないということです。確かにそれを確実な資料によって明確に描き出すことができないことも事実ですが、豊富な縄文土器の文様や巻貝型土製品や石笛から推測する試みを放棄してはなりません。その先鞭をつけた画家で民俗学者の岡本太郎は、著書『美の世界旅行』で「大地の奥底にひそんだ神聖なエネルギーが、地上のあらゆるものをゆり動かす、そんな超自然の力がここに圧縮され、あふれ、凝集している」「太い線が混沌の中から浮びあがり、逞しく、奔放に、躍動し、旋回する。幾重にも幾重にも、繰りかえし、のたうち廻り、ぎりぎりとうねって、またとんでもないところにのびて行く。この無限に回帰するダイナミズム。深淵をはらんだ空間性。凄まじいとしか言いようがない」と、縄文土器の持つ「神聖なエネルギー」を評しています。また、著書『日本の伝統』では、縄文土器の「美観」は「四次元との対話」から生まれたとも述べます。
「4、『むすひ』という霊力」では、『古事記』の冒頭に登場する造化三神は、天御中主神と高御産巣日神と神産巣日神で、このうち二神が「むすひ」という名を持っていることが紹介されます。それは自然の生成力を指す言葉で、大野晋は、「《ムスは、ムスコ(息)・ムスメ(娘)のムスと同じ。草や苔などのように、ふえ、繁殖する意。ヒはヒ(日)と同根。太陽の霊力と同一視された原始的な観念における霊力の一》生物がふえてゆくように、万物を生みなす不可思議な霊力」(『岩波古語辞典』)であると規定しています。著者は、「ここで注意しておきたいのは、『古事記』ではそれに『産巣日』という漢字を当て、『日本書紀』では、『高天原に所生れます神の名を、天御中主尊と曰す。次に高皇産霊尊。次に神皇産霊尊。皇産霊、此をば美武須毘と云ふ』とあるように、『産霊』という漢字を当てている点である」と指摘しています。
なぜ、「むすひ」という言葉にこのような漢字が当てられたのでしょうか。著者は、「間違いなく、そこに強烈な霊力を喚起せしめる必要があったということだろう。それが『日本書紀』の『産霊』という字に結実した。と同時に、その霊力は『日』の中にもっとも強くみなぎっている。そして『巣』あるいは母胎のようにいのちを産み出す源である。それが『古事記』の『産巣日』という漢字を選び出させたのではないか。『古事記』も『日本書紀』も和語を漢語に置き換える際にさまざま工夫を凝らしている。この「むすひ」を「物を生成することの霊異なる神霊」と捉えたのが国学者の本居宣長です
本居宣長によれば、「むすひ(むすび)」とは「物の成出る」さまを言い、『日本書紀』に「産霊」を当てているのは適切な判断であると見ています。特に「霊」の字はよく言い当てていると指摘しています。興味深いのは本居宣長が「産霊」を、「物を生成することの霊異」を現し出す「神霊」であると規定している点です。すべての「物」は「産霊」の霊力によって成り出づるという理解です。著者は、「これは平たく言えばものを生み出す不思議なエネルギーということだろう。岡本太郎のように、『大地の奥底にひそんだ神聖なエネルギー』と言ってもいいだろう。さらに本居宣長は、八百万の神々の中でもとりわけこの神聖エネルギーたる『むすひ』の神は尊く『有るが中にも仰ぎ奉るべく、崇き奉るべき神』であるとその根源性と尊貴性を強調している。日本人の霊性的感覚を考える時、このような『むすひ』の観念に結実してきた神聖エネルギーの感覚と思想の糸を手繰り寄せる必要がある」と述べます。
ところで、折口信夫は「産霊の信仰」の中で、「産霊の神は、天照大神の系統とは系統がちがふ」と指摘し、「人間の身体の内へ霊魂を容れる・霊魂を結合させる」ことが「産霊の技法」であると主張しています。折口信夫は「産霊の技法」とは水を掬い飲む時に水が身体の中に入っていくように「霊魂」が身体の中に入っていくことととらえています。別の言い方をすれば、霊魂は出し入れすることができるということであり、それが招魂やたまふり・たましづめやたまふゆとしての鎮魂であり、神楽などの神事民俗芸能はそのようなたまふり・たまふゆの技であったということになります。このような霊魂の出し入れや増殖生長に関わる呪的行為が「産霊の技法」とすれば、それは極めてシャーマニスティックな技術であったとして、著者は「宗教学や人類学の述語を使って言うならば、アニミズム的な霊魂存在論とシャーマニズム的な霊魂操作法が不可分になっているところに『産霊の技法』があると解釈できる。とすれば、本居宣長はアニミズム的な位相に目を向け、折口信夫はシャーマニズム的な位相に目を向けて『むすひ』を解釈したといえようか」と述べるのでした。
「5、『古事記』と『日本書紀』と『日本霊異記』の中の霊木信仰」の冒頭を、著者は「おおむね、カミもムスヒも、自然の持つ神聖エネルギーであると包括できるが、それがより具体的にまた感覚的に感知される場と物体が神社の杜と木である。神木ないし霊木として注連縄を張られ尊崇されてきた神聖樹木がそれである。木こそは『大地の奥底にひそんだ神聖なエネルギー』をもっとも具体的に集約した物体である。日本人はこの木の中にカミを見、そのカミの見えない姿の上にホトケの像を彫り出したのだ」と書きだしています。日本で最初に造られた仏像は木彫仏で、しかもその木は、雷鳴のような音響を発し、太陽のような明るい光を放っている楠木の流木でした。著者は、「まさにそれはかつて、『となりのトトロ』が棲んでいたような森の神木、霊木だったのだろう」と述べています。
そのような霹靂の木から最初の仏像を造ったことの意味は底深いものがあるといいます。それは言い換えると、ホトケをカミとして二重崇拝していることになるからです。著者は、「この限りにおいては、カミがホトケに化した、変化・変貌したのである。カミはきまったかたちを持たないから(ゆえに、鏡や玉や剣が御神体とされ得たのだから)、仏像に変貌することには何の感覚矛盾も論理矛盾もなかったといえる。しかもそれはもともと神木なのだからホトケという新しいカミに変化することには何の抵抗もなかったであろう。ここにアニミズムの風景を読み取ることは無謀なことではない。『アニミズム』概念や宗教進化論や宗教優劣論をめぐって批判的な論議も交わされているが、木というモノにいのち(霊性的生命)が宿り、たましいが宿っているという感覚を否定することはできないだろう」と述べています。
「6.『霊威』の位相学」では、いつ頃からか、日本人はある神聖感情を抱く対象を「カミ」と呼ぶようになったことが紹介されます。その「カミ」の種類を、雷や石や海や山や地震など自然現象や自然物を対象とする自然神、蛇や猪や鹿などの動物を対照とする動物神、杉や楠や桂などの植物を対象とする植物神、神功皇后やヤマトタケルや菅原道真や徳川家康などの英雄的活躍をした人物を対象とする人間神などと類別することができます。本居宣長が『古事記伝』で展開した「カミ」の定義は、「世の常ならず、すぐれたる徳のありて可畏きもの」というものでした。
このような「カミ」観念のもとでは、「お化け」や「妖怪」もまた「カミ」の一種です。柳田國男は「妖怪」を「零落した神々」と捉えました。著者は、「私は、『神』とは『フォルダ』であると捉える。神聖エネルギーに関わるさまざまな情報や状態や形態を統合し、まとめ束ねている結集点でありフォルダが『カミ』と呼ばれるようになったのだと。日本人が抱いてきたある特定の神聖感情や情報や力や現象を取り込んだフォルダが『カミ』で、そのフォルダの中にざまざまな『霊』や『霊威』や『妖怪』や『怪異』や『霊異』のファイルがあるというわけである。そのファイル群の中に、例えば『チ』・『ミ』『ヒ』・『モノ』・『ヌシ』・『タマ』・『オニ』・『ミコト』等々八百万ファイルが入っている。それらが神威、神格、霊性を表す言葉である」と述べます。
宮崎駿監督の人気アニメ『となりのトトロ』ではトトロを指して「森のヌシ」と呼び、『千と千尋の神隠し』ではヘドロに取り巻かれた神を「あれは名のある川のヌシだよ」と呼んでいました。プラス的イメージであれ、零落したり災厄をもたらしたりするようなマイナス的イメージであれ、「すぐれたるコト」のある「カシコキモノ」が総称されて「カミ」と呼ばれるようになったのです。また、『万葉集』では「カミ」に掛かる枕詞は、「ちはやぶる」ですが、その「ち」は「イカヅチ」などの「チ」の霊威・霊格と同じ語です。つまり、「ち」という霊威のある神聖エネルギーが、猛烈な速さ(はや)で、振動し運動している(ふる)状態が「カミ」と呼ばれるにふさわしいもの・ことというわけです。
さらにまた、『万葉集』では「いのち」に掛かる枕詞を「たまきはる」と呼びました。「たまきはる」とは、「魂・極まる」、「魂・来・経る(膨る)」の意味を持ちます。とすれば、「いのち」とは、「いのち」をして「いのち」たらしめる「たま」が体に入り込んで成長をとげ、やがて極まりゆくことを指しています。その「いのち」の「ち」も「ちはやぶる」の「ち」も同語です。著者は「こうして日本列島に神聖エネルギーの諸相と総体を「神」と呼ぶ文化が培われてきたのである」と述べるのでした。
「7、『源氏物語』とモノノケ」では、平安時代の宮廷の恋と雅の世界を描き、本居宣長によって「もののあはれを知る」美意識の典拠とされた『源氏物語』は、その影の側面を覗くと、「もののけの怖さを知る」文学であり、「霊異」のおののきに満ちていることが指摘されます。『源氏物語』の作者の紫式部は「物の怪」現象が単に「物語」の世界だけではなく、宮廷の日常生活の節々に浸透しているさまをつぶさに観察していました。『源氏物語』にも『紫式部日記』にも、「物の怪」を恐れ、調伏のためにありったけの精力と財力を使う平安貴族の心と行動が生々しく描かれています。とすれば、“平安京”とは実は、“平安の都”ではなく、修験者や陰陽師や神官・仏師によって十重二十重に霊的に防衛された“不安の都”でした。その都にはもろもろの怨霊や御霊や生霊や死霊が恨みを持ってさ迷い、人々に取り憑き不安にさせました。祟りも怨霊も呪い・呪殺も横行していた不安の都が平安京の真の姿でした。
霊的防衛都市としての平安京において、院を護る北面の武士の中から平氏や源氏が台頭し、やがて時代は武士の世に移り、霊的闘争は即物的な武力闘争に席を譲ります。験力や調伏よりも、刀剣や槍や鉄砲の数量や戦略・戦術など軍事力の物理的差が勝敗を決する「武者の世」(慈円『愚管抄』)となっていったのです。このような怨霊鎮魂の歴史哲学を踏まえ、南北朝の壮絶な戦いを経て編み出された鎮魂の芸能が世阿弥の猿楽・能でした。世阿弥は『風姿花伝』神儀篇の中で、「申楽、神代のはじまりと云ば天照大神、天の岩戸にこもり給ひし時、(中略)其時の御あそび、申楽の初と云々」と記し、猿楽の起源を神楽にあると述べていますが、だとすれば、猿楽の源は、「猿女氏」を経てアメノウズメノミコトの行なった「神楽・鎮魂・神懸り・俳優」にまでさかのぼります。
アメノウズメノミコトは手に笹葉を持ち、神懸りになって胸乳と女陰を露わにし、神々の笑いを引き出し、最高至貴の女神とされる日の神であり皇祖神である天照大神を岩屋から呼び戻すことに成功したと『古事記』や『日本書紀』や『古語拾遺』に描かれています。興味深いのは、身体中に植物のつたや葉っぱを巻きつけて飾り、舞台を踏みとどろかして踊りを踊り、太陽神の復活を実現したこのワザを『古事記』では「神懸り」、『日本書紀』では「顕神明之憑談」とも「俳優」とも記している点だといいます。この「顕神明之憑談」は「かみがかり」と訓ませ、「俳優」は「わざをぎ」と訓ませていますから、それが神懸りであり、神を呼び出し招きよせる(をぐ)ワザ(業・技・術・伎)であったことがわかるというのです。そして同時にこの神懸りとワザヲギが「神楽」の起源でした。
「10.上田秋成の『霊異』譚と平田篤胤の『霊性』観想」では、江戸時代になると、仏教や儒教によって影響を受ける前の日本人の心と文化を古言を通して研究しようとする思想運動が国学(古学)として展開されたことが紹介されます。その国学者の中でも「霊異」や「霊性」にもっとも強い関心を寄せたのが大阪出身の上田秋成と秋田出身の平田篤胤でした。篤胤は、人間は「天地初発」の時からみな「産霊神」によって善い「霊性」を与えられていて、死んでもその「霊性」は不滅あり、「幽冥大神」の審判を受けて「天国」に「復命」すると主張ました。また、天狗界に出入りするという仙童寅吉と呼ばれる江戸市中で評判の15歳の少年と出会い、筑波山の天狗界に戻る寅吉に自分の主著である『霊の真柱』と『神代文字の考』を持たせて批評を乞いました。そして寅吉から聞き書き調査した天狗界の情報を『仙境異聞』にまとめるのでした。
寅吉は神も仙人も天狗も存在しない、不思議な現象は存在しないという合理主義を「我意」あるいは「生学問の高慢」と批判しました。そして、神も仙人も天狗も怪異現象もあると断言しました。著者は、「おそらくそれは年来の篤胤の主張であり、そのことを篤胤は寅吉を証人として実証しようとしたのである。篤胤は、上田秋成と同様に、『鬼神』を否定する儒学などの『生学問の高慢』を激しく批判し、もののけの存在を知る実証的な神学としての幽冥学を切り拓いたのである」と述べます。この平田篤胤のもののけ・妖怪・幽冥界研究は、民俗学の成立に深い影響を与えました。柳田國男の『遠野物語』は「神隠し」や「ザシキワラシといふ神」など幽冥境伝承を満載し、折口信夫の『古代研究』は来訪する「まれびと」神や常世など幽冥伝承を古典と民俗事象から炙り出しました。
折口信夫は「神々と民俗」の中で「もののけ」を「庶物崇拝の対象」となる「小さな神」とか気の知れない「恐ろしい霊物」と言い、「ものゝけ其他」では「『ものゝけ』と言ふ語は、霊の疾の意味であつた。ものは霊であり、神に似て階級低い、庶物の精霊を指した語である。さうした低級な精霊が、人の身に這入つた為におこるわづらひが、霊之疾である。後には霊疾の元をなす霊魂其物を、ぢかにものゝけとばかり言ふ様になり、それを人間の霊と考へた」と指摘し、「平田国学の伝統」と題した講演において「篤胤先生が、仙童寅吉、生れ替り勝五郎を担ぎ上げてゐたのと同じものを、われわれがしてゐるのだといふ気がして、やつと或る喜びに達した」と自分たちの民俗学研究の先達としての篤胤を顕彰しています。著者は、「『霊異』の探求と表現という観点からすれば、日本民俗学の確立とは新しい『日本霊異記』の編纂と解析でもあったといえるだろう」と述べるのでした。
「11.近代の霊性研究」では、大本教の出口王仁三郎が取り上げられます。彼は「芸術は宗教の母」であると主張し、芸術生活運動を展開しました。この『芸術』とは、「私はかつて、芸術は宗教の母なりと謂ったことがある。しかしその芸術というのは、今日の社会に行わるるごときものをいったのではない。造化の偉大なる力によって造られたる、天地間の森羅万象を含む神の大芸術をいうのである。(中略)明光社(注―現「楽天社」)を設けて、歌道を奨励し、大衆芸術たる冠句を高調し、絵を描き文字を書き、楽焼をなし、時に高座に上って浄瑠璃を語り、ぼんおどり音頭をさえ自らとっておるのである。神の真の芸術を斯の上に樹立することが、私の大いなる仕事の一つである」と『月鏡』にあるように、第一義的には大自然の宇宙的創造力を指しています。
こうして王仁三郎が「神の大芸術」を讃美しつつ、「明光社」という芸術結社を結成して展開した芸術運動は短歌、冠句、絵画、書、陶芸、浄瑠璃、盆踊り音頭、演劇、映画など多様な大衆総合芸術芸能運動で、笑いと活力に満ち溢れたものでした。出口王仁三郎にとっては、最高最大の芸術家は「神」でした。なぜなら、この宇宙全体が「天地間の森羅万象を含む神の大芸術」であると捉えられるからです。この「自然の造化力」とは、古代日本人が直覚した「むすひ(産霊)」であり、岡本太郎の言う「神聖なエネルギー」そのものであると指摘する著者は、「そのことは、『真の芸術なるものは生命あり、活力あり、永遠無窮の悦楽あるものでなくてはならぬ』という言葉を引けば明らかであろう」と述べています。
卜部兼友や吉田兼倶や平田篤胤らと同じく、出口王仁三郎も「霊性」という言葉を用いて宗教・宗派を超える普遍的精神性の次元を表そうとしました。昭和8年(1933年)には、アメリカのジャーナリストであるJ・W・メーソンが『神ながらの道』を著し、神社には「自然の霊性」があり、そこは「普遍的霊性」に挨拶をする「霊的元気回復の場所」であると述べました。このように神道思想の中で「霊性」という語が使用されてきた一方で、鈴木大拙は昭和19年(1944年)に『日本的霊性』を出版し、敗戦後さらに強力に「日本的霊性」や「日本の霊性化」を主張しました。
大拙は「霊性」を二元対立を超える深層的な「無分別智」的「宗教意識」であると規定しつつ、「国家神道」を徹底批判し、中でも平田篤胤を軍国主義の元凶として激しく弾劾しました。このような鈴木大拙の霊性論は、かつて著者が『神道のスピリチュアリティ』(作品社、2003年)で指摘したように、神道的霊性論に対する研究不足と誤解と偏見に満ちています。しかし、著者は「この日本的霊性論が戦後の精神世界において国際的な影響力を持ったために、神道や日本の民俗宗教や神道系新宗教についての公正で総合的な見方が生まれることを阻害する結果となったといえる」と述べています。
「12.現代の霊性探求」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。
「現代の『霊性』問題を概観してみると、1960年代後半からの対抗文化運動の流れの中で、“spirituality”の語が、『霊性』と訳されつつも、その語のままでそれまでの霊性論を包括するものとして定着し、現代の『スピ系ブーム』にまでつながっている。島薗進は『精神世界のゆくえ――現代世界と新霊性運動』(東京堂出版、1996年)の中で、『新霊性運動』という概念を提示してその動向を宗教史・宗教学的に考察した。島薗はアメリカの『ニューエイジ運動』の『信念や観念のリスト』を19項目挙げ、その第1番目の信念として『自己変容あるいは霊性的覚醒の体験による自己実現』を指摘し、『新霊性運動』を『個々人の「自己変容」や「霊性の覚醒」を目指すとともに、それが伝統的な文明やそれを支える宗教、あるいは近代科学と西洋文明を超える、新しい人類の意識段階を形成し、霊性を尊ぶ新しい人類の文明に貢献すると考える運動群である』と定義している。
「13.今、ここでの死生観探求」では、アメリカの精神科医であるエリザベス・キューブラ―=ロスが『死ぬ瞬間――死にゆく人々との対話』において提示した①否認②怒り③取引④抑うつ⑤受容の「死の過程で現れる5つの心理的段階」を紹介し、著者は「がんなどで死を告知されたり、死を目前にした患者は動揺する。衝撃を受け、そんなはずはないと否定する。だが、その事実が打ち消し難いものと知ると、どうしてこの今、この自分が死ぬ羽目にならねばならないのかと怒りが湧いてきて、それを周りにぶつける。そして、何とかならないか、何とかした助かる方法はないかと延命への道を探し、いろいろと取引を試みようとする。何でもするから命だけは助けてほしいとかとすがる思いで神に祈ったりする」と述べています。
しかしそれも無駄なことだと分かると、いかんともし難いことの事態に無力を覚え、失望感を抱き、抑鬱状態に陥り、絶望と悲嘆に暮れます。そして最後に、死を受け容れるほかないと諦めるのです。著者は、「その死の受容の過程で、いろいろなレベルでの和解が生まれるかどうかが、死に至る最終段階の課題である。自分自身との和解、他者との和解(肉親・友人・知人・先祖・子孫など)、自然・生命・宇宙との和解。一言で言えば、『ごめんなさい。ありがとう。愛している。』ということを心の底から言えるかどうかである。もしその言葉が素直に言えるとしたら、死の受容は穏やかでピースフルなものになるだろう」と述べるのでした。
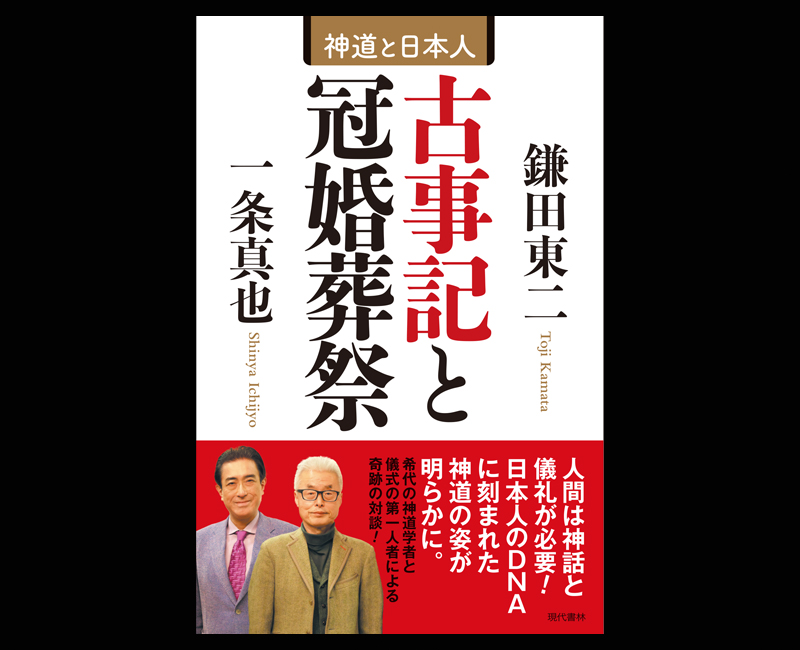 『古事記と冠婚葬祭』(現代書林)
『古事記と冠婚葬祭』(現代書林)
「『嘘をつけない自分』との直面」では、宗教の根本三要素は神話と儀礼と聖地だということが紹介されます。人は何によって生きるかという問いを宗教という観点から考える時、人にとって神話や儀礼や聖地がどのような意味とはたらきを持っているかを考えることはさまざまな示唆をもたらすことになるだろうとして、著者は「神話は、私たちの住むこの世界はどのようにして出来上がってきたのか、われわれはどこから来てどこへ行くのか、人間はどのような意味と価値を持っているのかなど、自分たちを支える根源の物語である。神話は人間のアイデンティティの一等根幹を支えている物語で、世界と人間についての物語的説明と言語表現である。その中に当然のことながら、死や死後世界(霊界・他界・異界)のことも含まれている。私たちは生きていく上で、何がしか、そのような根源的な物語を必要としている。それは生の必需品であると言える」と述べています。
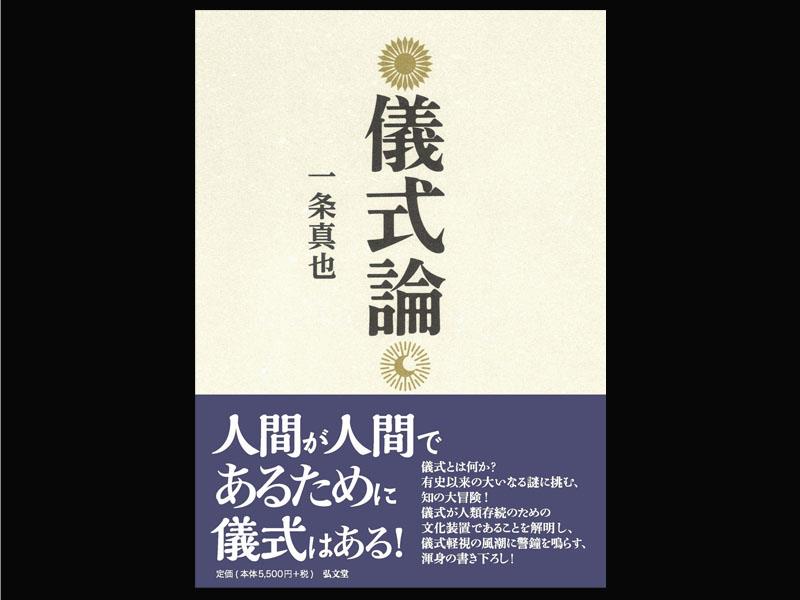 『儀式論』(弘文堂)
『儀式論』(弘文堂)
儀礼は神話に基づき、連携し補完し合いながら、神や霊などの超越的な存在世界との接触を果たし、この世界で生きていく活力や癒しを得る身心変容技法であり行為表現です。著者は、「私たちは生きていく上で、何らかの儀礼を必要とする。というよりも、人間的な生存の形がそもそも儀礼的な性格を持っている。歌うことも踊ることも祈ることもみな儀礼の形である。そして、神聖な物語である神話が語られたり、儀礼が執行されたりする聖なる場所が聖地である。そこは、神仏や精霊など、聖なるものが示現し立ち現れた場所であり、超越世界への孔・通路・回路・出入り口である。聖次元へのチャンネルとなる場所が聖地である。私たちは生きていく上で、何がしか特別な場所や空間を必要とする。例えば、自分の家や部屋や住処のような、自分の体と心が安全で平安でいられる場所が必要となる。そうした場所や空間なしに私たちは生きていくことができない。とすれば、神話(物語)と儀礼(芸術・芸能を含む)と聖地(家や部屋を含む)は、それぞれみな生活必需品である」と述べます。
宗教は「聖なるものとの関係に基づくトランス(超越)技術の知と実践の体系」といえます。トランスとは境界を踏み越えていくことを意味しますが、そのトランス(超越)の最も普遍的な(誰しも経験する)事態が死です。しかし、それを経験し終える時には、肉体を伴う自己を失っているので、厳密な意味で、生きたまま死を経験することはできませんし、死のリアルを語ることもできません。それに近い事態が臨死体験(neardeath experience)や体外離脱体験(out-of-bodyexperience)ですが、それも死そのものではありません。著者は、「そのような死の体験の普遍性と不可能性ゆえに、死についてはさまざまな観念や思想が語られてきた。宗教は死について各宗各派の独自の思想と儀礼を生み出した。だが、そのような伝統はあったとしても、死は個別的で一人ひとり代替の効かないものである。故に、人は皆死者になるし、同時に、死者に向き合う存在、弔い人ともなる」と述べます。
死を前にした時、人は否応なく嘘をつけない自分自身に直面します。例えば、死の不安が湧き上がってくるとして、それを避けることはできません。自分の心の中に起こることを否応なく見つめるほかなくなります。マインドフルネスを意識しなくても、マインドフルネス的な状況が生まれるのです。だがそこで、マインドフルネス瞑想などの身心変容技法をわきまえていたとしたら、動揺する自分の心をいくらか冷静に見つめ、チェックすることができるでしょう。それによって、次の心の状態に移行することも可能だといいます。この時人は、「嘘をつかない体=死に向かって衰弱していく身体」と「嘘をつけない魂(霊性・スピリチュアリティ)=見てみぬふりをできない自分」の間で揺れ動く「嘘をつきたがり、見えを張りたがる自分の心と行動」に気づくというのです。
これを別の角度から言うと、「死」は「史」を深め「詩」を物語る契機となる、ということになります。人は死を目前とした時、必ず自分の生涯を振り返り、なぜこの時を迎えるに至ったかを問いかけます。著者は、「私は何処から来て何処へ行くのか、と。ごまかしのきかない、その越し方・行く末を見通す作業とともに、それを確認し、反省し受容するためにも、それを物語る行為を必要とする。それが『死』が『史』となり『詩』を生み出すという事態である。最終的に、受容とは物語を作ることである、物語によって区切りをつけることである。そして、物語ることが手放すこととも解放ともなる。この物語は嘘をも含むが、同時にその嘘を見通している自分(魂・霊性・スピリチュアリティ)もはたらいているので、自分で自分をごまかすことはできない。より素直にならざるを得ない。そのことがまた次世代への継承やリレーともなっていく。そのような物語的連環を持ち得た時、人は人生の円環を閉じることができ、何によって生きるかの意味を確認し、納得することができるのではないだろうか」と述べます。
死がどのような形態であり過程であろうとも、葬儀の形が火葬であろうが土葬であろうが水葬であろうが風葬であろうが、それぞれ「各別各異」の道を通り、「宇宙の微塵」となって「無方の空」に散らばっていく過程を辿る、「時間の軸」の「移動」であることに間違いはありません。その「移動」の際に、「詞は詩であり動作は舞踊音は天楽四方はかがやく風景画」のような詩や舞踊や音楽や絵画とともに「行く」ことができるかが、この世における「各別各異」の人生修業になるといいます。その「各別各異」の生き方にごまかしはきかないとして、著者は「人は何によって生きるか。歌(詩)によって生きる。舞踊(踊り)によって生きる。音楽と共に生きる。輝く風景の中で生きる。目を覚ましてみれば、あらゆる事象がメッセージであり、歌となる」と述べます。『古今和歌集』で、紀貫之が述べた「生きとしいけるもの、いづれか歌をよまざりける」でうが、それは「嘘をつけない魂」に近づいていく道程だと言えるのです。
東日本大震災では、否応なく、このような行方不明者と身元不明者の葬儀と埋葬に関わらなければなりませんでした。わからなくても葬儀を行なう必要があったのです。そのようなやむにやまれぬ事情の中で、合同葬儀が執り行なわれることになりました。その時、神道、仏教、キリスト教、新宗教など、さまざまな宗教・宗派の宗教者が集まって合同礼拝の形で葬儀が執り行なわれました。身元不明者の場合、どのような宗教・宗派に属しているのかわかりません。わからないけれども、これ以上埋葬を先延ばしにするわけにはいかない。とすれば、さまざまな宗教・宗派の合同葬儀で死者に対し、遺体に対して哀悼の意を表しつつとりあえずの葬儀を執り行なうしかありません。どこの誰かがわからなくても、死者と死体に祈りを捧げ、儀礼的に弔わなければならないのです。著者は、「このような事態が東日本大震災の時に起こってきた。そのことは諸宗教・諸宗派の宗教者の連携を促すことになった。自分たちの一宗一派の立場などにこだわってはいられなくなった。合同で葬儀をし、共に敬虔に祈り、鄭重に弔う儀式を行なうことが死者への供養や鎮魂だとするしかなかった。そうした経緯や事情と経験を通して『臨床宗教師』という新しい公共的な宗教家が生まれてきた」と述べます。
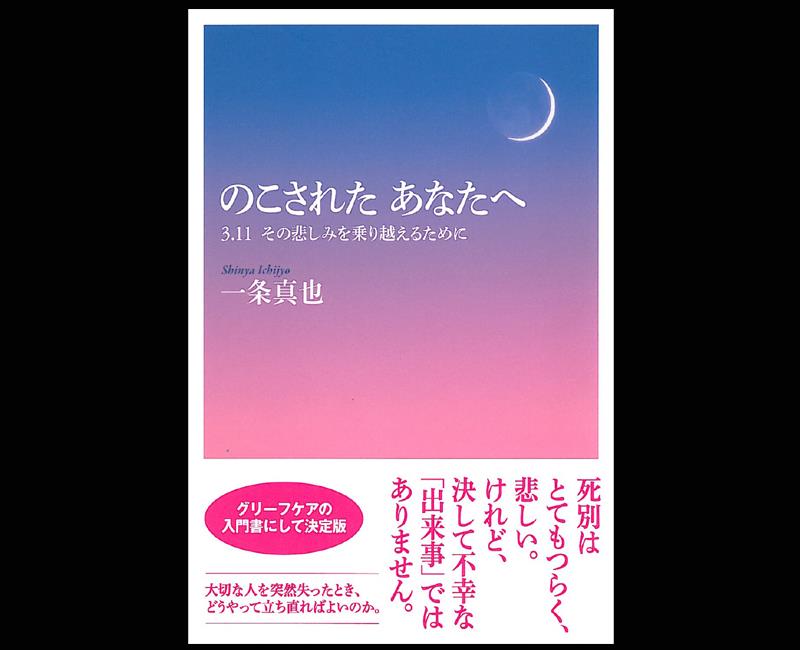 『のこされた あなたへ』(佼成出版社)
『のこされた あなたへ』(佼成出版社)
東日本大震災では、津波によるこれまでにない多数の行方不明者や身元不明者が出ました。気の遠くなるような捜索と確認の作業とその過程での悲嘆や絶望、そして葬儀の問題。死者をどのように見送り、埋葬し、鎮魂・供養すればよいのか?人間の生存にかかわる本質的な問題に直面せざるを得ませんでした。被災地の大半を占める東北地方には古くからのシャーマニズム的な民間信仰が色濃く残っていました。恐山のイタコのように、死者の霊と交信・交流する習俗も特異な事例ではありません。著者は、「この習俗化し身体化した民間信仰の基盤は知的な認識や意識的な行動を超えて、あるいは包み込んで作用する、まさにスピリチュアルなリアリティを持っている。そこで、幽霊体験なども多く報告され、死者との民間伝承的な交信現象も多数浮上してきている」と述べます。
「『むすひ』と『ナチュラルケア』」では、日本における「スピリチュアルケア(spiritual care)」のありようが、「ナルラルケア(natural care)(healing through nature、natural approach to care)」とでもいうべき自然の力動の感受と深く結びついているという点を著者は指摘します。直截に言えば、「人が癒す」つまり「人間関係の関わりの中で支えられ癒される」局面だけではなく、「自然が癒す」すなわち「自然と人間との関わりこそが癒しと支えの根幹となる」という事態があるということです。『古事記』における「むすひ」の神々の自然生成力への畏怖・畏敬の心ばえが、「草木国土悉皆成仏」という命題に集約される天台本覚思想などを生み出していくという、本源的に脱人間主義的かつ汎自然的な感覚と思想の問題となります。
自然「災害」が多発するということは、言い換えると、自然の奥深い底知れぬ「むすひ」の威力に対する畏怖・畏敬の念が強化され堆積されていくということでもあります。その畏怖・畏敬の念と不可分の「むすひ」感覚が「ナチュアルケア」として、日本型「スピリチュアルケア」を包含していると仮定します。ということは、「自然」や「むすひ」への認識なしに日本での「スピリチュアルケア」を実践することには根本的な欠落があるということになります。著者は、「日本のスピリチュアルケアは日本人の死生観を踏まえておく必要があるだろう」と述べるのでした。
「14.おわりに」の冒頭を、著者は「宗教史的に見ると、キリスト教の霊性論は『聖霊』や『愛』の思想と関係し、仏教の霊性論は『仏性』や『如来蔵』や『即身成仏』や『菩薩道』や『慈悲』と関係し、神道の霊性論は『神』や『たま』や『鎮魂』や『清浄』や『正直』と切り離せない。そして、精神世界やニューエイジの霊性論は瞑想や自己実現(自分探し)や神秘主義や近代批判と不可分である。またWHOの霊性論は第三世界から出てきた人間の幸福や価値や生きる意味(生活の質、QOL)の探究と結びついている」と書きだしています。こうした宗教思想史的な文脈を踏まえて、著者は、霊性―スピリチュアリティ論の意味の地平を整理し、以下の3つの志向性(外延)を示します。
(1)普遍志向性
(超宗教性・通宗教性)
(2)平等志向性
(3)開放志向性
(解放性、閉鎖性の突破)
また、霊性―スピリチュアリティ論が内包する要素として次の三要素を挙げています。
(1)全体性=丸ごと
(2)根源性=根っこ
(3)深化=深まり
霊性ないしスピリチュアリティという言葉は、精神性のより深い根源的・全体的次元への洞察と関心を示す言葉です。その語は、全体性と根源性と深化という3つの要素を含み持っています。それは、全体的で、根源的でありつつ、人間の深化と成熟と変容を指し示し得る言葉なのです。仏教学者の故玉城康四郎の言葉を借りれば、それは人類の「業熟体」実現を志向する言葉であるといえます。
こうして、霊性―スピリチュアリティという語は普遍志向性を持ち、すべての宗教に通じる超宗教性ないし通宗教性とすべての人間に通じるような平等志向性を持ち、人権思想をさらに深く支える基盤ともなり得ます。それ以上に人権を超えて、アニミズムやトーテミズムとも結びつく、あらゆる生命の生命性を包含する概念としても用いられ得ます。著者は、「かくして霊性―スピリチュアリティは、神性や仏性や心性や精神性とも異なる、より開放的で閉鎖性や偏りのない包括的概念として使用され得る可能性を持っている。私自身はそうした霊性―スピリチュアリティ論の中で、もののあはれやもののけやものがたりやものぐるいを含む『モノ学・感覚価値』研究を21世紀の『霊』あるいは『霊性』の探究として進化発展させたいと考えている」と述べるのでした。
第二章「うたといのりと聖地の死生観」の「1.はじめに」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。
「国学者たちが『古学=国学』に目覚めていったのは、まず何よりも『万葉集』の研究を通してであったことを確認しておきたい。『万葉集』研究は日本人の自己認識の学としての国学の起爆剤となった。契沖、荷田春満、賀茂真淵、彼らはみな万葉研究を志した。考えてみると、『万葉集』という歌集(=詩集)は世界にも類例を見ない書である。短詩型文学書とはいえ、これほど多種多様なアンソロジーが成立したということ自体、驚きである。当代の著名な宮廷歌人から、防人から、詠み人知らずまで、分け隔てなく歌の前での平等を享受している。雄略天皇の歌で始まり、大伴家持の歌で閉じる4500余首の集成は、日本人の心性と歌心を余すところなく伝えているといっていい。それは『源氏物語』研究を通して『もののあはれ』を抽出した本居宣長に倣って言えば、『もののあはれ』の宝庫であり、万葉研究こそ、万葉人の『もののあはれを知る』ための不可欠の作業であった」
そもそも、『源氏物語』も『伊勢物語』もその核心部分はすべて歌で表現されています。『古事記』、然りです。であれば、歌こそが日本文化のアイデンティティの根幹をなすものであり、国学がその歌の研究から出発したことの意味を繰り返し確認しておく必要があるでしょう。のちに、『古代研究』「追ひ書き」において、「新しい国学を興す事である。合理化・近世化せられた古代信仰の、元の姿を見る事である」として、民俗学と国文学との融合による「新しい国学を興す事」を宣言した折口信夫も、『万葉集』の研究から彼の「古代研究」を出発させています。折口が何度も稿を改めた「国文学の発生」とはまさに歌の発生の現場をつかまえる作業であったといえます。
「2、聖地の生物学的・惑星的基板」では、「聖地」とは、神仏や精霊あるいは超自然的存在などの聖なる諸存在が示現したり、または記念したりしたある特異な場所を総称して言うことが紹介されます。それは空間の特異点のような場所で、あの世とこの世とが交通し、往来する場所とされます。「3.聖地の特性」では、著者が、そうした聖地の特徴を以下にまとめています。
(1)魂を飛ばす場所(異界・他界への境界)
(2)魂をつなぐ場所(神・精霊/人/自然)
(3)魂を浄化する場所(祈り・修行)
(4)魂を強化し生命力を活性化する場所
(神遊び、神事芸能)
(5)タマフリ・タマシヅメ・行の場所(鎮魂・瞑想)
(6)宇宙的調和と神話的時間を感じとる処
(7)異次元回路としての次元孔
こうした聖なる場所において人間は特異なイマジネーションを発動してきたといいます。ゲーテはそうしたイマジネーションを、「花崗岩について」と題するエッセイにおいて、花崗岩を「時間の記念碑」と読み解き、そこから大地の生成をパノラマのように幻視する力であるとしています。つまり、花崗岩を地球の運動の軌跡を覗き込む時空孔と見ているのです。ライアル・ワトソンの言葉を使えば、「この惑星上でもとりわけ調和がとれている場所」が聖なる場所であるということになります。著者は、「私は、場所はエネルギーと情報を保持していると考えている。そして、聖なる場所はそのエネルギーと情報において、特異で強烈なメッセージを孕んでいる。その『聖地』において、詩人やシャーマンたちの意識の変容が起こり、気・波動・トランス・癒しなどが生起するのである」と述べます。
「4、『うた』はどこで歌われたのか?」では、「聖地」と歌との関係が問題になります。歌はどこで歌われたのかという問題です。著者は、古くは、歌は「聖地」において、特別の聖なる時に歌われたと考えています。民俗学的に言えば、ハレの日です。もちろん、恋の歌など、日常生活の中で恋する人々の間で歌われ、交換されたであろうことは容易に推測されますが、しかしそれとても特別の聖なる時(性なる時)があったと思われるといいます。「5.どこで、『祈り』が捧げられたか?」では、祈りが捧げられる祭りの場所を古語で「斎庭」と呼んだことが紹介されます。その「斎庭」はまた「さには」(沙庭・審神者)とも呼び、本来、それは聖なる祭儀の庭であり、神懸りの場でしたが、それが次第にそこでの神懸りの言葉を判定する審神者の意味に転じていきました。このことが『古事記』や『日本書紀』や『古語拾遺』などで、天の岩戸の前での神祭り(神事)として記されています。
興味深いのは、アメノウズメが「神懸り」になることが、別の言い方で、「わざおぎ」、すなわち魂を招き寄せる「俳優」の振る舞いをすると記されている点です。この時のアメノウズメの状態は、『古事記』には「神懸」、『日本書紀』では「顕神明之憑談」「俳優」と記されています。「わざおぎ」とは、神を呼び出す(おぎ)業=技=術=伎(わざ)で、やがてそれは滑稽な振る舞いをも伴い、芸能化していきます。これが、「神楽」の始まりであり、神事・芸能の起源神話です。このように、アメノウズメの「ワザオギ(俳優)」が「神懸り」であり、「神楽」でもあり、「鎮魂」でもあり、「神の怒り」を鎮める行為でもあり、それが日本の祭祀の原型を表現しているという点は注目すべきであるとして、著者は「『古語拾遺』には、『凡て、鎮魂の儀は、天鈿女命の遺あと跡なり』と記されていて、鎮魂のワザがアメノウズメのワザオギの重要部分をなしたことがわかる。それがやがて神楽となり、芸能的要素を交えて神々の御霊を慰め、怒りや祟りを鎮める所作ともなったのである」と述べます。
もう1つ、著者が注目するのは、この女神が神懸りになった時、その場にいた神々が喜び、楽しみ、「天晴れ。あな面白。あな手伸し。あなさやけ。おけ」と口々に囃し立てたと『古語拾遺』に記されている点です。これは歌舞音曲や歌の始まりとも関わりのある伝承ですが、著者は「ここで神々によって、ある言葉が発せられたことを重要視したい。上記の言葉は、歌謡の原型をなすものと考えられるからである。いずれにせよ、アメノウズメの『俳優=神懸り=鎮魂』の所作によって、天が晴れ、神々の顔に光が射して面が白くなり、神々が手を振りかざして『手伸し=楽し』のわざを踊りで表し、歌い、それに草木も一緒になって靡いたのである」と述べるのでした。
第三章「いのちをめぐる東西の自然理解と死生観――環境・生命・倫理~神道の立場から」の「1.『いのち』と『命主社』――出雲神話から探る」では、「いのち」の感覚と思想は、『古事記』の中では「神産巣日神」の「産巣日」、すなわち「むすひ」として表されていることが指摘されます。それが、『延喜式神名帳』では、「神魂伊能知奴志神社」の「魂=むすひ」として表記されました。それは天然自然万物の根源的な生成力・生命力を表す言葉です。それに対して、仏教的存在観・現象観は「(諸行)無常」として捉えられますが、共に生成変化する存在の裏表をなす感覚です。生成変化の創造性の方にアクセントを置いた語が「むすひ」で、その破壊・崩壊・消滅の方にアクセントを置いた語が「無常」であると捉えることができます。とすれば、「むすひ(産巣日・産霊)」と「むじょう(無常)」はそれほど隔たっているわけではないとも考えられます。そのような「むすひ」と「むじょう」の両方を包み込む語が「いのち」なのです。
「いのち」は生と死の両極を含み持つ言葉です。例えば、『万葉集』に見られる「いのち」に掛かる枕詞は「たまきはる」ですが、それは、「魂・来・経る(膨る・張る)」、すなわち「魂が来訪して膨らみ経ていくもの」の意味で、魂の来訪と通過を核として成立しています。とすれば、「いのち」の中には「たま(たましい)」をも含んでいるということになるといいます。「2.『いのち』と『むすひ』――『古事記』における『成れる神』と『生まれる神』」では、いのちの出現は、生成と出産の二つの過程として表現されていることが指摘されます。和語で言えば、「なる(成る)」と「うむ(生む・産む)・うまれる(生まれる・産まれる)」です。造化三神の中で、なぜ「むすひ」の名を持つ二柱の神々が現れ出てくるのかといえば、男女や夫婦や陰陽のように、対極にあるものを結びつけることによって生成していく対構造を示す必要があったからではないかと、著者は推測します。
「3.神道とは何か」では、プレートと海流と文化・文明の十字路の上にあるのが日本列島であると指摘します。これは生命多様性と文化多様性が「神仏多様性」を生み出すことになる条件であり、土壌でした。この習合的宗教文化は、単なるごった煮や雑居ではありません。独自の神仏関係理論(本地垂迹説や反本地垂迹説など)や様式を持ち、実験的洗練を重ね、美と聖と霊性が具体的な形態表現を通して練り上げられ、それがたとえば寺社建築や祭りや庭園や能楽や茶道や華道などにも発現しています。そこで著者は、『霊性と東西文明――日本とフランス「ルーツとルーツ」対話』(竹本忠雄監修、勉誠出版、2016年)の中の論考を「神道とは何か?――ユーラシア・環太平洋交響楽としての神道」と題して、神道を「ユーラシア・環太平洋交響楽」として観る視点を提示しました。
「5.いのちの言葉としての『言霊』という事例」では、太陽神天照大御神の洞窟籠りによって世界は光を失い、真っ暗闇になって神々の悪しき喧騒の声が満ち溢れ、再びありとあらゆる禍が起こったエピソードが取り上げられます。この禍を取り除き、光を取り戻すために行なわれたのが、「祭り」でした。そこで、「祭り」は神々の世界再生計画の実施であり、生存戦略でした。著者は、「太陽神が天の岩屋戸という洞窟に隠れてしまったために、世界にあらゆる災いが次々に起こってくる。この時、世界は、何も見えず、何もわからず、何もできず、何も生まれることのない、非生産的な世界に墜ちる。それは、生命力の根源である「むすひ」の力と働きが死に絶えた生命力の枯渇した死の世界である。そこには未来も希望もない。いのちの輝きもない。高天原といういのちの根源をなす世界が崩壊する。この絶体絶命の危機と崩壊を食い止めるにはどのような方策があるか。神々はこの暗黒の世界の中でどうするか『神集い』して相談論議した。そして、思金神という名の智略の神が神々の議論を取り仕切り、結論を出した。祭りをしよう、と」と述べています。
第四章「モノと霊性――ものづくりからもののあはれまで」の「2.ものづくりと手わざ」では、「仏作って魂入れず」という言葉が取り上げられます。この言い方は、仏の中に神=魂=心が入り込むことによって真の霊力が発揮されるという信仰と技術のありようを物語るものです。そうした日本の仏像群の中でも、柳宗悦は特に木喰仏の中に深い健康な美を見出しました。それは、全国津々浦々の名ものない無名の陶工たちが生み出すものづくりの健康な深い美の世界に通じていました。柳宗悦はこうした「民衆的工芸」を、「民藝」と名づけ、その美的価値を高く評価し、雑誌『工藝』を創刊して、民衆の生活世界に伝承されてきた手わざの数々を取り上げ、そこに埋もれている力強い健康な「用の美」を評価していったのです。
昭和11年(1936)、柳は「日本民藝館」を創設し、「民藝」運動を全国展開します。柳によれば、手仕事の中に「民族的な特色」が色濃く現われ、そこに「自由と責任」が保たれる。そうした手仕事には「悦び」が伴い、「新しいものを創る力」が現れてくる。日本とは、そのような創造力のみなぎる「手の国」である。そしてその手仕事は同時に「心の仕事」だと道破し、質の高い美しい特色のあるものを創り出すことが日本人の「誇り」となると主張しました。それが、「民藝」なのだというのです。柳は、「その土地で生れた郷土の品物」、「日本のものとして誇ってよい品物、即ち正しくて美しいもの」を訪ね歩き、収集し、整理して、『手仕事の日本』で紹介しました。
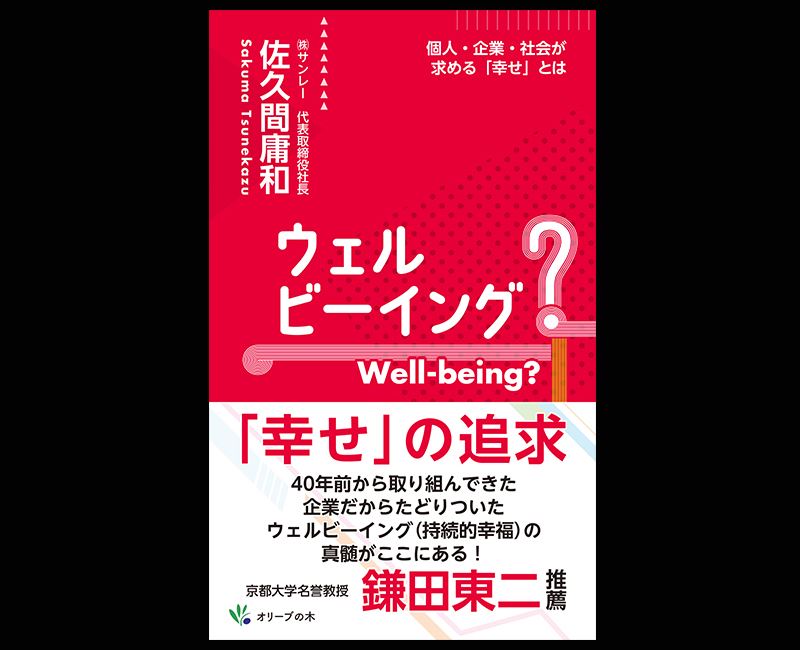 『ウェルビーイング?』(オリーブの木)
『ウェルビーイング?』(オリーブの木)
『手仕事の日本』には日本のものづくりの核心が実に明晰かつ具体的に示されています。陸奥津軽のこぎん、信濃福島の曲物、飛騨白河の鉈鞘、阿波の藍などなどの「日本の品物」への愛と賞讃。「民藝」の美を「健康の美・用の美・無心の美・伝統の美」と規定した柳は、「私たちは健康な文化を築かねばなりません。日本を健康な国にせねばなりません。それには国民の生活を健全にさせるような器物を生み育て、かかるものを日々用いるようにせねばなりません」と言います。著者は、「この柳の言う『健康』とは何であろうか。それをスピリチュアリティ(霊性)とも言い換えることができるだろう。もの(物)の中にモノ(霊)が生き生きと宿りはたらくさま、それが真の『健康』なのだと」と述べます。わたしは、「真の『健康』」という言葉から「ウェルビーイング」を連想しました。ちなみに拙著『ウェルビーイング?』(オリーブの木)には、著者が寄稿して下さいました。
「4.『もの』の本義とグラデーションと霊性」では、日本の伝統的「ものづくり」は「物忌み」と無関係ではないどころか、そのような「もの」への対し方の中から創造性を高め、深める不断の努力をしてきたことが指摘されます。鍛冶場にせよ機織り場にせよ、そこには火の神や蚕の神などの神霊が祀られ、人々の仕事が安全に、つつがなく進むよう見守る。剣道場や柔道場などの伝統武術・武道の道場にも鹿島の神などの武芸の神が祀られることが多いですが、それも同様です。そこでは「ものづくり」は、神の力を得て細部にまで神経の行き届いた「もの尽くし」に通じる回路を持っています。武芸や芸能の修行者もまた神霊の加護を得て初めて「物の上手」となります。者を媒介者として、霊(モノ)から物へ、また物から霊への往還運動が起こっているのです。
そもそも、日本の最初の「ものづくり」とはどこから始まっているのかといえば、それは天の岩戸の前で行った神事のための祭具を作ることから始まっているといいます。神代の昔、スサノヲノミコトの乱暴に耐えかね、天の岩戸に籠った天照大神を再び呼び出すために祭りが執り行われることになりました。忌部氏の先祖の天太玉命が神籬を立て、中臣氏の先祖の天児屋命が祝詞を奏上し、猿女氏の先祖の天宇受売命が踊りを踊って神懸りとなり、乳房と女陰(ほと)を露にした様子に高天原の神々が笑いさざめいたので、不審に思った天照大神が岩屋の外を覗き見て、再びこの世界に光が戻ったというストーリーが『古事記』や『日本書紀』や『古語拾遺』に記されています。
この祭りの場において、神霊を映し出し、またその依り代とする鏡や玉を作ったのが鏡造りの先祖の伊斯許理度売命と玉造りの先祖の玉祖命でした。これが日本の「ものづくり」の起源を物語る神話です。とすれば、「ものづくり」とは本来神聖エネルギーを呼び出すための神聖サービス(奉仕)だったのです。鏡にせよ、玉にせよ、他のどんな道具にせよ、その「物」に「物理」を超えた「霊理」をエンパワーメントする。それが「物」にたましいを入れるという行為でした。それは逆に言えば、すべての「物」が霊としての「モノ」を前提として成り立っているということです。あらゆる「物」の中に魂がある、そんな存在感覚から日本の「ものづくり」は始まっているのです。
終章「言霊と神道――草木言語から人間言語・地域言語への射程」の「2、言霊概要」の冒頭を、著者は「言霊とは何か? それは、『いのちの宿る言葉』である。『いのちを賦活する言葉』である。単なる意味を超えて、その人の霊性的本心に根ざす知情意のまことの籠った言葉である。それを、『こころの言葉』とも、『たましいの言葉』とも言うことができる」と書きだしています。身体と心と魂(霊性)との関係を、著者は「からだはうそをつかない。が、こころはうそをつく。しかし、たましいはうそをつけない」と捉えます。嘘ではないまことの言葉、言霊はそのような「まことの言葉」です。
「6.神道概要」では、「神道の霊性」を示すものとして、著者が神道の「潜在教義(思想)~神道七則」を以下のように提示します。
●「場」の宗教としての神道
●「道」の宗教としての神道
●「美」の宗教としての神道
●「祭」の宗教としての神道
●「技」の宗教としての神道
●「詩」の宗教としての神道
●「生態智」としての神道
最後、第7に、「生態智」(エコソフィア)としての神道。これらを総合すると、いのちのちからと知恵を畏怖・畏敬し伝承する神道の心と霊性(スピリチュアリティ)があります。それは、生命美を感得し、いのちの尊厳とかけがえのなさを感受する宗教文化です。
「生態智」とは、「自然に対する深く慎ましい畏怖・畏敬の念に基づく、暮らしの中での鋭敏な観察と経験によって練り上げられた、自然と人工との持続可能な創造的バランス維持システムの技法(ワザ)と知恵」です。それは、神社として伝承された癒しや浄化の空間としての聖地、祭りとして伝えられ古代からのさまざまな生活文化のワザの中に保持されてきました。聖地とは、「聖なるモノの示現するヌミノーゼ的な体験が引き起こされる場所」であり、そこには「生態智」と呼ぶことのできる知恵と力が宿っているがゆえに長らく祈りや祭りや籠りや参拝や神事やイニシエーションなどの儀礼や修行(瞑想・滝行・山岳跋渉等)が行われてきた。このような「神道七則」を「神道の潜在教義」あるいは「神道の霊性」と著者は考えます。
「祭り」とは、「いのちの出現=みあれ」に対する祝宴である。それは、生命力を賦活し、活性化させる「鎮魂(たまふり)」であり、神々や人々の身心を生命的横溢と共鳴状態に変容させる「技」である。その「技」の中核をなすのが「ワザヲギ」です。「ワザヲギ」とは、アメノウズメノミコトが行なったたましいを呼び出し、付着させたり、活性化させたりするスピリチュアル・アート・パフォーマンスを指す言葉として『日本書紀』に初出します。それはまた、さまざまな妖艶・怪異なシンボリズムと手法も組み込んだエロティシズムの時間と空間の創造でもあります。
この非日常的なエロス的な時空は、生活の中に神話的な時間と空間が開基してくる特異点であり「詩」ですが、そうした「詩」によって世界といのちを物語的にとらえ、祭りの回路を通して再受肉します。神道はそのような意味での「詩の宗教」であり「物語宗教」です。いのちのちからと知恵を畏怖・畏敬し伝承し、暮らしの中に生かす伝え型の宗教が神道なのです。教え型の宗教にして悟りの宗教としての仏教に対して、神道は伝え型の宗教にして畏怖の宗教であると言えるでしょう。
「7.神道と仏教との対比とその融合」では、神道は日本列島におのずと形成されてきた「神」信仰に基づく民族宗教ですが、仏教は悟りを開いて「仏」になる(成仏・成道)世界宗教であることが指摘されます。その神道の世界観の根幹にある思想が「むすひ」(神秘的で神聖な自然生成力)で、仏教の世界観の根幹にある思想が「無常」(あらゆる事象は変化してやむことがない)です。この「むすひ」が生成の起点(生まれてくること)に焦点を当てた概念と言えるのに対して、「無常」は生成の終点や収束(壊れていくこと、終わっていくこと)に焦点を当てた概念と対置できるでしょう。著者は、「とすれば、『むすひ(産霊)』と『むじょう(無常)』はコインの裏表であり、正反対の概念ではない」と述べています。
 わが‟魂の義兄”鎌田東二先生と
わが‟魂の義兄”鎌田東二先生と
神と仏は180度異なる存在です。そのまったく異なる原理や志向性を持つ2つの神聖概念が、いろいろな物事をメルトダウンしてきた日本列島の中で、「神仏習合」思想ないし文化という接合形態が生まれ、増殖しつづけました。これを仏教の神道化とも、神道の仏教化とも言うこともできますが、いずれにしてもはなはだしい仏教の「日本化」が起こった。「一仏成道観見法界、草木国土悉皆成仏」と命題化された天台本学思想はその極地です。最後に、著者は「日本という『自然風土』の中で形成されてきた『神道』と、その影響もしくは濾過作用によって変容し続けてきた『日本仏教』。そして、その両者の習合形態としての『修験道』。日本の宗教文化は賑やかで豊かで面白い。その日本の宗教文化の根幹に『言霊』の感受とはたらきと思想があるのである」と述べるのでした。まさに「霊性の思想史」というべき著者懇親の一冊を読み終えて、わたしは本書がまさに稀代の宗教哲学者であった著者の集大成だと確信しました。鎌田先生、死の直前にこんな超弩級の本を書かれて、あなたは本当に凄い方です!
