- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2407 宗教・精神世界 『スピリチュアルケア』 日本臨床宗教師会編著(作品社)
2025.06.30
『スピリチュアルケア』日本臨床宗教師会編著(作品社)を読みました。「臨床宗教師によるインターフェイス実践の試み」というサブタイトルがついています。京都大学名誉教授で宗教哲学者の鎌田東二先生から献本された本です。鎌田先生は5月30日に帰幽されましたので、今日はちょうど死後1ヵ月となります。仏教ならば「初月忌」となりますが、鎌田先生の場合は神道です。死後100日には、百日祭の「かまたまつり」を9月13日に行います。
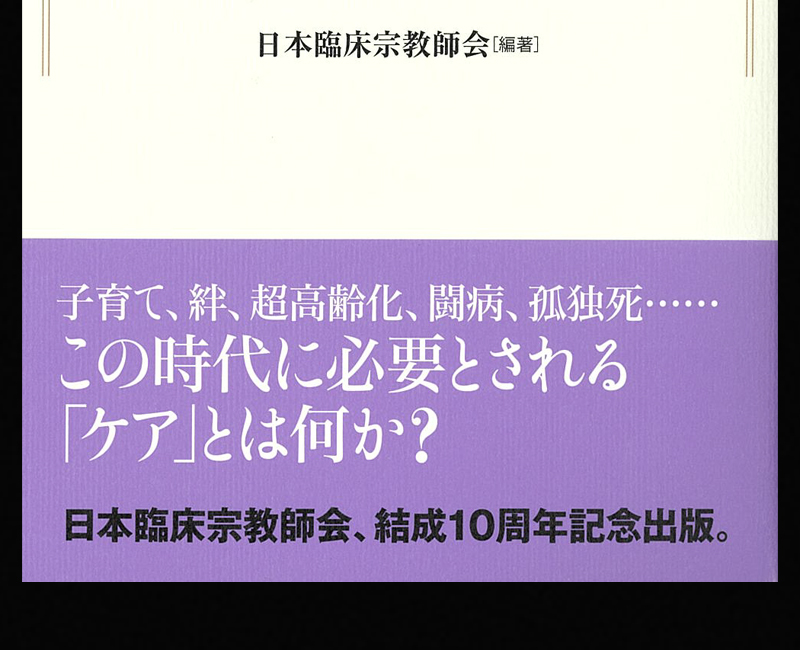 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、「子育て、絆、超高齢化、闘病、孤独死……この時代に必要とされる『ケア』とは何か?」「日本臨床宗教師会、結成10周年記念出版」と書かれています。
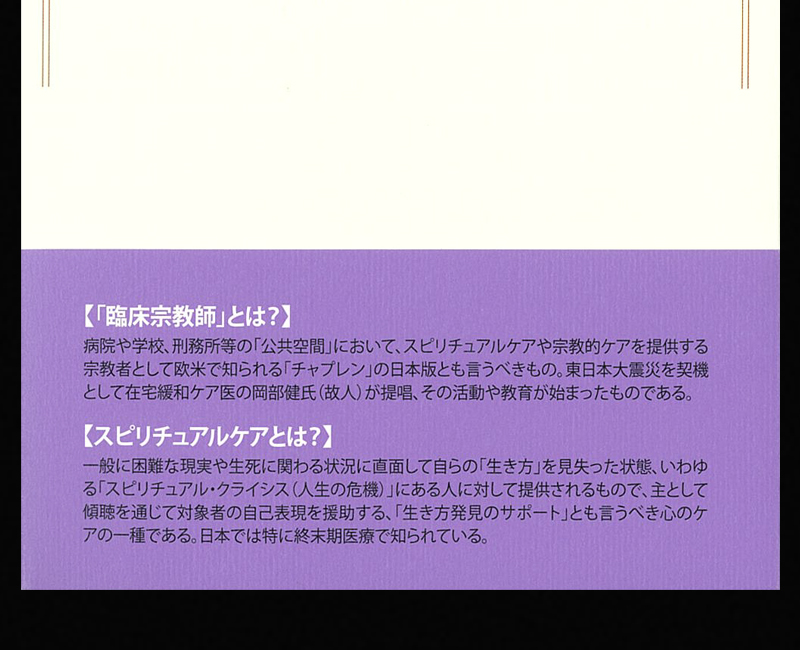 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、以下のように書かれています。
「【「臨床宗教師」とは?】病院や学校、刑務所等の『公共空間』において、スピリチュアルケアや宗教的ケアを提供する宗教者として欧米で知られる『チャプレン』の日本版とも言うべきもの。東日本大震災を契機として在宅緩和ケア医の岡部健氏(故人)が提唱、その活動や教育が始まったものである」
「【スピリチュアルケアとは?】一般に困難な現実や生死に関わる状況に直面して自らの『生き方』を見失った状態、いわゆる『スピリチュアル・クライシス(人生の危機)』にある人に対して提供されるもので、主として傾聴を通じて対象者の自己表現を援助する、『生き方発見のサポート』とも言うべき心のケアの一種である。日本では特に終末期医療で知られている」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
まえがき 臨床宗教師の先達モデルとその意味を問う
(鎌田東二)
序論
第1章 インターフェイスの本質を探る
――インターフェイスの集い1
コラム①臨床の宗教とカフェモンク
第2章 インターフェイス・スピリチュアルケアの実践
――インターフェイスの集い2
コラム②地域密着とネットワーク――慈愛会の活動
第3章 臨床宗教師としてのインターフェイスの実践
――「インターフェイスの集い」を振り返っての座談会
コラム③熊本地震被災地での臨床宗教師の活動
第4章 アメリカのインターフェイス・チャプレン
コラム④医療における臨床宗教師
インターフェイスと「ビリーフ自由」 解題に代えて
インターフェイスと「ビリーフ自由」
――解題に代えて(小西達也)
「おわりに」(窪寺俊之)
「用語集」
「臨床宗教師の養成に関する年表」
「まえがき 臨床宗教師の先達モデルとその意味を問う」の1「『臨床宗教師』とかけて、なんと解く?」の冒頭を、鎌田東二氏は以下のように書きだしています。
「『臨床宗教師とかけて、なんと解く?』『いのちにむきあうひとごころ(命に向き合う人心)、と解く』『そのこころは?』『人と人との奥底にある(あるいは奥にある)いのちの声をいのちをかけて、いのちを通して、聴きとり、取り次ぎ、つなぐわざである』からである。そんな『臨床宗教師』の先達モデルとして、わたしはつねづね遠藤周作の遺作『深い河』(講談社、1993年)に出てくる大津と石牟礼道子を思い描いてき、機会あるごとにそのことを主張してきた」
それでは、どこが先達モデル足りるのでしょうか? 1つは、宗教的なバックボーンを持ちながらも、そこに縛られず、自分自身の感性(命の声の感受)と思想(命に届く言葉の創出)に基づいた自由な(自在な)アクション(行動)に身を投じるところ。2つめは、公私の間に独自の倫理的な距離を形成しているところ。教団や国家や地方自治体などの行政組織に対峙しながらも、それにおもねることも、しばられることもなく、自身の感性と思想に根差す行動をしながら、しかも、自分勝手ではない、他者との交流・共感・協働をいつも大切にしているところです。3つめは、どこか、この世の漂泊者のような、旅人のような、巡礼者のような、頼りなげだが純真・純朴なたましいをもちつづけ、いきつづけているところです。4つめは、それに関連して、この世的にはとても要領が悪く、世渡り上手の反対のような生き方をしているが、彼らの周りの人びとの霊性に深く届く行為と言葉を伝え残したところ。
深い河 新装版 (講談社文庫)
深い河 新装版 (講談社文庫)
作者:遠藤周作
講談社
Amazon
2「『深い河』(1993年)の大津と『実在する神』としての『やき芋』と『玉ねぎ』」では、作家・遠藤周作について言及されています。彼は1923年3月に東京で生まれましたが、半年後の9月に関東大震災が発生。1935年に灘中学に入学、1938年7月の阪神大水害を体験。1940年に灘中を卒業するが翌年太平洋戦争が始まり、“戦中派”として戦争のさ中に青春時代を過ごします。そして小学校中学校時代をすごした神戸で阪神大震災が発生した翌年1996年に死去した。生まれた年と晩年に大震災が発生しています。鎌田氏は、「遠藤の中から生みだされた文学作品、特に『深い河』を考察することは、『被災者あるいは弱き者を前にした文学・宗教は何ができるのか』という問いを解くヒントを与えてくれるだろう。『神と人の痛みの文学』を。『弱さ』を生きざるを得ない人間のありようとそこにおける宗教のはたらきを」と述べています。
医療者と宗教者のためのスピリチュアルケア 臨床宗教師の視点から
医療者と宗教者のためのスピリチュアルケア 臨床宗教師の視点から
作者:谷山 洋三
中外医学社
Amazon
序論の2「なぜインターフェイスなのか?」では、東北大学大学院文学研究科教授の谷山洋三氏が「そもそも、臨床宗教師について考える際に、なぜ『インターフェイス』という言葉に注目するのか、について整理しておかねばならない。カタカナで『インターフェイス』と書くとき、interfaceとinterfaithの二つの英単語を想定するだろう。前者は『(コンピューターで)接続(する装置またはプログラム)』を意味する名詞または動詞で、後者は『異教徒間の、宗派を超えた』を意味する形容詞であり、ここでは後者を扱う。臨床宗教師は、日本版のチャプレンであり、chaplainの新しい和訳とも言えるのだが、この日本語を再び英語で説明する際に、interfaith chaplainを用いてきた」と述べています。
人は人を救えないが、「癒やす」ことはできる
人は人を救えないが、「癒やす」ことはできる
作者:谷山洋三
河出書房新社
Amazon
4「ケア提供者の内面」では、谷山氏は、仏教の慈悲とキリスト教の愛は、一定の共通点があると指摘します。慈悲の慈(metta)は無制限の友情といった意味ですが、これはおそらくアガペー(agape:無限の愛)と対比することができます。他方で、仏陀(如来)は人間の完成形であるので、人間を完全に超越した一神教の神(ヤーウェ、アッラー)とは比較することさえ難しいとして、谷山氏は「このような異同を踏まえた上で、類似点に焦点を当てれば他宗教を肯定的に見ることができる。とはいえ、各宗教には宗派や教派が多数あり、新宗教も含めれば、すべてを網羅して「仏教のすべて」「イスラムのすべて」を理解することさえ困難である」と述べています。
頭で教義を理解したとしても、感情的には受け入れられない側面もあるでしょう。つまり、他宗教を肯定的に見るとしても、自ずと限界があるということです。そのような限界を知り、自らの無知を受け入れることもまた、「一対多」において必要なことだと思うとして、谷山氏は「もし『無知の知』という謙虚さをもたないと、八つ当たりのように初対面の宗教を否定したり、攻撃するおそれがあるからだ。おそらく、自宗教への信頼と、他宗教への信頼がなんらかの形でバランスをとることで、『一対多』が可能になるのだと思う。グラデーションのように表現できる場合もあれば、多層的に表現される場合もあるだろう。真実と方便、という姿勢もあるかもしれない」と述べます。
インターフェイス・スピリチュアルケア――永遠と対話の根源へ
インターフェイス・スピリチュアルケア――永遠と対話の根源へ
作者:小西達也
春風社
Amazon
第1章「インターフェイスの本質を探る――インターフェイスの集いⅠ」の2「『インターフェイス(interfaith)』とか」の2-1「『インターフェイス』とは」では、第1回「インターフェイスサミット」の様子が記録されています。武蔵野大学教養教育部会教授・科長の小西達也氏が「『臨床宗教師』は最も単純には「日本版チャプレン」という言い方ができますが、実は『臨床宗教師』および世界中のチャプレンが提供するケアのほとんどは『インターフェイス・スピリチュアルケア』、あるいはより簡単に『インターフェイス・ケア』である。インターフェイス・ケアというのは、『ケア提供者』と『ケア対象者』の信仰が異なるような関係性におけるケアを意味します」と語っています。
今後、世界そして日本において、社会の多文化・多宗教共生化のさらなる進展が予測されているわけですが、その場合、異なる文化・宗教の人同士の関係性が増加していくわけですから、「インターフェイス」、そして「インターフェイス・ケア」ということもますますその重要度を増していくことが予想されるとして、小西氏は「にもかかわらず、実は『インターフェイス・スピリチュアルケア』の理論ということ、そもそもインターフェイスでのスピリチュアルケアがいかなる原理により可能となるのか、といった極めて基本的な事柄が、日本だけでなく実は世界的にも未だ明らかにされていない、ということがあるといいます」と語ります。
2-5「異なる信仰の理解」では、わたしたちが他者を理解する場合、そこには理解する人とされる人の間に何らかの共通基盤のようなものが必要となるといいます。哲学的には「共約可能性」と言われる問題です。果たして異なる信仰の間の共通基盤というのは存在するのか。日本を代表する仏教哲学者、中村元による「宗教」という言葉についての説明が参考になります。「宗教」という言葉は、「宗」と「教」という2つの漢字から構成されるわけですが、中村元はその2つの漢字の意味について説明を加えています。まず「宗」のほうは「元のもの」、「言語表現を超えた根本のもの」という意味を持つものである。それに対して「教」の方は、「「宗」を各々の文脈に応じて言語表現化したもの」と説明します。小西氏は、「この考え方に基づくならば、『宗』は対立を超えた次元のもの、対立を包含するもの、『ビリーフ自由』の次元のもの、ということになります。もしそうであるならば、私たちはこの『宗』の次元に目覚めることで、そこから多様な信仰の理解が可能になってくるわけです」と述べます。
2-6「『ビリーフ自由』と危機」では、小西氏は以下のように述べています。
「実は私は、スピリチュアルケアにおける『対象者』との向き合い方には、武道と非常に近い面があると感じております。これをお聞きになられた方は、『スピリチュアルケアが相手をケアするものであるのに対して、武道は戦いであるので、両者はむしろ対極的なものなのではないか』とお感じになられるかもしれません。しかしスピリチュアルケアの場というのは、双方が全身全霊をかけた真剣勝負の場でもあるのです。スピリチュアルケアの『対象者』の方には、文字通り命がかかっている状況の方が非常に多いわけです。そこで全身全霊で生きようとしている。そうした方々をケアするためには、こちら側も本当に全力を挙げて向き合うということをしないと、そもそも関係性が成立しない、ということがあるわけです」
3「私のインターフェイス」の3-1「インターフェイス五態――『超宗教』『通宗教』『共宗教』『原宗教』『交宗教』」では、鎌田東二氏が、インターフェイスを以下の5つの言葉に言い換えます。
(1)「超宗教(Meta Religions)」
(2)「通宗教(Cross Religions)」
(3)「共宗教(Co Religions)」
(4)「原宗教(Proto Religions)」
(5)「交宗教(Inter Religions)」
この5つです。メタレベルで宗教やビリーフを超える、俯瞰する(「超宗教」)。同時にクロスする(「通宗教」)。また、共にある「with」とか「co-operate」とか「collaborate」(「共宗教」)。そして、その元になるもの、「原宗教」もあるでしょう。そういう中で「Inter Religion」、つまり、「交通・交差・交流・協働」するレリジョンやビリーフがあります。
従来、こういう問題領域を本格的に問うてきたのは宗教哲学だったと思うとして、鎌田氏は「。その宗教哲学の中に比較という部分があって、比較思想、比較哲学、比較宗教学、比較神話学、比較文明学などなどを含みながら、それを『通』『共』『原』『交』『超』という形でまとめていく、見通していくという中で、インターフェイスの枠組みや理論や理解が深まっていくのではないかと考えています。しかし、それは俯瞰の道、『鳥の眼』になることであって、我々は鳥の目だけでは生きていけない。この現実の一番フィジカルなレベルで、『虫の眼』を持たなきゃいけない。その虫の眼が民俗学だと私は考えていて、したがって私の学問的な探究の中で、宗教哲学と民俗学の両方が常に大事だということになります」と述べています。
鎌田氏は、映画「地球交響曲」の監督で2023年に逝去した故龍村仁氏の姉であるニューヨーク在住の龍村和子氏とやり取りをし、「Interfaith Peace Gathering」とある、「Interfaithは日本語に訳すと何と言うのですか?」と質問したそうです。そうすると、「Interfaithは「超宗教」とか、「どんな種の宗教も入って」とかです」と答えが返ってきました。鎌田氏は、「彼女はニューヨークに50年近く住んでいて、英語も堪能。その彼女の中では、インターフェイスは『超宗教』とか、『いろんな種の宗教も入って』という意味となる。ですので、こういうふうに、異なる国々や地域に住む、異なる人種性、民族性、歴史性を持ち、異なる宗教や信仰を持って生きている人々同士が集って、平和を実現していこうとする集い、ギャザリングをしたということですね」と語っています。
3-3「『インターフェイス』と社会問題への取組み」では、鎌田氏は以下のように語っています。
「今さまざまな危機があります。環境、食料、エネルギー、経済、政治、文化、教育、家庭、健康、宗教、至るところが絶体絶命の状況ですよね。その絶体絶命の状況の中で、どのような『ひらけ』が生まれてくるかといったら、やはり、宗教や芸術というのは、その『ひらけ』に向かう大きな力になり得ると思うし、しかし同時にまたそれが、特に宗教が、その反対に閉じてしまう方向に行く力をも持っている。対立や分断や排除や差別や暴力に向かう力と構造も持っている。そこで私は、宗教よりもより危険度、リスクの低いと思われるアートに注目し、そこから『ひらけ』を具体的に模索しました。先ほど、小西さんは武道がスピリチュアルケアとか、インターフェイスに近いと言われましたが、私はやっぱりアート。そして、芸術、芸能、芸道、まさにそれらは、広い意味でのアートだと思うんですね。そのアートに着目ができてきたのが、心のケアが話題になった阪神淡路大震災以降であると思います。そして、東日本大震災で、それがさらに展開されていった」
3-4「『インターフェイス』とアート」では、鎌田氏がブログ「『「顕神の夢」展』で紹介した展覧会の監修を依頼され、川崎市の岡本太郎美術館で2023年4月29日に始まって、足利市立美術館、久留米市美術館、町立久万美術館、壁南市藤井達吉現代美術館で、50数名の方々の展示が行われたことが紹介されます。鎌田氏は、「その中には、出口なおも、出口王仁三郎も入っていて、横尾龍彦さんも宮沢賢治も入っている、という展覧会。その中の横尾さんは、幻視のパートで出てくる。横尾龍彦、『内的光を求めて』。この内的光を求めるというところに、インターフェイスの1つの形はあると思うんですね。共通のものとか根源のもの。ある種、神秘主義であるとか、修行の段階のある側面で幻視とか、という言葉は必ず出てくる。あるいは内観というものが必ず出てくる。その内なる小宇宙というようなものをどう見通して、外なる大宇宙と内なる小宇宙というものがどうクロスし、融合していくかということが、常に大きな課題になり、これは神秘体験の重要な側面であった」と語ります。
4-2「震災でのインターフェイス体験」では、通大寺住職(曹洞宗)で傾聴移動喫茶「Café de Monk」マスターの金田諦應氏が、医師であり、またケセン語の聖書で有名な山浦玄嗣を紹介します。彼は、ケセン語という、岩手県沿岸大船渡を中心にしたごく限定された地方の言語で「ギリシャ語」「ヘブライ語」から福音書を翻訳し直したという人です。金田氏は山浦玄嗣について、「先生は代々クリスチャンの家系で育ったのですが、いつの頃からか、日本語に翻訳された聖書に違和感を持つようになった。そこでギリシャ語やヘブライ語を参照しながら翻訳し直しました。しかもそれを先生の地元の言葉『ケセン語』で翻訳解釈していった。大変な作業だったと思います。単に日本語では『祈り』と訳されているのですが、実は祈りの使い方が大きく分けて4つあるということです。その中の1つ『プロセウコマイ』と表現される『祈り』はこちらからあちらへ気持ちを通じさせるというよりも、むしろ『聴く』という意味があるということでした。従って『祈り』とは、己を捨てて、神の言葉を全身全霊で聴くことであるということです。また『言葉』についても興味深い解釈をされて、言葉とは『ダバール』つまり出来事である。つまり、神の言葉としての出来事に対して、私心なく聴き、そして神の使命として行動することである、という説明に対して親近感を覚えました」
金田氏は、鎌田氏との思い出も語ります。金田氏のお寺の近くに小さな美術館があり、鎌田氏がそこで講演しました。講演前にこの地方のことをご紹介がてら、一緒にドライブをしたそうです。創建が奈良時代という箟岳山箟峰寺があり、その近くには金が採れる涌谷という場所がありました。ここで採れた金、奈良の大仏の金メッキに使われたということです。この箟岳山に立ったときに、鎌田氏が、川を見て「金田さん、あそこは何だ」と訊くので、「あれは北上川と迫川の合流点です」と答えたら、「金田さん、すぐ行こう」と言うので、車を走らせ、最後は藪の中を漕いで、その北上川と追川の合流点に行き、そこから合流点に向かって法螺貝を吹いたそうです。金田氏は、「私の住む栗原には栗駒山があって、そこから3本の川が流れている。そしてそれらの川は、やがて箟岳山の麓で北上川と合流します。北上川は東北を縦断し石巻湾、追波湾へと至る広大な風土、文化の流れを繋ぐ川です。法螺貝は命と人を支え、そして結ぶ。この風土への敬意、畏敬と言うのでしょうか。私は今までそういう視点を持たなかった、先生が気づかせてくれたと思います」と語っています。
4-4「霊と対話」では、被災地には一般的には霊的現象と言われている様々な現象が起こったことが紹介されています。平常時では考えられないような出来事・現象を体験して苦しんでいる人々の相談を受けたり、逆にそれによって慰めを得ている人々の話を聴いたり、金田氏はさまざまな経験を持ったそうです。ある日の夜、1人の女性から電話がありました。亡くなった人が自分の身体を支配し、苦しくて自殺したい、どうにかして欲しいとのことでした。その夜、家族を伴って来寺。すでに憑依状態にあり、憑依している人の声で苦しさを訴えていました。その日から約1年弱に渡る、金田氏と彼女に憑依している霊との対話が始まりました。合計すると26名程になったとか。
その体験はロンドン・タイムス日本支局長、リチャード・ロイド・パリー氏の著書『津波の霊たち』がロンドンで出版されてから一気に世界に広がりました日本では奥野修司氏の『死者の告白』が出ました。これらの本の影響があって、その後「Netflix」でドキュメンタリー映画化。「Arte」というフランス、スイス、オーストリアが出資している番組に、日本人の死生観という切り口で取材に来ました。金田氏は、「彼らは幽霊を実体のあるものと捉えて、そこから議論を展開しようとしておりましたが、私たちはそれを現象として捉えて説明を試みました。それはどこまで行っても平行線で、私たちの文化の中の幽霊現象は証明と言語化をやんわりと拒み続けていました」と語っています。
金田氏は、「『幽霊』は、日本という精神風土の中に立ち上がる『生と死の物語』であり、確たる『存在』というよりは留まらぬ『表象』の中の出来事。そして出来事は、時空を巻き込みながら絶えず変化する『あわい』の世界だと思います。大きな括りでいう『西洋と東洋』の越え難き壁を感じました。一連の被災地での『霊との対話』は能の世界そのものの中にいる感じがいたしました。能の演目の一つ『井筒』は在原業平を恋慕する幽霊と旅の僧との物語。この物語は、夢の中で夢が語られ、そして暁とともに物語が端向こうへ消えていく、導入もなく、結論もなく、シテ・ワキ・観能者の物語の交差。始まりも知れず、行方も知れず、夢の中で夢が語られる。ここに究極のスピリチュアルケアの有様を感じます」と述べています。
曹洞宗の僧侶である金田氏がキリスト者と共に歩いた四十九日追悼行脚の時は、遺体とヘドロの匂いの中、経文を唱え讃美歌を歌いながら歩いたそうです。海岸が近づくにつれて、経文は叫びに、牧師は歌う讃美歌が見つからない状態になったのといいます。そして破壊された海岸に立った時、学んできた教義教理が崩れていく感覚に襲われたそうです。金田氏は、「この状況をどのように理解し、向き合えばいいのか。あらゆる宗教的言語から削ぎ落とされてしまう自己を感じました。神仏の姿を見失う感覚です。限りなく自我が削ぎ落とされていくプロセスがここから始まったと思います。自己と他者との関わりを『慈悲』や『愛』に置き換えることができるのではないかと思います」と語っています。
4-5「臨床宗教師活動のはじまり」では、傾聴活動(カフェデモンク)で仮設住宅に入ると、金田氏たちに向けられた問いは、あらゆる宗教言語を拒否する凄みがあったと明かされます。「どうして俺が生き残った」「誰が生と死の境を決めている」「助けることができなかった」「孫の遺体が見つからない」「亡くなった人はどこにいる?」死別の苦しみ。将来への不安。遺体の見つからない空虚な心。狭い集会所の空間には人々の心の叫びが溢れていました。次第に「自と他」の境界線が透明になっていく感覚が湧き起こってきます。金田氏は、「これが『慈悲』というものなのか、と感じました。しかし、自他を繋げる力が『慈・愛』ならば、繋がれば繋がる程どうにもならない現実に直面する。それが『悲』なのかと思います。引き寄せられたり、逃げ出したり。人には『慈』と『悲』が同時に存在し、その相反する力の自己展開が人を、宗教者を成熟させていくと感じます」と語ります。
金田氏は、被災地では「ガンジー金田」と名乗っていたそうです。他のメンバーもそれぞれニックネームを付けて呼び合っていたといいます。これには3つ意味があって1つは脱教団、脱肩書です。被災地では今までの肩書では活動しない、求道の者としてそこに居るという表現として。1つは場をほぐすユーモアとして。そして最後はマハトマ・ガンジーへの敬意ということでした。金田氏は、「ガンジーは、宗教的属性を超えたあくなき真理の探究者であり、品格、尊厳、良識、正義に対する温かく厳しく、そしてユーモラスな眼差しを持った方でした」と述べます。ガンジーの有名な言葉に、「私はヒンドゥー教徒であり、イスラム教徒であり、キリスト教徒であり……」という言葉があります。まさに金田氏もこのように「他者」に向き合いたいという思いがあったそうです。
カフェデモンクの原点は「火を興すことと芋を焼く」ことでした。今日のインターフェイスの集いも、火をいじりながら、焼き芋を焼くような感覚でやりましょう、ということでした。「火を興し、火を囲む、芋を焼いて、分かち合う」。ここにたくさんの宗教者、多種多様な専門職が集まって、火を見つめながら、共にこの被災地のことを考え共に苦悩する、金田氏はそのような姿を多く見てきました。金田氏は、「火を囲んだ時、宗教・宗派・教理・教義、そして言葉すらいらないのです。そして、次第に教義を超出していくという感覚です。そして、常に崩壊する世界の先端にいて世界を紡ぎ続ける。言い換えれば『絶体絶命』の時、常に先端にいて世界を語り続ける、これがインターフェイス・チャプレンシー(臨床宗教師)の大きな役割ではないかと思います」と述べるのでした。
4-6「インターフェイスと人類の危機」では、この火を囲んでいる時、200キロ先の福島第一原発では、核燃料がメルトスルーしていました。そのような状況について、金田氏は「原子の火は、人類が最高に到達した温度。そして目の前に熾きている炭の火は、人類が最初に発見した火。そして、最初に料理したのは、おそらくお芋だったと思います。その芋を焼いて、それを持ってみんなで分かち合いながら、人類は偉大なる旅に出て、そして地球に今でも生存し続けているということだと思います。これが人類の原点だと思います。私たちは生老病死、自然災害、文明禍、疫病禍を共に歩んでいるという視点を決して忘れてはいけない、その時に宗教宗派の差などどれほど意味があるのでしょうか」と語っています。
5「鼎談」の5-1「価値判断を加えず、現在進行形に身を置く」では、小西氏が「武道における二者の関係性というのも、実はその本質はスピリチュアルケアとあまり変わらないのではないか、と思ったりもします。自力と他力のバランスであるとか、『間』というような話もありましたが、やはりその辺りのことなのではないかと思います」と言えば、金田氏は「音楽なんかもそうですよね。特にインプロビゼーションを大切にするジャズなんかは、相手の音をよく聴くことがとても大切です。相手の音をよく聴いて、そしてその音にどのように自分を織り込んでいくか。マイルス・デイヴィスはセロニアス・モンクとのセッションの時、30分間じっとモンクの音を聴き、音を出しませんでした。お互いにすごい緊張関係があって、どんな音を出していったらいいのかということを感じ合っていたのだと思います。Don't think,feel.長い沈黙。沈黙には意味があり、沈黙の中から音(言葉)が紡ぎ出されていくわけです」と述べます。
5-2「『ビリーフ自由』と能」では、鎌田氏が禅に言及し、「やっぱり禅を通して、そういう世界っていうのが体得されるというか、にじみ出てくるというか。体を通して、その人の心を通して、風が吹いているような状態ね。それを禅では、『行雲流水』って言ってきた。『雲水』っていうのは、まさに『行雲流水』の回国行者、『諸国一見の僧』になるわけでしょう。そして、それは能の世界で成仏させる力になって、『諸国一見の僧』はまず傾聴して、そして、祈る。読経するとか。そして、その祈りを聞いて、恨みの言葉が消えて、舞を舞って、あの世に還っていく。これは金田さんが言われるように、究極のスピリチュアルケアで、私は能は『平時の武道』と言ってるんですよ。平和の時代の武道が能で、能の達人は武道の達人です、間違いなく。能がきれいにできるためには、武道がきれいにできるのと同じこと。ですから、合気道もさまざまな剣道や武術も、全部能の中にその根幹はある、それは共通している。だから、日本文化の精髄と言えるんじゃないかな、能はね。ある種、プロトタイプを成していると思います」と述べます。それに対して、金田氏は「私もそう思います。それで面白いのは、能っていうのは、橋向こうから始まって、橋向こうに消えていく、始まりもなく、終わりもない、そして語るべき結果もないというようなケアの究極の在り方みたいなものを感じます。ワキ・シテ、そして観客が夢の中で物語に絡んでいく。そういう日本芸能の伝統の中に、日本風土に根差したスピリチュアルケアの原型を感じます」と応じるのでした。
5-3「インプロビゼーション(Improvisation)」では、鎌田氏が「臨床宗教師のケアっていうのは、まさにそのインプロビゼーションなんですよね。そのインプロビゼーションが、あの能の林の中に仕込まれているんです。『う~う~』という掛け声であるとか間合いであるとか。もちろんそれは一つの曲の形式性がありますけど、その場で立ち上げる。その場の空気、場の流れの中で。だから、インプロビゼーションの構造を持ってる」と言えば、金田氏は「しかし、インプロビゼーションが成り立つのは、きちんと基本ができてないと出来ないと思います。自由自在と自分勝手は違う。自由自在に世界を観察し、この身心を以て世界を表現する。臨機応変な世界観を問い続けていないとインプロビゼーションは成立しません」と語っています。
そこで小西氏は、以下のように語っています。
「金田さんも『ケアはアートだ』とおっしゃいますし、鎌田先生もアートということをおっしゃるわけですけど、『アート』ということの定義に関して、インドの哲人、クリシュナムルティという人が、これは果たしてこの人のオリジナルなのかどうかはわからないのですが、『あるべきものをあるべきところに置くのがアートだ』ということを言っています。それは例えばケアにおいても、その場において、一番ふさわしいものを見つけて、それを置いていく。つまりその場その場で真に最適・最善な唯一無二の反応を見出し提供していく。それができるということがケアの本質なのではないかと。私もスピリチュアルケア教育の中で、『ケアとは、こういうことをすることですよ』とか『まずはこういう訓練が必要ですよ』とか、いろいろ申し上げているのですが、結局のところはそれはやはりどこまでもインプロビゼーショナルなものであって、そこで最も適切なものを、その瞬間に見つけることが、一番の核心なのではないかといつも感じています」
5-4「スピリチュアルケア、インターフェイスと日本文化」では鎌田氏が「スピリチュアルケアは、日本の武道に近いということを言われましたね。私はお茶もすごくスピリチュアルケアに近いものがあると思う。お茶は言語を介さない部分が結構重要。能は揺があり、舞があり動的です。でも、お茶は非常に静的。沈黙の中で、つつましい空間の中で、小さい空間の中で、しかし、大宇宙につながる。あの能とお茶を極めることができたならば、日本の武道的な精神とか、日本の文化の根幹にあるものの世界に通じていく、もともと型を持っているがゆえの、自由なインプロビゼーションになり得るものじゃないか。そういう伝統遺産だと思う。その辺のことを今日は非常に強く感じさせてもらいました」と語っています。ここは、非常に重要な発言であると思いました。
その後、以下の興味深い対話が展開されます。
金田 実は私の母は裏千家のお茶の教授で、父は喜多流能楽の教師をしております。私自身その二つとも実際に修めてはいませんが、子供の頃より染みついた感覚があったんでしょうね。
鎌田 え~。能茶……。
金田 能茶一如なんですよね。活動が始まって何年かやってみて、カフェデモンクの傾聴空間のこと考えたときに、何だ、これ母がやってるお茶と全然変わらないなあ。自分は父の謡の中の「諸国一見の僧」の役割を果たしているだけなんだ、と気づき始めました。カフェデモンクの傾聴空間には様々なグッズを仕掛けていきます。様々な言葉、置物だとか、掛け軸だとか、お花だとか。そういうグッズで心を揺らしながら、ほぐしていく。特別なテクニックで特別なことをしていたわけではない。場を開き・場をほぐしながら何もしないで人を待っていた、それだけだったんだなあと思います。
6「質疑応答」の6-1「なぜインターフェイスは必要なのか」では、金田氏は「私にとって異文化・異宗教との強烈な出会いは、ロンドンタイムズ日本支局長リチャード・ロイド・パリーさんの『津波の霊たち』が出版されてから様々な海外メディアとの対話がありました。その対話は出版されたりテレビ放送・映画放映されたりして広く海外に広まりました。『幽霊』という言葉自体、ヨーロッパのキリスト教文化圏には該当する言葉がない。日本の風土や宗教感情・民俗信仰等について、彼らにも理解出来るように、苦し紛れにユング深層心理学や大乗仏教の唯識論等を駆使しながら説明を試みたのですが、『諸国一見の僧』『始まりなく終わりなし』『淡の世界』とか所謂『味わいの世界』が分からない。最後までそれは平行線でした。でも、彼らは一生懸命理解しよう、理解しようと努めておりました。これは彼らの口から出た言葉ですが、行き詰まったヨーロッパ合理主義をなんとか東洋の世界観で乗り越えたいということでした」と語っています。
6-2「臨床宗教師としてのアイデンティティ」では、鎌田氏が以下のように語っています。
「私は言霊の思想というテーマで博士論文『言霊思想の比較宗教学的研究』(2000年、筑波大学提出、のちに、『言霊の思想』青土社、2017年)を書いた人間なのですが、言葉が持っている霊性的な力とか、深いものがやっぱりあるんですね。ダバール、出来事だというようなことも含めてですけれど。だから、名称というのは『名詮自性』という、名は本質を表すという部分があるので、非常にそれぞれ大切な起源というのか、成り立ちを持っていると思うんです。それをどうやって尊重し、開いていくことができるか。私はあえて、『神職』という言葉を使わずに、古語で『古事記』や『日本書記』の中で『神主』という言葉が出てくるので「神主」という言葉を使いたい。だから、『フリーランス神主』と名乗っています」
コラム①「臨床の宗教とカフェデモンク」では、金田氏が「泥の中を神仏の言葉を探しながら歩いた日々。そして1年後、四十九日と同じ海岸に立って感じた再生の風。『色即是空・空即是色』が回転を始め、諸法のありのままの姿を受け入れている自分がいた。それはまさに信仰の崩壊と再生の物語だった。生きるということは過去・現在・未来という時間軸と家族・社会・風土という空間軸が仮に『私』と名付けられた結束点の上で展開するかけがえのない物語。人はそれぞれの物語を創造しながら生きている。私達の活動目的は1つ。突然の出来事で破壊され、凍り付いた時間と空間を再び繋ぎ合わせ、共に未来への物語を共に紡ぐことである」と書いています。
初盆の時流した三つの灯籠が、沖で一つの塊となって消えていったのを見て、津波で亡くなった妻・娘・孫が大きな命の輪の中に帰り、三人一緒に暮らしていることを確信した老人。津波で亡くなったおじいちゃんの腕時計を修理し、おじいちゃんが生きる事が出来なかった未来を、共に歩み出すことを決心したおばあちゃん。それらを挙げた後、金田氏は「人は未来への物語を創造する能力、大きな命の源に繋がる能力を持っている。その能力をひたすら信じ、それぞれの物語が動き出すまでじっと待つ。宗教者には物語が展開していく『場』の創造、その『場』に留まり続ける『耐性』、そして個々の人生に添って創造される物語を受け止めるレンジの広さが要求された。悟りや救いを饒舌に説くことは宗教・宗派の教義の自己満足になっても、一人一人の救いにはならないのだ。宗教・宗派的な文脈で語られる『救い』ではなく、その人の物語の文脈で語られる『救い』が自然に落ちてくるまでじっと待つことが求められるのだ」と書くのでした。
第2章「インターフェイス・スピリチュアルケアの実践――インターフェイスの集いⅡ」の1「はじめに」では、鎌田氏が「『インター(inter)』と『信仰』を表す『フェイス(faith)』というものを2つつなげると、私たちの思考の幅というのが広がる。臨床宗教師って何をするんですかって聞かれても、臨床宗教師は公共空間でうんぬんというのは、なかなか分かりづらいんですよ。でもインターのフェイス、信仰なんですねっていうのは、英語を最近では小学校から学んできていますから、インターフェイスという英語で、そのまま理解するほうが概念として分かりやすい」と語ります。
2-2「『フェイス(faith)』の本質」では、兵庫大学大学院非常勤講師の窪寺俊之氏が、「インターフェイスの働きは、目に見えない神仏だとか神秘的な存在とか、超越的な存在に関わる働きです。これが実は、生き方を選択するときの根拠になってくる。自分が心地よいという思いを持つための関係性と非常に関わってくる。あるいは、その信仰とか信条ということが、生きるときの確かさの実感を与えることになっていきます」と語っています。また、重要なのは、健康な宗教的な感性を持つということだとして、窪寺氏は「健康というのは平凡であるかもしれませんけれど、バランスがあるということだと思いますね。それから、健康とは善悪などの倫理性とは必ずしも一致しない。必ずしも健康だからといって、それが善とは限らない。倫理的とは限らない。しかし、倫理を逸すると健康を害するということはあると思います。そういう面を持っているということですね」と語ります。
6「質疑応答」の6-1「『インターフェイス(Inter-face)』と『インターフェイス(Inter-faith)』」では、上智大学グリーフケア研究所客員所員の伊藤高章氏が、「私はもともとは英国教会の伝統に属するクリスチャンです。大学院ではインドへのイギリスの宣教の勉強をしました。桃山学院という英国教会の宣教師が建てた大学に勤めて、その後、カトリック教会の中のイエズス会が創設した上智大学に勤めて、今は立正佼成会の佼成病院のチャプレンをしています。1人でインターフェイスを渡り歩いているところがあります」と語ります。
伊藤氏はさらに、「人と人が顔を合わせる。顔と顔が向き合っちゃう『インターフエイス(inter-face:境界面、向き合うこと)』の場面では、常に『インターフェイス(inter-faith:異なる宗教間の)』なのではないか。つまり、人と人が生に向き合う場では、それぞれの人たちが自分たちのビリーフだとか信条だとかを手放さないと、そもそも傾聴ができないのではないかという気がしています。『インターフェイス(inter-face)』は『インターフェイス(inter-faith)』」とも語っています。
6-2「『ビリーフ自由』は可能か」では、伊藤氏がアマルティア・センの『アイデンティティと暴力――運命は幻想である』(勁草書房、2011年)という本を紹介し、その中に、人が他の人を帰属で見たときに、初めて人は他者に対して暴力的になれるっていう記述があることを指摘します。だから、「インターフェイス(inter-faith)」の状況で、あなたのフェイス(信仰)はこれですね、私のフェイスはこれですねって言ったら、そこには暴力性の気配みたいなものがあるというのです。
6-6「『ビリーフ自由になるべき』とのビリーフからの自由」では、小西氏が、「インターフェイス」を単に信仰の違いというだけではなく、文化の違い、さらには「違い」一般、いわば「異他性」とどのように向き合うか、というテーマとして捉えると、またより一般性の高いものになってくるのではないかと思うと述べています。また、「ビリーフ自由が重要」となると、「ビリーフ自由を目指しましょう」という目標を立てることになりがちですが、それでは「ビリーフから自由になるべき」とのビリーフを持つことになってしまいます。小西氏は、「『ビリーフから自由になるべきである』との新たな『ビリーフ』を持つことになる。しかし逆に、先ほども『ビリーフ自由など無理なのでは?』とのご意見もあったかと思いますが、『ビリーフ自由』とは、『ビリーフ自由など無理である』というビリーフを持つことでもない」と語るのでした。
「インターフェイスと『ビリーフ自由』――解題に代えて」では、小西氏が、「スピリチュアルケア」には統一的定義は未だ存在していませんが、一般には困難な現実や生死に関わる状況に直面して自らの「生き方」を見失った状態、いわゆる「スピリチュアル・クライシス(人生の危機)」にある人に対して提供されるもので、主として傾聴を通じてケア対象者の自己表現を援助する、「生き方発見のサポート」とも言うべき心のケアの一種であることを指摘します。日本では特に終末期医療で知られています。一般に宗教者が提供する「宗教的ケア」は、その提供者が所属する宗教宗派の教えが示す「いかに生きるべきか」に基づき、「対象者」の生き方を導くものですが、それに対して「スピリチュアルケア」は、そうした教えを持ち出すことなく、「対象者」の内面にあるものを引き出す形で生き方発見をサポートすることを特徴とするといいます。
「おわりに」では、窪寺氏が「異なる宗派の宗教者が協働することは非常に望ましいことであり、今までもいろいろの形で協働の形が議論され、実際になされてきましたが、なかなか結論は出ていないと思われます。欧米でも日本でも多宗教間対話などとして議論されてきました。宗教者が公共空間で働く際の課題を真剣に議論するきっかけを与えてくれたのは、東日本大震災でした。異なる宗派の宗教者が被災地に入り、被災者と直接対話し、被災地の現場を見て自分自身のあり方を反省し、考える機会となったのです。自分達の宗教のあり方を根本から問い直す機会となりました」と述べています。本書は編集が硬くて、けっしてリーダブルな読み物ではありません。しかし、これまで鎌田東二先生から何度も「グリーフケアとスピリチュアルケアの関係をどのように考えていますか?」という質問を受けてきたわたしにとって、「スピリチュアルケア」について学び直す良い機会となりました。最後に、「インターフェイス((inter-faith))とか「ビリーフ自由」といった本書のキーワードは、わたしの考えにも合致するものであることを申し上げておきます。