- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2421 オカルト・陰謀 『オカルトがなぜ悪い!』 井村宏次・稲生平太郎・吉永進一著、横山茂雄編(ビイング・ネット・プレス)
2025.10.02
『オカルトがなぜ悪い!』井村宏次・稲生平太郎・吉永進一著、横山茂雄編(ビイング・ネット・プレス)を読みました。雑誌「別冊歴史読本」特別増刊『オカルトがなぜ悪い!』(1994年8月刊行)に掲載された内容に、鼎談「『異端』と『正統』の思考」を新たに収録した本です。
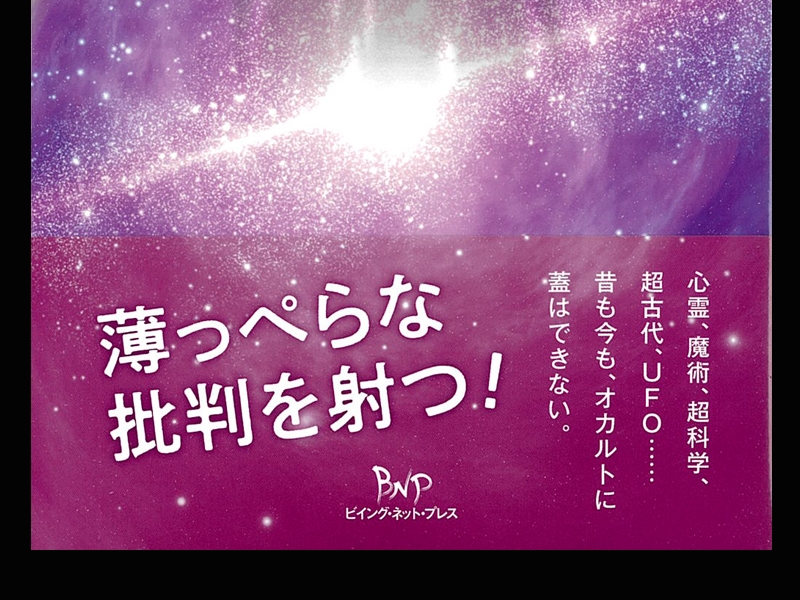 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、「薄っぺらな批判を射つ!」と大書され、「心霊、呪術、魔術、超科学、超古代、UFO……昔も今も、オカルトに蓋はできない」と書かれています。
本書の内容は、すでに30年前に雑誌で読んだ文章がほとんどでしたが、再読してもなかなか新鮮でした。なお、共著者のうち、超心理学研究家・東洋医学研究家の井村宏次氏は2014年に、宗教学者の吉永進一氏は2022年に他界しています。稲生平太郎氏のみ健在ですが、その正体は、編者である英文学者の横山茂雄氏のペンネームです。
アマゾンには、以下の内容紹介があります。
「心霊、呪術、魔術、超科学、超古代、UFO……、オカルトはいつの時代にも、場所にも存在しました。1970年代後半オカルトムーヴメントが日本にもおこりました。80年代に精神世界という言葉とともにヨガ、チャネリング、占星術がブームを起こし、90年代にはカルト宗教が社会問題化しオカルトへの批判が高まりました。オカルトの本質は何なんだろう?なぜ人の心にオカルト衝動は潜むのだろう?人間存在への探求がなくてはオカルトの本質を理解することはできません。本書は、古くて新しいオカルトの問題を提起して、その本質を探ります」
本書の「目次」は、以下の通りです。
鼎談1 オカルトがなぜ悪い!
(井村宏次・稲生平太郎・吉永進一)
第1部 浅薄な批判に断固反論
第2部 真実と信念の違い
第3部 批判するより勉強せよ
鼎談2 「異端」と「正統」の思考
(井村宏次・稲生平太郎・吉永進一)
人類を呪縛してきたオカルト衝動(井村宏次)
オカルトという言葉の正体――
未整理な「経験」に貼り付けられたラベル
(吉永進一)
「異端科学狩人」たちのオカルト狩りを笑いとばす
(吉永進一)
天に光、地に要請――UFO体験をめぐって
(稲生平太郎)
「初出一覧」
「解説」横山茂雄
「人名索引」
鼎談1「オカルトがなぜ悪い!」の第1部「浅薄な批判に断固反論」の「隠された知の体系――オカルトの起源」では、吉永氏が「『オカルティズム』という言葉は、最初は、キリスト教以外の怪しげな術を指したのが始まりだったはずですよね、19世紀までは」と言えば、稲生氏は「でも、ルネサンス期の『オカルト』的な思想は、アンチキリスト教じゃないでしょう。人文主義者たちは、むしろキリスト教的カバラとかキリスト教的魔術を標榜していたわけで、ルネサンス期において別にアンチのニュアンスはないと思うんですが」と語っています。
また、オカルトは語源的には「隠されたもの」ということであると指摘し、「ルネサンス期には、それまで失われていた知識がまた出てくるわけですね。ギリシア、ローマ、それからイスラム圏の知識なんかも含めて、そういうものが復興してくるわけで、そういう流れもあったと思うんです。要するに、中世ヨーロッパの知の主流体系以外に別の体系があるんじゃないかみたいな」と述べています。
井村氏は、キース・トマスの『宗教と魔術の衰退』[荒木正純訳、法政大学出版局、1993年]という本を紹介し、「中世から現在に至るまでの魔術の内容がずいぶん詳細に書かれています。その中に、ワイズマンとか、ウィッチとか、ウィザードとか、日本語に訳しにくい、シャーマニズム的な呼び名が出てきます」と説明します。それを受けて、稲生氏は「それも言葉の問題ですね。ウィッチクラフトという言葉自体、日本語に翻訳できない。ただし、概念は日本でも一緒だと思うんです。ウィッチクラフトという言葉は、うまく言えないんだけど、日本でいえばさっきも言ったように、イタコとか、民間にいたおまじない屋さんのおばさん――おじさんでもいいんだけども、そういう人をイメージしてもらえば、たぶんそれで合っているんじゃないかな」と述べます。
「宗教に包含されるシャーマンの系譜――オカルティズムとキリスト教」では、井村氏が再び『宗教と魔術の衰退』を取り上げて、「中世期というのは教会が率先して魔術を使ってたわけですからね。たとえばお札を出したり……」と述べます。吉永氏が「いわゆる『免罪符』というやつですね」と言うと、井村氏は「今でいう意味のオカルトのオンパレードなんですよ。おまじないからお札からお祈りから、心霊治療まである。キリスト教を広めるために、そういう力を利用していったと書いてある。……ということは、キリスト教が興起するまでは、民衆の間にいろんな術の体系が、キリスト教が利用するもとになるものが、ぼくはやっぱりあったのだと思う。それを逆にキリスト教が、キリストあるいは教会の名において取り上げていったわけですから」と述べています。
稲生氏は、「たとえばカトリックでは『セイント』、つまり『聖人』があります。これは教会が公認するんですが、セイントというのは、ほかの文化圏に行けばシャーマンなんですよね、たぶん。カトリック教会による非常に巧みな操作だと思います。シャーマンではキリスト教の体系に組み込めないけど、キリスト教でもシャーマン的なものは発現するわけ。それをどうするのかというと、セイントにしておけば安全なんです。聖人が奇跡を行なうわけですね。そうすると、それはキリスト教の偉大さを証明するということになりますから。けれど、実際にはあれはやっぱり間違いなくシャーマンでしょうねえ(笑)。キリスト教の人は怒るかもしれないけれども」と述べます。
それを受けて、以下の会話が展開されます。
吉永 宗教学者エリアーデはシャーマンが動物の叫び声を真似するのと、聖フランシスコが小鳥と話をしたというのは、ともに楽園へのノスタルジアという人間実存の根本にある郷愁の現われだとみています。
稲生 体が宙に浮いたり、空を飛んだり、病気も治す。セイントというのは間違いなくシャーマンですよ。
吉永 聖者が空を飛んでもかまわないけど、ダグラス・ヒュームが空を飛ぶと問題になる(笑)。
稲生 そうそう。霊媒は空を飛ぶと怒られるし、田舎のおばさんが飛ぶと魔女だと言われて火あぶりにされるんです。だけど、そういうものは絶対出てくるから、完全にフタをしてしまったらキリスト教はもたない。そういう意味で、聖人というものをつくってそこに入れておけば何とか制度として機能するし、キリスト教も壊れずに、普通の民衆社会にあるものも何とか爆発しないでいける。そういう巧みな操作だと思います。
井村氏が「たんに操作だけですむ問題ではなくて、民衆自身がエクスタシーを求めている。それに応える形で、いろんなものが出てくるわけですからね」と発言すると、以下の会話が展開されます。
稲生 そう、たとえば聖母マリアの顕現とか。カトリック圏では、今でもマリアを見たという人が次々出てきてますから。マリア信仰ということでなんとかカトリックは維持してるけれど、やっぱり見る人が出てくるんです、必ず。
吉永 そうですね。カトリックの場合は、ミサとかルルドの聖水とかそういう形で魔術的なものも絡んでいる……。
稲生 近代というのはプロテスタントの出現と重なってますでしょう。これは大きいと思います。クェーカー、シェイカーといった流れはあるにせよ、プロテスタントの本流は、シャーマニックなものを極力否定する方向にいくわけで、シャーマン、セイントというのを認めない。
井村 ところが、最近また言われてきています。ぼくはそれを「ニュー・クリスチャニズム」と呼んでいるんですが、そういう奇跡を実際に起こしてみせる、みたいな流れがどんどん強まってきているんですよ。
また、以下の会話も興味深いですね。
吉永 アフリカあたりで宣教師が不況していると、シャーマン、マジシャンと魔術合戦になったり、対決したりすることもあるみたいです。
井村 そういう宗教の現場では、オカルトと呼ばれているような部分のものが現実に今も行なわれているし、キリスト教の布教過程にも濃厚に出ているわけですから、これは、そういったものをテレビで取り上げたり、ブームになるのがいい悪いというふうに紋切り型に、たんに高圧的にいってすむ問題ではないですよ。
稲生 そうですね。キリスト教は、カトリックもプロテスタントも、いわゆるオカルトについては悪魔が背後に潜んでいるといって非常に警戒しているわけです。ところがキリスト教を客観的に見たら、やっぱり同じような衝動を抱えているというか、根は一緒だと思います。そういう関係がある。
「知と熱狂のバランスシート――繰り返されるオカルト批判」では、井村氏が「オカルトの歴史というのは、それを日本と重ね合わせると、もう歴史そのものという思いがします。また人間そのもの、あるいは宗教の本質と言ってもいい。さっきも強調したけど、熱狂の状態では、その中で価値観がコロッと変わってしまうんですよ。だから、聖者が空を飛ぶというのもまともに信じられるようになる。そして、その熱狂の反対側にあるのが、知なんです。知識の知というのは、クールつまり冷ですが、宗教的なものの本質は熱狂だから、これはホット、熱なんですよね。その知と熱狂、冷と熱という二つのものが揺れ動いていて、どちらかがのし上がったり、抑圧されたり。その繰り返しみたいに思います。その両者が一体となって、一人の人間の中に顕現してくると、ヒトラーみたいなことになってくるんでしょう。その場合に、熱狂だけが悪いと言われても、しようがない面がある。いかにクールな知をもって熱狂を冷やしていくか、そのことが大切だと思います」と語っています。
第2部「真実と信念の違い」の「無神論vs.有神論のイデオロギー闘争――客観的心理とオカルト批判」では、三者の以下の会話が興味深いです。
吉永 マーティン・ガードナーの本なんかを読むと、やはり今でもオブジェクティヴ・トゥルース(客観的真理)が存在するという言い方をしています。ただ、社会学とか哲学の一派では、今やオブジェクティヴ・トゥルースという言い方はあんまりされなくなっている。客観的な真理が本当にあるのか怪しいなというのが、20世紀の学問の一つの収穫だと思うんですけれども。
稲生 そのへんが厄介ですね。そりゃもう日本の科学者の大多数は、客観的真理があるという、それ一本ですから、そういうことを言っても通用しない。怒られるだけなんです。何をたわごと言ってんだと。
井村 日本では客観的真理は、本当に錦の御旗だからね。
また、以下のような会話も展開されています。
井村 東洋のアイデアって言えば、僕の知り合いの英語学者は、英文の構造を分析する際に「陰」と「陽」の理論をもちいて、コンピュータ分析して、学会で発表したんだけど、アメリカからの留学者にひどく受けたんだって。こんな手法はあらゆる学問分野に応用できるし、行き詰まった学説や理論を切り開くメス、概念として用いることができると思うよ。
稲生 やっぱり、明治以降の近代化の代償をまだ払い終えていないってことなんでしょうね。
井村 それが端的に言えるのは、明治30年ごろから起こってきた迷信批判です。その立役者だったのが、井上圓了と森田式療法の森田正馬、そして精神科学者になった中村古峡。この三者によって強力に推進された流れの中で正面衝突したのが福来事件なんだよね。福来友吉は、迷信の領域に突っ込んだということで排除されてしまった。それ以降、何だかちょっとオカルト分野に関して変てこな空気が学界にあるわけだけど、その迷信批判みたいな形がここでまた再燃しているという感じがぼくにはあります。
さらに、念写実験をめぐる福来友吉博士の事件をめぐって、以下のような会話が展開されています。
井村 福来事件の当時の記録をいろいろ調べてみると、当時でいう理学――今でいう物理学で工学も含んでいますが――と心理学の対決という図式が基本に出てくる。
吉永 そして理系の方が勝利を収めた。すでに当時から物理学優位と、それははっきり決まっている。
稲生 だって、心理学や精神医学は心と肉体、精神と物質が交錯する生々しい現場としていろんなことが起きるわけでしょう。一方では中村古峡みたいに、そんなことは迷信だと言う人も出てくるし、他方で、福来みたいに、やっぱり現実にあるんじゃないかと考える人も出てくるわけです。ところが、理学というのは、そういう意味での現場を抱え込んでいませんからね。
吉永 明治末までには、物理学の方が優位である、学問の女王であるという、西洋から輸入した形がすでに日本でも根づいていた。でも、おもしろいことに、ハーヴァード大学そのころウィリアム・ジェイムズが同じような心霊研究をやっていて、別におとがめがなかったわけです。もちろんハーヴァードの花形教授だったということもありますが。
第3部「批判するより勉強せよ」の「封印できない2つの衝動――セックスとオカルト」では、井村氏が以下のように語るのでした。
「近代以降、とくにそうなんだけど、それ以前でもやっぱり人間の活動の中で不当に扱われてきたもののサンバーワンとナンバーツーは、セックスとオカルトだと思うんです。それはすごく思いますね。つまり、セックスも一つの衝動が根底にあるし、オカルトもやはりオカルト衝動的な、まあ中村古峡的に言うと好奇心とか神秘への憧憬みたいな(笑)。この熱狂したいという願望でくくると、その二つの不当に扱われたものがくくれると思うんです。根っこが一緒だから、そこでたとえば性とオカルトが一致したかのようなタントリズムが出てきたりね。性を通した悟りへの段階みたいなものが出てくるということです。この二つに共通するのは、絶対、封印できないということ。『きょうから性を断て』と言われたって困りますし、またオカルトが好きな人にオカルト封印というのはなかなか難しいでしょう。そうかといって、それがあんまり表の世界にバンバン出てきちゃうと、ちょっと変てこなことになってくるんですよ」
鼎談2「『異端』と『正統』の思考」の「血の呪縛からの解放――メスメリズムの流れ」では、井村氏が「西欧文化は『血』をすごく重視するでしょ。血は聖なるものであり、また同時に非常に恐ろしいものだと。ルネサンス期には、血を『生命の汁』と呼んでいた。そしてそれは、キリスト教信仰によって補強され、一体となってキリスト教科学として発展したわけです。その『血』の思想を打ち破ったのがメスメルですね。彼は血を重視せず、宇宙に偏在している「動物磁気」というエネルギーの存在を提唱した。今はやりの『気』みたいなものだよね。それに賛同したのがH・P・ブラヴァツキー。どんどんメスメリズムを取り込んで進化させた。その進化したメスメリズムがアメリカに投げ込まれて、いろんな新しい宗教が生まれた」と語っています。
このアメリカで生まれたいろんな新宗教は、気のエネルギーと想念のエネルギーを同一視しています。それはコンタクティーの代表的存在として知られるジョージ・アダムスキーの考えに似ていると、井村氏は指摘します。井村氏が「アダムスキーの説は、たとえばクリスチャン・サイエンスに代表されるような部分と似通っているように思う」と発言すれば、UFO問題に詳しい稲生は、「そうですね。アダムスキー自身、戦前は東洋系のオカルティズムで食っていて、セオソフィスト(神智学信奉者)に近かった。さらに彼の友人で、コンタクティーのウィリアムスンという人物はもっとセオソフィスト寄りですから、彼あたりを介しても、そういう思想の影響を受けていたと思います」と語ります。すると、井村氏は「だからアダムスキーの場合は、セオソフィストのいろんな――たとえば『七つの人類説』――部分をそっくり宇宙にゆだねたんじゃないかと思うんだよね。だから、非常にわかりやすい。いわゆる信念の魔術的なものとか、愛とか、非常にわかりやすい部分をアダムスキーは含んでるから、今でも人気あるんだと思う」と述べるのでした。
井村宏次氏による「人類を呪縛してきたオカルト衝動」の「日本と西洋で異なるオカルトの意味」では、「オカルト」という言葉が広く用いられるようになったのはそう古いことではなく、本来は隠された(古代の)知恵を指していたのであると指摘しています。すなわち、この奥秘に接近し得た者だけが窮極の真理を手中にすることができるというのです。しかし、20世紀以降には、そこに英国を主としたスピリチュアリズムやヨガ、チベット密教などのペイガニズム(異教)も含められるようになりました。日本においては、コリン・ウィルソンの大著『オカルト』(中村保男訳、新潮社、1973年)が出版されて以来、この言葉が広く知られるようになりました。ウィルソンは同著において、オカルトを“人類が追求してきた謎のパワー「X」”の追求史としてとらえています。
オカルトという言葉の意味に対する東西の相違は、すなわち文化と尺度の異なりを表明しているのだと指摘し、井村氏は「西洋における“公認”の宗教はキリスト教のみであり、他のすべては異教にしかすぎない。それなら西洋人の全員がキリスト教を信奉すればよいと思うが、歴史がふすように教会は異教徒とオカルトに手を焼いてきたのだ――異教徒とオカルティストに対して教会は拷問と死刑をもって対処してきたにもかかわらず、オカルトという異物をとり除けなかったのである。つまり、正統キリスト教の伝統と教義こそがオカルトを判別する尺度であったのだ。後でみるように西洋において、科学が進歩したからオカルトが衰微したのではない。それどころか科学全盛のこのご時世に、オカルトの花は過去の諸世紀にも増して毒々しく咲き乱れているのである」と述べています。
「“真実の光”を求める者たち」では、1994年当時、“古代のオカルティスト”と規定されている人々は、見える世界と見えない世界をとり結ぶ原理を発見すべく努力を傾けてきたといいます。メソポタミアの呪術と占星術、ペルシアのゾロアスター教、ヘブライの古代宗教、ギリシアとローマの錬金術と宗教などは後世のオカルティストたちの聖典となったのでした。井村氏は、「メソポタミア起源の占星術は現代にも生き、楔形文字は長い間、その意味が不明であるという理由(!)から長期にわたって護符として用いられたのだ。また、[開祖の]ゾロアスターは錯綜した古代宗教を整理し新しい枠組みを提出した。彼は古代宗教のいう善と悪の精霊の世界にとどまらず、その本源に到達したのだ。つまり、光の王(アフラ=マズダ)と闇の王子アーリマン(アングラ=マイニュ)をヒエラルキーの頂点におく彼の“予言”は、その後、キリスト教、グノーシスやイスラム教の中にさえその影を落としているのである。今日、キリスト教とイスラム教がよく似ているといわれるのは、両者がその体系の中にゾロアスターの教えを編み込んでいるからに他ならないのである」と述べます。
「人類を駆り立てるオカルト衝動」では、井村氏は「戦後まで、日本の精神的風土は儒教であったと考えられる。この点からヨーロッパと同じく日本もまた父権的社会であったのだ」と指摘します。そこに、明治維新による形だけの民主主義が到来し、抑圧されてきた女性たちのオカルト衝動は中山みきと出口なお(大本の教祖)の出現という形で爆発しました。井村氏は、2人が“御筆先”という心霊術的な才能を備えていたことに注目します。また、御筆先は儒教的教訓を伝えつつ新しい宗教的世界観と予言を核にしていたことも重要であるといいます。つまり、2人とその背後に存在する“勢力”は儒教的精神と父性に挑戦したのだというのです。つづく郁子と千鶴子の出現は、維新以後の社会を支配するであろう(物質)科学の進歩に対する歯止めであったのかもしれないとして、井村氏は「隠密の知[である]オカルトと理性の知である科学は対決を余儀なくされたのである」と述べるのでした。
「解かれたオカルトの封印」では、明治時代における日本のオカルト研究について言及しています。日本発の心理学雑誌「心理研究」には、こっくりさん、プランセット(心霊術で用いられる自動書記の補助具)の記事と人格転換や諸民族の優劣論の研究が同居していました。井村氏は、「当時の“心理学”は、そのそれぞれが真理につながる可能性があるかどうかはともかく、メスメリズムや催眠、心霊研究が本場西欧においてオカルトであるという根強い偏見にさらされていることを肌で感じることができなかったのである。ただひとついえることは、理学者たちが『外的宇宙』の解明に熱い思いを抱いていたのに対し、心理学者たちは人間の『内的宇宙』への探検を目指していたことである。そして当然に、両者が真に出会うことはありえなかったのである」と述べています。
井村氏によれば、日本人は本来判官びいきであるといいます。民衆の多くは理不尽な当局に憤り福来に同情しました。連日、面白おかしく書きたてる新聞。憤りから念写能力者を発見して福来を助けようとする者まで現われました(高橋宮二『千里眼問題の真相』〈人文書院、1933年〉)。福来を攻撃する山川健次郎らの理学者は勝利したものの、民衆の心をつかみそこねたのは事実でした。その証拠に、民間の催眠術師や霊術家はここぞとばかりに活動を活発化し、大正期以後すさまじい「霊術ブーム」が巻き起こったのです。すでに政府は明治初年に「市子(霊媒)禁止令」「禁厭禁止令」「修験道禁止令」を発していましたが、それらはどこ吹く風、巷には霊術の看板のもとに、東西の占いをはじめ伝統的呪術、メスメリズムと催眠を日本風にアレンジした霊術など、ありとあらゆる呪術的治療法が地下から浮かびあがってきたのでした。井村氏は、「社会制度の不備、医療技術と機会の乏しさ等の社会状況から民衆はいっせいにオカルトに走ったのである」と述べるのでした。
吉永進一氏による「オカルトという言葉の正体――未整理な『経験』に貼り付けられたラベル」の「広い領域をカバーした魔術という言葉」では、オックスフォード英語辞典(OED)を開けてみると、「オカルト」という言葉は、元々「隠された」という意味で、現在使われるような「秘密の神秘的媒介物の知識や使用を伴うと考えられている学問」などへの形容詞として[英語で]使われるようになるのは、17世紀、コルネリウス・アグリッパ(1486~1535)の『隠秘哲学』からだとあることが指摘されます。魔術、錬金術、占星術、神智学といった学問を総称して「オカルト学」と呼びますが、アグリッパはルネサンスでもっとも有名な「オカルト学」の大家でした。さらにOEDによると、「オカルティズム」という語は神智学徒A・P・シネットの『隠れた世界』(1881年)が初出とあります。この語はもともとフランス語で、「オカルト学」から「オカルティズム」を造語したのは、フランスの魔術師エリファス・レヴィ(1810~75)。おそらくシネットは神智学の創始者でオカルティズムの師であったロシア人女性ヘレナ・ブラヴァツキー(1831~91)を通じて知ったのだろうと、吉永氏は推測します。
まずルネサンス魔術は15世紀半ば、マルシリオ・フィチーノがヘルメス文献と呼ばれる古代の魔術文献を翻訳したことに始まるといいます。アグリッパも彼の流れを汲む1人で、その世界観をかいつまんでいうと、万物には人間の目には見えない隠れた力があって、宇宙にはこの隠れた力を伝える媒体が存在しているというものでした。「私たちの魂の力が精気によって肉体に伝えられるのと同様、世界の魂の力は第五元素によってあらゆる物に伝えられる」のですが、「この精気の力を借りて、隠れた性質は太陽、月、惑星さらにはその上の恒星を通じて、草や石や金属や動物に伝えられる」(アグリッパ『自然魔術の哲学』)。万物は見えない媒体を通じて天体の影響力を受けたり相互に影響しあっているが、儀礼によってそうした惑星の神的存在(ダイモンと呼ばれた)へ働きかけ、その力を人間の自由にすることも可能であるとされました。これが儀礼魔術です。
「出揃ったオカルトの要素」では、19世紀半ばについて述べられます。プロテスタントが生まれ、自然科学が勃興。18世紀には理神論という合理的なキリスト教義が生まれ、イギリスではカソリックは「迷信」とさえ呼ばれるようになりましたし、自然科学の教義を守るために「合理主義」というイデオロギーが誕生していました。19世紀に入って科学技術はさらに進展しキリスト教的宇宙観は消えかけ、ダーウィンにとどめを刺されるばかりになっていました。しかも「大衆」が出現しつつあったのです。その意味で「オカルティズム」という語を作ったエリファス・レヴィが、神学生くずれの社会主義運動家だったというのは面白いと指摘する吉永氏は、「彼の功績の1つは、降霊魔術、占星術、カバラ、人相学、錬金術、魔術書、メスメリズム、ウィッチクラフト、タロットなどなど、ある意味ではエリートの学問だった『オカルト学』の範囲をさらに雑多で卑俗な現象へと広げたこと、そしてもう1つは、魔術の伝統を再発見し近代的な装いで蘇らせたことだろう」と述べています。
ただしレヴィが発明した「オカルティズム」という言葉を一般に広めたのは、ブラヴァツキー夫人でした。彼女は伝統的な西洋オカルティズムに東洋神秘主義を取り入れて、神智学という独自の教義を打ち立てました。吉永氏は、「彼女のインド理解はどうであれ、西欧人にインドの精神的価値に目を開かせた功績は大きい。その彼女の定義では、『オカルト学』と『オカルティズム』は別物とされ、前者は、魔術や錬金術など隠れた自然の力を使う術のことであり、それに対し後者は神智学の別名で、神の叡知を得るために利己的欲望を断つことだという(ブラヴァツキー「オカルティズム対オカルト術」)。魔術的現象(その存在は肯定されている)を越えたところにある、より深い神秘主義的な境地こそが本当のオカルティズムというわけだが、もちろんこの定義は普及しなかった。なぜなら、みんな現象が好きだからであり、オカルティズムという言葉と神秘主義の差異をどこかで感じたからに違いない」と述べます。
もっと広範囲の大衆がオカルト的なものを手にしたのは、スピリチュアリズム運動でした。何しろ、修行も資格も必要なし、霊媒とテーブルさえあればどこでも「現象」が起こるのです。霊媒の現象はどんどんエスカレートし、マスコミがあおりたて、科学的に奇蹟が実証できたとスピリチュアリストは主張し、手品師や科学者は霊媒のインチキを暴きたてました。社会風俗の点では、この文章が書かれた1994年当時とまったく同じ構図でした。吉永氏は、「意志の力という教理からすれば当然だが、レヴィはスピリチュアリズムを徹底的に嫌って、有名な霊媒D・D・ヒュームを『自分でも訳のからない恐ろしい力におもちゃにされているだけだ』と酷評している。最初はスピリチュアリストだったブラヴァツキーも、神智学協会設立後はスピリチュアリズム非難に回っている。そうした違いはあれ、いずれにも共通する点がある。それは『科学』(神智学は「真理」)を謳っている点である」と述べています。さらに吉永氏は、「魔術の伝統と復興、心霊現象、大衆運動、『科学』信仰、東洋憧憬。結局、現代の『オカルト』の要素は、すべて19世紀に出揃ったということだろう。それをいつ『オカルト』と総称するようになったのか、またなぜなのかはよく分からない。おそらく『心霊』より曖昧で何でも取り込める便利な言葉だったからだろう」と述べるのでした。
稲生平太郎氏の「天に光、地に妖精――UFO体験をめぐって」の「UFO体験の存在を出発点に」では、1947年のケネス・アーノルドの空飛ぶ円盤目撃事件以降に限ってみても、世界中で夥しい数の人々がUFO、空を舞う正体不明の「何か」を目撃したと主張していることが指摘されます。こういった人々の体験を、真剣な円盤研究のパイオニア、アレン・ハイネックにならってUFO体験と呼ぶ稲生氏は、「UFOや円盤なるもの自体の存在については肯定でも否定でも勝手にしていただいたらよいが、でも、UFO体験が存在することだけは、よほど強硬な改訂論者でもないかぎり、絶対に否定できないはずだ。そして、すべての論議はここから始まるべきなのだ――UFO体験はたしかにある、存在するというところから」と述べています。
稲生氏は、「『地球外起源説(ETH)』、すなわち、UFO即宇宙人の乗り物という考えは頭から追い払っていただきたい」と読者に訴えます。これは長年流布してきたから、その汚染から逃れるのはかなり困難かもしれないとしながらも、それをやっておかないと、UFO体験の本質には迫れないといいます。ETHは絶対誤りだと断言するほど僕も強心臓ではないけれど、しかし、それはあくまでひとつの仮説にすぎないのです。稲生氏は、「UFO体験と直接向き合おうとするとき、ひとつの仮説だけに囚われていては邪魔になるばかりだ。ともかく、UFOを操ってるのは宇宙人、だから皆の衆、大変だ、あるいはそんな馬鹿なことがあるか、と喧嘩してると、またもや肝腎のUFO体験はどこかにいってしまうだろう」と述べます。
「空に何かが見える」では、真に重要なのは、認識、解釈が変化したのはともかく、人間は大昔から現在にいたるまで空に何かを見続けてきたことだといいます。UFO体験は20世紀半ばにおいて発生したものではさらさらなく、おそらく人間という生き物と共に最初からあるのだとして、稲生氏は「UFO目撃体験の多くが、光体、光をめぐるものであるのは示唆的であろう。なぜなら、古今東西の宗教家やシャーマンなどの神秘体験を調べてみればすぐに分かるように、そこでは『光』を見るということが大きな役割を果たしている。光の体験が超越的世界へ通じるチャネルとして機能している。一方、目撃体験者もまた、空を飛ぶ光を見たことによって、日常世界の崩壊、変容を意識するのだ。そして、光の彼方に口を開いているのは、理解不能の世界に他ならない……」と述べています。
「人間を誘拐する妖精たち」では、妖精とUFOの結びつきを取り上げています。西欧の妖精伝承と搭乗員体験との類似については、秀れたUFO研究者ジャック・ヴァレが早くも1970年に指摘しています。著書『何かが空を飛んでいる』[新人物往来社、1992年]に詳しく書かれていますが、小人型搭乗員目撃例と、「小さい人々」とも呼ばれる妖精の過去の伝承、目撃例は驚くべき一致をみせています。別の言い方をすれば、ほぼ同一の体験が、過去においては妖精、現代においては宇宙人と解釈されているともいえます。稲生氏は、「これは空を飛ぶ何かがかつては馬車、今は宇宙船と考えられているのと軌を一にしており、僕たちはつねに文化的、歴史的文脈の制約の下でしか解読できないらしい」と述べます。
「幻想と現実の区別ではなく」では、UFO体験、それは恐怖や驚異に満ちた「実体験」として認識されていることが重要であるといいます。それが実際に現実であるか幻想であるのかという問いかけも無効かもしれないとして、稲生氏は「幻想が現実として認識、体験されるとき、それは体験の主体にとってはやはり現実の一部なのだから。そして、過去の口碑の背後に存在するのも同様な体験であるのかもしれない」と述べます。そして、「パラレルな事象――性的虐待」では、稲生氏としては、誘拐事例と幼児虐待はその深層において通底しているのを疑わないことを告白し、「誘拐事例が完全な幻想だとしても、それは僕たちの生の暗部で起こりつつある何かを反映しているのだろう。その意味において、UFO体験とは、僕たちの生の闇の部分、抑圧された不安や恐怖が噴出する場なのであり、まさに『隠れたもの』なのだ。UFO体験の裡に顕現する錯乱した世界とは、じつは僕たち人間という存在の本質を逆に照射し、現実とは何かについて根源的な問いを投げかけるものでもある。光体が空を乱舞し、小人たちが跳梁する奇怪な世界、それを一笑に付すのはとてもたやすい。でも、繰り返しいっておきたい――UFO体験は僕たちを襲うのをやめはしないだろうと」と述べるのでした。
「解説」では、稲生平太郎氏の本名である横山茂雄氏が「わたしは1974年、吉永は76年、共に大学生の頃に井村と初めて出会い、二人とも大きな影響を受け続けた。『オカルトがなぜ悪い!』の刊行時には井村とは既に約20年に及ぶ交流を結んでいたことになる。わたしと吉永は70年代末頃から近代西欧におけるオカルティズムに強い関心を抱くようになり、『ピラミッドの友』という同人誌に論考や翻訳を発表しはじめた。そして、1986年には、両者の共同編集で論集『オカルト・ムーブメント――近代隠秘学運動史』(近代ピラミッド協会編、創林社)を刊行するにいたった。その後、わたしの場合は、近代オカルティズムとナチ人種論の関係を扱った『聖別された肉体』(横山茂雄名義、書肆風の薔薇)、UFO論『何かが空を飛んでいる』(稲生平太郎名義、新人物往来社)をそれぞれ1990年、92年に上梓する」と書いています。すでに井村氏も吉永氏もこの世にはいませんが、長年の畏友であった横山氏による本書の出版が2人にとって何よりの供養となったことでしょう。