- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2025.10.21
『生きがい』茂木健一郎著、恩蔵絢子訳(新潮文庫)を読みました。「世界が驚く日本人の幸せの秘訣」とのサブタイトルがあります。もともと、2018年に『IKIGAI 日本人だけの長く幸福な人生を送る秘訣』として新潮社から刊行された単行本ですが、文庫化にあたって改題されました。著者は、1962(昭和37)年、東京生れ。脳科学者/理学博士。ソニーコンピュータサイエンス研究所シニアリサーチャー。東京大学理学部、法学部卒業後、同大大学院物理学専攻課程を修了。理化学研究所、英ケンブリッジ大学を経て現職。クオリア(意識のなかで立ち上がる、数量化できない微妙な質感)をキーワードとして、脳と心の関係を探求し続けています。主な著書に『脳と仮想』(小林秀雄賞受賞)、『今、ここからすべての場所へ』(桑原武夫賞受賞)など。
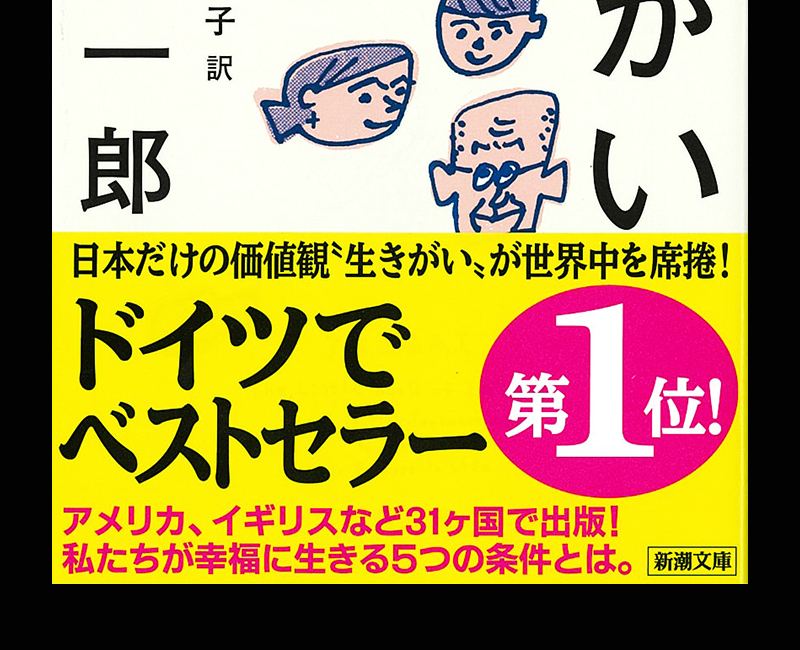 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、「日本だけの価値観〝生きがい〟が世界中を席捲!」「ドイツでベストセラー第1位!」「アメリカ、イギリスなど31ヶ国で出版! 私たちが幸福に生きる5つの条件とは。」と書かれています。
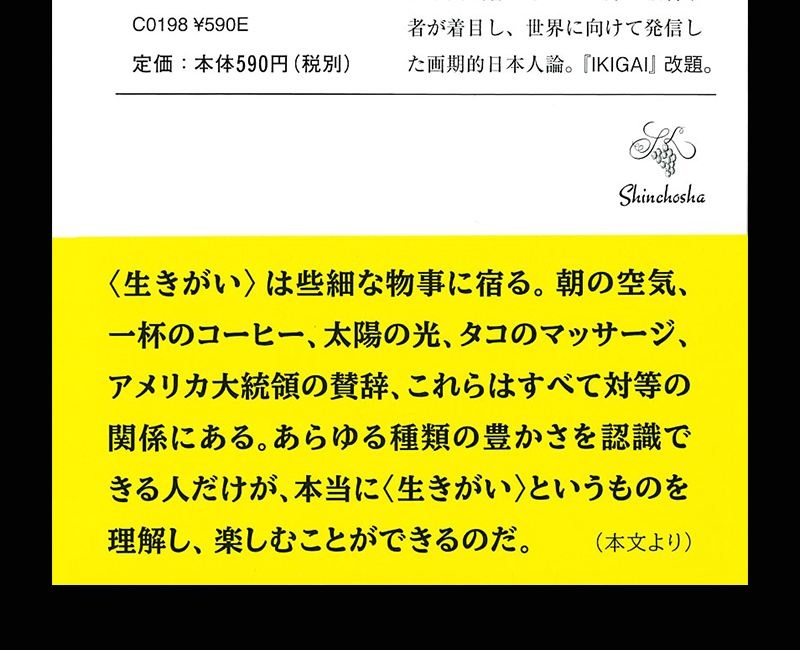 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、「〈生きがい〉は些細な物事に宿る。朝の空気、一杯のコーヒー、太陽の光、タコのマッサージ、アメリカ大統領の賛辞、これらはすべて対等の関係にある。あらゆる種類の豊かさを認識できる人だけが、本当に〈生きがい〉というものを理解し、楽しむことができるのだ。(本文より)」
本書のカバー裏には、以下の内容紹介があります。
「飾らず、おごらず、欲を持たず、控え目さと調和を愛し、今ここにいるという小さな喜びを大切にする――。日本人が古来より守ってきた素朴な価値観が、世界で注目を集めている。96歳で現役をつらぬく寿司職人、毎日午前2時に目覚めて仕事を始めるマグロの仲買人、下位のまま現役を続ける力士――。寡黙な実践者たちの生き方に脳科学者が着目し、世界に向けて発信した画期的日本人論。『IKIGAI』改題」
本書の「目次」は、以下の通りです。
読者への覚え書き “生きがい”の五本柱
第一章 “生きがい”とは何か
第二章 朝、目を覚ます理由
第三章 “こだわり”と小さく考えることがもたらすもの
第四章 “生きがい”の感覚的美しさ
第五章 フローと創造性
第六章 “生きがい”と持続可能性
第七章 人生の目的を見つける
第八章 あなたを殺さぬものがあなたを強くする
第九章 “生きがい”と幸福
第十章 あなたがあなたであるために、あなた自身を受け入れる
結論 自分自身の“生きがい”を見つける
「日本語版への序文」を、著者は「自分自身のことは、案外わからないものである。『他人』という『鏡』に映してみなければならない。今回、英語で本を書き、出版するという経験を通して、改めてそのことを痛感した。この本を書くことを通して、日本人にとっての〈生きがい〉、そして私自身にとっての〈生きがい〉について、改めて考えさせられたのである」と書きだしています。
英語で本を書くのは、著者にとって長年の課題であったといいます。2017年9月、本はロンドンで出版されました。反響は大きく、米国でも出版され、これまでに31カ国、28言語での出版が決まっています。著者は、「日本に住んでいると、なかなか、日本の本質がわからない。外からの眼で見た方が、かえって日本の本質がわかる。日本を知るためには、一度、日本を離れなければならない。英語で本を書くのは、その1つの方法だったのだろう。寿司、大相撲、雅楽、伊勢神宮。コミケ、アニメ、ラジオ体操。日本のさまざまがつまったこの〈生きがい〉の本が、読者のみなさんにとっても生きる上で最高の『気づき』のきっかけになることを願っています」と述べるのでした。
読者への覚え書き「“生きがい”の五本柱」では、〈生きがい〉には大事な5本柱があるとして、以下のように紹介されています。
柱1:小さく始める
Starting small
柱2:自分を解放する
Releasing yourself
柱3:持続可能にするために調和する
Harmony and sustainability
柱4:小さな喜びを持つ
The joy of little things
柱5:〈今ここ〉にいる
Being in the here and now
第一章「“生きがい”とは何か」では、2014年春にバラク・オバマ米大統領(当時)が日本を公式訪問したとき、世界で最も有名で素晴らしい寿司屋の1つである「すきやばし次郎」が会食会場に選ばれたことが紹介されます。「すぎやばし次郎」は、ミシュラン3つ星の料理人の中で世界最高齢、現在(2025年11月)で100歳の小野二郎氏が率いる店です。オバマ大統領は、今までに食べた中で一番の寿司だったと述べたそうです。
〈生きがい 〉とは、「生きる喜び」、「人生の意味」を指す日本語であることが示されます。この言葉は確かに「生きる」と、「値うち」を指す「甲斐」から成っています。日本語では、〈生きがい〉は様々な文脈で使われています。大きな目的や業績だけでなく、日々の小さなことにも用いられます。著者は、「日常生活の中で極めてさりげなく、特別な意味を持っていることなどまったく意識せず人々が使うような、当たり前の言葉なのである」と言います。
著者によれば、最も重要なのは、〈生きがい〉は、あなたが自分の専門領域で必ずしも成功をおさめていなくても、使うことのできる言葉であることです。この意味で、これは、生き方の多様性を賛美している、とても民主的な概念なのです。〈生きがい〉を持つことで、成功につながることがあるのは事実ですが、成功は、〈生きがい〉を持つための必要条件ではありません。〈生きがい〉はどんな人にも開かれているのです。
〈生きがい〉は、世界的な認知だとか賞賛だとかの領域に限られません。著者は、「おそらく小野は微笑みを浮かべて待っている客にどう一番良いマグロを出すかに、シンプルに〈生きがい〉を見出しているのだろう。また、市場に魚を買いつけに行こうと早起きして外に出た、その早朝の空気の心地よい冷たさにも、彼は〈生きがい〉を感じていることだろう。小野は、毎日のはじまりに啜る一杯のコーヒーに、あるいは、東京の真ん中にある彼の店まで歩いていくときに浴びる木漏れ日に、〈生きがい〉を感じているかもしれない」と述べます。
著者は、以下のように述べています。
「〈生きがい〉を持っていることは、幸せで活動的な人生を築くことができると感じる精神状態にあることを指す、とは言えそうだ。〈生きがい〉は、ある意味で、その人の人生への展望の明るさを示すバロメーターなのだ。さらに、〈生きがい〉が『ある』と答えた人たちの死亡率は、『ない』と答えた人たちの死亡率よりも、統計的有意に低かった。死亡率が低かったのは、循環器系の病気に罹るリスクが、この人たちの方が低かったためだ。面白いことに、〈生きがい〉が『ある』と答えた人たちと、『ない』と答えた人たちとの間で、がんの罹るリスクについては、有意差はなかった」
なぜ〈生きがい〉を持つ人々の方が、循環器系の病気を患うリスクが低かったのでしょうか? 良い健康状態を維持するには、さまざまな要素が絡んでいます。決定的にどの要素が重要なのかを明確にするのは難しいですが、循環器系の病気の罹患率の低下は、〈生きがい〉を持つ人々の方がよく運動をしていることを示しているのだろうと推測し、著者は「なぜなら、よく体を動かすことで、循環器系の病気が減る、という事実があるからだ。確かに、大崎での研究は、〈生きがい〉が『ある』と答えた人は、『ない』と答えた人よりも運動をよくしていることを明らかにしていた」と述べています。
〈生きがい〉は、日本文化の中に昔からありました。それは、わたしたちの中に深く根づいた概念なので、それが何をもたらすかをはっきりとさせるため、著者は、現代の行動様式との関連性を探りつつ、日本文化の伝統を深く掘り下げていくことになります。〈生きがい〉は、認知と行動の中心だと思っているという著者は、「〈生きがい〉の周りで、さまざまな生活習慣や価値体系が組織されているのである。日本人が毎日の生活の中で、必ずしも意味を正確に知らないままに〈生きがい〉という言葉を使ってきたという事実こそ、〈生きがい〉の重要性を示している」と述べます。〈生きがい〉は、島国という緊密な社会の中で何百年という時間をかけて進化してきた日本人の生活の知恵や、独特の感受性、日本社会になじむ行動様式を象徴しているのです。
第二章「朝、目を覚ます理由」では、睡眠時間を十分にとれたとするならば、朝、脳はその重要な夜の仕事を完了していると述べられます。これから1日の活動を始めるにあたり、脳は、新しい情報を吸収する準備のできた元気いっぱいの状態にあります。そこで朝の挨拶をする、つまり「おはよう」と言って、人と目を合わせることは、脳の報酬系を活動させ、ホルモンの調整機能をうまく働かせ、免疫系の機能を高めることになるとわかっています。どういう因果関係があるのかは完全にわかっていませんが。著者は、「早起きの精神は、日本文化の中に深く浸透しているから、『おはよう』をいつどのように言うべきかのルールがあると聞いても、驚くに当たらない。こんなことが大真面目に考えられているのである! 脳の中のさまざまなホルモン調節は、太陽の進行に合わせてなされていることがわかっている。だから太陽に合わせて生活することには意味がある。24時間の体内時計が自然界の昼夜のサイクルに調整されているのである」と述べています。
聖徳太子は十七条憲法を作るなど、積極的に政治改革を行ったとされています。十七条憲法とは、そのまさに第1条で、「和」(調和)を重んじることを強調したことで有名なものです。中国の皇帝へ公式な手紙を送るとき、聖徳太子は「日出ずる処の天子より」という文章で始めました。これは、日本は中国の東に位置するという事実への言及です。東から太陽は昇るわけです。このイメージが強く、日本は西洋文明においても、「日の出ずる国」というイメージが今だにもたれているところがあります。著者は、「太陽は、日本ではずっと、生命とエネルギーを象徴するものとして、崇拝の対象だった。今だに元旦には、多くの人々が早起きをして(あるいは夜通し起きていて)初日の出を見る。夜富士山に登って、頂上からご来光を拝むという習慣もある。また、ビールやマッチ、新聞、生命保険、テレビ局と、多くの日本のブランドが、朝日をテーマに用いている」と述べるのでした。
第三章「〈こだわり〉と小さく考えることがもたらすもの」では、国家としての近代化以来、日本政府は外国からの観光客を呼び込もうと努力してきたことが紹介されます。明治時代(1868~1912)には、数々の西洋式ホテルが建てられ、ヨーロッパやアメリカからの観光客を迎えていました。当時の日本は、輸出産業主体の経済ではなかったので、観光客がもたらす外貨が不可欠だと考えられていました。第二次世界大戦後、経済が急速に成長してからは、電気製品や自動車の製造で外貨を稼げるようになり、訪日外国人の数は、そこまで重んじられなくなりました。著者は、「しかし、近年は再び、外国人観光客の誘致が必須になっていた。日本の産業は今、アメリカ合衆国発のインターネット経済の勢いに押され、中国、韓国、台湾といった国々との競争も迫られて、精彩を欠いている」と述べています。
外国からの観光客はしばしば、繊細なもてなしや案内、気配りの質の高さが日本の主要な魅力だと言います。ほぼ欠点なしの新幹線のオペレーションから、細部まで効率的で素早いファスト・フード・チェーンでの牛丼の提供まで、日本人が当たり前だと思っている物事が、他の国の人々を驚かせ、畏れさえ感じさせてきました。訪れる人々は、一貫して日本は清潔で整っており、すべてが上手く時間通りに動いているという感想を持つ。公衆トイレから、コンビニエンス・ストア、そして公共交通機関まで、一般に、細かすぎるほど的確に運営されていると思われています。また、日本人は、親切で面倒見が良いと賞賛されています。
なぜ日本は一貫してそんなに高い質で製品やサービスを提供できるのか、ということを考える際には、〈こだわり〉という概念を理解することが重要です。〈こだわり〉の概念は翻訳しにくいものです。英語では「Commitment(傾倒)」とか「Insistence(固執)」という言葉が当てられることがよくありまが、言葉の概念は特定の文化的文脈の中で育まれていくもので、やはりこれらの訳語は、〈こだわり〉という言葉の真髄を完璧に捉えてはいないと指摘し、著者は「〈こだわり〉は、個人が確固たる態度で守っている私的な基準である。この言葉は、必ずというわけではないが大体は、質の高さや、個人が保っているプロ意識について使われる。その人の人生を通して維持されることの多い1つの態度であり、〈生きがい〉の中心的要素を構成する。〈こだわり〉は本質的に私的なものであり、自分がやっていることへのプライドの表明である。要は、〈こだわり〉は、ものすごく小さな細部を尋常でなく気にする、その方法のことなのだ」と述べるのでした。
第四章「〈生きがい〉の感覚的美しさ」では、日本の古典文学である『枕草子』が取り上げられます。『枕草子』に表れている清少納言の方法は、現代で言えば、「マインドフルネス」の概念に近いものだといいます。マインドフルな状態になるためには、物事に対して何でも急いで判断を下そうとせずに、「今ここ」に注意を払うことが重要です。また、自己への執着はマインドフルネスを達成するためには邪魔になると考えられています。著者は、「『枕草子』が書かれた時期(完成は1002年頃)を考えてみると、この随筆の徹頭徹尾世俗的な性質は、現代の時代精神を1000年も先取りしていると言えるだろう。清少納言が生きた時代は現代だとすら言ってしまいたくなるくらいだ」と述べています。
人生の意味という点において、人生哲学に日本人が貢献していることがあるとすると、無我の精神なのかもしれません。神谷恵美子氏がその有名な著書『生きがいについて』で強調しているように、心配事のない子供には〈生きがい〉をわざわざ持ち出す必要はありません。のびのびと遊び回る子供は、ただ遊ぶことで得られる喜びこそが〈生きがい〉であって、真の仕事で、自分を社会的に定義するという重荷を背負わされていないのです。著者は、「人生を通して、子供の方法を維持できたら素晴らしいだろう。これが〈生きがい〉の2番目の柱『自分を解放する』ということなのだ」と述べます。
現代の意識の科学では、経験に伴う感覚的な質感、例えば、おいしいものを食べる時に伴うそれらのことを、「クオリア」と呼びます。この言葉は、感覚的な経験の現象学的な特性のことを指します。すなわち、赤の赤らしさ、薔薇の香り、水の冷たさなど、1つひとつの質感がすべてクオリアです。クオリアが脳の神経細胞の活動からどのように生じるのかということは、神経科学において、否、科学全体において、いまだ誰にも解かれていない最大の謎であるという著者は、「偉大な謎ほど、我々に火をつける物はない。もしもあなたがイチゴを口に入れたなら(別に「千疋屋」で売られているような高価で完璧なものでなくてかまわない)、あるクオリアのスペクトルが感じられるのであって、それによってあなたに喜びが与えられることになるわけで、つまり、食べ物の喜びは、人生の謎に等しいのだ」と述べるのでした。
第五章「フローと創造性」では、多くのアニメ映画の名作を作って来た宮崎駿氏が取り上げられます。著者は、「宮崎駿氏はアニメをフロー状態で作っている。それは彼のアニメ自体が証している。彼の仕事から発せられている最高の幸福をあなたも感じとっているだろう。こういう点では、子供ほど正直な消費者はいない。例えば、それがどれほど教育的に価値があるとあなたが思っても、子供には見ること強要することはできない。それゆえにスタジオジブリのアニメ作品を見せられた子供が、自発的に見続けて、もっともっとせがむという事実は、宮崎によって作られた映画の質がどういうものかを示す一番の証拠なのである。思うに、この人は、子供の心理を理解し尽くしている。そして、それはおそらく彼自身の内部に小さな子供が生きているからである」と述べます。フロー状態にいるというのは、「〈今ここ〉にいる」のを大切にするということです。子供は、「現在」に生きていることの価値を知っています。実際、子供は、過去や未来といった明確な観念を持っていません。子供の幸せは、「現在」の中にあります。宮崎駿氏の幸福もちょうどそんな風なのだといいます。
ある意味では、ウォルト・ディズニーも、「〈今ここ〉にいる」ことの大事さの伝道者であるといいます。彼もまた、遺した作品の質からするに、フロー状態でアニメーションを作っていました。59回アカデミー賞にノミネートされていて、名誉賞も加えれば26回オスカーを獲得しているなど、彼は大きな成功をしたわけですが、アニメーション作りという時間のかかる、恐ろしく複雑な仕事に没入したいと思うことがなければ、こうした目のくらむような高みに到達することはなかったでしょう。今日では、老いも若きも、たくさんの人々がディズニーアニメを見ながら、また、ディズニーランドの乗り物に乗りながら、フロー状態を経験しています。著者は、「ウォルト・ディズニー氏の最も偉大な遺産は、フロー状態を誰でも持続的に経験できるようにしたことなのかもしれない。彼のおかげで子供時代の魔法を永遠に失っていたかもしれない何百万という普通の人々が、フロー状態を共有できるようになったのだから」と述べます。
続いて、日本文化を代表する茶道が取り上げられます。「今ここ」に没入し、喜びを引き出し、それと同時に、最も小さな細部に対して注意を払う。これは、茶道の本質でもあります。茶道の完成者、16世紀に生きた千利休が、戦国時代にこの思想に到達していたというのは驚くべきことです。当時は、武将たちが互いに争っていて、戦に次ぐ戦、まったく終わりが見えず、おそらく毎日が非常に緊張を強いられる時代でした。千利休が設計したと伝えられる唯一現存する茶室、「待庵」はとても小さなものです。主人と数人の客が座るのもやっとというくらいの広さです。その茶室はあえてコンパクトに設計されており、そのおかげで当時の茶会の常連であった武士たちが親密に会話できるようになっていました。
「一期一会」という日本語の概念(文字通り「一生に一度しか出会えない」という意味)は、もともと茶道の伝統から来たものです。利休がこの重要な概念を創ったと考えてよいでしょう。「一期一会」は、人生の中にある、人や、物や、出来事とのどんな出会いに関しても、その時にしか存在しないことを認識せよという意味です。出会いというのははかないもの。だからこそ、真剣に扱う必要があるのです。著者は、「結局人生は、一度しか起こらないことで満ちている。人生の出会いにある一回性の認識とその喜びが、〈生きがい〉という日本語が作られた基礎であったわけで、日本人の人生哲学の中心になっているのである。あなたが人生の細部に注意を向けるようになれば、何1つとしてくり返されるものはないと気づくだろう。1つひとつの機会が特別なのだ。だからこそ日本人は、どんな日課に関しても、その細かすぎる細部を、まるで生きるか死ぬかの問題のように真剣に取り扱うのである」と述べます。
茶室の中で得られる心の豊かさは、日本語の「和」という古の概念に共鳴します。「和」は、他者の間で調和して生きながら、どうやって自分自身の〈生きがい〉の感覚を育てていくことができるのかを理解するための鍵です。604年に聖徳太子が制定した十七条憲法は、「和を以て貴しとなす(和を重んじよ)」と宣言しています。以来、「和」は日本文化の決定的特徴の1つ、そして〈生きがい〉の重要な成分の1つであり続けてきました。著者は、「聖徳太子は、この意味で〈生きがい〉の先駆者の1人である。他の人々や周りの環境と調和して暮らすことは、〈生きがい〉の本質的要素である」と述べています。
日本の皇室は歴史的に、文化を受け継ぐということを重んじてきました。科学や芸術は、皇室が愛し支える重要な分野である。音楽はその中心です。皇室に仕える音楽家は、毎年皇居で開かれる何百という儀式、祭礼のため、特別な音楽を供する役割を担っています。このような伝統的な、古い宮廷音楽と舞踊は、合わせて「雅楽」と呼ばれます。「雅楽」は1000年以上もの間、宮廷で演じられ続けてきました。著者は一度、雅楽を供する楽家に生まれた著名な雅楽師、東儀秀樹氏と会話をしたことがあります。「東儀」は奈良時代(710~784)から雅楽に関わってきた東儀家、すなわち1300年以上も続いている家の名前である。東儀は、雅楽師が演奏する機会はたくさんあると著者に言いました。
例えば、ある天皇の1200年記念ということで演奏する。著者がそういった音楽は誰が聴くのかと尋ねると、彼はあっさりと「誰も聴かない」と答えたそうです。「私たちは皇居の静けさの中、誰も聴く人がいないところで、楽器を鳴らし、歌い、踊るんです。深夜まで演奏します。そんな時には、亡くなった天皇の魂が天から降りてきて、私たちとしばらくの間過ごし、音楽を楽しまれていくような、そんな感覚がするものです」。東儀は、自分が言っていることがごく当たり前のような感じでこう語ったといいます。雅楽という伝統の中にいる音楽家にとって、聴衆が誰もいない中で演奏するというのは、何ら特別でない、いつものことのようだったのです。
第六章「〈生きがい〉と持続可能性」では、個人の自由や成功について抑制的に振る舞うこと、万事控えめで自制的であることは、実は、日本人の最もユニークで価値ある側面――「持続可能性」と密接につながっていることが示されます。個人の欲望を大々的に追求することは、社会や環境全体の持続可能性と往々にして釣り合いません。なんといっても強靭で健康な社会や環境がなければ、自分の目的を追求することはできませんし、自分の野望の達成を目指すことはできないのです。
日本人の自然との関係性を見てみると、日本人は、個人の欲望の抑制を、奥床しさや渋さ、また「足るを知る」というような1つの美の形に高めてきました。日本の観念論の中では、控えめな美「わび・さび」ということがよく言われます。滑らかで、なんら装飾のない寿司屋のカウンターの木が、その典型的な例です。風呂に使われている、香りよいヒノキの木もまた一例で、それに柚の皮を数片いれた風呂など、天国とでも言うべきものになります。そのような風呂にする理由は、清潔を保つだめだけではなくて、リラックスするためです。
また、自然の中、屋外で湯に浸かることは、極めて一般的なことで、そのような露天風呂を含む「温泉」の文化は、今や世界中の人が知るところとなってきています。都市部では、建物の内装に贅沢感を与えて、かつ快適にするために、室内に自然を取り込むことがよくあるとして、著者は「例えば、銭湯(公衆浴場)の壁に富士山が描かれているのを見たことがないだろうか?――これは日本ではとても一般的な芸術的仕かけなのである」と述べます。
日本は持続可能性の国です。この「持続可能性」は、人間と自然との関係だけでなく、社会的文脈の中でどう個人が活動するか、ということでも同じです。日本では、他者に対して適切な配慮をすることが重んじられ、自分の行為が社会全体にどんなインパクトを与えるのかということについて、注意深くなければなりません。理想的には、すべての社会的活動が持続可能であるべきです。刹那的な欲求を一時的に満たすような派手な方法ではなく、控えめだが持続的な方法で何かを追求するというのが日本の精神です。結果として、日本で何かが真剣に始められたら、それは「まさに」長い間続けられることになるのです。
日本の天皇家は、世界で最も長く続いてきた王室です。2019年5月1日に即位した今上天皇は、第126代です。多くの文化的組織もまた、数世紀に亘って引き継がれてきました。能、歌舞伎などの舞台芸術は、何世代にも亘って受け継がれてきたものですが、日本にはその他にも文化的、経済的に伝統の火を引き継いできたたくさんの古い家があります。著者は、「日本文化は、持続可能にするためのエンジンとして、〈生きがい〉を実行している組織やミーム(文化的遺伝子)であふれている。日本人が〈生きがい〉をどう見ているかを理解するためには、日本式の『持続可能性』を解剖して構造を理解する必要がある。それは、伊勢神宮を見ると、はっきりする」と述べるのでした。
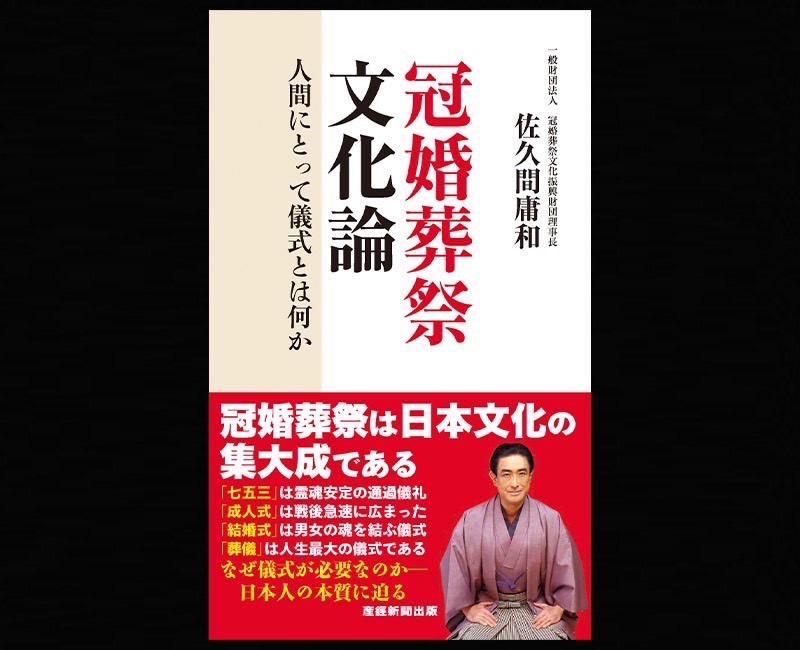 『冠婚葬祭文化論』(産経新聞出版)
『冠婚葬祭文化論』(産経新聞出版)
日本式の「持続可能性」ということを考えた場合、「冠婚葬祭」の存在が大きく浮かび上がってきます。わたしは、一般財団法人 冠婚葬祭文化振興財団の理事長を務めています。この財団は、人の一生に関わる儀礼である冠婚葬祭に代表される人生儀礼の文化を振興し、次世代に引き継いで行く事業を行い、わが国伝統文化の向上・発展に寄与することを目的としています。「冠婚葬祭文化」といいますが、冠婚葬祭は文化そのものです。日本には、茶の湯・生け花・能・歌舞伎・相撲・武道といった、さまざまな伝統文化があります。そして、それらの伝統文化の根幹にはいずれも「儀式」というものが厳然として存在します。たとえば、武道は「礼に始まり、礼に終わる」ものです。すなわち、儀式なくして文化はありえません。その意味において、儀式とは「文化の核」と言えます。そして、「冠婚葬祭」とは「日本文化の集大成」です。そして、それは本書のテーマである「生きがい」と深く関わっています。
第七章「人生の目的を見つける」では、やはり日本文化を代表する相撲が取り上げられます。持続可能性で言うと、意外にも日本では、相撲の世界に宝物のような例がたくさん隠れているといいます。相撲は、古代から続く、日本の伝統的格闘技です。プロの相撲取りが現れたのは、江戸時代の初期、17世紀です。西洋では、2人の裸の男が、おかしな髪型をして、ウエストに奇妙なベルトを巻いて、押し合いへし合いするものだというような、相撲についての(誤った)イメージが広まっています。そのイメージは、多くの場合滑稽で、(おそらく)多少は軽蔑的意味合いがあると思われますが、この古代からの運動競技にはもちろん、それ以上の深みがあるのです。そうでなければ、知的で洗練された人々が、相撲観戦に夢中になるはずがありません。まして自分が相撲取りとして、全人生を捧げることなどありえないはずです。
わたしたちが学んできたことは何か? それは、〈生きがい〉は環境への適応であるということです。その環境の性質の如何は問いません。相撲から、クラシック・バレエに至るまで、〈生きがい〉を見つける人は、勝ち負けという単純すぎる価値を超えて喜びを見出すことができます。〈生きがい〉を持つことで初めて人生の状況を最も良いものにしていくことができるのです。著者は、「あなたは、小さな物事の中に〈生きがい〉を見つける必要がある。そして小さく始めなければならない。『今ここ』にいることが必要だ。そして最も重要なことだが、〈生きがい〉がないと言って、環境を責めることはできないし、責めるべきではない。結局、あなたの道で、自分の〈生きがい〉が見つけられるかどうかは、あなた次第なのだ。この意味で、第二次世界大戦の直前に、イギリス政府が作成し、今では大変有名になっている宣伝ポスター、『平静を保ち、普段の生活を続けよ(Keep Calm and Carry On)』は、〈生きがい〉の精神を示していると言えそうだ」と述べるのでした。
第八章「あなたを殺さぬものがあなたを強くする」では、神道が取り上げられます。何をすべきか、どう生きるかということについて命じる唯一神と、八百万の神という日本人の考え方の間には、天と地ほどの違いがあります。唯一神は、何が善で何が悪かを示し、誰が天国へ行き、誰が地獄へ行くかを決定します。「八百万の神」を信じる神道では、その信仰の作用は、より民主的です。神道は、自然や環境に対して注意深く気を配る、小さな儀式からなっています。キリスト教のように、死後に焦点を当てるというよりは、神道では「今ここ」、すなわち、人間が、今あるがままの世界を作っている要素の1つとして他の物とからみあっている、その様相がより強調されるのです。著者は、「日本人は、厳格な宗教的教義の制約からは自由で、実際に現世を生き抜くためにはさまざまな要素が必要だと信じており、八百万の神という考えは、そのような哲学の一種のメタファーなのである」と述べています。
日本人は、たとえある宗教的組織への献身を示していようとも、他の宗教を排除するまで厳格になることはほとんどありません。日本人が元日に神道の神社を訪れ、クリスマスを恋人と祝い、キリスト教的スタイルで結婚式を挙げ、仏教的な葬式に出席する、というのは珍しくありません。最近では、多くの日本人にとって、クリスマス、ハロウィン、バレンタインデーというのが、外出や買い物をして楽しむ祝祭になってきています。別の言葉で言えば、日本人はこれら海外からの宗教的伝統を八百万の神の文脈の中に取り込んで同化してしまうのです。著者は、「これまで、このような『柔軟さ』は、『真の』宗教的信仰の欠如だと批判されてきた。しかしながら、現代の世界的情勢に鑑みると、異なる宗教的背景を持った人々がときに悲惨な結果を伴うまでにぶつかり合っているわけで、見かけは宗教に不真面目な日本人の考え方は賛同を得るのではなかろうか。ありとあらゆる個々の〈生きがい〉を日本式に追求していくことは、今、過激主義が幅を利かせる世界の中で、心の平和を育むことにつながるのではないだろうか」と述べます。わたしも、まったく同感です。
第九章「〈生きがい〉と幸福」では、人は、幸せになるためには必要な条件があると思い込んでいることが紹介されます。幸せになるためのその仮説では、教育や、雇用や、結婚相手や、お金など、いくつかの要素を手にしていること、あるいは、それにアクセスできるようになっていることが必要だとされます。しかし実際の科学的研究は、人間の人生の中で、幸せになるために絶対に必要な要素など、ほとんどないことを示しています。例えば、一般に信じられていることとは対照的に、たくさんのお金は、必ずしも幸せにはつながりません。確かに快適に暮らすために十分なお金を持っていることは必要ですが、それ以上持っていても、お金で幸せを買うことはできないのです。
子供を持つことも、より幸せになることに必ずしもつながりません。結婚も、社会的地位も、学問的成功も、幸せになるために必要なものだとしばしば考えられていますが、これらの要素は、実際には幸せの本質とはほとんど関係がないと示されています。ある研究者は、「フォーカシング・イリュージョン」と呼ばれる現象を調査してきました。人々は幸せに必要なものとして、人生のある物事を、実際にはそうでないのに、重要視する傾向があります。「フォーカシング・イリュージョン」という言葉は、人生のある側面に、人生の幸福が全部それにかかっていると思い込んでフォーカス(注目)してしまうことがあるという考えから来ています。
著者は、以下のように述べています。
「幸せの絶対的公式などないのだ。――各自の特殊な人生の条件が、各自の方法で、幸せの基礎となり得るのだ。結婚して子供がいたら幸せかもしれないし、結婚して子供がいなくても幸せかもしれない。独身で、大学を出ていても、出ていなくても、幸せかもしれない。痩せていて幸せかもしれないし、太っていて幸せかもしれない。カリフォルニアのような暖かい気候で暮らしていて幸せかもしれないし、モンタナという厳しい冬のあるところで暮らしていて幸せかもしれない。相撲取りとして、横綱になれたら幸せかもしれないし、ずっと雑用をやりつつ、負け続けていても、諦めず、幸せかもしれない。要は、幸せになるためには、自分自身を受け入れる必要があるのだ。自分自身を受け入れることは、わたしたちが人生で直面する中で最も重要で、難しい課題の1つである。しかし実は、自分自身を受け入れることは、あなたが自分自身のためにやれることの中では最も簡単で、単純で、有益なことである。――これこそ幸せになるための、低予算、メンテナンス不要の公式なのです」
第十章「あなたがあなたであるために、あなた自身を受け入れる」では、〈生きがい〉を「社会全体と調和する中で、個として生きること」と定義すると、競争や比較をすることで受けるストレスの大半を減らすことができるはずだといいます。著者は、「あなたは、自分の個性について、大々的にトランペットを吹き鳴らす必要はない。ただときどき自分自身にささやけばよいだけなのだ」と言います。〈生きがい〉の最も重要な秘密は、究極的には、自分自身を受け入れることにほかなりません。たとえその人がどんなに変わった特徴を持って生まれていても、です。〈生きがい〉には唯一の最適な方法などないとして、著者は「私たちの1人ひとりが、自分自身で、我々の比類なき個性の森を探求しなければならない。しかし、あなたの〈生きがい〉を探している間、良い笑いとともにあることを忘れずに。――今日も、そしていつでも!」と述べるのでした。
結論「自分自身の〈生きがい〉を見つける」では、〈生きがい〉という概念は、日本で生まれたものだと指摘されます。しかしながら、〈生きがい〉は国境を遥かに超えて深い意味を持っています。日本文化がこの点で何かしら特別だと言うのではありません。ただ日本に特有の文化的条件と伝統が〈生きがい〉という概念を育むに至っただけです。著者は、「実際、世界で話されている何千という言語の中には、〈生きがい〉に似た概念がいくつかあるかもしれない。すべての言語は結局、何世代にも亘ってその話者が生きる努力、また生かす努力をしてきた結果だという点で、平等な立場にあるのだ」と述べます。
日本を代表する文芸評論家であった小林秀雄は、可能な限り長く生きたいと言っていました。彼は自分自身の経験から、人生にもう1日あれば、また別の発見があって、もっと知恵を得られると信じていました。彼の担当編集者だった池田雅延氏によれば、小林は、人生で何が重要かを表すメタファーとして、すべてのヨットに装備されている「ユニバーサル・モーター」の話を良くしていたそうです。〈生きがい〉は小林の言うところの「ユニバーサル・モーター」であるとして、著者は「何が起ころうとも、〈生きがい〉を持っている限り、あなたは、人生の困難な時期をなんとか切り抜けていくことができる。あなたは、必ず安全な避難所へ戻ってくることができる。そこから、また人生の冒険をやり直すことができる」と述べるのでした。
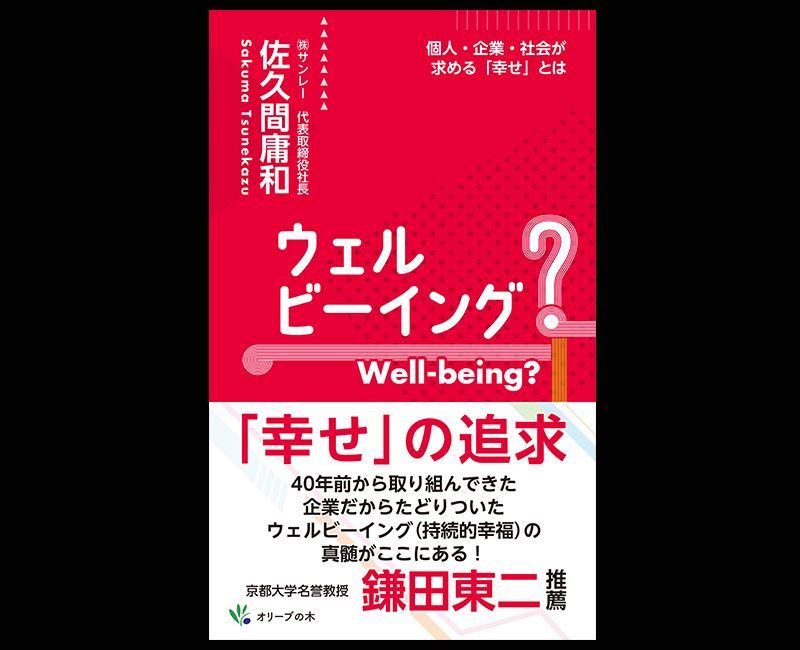 『ウェルビーイング?』(オリーブの木)
『ウェルビーイング?』(オリーブの木)
わたしは本書『生きがい』で繰り返し語られている「持続可能性」と「幸せ」という言葉から、現在流行語となっている「ウェルビーイング」を連想しました。ウェルビーイングの定義は、「健康とは、たんに病気や虚弱でないというだけでなく、身体的にも精神的にも社会的にも良好な状態」というものです。そして今までは、身体的健康のみが一人歩きしてきた――そんな印象でした。じつは、わが社は約40年前から「ウェルビーイング」を経営理念に取り入れており、わたしもは当時のサンレー社長であった父から、「ウェルビーイング」の考え方を学んできました。その実現方法についても語り合ってきました。結果、わたしの一連の著作のキーワードにもなった「ハートフル」が生まれ、わたしなりに経営および人生のコンセプトにしてきました。「ハートフル」のルーツは、まさに「ウェルビーイング」だったわけです。いま、「ウェルビーイング」は、「SDGs」の次に来る人間の本質的な幸福を目指すコンセプトしてクローズアップされています。拙著『ウェルビーイング?』(オリーブの木)では、父の先見性と想いを再確認しながら、新たなわたしなりの「ウェルビーイング」を追求してみましたが、それは限りなく本書『生きがい』の世界へと通じるものでした。最後に、わたしもいつか英語で本を書いて見たいです。
