- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2025.12.02
『誰が「お寺」を殺すのか』小川寛大著(宝島新書)を読みました。大変面白かったです。「貧困化する寺院と多様化する葬儀ビジネスの裏側」というサブタイトルがついています。著者は1979年、熊本県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。宗教業界紙『中外日報』記者を経て、2014年に宗教専門誌『宗教問題』編集委員、15年に同誌編集長に就任。わたしの大学と学部の後輩にあたるのですね。
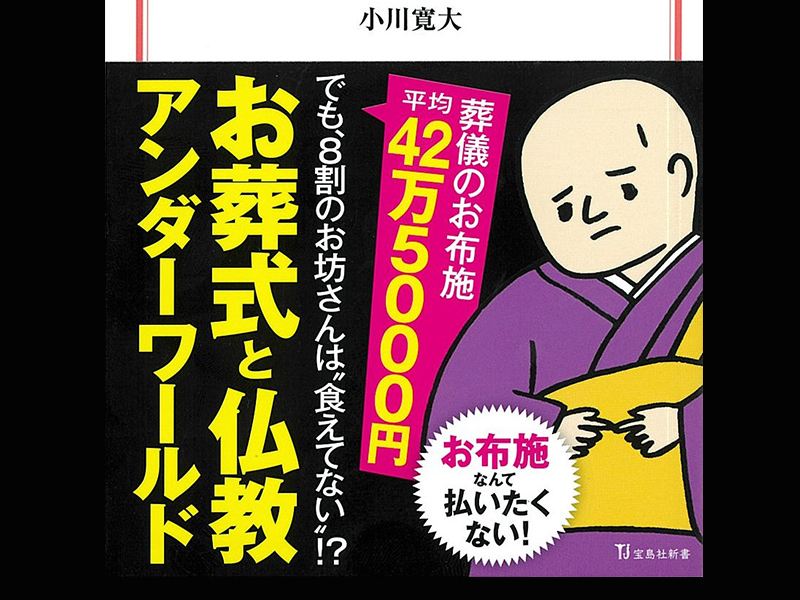 本書の帯
本書の帯
本書の帯には困っているお坊さんのイラストとともに、「葬儀のお布施 平均42万円5000円」「でも、8割のお坊さんは”“食えてない”!?」「お葬式と仏教アンダーワールド」と書かれています。また帯の裏には、空の財布を手に頭を抱えるお坊さんのイラストとともに「形骸化する『死者への弔い』と迷走する『仏教界の舞台裏!』」と書かれています。
 本書の帯の裏
本書の帯の裏
カバー裏には、以下の内容紹介があります。
「8割のお坊さんが“食えていない”―!?多死社会を迎え、葬儀の数は右肩上がりで増えていくことが予想されているが、お坊さんたちの存在感は薄くなる一方である。葬儀業者にお葬式の主導権を奪われ、葬儀の簡素化・低価格化で最大の収入源である『お布施』のデフレ化も止まらない。迷走する“お寺業界”はどこへ向かうのか―。葬儀ビジネスと仏教界の裏側を宗教専門誌編集長がレポート」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
第一章 お坊さんの家計簿
第二章 葬儀デフレ化の真
第三章 「脱・葬式仏教」論争の内幕
第四章 過熱する“葬儀ビジネス”
第五章 仏教界に未来はあるのか
「おわりに」
「はじめに」では、一般財団法人日本消費者協会が2022年にまとめたところによると、日本の葬儀の平均費用は161万9000円であったことが紹介されます。国税庁が2023年に調べた日本人の平均年収は460万円なので、この“葬儀にかかる費用”は決して安いものではありません。つまり、家族の誰かが不意に死んでしまうようなことが起こった場合、その遺族は実に年収の約3分の1を支払う必要に迫られるわけです。日本人の多くは仏教式で葬儀を行っており、その葬儀の場には僧侶が来て、お経を読み、故人に戒名を付けます。そのために僧侶へ支払われる「お布施」の平均額は42万5000円である紹介されます。
約161万円という日本における葬儀の平均費用ですが、この統計は実は2008年段階では231万円という数字でした。つまりここ10数年ほどの間で、日本の葬儀費用は3割ほど下落しているのです。「今の葬儀費用は高すぎる」という世の中の声が、実際に状況を動かした結果でしょう。また、いま日本のお寺の数は減っています。文化庁の統計によれば、1995年の時点で日本にあった仏教系宗教法人の数は7万8002でしたが、これが2005年には7万7519に、15年には7万7304に、そして24年には7万6602になっているといいます。
もともと宗教法人は、一般の営利企業ほど簡単に倒産するものではありません。しかし、「寺や神社は伝統的かつ永遠なるもので、潰れることなどはない」といった、多くの一般人がぼんやりと思っているような“常識”は、実は今、覆されつつあるのです。つまり、現在のお寺業界とは「宗教法人として、ほとんど税金も払わず楽をしている」とか、「坊主は丸もうけ」などといった世間的なイメージとは、かなり遠い苦境に置かれつつあるのです。
第一章「お坊さんの家計簿」の「僧侶は全国に何人いるのか?」では、『宗教年鑑』によると、現在の日本には「仏教系」の「教師」が34万8804人いることが紹介されます。「教師」とは各種の宗教教団組織のなかで、正規の聖職者として認められている人のことを指す、宗教業界の専門用語です。すなわち仏教界においては、「僧侶、お坊さん」と同義と考えてもらっていいとして、著者は「この『宗教年鑑』が示す仏教系の教師数もまた、新宗教関係の人々を含んだ上での数である。
著者は、おおむね今の日本には「伝統仏教のお坊さん」が30万人くらいいると考えていいだろうと述べます。2020年の国勢調査によれば、日本で「電気・ガス・熱供給・水道業」に就いている人の数は31万7856人だったといいます。また、自動車メーカーであるトヨタにおいて、そのグループ全体で働いている人の数は38万人なのだそうです。“だいたい30万人”程度いる日本の“お坊さん業界”の規模感も、ひとまずそんなところだと思ってもらっていいでしょう。
「僧侶の収入と仏教界の市場規模」では、厚生労働省が発表している賃金構造基本統計調査(2023年)の「宗教家」の項目(平均賃金額)を調べると、「きまって支給する現金給与額」、つまり月給の額として34万7400円という数字があり、また「年間賞与その他特別給与額」、つまりボーナス額として97万4500円とあります。これに基づけば、日本の「宗教家」の平均年収は34万7400円×12+97万4500円=514万3300円となります。なお、この「宗教家」のカテゴリにはお寺のお坊さんのみならず、神社の神主やキリスト教会の牧師、また新宗教団体の職員なども含まれます。
2020年以降に行われた日本の葬儀の平均費用は、161万9000円ということになっていますが、このお金がすべて寺、僧侶に渡るわけではありません。まず「葬儀費用一式」、すなわち祭壇を用意するお金や、それを飾る花代、遺影の準備代金など、つまり葬儀社に渡すお金が111万9000円となっています。そして「通夜からの飲食接待費」が12万2000円。「寺院へのお布施」が42万5000円である。つまり葬儀が一度行われるたび、寺には42万円ほどのお金が入ってくるという計算になります。
「檀家が200~300軒ほどいれば、そのお寺は“寺だけ”で何とか食っていくことができる」とされています。つまり逆を言えば、檀家が50軒とか100軒とかしかない寺は、お寺だけの収入、すなわち葬儀などの収入だけでは食べていくことができず、その住職たちは寺以外の何らかの副業をやらないと生活が成り立ちません。「年商1000万円超には檀家250軒が必要」では、1年の間に寺の抱えている檀家からは、だいたい5%ほどの葬式が出るといわれていることが紹介されます。つまり100軒の檀家を持っている寺があった場合、その檀家全体からは年間5人の死者が出る、すなわち寺としては5回、葬儀を執り行うことになるという話です。
現在の日本の寺の収入とはおおむね、葬儀を執り行うことによって得られるお布施を主要な柱とするのですが、ほかにも護持会費、つまり檀家から得られる“会費”も、サブ収入といった形で存在します。この護持会費はおおむね、墓地の管理料を兼ねている場合が多く、相場は1万~2万円程度と言われます。250軒の檀家がいる寺の護持会費収入は250万円であると考えましょう。また、寺は檀家の法事、すなわち一周忌や三回忌などの際に、法要を執り行います。この法事の際のお布施の相場は、数千円~3万円、多い場合でも5万円程度だとされています。これも250軒の檀家がいる寺の場合は、だいたい檀家1軒あたりから年間1万円ほどの法事収入があると推測し、250万円と考えてみます。
「檀家数『200軒未満』が7割超」では、日本のお寺業界は「檀家が200~300軒ほどいれば、そのお寺は“寺だけ”で何とか食っていくことができる」という認識が存在してはいるものの、曹洞宗および浄土真宗本願寺派の宗勢調査を見る限りにおいて、その“食っていける最低ライン”であるところの200軒以上の檀家を持っている寺は、全体の25%ほどしかないことが示されます。あくまで“事業”として見ると、日本のお寺とは年商で1000万円もあれば結構な存在感があり、しかも全体の7~8割は、その規模に届きません。著者は、「一般的な産業界に比べたら、相当なスモールビジネスである。しかも近年、『葬式に僧侶を呼ぶ必要はない』『そもそも葬式自体、する必要がない』といったことが声高に叫ばれ、寺の“事業環境”は相当に悪い」と述べるのでした。
第二章「葬儀デフレ化の真実」の「ベストセラー『葬式は、要らない』の衝撃」では、2010年に幻冬舎から刊行された、『葬式は、要らない』という本が取り上げられます。著者は宗教学者の島田裕巳氏。島田氏はこの本の冒頭部分でまず、日本の葬儀費用の全国平均は231万円であると示し、「これはあまりにも高すぎるのではないか」という認識のもと、僧侶を呼ばない葬儀の形式である「直葬」の紹介や、戒名無用論のような主張を展開しています。著者は、「この『葬式は、要らない』はかなり売れた本で、これまでの累計発行部数は実に30万部だという。いわゆる“超ベストセラー”だ。当然、社会的な影響も絶大だった」と述べています。島田氏は同書の中で、日本の葬儀費用の全国平均は231万円であると書いています。
「葬儀費用は下落の一途」では、日本の葬儀費用は2008年段階で231万円。そのうち寺へのお布施は54万円で23%を占めることが確認されます。これが2020年には161万円となり、寺へのお布施は42万円で全体の26%。著者は、「仮にこの減少率がこのまま続くとして計算すれば、2030年に葬儀の平均費用は102万円になり、2040年には44万円になる。寺へのお布施がその25%だと試算すれば、それは2030年には25万円、2040年には11万円にまで下落する」と推察しています。
日本の葬儀の単価が現在下がり続けている原因は、単純に日本人の可処分所得が下がっているからであると、著者は言います。高度成長期やバブル経済といった、日本経済史のなかでも特筆すべき戦後の好景気時代を終え、日本は「失われた30年」などとも呼ばれる低成長時代となりました。日本の葬儀は特にバブル期、かなり急な単価上昇局面に入っていた事実があり、ある意味では現在、それが“正常化”しているというのです。
また日本の少子高齢化、それにともなう地方の過疎化や都市への人口集中といったこと、すなわち日本人のライフスタイルがここ数10年で大きく変化していることも重要だといいます。付け加えれば、単身家庭や核家族の増加、また女性の社会進出などといった話もあります。著者は、「それらのことによって旧来の、とくに地方にある寺院を下支えしていた地域コミュニティが崩壊している現実があり、それに寺側がほとんど対応できていないのである」と述べるのでした。
「『戒名』のインフレ化」では、現在の日本において、葬儀の際に寺へ払うお布施の中の少なくない割合は、「お坊さんに戒名を付けてもらうお金」になっていることが指摘されます。中には「戒名はお金でやり取りするものではない」などといった趣旨から、”“戒名料”という言葉の使用を非常に嫌う僧侶もいます。しかし、現実に“戒名料”としか言いようのないお金が葬儀の現場でやり取りされているのは事実です。
「“立派な戒名”が可視化された時代」では、1987年に世を去った戦後日本が生んだスター俳優・石原裕次郎の戒名は「陽光院天真寛裕大居士」というものだったことが紹介されます。“大居士”とは居士の上にあるランクの戒名で、江戸時代ならば大名などにしか付かないものでした。また、同じく戦後の大スター、歌手の美空ひばりが死去したのは1989年のことでしたが、彼女の戒名は「慈唱院美空日和清大姉」でした。これも大姉という立派な戒名です。著者は、「あえて言うが、たとえば江戸時代などにおいて石原や美空のような人物、すなわち役者などをしていた階級の人間が、居士の戒名を付けることができたかというと、そう簡単ではなかったのではないか。しかし、戦後の日本とは、石原や美空のような“実力で成り上がった人間”が、その財力で自由にふるまえる時代だったのだ」と述べています。
石原や美空の葬儀はワイドショーなどによって生中継されており、それを多くの人々が見ました。まさに彼らは死してもスターだったわけですが、そういう流れは葬儀の世界にもある変化を生んだとして、著者は「彼ら著名人の葬儀を―――テレビなどを通じてだが―――間近に見て、その“立派な戒名”などをも目にした一般市民たちも、また居士や院号などの戒名を欲するようになっていったというのだ。寺や葬儀社側も、とくに断るようなことでもなく、かくして戦後の日本人は“立派な戒名”を誰でも付けるようになった……という話が、お寺や葬儀業界の周辺ではよく言われているのである」と述べます。
「立派な戒名を付けないと、かわいそうですよ」では、日本消費者協会の「第12回『葬儀についてのアンケート調査』報告書」(2022年)の、地方別に分けたお布施額が紹介されます。それによれば、北海道では25万4000円、東北では34万2000円、関東では48万7000円、東京では57万2000円、北陸では31万6000円、東海では43万6000円、近畿では38万7000円、中国四国では43万7000円、九州では35万円で、これらを平均すると42万5000円(地域が不明な回答者の支出額なども含む計算)という数字になります。
北陸地方は浄土真宗信仰が非常に盛んな「真宗王国」とされる地ですが、お布施の額は全国平均から10万円以上安いです。近畿には大都市もありますが、京都や奈良など昔からの仏教文化が息づく地で、またその地域文化の中で、寺が果たす役割は今なお大きく、よってこの地域のお布施の額も全国平均より下です。全国で最もお布施の額が安い北海道は、歴史が浅い土地ゆえに明治時代以降、各仏教宗派がたくさんの僧侶を送り込み、熱心に布教を展開してきた場所という事実があります。それゆえ人々もお寺に対する親近感が、むしろ本州以南より強いようです。
「東京のお布施がダントツに高額な理由」では、首都圏であるところの関東では、お布施の額が平均よりかなり高めであり、東京に至っては全国平均より15万円も高くなっています。この差はどこから生まれているのかというと、実はこれは葬儀を執り行う際に、葬儀社の関与がどれくらい深くあるかで決まってくる問題なのです。そもそも「自分の実家の菩提寺の宗派がわからない」といった人は、日ごろから宗教的なことに関心の薄い生活を送ってきた可能性が高いです。僧侶サイドからしてみれば、そういう人が執り行う葬儀に派遣されたところで、新たに正式な檀家になってくれるなどの長い付き合いになるかどうかも不明です。
つまり、寺との関係が薄く、葬儀社任せになるわけです。「プロをスポットで呼ぶという話になるわけだから、派遣サービスで行く葬儀のお布施に関しては、高めのものを求めざるを得ない」といったことを、率直に語る僧侶も存在するそうです。だから、都市部でのお布施額は高くなってしまうのです。そして都市住民とは現在の日本のなかでは多数派であり、また日本経済はかつてほど勢いがあるわけでもありません。ここから「葬儀にかかるお金が高すぎる」という不満が噴出し、葬儀・戒名不要論のような話が人気を博す土壌が形成されているわけです。
「葬式は地域が担う時代から葬儀社の時代へ」では、かつて、地域共同体というものがしっかりしていた時代にあっては、葬儀とは“葬儀社が仕切るもの”ではなかったことが指摘されます。村の中のどこかの家から死者が出れば、村人みんなでその家に駆けつけ、遺族を励まして葬儀の準備、雑務を手伝い、会葬者にふるまう料理なども村人たちで作りました。著者は、「それこそ戦前や江戸時代などであれば、村人たちで棺桶を担いで、遺体の焼き場や土葬墓地まで運んでいったのだ。そういう“村の仕事”が葬儀だったのであり、またそのような地域コミュニティの核には大抵、寺や神社などがあったのである」と述べています。
しかし、今の日本でそうした“コミュニティとして出す葬儀”を行えるような地域は、ほとんど滅んでいると言って過言ではありません。地方の町や村は少子高齢化や過疎化で活力を失い、一方の都市部では単身家庭や核家族が増えて、「隣に住んでいるのは誰かもわからない」といった生活をしている人も、まったく珍しくありません。著者は、「葬儀屋とは、たとえば棺桶を売る『葬具屋』などと呼ばれた商人として、江戸時代以前から存在した仕事ではある。しかし戦後になって、そういう“葬儀を担える地域コミュニティの消失”とともに、急速に“葬祭プロデュース業”へ変身しながら現在に至っている」と述べます。
1980年代あたりから急速に広がったのが、葬儀社が葬儀会館(ホール)を建て、そこで効率的に葬儀の執行を“回していく”というスタイルでした。霊柩車で火葬場まで棺桶を運んでくれるのも葬儀社の仕事で、さらには役所への死亡届の提出まで、葬儀社が代行してくれる。今、身内に死者が出ても葬儀社に任せておけば、遺族はほとんど何もしなくていいということもある。しかし、葬儀社に葬儀を依頼するとお金がかかります。161万9000円という葬儀費用の内訳として最大を占めるのが「葬儀一式の費用」、すなわち葬儀社に支払う代金で、これが111万9000円。実に寺へのお布施(42万5000円)の倍以上の額です。しかし、これも寺へのお布施と同様低落傾向にあります。
葬儀社への支払い費用は、どういう理由で減っているのか。ズバリその答えは、葬儀の小規模化です。「6割超が『家族葬』を選択」では、葬儀の規模が小さくなることでまず収入減に直面するのは葬儀社ですが、寺の側でも、「身内しか来ない、小ぢんまりとした葬儀なのだから、故人にランクの高い戒名は付ける必要はないだろう」といった感覚の遺族は増えていくことを指摘し、著者は「これも葬儀に際してのお布施が減る原因にはなろう(少なくとも、葬儀の小規模化がお布施の額を増やすような流れは、あまり考えられない)」と述べます。「消えた『社葬』」では、今では政治家や人気芸能人の葬儀でも、まずは近親者のみの家族葬で行われることが多くなったといいます。この流れと同様に、今、日本からほとんど消えかかっているのが「社葬」です。
「葬式は『仏教式』が9割」では、“寺から離れていく檀家たち”の話を現場で聞いてみると、何か“宗教への敵意、無関心”のような感情で動いている例は、意外なほど少ないといいます。単純に、寺にお布施を出す余裕がないこと、あとは体力や距離の問題が出てきて、寺と関係が持ちにくくなった、つまりは“わずらわしくなった”ことが原因だと、申し訳なさそうに語る人のほうが多いというのです。「『葬式に僧侶はいらない』は少数派」では、「日本のお寺が苦境にあえいでいるのは、日本人の信仰心がなくなっているからだ」といった話は、あまり関係ないように思うとして、著者は「バブル期に高騰したお布施の額などが落ち着き、現在の日本人の経済状況に見合ったレベルにまで葬儀費用のあり方が変われば、いわゆる“葬式不要論”や“戒名不要論”のようなものは、相当払拭されるのではないかとも考えられる」と述べるのでした。
第三章「『脱・葬式仏教』論争の内幕」の「葬儀のルーチン化」では、著者は以下のように述べています。「あえて誤解を恐れずに書くが、葬儀社にとっての葬儀とは、日々ルーチン的に回していく“舞台演劇”のようなものである。なにしろ、彼らが持つ葬祭ホールでは(とくに人口の多い都市部などの場合)1日に何件もの葬儀が執り行われる。タイムテーブルをきちんと管理しなければ回らないわけで、葬儀は葬儀社の社員などが“司会”として立って取り仕切り、いわば彼らがつくる“台本”に沿って、喪主があいさつをし、会葬者が焼香などをし、想定された時間の範囲内に終了する。そのなかにおいて僧侶とは、『葬儀社の決めたタイミングで葬儀会場に現れ、一定の時間内でお経を読んで退出していく一種の役者、道具立て』のようなものなのである」
また、著者は「従来、日本の各伝統仏教教団は葬儀を、「檀家たちに仏教徒としての思いを新たにしてもらう場」と位置付けて重視してきた流れがあり、「葬儀の場こそ布教の場である」といったことを語り、通夜の場などでの法話に力を入れる僧侶も多かった」と述べます。しかし、今その状況は大きく変わっています。「葬儀が祈りの場、布教の場でなくなった」では、著者は「人が亡くなった際、火葬場の手配から死亡届を役所に提出することまでやってくれるのが現在の葬儀社で(当然、その葬儀社の仕事のなかには「僧侶の手配」まで含まれる場合もある)、『葬儀をどうやればいいのか』に関して遺族に最も“寄り添っている”のは、今やお坊さんではなく葬儀社だ」と述べるのでした。
「“消費者不在だった改革論争」では、日本人の約8割は今なお葬儀の場に僧侶がいたほうがいいと考えているし、実際の葬儀も約9割が仏教式で執り行われていることが指摘されます。世の中の一般の人たちは、“改革派僧侶”らが思うほどには“葬式仏教”を否定的にみてはいないのだというのです。「“葬式仏教”をどうとらえ、どうしていくべきか」といった話は、21世紀に入った前後頃から仏教界およびその周辺で実にやかましく議論されてきたことでした。その中で島田裕巳氏は「寺や僧侶は社会から必要とされなくなっていく」とドライに分析し、高橋卓志氏や秋田光彦氏などの“改革派”は、そうはさせじと“脱・葬式仏教”を掲げて、寺を変えていくことを考えたわけです。
しかし、一般市民の側にそのような問題意識があまりなかったのだとしたら、それは仏教界の関係者だけが“消費者不在”のなかで盛り上がっていた、いわば独り相撲だった可能性もあるといいます。著者は、「たしかに、バブル期に高止まりしてしまった戒名料のあり方をどう変えていくかや、また地域コミュニティの衰退による寺と檀家との関係変化、またそれが生んだ“お布施の目安”の不明瞭化など、“葬式仏教”が変えていかねばならない細部の問題はいろいろとある。そういう不満が社会に鬱積しているがゆえに、島田の『葬式は、要らない』といった本がベストセラーにもなったのだろう。しかし、だからといって『“葬式仏教”そのものを解体していかねばならない』というような考え方は、世間にはあまり存在しないのではないだろうか」と述べます。
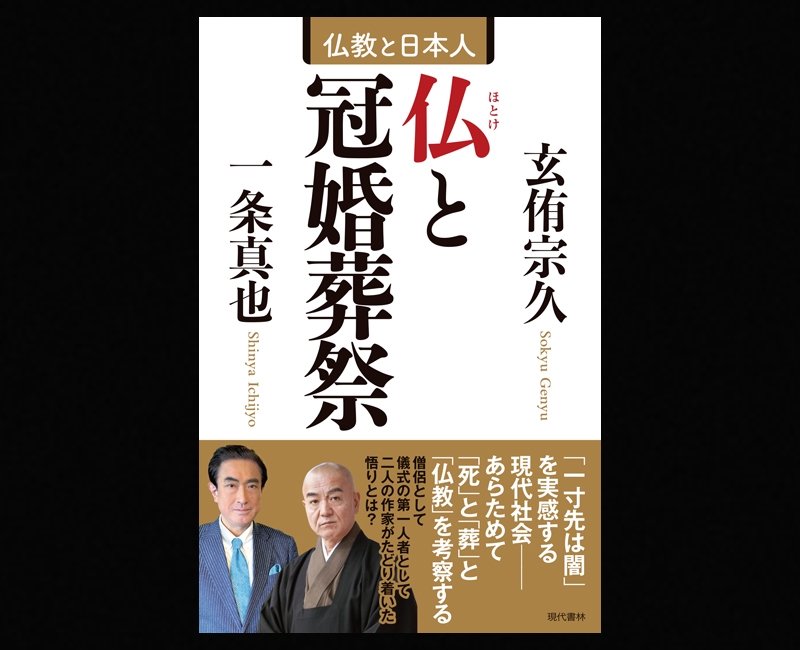 『仏と冠婚葬祭』(現代書林)
『仏と冠婚葬祭』(現代書林)
「スター僧侶の不在」では、“葬式仏教論争”以前の仏教界には、仏教界の枠を飛び越えて、世間一般のなかで“ごく普通の有名人”として認識されているような僧侶がいたことが指摘されます。たとえば奈良・薬師寺管主の高田好胤(1924~1998)や、作家の今東光(1898~1977)、瀬戸内寂聴(1922~2021)らです。瀬戸内寂聴は、“お坊さん”という肩書を外しても“一流作家”として名のあった人でした。著者は「現在は、そのようなスター僧侶がいないというのですが、わたしは異論があります。本書にも改革は僧侶の1人として紹介されている玄侑宗久氏は芥川賞作家でもあり、「スター僧侶」の名に値する方であると思います。わたしは玄侑氏と対談する機会に恵まれましたが、玄侑氏について「この方は、やはり当代一の僧侶だ!」と感心することしきりでした。対談の内容は『仏と冠婚葬祭』(現代書林)にまとめられています。
第四章「過熱する“葬儀ビジネス”」の「お布施を『定価』にしたくない理由」では、宗教法人の課税優遇特権の問題が取り上げられます。宗教法人に税金がかからないことは有名な話ですが、それはあくまで「宗教法人の行う宗教行為で得たお金」、すなわちお布施などには課税がされないという話です。たとえば宗教法人でも飲食業や物品販売など、“普通のビジネス”を行えば、その収益に関して税金はかかります。著者は、「仏教界内部には、“お布施に定価がつくこと”が普通になれば、やがて行政は『定価があるようなサービスに関するお金のやりとりは、宗教行為ではなく単なる商売である』などと言い出してくるのではないか、という危惧が古くからあって、それで“お布施の定価”に否定的であるという側面もある」と述べます。これは非常に納得できました。
お布施に“定価”がないのは実は檀家サイドのためという主張もあるそうです。少なくとも、かつてのようなしっかりとした地域コミュニティがある中では、寺と檀家は常に親しく交流していて、寺側は檀家の家庭事情にも明るかったと言えます。檀家に何かの事情があって収入が減っているようなことがあれば、寺は“お気持ち”として、むしろお布施の額を安くするということも、またあるのです。著者は、「たとえば2011年の東日本大震災の際には、津波被害などで家族を失った檀家たちを前に『お布施なんていいから』と、ほとんど無償で葬儀を行っていた僧侶の存在もあった。筆者はある東北の僧侶から、『ネット葬儀社たちは大災害が来たときも、人に“定価”を請求していくのだろうか』と皮肉っぽく言われたことがあるのだが、こういう視点は確かに大切だ」と述べます。わたしも、まったく同感です。
「都市部で急増『ビル型納骨堂』」では、世にネット葬儀社が現れ始めたのと軌を一にして、21世紀に入った前後から、東京や大阪などの都心部で、高級マンションのような外観を持った巨大な納骨堂がニョキニョキと林立し始めたことが紹介されます。著者は、「そこに一歩入ると、まるで高級ホテルのロビーのような空間が広がり、遺骨は特別の礼拝スペースに遺族が訪れたときのみ、コンピューター制御で奥の安置室からベルトコンベアなどに乗って現れる。屋内なので雨のときにも気楽に墓参ができ、駅から至近のものほど人気は高い。草むしりなどのケアも不要で、原則としては、業者が責任を持って遺骨を管理してくれる。言ってみれば、ネット葬儀社や僧侶派遣サービスなどの隆盛を支えた“個の時代”のニーズに、よく合致したのだろう」と述べています。
「『自然葬』人気の裏側」では、現在お寺業界を苦境に追い込んでいるのは外部事業者たちだけでないことが指摘されます。キーワードは「自然葬」の流行であるといいます。たとえば、従来型の墓石の代わりに墓地に木の苗を植える「樹木葬」や、遺骨を海にまく「海洋散骨」などの人気が、かつてなく高まっている事実があるといいます。そして、そのプレイヤーとして目立つのは神社だとして、著者は「福岡県にある和布刈神社は、海洋散骨を非常に熱心に行っている神社として著名な存在だ。その取り組みを紹介したウェブサイト『マネーポストWEB』の2024年8月31日付記事によると、同神社が海洋散骨を始めたのは2014年のこと。以来、3000件の実績を上げ、それまで500万円ほどだった神社としての年間収入は1億4000万円に迫るという」と述べています。
「神葬祭の魅力とは?」では、和布刈神社はたしかに歴史的な格のある神社ですが、もともとの年間収入は500万円程度だったといいます。同じく神葬祭で注目されている常陸国出雲大社は1992年に建てられたばかりの神社であす。双方とも、「昔から大きな財政基盤を抱えてきた、神社界の上流階級」などではありません。つまり今、神社とは日本の宗教界において、「葬儀を手がけることによって急成長できるポテンシャルを持った存在」になってきているわけです。これはなぜか。まず神葬祭は仏教式の葬儀に比べて、明らかに安いという事実があります。加えて、海洋散骨や樹木葬といった「自然葬」を神社が執り行っていることが重要で、それらの自然葬は寺よりも自然崇拝のアニミズム宗教である神社の方がふさわしく、何といっても説得力があります。そして、この自然葬の値段が安いことが注目されている最大の要因でしょう。
第五章「仏教界に未来はあるのか」の「徳川幕府期に成立した『檀家制度』」では、この令和、21世紀の現代になってなお日本のお寺を支えている檀家制度は江戸時代の初期、すなわち400年以上も前に幕府によってつくられたかなり“政治的な仕組み”であることが指摘されます。「僧侶の『妻帯』が公認」では、寺には「過去帳」という、檀家たちがどういう家庭環境にあって、いつ死んで、どういう戒名を付けたかといった記録があるわけですが、江戸時代においてこれは事実上の戸籍簿、住民票のような扱いを受けていたことが紹介されます。当然、それを管理するのもお坊さんの仕事でした。
「過去帳」の例からもわかるように、江戸時代における僧侶とは一種の行政官の立場を与えられていたのです。しかし、そういう公的な立場であったからこそ、江戸時代の僧侶たちは権力の側から一定の統制も受けました。幕府や諸藩には、「寺社奉行」という寺や神社を統制する裁判所のような機関が置かれていて、仏教の教えに反した行動をとっているとみなされた僧侶はこの寺社奉行によって処罰されることがありました。すなわち、僧侶なのに肉を食べていたり、女性と性的関係を持っていたりといった、仏教の戒律に違反した僧侶を捕える権限をこの寺社奉行は持っていたわけです。
「『格差』が固定化された世界」では、釈迦が定めた仏教の戒律は明確に、出家者たるお坊さんたちに異性との交遊を禁止していることが指摘されます。つまり、日本の僧侶の多くが結婚して家庭を持っている現状は、仏教の教義から見て何かがおかしく、それをいろいろと批判する声は実にさまざまなところから上がっています。しかし著者は、「この日本の僧侶が妻帯していることの一番の問題は、『お坊さんが結婚しているのは戒律違反だ』といった教義上の話よりも、それによって寺の世襲が当然のことになってしまい、仏教界の格差、階級構造が固定化してしまっていることにある」と述べています。
 『葬式に迷う日本人』(三五館)
『葬式に迷う日本人』(三五館)
「檀家制度を廃止し9000万円の売り上げ」では、現代の日本人が葬儀について思っている感情とは「“葬式仏教”のあり方に、何か注文があるわけではない。しかし、葬儀にかかるお金は、なるだけ明瞭かつ安価にしてほしい」ということだと、著者は喝破します。この“ニーズ”を汲み取ることができれば、仏教界全体の権力構造云々といった話はまた横において、少なくとも個別の寺単位で生き残っていく道は模索できるといいます。「『葬式仏教』の歴史は短い」では、“寺領”を持っていない状態で、“檀家制度”を維持したまま“世襲”によって各寺院が運営されているという今の日本の仏教界のあり方について、著者は「日本の歴史全体を眺めてみても、本当に太平洋戦争に敗れてから、ここ80年くらいの間にしか存在していない状態なのである」と述べています。
「まずは運営実態の情報公開から」では、歴史的にお寺の運営のあり方は、いろいろな形で揺れ動いてきたことが指摘されます。江戸時代には徳川幕府の意向によって、檀家制度というものを抱えることになりました。明治維新によって寺は世襲化し、太平洋戦争の敗北で寺領という経済基盤を失いました。そして、戦後の経済成長に影響される形で、葬儀の現場では多額の現金が飛び交うようになりましたが、バブル崩壊以降はそういう形が維持できなくなったとして、著者は「今ではネット葬儀社などの“外部事業者”に、葬儀や墓、納骨堂のあり方をどうするかといった“主導権”を奪われつつあり、軌を一にして進行する過疎化や少子高齢化の前に、その将来が大変不安視もされている」と述べています。
ただ、この流れを見てもわかるように、お寺側は常に“受け身”なのだといいます。これらのあり方の変遷は、決してお寺の側から仕かけていったことではないのです。著者は「現在、日本の寺の多くは経営的にかなり苦しいところに追い込まれつつある。直接的な原因は、ほとんどの寺がその収入源としている葬儀のお布施収入が下落の一途をたどっていることにある。そして、その理由のより根元的な部分を探っていくと、それは日本の寺が21世紀になった現在でも、“檀家制度”という江戸時代にできたシステムを基盤に運営され続けてきたことに突き当たる。日本のお寺とはすなわち、そういう封建制度のあった時代に形成された、素朴かつ濃密な地縁共同体、地域コミュニティを背景に、その檀家組織を維持して経営を成り立たせてきた存在である。ある意味では、そもそも“現代社会のあり方にはなじまない存在”なのかもしれないのだ。それが戦後も80年というタイミングで、いよいよ本格的に持たなくなってきているという見方もできる」と述べるのでした。
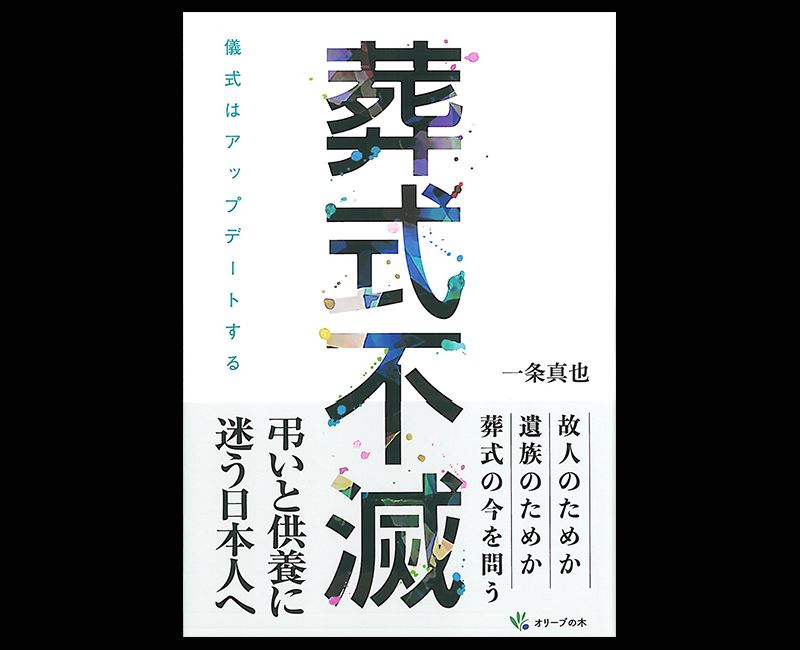 『葬式不滅』(オリーブの木)
『葬式不滅』(オリーブの木)
わたしには葬儀に関する著者が何冊もあります。また、冠婚葬祭互助会を経営しているわけですから、当然ながら葬儀および寺院の現状については最新の情報が絶えず入ってきます。それでも本書には知らないことも書かれており、しかも興味深い内容ばかりでした。また、一般財団法人日本消費者協会が発表したデータに基づきながら、つねに数字を挙げて、葬儀および寺院の現状を説明しているので説得力がありました。現代の日本人が葬儀について「“葬式仏教”のあり方に、何か注文があるわけではない。しかし、葬儀にかかるお金は、なるだけ明瞭かつ安価にしてほしい」と思っていることをずばり指摘した点も良かったと思います。勉強になりました。
