- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2446 プロレス・格闘技・武道 『ローラン・ボック』 アンドレアス・マトレ著、沢田智訳(サウザンブックス社)
2026.02.12
2025年12月19日、「地獄の墓堀り人」と呼ばれた元プロレスラーのローラン・ボックが亡くなりました。享年81でした。彼の伝記である『ローラン・ボック』アンドレアス・マトレ著、沢田智訳(サウザンブックス社)を読みました。「欧州最強プロレスラー、人生の軌跡」というサブタイトルがついています。著者は、自身も熱烈なプロレスファンで、体操選手キム・ブイのアスリート人生を描いた『45 Sekunden-KIM BUI』がシュピーゲル誌ベスト・セラーに選ばれたジャーナリストのアンドレアス・マトレ。名著です!
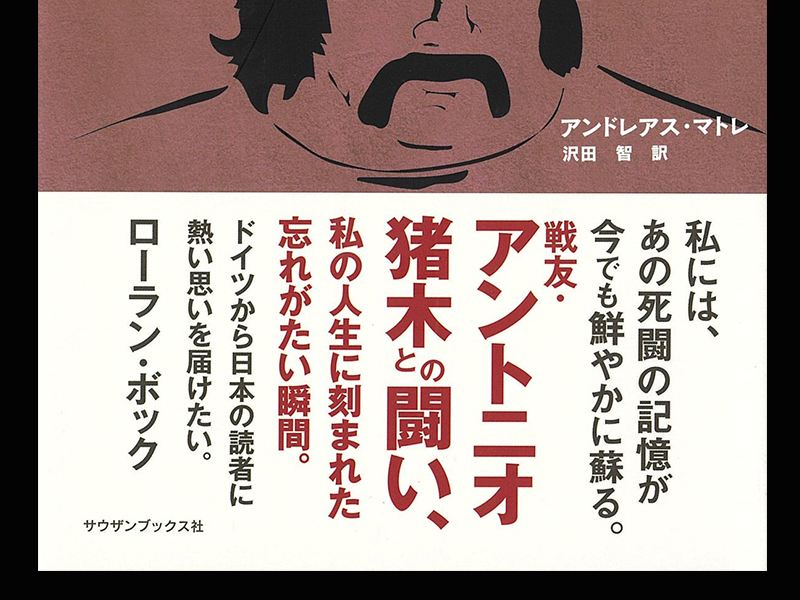 本書の帯
本書の帯
本書のカバー表紙には、ローラン・ボックのイラストが描かれ、帯には「私には、あの死闘の記憶が今でも鮮やかに蘇る。戦友・アントニオ猪木との闘い、私の人生に刻まれた忘れがたい瞬間。ドイツから日本の読者に熱い思いを届けたい。ローラン・ボック」と書かれています。
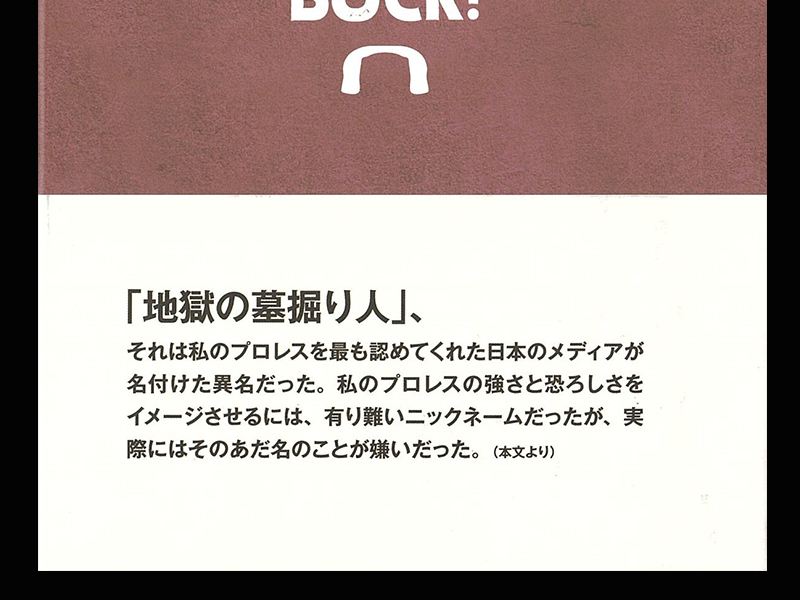 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には「『地獄の墓堀り人』、それは私のプロレスを最も認めてくれた日本のメディアが名付けた異名だった。私のプロレスの強さと恐ろしさをイメージさせるには、有り難いニックネームだったが、実際にはそのあだ名のことが嫌いだった。(本文より)」と書かれています。カバー前そでには、「貧困の少年時代を経てアマレス欧州王者、オリンピック出場を果たす。プロに転じ、アントニオ猪木との死闘で名を刻む。だが、その結末は逮捕・収監。そこから実業家として奇跡の再起。“ディスコ王”と称されるも波乱は続く。東南アジアへ移住するも、事業失敗と感染症により帰国。そして新たな挑戦へ―――絶な生涯を描いた一冊。ボックは、まだ人生を諦めていない」と書かれています。
版元のHPには、ローラン・ボックについて「1944年ドイツ生まれ。14歳の時に地元のレスリングクラブでアマレスを始める。ヨーロッパ選手権で実績を残し、1968年のメキシコ五輪に出場。1972年のミュンヘン五輪の最有力候補となるもド イツアマレス協会と対立して除名される。1973年にプロレス転向。レスラー兼プロモーターとして活躍し、モハメド・アリと引き分けた男「アントニオ猪木」と闘うために1978年にヨーロッパでのビッグイベントを主催。プロレス史に残る激闘を展開するも、興行的には大損失を負い、さらにその清算において脱税・詐欺行為が発覚して逮捕・収監された。出所後には、実業家として再起し、大規模なディスコ経営を手掛けて、王のような暮らしを手に入れる。1990年代は、事業を社員に任せ、東南アジア・タイへ移住。楽園の暮らしを楽しんだ。2000年代はドイツに戻ったが、その時点では、経営不振となったディスコは人手に渡っていた。しかし、その後も新たな事業に突き進む野心は衰えず、新たに起業してドイツで暮らしている」と書かれています。
本書はクラウドファンディングによる出版物ですが、その発起人を務めたのは翻訳者でもある沢田智氏です。プロレスファンとして独自のホームページを立ち上げて情報を発信している沢田氏は、版元のHPで「『幻の最強レスラー』ボックの足跡を日本のプロレス史に残したい」として、「アントニオ猪木を極限まで追いこんで勝利した『ローラン・ボック』を私は1980年代に入ってから知りました。真の世界チャンピオンを決める新日本プロレスのIWGP構想に向け、プロレス中継で古舘アナがボックの話題に触れ、雑誌でも『まだ見ぬ強豪』として取り上げられるようになった頃です。そして初来日。木村健吾戦、長州力戦の衝撃。一切妥協を許さないローラン・ボックの闘い。猪木との完全決着が待ち望まれながら、突然の引退。その後、ボックに関する情報は更新されることなく、最強幻想だけが生き続けました。ローラン・ボックについて、同じような感覚で決着のついていない『昭和プロレスファン』は多いのではないでしょうか?」と述べています。
また、沢田氏は「2021年にドイツでローラン・ボック自伝が刊行されると、日本でも翻訳出版が期待されました。しかしその動きは無く時間ばかり経過する中、原書を購入してでも読みたいと思うに至りました。そもそも私はプロレスファンなので、1978年の欧州選手権ツアーの項目だけを読むつもりでしたが、最強の男に成長した経緯、なぜ突如引退し、その後はどう生きたのか、次から次へと興味が湧き、一気に読み進めました。この本の感動を多くの人と共有したいと思い、ブログ等で紹介してきました。そして翻訳出版の可能性を探りましたが、ニッチな分野の本の出版については出版社は消極的です。そこで『クラウドファンディング』での出版を企画するに至りました。『ローラン・ボックとは何か』を探している昭和プロレスファンの力で、『幻の最強レスラー』を再発見し、ボックの足跡を日本のプロレス史に残していきましょう」と述べるのでした。
本書の「もくじ」は、以下の通りです。
「プロローグ」
第1章
1-1 瓦礫の街、シュツットガルトに生まれて
1-2 実の父との対面、もう1つのトラウマの正体
第2章
2-1 逞しい筋肉をまとった15歳の少年
2-2 ボーデン湖畔の初体験
2-3 シュタドルの繁華街、“ギャング”のボスはボック
2-4 銀行の実習生時代、地下室の大パーティー
2-5 プロレスラーとの対決
2-6 学校教師、カローラとの出会い
2-7 自信に満ちあふれていたメキシコ五輪
2-8 大盛況〈ビッグ・ボーイ〉
2-9 ヨーロッパ選手権制覇
2-10 ミュンヘン五輪金メダル候補、絶頂期の挫折
第3章
3-1 最強プロレスラー、ローラン・ボックの誕生
3-2 プロレスは、ビッグマネー稼ぎ出すビジネス
3-3 不穏試合、ボック対ゴーディエンコ
3-4 グルーぺは懇願した、殺さないでくれ
3-5 エロティシズムを超えた闘いのドラマ、女子プロレス
3-6 「世紀の一戦」モハメド・アリ対アントニオ猪木
3-7 人間と野獣の危険な戦い! 巨大ヒグマ対ボック
3-8 世界初、トップレス女子プロボクシング
3-9 新日本プロレス、新間寿との交渉
3-10 欧州ツアーの最重要課題、500万マルクを集めろ!
3-11 “キラー猪木来たる!”
ミルデンバーガー戦、デートリッヒ戦
3-12 ローラン・ボック対アントニオ猪木はプロレスを超えた
3-13 『ハリケーン・ロージー』映画俳優ボック
3-14 ジンデルフィンゲンの死闘、
アンドレ・ザ・ジャイアント戦
3-15 日本遠征、木村健吾、スタン・ハンセン、猪木再戦
第4章
4-1 実業家ボックの野望、廃工場の再生
4-2 鉄格子越しの凍った空
4-3 ハイルブロンから解き放つロックの嵐
4-⒋ グラン・カナリア島、ストーンズ、マドンナ、マイケル
4-5 楽園での生活、タイ移住
4-6 ドイツ帰国、ビジネスへの飽くなき挑戦
4-7 “シュツットガルトの闘い”を見た少年
「エピローグ」
「訳者あとがき」
「プロローグ」には、本書の主人公であるローラン・ボックの「私がやってきたプロレスについて語ってほしいと、友人やマスコミからも依頼されることがある。しかしそれは私にとって、モノクロの無声映画の世界にいたような記憶だ。今、『プロレス』といえばテレビに映るアメリカのプロレスだ。私が目指した伝統的なプロレスと起源は同じだが、もう別のものとなっている。画面の中では、レスラーたちが真剣な表情で対戦相手を投げつけ、踏みつぶしている。攻撃を受ければ、うめき声を上げる。10分間のショー・アーティストなのか、それともスタントマンなのか。最後に劇画から飛び出した英雄のように鍛え上げた腕を高く突き上げる。そしてマイクを持ち、相手を言葉でも挑発する。一連の流れの中に『プロフェッショナル・レスリング』という言葉で置き換えることができる瞬間があれば、なんとかそこに色と光が見えてくる」という言葉が紹介されています。
ボックが主催したプロレスの仕事がうまくいかず、金や観客が集まらなくなると、レスラーとスポンサーに責め立てられたそうです。カミソリを使った流血、ヒグマとの対決、女子ボクシング。あらゆる知恵とアイディアで観客席を埋めることだけを考えたとか。しかし、ボックは「闘いのないプロレスが観客を惹きつけるのは一時的なことだった。レスラーたちの乾いた血の報酬は恐ろしく低く、やがて年老いていった」と述べます。ボック自身がレスラーとしてリングに上がり、レスリングにこだわった試合をすると、「ローラン・ボックはレスラーを壊す」と非難されました。技術を磨き上げたプロフェッショナルなレスリングを行いたかったのですが、それは興行に求められる「プロレス」とはかけ離れていたというのです。
融通の利かないプロレスしかできないボックを誰かが「地獄の墓掘り人」と呼び始めました。ボックのプロレスを最も認めてくれた日本のメディアが名付けた異名でした。ボックは、「私のプロレスの強さと恐ろしさをイメージさせるには、有り難いニックネームだったが、実際にはそのあだ名のことが嫌いだった。本当の『墓掘り人』が幼少期の私を苦しめ、傷つけ、悪夢を見せ続けた過去を思い起こしてしまうからだ」と述べるのでした。ここから第一章の1-1「瓦礫の街、シュツットガルトに生まれて」では、ボックが幼少期のトラウマを語り、「私の体にはあざが絶えることがなかった。しかし、それよりも最悪だったのは、祖父が私に暗闇への恐怖を植え付けたことだった」と述べています。ボックは後に数々の世界最強の男たちを相手に戦ってきましたが、この暗闇を上回る恐怖を感じたことはないそうです。ボックは、「祖父のいる暮らしは悪夢の日々だった。私は祖父の残忍さ、他人を辱めることに喜びを感じるだけの、この男のイメージを『墓掘り人』という職業に重ね合わせていた」と述べます。
ボックがトラウマを与えられたのは祖父だけではありませんでした。夕食は太った祖母が作ってくれました。時々食事でお腹がいっぱいになって食べきれず、ボック少年は皿に少しだけ残してしまうことがありました。そんなとき祖母は、「あらあら、残っているわよ」と言いながら、残った食べ物を長い木のスプーンでボックの口の中に押し込んでくるのでした。ボックは、「残忍さという点においては、太った祖母も墓掘り人の祖父に劣らなかった。私の胃袋に食べ物を限界まで詰め込んできた。喉の奥に酸っぱい胃液があふれ、嘔吐すると、今度は頭から血が流れるまで殴りつけた。そして嘔吐物をスプーンですくい、『これも全部食べなさい』と言うのだった。そんな日々を過ごしているせいもあるのだろう、私は毎晩ベッドでおねしょをしていた」と述べます。
しかし、祖父母以上に最大のトラウマを与えたのは実の父親でした。1-2「実の父との対面、もう1つのトラウマの正体」では、母に暴力をふるっていた父は幼いボックにも襲いかかってきた様子が描かれています。ボックは、「突然、ある光景の記憶が残忍な力で私に襲いかかってきた。ふさふさした眉毛、大きな鼻、肉厚な唇。頭を水面下に押し込まれて、窒息するような感覚、濁った石鹸水のぬるま湯を通して見えた表情。台所の流し台に置いたベビー用の浴槽に幼い私を浸けていた男の顔だった。私を浴槽で苦しめた後、私を持ち上げて悪意を持って勝ち誇ったように笑った男だ。三面鏡に映った薄暗いシルエット。四つん這いでうめき声を上げながら泣き叫ぶ女性。背後から襲いかかる動く影。この男は私の息苦しくなるような、不快で恐ろしい記憶の中に現れる男だった」と回想しています。
「2-1.逞しい筋肉をまとった15歳の少年」では、ボックがレスリングを始めたことが紹介され、「レスリングとは闘いだ。体毛を蓄えた私たちの祖先たちが、棍棒を手にサバンナを駆け回っていた時代から続いている。後に古代ギリシャの闘技場で文明化され、男が裸の姿で対峙し、褒美を求めて力を競い合った。その後、独裁者がコロッセオに進出し、死刑を宣告された者たちを闘わせたりした。それは試合ではなく、残忍な殺し合いだったこともある。そして現代では競技化されて、技術を競い合うが、そこには間違いなく闘いがある」と書かれています。レスリングもプロレスも四方から見られることで、隠すことができないから正直です。しかし相手と観客を騙すために噓をつきます。視線、細めた目、わずかな体重移動を感じた相手は予期せぬ攻撃に備えます。相手の攻撃を受けるとき、相手を誤解させようとします。ボックは、「痛みの感覚は真実だ。それは自分の意志であり、感情から切り離せば乗り越えられる。服従するか、征服するかを競い合う。それには決められた結末は関係ない」と述べています。
「2-7.自信に満ち溢れていたメキシコ五輪」では、1968年のメキシコオリンピックのことが書かれています。ボックは、この祭典が自分のために行われているような錯覚に陥っていたといいます。参加しているすべてのアスリートと観客の大家族の中にいる安心感がありました。空高く飛び立った1万羽の平和の鳩も私の心の平安を祝福しているようだったとして、ボックは「脳裏に焼き付いているすべての嫌な記憶が、この情景の中に消え去るような気がした。墓掘り人の祖父に、メキシコのスタジアムの中心にいる自分を見せつけてやりたかった。墓掘り人はもう私に勝てないことを悟り、黒革のブーツを地面に打ち付け、割れた大地に落ちていくだろう。実の父親は私が遂にオリンピック大会に辿り着いたことを知って、成功した息子に捨てられるような非道な行いをしたことを激しく後悔するだろう。私はすべての厭わしい記憶に打ち勝てると感じるほど、自信に満ちあふれていた」と述べています。
メキシコオリンピックのレスリング会場の隣に、ボクサーズホールがありました。そこでは、後のボクシング世界ヘビー級チャンピオンになる19歳のジョージ・フォアマンがサンドバッグを打っていました。ボックがフォアマンと雑談した時、フォアマンは「レスリングの練習方法にも興味がある」と話したそうです。ボックは、「フォアマンは初戦からメダルは確実だと思わせる戦いをした。周囲の予想どおり金メダルを獲得した授賞式で、彼はアメリカの国旗に向かって手を振った。自国アメリカの人種差別政策に抗議する黒人選手が多かった中で、フォアマンのこの行動は、すべての人種が平等であるという考えを平和的に示そうとしているものだった。ドイツにとっても、メキシコオリンピックは、西ドイツと東ドイツが分裂して参加した初めての大会だったが、私は政治的な事柄には全く無関心で、メダルを獲得することだけを考えていた。レスリングの試合は、ピスタ・ヒエロ(La Pista Hielo)と名付けられた新しいホールで実施された。このオリンピックでの私の成績は、絶好調で現地入りしたのにもかかわらず、グレコローマンスタイルのヘビー級で11位だった」と述べるのでした。
「3-1.最強プロレスラー、ローラン・ボックの誕生」の冒頭には、「カインとアベル以来、人間と人間の闘いは長い歴史の中で語り継がれてきた。現代においても闘いはエンターテインメントとして、欠かせない要素だ。無法者の夫パンチとその妻ジュディ、保安官ケイン対悪漢ミラーの真昼の決闘、ルーク・スカイウォーカー対ダース・ベイダーのライトサイドとダークサイドの闘い。善と悪が完全に区別できない闘いに人々は魅了されてきた。プロレスもまた、相反するイデオロギーの対立を演出して、大衆を惹きつけてきた」と書かれています。リング上のベビーフェイスレスラーはヒールレスラーを打ち負かし、観客が望んでいる正義を実行してみせます。ヒールレスラーは観客の心を揺さぶり、怒りを解放します。プロレスはリングの中で秩序ある世界を破壊し、人々の退屈な日常を忘れさせます。観衆はプロレスラーの戦いを見てストレスを発散します。著者は、「客席の男たちは、日常生活では決して口にできない言葉を悪党レスラーに浴びせかけ、徹底的に否定する。唾を吐き、拳を握り、激怒し、足を踏みならす」と述べています。
プロレスラーの先輩であるポール・バーガーから、ローラン・ボックは貴重なアドバイスを受けます。それは、「君は本気で闘えばいい。カシアス・クレイの試合を思い出してみろ。彼の言動や闘い方は、常に観客の注目を集めているだろ。そこには少なからず芝居がかっているようにみえる部分があるが、それも含めてプロボクサーの真剣な仕事なんだ。間違いなくクレイは本物で最強のボクサーだ。ローラン、ほんの少しの芝居の才能が必要になるが、それも本気でやるんだ。そうすればプロレスでも本物のレスリングを見せることができる。最後に首にメダルを掛けてもらって喜ぶより、札束を手にする方が面白い仕事だと思わないか」というものでした。
ボックがプロレスの試合に何が重要なのかを学び、それに従った試合ができるようになるまでに時間はかからなかったそうです。プロレスは勝ち負けや強さを競うだけのものではないことを理解しました。劇場の舞台に立っていると開き直ればいいのです。ただし、ボックにはアマレス最強、善良で公正なレスラーというキャラクターが与えられているため、過度な芝居はしないようにしました。観客も、全く段取りのない試合などは望んでおらず、派手なパフォーマンスやアピールが繰り広げられることを期待していました。どこまでが真剣で、どこからが段取りかの議論をすることも、ファンにとってのプロレスの楽しみ方だったのです。
「3-3.不穏試合、ボック対ゴーディエンコ」では、ドイツ国内で開催されたプロレスのトーナメントについて言及されていますが、ミュンスターランドのトーナメントでは、予期せぬアクシデントが発生しました。この大会にはすべてのレスラー、関係者からも認められている強豪カナダ人レスラー、ジョージ・ゴーディエンコが参戦していました。口ひげを生やし、がっしりとした体格の男で身長182センチ、体重140キロ、少しお腹が出ているが驚くほど機敏でした。ゴーディエンコについて、ボックは「実力だけでなく、歯をむき出しにする表情のほか、彼の佇まいのすべてに説得力があった。今回カイザーのプロモーションに参戦してから何度も対戦したが、タフな男であり、私の技をしっかりと受け止めてくれたので、遠慮なくぶつかっていくことができた。彼が典型的なシューターであり、もし試合が不穏な方向にいってしまったときは、躊躇せず相手をノックアウトしてしまう選手だと恐れられていたことは、後になって知った」と述べています。
ボックはミュンスターランドの最終戦でも、このゴーディエンコと対戦しました。ボックは自分が危険なトラブルに巻き込まれていると気付き、闘いのモードを入れ替えました。ボックは、「確かにこの巨像、ゴーディエンコを仕留めることは簡単ではなかった。それでも、タックルで倒し、スープレックスで投げ、そこからは優位に試合を運ぶことができた。ゴーディエンコを仰向けに倒した時、彼の足を掴んで万力のように強く捻ると、ゴーディエンコは痛みを我慢できず、ゆがむ顔を両手で覆った。ゴーディエンコの足に何か問題が起こったことはレフェリーも気が付いていた。最後はゴーディエンコが勝ち名乗りを上げるように試合を運んだ。勝利したゴーディエンコは足を引きずりながらトロフィーを受け取ったが、そのあと病院に運ばれて行った」と述べます。ゴーディエンコはプロモーターのカイザーから、通常のプロレスの範囲を逸脱しても、ボックを限界まで追い込み、戦意を喪失させて勝つよう指示されていたと告白しました。ボックは、「おそらくカイザーは、次期シリーズでホースト・ホフマンと私を対戦させるとき、ホフマンをエースとして推し、私には反発をさせないように、カイザー・プロモーションの力を知らしめておきたかったのだろう」と述べるのでした。
その後、ボックは「プロレスラー対ヒグマ」という新しい企画に取り組みましたが、その頃、日本では「世紀の一戦」が行われようとしていました。ボックが敬愛していたプロボクサー、モハメド・アリと日本のプロレスラー、アントニオ猪木のミックスド・マッチです。ボクシング世界チャンピオンのモハメド・アリはこの頃、短期間で3度のタイトル防衛戦を行っていました。このことはアリを取り巻く周辺の財政状況によるものだと思われました。いわゆるアリ・ファミリーは、アリをプロモートし、アリの試合やメディア露出、トレーニングなどを任されていたのです。ボックは、「彼らはアリを使ってできるだけ金を稼ぎ出すことばかりを考えていると噂されていた。そういった背景から、今回のアリ対猪木のミックスド・マッチもアリ・ファミリーの手によって合意に至ったのだろうと私は思っている」と述べます。
1976年6月26日、ついに実現したアリと猪木の「格闘技世界一決定戦」ですが、両者は15ラウンドにわたる睨み合いを演じ、結果は引き分けに終わりました。著者は、「猪木は、アリのパンチを受けないよう、終始倒れ込んだ状態で闘った。ほとんどの時間、リング上をカニのように這い回り、アリの膝の裏を蹴り続けた。アントニオ猪木は日本のプロレスファンの間では英雄的な存在であり、会場に集まった観客は無条件に猪木を支持していた。しかし、満足のいく結果にならなかったばかりか、全く見せ場のない15ラウンドの闘いに、集まった観衆は落胆し、一部は激怒してリングに向かって、『金返せ!』と罵声を浴びせかけた。試合結果は、完全な失望だけを残した」と述べます。しかし、実際は猪木のキック攻撃が、アリの膝の裏に血アザを作り、アリを病院に送り込むほど厳しい攻撃でした。ボックは「そうでなければ、本当に茶番だった。私もプロレス側に身を置く者として救われた気がした。猪木がアリにもっとチャンスを与える闘いを作っていたなら、アリはどんな闘い方をしたのだろう。もしも引き分けだったとしても、世界中が再戦を懇願するような名勝負を作ることができたはずだ。後に私がこの試合の内部関係者から聞いた話では、アリはこれが単なるエキシビションマッチの一種だと考えていたのに対し、猪木は真剣勝負を望んでいたということだった」と述べています。
ボックは、アリと猪木の闘いが実現したこと自体に衝撃を受けたそうです。この日から、ボックは頭の中には嵐が巻き起こったように、この試合のことばかりを考えるようになりました。彼は、「私が猪木のようにモハメド・アリをプロレスのリングに引きずり出し、闘って倒す、あるいは名勝負を演出することは、資金的に不可能かもしれない。金銭の問題以前に、すでに猪木と闘って大きな肉体的ダメージを受けてしまったアリは、今後はプロレスラーとの闘いを拒否する可能性も高い。そうだとしても、アントニオ猪木と闘うことならできるはずだと考えるようになった」と述べます。ドイツでプロレスが開催できる最大のホール、ネッカーシュタディオンで、“モハメド・アリと闘った男”アントニオ猪木対ローラン・ボックを実現する。ドイツ全土に生放送でテレビ中継をする。翌日の新聞の見出しは、「ボック対猪木」の見出し一色だ。ボックには、次々とビジネスの構想が浮かんでいました。
「3-9.新日本プロレス、新間寿との交渉」では、ボックが日本を訪れ、新間氏に新日本プロレスの道場まで案内された様子が述べられています。そこでは、新日本プロレス所属の選手たちが熱心にトレーニングをしていました。ボックは、「私のアマチュアレスリング時代の厳しい練習を思い起こさせる光景だった。ヨーロッパでは、プロレスラーたちが体を鍛えている姿などほとんど見たことがなかった。熱心に練習をしていたのは、ピエール・ルデュクかピート・ロバーツぐらいだった。新日本プロレスの道場では、若手選手が指導者から本当にいじめられているかのようにシゴかれていた。ほとんど会話はなかった。聞こえてくるのは、指導の短い命令と若手レスラーのうめき声だけだった。その練習の中心にアントニオ猪木もいた」と述べています。
猪木はボックの姿を見つけると、挨拶代わりなのか、軽く頷いて見せたそうです。猪木はレスラーがフォールをとられることを防ぐための基本的なトレーニング、ブリッジの体勢をとりました。仰向けになった体は、首とつま先だけで支えられ、美しいアーチを描いていました。猪木は若手レスラー3人を自分のブリッジの上に座らせ、体を前後に揺さぶっていました。強靭なブリッジでした。ボックは、「私たちは新日本プロレスとの交渉を成功裏に終結させた。最終的に猪木の試合数が22試合となり、報酬も当初の交渉額50万マルク(約5000万円)から倍増した金額、100万マルク(約1億円)で合意した。最初に私が提案した試合数から大幅に増やした大規模ツアーとなるので、観客の入場料金でなんとかなる金額だと見込んでの契約だった」と述べます。
ボックが企画した猪木の欧州ツアーは、猪木が9月に1週間ドイツを訪問して、欧州選手権ツアーのPRを行い、本番のツアーで11月初旬に再度ドイツ入りすることになりました。ボックの次の課題は、猪木ツアーの資金を集めることだった。またこの頃、日本の福田赳夫首相が、西ドイツのボンで開催される世界経済サミットに参加する予定がありました。この時に福田首相からドイツのヴァルター・シェール大統領に、アントニオ猪木がドイツでプロレスの欧州選手権ツアーに参戦すると伝えてくれることになっていると新間から聞かされたボックは、「新日本プロレスが政治の中枢に働きかけて、プロレスの興行を国民的なイベントとして開催していることに、私たちは度肝を抜かれていた」と告白しています。
「3-10.欧州ツアーの最重要解題、500万マルクを集めろ!」では、欧州ツアーにウィレム・ルスカの参戦が決定したことが紹介されています。ルスカは、ボックが金メダル獲得を目指していた1972年のミュンヘンオリンピックの柔道競技で、93キロ超級と無差別級の両方で優勝していました。当時、1つのオリンピックで2つの金メダルを獲得した唯一の柔道家でした。ルスカは2年前に日本で猪木と対戦し、その試合は世界的な話題になっていた。猪木にととっては初の「格闘技世界一決定戦」であり、現在では純粋なプロレスの試合だったことが明らかになっていますが、当時は「プロレスvs柔道」の真剣勝負として大きな話題を呼びました。結果は、バックドロップ3連発で猪木がルスカを下しました。
欧州ツアーのプロモーターであるローラン・ボックは、ロッテルダムとアントワープで、アントニオ猪木とルスカの再戦を組むことにしました。ルスカは、母国でさらに高く評価されているもう1人の柔道家、アントン・ヘーシンクをボックに紹介してくれました。ヘーシンクは1961年に日本人以外で初めて柔道世界選手権を制覇した柔道家です。1964年の東京オリンピックでは金メダルを獲得しています。引退後はプロレスラーに転身し、金メダルを獲った日本を主戦場に闘っている選手でした。ジャイアント馬場が率いる全日本プロレスが主戦場でしたが、プロレスラーとしての評価は高くありませんでした。ボックは、「デートリッヒ、ミルデンバーガー、ルスカ、ヘーシンクと大物格闘家が続々と集まり始め、猪木ツアー成功の予感に私は胸を躍らせていた」と述べています。
しかし、大変なアクシデントが発生しました。アムステルダムでウィレム・ルスカとアントン・ヘーシンクが同席する記者会見が開かれたのですが、2人のオリンピック金メダリストがそろって猪木ツアーに参戦することは、彼らの母国オランダでは、大きな話題となっていました。会見が進み、ヘーシンクにマイクが回った時に事件は起きた。突然ヘーシンクが、「プロレスはショーである。事前に結果が決まっているような試合には興味がない。私はこのツアーに参戦しないことを決めた」と表明したのです。ルスカにとっても予想外の展開であり、報道陣もざわつきました。その記者会見は、本来ならルスカ、ヘーシンクが猪木と闘うドリームマッチの決定を発表する場でした。さらにルスカとヘーシンクを対立させて、2人の対戦を煽る計画もありました。
この予想外のアクシデントについて、ボックは「プロレスにはショー的要素がつきもので、ときには喧嘩もするが、すべてが合意に基づいており、その成果に応じて報酬が与えられるものである。ヘーシンクは日本で十分なプロレスの経験があり、そのことを理解していないはずはなかったし、今さらそれをツアー不参加の理由にすることは考えられないことだった。この一件で、ルスカはヘーシンクのことを全く信用できなくなってしまった」と述べます。わたしが推測するに、おそらくはジャイアント馬場の全日本プロレスからヘーシンクに指示が飛んだのでしょうね。当時のわたしは、猪木とヘーシンクの戦いを心から楽しみにしていたので、実現しないと知ったときは落胆しました。
「3-11.“キラー猪木来たる!”ミルデンバーガー戦、デートリッヒ戦」では、1978年11月9日に行われたツアー第3戦となる猪木とヘビー級のプロボクサーであるカール・ミルデンバーガーの一戦について述べられています。ボックは、「リングに立ったミルデンバーガーが、かぶっていたフードを外し、ガウンを脱ぐと、シルバーグレーの頭髪と汗ばんだ体がスポットライトに照らされた。その姿は、アントニオ猪木の無駄のない引き締まった体とは対照的だった」と述べます。猪木はハンディキャップを承知で、グローブを着用して、ボクサーであるミルデンバーガーとの闘いに挑みましだ。しかも猪木は純粋なプロレスラーであるにもかかわらず、ミルデンバーガーに有効なパンチを数発ヒットさせました。猪木は4ラウンドに空手の技でミルデンバーガーを攻略。宙に高くジャンプして、ミルデンバーガーの後頭部を足の甲で強烈に蹴り飛ばしました。マットに倒れ込んだミルデンバーガーを猪木は逆エビに固めました。ミルデンバーガーは自分の体を痛める前に、あっさりとギブアップの意志をレフェリーに伝えたのでした。
「3-12.ローラン・ボック対アントニオ猪木はプロレスを超えた」では、11月25日にシュットガルト・キレスブルクの展示ホールで行われた猪木とボックの決着戦の様子が述べられています。8000人の観客が集まりましたが、ボックは試合を前に控え室で猪木と話し合ったそうです。そこには、新間寿とこの試合のプロモーターであるポール・バーガーも同席しました。口火を切ったのはポールで、「今日はローランに勝たせなくてはならない。シュツットガルトはローランの故郷であり、このツアーの最大のビッグマッチだ。日本での再戦は約束する」と言ったそうです。猪木は、ここまでボックが提示するすべてのマッチメイクを受け入れましたが、この日初めて意見の相違が生じました。新間は、「今日は日本のテレビの収録がある。モハメド・アリと引き分けたアントニオ猪木が、ローラン・ボックに負けることはありえない」と言いました。
ボックは、この日のシュツットガルトでの猪木戦のために、これまでの2試合で猪木に勝ちを譲り、1敗1分けの星としていました。この試合でボックが勝つことで、1勝1敗1引き分けとなるのなら、猪木にとっても「ローラン・ボックに負けた」というキズはつかないはずだと考えたボックは、「どうしても、この試合での勝ちは譲れなかった。双方とも譲らない交渉は一進一退となっていた。ポールが最後の妥協案を出した。4分10ラウンドをフルに闘う。決着がつかないが、裁定は審判の判定に委ねて、最終的に2対1の僅差でローラン・ボックの勝ちとなる案だ。この結果なら猪木は面目を失うことなく、東京での再戦にもつながる。最終的に猪木サイドもこの提案に同意した」と述べています。
シュツットガルトでの猪木との決着戦について、ボックは「第7ラウンドだっただろうか。それとも8ラウンドだったか。私は猪木の足を極めていた。猪木は動けなかった。猪木が少しでも抵抗して力を入れれば、骨折しただろう。時間が減速しているような感覚だった。猪木は私の目を見つめ、長いアゴをさらに突き出した。猪木は抵抗することをやめ、自分の足を完全に私に預けてきた。私が捻る角度をほんの少し変えるだけで、猪木の足は破壊される。ここで猪木をつぶして、“モハメド・アリと闘った男に完勝した”という称号を手にしたい衝動にかられた。それはやろうと思えば簡単なことだった。しかし、ルールを守れない男として軽蔑され、プロレスの世界から追放されるリスクも十分にある」と回想しています。
同時に、ボックはロンドンのロイズ社の保険証書も頭に浮かんだそうです。猪木の負傷でツアーが中止になり、保険金が手に入れば大損害はまぬがれるかもしれません。ボックは、「猪木の骨折した足のレントゲン写真があれば、プロレスは真剣勝負であることを世間に知らしめることもできるではないか。・・・・・・勝利、名誉、裏切り、違約金、ツアーの中止、保険金。損得を瞬時に判断することはできなかった。その時、私の目の前には、あの忌まわしい『墓掘り人』が姿を現した。この男なら必ず猪木の足をへし折っているはずだ」と回想します。ボックの悪魔が「たった1回だけだ。ビジネスのためだ。やれ!」と囁きました。ボックが躊躇しながら、猪木の足を固めていた時間は1分あるかないかだったそうです。
そのとき、会場から応援の大合唱が聞こえてきました。そこでは「♪帝王ローラン・ボック、ボックこそが神♪」と謳われており、ボックの思考は現実に引き戻されました。そして、ボックは猪木の足を解放したのです。流れ出した血がボックの目の上にこびりついていました。10ラウンドが終了し、ボックも猪木も疲れ果てていました。ボックは、「2人は全く遊びを受け入れず、全力を尽くしたのだ。リングアナウンサーが判定結果で私の勝利を発表し、私はリング上で少年のように飛び上がって喜びを表現した。猪木は激怒し日本のテレビのリポーターに対して不満をあらわにした。マネージャーの新間はジャッジの判定に対して抗議をしていた。猪木の攻撃でできた私の眉間の傷と胸のミミズ腫れに偽りはなかった。猪木は手加減のない、本物のプロレスで勝負してくれた」と述べるのでした。
「3-14.ジンデルフィンゲンの死闘、アンドレ・ザ・ジャイアント戦」では、1979年の夏、ドイツ南部のカールスルーエで「国際ドイツ選手権大会」と称したプロレスイベントが3週間にわたって開催されました。ボックは、映画出演で稼いだ金を元手に、年末にビッグマッチを考えていました。そのビッグマッチとは、“世界の大巨人”アンドレ・ザ・ジャイアントを招聘して対戦する計画でした。アンドレ・ザ・ジャイアントは1960年代にパリでプロレスデビューしましたが、その後フランスを離れ、アメリカと日本を主戦場にして闘っていました。アンドレは、どこのマーケットでも会場を満員にできました。身長224センチ、体重240キロ。規格外の体型は、「世界七不思議」に続く次の不思議だとして、「世界八番目の不思議」と言われていました。
アメリカでもヨーロッパでも各地に“世界チャンピオン”はいましたが、アンドレ・ザ・ジャイアントだけは別格であり、1970年代から1980年代前半まで、誰もが認める「世界最強のプロレスラー」として君臨していたのです。アンドレ・ザ・ジャイアントを招聘しての興行は、6カ所の都市で開催しました。1979年12月16日、短期シリーズの最終戦、ジンデルフィンゲンのグラスパラストでは、ボックがWWU世界選手権を賭けてアンドレ・ザ・ジャイアントを迎え撃った。観客は3000人が集まり、満員でした。試合が始まると、巨大なアンドレの体をボックがリングの上で扱うことは簡単ではありませんでした。試合中にアンドレの全体重がボックの左足にかかってしまい、危うく負傷するところだったそうです。それでもボックはなんとかスープレックスの体勢に入り、アンドレを後方に投げ飛ばすことに成功。
2人はそのままリング下に転がり落ち、場外で乱闘になりました。アンドレは10カウント以内にリング上に戻ることができませんでした。6連戦のアンドレ・ザ・ジャイアント・ツアーは無事終了しましたが、ボックは「数日後、プールで泳いでいる時に、左下肢が硬く腫れ上がり、赤くなっていることに気が付いた。それを見た妻のアンドレアは、私に病院へ行くことを強く勧めた。医師の診断は、『血栓症』だった。このまま放置すると、足に障害が残り麻痺することもあると言われた。医師に数日前のアンドレとの激しい試合のことを話すと、私の足にアンドレの体重がかかった時に、血栓ができた可能性は十分にあると言われた。手術室に直行することになった。私は抗凝血剤『マルクマール』を一生服用するよう指示を受けて、1週間後に退院した」と述べています。
「3-15.日本遠征、木村健吾、スタン・ハンセン、猪木再戦」では、1980年の夏、血栓症の発症から半年以上が経過して、ボックにやっと医師からゴーサインが出ました。軽いトレーニングができるようになったボックは新日本プロレスと連絡を取り、翌1981年の夏、日本に遠征しました。そこでは木村健吾や長州力と対戦。難なく勝ちました。同年12月にも日本のマットに上がりましたが、そこにはスタン・ハンセンも参戦していました。アントニオ猪木との闘いで外国人のトップレスラーに上り詰めていたテキサス出身のハンセンは、ボックの試合を見て「硬いプロレスだな」とつぶやいたそうです。そして、ハンセンはボックに「日本で闘うなら、もう少し相手に攻め込むチャンスを与えなければいけない」とアドバイスしたといいます。
この年、ボックは日本のアンドレと再会しましたが、それ以来、二度と彼に会うことはありませんでした。1993年にニュースで、アンドレが生まれ故郷のフランスで心不全によって亡くなったことを知りました。ちょうどアンドレが父親の葬儀でフランスに戻った時の出来事で、46歳の若さでした。アンドレは痛みのせいで現役終盤の数年間は、リングコスチュームの下にコルセットを着用して試合をしており、ついにはそれも不可能になってしまっていたということも知りました。ボックは、「アンドレにとってプロレスのリングが人生のすべてであり、最後に疲れ果ててしまったのだろうと、私はアンドレの生涯に思いを馳せた」と述べています。
ボックがアントニオ猪木と対戦したのは、最後の訪日となった1982年1月1日でした。この試合は、新日本プロレスにとっては、1982年の新しいシリーズの開幕を前にした新年の特別興行でした。ボックは、高額なファイトマネーの上乗せで交渉が成立したことに満足していたそうです。ボックは、「東京の試合会場、後楽園ホールは超満員だった。私は負けを受け入れていたが、試合中に邪悪な気持ちが何度も湧いてきた。猪木が飛び上がり、私の胸にドロップキックを狙ってきたときには、私は1歩後ろに下がり、猪木は宙を舞っただけでマットに落ちていった。観客の間にざわめきが響き渡った。相手がただ愚かに見えるだけの技のかわし方であり、そのことが互いの次の攻防の伏線にならない限り、通常はやってはならない行為だった。試合中、そんな場面を何度か作ってしまった。試合の結末は私がロープ際でレフェリーの制止を無視して猪木の首を絞め続けたため反則負けとなり、猪木の勝利が宣せられた」と述べています。
アントニオ猪木とローラン・ボックとの関わりは、結果的にこの日、1981年の元日が最後になりました。その後、猪木が長年にわたって日本一のプロレスラーとして君臨できたことは、少しも驚くべきことではなかったというボックは、「アントニオ猪木と交流して、彼の考え方と行動力に共感し、彼のプロレスをロールモデルとして目標にしてきたのだ。後に猪木が政党を設立し、政治の世界に入ったことは驚きだった。そしてもう1つの驚きは、猪木がイスラム教に改宗したことだった。私がそれを知った時、猪木はモハメド・アリになりたかったのではないかと思った。私は政治や宗教にはあまり興味を持っていなかったし、それは私の目指した方向とは違っていた」と述べます。帰国したボックは、妻のアンドレアに「もうプロレスラーもプロモーター業も辞める」と伝えました。彼女以外には、そのことを誰にも言いませんでした。プレスリリースもせず、誰にも気付かれないように、この世界から身を引くことにしたのです。ボックは37歳になっていました。
「4-3.ハイルブロンから解き放つロックの嵐」では、ボックが主演のオファーを受けたのにもかかわらず断った映画「マルコ・ポーロ」のエピソードが紹介されています。1983年、ボックは「猪木ツアーで詐欺行為を行い、投資家から不当に資金を奪い取った」という容疑で逮捕され、刑務所の中にいました。12月、クリスマスの夜、レーゲンスブルク大聖堂で少年合唱団が歌う「サイレント・ナイト」が刑務所のスピーカーから流されました。多くの房からは、鼻をすする音が聞こえ、聖なる夜の寂寥感を増幅させたといいます。談話室のテレビでは、ケン・マーシャル主演の映画「マルコ・ポーロ」が放映されていたのです。ボックは思いがけずそれが目に入ってしまい、一気に疲れた気分になってしまったそうです。
そのとき、ボックは「私がもし、『マルコ・ポーロ』の出演オファーを受け入れていたら、スクリーン上でヒーローとなり、また次の映画を撮っていただろう。シュワルツェネッガーやスタローンと並ぶスターになれたのではないかという思いを捨てきれなかった。そして、私の背景にある“元プロレスラー”という偏見は完全に消え去っていただろう」と思ったそうです。そうだとしたら今回の事件でも、間違いなく執行猶予付きの判決で済んだはずだと考えました。ボックは、「信じられないようなビッグチャンスのオファーを『撮影時間が長い、結婚生活が崩壊するかもしれない』という理由で断った。本当に愚かだった。そんな、もうどうにもならない過ぎ去ったことに思いをめぐらし、落ち込んでしまった」と述べるのでした。じつに素敵なエピソードですね。
「訳者あとがき」の冒頭を、沢田智氏は「2021年、ローラン・ボックの自伝『BOCK!』がドイツで発売されたことをネットニュースで知りました。しかし、日本語版の出版に関する情報は待てども一向に流れてこず、気になりながらも時間だけが過ぎていきました。それでも読みたいという思いは募るばかりで、2023年の秋、ついに『BOCK!』の原書を入手することに決めました」と書きだしています。この本はローラン・ボック本人による「自伝」(正確には、ボックの口述をライターがまとめたもの)ですので、多少の誇張や自己弁護、脚色が含まれている可能性はあると思うとしながらも、沢田氏は「一方で、当時のプロレスマスコミが正確に伝えきれていなかった事実もあるかもしれません。そうした点を意識しながら読むことで、より深く興味を持って読むことができました」と述べています。
沢田氏は、「ローラン・ボックは、どちらかといえばマイナーで、マニア好みのプロレスラーです。スタン・ハンセンやアブドーラ・ザ・ブッチャーのように広く知られている存在ではないため、このレスラーに関心を持ってくださる方を見つけること自体が、大きなハードルでした。しかし、出版社の担当者からは、『ターゲットが狭い分、的を絞って伝えれば、届いたときには確実に支援につながる。それはむしろ強みです』と励ましの言葉をいただきました。その言葉を信じて、活動を続けてきました」と述べておられます。クラウドファンディングで本を出版するのは大変なことだと思います。それなのに沢田氏は、自ら翻訳も担当し、460ページを超える堂々たるハードカバーの本書を世に送り出しました。本書のおかげで、ヨーロッパのプロレス事情を知ることもできましたし、かの「シュツットガルトの惨劇」の真実を理解することもできました。大満足です。沢田智氏に心から拍手を送りたいです。最後に「欧州最強プロレスラー」であったローラン・ボック氏の死を悼み、その魂が安らかであることを祈ります。