- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2015.05.11
『新装版 比較文明』伊東俊太郎著(東京大学出版会)を読みました。
著者は1930年生まれの文明史家です。東京大学名誉教授、国際日本文化研究センター名誉教授、麗澤大学名誉教授であり、日本における比較文明論の第一人者として知られます。『唯葬論』に「文明論」および「文化論」の二章を設けることになり、「文明と文化の違い」について考えていました。それを「京都の美学者」こと秋丸知貴さんに話したところ、最良のテキストとして本書を紹介して下さったのです。なお、秋丸さんには『ポール・セザンヌと蒸気鉄道―近代技術による視覚の変容』 (晃洋書房)という著書があり、比較文明学会研究奨励賞(伊東俊太郎賞)を受賞されています。
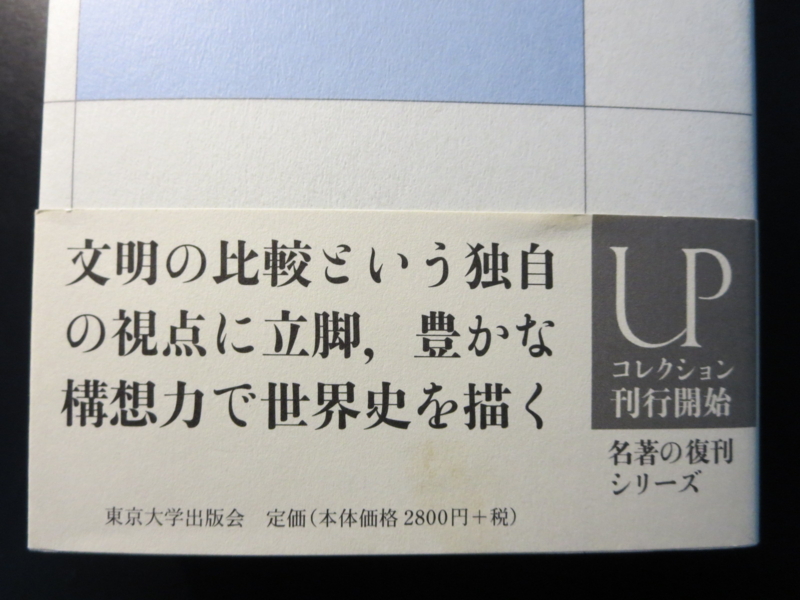 本書の帯
本書の帯
本書は東京大学出版会の名著の復刊シリーズである「UPコレクション」の1冊です。もともとは1985年に刊行された本ですが、2013年に「新装版」として復刊されました。帯には「文明の比較という独自の視点に立脚、豊かな構想力で世界史を描く」と書かれています。
本書の「目次」は、以下のようになっています。
「はじめに」
(1)比較文明論の枠組
1.文化と文明
2.地球的文明史に向かって
3.新しい人類史の時代区分―五つの「革命」について
(2)比較科学史の射程
4.比較科学史の基礎視角
5.比較数学史への途
6.自然の概念―東洋と西洋
(3)地中海世界―イスラムとヨーロッパ
7.地中海文明の構造
8.十二世紀ルネサンス―西欧文明へのアラビアの影響
9.地中海世界の風景
(4)比較文明論の対話
10.比較文明学の建設(対談/梅棹忠夫)
11.比較思想の地平(対談/中村元)
12.地球時代の文明史像(対談/吉沢五郎)
結び「世界学」のすすめ
「あとがき」
「新装版あとがき」
1「文化と文明」に、わたしが知りたかった文化と文明(cultureとcivilization)の違いがわかりやすく説明されていました。まずは「culture」について以下のように書かれています。
「cultureは、もともとラテン語の動詞colereに由来し、その未来分詞形から導かれた名詞がculturaである。colereとは『世話をする』『耕す』『栽培する』『養育する』などの意味をもつが、その根本義は『世話をする』であり、『土地の世話をする』ことから、『耕作』cultura agri,agriculturaという言葉が生じ、『動植物の世話をする』ことから『栽培』『養殖』の意味になり、ついにキケロでは、『心の世話をする』ものとしての『哲学』を指す言葉にもなる(cultura animiphilosophia est)。われわれの『カルチャー』が『教養』という意味をもつのも、こうした『心の世話、培養』ということとつながりをもつであろう。かくしてculturaはまず『耕作』をも意味し、ついで動植物の『栽培、養殖』をさすものとなるが、さらには『心の培養』、つまり『教養』をも意味するものとなった」
これに対して「civilization」については以下のように書かれています。
「civilizationは、ラテン語のcivis,civilisに由来し、その抽象名詞がcivilisatioである。civisは『市民』を意味し、civilisは『市民の』という形容詞であり、civilisatioはそうした市民的身分をもつこと、またはそれをもつような状態になることをいう。したがってcivilizationは何よりも『都市』civitasの概念と結びつき、都市における市民の政治的権利を内包すると同時にそうした市民にふさわしい品位や洗練さをも意味するものであった」
著者は、文化と文明について、以下のように2つの考え方を示します。
「1つは、文化と文明は本質的に連続したものであり、文明は文化の特別発達した高度の拡大された形態であるとするものである。したがって最初の原初的な状態は”文化”であり、それがある高みにまで発展して、広範囲に組織化され制度化されたものになると”文明”になるという考え方である。たとえば『エスキモー文化』とはいうが、『エスキモー文明』とはいわない。またアフリカのマンデ族の文化とはいうが、マンデ族の文明とはいわない。また石器時代の『アッシュール文化』とはいうが、『アッシュール文明』とはいわない。それに対してもっと広範囲に発展して高度に組織化され、もっと全体的な大きなボディをなしてきたものには、たとえば『エジプト文明』『中国文明』『ヨーロッパ文明』というような言い方をする。これが主としてアングロサクソン系の文化人類学などで用いられる用法ではないかと思う」
それでは、もう1つの考え方とは何か。
「もう1つの”文化と文明”に対する考え方は、”精神文化”と”物質文明”というように、これが連続的なものではなく、かえって対立したものとして把えるものである。つまり哲学、宗教、芸術のような精神文化と、科学、技術というような物質文明は本質的に異なっており、一方は内面的なものであり、他方は外面的なものであり、一方は個性的なものであり、他方は普遍的なものであり、一方は価値的なものであり、他方は没価値的なものである、というような対立でとらえていく。これは主としてドイツの文化哲学や文化社会学の用法で、これが日本語の”文化”や”文明”のニュアンスにも入っているのではないかということは前にも述べた。もっとも日本語のなかには第一の”文化”や”文明”の意味も、はっきりとは自覚されてはいないが、やはり併存しているように思う」
著者は、世界のあらゆる文化・文明の発展は5つの段階を経てきたと述べます。5つの段階とは、以下の通りです。
「人類がこれまで経験してきた巨大な文明史的転換期とは、人類革命(人類の化成)、農業革命(農耕の発見)、都市革命(都市の形成)、精神革命(哲学や普遍宗教の誕生)、科学革命(近代科学の成立)の5つである。そして現在は、5番目の『科学革命』が1つの袋小路に入って新しい文明の形態が模索されている6番目の大きな転換期だろうと思う」
著者のいうように「精神文化」と「物質文明」という対比で考えると”文化と文明”の違いが良く理解できます。著者は以下のように述べます。
「”文化”というのはこの立場からすれば、精神的なもので、心の内部に基盤をもつものである。それに対して”文明”のめざすものは物質的条件の改善、生活の便宜とか快適さとかであって、いわば精神の深部ではなく、外面的なものにかかわる。前者は精神的・内面的なものであり、後者は物質的・外面的なものをいうことになる。それから”文化”には中心があって、そこに凝集していくような性質であるに対して、”文明”は拡散し拡大していく性質をもっている。”文化”は民族的であり、”文明”は普遍的であるというのもこのことと関係している。また”文化”は本質的に魂の救済を求めているのに対して”文明”は物質の享楽を求めているともいえよう。したがって、別の言葉でいえば、”文化”では生きがいが問題になり、”文明”では便利さが問題になる。そして”文化”を担うものは哲学、宗教であり、”文明”を促進するものは科学、技術ということになる」
これを著者は、以下のようにまとめています。
「”文化”は精神的、内面的、求心的、民族的、そして魂の問題であり、それは哲学や宗教が深めていくものである。”文明”は物質的条件の改善発展であり、外面的、遠心的、普遍的であり、そして生活の便利さを求めていくもので、それを進めるのは科学技術である」
そして、「文化と文明」の最後に、著者は「精神文化」と「物質文明」との、「心」と「物」とのあるべき調和を実現することが本来の人間だろうとして、以下のように述べています。
「われわれは文明の進歩の名において非常に物質の側にかたよってしまって、精神的なものを忘れかけている。現代は進歩の果てにあまりにも非人間化して精神の内部が荒廃している。学校の教育でもそうだと思うし、会社での生き方も、家族のあり方もそうである。こうした状況をもう一度反省し”文明”を本当の意味で人間化すること、別の言葉でいえば”文明”のなかにこの意味での”文化”を生き返らせることが重要ではないだろうか。これは「物」と「心」、科学・技術と哲学や宗教をそのあるべきすがたに統合することを意味する」
ちなみに、本書の続編ともいえる著者の『比較文明と日本』(中央公論社)の第2章第2節の「比較文明論の枠組み」でも「文化と文明の違い」が論じられています。その要約は、(1)「文化」は風土に根差した特殊なもので「文明」はそれが高度に抽象化された普遍的なものであること、(2)「文化」は精神的なもので「文明」は物質的なものであること、の2点です。また、同書で著者は以下のようにも述べています。
「『文明』がハードであり、『文化』がソフトであるといわれるのは、正しいであろう。この二つのものは互いに相互作用を及ぼしているが、いったんハードとしてシステム化された文明は、しばしばそれを生み出した文化から独立し、他の文化に取り入れられる。これが『文明移転』である」
産業のレベルで「文化」と「文明」について考えてみると、一般にサービス業は文化産業であり、製造業は文明産業であると考えられます。しかし、わたしはサービス業の中にも文化産業と文明産業があると思います。たとえば、わたしの生業である冠婚葬祭業などは明らかな文化産業であると思います。結婚式場や葬祭会館を各地で多店舗経営するという冠婚葬祭チェーンであっても、やはり地域によって儀式やサービスの内容、あるいは参列者数、単価などに大きな差があります。わが社は以前は北海道から沖縄までの全国展開を目指していましたが、「冠婚葬祭とは地域色豊かな文化であり、均一的な文明ではないのだ」ということに気づいてからは、北九州、北陸、沖縄など当社の企業文化と相性の良い営業エリアだけに絞り込みました。世界中どこでも同じ店を展開できるマクドナルドやスターバックスは「文明移転」を基本とした文明産業であると思います。しかし、「文化」を意味する”culture”の語源である”cultivate”は「耕す」ということ。冠婚葬祭業とは、まさに地域の儀式文化を耕すことにほかなりません。それはいわば「垂直」を志向した産業であり、全国展開という「水平」を志向する文明産業とは一線を画するのです。
さて、本書『新装版 比較文明』に話を戻しましょう。2「地球的文明史に向かって」では、世界史の西欧的パターンが以下のように述べられています。
「今日ほとんど通念化されているといってよい西欧中心主義的な世界史像とはどのようなものであるかといえば、それは多くの歴史教科書に書かれているように、まず歴史のはじめにオリエント(メソポタミア・エジプト)文明の発生があるが、ついでこの素朴な段階を克服した偉大なギリシア文明がある。それがヘレニズムやローマ世界にうけつがれて地中海文明となり、近代の西欧文明はこの地中海文明の直系の嫡出子ということになっている。そしてその後の世界史とは要するに、この西欧文明が非西欧諸国に浸透拡大してゆく過程にほかならないとみるのである。この〈オリエント文明→ギリシア文明→ローマ地中海文明→西欧文明→西欧文明の拡大〉という世界史の単線的系譜は、今日ではすでに常識化した見解となっているが、しかしこれは実のところ19世紀におけるヨーロッパの世界支配という既成事実ができあがった時点で、西欧の歴史学者によってつくりあげられた、西欧中心のいわば身勝手な一面的世界史像なのである」
ここに「ギリシャ」→「ローマ」→「キリスト教的近代ゲルマン諸国家」というヨーロッパ中心の、しかも西欧近代国家の成立を究極の目標とする国家史観に基礎が据えられました。その後の西欧の世界史像は本質的にこのヘーゲル的立場を出ていないとして、著者は次のように述べます。
「たとえば『哲学は歴史の敵である』と考えて、ヘーゲルとは反対に理念や普遍者から恣意的に歴史を構成するのではなく、かえって個体的なものから普遍的なものを導出することを主張した『経験的歴史主義者』ランケの世界史も、人類史の総体を把握すると称しながら、依然として西欧中心主義に立脚して、オリエントにはじまり、ギリシアを経てローマに至り、このローマ的なるものと融和した『ローマ的・ゲルマン的諸民族』の成立を世界史の骨組としている」
しかしながら、ランケとほぼ同じ時代に、ヘーゲル、ランケを貫いて19世紀ヨーロッパ史学の共通の地盤となっていた「国家」や「民族」に主体をおく歴史でない考え方が登場しました。それは、経済的な関係、すなわち生産力と生産関係の矛盾に歴史の発展の原動力を認める考え方でした。そのような考え方が、カール・マルクスの唯物史観によって提出されたのです。著者は、マルクスの唯物史観について以下のように述べます。
「マルクスはヘーゲルの普遍的精神の過程を経済社会のメカニズムにおきかえ、国家や民族間の軋轢や闘争が歴史の発展を支えるのではなく、社会的関係、階級闘争こそ歴史の主題であるとする。ランケがヘーゲルの国家史観、民族史観をうけついだのに対し、マルクスがヘーゲル批判から出発しながら、こうしたナショナリズム的『国家史観』をのり越えて新しいインターナショナルな『社会史観』ともいうべきものを打ち出したのは対蹠的である。しかしここに注目すべきことは、このマルクスの歴史観も依然として西欧中心主義の上にのっているものであるということである。彼の描いた世界史のコースは、周知のように〈アジア的生産様式、古代奴隷制、中世封建制、近代資本主義〉という4つの生産様式の発展段階によって把えられるが、これは明らかにさきの西欧的世界史像を土台とするものであり、ここでも、中国やインドはまたしても『アジア的停滞性』の一語で片づけられ、この発展の最初の段階にすべて封じ込まれてしまっているのである」
このように最初は「文明と文化の違い」について知りたくて本書を読み始めたのですが、ついには歴史観についての哲学的思考にまで至りました。思うに、戦後日本の「思想の巨人」であった吉本隆明の『共同幻想論』は、マルクスの唯物史観に対するアンチテーゼでした。そして、『共同幻想論』は岸田秀氏の『唯幻論』や養老孟司氏の『唯脳論』へと流れてゆきました。いずれも唯物史観に異を唱えています。わたしは、さらに突き進んで「唯葬論」というものを考えています。本書からは、多くを学ばせていただきました。本書を推薦して下さった秋丸知貴さんに感謝いたします。
