- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2015.06.03
『〈凡庸〉という悪魔』藤井聡著(晶文社)を読みました。
「21世紀の全体主義」というサブタイトルがついています。著者は1968年奈良県生まれ、京都大学土木工学科卒。東京工業大学教授などを経て、現在は京都大学大学院工学研究科教授(都市社会工学専攻)です。2011年より京都大学レジリエンス研究ユニット長、ならびに第二次安倍内閣・内閣官房参与(防災減災ニューディール担当)に就任。
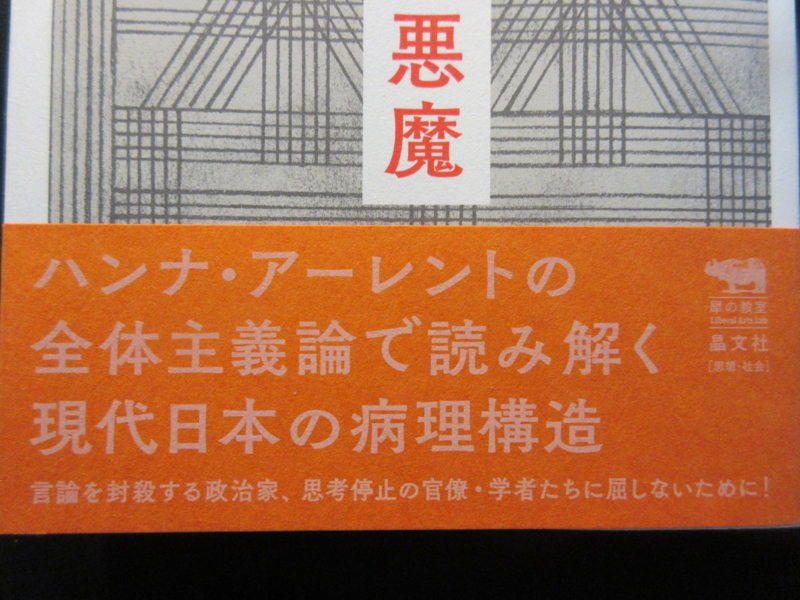 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、「ハンナ・アーレントの全体主義論で読み解く、現代日本の病理構造」「言論を封殺する政治家 思考停止の官僚・学者たちに屈しないために!」と書かれています。またカバー前そでには、以下のような内容紹介があります。
「『思考停止』した『凡庸』な人々の増殖が、巨大な悪魔=『全体主義』を生む。21世紀の全体主義は、ヒトラーのナチス・ドイツの時代と違い、目に見えない『空気』の形で社会を蝕む。ハンナ・アーレント『全体主義の起原』の成果を援用しつつ、現代日本社会の様々な局面で顔をのぞかせる、『凡庸という悪』のもたらす病理の構造を鋭く抉る書き下ろし論考。思考停止が蔓延する危機の時代に読まれるべきテキスト」
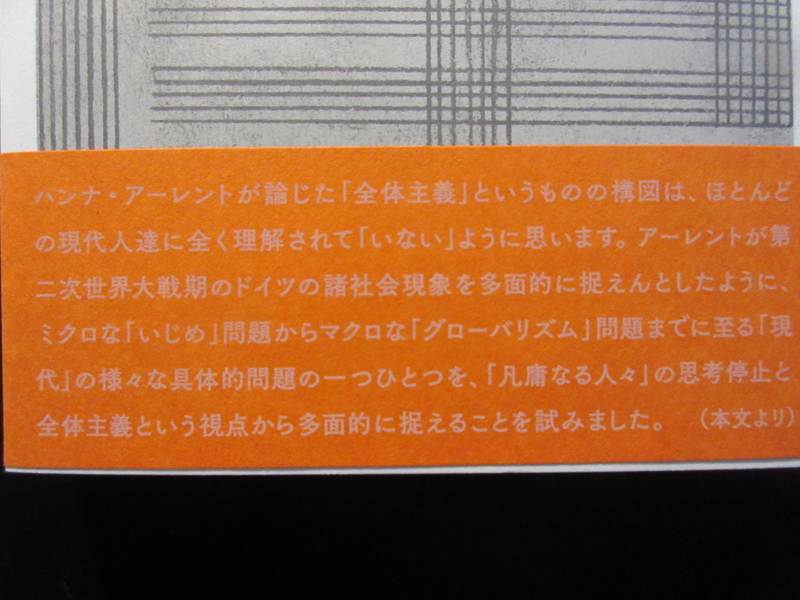 本書の帯の裏
本書の帯の裏
本書の目次構成は、以下のようになっています。
序 章 全体主義を導く「凡庸」な人々
第1部 全体主義とは何か?─ハンナ・アーレントの考察から
第1章 全体主義は、いたって特殊な「主義」である
第2章 ナチス・ドイツの全体主義
第3章 〝凡庸〟という大罪
第2部 21世紀の全体主義─日本社会の病理構造
第4章 いじめ全体主義
第5章 「改革」全体主義
第6章 「新自由主義」全体主義
第7章 グローバリズム全体主義
おわりに 「大阪都構想」と「全体主義」
序 章「全体主義を導く『凡庸』な人々」で、著者は哲学者ハンナ・アーレントが、全体主義の中心にある概念を「テロル」と表現したことを紹介し、次のように述べます。
「これは、『従わぬ者に対して仕向ける、あらゆる暴力』(および、それに対する恐怖)を意味しています。つまり、全体主義は、その究極において必ず大殺戮に行き着くのです。いわば、『兎に角!』という押しつけを極限にまで突き詰めれば、それに従わぬ者を殺める他、なくなっていくわけであり、実際に、先の大戦では、数百万人、数千万人という人々に対する殺戮をもたらしたわけです。つまり全体主義というものは、文字通りの世界史上最大の『悪魔』なのです」
第1章「全体主義は、いたって特殊な『主義』である」では、著者は全体主義について以下のように述べます。
「全体主義というものは、表面的には、テロルを含めた、強大な力を持つものであるとしても、原理上、『カラッポ』(empty/エンプティ)なのです(哲学的な言葉を使うなら、全体主義の本質は、その定義上、必然的に『ニヒリズム=虚無主義』、すなわち、真理や道徳的価値の客観的根拠を認めないという立場を取らざるを得ない、ということになります)」
第2章「ナチス・ドイツの全体主義」では、ハンナ・アーレントが描写した全体主義の起源は大きく言って(1)反ユダヤ主義(2)帝国主義(3)大衆化の3つであると紹介し、それらのものが折り重なってできあがったものがナチス・ドイツにおける全体主義であると分析。そして、その展開を著者は次のように1つの文章で表現しています。
「(1)『反ユダヤ主義』と共鳴し合うことで深化した『選民思想』が、
(2)ドイツの国内的な経済問題を解消するために求められていた(諸外国・他民族を暴力=テロルに基づいて侵略し、『官僚主義』に基づいて支配する)『帝国主義』の展開を大きく促すと共に、
(3)当時ドイツ国内で階級社会が崩壊することで立ち現れていた『大衆人達』が、それらの国家政策を徹底的に支持・参加することで大きく展開していったのが、ヒトラーを中心としたナチス・ドイツにおける『全体主義運動』であった」
また、アーレントの『イエルサレムのアイヒマン』という書籍に触れ、著者は次のように述べています。
「そもそも人間というものは自らの意志で行った行為については責任を感じ、罪の意識を持つものですが、他者の命令にただ従って行うことについては、仮にその自らの行為によって何千人、何万人の人々が殺められようとも、責任を主観的には感じ得ないのです」
第3章「〝凡庸〟という大罪」では、「考える責務」という十字架はどこから来たのかという問題が取り上げられます。著者は「そもそも『考える』という行為は、人間だけに見られる固有の振る舞いです。他の自然界の動物は『考える』ことはしません。つまり、『考える責務』なる十字架を背負っているのは、様々な動物の中でも、人間だけなのです」と述べています。そして、「人間」について、著者は以下のように書いています。
「人類学者のエドガー・モーリンは、人間とは、不条理な幻覚を抱く唯一の種族であると論じています。どんな動物も、必要以上に殺生はしません。どう猛な虎やライオンも、満腹になれば、他の動物に見向きもしなくなるのです。しかし、人間だけはそうではありません。恨みや嫉み等、本能図式には全く記載されていないような過剰な意味を持つ存在であり、その結果、必要以上の殺生を繰り返すことができる存在なのです。こうした背景から、しばしば人類はホモ・サピエンス(知恵ある人)ではなく、ホモ・ディメンス(狂った人)と定義すべきではないかと指摘されています。つまり、人間は、他の動物が当たり前に持っている『本能図式』をなくしてしまった存在なのです」
「人間」の定義に関しては、わたしは『唯葬論』において、「ホモ・サピエンス」(賢いヒト)や「ホモ・ファーベル」(工作するヒト)などを紹介しました。オランダの文化史家ヨハン・ホイジンガは「ホモ・ルーデンス」(遊ぶヒト)、ルーマニアの宗教学者ミルチア・エリアーデは「ホモ・レリギオースス」(宗教的ヒト)を提唱しました。同様の言葉に「ホモ・サケル」(聖なるヒト)というものもあります。わたし自身は、「ホモ・フューネラル」(葬るヒト)を提唱しました。しかし、「ホモ・ディメンス」(狂ったヒト)というのは初めて知りました。さらに、著者は「人間」について以下のように述べています。
「他の動物なら当たり前のように持っている天から与えられた本能という羅針盤を持たぬまま、人間は大海に投げ出されてしまったのです。だから人間は、生きていくためには四六時中、『思考』せねばならなくなったのです。羅針盤なき航海で、星の位置や風向きなどを把握しながら考えることを一切とりやめた船乗りに訪れるのは、遭難の果ての『死』以外に何もありません。かくして、私たちは、『考える責務』なる十字架を背負ってしまったのです」
そして、本能を持たない人間が得たものは「文化」でした。著者は、以下のように述べています。
「私たち人間の航海である『生きる』ということそれ自身のために必要な最低限の知識こそが、長い歴史と伝統で育まれた『文化』なのです。挨拶や返礼や謝罪の仕方やその際の言葉使い、要求や譲歩のはかり方やその表現方法、そして、親愛や隣憫の情の伝え方等、そうした『言葉』を中心とした先人達からの英知としての文化こそが、私たちが失ってしまった本能の代わりに、私たちの日常の振る舞いを指し示す、本能図式の代替物となり得るのです」
このあたりは岸田秀氏の「唯幻論」の影響を強く感じてしまいますが、著者は「本能の代用品としての『文化』」について以下のように述べます。
「人類は、こうして、本能図式をいったん壊して『錯乱』することとひき替えに、自らの手で作りあげることができる凄まじい柔軟性を持ち得る『文化』を手に入れ、それを通して大きな発展を実現することができるようになったのです」
著者は「あらゆる領域で全体主義が蔓延する現代」で、その主張を以下のようにまとめています。
「我々人間が、人様に迷惑をかけずに、つまりプチ・テロルを仕掛けることなく他者と関わるためには、安定した社会状況の中でその社会の伝統や文化を一定程度身に付けておくと共に、不安定な状況下でも不都合無く振る舞い得るために、物事を『考える』姿勢を常に保ち続けることが求められています。つまり、我々は、人間として他者と交わりながら生きていく上では、一定程度の伝統、文化、規範という『運転知識』と、それを踏まえながら臨機応変に頭を使って考えながら対応し続ける、『思考能力』(ability to think)という『運転技術』の双方を所持しなければならないのです。したがって、運転についての知識と技術を持つ者だけに『運転免許』が付与されるように、伝統、文化、規範を『常識』として学び、『考える能力』を一定程度鍛え上げられた人間だけが、この社会の中で生きていく資格を得ることができるのです」
そして、「全体主義」について、著者は以下のように総括します。
「いわば全体主義とは、人類が人類である限り逃れ得ることができない宿命なのです。この全体主義という宿命を避けるためには、我々は常に『考え』続けなければなりません。
もしも我々が『考える』という十字架から逃れようとすれば、我々はすぐさま、自らの誇りや尊厳、さらには全ての人格を溶解させ、どろどろのまっ黒な辺泥のような液体と化し、互いに溶け合い混ざり合い、あらゆるおぞましき化学反応を起こしつつ、『全体主義』という巨大な悪魔をつくりあげてしまうのです。つまり人畜無害に見える凡庸な人々こそが、意図せざる内に巨大なる『悪魔』そのものとなるのです」
第6章「『新自由主義』全体主義」では、市場理論を提唱し、古典派経済学の源流となったアダム・スミスが、じつは人間の「道徳感情」を見つめ続けた学者であった事実を指摘し、著者は次のように述べます。
「ですから、彼が、倫理や道徳など不要で、市場を自由化しさえすれば、皆が幸せになると考えていたことなど、万に1つもありません。あくまでも彼は、人間が『道徳的に振る舞う』ということを前提とする社会がそこに存在し、その社会が存在する限りにおいて、『自由』な競争があれば人々はより幸福になれる、と考えていたに過ぎません。こうしたアダム・スミスの理論は、誰もが納得しうる極めて常識的な考え方です」
今日、「新自由主義」と呼ばれる考え方が注目を集めています。著者は、その考え方の大きな特徴は「道徳論が不在」であり、「市場に任せさえすればそれでよい」と考える市場原理主義という、思考停止を半ば強要するような極めて「全体主義的」な色彩を強く帯びたものであると指摘し、次のように述べます。
「この新自由主義がはびこればはびこるほどに、人類は不幸になっていきます。そもそも政治哲学で一般に言われるように、秩序を守るためには、『カネ、チカラ、コトバ』の3つの要素が必要です。チカラとは『政治や権威、武力』であり、コトバとは『道徳や倫理、言論』です。だから、『カネ』の力だけで何もかもを解決しようとする『市場原理主義』では、秩序を守ることなどできるはずはないのです。新自由主義が浸透し、様々なものが改革され、自由化されていけば、社会の秩序は乱れ放題になっていきます」
「道徳論が不在」で、歪んだ新自由主義がはびこっているといえば、わたしは日本の葬儀業界が思い浮かびます。家族葬、直葬、0葬・・・・・・一連の「薄葬」の背後には、親が亡くなったら子がきちんと送り出すといった「道徳論」が決定的に欠けています。
そういえば、本書の存在を教えてくれたのは、「出版界の真実一路」こと現代書林の坂本桂一社長でした。同社からはもうすぐ『0葬』への反論書である『永遠葬』を上梓しますが、「葬式は、要らない」とか「0葬」といった考え方は一種の全体主義であると思います。そこには明らかに「思考停止」と「全否定」による根絶主義があるからです。
本書の最後では、おわりに「『大阪都構想』と『全体主義』」として、橋本徹氏の「大阪都構想」に対する批判が大々的に展開されています。わたしのブログ記事「大阪都構想の終焉」に書いた、ルサンチマンを抱えた凡庸な大衆人達は、アノミーのままに「リセット願望」という俗情を持ち、「とにかく改革すればいい」という改革全体主義に走ったのです。極端な「改革全体主義」は「0葬」につながっています。人が亡くなっても葬儀を行わず、そのまま遺体を火葬場で焼き、遺骨や遺灰も火葬場に捨ててくるという行為は、「アノミー → リセット願望 → 0葬」という構図そのものです。
わたしには、本書が「0葬」批判の書に思えてなりませんでした。
