- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2015.09.17
『皇室はなぜ尊いのか』渡部昇一著(PHP文庫)を読みました。
「日本人が守るべき『美しい虹』」というサブタイトルがついています。
2011年9月にPHP研究所より刊行された単行本の文庫化です。
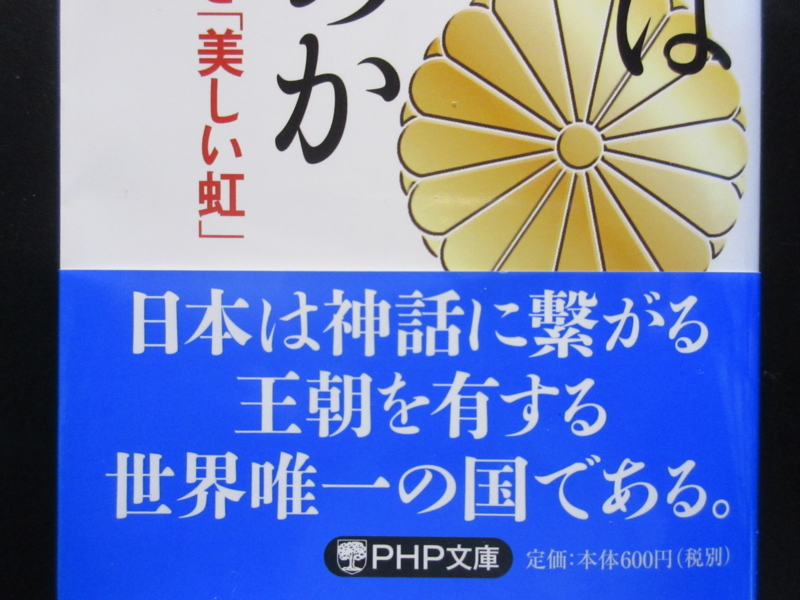 本書の帯
本書の帯
表紙カバーには菊の御紋のイラストが使用され、帯には「日本は神話に繋がる王朝を有する世界唯一の国である」と書かれています。
またカバー裏には以下のような内容紹介があります。
「神話に起源をもつ皇室は、世界がうらやむ日本の宝。それは、ギリシア神話のアガメムノンの末裔が、いまもヨーロッパの王室として繋がっているのと同じことだから―。本書は、幾度となく訪れた『皇統の危機』を乗り越え、二千年以上にわたって途切れることなく続いてきた皇室と日本民族の紐帯の歴史を、『美しい虹』のごとく描き出した著者渾身の力作。日本人が守り受け継ぐ国史がここにある」
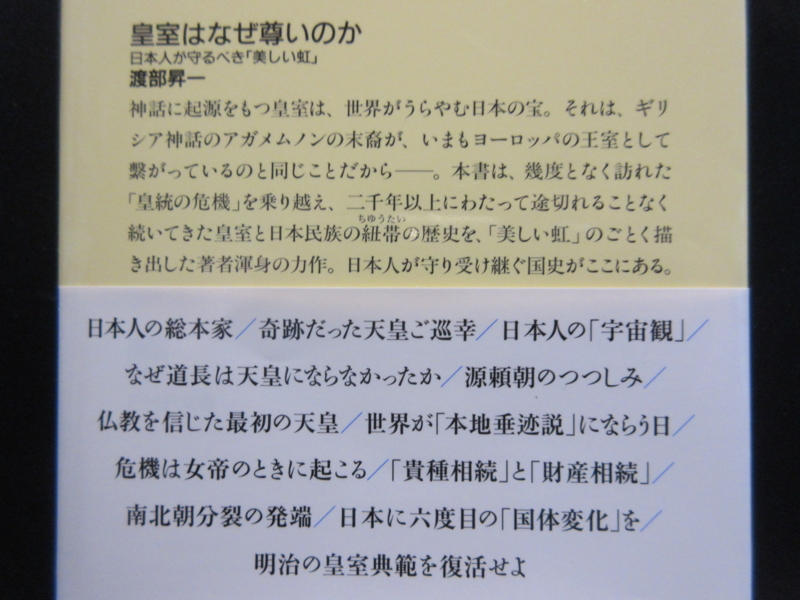 本書のカバー裏と帯裏
本書のカバー裏と帯裏
本書の「目次」は以下のような構成になっています。
第1章 外国人から見た皇室
第2章 日本史のなかの皇室
第3章 皇統はなぜ保たれたのか
第4章 皇室伝統を再興するために
第5章 小林よしのり氏 女系論への弔鐘
「あとがき」
第1章「外国人から見た皇室」の冒頭には、「日本人の総本家」として以下のように書かれています。
「皇室について、いまの日本の子供たちがどういうイメージをもっているかは分からないが、戦前、私たちが子供だったころは、皇室は『日本人の総本家』というイメージで共通していたように思う」
学校に行くようになると、「皇室は日本人の総本家」というイメージがいっそう明瞭になってきます。たとえば、歴史の授業で鎌倉幕府を開いた源頼朝について習うとします。源氏のルーツをたどれば、皇室から出て「源」姓を賜った家だということがわかります。子供たちは「なるほど、皇室が本家なんだ」と納得するわけです。
戦後、大人になった著者はドイツに留学します。
そこでドイツ人から「日本人はトロイな国民だ」と言われます。
「トロイな国民」とは「忠実な国民」という意味ですが、この「忠実」には「忠誠を忘れなかった」というニュアンスがあり、つねに皇室への忠誠を忘れなかった日本人にぴったりの表現でした。
ここで著者は「皇室が日本のお国自慢の種になるのではないか」とひらめきます。しかし、向こうの知らないことは自慢になりませんから、向こうの知っていることに合わせて表現しなければなりません。著者は述べます。
「そこで思いついたのが、ギリシア神話である。トロイ遺跡をドイツ人のシュリーマンが発見したこともあり、ドイツで一番有名なギリシア神話はトロイ戦争だ。トロイ戦争の英雄であるアガメムノンはミケーネの王様で、ギリシア軍を率いた葬対象、王のなかの王であることはよく知られている。そのアガメムノンの父親はプリステネス。この人はあまり有名ではないけれども、その親がアトレウス、その親がペプロス、その親がタンタウルス。タンタウルスぐらいになると神話の時代になり、タンタウルスの親がギリシア神話の最高神、ゼウスである」
日本もまた、初代神武天皇の上は神話の神々につながっています。
著者は「皇室を語るときに、アガメムノンと神話の話を使えばいい」と考えついたわけですが、「いまにして思うと愉快である」と述べています。
著者はドイツ人に「神武天皇から五代さかのぼると皇室の先祖として崇められている伊勢神宮の神様に辿り着く」ことを伝えました。そして、「アガメムノンの子孫が堪えずに、いまもギリシアの国王であったとしたならば、どうであろうか」と問いました。その反応を、著者は次のように書いています。
「誰もがアガメムノンを知っているし、いまのギリシアの状況も知っているから、『ああっ』という表情になる。彼らにしてみれば、日本は19世紀のペリー以後、急に世界史に躍り出た新参者という印象が強い。しかし、『アガメムノンの子孫が現在まで続いていたら・・・・・・』というイメージを通して眺めさせれば、日本が古い国であることを知らしめることができたのである」
第2章「日本史のなかの皇室」でも、「神話と歴史がつながっている国」として、著者は以下のように述べています。
「神話に連なる歴史を有する国は、世界にほとんどない。現代のゲルマン人にとって神話は神話であり、ギリシア人にとっても神話は神話である。いずれも歴史と関係がない。司馬遷が『史記』を書いたときに神話・伝説の類をはずしたとされるように、シナ人にとっても神話と歴史は切れていて、神話から歴史がつながるという発想はなくなっている。したがって、シナの歴史を考える場合にも、神話を考慮する必要はない」
しかし、神話と歴史がつながっている民族は他にもあります。
それはユダヤ人です。著者は以下のように述べています。
「強いていえば、神話と歴史がつながっているのはユダヤ人である。ほんとうに7日間で宇宙ができたと思っているかどうかはともかく――つまり『創世記』は別として――、旧約聖書の後半部分はそのまま信用し、エジプトでの奴隷状態からモーゼが”約束の地”パレスチナに連れてきてくれたと信じている。ユダヤ人にとって神話は神話ではなく、歴史につながるものである。だからこそユダヤ教を必死になって守る。したがって『ユダヤ人、存続六千年』なら理解できるかもしれない。ただし、ユダヤ人は離散依頼、イスラエルの建国まで国家をもっていなかった。国の歴史として神話が重要だといえるのは日本しかないと私は思う」
第4章「皇室伝統を再興するために」では、「皇室が『馬から落ちそうだったとき』」として、著者は以下のように述べています。
「皇室と日本の歴史をあらためて振り返ったとき、G・K・チェスタトンがローマ法王庁について述べた言葉を思い出す。19世紀イギリスの大歴史家トマス・マコーレイ卿の言によると、『ヴェスビアス火山が火を噴き、ローマのコロシアムでライオンや豹が踊っていたころから、ローマ法王庁はある』。聖ペトロに始まるので法王庁の歴史も2000年くらいだから、偶然にも日本の皇室と同じころに始まったと考えていい」
また、著者はローマ法王庁と皇室について次のようにも述べます。
「教会の存続自体が危ない時代もあった。宗教改革などは、ほんとうにカトリックがなくなってもおかしくなかった。そういう危機的状態から、ローマ法王庁は立ち直っている。チェスタトンはこれを文学的に表現して、『名馬に乗った騎士が、山あり谷ありというところを駆けてくるような感じである』といった。馬から落ちそうなときもあったし、ちゃんと乗っているときもあったが、全体として見ると見事に駆け抜けているというのである。
これは皇室の歴史にもあてはまるだろう。考えてみれば、世界の組織で2000年続いているのは、ローマ法王庁と日本の皇室しかない。だから、似ていておかしくないのかもしれない」
 バーフィールドの言葉を紹介した『永遠の知的生活』(実業之日本社)
バーフィールドの言葉を紹介した『永遠の知的生活』(実業之日本社)
「あとがき」の冒頭には、「一国の歴史、つまり国史とは、それは、その国民の見る「虹」のごときものであるということを、私はオウエン・バーフィールドというイギリス人の小著から偶然学んだ」と書かれています。
バーフィールドの言葉はすでに著者の多くの著書、およびわたしとの対談本である『永遠の知的生活』(実業之日本社)でも紹介されていますが、以下のような内容です。
「歴史的事実は雨後の空中の水滴のごとく無数にある。しかしそこに虹を見るためには、ある一定方向と、ある程度の距離が必要である。歴史的事実という無数の事件の連続のなかに、1つの虹を見ること。それがその国民の歴史、つまり国史であり、その国民の共通の意識表象となるものである」
バーフィールドは、「事実」と「意識」の関係に深い関心と洞察をもっていました。それは「何事も陽にとらえる」というわが信条にも合致します。
バーフィールドは、『見かけの重要さ』という著書のなかでも次のように虹の比喩を使っています。
「虹が向こうに見えるので、そこに行ってみたら虹はなく、あるのは水滴だけである。では水滴は実在するが、虹は実在しないといえるかどうか。素粒子は存在するが恋人は存在しないといえるか。恋人も分析すれば分子になり、さらに分析すれば原子、素粒子になってしまう。科学的アプローチは虹の水滴、つまり恋人の分子、原子に向かう。しかし人間の意識は水滴を見ず虹を見、分子を見ないで恋人を見る」
わたしはバーフィールドの見方に100%賛同する者ですが、著者も「日本の歴史を水滴集団のごとき事実として研究もできるが、1つのユニークな国史として、つまり一種の虹としても見ることができると思う。日本民族の歴史を私が虹のごとく見たのが本書である」と述べています。本書を読めば、日本人が守り受け継ぎ、遥か未来へと繫ぐ国史の核心がわかります。歴史家としても超一流である著者による見事な皇室論だと言えるでしょう。
