- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2015.12.28
『聖と俗』ミルチャ・エリアーデ著、風間敏夫訳(法政大学出版局)を再読しました。
「宗教的なるものの本質について」というサブタイトルがついています。本書は「20世紀最大の宗教学者」と呼ばれたルーマニア出身のエリアーデの代表作とされ、ドイツの「ローヴォ―ルト叢書」から1957年に出版されました。邦訳は法政大学出版局の「叢書・ウニベルシタス」から69年10月20日に初版が刊行されています。わたしが読んだのは78年12月5日に刊行された第9刷で、これまでに何度か読み直してきました。今回、『儀式論』(仮題、弘文堂)を書くにあたり、久々に再読しました。
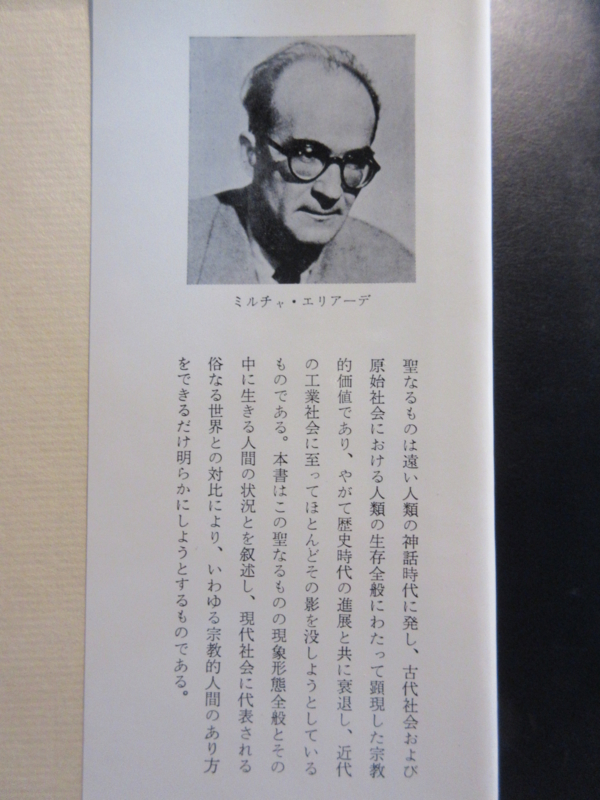 本書のカバー前そで
本書のカバー前そで
カバーの前そでには、著者の顔写真が掲載されています。
顔写真の下には、以下のような内容紹介が書かれています。
「聖なるものは遠い人類の神話時代に発し、古代社会および原始社会における人類の生存全般にわたって顕現した宗教的価値であり、やがて歴史時代の進展と共に衰退し、近代の工業社会に至ってほとんどその影を没しようとしているものである。本書はこの聖なるものの現象形態全般とその中に生きる人間の状況とを叙述し、現代社会に代表される俗なる世界との対比により、いわゆる宗教的人間のあり方をできるだけ明らかにしようとするものである」
本書の「目次」は以下のような構成になっています。
「序言」
第一章
聖なる空間と世界の浄化
第二章 聖なる時間と神話
第三章 自然の神聖と宇宙的宗教
第四章
人間の生存と生命の浄化
付録「宗教学の歴史」
「現代と東洋の宗教」(訳者あとがきに代えて)
「索引、参考書目」
「序言」で、著者のエリアーデは以下のように述べています。
「古代社会の人間は、聖なるもののなかで、あるいは浄められた事物のすぐそばで生活しようと努める。この傾向はもっともなこととして理解される、というのも〈原始人〉およびすべて前近代的社会にとって、聖なるものとは力であり、究極的にはとりも直さず実在そのものを意味するからである。聖なるものは実有に充ちている。聖なる力は実在と永遠性と造成力とを同時に意味する。聖と俗との対照はしばしば現実と非現実あるいは偽の現実との対照として現われる。(もちろん古代語のなかにこれらの現実非現実という哲学用語を見出そうと期待してはならない。)存在し、実在にあやかり、力に充ち満ちてあることを、宗教的人間が熱望する所以もこの故に理解される」
第2章「聖なる時間と神話」では、「模範的典型としての神話」の項の最後に、著者は以下のように書いています。
「神の模範を正確に反復することには2つの意味がある。1つには、人間は神々を模倣することにより、聖なるもののなかに、したがって実在のなかに地位を確保する。他方、神々の模範的行為を不断に再現することにより、世界が浄められる。人間の宗教的振舞いは世界の神聖性を維持するのに寄与する」
儀式には「神話の再現」という一面があります。
結婚式ならびに葬儀にあらわれたわが国の儀式の源は、小笠原流礼法に代表される武家礼法に基づきますが、その武家礼法の源は『古事記』に表現される「日本的よりどころ」なのです。すなわち『古事記』に描かれたイザナギ、イザナミのめぐり会いに代表される陰・陽両儀式のパターンこそ、後醍醐天皇の室町期以降、今日のわが国の日本的儀式の基調となって継承されてきました。日本人は、神々の模範的行為を不断に再現することによって、世界を浄めてきたわけです。
また、第2章「聖なる時間と神話」の「聖なる歴史、歴史、歴史主義」という項の冒頭には、以下のように書かれています。
「宗教的人間は俗なる時間と聖なる時間との二種類の時間を知る。一方は流れ去る時間持続であり、他方は聖なる暦を形成する諸祝祭において回復することのできる、〈一連の永遠〉である。この暦の祭礼の時間は、閉じた円環をなして経過する。それは〈神々の所業〉によって浄められた、歳の宇宙的時間である。そして神々の大業は世界創造であったから、多くの宗教において、宇宙開闢の祝祭は重要な役割を占めている。新年は創造の最初の日に一致する。歳は宇宙の時間的広がりである。一年が経過したとき、〈世界が過ぎ去った〉と人は言う」
じつは、葬儀も世界創造神話を再現したものだといわれます。
1人の人間が死ぬことによって、世界の一部が欠ける。その不完全になった世界を完全な世界に修復する役割が葬儀にはあるのです。特に、古代社会において、王の存在は絶対的なものであり、その死は「世界の死」を意味しました。王が死んだ時点で、それまでの時間と空間が歪むのです。そのため、盛大な葬儀を行うことによって歪んだ時間と空間を破壊し、新たな時間と空間を再創造する必要があったのです。
第4章「人間の生存と精米の浄化」には「移行儀礼」の項があります。
その冒頭で、著者は以下のように書いています。
「移行儀礼が宗教的人間の生活に重要な役割を果たすことは、すでに久しく知られている。移行儀礼の最たるものはもちろん、1つの年齢階級から他の年齢階級への(子供あるいは少年時代から青年への)移行たる、思春期の加入式である。しかし誕生の際、結婚の際、そして死去の際にも移行儀礼が存する。これらもその本質は加入式であるということができよう。なんとなればそれらはみな存在論的および社会的状態の、基本的変化を伴なうからである」
著者は、移行儀礼としての結婚式について以下のように述べます。
「結婚に際してもまた1つの集団から他の集団への移行が存する。新郎は独身者の集団を去って、以後家長の集団に属する。結婚はすべて緊張と危険を意味し、それによって1つの危機を誘発する。それゆえ結婚は移行儀礼によって成就する。ギリシャ人は結婚をtelos、浄化と名づけた。そして結婚式は秘教の儀礼に似ていた」
また著者は、葬礼についても以下のように述べています。
「葬礼は一層複雑である、というのはこれは(生命―あるいは霊魂が―身体を去る)〈自然現象〉だけの問題ではなく、存在論的であると同時に社会的な生活様式の転換であるからである。死者は彼自身の死後の運命を決定する一定の試練を受けねばならぬ。そのうえ、また死者の社会によって承認され、受け入れられねばならない。或る民族では埋葬の儀礼によって始めて死が確認される。慣習通りに埋葬されなかった者は死んだことにならないのである。他の場所では、死は葬礼が行なわれた後に始めて効力を発する。あるいは死者の霊が祭儀上の手続きをへてあの世の新しい彼らの住所に導かれ、そこで死者の社会に受け入れられた刹那から有効となる」
「死と加入式」という項の冒頭では、著者は以下のように述べています。
「加入式においても、英雄伝説においても、また死の神話においても、怪物に呑み込まれるという象徴とその儀礼が重要な役割を果たしている。体腔への帰還という象徴は常に宇宙的な意味をもっている。全世界は新入者と共に象徴的に宇宙の夜へ回帰するが、それは再び新たに創造され、したがって再生しうるためである」
続いて、著者は以下のように加入式について述べます。
「世界発生の神話が治療の目的で誦唱される。病人を癒すためには、彼を今一度誕生させねばならぬ。そして誕生の原型は宇宙開闢である。時の仕事が廃棄され、創造に先行する朝の若わかしい刹那が再び獲得されねばならぬ。それは人間の地平では、人が生存の〈白紙〉、未だ何も汚され損なわれていなかった絶対の太初へ戻らねばならぬことを意味する」
さらに、著者は「死と加入式」について以下のように述べます。
「今やわれわれは、何故―苦悩、死、復活(=再生)―という同一の加入式図式がすべての秘教において、成年式のみならず秘密結社への入会儀礼に際してもまた、くり返されるかを理解する。何よりも明らかなことは、原始社会の人間が、死を、移行儀礼に変えることによって克服しようと努めていることである。言い換えれば、原始人にとって、人間は死により常に、本質的ではなかった生存を捨てるに過ぎない、すなわち人間は何よりも世俗の生命から死去するのである。死は最高の加入式、新たなる精神的生存の始まりと見なされるに至る。さらにそのうえ、出生と死と復活(=再生)とは同一神秘の3つの契機として把握され、古代人はその全精神力を挙げて、これら諸契機の間にいかなる断絶もあってはならぬことを示そうと努めたのである」
「〈第二の誕生〉と精神的生殖」という項の冒頭では、こう述べています。
「死と再生は、高度に発達した宗教においても重要な役割を果たしている。有名な例はインドの祭式である。その目標は死後天界に昇り、神々と共に住み、あるいはさらに神性を獲得することである。祭式によって人は超人間的存在様式を克ち得る。したがってその追求する目標は、古代の加入式の目標と同一の関係に置くことができる。祭主はしかしながらあらかじめ祭官らによって浄められねばならない。そしてこの潔斎は助産婦的構造をもつ加入式象徴を含んでいる。精確に言えば、ディークシャー[潔斎]は祭儀の上で祭主を胎児に変え、再び出生させるのである」
祭主を胎児に変え、再び出生させる!
まさに、加入儀礼の本質を見事に表現していると言えるでしょう。
「現代と東洋の宗教」(訳者あとがきに代えて)では、本書の訳者である宗教学者の風間敏夫氏が次のように書いています。
「宇宙が聖なるものの現われであると全く同様に、聖なるものは人間の内部にも顕現する。この意味で人間は一筒の小宇宙であり、そのあらゆる行動、生理過程に至るまで、人間の生命全体が浄化可能である。しかしながら生まれたままの自然の状態では、人間はこのような真の生存にあずかることが出来ない。古代社会ではそれゆえ成年式に代表される『加入儀礼』(Initiation)が重要な意義をもつ。その本質は人間がいったん死ぬことにより、あらためて高次の生に入る象徴的な移行儀礼である。ここで当然人間の生と死と、そして復活再生が問題となり、これを支える宗教的な力としてまたまた宇宙創造への回帰が、個人の生涯の過程において反復される。人間存在は一連の移行儀礼によって完成に達するのであり、やがて個体の終焉としての死すら、古代人はこれを1つの移行儀礼に変える。自我を歴史の主体的能作となしつつある近代人の生き方と対比すれば、全く次元の異なる生存状況がここに見出されるであろう」
また風間氏は、古代社会が祭式中心であったことを指摘し、「祭式の終わりは古代の終わり」と言った上で、以下のように述べています。
「古代人は祭式によって宇宙開闢の時を再現し、世界の中心に住み、周期的に生を新たにした。孔子の場合は礼という形においてややその伝統を保持しているが、それとて祭式中心というにはほど遠い。まして時代の下った南宗禅においては、もはや祭式とは無縁である。そして或る周期的な、また集団的聖の回復ではなく、個人的な、あるいは一般人間的な、かつ行住負坐臥、つまり日常不断の道である点に大きな差異が存する。そこで純粋な古代社会とこれら俗なる時代における道との異同をいますこし究明するためには、インドの事情を参照せねばならない。なぜなら恐らく世界じゅうで最も大規模にして複雑な祭式体系を発展させたのは古代インドであり、かつ今日まで豊富な資料が遺っているからである」
訳者の風間氏は東京大学文学部のインド哲学梵文学科を卒業し、法政大学教授を務めましたが、『新釈・碧眼集』などの著書を残しています。いわばインド思想の専門家ですが、「現代と東洋の宗教」(訳者あとがきに代えて)で以下のように述べます。
「古代インドの祭式は発展の後、それ自体が独自の力をもつに至った。すなわち神々すら祭式の力によって動かされ、祭式を司る祭官(婆羅門)は神々と同等の力をもつと信ぜられた。宇宙、祭式、および人間の個体はたがいに相応連関し、祭式の完成により祭主の個体は宇宙的なものとして完成する」
続けて、風間氏は古代インドの祭式について述べます。
「この時代にはまたプラジャーパティという神が最高神として崇拝されたが、この神は普通考えられる一神教的な神とは趣を異にし、空間的な一切宇宙であると共に、《歳》として時間的にも一切宇宙であり、同時に《祭式》そのものである。そこで祭主の個体(アートマン)も究極的には、このプラジャーパティと一如することになる。やがて祭式は、具体的な祭儀から一転して内面化し、いわば人間個体のなかで常恒不断に行なわれる祭式となる。宇宙の本体を表わす原理はブラフマン(梵)と呼ばれるようになり、このブラフマンと人間個体の本質たるアートマン(我)との一如を説くウパニシャッドの哲学が成立する。古代インド思想はここで一応その頂点に達するが、このとき具体的祭式はようやくその支配的地位を、このような本質的《知》の到達に譲る」
最後に、風間氏は古代の祭式の時代が終焉するとともに、孔子やといった偉大な聖人が出現したという興味深い見解を示し、こう述べています。
「シナにおける孔子、インドにおける釈迦は共に古代の祭式中心の時代がようやく終りを告げる頃、歴史的時代における一個の人格として出現し、独自な人間の道というべきものを開拓したと考えられる。それは古代祭式に還る道ではない。さらに人類を神話伝説のいわゆる『黄金時代』に還すことは当時にあってもすでに不可能であった。またインドの場合にみたように、祭式による周期的な生の更新という途が、果たして人間のあり方として完全な成功を収めうるものであったか否か、についての大きな疑問が存する。孔子や釈迦の場合はこのような祭式の内面化から、やがて日常の時々刻々、到るところ、つまり造次順沛が常に新しい宇宙的生の創造でありうるような道であった。それは古代の伝統を汲む、宇宙的な人間のあり方である」
エリアーデの言葉を使えば、孔子やブッダは「宇宙的責任を引き受ける」ところの人間でした。そして、彼らはこの宇宙的創造力を基礎にすることによってかえって世俗的人間関係が適正に行なわれうる道となることを知っていたのです。歴史的人格といっても、孔子やブッダの場合は、ユダヤ・キリスト教における預言者の歴史性とは本質的に異なります。それは、歴史性そのものに絶対的価値を認めようとするものではないからです。
本書を読んで、「祭式」と「聖人」との関係がよく理解できたように思います。
