- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2016.02.26
『日本の祭』柳田国男著(角川文庫ソフィア柳田国男コレクション)を再読しました。『儀式論』(仮題、弘文堂)の参考文献です。帯には「『日本の祭』は、正真正銘、柳田国男の民俗学の到達点としてある」という文芸評論家の安藤礼二氏の言葉が記されています。
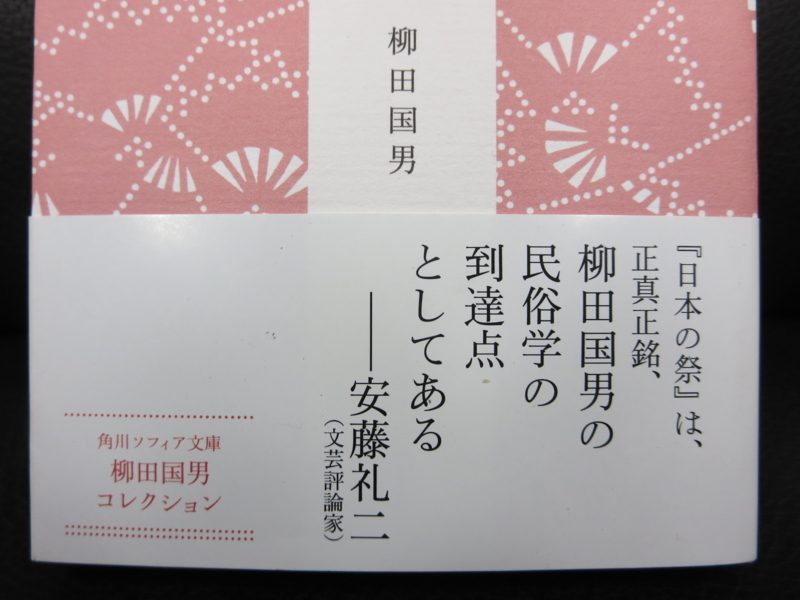 本書の帯
本書の帯
本書のカバー裏には、以下の内容紹介があります。
「古来伝承されてきた神事である祭。その歴史を、『祭から祭礼へ』『物忌みと精進』『参詣と参拝』等に分類して平易に解説。村落共同体の体験を持たずに社会に出て行く若者たちに向け、近代日本が置き忘れてきた伝統的な信仰生活を、民俗学の立場から説く講義録」
本書の「目次」は、以下のようになっています。
「自序」
学生生活と祭
祭から祭礼へ
祭場の標示
物忌みと精進
神幸と神態
供物と神主
参詣と参拝
「注釈」
「解説」大藤時彦
「新版解説」安藤礼二
「索引」
「祭から祭礼へ」の冒頭には、以下のように宗教の問題が語られています。
「現在宗教といわるるいくつかの信仰組織、たとえば仏教やキリスト教と比べてみてもすぐに心づくが、我々の信仰には経典というものがない。ただ正しい公けの歴史の一部分をもって、経典に準ずべきものだと見る人があるだけである。しかも国の大多数の最も誠実なる信者は、これを読むおりがなく、また文書をもってその信仰を教えられてもいなかった。それゆえにまた説教者という者はなく、少なくとも平日すなわち祭でない日の伝道ということはなかった。そうしてこれから私の説いてみようとするごとく、以前は専門の神職というものは存せず、ましてや彼らの教団組織などはなかった。個々の御社を取り囲んで、それぞれに多数の指導者がいたことは事実であるけれども、その教えはもっぱら行為と感覚とをもって伝達せらるべきもので、常の日・常の席ではこれを口にすることをはばかられていた。すなわち年に何度かの祭に参加した者だけが、次々にその体験を新たにすべきものであった。温帯の国々においては、四季の循環ということが、誠に都合のよい記憶の支柱であった。我々の祭はこれを目標にして、昔から今に至るまでくり返されていたのである。祭に逢わぬということは非常な損失であり、また時としては宥し難い怠慢とさえ考えられていた。祭は国民信仰の、言わばただ一筋の飛石であった。この筋を歩んでいくより他には、惟神之道、すなわち神ながらの道というものを、究めることはできなかったわけである」
また、著者は日本の祭の大きな変化について、以下のように述べています。
「日本の祭の最も重要な1つの変わり目は何だったか。一言でいうと見物と称する群の発生、すなわち祭の参加者の中に、信仰を共にせざる人々、言わばただ審美的の立場から、この行事を観望する者の現れたことであろう。それが都会の生活を花やかにもすれば、我々の幼い日の記念を楽しくもしたと共に、神社を中核とした信仰の統一はやや毀れ、しまいには村に住みながらも祭はただながめるものと、考えるような気風をも養ったのである」
「物忌みと精進」では、著者は「籠る」ということが祭の本体であると述べています。それを踏まえて、さらに次のように述べています。
「すなわち本来は酒食をもって神をおもてなし申す間、一同が御前に侍坐することがマツリであった。そうしてその神にさし上げたのと同じ食物を、末座において共々にたまわるのが、直会(ナオライ)であったろうと私は思っている」
また、著者は「祓い」についても次のように述べています。
「祓いという方式の起こりはむろん非常に古い。しかしその利用の範囲は近世に入るほど拡張している。これに信頼して日ごろは自由な生活をする者、今に祓ってもらうからよいわと言って、祭の前の晩まで牛肉を食う者などは元は決してなかった。その上に祓いの方法も近ごろは極度に簡単になった。いわゆる御幣を頭の上で振ってもらえば、それでまがこと罪穢れが銷除するなどということは、私の見るところではハライの学説の進歩に他ならぬ。古いかつ最も本式なる祓の方法は、近ごろ再び復活しかかっているミソギである。これはたしかに印象の深い行事で、元はこれによって肉身の改造に近い結果が得られるように考えられ、またそれが第一の目的であったかもしれぬが、これと共に一時的に身の穢れや罪を自覚する者も、これによって清め拭われようとしたらしいのである」
「清め拭い」について、著者は葬式の場合を次のように述べています。
「たとえば葬式から帰って来ると、水を張った盥を跨ぎ、臼のまわりを廻り、もしくはちょっと塩を嘗めるまねをするというくらいなことで、多数の人々が喪に参加することになっては、そう大げさなこともできまいが、これでは完全に穢れの不安は取れず、したがって人が無感覚になるより他はなかった。それよりもいちだんと濃厚に近ごろまで残っていたのは、産の穢れの浄めで、これも山間の村とか、または讃岐の伊吹島のような海近い村々が主であるが、女は月ごとの忌まれにも昔どおりの森戒を守り、厳寒にも荒海の浜に下りて身を滌ぐ者があった。山で大きな野獣と闘うべき人々、東北でいうマタギなどが、やはりこの水の祓いをことに重んじていた。ただに物質上の穢れだけでなく、山言葉の禁条を無意識に犯した場合にも、やはり谷川に身を浸すことを強制せられ、または何十杯も冷水を頭から掛けられた。すなわちミソギはこういう人々の間には、昔から引き続いて守られているのである」
「神幸と神態」では、祭礼の式と行列について、以下のように述べられています。
「式と行列とは最初から、関係のあったものに相違ない、ヤソ教の祭典にもやはり小規模ながらプロセッションは見られる。もともと儀式は足を使うものが多く、したがって空間を必要とし、またその行事が細かく立会人が多くなれば、順序をまちがいなく守るためにも、行列を作らずにはいられなかったであろう。葬式でも嫁入りでも、また軍隊の行進でも、行列の起こりは1つであったと思われる。ただ日本ではそれに加うるに、我々の信仰の特殊性が、異常にこれを発達せしめて、それが今日では祭の大小の差別となり、行列のないのがただのマツリ、いわゆる祭礼は必ず行列を伴うというふうに、一応はきめてしまってもいいようになったのである。こういう差別がもしも昔からあったのならば、あるいは我々の固有信仰には、最初から二とおりの起源があると言うべきであろうが、私などの見るところでは、これは皆中期以後の著しい片よりであって、根本の一致点がこれによって、いくぶんか蔽われ埋もれているだけなのかと思う」
著者は「神舞」についても以下のように述べています。
「神舞という伎芸の世と共に盛んになってきたのも、あるいはこういう側面から説明し得るかもしれぬ。私は舞と踊との二つの流れについて、だいぶ久しい前から人とは少し変わった意見を抱いている。簡単な語でいうと、踊は行動であり、舞は行動を副産物とした歌または『かたりごと』である」
また、「わざおぎ」についても、著者は以下のように述べます。
「『わざおぎ』という言葉はいわゆる芝居の意味に、今も風雅の人々は使っているが、ワザの所業であり行動でありまた技術であることは知っていても、オギが招くを意味することは解し得ない人が多い。私の見るところでは、ワザによって神をオグすなわち招くというのが、この名称の由って来たるところであった。あるいは経験の結果として、始めから歌詞に伴う舞の形を案じてかかったものもあったろうが、その経験を得るためにも、まず我々は神と共に、この『たたえ言』の尊さに動かされなければならなかった。空にこのような舞の形のみを、案じ出すということは想像し得られぬからである。すなわち最初にあったものは言葉のあやまたは力で、舞はむしろその直接の効果、今一歩を進めて言うならば、これによっていよいよ神の依られんとする状態が、本来は舞というものの姿ではなかったかとも思っている」
さらには「昔語り」について、著者は以下のように述べます。
「多くの昔語り、すなわち神秘なる古代人の生活伝承が、歴史の最も大切な部面として我々を動かすのも、本来は神を信じた人々のきわめて真摯なる礼讃だからであった。たとえば人間に災禍をもたらす鬼どもの退治、その鬼は後世狒々となり大蛇となりまたは山賊とも変わっているが、今なお文芸の一趣向として、大衆小説の中にまで続いているのは、言わば我々の遠い親たちの空想の遺産だからではなかったか。あるいは清い少女を悪魔の厄難から救い出す話、後にそれを娶って人間の最もすぐれたる英雄を生ましめた話、その他いやしくもローマンスを愛する人々のいつでも胸にえがくことのできるいくつかの物語は、試みにその水源にさかのぼってみれば、一つとして神に属しなかったものはないのである。しかも最初にはじめてその不思議な出来事を教えたまいしは神であったとしても、これを燦爛たる近世の演奏にまで持って来たのは、すべて我々人間の力であった」
「供物と神主」の冒頭では、著者は以下のように述べています。
「今日マツリの総称の中に入れられるいっさいの信仰行事を通じて、必ず備わっている要件、そうして日本以外の民族にあってはしばしば欠けている要件は二つある。その一つはミテグラを立てること、もう1つは必ず食物をお進め申すことである」
家の神祭りというものがあります。著者は次のように述べています。
「今日年中行事と呼ばれている我々の家の神祭りでは、今でもその日に家の者が食べる御馳走と同じ物の初穂を上げる。というよりもむしろ神様の召し上がるのと同じ物を、神前に列坐して共々に食べるのがきまりである。この日のために特別の鍋釜や特別の膳椀があり、また常の日と変わった食品を調えて上げるとすると、それが同時にまた人間にとっても、そういう珍しいものが食べられる日となるので、節供という名もその文字が示すごとく、基づくところはこの節日の供物にあった。それが後々はいつでも食べたい時に粽をこしらえたり、店屋へ買いに行けば年じゅう餅があるというようになって、晴れの膳という観念ははなはだ不明なものになったが、それでもまだ我々は突然小豆のこわ飯などを出されると、きょうは何だったかと訊きたくなるような気持ちだけはもっている。祭日と食物との深い結びつきは、丸っきり断絶してしまってもいないのである。ただ現在は一般に公けの祭だけが、神に御供え申す品物と、同じ時刻に人々の食べるものとを、二つ全く別々にしているので、著しくこの民間年中行事の信仰上の意義を、希薄にしてしまったことは争えないのである」
神に供える食べ物についても、著者は以下のように述べています。
「今日のように、神様にはすべて原料のままでお目にかけるだけとなっては、たとえ古来の慣例によって、今なお村じゅうがそれを食することになっていようとも、双方にはもう連絡がなく、言わばただ一つの奇習となってしまうのである。国の祭式の統一ということは歓ばしいが、そのために特殊神饌の省みられなくなったものが多く、神と人との最も大切な接触と融和、すなわち目には見えない神秘の連鎖が、食物という身の内へ入って行くものによって、新たに補強せられるというような素朴な物の考え方が、いよいよ近代人の共鳴しがたきものになってくるのである」
さらに、神様の供物について、著者は以下のように述べます。
「神様の供物が人間の食べ物と分かれてきた端緒は、あるいはこういうところにもあったのかもしれぬ。中世の記録にはたしかに食品であった熨蚫(ノシアワビ)や昆布、榧とか搗栗とかいうものも、もうそのままでは食わぬ人が多くなった。人は世につれて自由に好みを変え、醤油とか砂糖とか胡椒、その他いろいろの調味品を使いながら、神様だけを元の御習わしに置き残し申すというのも相すまぬ話だが、それにもまして困ったことは、神と人と同時に同じ物を味わい楽しむという、太古以来の儀式の趣旨が、おいおいと忘れられていくことであった。これは全く祭が新たなる文化を利用した結果、だんだんとその中心を供饌以外のものに移していって、大きな注意をこの点に払わなくなったためであり、さらにまた一般に祭奉仕の役目を、限られたる家または人に委ねてしまったがためであろう」
「参詣と参拝」では、「オヒネリ」という言葉について以下のように述べられています。
「オヒネリという古風な言葉は、東京でも一部にはこれを使う者がいるが、その意味はすこぶる全国の田舎と違っている。こちらでは俗にいうチップ、すなわち目下の者に向かってぽいと抛ってやるようなはした金に、この名を適用していた時期がしばらくあったのだが、それもすでに必要がなくなろうとしている。以前はこんなものがオヒネリでなかったことは、賽銭箱の中からでもうかがわれる。地方はこれが今いちだんと厳粛で、オヒネリを包むべき日と場合とは一定し、他にも応用はあるが主としては神詣での用であった。そうしてさらに何よりも顕著なことには、この紙包みの中には必ず洗い米が入っていたのである」
著者は、日本のマツリゴトにおける「承認」について、以下のように述べています。
「世界に比類なき神国のマツリゴトの、最も重要なる原則は「承認」であったと思う。朝家が御親ら祭りたまう一国の宗廟と大社に対して、万民が無限の崇敬をいたすべきことは言うまでもないが、同時に他の一方には臣庶の祭り来たれる個々の御社を、洩るるところなく公認なされ、その若干の最も有力なるものに向かっては、祭の日に勅使を派し、あるいは官府国司をして幣帛を贈進せしめられた。この方策は武家封建の時代にも継承せられ、さらに復古の世になって著しく官知の範囲が拡張せられたのである。国民のいわゆる精神文化の統一はこのごとくにして成った。いまだかつてこの神を祭れといい、その方式を改めよという類の制令を下すことなくして、天下はことごとく安んじたのである」
最後に、神と人との関係について、著者は次のように述べています。
「神は人の敬によって威徳を加えたまうということは、『貞永式目』以来の信条であったけれども、同時にその反面において我々の祭が、常に公共の福祉を目的とした、純一無私のものであったればこそ、総国敬神の念は期せずしてこれに集注したのだとも言えるのである。ところが我々のまだはっきりと意識せぬうちに、少しずつこの根本の要件は変わってきた。第一には個人祈願、他には打ち明けることできない身勝手な願いごとを、氏神様に向かって掛けるものができて、これにはもちろん神主の仲介を頼まない。私祭はほとんど内外の区別を無視せんとしている。次には部内の祭の唯一条件であった共同の謹慎を、守り得ない者が多くなってきた。精進潔斎の戒律が日にゆるんで、しかもなお不浄を忌まわしとする感覚だけは残っているがゆえに、神の黙約に基づく年来の恩沢が、はたして持続しているかどうかを危ぶむの念は、愚直な者の間にようやく瀰漫せんとしている。国の固有信仰の伝統において、まことにこれは1つの大いなる危機である。しかも一方にはただ歴史ある敬神の国是を強調することによって、永く神国の伝統を支持し得べしと、思っているらしき人がいるのである。虚礼に陥ることなくんば幸いである」
本書は非常に読みやすく興味深い内容ですが、もともとは東京大学の教養特別講義として話されたものでした。当然ながら聴き手は大学生でした。著者がこの題目を選んだ理由もそれを考えての上であったとして、民俗学者の大藤時彦は「解説」で以下のように述べています。
「現代の大学生は祭りの参加者でなく見物人の側にいる者が大部分である。つまり学生は祭りに対して疎遠となっている。しかし本来は祭りは青年が中心となって行なうべきものであった。氏子として祭りに参加することは青年の義務であり権利であった。神事の中でも神輿をかついで御神幸に供奉し、いろいろな芸能を演ずるのは青年でなければならなかった。青年は祭りに参加することによって村落社会の一員たることが認められた。獅子舞その他の芸能に長男だけがそれを演ずることができるとしている村が少なくない。つまり将来一人前の戸主となるべき者にだけ祭りの役につくことを認めたので、祭りが村落社会の上に持っていた重要性がわかる。芸能の如きも年齢によって演目が異なり、その演技を村人が批判する一種成年式の試練のごとき意味を持っていた。こういう村落共同体の一員としての体験を持たない学生は伝承的なものに触れる機会がなくして実社会に出ていくわけである。そのことの当不当は別としてこう事実だけは承知していなければならない」
「新版解説」では、文芸評論家の安藤礼二氏がその冒頭に「『日本の祭』は、柳田国男がたった一人で創り上げてしまった民俗学という新たな学問が一体どのような可能性をもつものであったのか、おそらくは最も体系的に説明してくれる稀有な書物である」と書いています。
柳田民俗学の核心はどこにあるのか。 柳田の民俗学を受け継ぎ、それを独自の古代学として大きく発展させた折口信夫の研究者でもある安藤氏は以下のように述べます。
「柳田に生涯師事することをやめなかった折口は、第二次世界大戦の傷跡もいまだ癒えない昭和22年(1947)になされた『先生の学問』という示唆的な講演のなかで、柳田の学の本質について、次のように語っている―『一口に言えば、先生の学問は、「神」を目的としている。日本の神の研究は、先生の学問に着手された最初の目的であり、それがまた、今日において最も明らかな対象として浮き上って見えるのです』 折口が『先生の学問』で考察の対象としているのは、戦争が激しさを増すなかでまとめられた『日本の祭』(1942年)を皮切りに、『先祖の話』(1946年)を経て、『祭日考』『山宮考』『氏神と氏子』と続く一連の柳田の仕事である。『日本の祭』を中核として柳田が書き継いできた近年の作品群こそ、柳田の民俗学の起源と直結し、その初発の意図をよりはっきりと理解させてくれるものとなっているのだ。折口はさらに続けていく。柳田の学問に最も大きな影響を与えたものは『経済史学』であった、と」
しかしながら、折口は「だが経済史学だけでは、どうしても足りません。それだけで到達することの出来なかったのは、神の発見という事実です」とも述べています。「神の発見」こそが、柳田をフォークロア(民俗学)へと導いていったのです。
明治が終わる頃、柳田国男は『後狩詞記』『石神問答』『遠野物語』の3冊を相次いで刊行しました。これら3冊の著作によって、日本に民俗学という新しい学問が誕生したとされています。 安藤氏は、柳田の民俗学について以下のように述べています。
「山神、石神、荒神、道祖神、宿神、客神・・・・・・。柳田は、境界の神を調べ上げていく。こうして、椎葉村での経験は『後狩詞記』となり、境界の神々の調査は『石神問答』となり、遠野の青年の話は『遠野物語』となった。まさに折口信夫が洞察した通り、『経済史学』に基盤を置きながら、『日本の神』の発見によって、柳田国男は民俗学(フォークロア)を創出することが可能になったのである。次に解決しなければならない問題は、2つの世界、俗なる日常の世界と聖なる非日常の世界が境界の地で1つに交わるとき、人々は一体何を行っているのか、という点に絞られる。地上の人々は、天上の神々を迎えるための『祭』を行っていたのである。『組合』の論理は『祝祭』の論理として完成する。だからこそ本書、『日本の祭』は、正真正銘、柳田国男の民俗学の到達点としてある」
「新版解説」の最後に、安藤氏は以下のような格調高い文章を書いています。
「柳田は、学生たちにむかって、祝祭の論理を素描してゆく。祭は『神々の降臨』とともにはじまる。神々を地上に招く目標として聖なる樹木が立てられ、神々を迎える場が浄化される。聖なる樹木を通じて、2つの世界の交通が可能となる。それとともに神々を迎える人々もまた『籠り』、精神と身体を清浄なものへと変成させ、神々との共食に備える。饗宴のなか、神と人とは共食する。『神と人との最も大切な接触と融和、すなわち目には見えない神秘の連鎖が、食物という身の内へ入って行くものによって、新たに補強せられる』。そして神々と人々はともに歌い、踊り、一体化してゆく。そのとき、森羅万象あらゆるものもまた聖なる言葉を発し、唱和する。『霊界の人は常に語ろうとしている。鳥でも獣でも草木虫魚でも皆通信している』。祝祭は、言葉、音楽、舞踏、すなわち諸芸術の起源でもあった」
