- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2016.04.20
『文化と両義性』山口昌男著(岩波現代文庫)を再読しました。 再読というか、もう数え切れないほど読み返しています。次回作『儀式論』(弘文堂)の参考文献として書棚から取り出したのですが、これまでは文庫版ではなく函入りのハードカバーで読んできました。初版は1975年です。
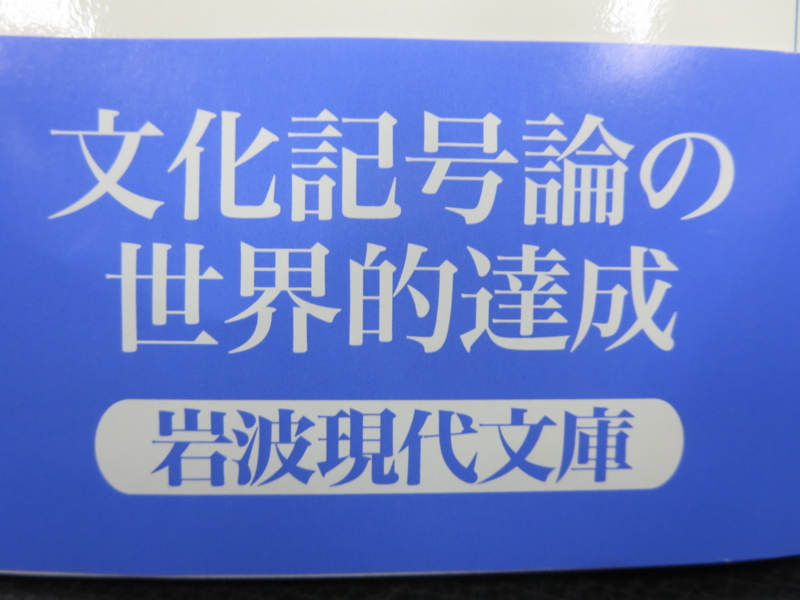 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「文化記号論の世界的達成」と書かれています。 また、カバー前そでには以下のような内容紹介があります。
「膠着した状況を活性化し、文化が本来もつ創造力を回復するために、風土記からロシア・フォルマリズムに及ぶ文化の広大な領野に記号論的アプローチを試みる。著者はさらに現象学を援用しつつ、文化のもつ両義的な性格に着目し、それを分析の軸とした新たな文化理論を提起する。70年代後半以降の日本の文化界に多大な影響を与えた名著」
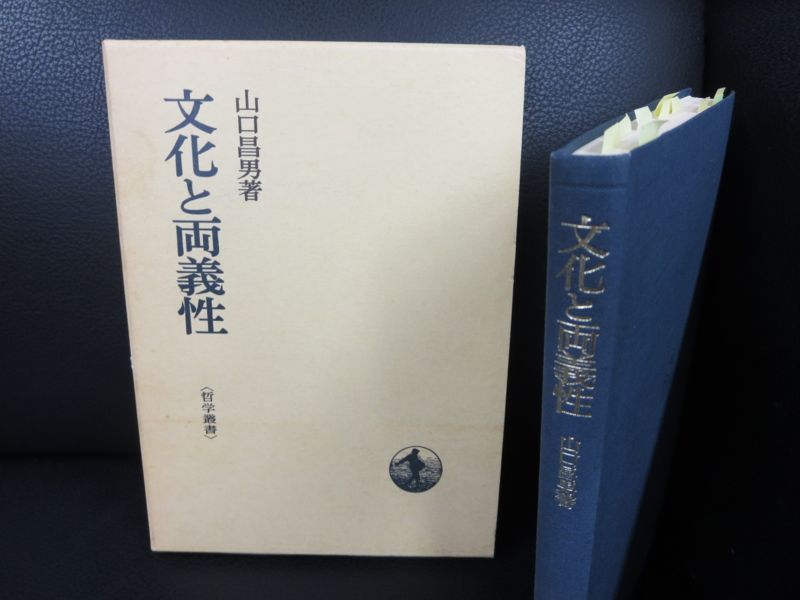 何度も読んだ函入りハードカバー
何度も読んだ函入りハードカバー
著者は、1931年に北海道美幌町に生まれました。東京大学国史学科卒業後、東京都立大学大学院で文化人類学を学び、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所長、札幌大学学長などを歴任されました。日本民族学会会長も務められ、欧米の大学でも教えるなど国際的に活躍されたことでもよく知られます。2011年には文化功労者になられています。しかし、そんな通りいっぺんの経歴ではとても説明できません。 それほど、著者は日本の思想界におけるスーパースターでした。1970年代初頭から哲学者の中村雄二郎氏とともに、創刊間もない青土社の思想誌「現代思想」(青土社)に寄稿し始めます。そこで、構造主義や記号論といった世界における最先端の思想を紹介しました。それによって日本における既存の学問の方向性をシフトした上で議論を活性化させたのです。
 わが書斎の山口昌男コーナー
わが書斎の山口昌男コーナー
著者の一連の活動は、1980年代のニューアカ(ニュー・アカデミズム)」ブームの下準備をしたとされています。浅田彰氏や中沢新一氏といった当時の「知のニュースター」たちも、著者が切り拓いた道があったからこそ登場できたと思います。1984年から10年間は磯崎新氏、大江健三郎氏、大岡信氏、武満徹氏、中村雄二郎氏らとともに岩波書店の総合誌「へるめす」の同人として活躍されました。著者の発言は、日本の思想界に多大な影響を与えました。わたしの書斎の最上段の書棚には、大佛次郎賞を受けた『「敗者」の精神史』(岩波書店)をはじめ、著者の代表作がずらりと並んでいます。バリ島で求めた女神像が、それらの名著を守っています。
 いずれも時代を揺さぶった名著でした
いずれも時代を揺さぶった名著でした
著者は、アフリカなどのフィールドワークをもとに提起した「中心と周縁」理論や「トリックスター」論など独自の文化理論で知られます。守備範囲も広く、演劇や舞踊など多方面に影響を与えました。わたしは学生時代から著者の大ファンで、著書はほとんど全部読んでいます。いずれも時代を揺さぶった名著ばかりで、わたしは貪るようにそれらを読みました。わたしのブログ記事「山口昌男先生の思い出」に書いたように、著者は2013年3月10日に逝去しましたが、日本の思想界に大きな影響を与え続けた生涯でした。
本書の「目次」は、以下のようになっています。
第一章 古風土記における「文化」と「自然」
第二章 昼の思考と夜の思考
1 双面の神
2 神話の普遍文法
第三章 記号と境界
1 意味の多義性
2 混沌と秩序の弁証法
3 彼ら―異人
第四章 文化と異和性
1 文化のプラクシス
2 女のディスクール
3 排除の原則
第五章 現実の多次元性
―A・シュッツの理論をめぐって―
1 学の対象としての生活世界
2 妥当性(レレヴァンス)
3 ムシル『特性のない男』における多元的現実
第六章 象徴的宇宙と周縁的現実
1 世界の統一的把握
2 周縁的現実としての夢
3 社会における「中心」と「周縁」
第七章 詩的言語と周縁的現実
―両義性の彼方へ―
「解説」中沢新一
第二章「昼の思考と夜の思考」の2「神話の普遍文法」において、著者は祭式の問題を取り上げ、以下のように述べています。
「祭式には2つの種類がある。1つは不定期現象を組織するもので、早魃期に行う降雨儀礼などがこれに当る。他の1つは定期的現象で、正月儀礼などがこれに当る。前者に比して後者は比較にならない程の安定性と不可謬性に基づいている。それは、季節変化のリズムに対応した農事暦の上に自らの権威を確立し、多くの文化では、政治的権威の基礎にまでなっている。儀式は最終的には、四季と結びつくとき『完全化』に達する。つまり追放されるべき季節が悪神に見たてられ、穢れを背負って境界の外に立ち去って行くという物語構造は、直接、間接的に1つの儀式の位置を『究極因』的に規定しているというのである」
第三章「記号と境界」の2「混沌と秩序の弁証法」では、混乱(=混沌)の要素は民俗の中にもさまざまな形で挿入されているとし、著者は述べます。
「日本民俗においても、秩序だった農耕儀礼を中心とする年中行事の合間を縫って、或いは、その一部として、反良俗、反秩序の醸成を前提としているとしか思えないような行事が、組み込まれていた。それらは、年中行事の中ばかりでなく、俗信、迷信、昔話、伝説、巡礼、旅芸人等、様々の『民俗的類型』として、日常生活の秩序に対し、歓迎される、されないの違いは別として、不吉または、異質の要素として侵犯性というイメージを帯びて存在しつづけてきた。しかしながら、これら『徴つき』の習俗を記号論的に読み換えてみると、それらが宇宙論的なレヴェルで、『徴なし』の日常生活に対して持つ意味が明らかになる筈である」
3「彼ら―異人」では、著者お得意の祝祭理論が展開されます。 著者は、カーニヴァルの祝祭について、以下のように述べています。
「カーニヴァルの祝祭は、本質的に、転換の意識に付随する両義的な世界感覚の表現である。したがって、この日は、阿呆王を選び出して、戴冠をし、一日中悪ふざけに熱中し、すべての秩序を停止し、混沌をして世界の基調たらしめる。あらゆる価値、人、事物は、それが通常属している文脈から離れて、他の事物と、意外としか言いようのない事物と結びつき、それらが日常生活では現わさない潜在的意味を表面させる。つまり、存在する事物が、日常の効用性の文脈では示さない異貌ともいうべき「響き」が、祝祭日の宇宙の基調となるのである。騒音すらもこの日の意識の過渡的状態を仲介する不可欠の要素になるのである」
さらに、著者は以下のようにも述べています。
「人は、自らを、特定の時間の中で境界の上または中に置くことによって、日常生活の効用性に支配された時間、空間の軛から自らを解き放ち、自らの行為、言語が潜在的に持っている意味作用と直面し、『生れ変る』といった体験を持つことが出来る。遊戯、祝祭、見世物にはそういった境界性の機能が備っているが、逆に、身体の運動が拘束される「病気」においても、―それが日常化しない限りにおいて、人は逆の方向においてであるが、極めて間接的に死の影をかすめるというだけで、似たような体験を持つことができる」
第四章「文化と異和性」の1「文化のプラクシス」では、儀礼的行為について、著者は以下のように述べています。
「宇宙の様々な次元(太陽、星辰、植物界、動物界、人間の世界、家屋、身体等)が、それぞれ象徴的・神話的論理で組みたてられていると考えられ、その各々の次元を貫く論理が共通の基盤を持っているとしたら、いうまでもなく、それは、結合と排除の原則である。儀礼的行為といわれるものの多くは、こうした原則を確認するために、原初の状態を再現する行為から成っている」
また、社会が生きのびてきた背景には儀礼や象徴や記号などの存在があったとして、著者は以下のように述べています。
「すべての時代のすべての文化は、一貫して社会的結合を必要としていたということによって、何故、何時の時代にも人間は、家屋や身体のそう遠からぬ部分に脆弱な部分を作り出してきたかということは説明される。社会は、例えば躾けなどあらゆるレヴェルでの無秩序に対する儀礼的・象徴的・記号論的戦いを奨励することによって生きのびてきたのである。記号はそのための弾丸としての側面を常に持っている。 身体すらも、こうした秩序=混沌の分類に対して例外ではあり得ない。というよりも、身体こそ、宇宙における秩序の基礎であるといっても差支えない程、身体は多くの文化において大宇宙を反映する小宇宙であるという考え方は、西欧中世のみならず、様々の世界に見られる」
第六章「象徴的宇宙と周縁的現実」の2「周縁的現実としての夢」では、著者は夢について以下のように述べています。
「夢は、歴史の深層を探るために、非現在性に対するより大きな譲歩を行う意識の場の1つである。こうして夢は、歴史の深層を、現在的プラクシスに変換させるための重要な装置である。それは或る意味では、敵中に潜入したスパイの如く、敵地(非理性)の文化のプラクシスに偽装した理性の一形態である。それは1人の人間が或いは1つの文化が許容しうる周縁的な現実の最前線ということもできる。こうして夢の分析によって、我々は、意識の埋れた層を発掘することができる。それはとりもなおさず、人間性の歴史の様々な層を顕わす技術にもなる。勿論或る文化では個人の夢で現われる人間性の歴史の古層が、他の文化では、神話或いは、芸術形式で容易に現われるということがあり得る。レヴィ=ストロースの神話体系の分析は、こうした神話を介して立ち現われたプラクシスの探求である」
3「社会における中心と周縁」では、この読書館でも紹介した『儀礼の過程』の著者であるヴィクター・ターナーの理論に言及し、以下のように述べています。
「ターナーの立場を理解するために、先ず、彼が使う独特の概念『コミュニタス』を理解しなければならない。この概念は既に『儀礼の過程』の中で展開されたものであり、規範の共同体である『コミュニティ』に対して、広義の感性の共同体の意味を与えられている。それは、主に、先ず精神の文化、つまり宗教、芸術、文学、演劇といった分野において観察されるが、規範の文化、つまり法、倫理、親族、更に経済といった構成要素をも潜在的に規定していることが知られる。これは、一見して、中間領域と考えられる部分に顕在化する。従って、ターナーによると、それが容易に観察されるのは、通過儀礼であるとか、千年王国の運動であるとか、僧院行動であるとか、反文化を始めとするインフォーマルな行動形態においてである」
また、著者は「過渡性」が『通過儀礼』の著者であるファン・ヘネップが使った言葉で、社会的位置や、一定の年齢の推移に伴う「過渡的形態」を指していることを示し、次のように述べます。
「これらの推移は、3つの段階から成ると、ターナーはファン・ヘネップに依拠して述べる。それらは、分離、周縁(またはリーメン)、再統合である。ここで彼は、たとえば、成年式とか、エレウシスの秘儀に観察されるような、儀礼の展開に伴う意識の推移状態を説明する。それは簡単にいえば、儀礼の推移に伴って、それに参加する人間にとって、社会の規範が不分明になるといった意識内の変化が起るということである。それは、シュッツ的な言い方に置き換えれば『妥当性』の領域の変動ということにもなる。 我々が『周縁性』と呼ぶところのものと『過渡性』とターナーが呼ぶものは、それらの概念が本来空間的な関係をモデルとして概念化されたか、または時間的な関係をモデルとして概念化されたかの違いと理解することができる」
そして、著者は以下のように述べるのでした。
「コミュニタスの表面化しやすいきっかけとしてターナーが挙げる第二の要素は、他所者性である。これは特定の社会組織の構造的組み合わせの外部に身を置く状態である。このような他所者として、ターナーは、シャーマン、占い師、霊媒、司祭、僧院で隔離状態にある者、ヒッピー、サーカス道化、ジプシーを挙げる。しかしここで、ターナーは、我々にとっていささか重要な指摘を行う。彼は、こうした役割に現われる他所者性は、『周縁人』とは区別されなければならないという。彼の周縁人とは、社会的な規定も文化的な規準も異なり、時には相反するような2つまたはそれ以上の集団に同じ時期に属しているような人間をいう。彼が念頭におくのは、移住外人、二世市民、混血、成り上り、階級的落魄者、田舎より都市への移住者、変動下の非伝統的役割を演ずる女性といった存在である」
「解説」の冒頭では、中沢新一氏が以下のように書きだしています。
「『文化と両義性』が書かれていた頃の山口昌男は、その存在自体がじつにチャーミングだった。彼の書くものは私たちに魔術のような効果を発揮したのだ。山口昌男の思考が歩いていくと、平板だった風景が三次元の凹凸をつけられて、山あり谷ありのおもしろい景色に変貌した。禁欲的なモノクロームで描かれていた世界が、彼の文章の魔法の杖の一振りで、あざやかな天然色に染め上げられた。融通のきかないきまじめな知性のおかげで、すっかり殺風景な趣きに仕立てられていた庭には、鳥が鳴き、花が咲き出したように感じられた。ときどきはずいぶん荒っぽい足取りだと感じられることはあっても、まあその程度の欠点は大目に見ようという気にさせてしまうような、ほがらかな空気をまき散らして、山口昌男の知性は、さまざまな領域で、確実に時代の景色を作り替えていったのである」
中沢氏によれば、本書が書かれた75年の頃、若者たちは著者のような知性の出現を心から待ち望んでいたといいます。戦後民主主義は深刻なデッドロックに乗り上げ、大学の機能はなかば死にかけていました。知識人たちは、口を開けば倫理と責任について語り、批判の刃を四方八方に突きつけていました。中沢氏は述べます。
「そこに山口昌男が出現して、倫理や責任の圧迫から私たちを解放してくれたのだ。彼は当時の私たちにとっては、目もくらむような博識ぶりを開陳して、有無を言わさぬ力で、日本の知的な世界を支配していた純粋主義の重力からの脱出の方法を、私たちに伝えようとした。さまざまなイメージが、神話の世界から、オペラの舞台から、場末の滑稽芝居小屋から、地方の神社の神楽殿から、小説から、絵画から、つぎからつぎへと駆り出され、孫悟空や役行者に使役される小鬼たちよろしく、おもしろおかしい身振りや記号論とかいう奇妙な武器を手にして、重力の暗雲を払いのける大立ち回りを演じ出したのである」
それにしても、もともと国史を専攻していた著者は、なぜ人類学という学問を選んだのでしょうか。中沢氏は「彼は自分の思考を積極的に戦前日本の知的伝統につなげようとしたのだろう」と推測し、さらに述べます。
「山口昌男にとって、人類学とは1930年代に絶頂を迎える戦前的思考の生命を、戦後の世界につなげる通底器としての働きを持たなければならないものだった。だから、どうしても戦後史学ではだめで、スマートな文化人類学でもだめで、民族学的な人類学でなければならなかったのだろう」
そして、この著者への限りないリスペクトと愛情に満ちた「解説」の最後に、中沢氏は仏教を例にとり、以下のように述べるのでした。
「インドでいったん滅びたからといって、仏教が敗者だったことなどがあっただろうか。インドで滅びたその思想の種は生き延びて、外の世界で別種の華を開かせてきたではないか。山口昌男の学問は、それとよく似た性格を持っていると、私は思うのだ。生まれの土地に根強い傾向に逆らって自己を形成した思想は、かならずや生まれの土地からの報復を受ける。しかし、そのことによって、仏教の場合はかえって普遍性を獲得した。日本的な純粋主義を逆撫でしつづけた山口昌男の学問に、私はそういう未来を見たいのだ」
