- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2016.05.06
ゴールデンウィーク中は、ずっと『儀式論』を書いていました。
いま、ちょうど「宗教と儀式」という章を書き上げたところです。
そこで『聖なるもの』オットー著、久松英二訳(岩波文庫)を引用しました。
『儀式論』の参考文献としてユングの『心理学と宗教』を読んでいたら、オットーの「ヌミノーゼ」という言葉が登場したので、出典である『聖なるもの』を再読しようと思ったのです。原書は1936年に刊行されており、宗教学の古典として有名です。山谷省吾による旧訳はすでに読んでいましたが、2010年2月に刊行された久松英二氏による新訳は非常に読みやすかったです。
著者のルドルフ・オットーは、1869年生まれのドイツの宗教哲学者です。イマヌエル・カントとド・フリースの研究から、「崇高で聖なるものとは」という問題意識を持つようになり、宗教哲学の研究に移行しました。キリスト教の教義に依拠せず、哲学の立場から宗教にどうアプローチするかということになると、必ずオットーにたどり着きます。古代インド神話学にも通じていたというオットーには神秘学、罪、宗教哲学概説といった分野の業績があります。マールブルク大学の教授で退官し、1937年に死去しました。
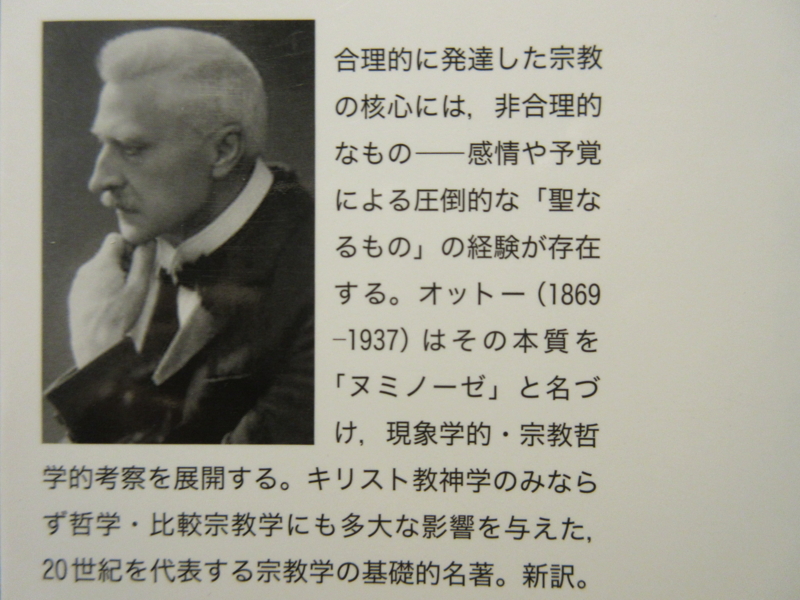 本書のカバー表紙
本書のカバー表紙
本書のカバー表紙には、以下のように書かれています。
「合理的に発達した宗教の核心には、非合理的なもの―感情や予覚による圧倒的な『聖なるもの』の経験が存在する。オットー(1869-1937)はその本質を『ヌミノーゼ』と名づけ、現象学的・宗教哲学的考察を展開する。キリスト教神学のみならず哲学・比較宗教学にも多大な影響を与えた、20世紀を代表する宗教学の基礎的名著。新訳」
本書の「目次」は、以下のようになっています。
「凡例」
第1章 合理と非合理
第2章 ヌミノーゼ
第3章 ヌーメン的対象に引き起こされる感情の自己勘定における反射としての「被造者感情」
(ヌミノーゼの諸要因その1)
第4章 戦慄すべき神秘
(ヌミノーゼの諸要因その2)
第5章 ヌーメン的賛歌
(ヌミノーゼの諸要因その3)
第6章 魅するもの
(ヌミノーゼの諸要因その4)
第7章 ウンゲホイアー
(ヌミノーゼの諸要因その5)
第8章 類比辞令
第9章 ヌーメン的価値としての聖なる者、高貴なもの
(ヌミノーゼの諸要因その6)
第10章 非合理とはどういうことか
第11章 ヌミノーゼの表現手段
第12章 旧約聖書によるヌミノーゼ
第13章 新約聖書によるヌミノーゼ
第14章 ルターにおけるヌミノーゼ
第15章 発展
第16章 アプリオリな範疇としての聖なるもの―第1部
第17章 アプリオリな範疇の歴史における現われ
第18章 「粗野なもの」の諸要因
第19章 アプリオリな範疇としての聖なるもの―第2部
第20章 顕外化した聖なるもの
第21章 原始キリスト教における予覚
第22章 今日のキリスト教における予覚
第23章 宗教的アプリオリと歴史
付録1 ヌーメン的詩歌
付録2 補遺
「原注」
「訳注」
「解説」
「オットーの主な研究業績」
「人名索引」
本書『聖なるもの』には「神的なものの観念における非合理なもの、およびそれの合理的なものとの関係について」という副題がついています。
第1章「合理と非合理」の冒頭には以下のように書かれています。
「人格神を信仰対象とする宗教全般、とくにその典型であるキリスト教の神観念の本質的な特徴とは、神的な存在が、精神、理性、意思、決意、善意、権能、統合的本性、意識などといった人格的な特性を表わす用語で明確に把握され、表現されるということである。つまり、人間が自分自身のなかで、限られた不十分なかたちで自覚しているような人格的・理性的な要素を神に当てはめて考えるということである(同時に神の場合、前出の人格的な特性を表わす用語はみな、『絶対的な』、つまり『完全な』ものだと考えられている)」
第4章「戦慄すべき神秘(ヌミノーゼの諸要因その2)」には、本書のキーワードである「ヌミノーゼ」が以下のように説明されています。
「ヌミノーゼとは、それ自体が非合理なもの、つまり概念としては説明できないものである。だから、それを言葉で表明しようとするならば、ヌミノーゼを体験している心情内に誘発される特別な感情反応を手がかりにするしかない。『それは、ある種の特定感情によって人間の心情を捉え、動かすようなものである』。われわれは、この『ある種』の特定感情について、なにがしかを語る必要がある」
また、著者は「敬虔な感情」について以下のように述べています。
「われわれは、敬虔な感情が強く掻き立てられているときのもっとも深い底の部分にあるもの、救いへの信仰や信頼感や愛といったものよりも深いところにあるものについて考えてみたい。それは、そういう付随的なものとは無関係に、ときとしてわれわれの内部でほとんど困惑させるほど激しく心情を揺り動かし、支配するようなものである。われわれが探求しようとしているのはこれである。それを探求するために、われわれの周りにいる人々への共感力や追感力を使って、信仰心の強烈なほとばしりとそれが生み出す気分、荘厳かつ厳粛な儀式や典礼、宗教的な記念碑や建造物、また寺院や教会などが醸しだす雰囲気といったものに感情移入してみよう」
続けて、著者は以下のように述べます。
「そうすると、探求しているものにふさわしい表現が1つだけ浮かびあがってくる。戦慄すべき神秘〔mysterium tremendum〕という感情がそれである。この感情は、ある場合は、穏やかな満ち潮のようにゆっくりと心情を満たし、静かで深い敬虔の念を抱かせることができる。その場合、この感情は、一定不変に持続する魂の状態を呈するようになる。この状態において、魂は長時間感動にうち震えつづけるが、やがてそれもしだいにおさまっていき、再び日常世界にもどる。一方、この感情は突然強い衝撃と震撼を伴 って魂から噴出することもある。また、ときとしては、異常な興奮、陶酔、法悦、エクスタシーへと導くことがある。この感情は、荒々しい魔神的な形をとるし、ほとんど幽霊的な恐怖、戦慄へと沈みこみうる。その初期段階は粗野で野蛮な現われ方をするが、洗練されたもの、純化されたもの、光明に満ちたものへと発展する。この感情は、被造物たるがゆえのへりくだりから来る静かな慄きと沈黙へと化すこともある。では、いったい誰に対してか。全被造物を超越した名状しがたい神秘の中にある者に対して、である」
さらに、著者は「宗教の起源」について以下のように述べます。
「宗教は、自然的な恐怖からも、漠としたいわゆる『世界不安』からも生まれない。〔宗教の起源としての〕『恐怖』とは、自然的なふつうのおそれではない。それは、さしあたり『不気味さ』という粗野なかたちではあるが、それでも、すでに神秘的なものが心に触れ始めたことをほのめかす恐怖である。言いかえれば、それは、日常の自然的なレベルでの体験領域に属さない、自然的なものと無縁の〔ヌミノーゼの〕範疇の最初の評価適用である。この種の恐怖は、いかなる『自然的な』能力とも決定的に異なる特殊固有の心的素養が目覚めている者にしかありえない。その心的素養は、はじめこそ、いわばうごめく程度の粗野な現われ方ではあるが、人間精神のまったく固有の新しい体験の働き、評価の働きを物語るものである」
第9章「ヌーメン的価値としての聖なる者、高貴なもの(ヌミノーゼの諸要因その6)」では、著者は「神秘的・ヌーメン的な領域」について以下のように述べています。
「『救い』『聖別』『保護』といった宗教的価値は、神秘的・ヌーメン的な領域では真正なもの、欠かせないものであるのに対し、合理的・倫理的領域では疑わしいものとして扱われるのである。
とくにはっきりしたかたちで『保護』という要因に出会うのは、ヤハウェ宗教においてであり、とくにこの宗教の儀礼と儀礼が醸しだす感情においてである。ただ、ほかの諸宗教にもはっきりしたかたちではないが、やはりこの要因が見出される。そこでは、まずヌーメン的な『おそれ』が現われる。すなわち、おのれのような卑俗なものは簡単にヌーメンに近づきえないという気持ちから、ヌーメンの『怒り』に対して保護ないし庇護を求める欲求が生ずる。この『保護』が『聖別』、つまり、ヌーメンに近づこうとする者に、戦慄すべき威厳との交流を可能にする手続きである。しかし、聖別の手段、すなわち本来の意味での『恵みの手段』は、ヌーメン自身に由来し、ヌーメン自身が与え、指定する」
第11章「ヌミノーゼの表現手段」では、「直接的手段」として以下のように述べられています。
「うやうやしい態度やふるまい、声の調子や表情、ことがらがすこぶる重大であることを示す表現、教会共同体の儀式集会や礼拝式などはヌーメン的感情をいきいきと伝える。それを言葉で言い表わそうとしてわれわれは独自にさまざまな言い方や消極的な呼び方を見出したのであるが、そういうものではなかなか伝わらないのだ。実際、そういう言い方、呼び方は決してわれわれが扱っている対象を明示的に表わすものではない。それらは、たとえば不可視なもの、永遠なるもの(無時間的なもの)、超自然的なもの、超世界的なものというように、とにかくあるなんらかのことを言おうとはするが、それはせいぜい別のことがらとの対比、つまりそれとは区別されると同時にそれより下位にあるものとの対比で語られるという点にしか、その有用性がない。あるいは、それらは簡単に言えば、ヌーメン的感情という特殊固有の感情の内容そのものを表わす表意文学的表現である。だがその場合、その表意文字的表現の意図するところのものを理解するためには、当然この感情内容を自ら知る経験をあらかじめもっている必要がある」
また、「間接的手段」として以下のように述べられています。
「ハレルヤだとかキュリエライスだとかセラとかいった聖書や賛美歌集のなかにある古めかしくて意味がとれなくなってしまった表現や、それらのなかにある『ほかの』言い回し、またぜんぜん、あるいはせいぜい半分しか理解できなくなってしまった儀式用語といったものが、礼拝的気分を減じるどころか、かえって高揚させてくれるという事実、まさにそういったものこそ特別『荘厳に』感じられ、愛好されているという事実をどう説明したらよいだろうか。それは好古趣味もしくは伝統への固執なのだろうか。決してそうではなかろう。そうではなく、それらによって神秘の感覚、『まったく他なるもの』であるという感じが呼び覚まされるからである。そのような感覚がそれらと結びついているからである」
続けて、著者は以下のように述べています。
「素朴なカトリック信徒には必要悪としてではなく、特別に聖なるものとして受けとられているミサ用ラテン語、ロシア正教の典礼における古スラヴ語、われわれ固有の典礼儀式に使われるルター・ドイツ語、それに中国や日本での仏教儀式で用いられるサンスクリットやホメロスの作品中のいけにえの儀式に登場する『神々の言葉』、そのほか多くの例がそれに該当する。ギリシア正教の典礼の聖体礼儀やそのほかの多くの典礼儀式に見られる半ば顕わな、半ばベールに包まれた要素も同じ意味で注目されよう」
「直接的手段」「間接的手段」に続いて、「芸術におけるヌミノーゼの表現手段」として、著者は「芸術においてヌミノーゼを表現するもっとも有効な手段は、ほとんどの場合、崇高なるものを表現することである。このことはとくに建築芸術にあてはまる。崇高なるものは、その表現手段をまず建築術に見出したと言ってもよいだろう」とし、さらに以下のように述べています。
「崇高なるものという要因が、すでに巨石文化時代に目覚め始めていたのではないかという思いは否定しがたい。〔ストーンヘンジに見られるような〕あの巨大は岩の塊を自然のままであるいは削りとって、1個の塊あるいは大きく円を描くような形に並べた意図は、元来は魔術的な方法でヌーメン的なものを『力』として大量に蓄積し、その場所に留めて確保しておくためであったのかもしれない。しかしその意図が、崇高なるものを表現するという動機に変化しようとする動きはすぐに非常な勢いで始まった。実際、このような動機の変化はごく初期に起こった。巨大なものの壮麗さや華麗で崇高な雰囲気に対するおぼろげな感受性は、ごく初歩的なもので、『原始的な』人間にもふつうに見られるものである」
「芸術におけるヌミノーゼの表現手段」について、さらに著者は述べます。
「多くの建造物をはじめ、歌やなにかの決まり文句、一連の仕草や音楽、とくにある種の装飾的芸術作品、ある種のシンボルや紋章、蔓草模様ないし線描模様などについて、われわれはよく、これらのものは『まぎれもなく魔術的な』印象を与えるものだと言う。実際、われわれは、いろいろ異なった条件や状況にあっても、かなり確実に、この魔術的なものの様式や特殊性を感知している。そのような『魔術的』印象が並外れて深く豊かなのが、とくに中国や日本やチベットにおける道教や仏教に見られる芸術である。それに精通していない者でも、この魔術的な特徴は容易に感じとれる。ここでの魔術的という言い方は、歴史的視点から見ても正しい。というのも、この言葉の語形の起源は、もともと本来的な意味で魔術的な描写、象徴、処方書やはたらきに由来しているからである」
ところが、じつはこの「魔術的なもの」とは、ヌミノーゼの抑制され、減光されたかたちにほかならないのだといいます。著者は述べます。
「正確に言えば、それはさしあたりヌミノーゼの粗野なかたちであるが、傑作といわれる芸術において洗練され変容される。そうした芸術では、もはや『魔術的なもの』は云々するに及ばなくなる。そこでは、むしろヌミノーゼそれ自身が、その非合理的な威力のうちに、魅惑的な動きを伴って力強く律動しながらわれわれのまえに立ち現れる」
続けて、著者は以下のように述べています。
「このヌーメン的・魔術的なものをとくに強く感じさせるのは、不思議に印象深い古代中国芸術の仏像で、それを観る者は『概念抜きに』、つまり大乗仏教の教えや考え方についてなにも知らなくとも、ヌーメン的・魔術的なものの作用を心に受ける。深い瞑想に浸かったまま現世をはるかに超越したこの仏陀の容貌には、崇高なものと精神化・卓越したものとが現われている。ヌーメン的・魔術的なものはそれと結びついているが、同時にそれ自身が仏像の姿形を光で満たし、それを『まったく他なるもの』が透けて見える透視画にさせているのである」
ここで、著者は西洋を代表するヌーメン的芸術としてゴシックをあげ、以下のように述べます。
「われわれ西洋人にとってのヌーメン的芸術といえば、まずその崇高さからしてゴシックであろう。が、崇高さだけがゴシックなのではない。ヴォリンガーの功績は、その著『ゴシックの諸問題』のなかでつぎの点を証明したことにある。すなわち、ゴシック様式のあの独特な印象は、その崇高さだけによるのではなく、太古の魔術的な造型から受け継がれてきた遺伝的特性によるとして、その魔術的造形の歴史的な由来を示そうとしていることにある。このように、かれにとってゴシックが与える印象とは、主として魔術的な印象である。その歴史的な跡づけの当否はともかく、かれの主張そのものが当をえていることは確かである。ゴシック様式は印象の魔術をもっているが、この印象は崇高さの印象を凌ぐ」
また、音楽について、著者は以下のように述べます。
「あらゆる感情を種々多様に表現しうる音楽でさえも、聖なるものを表現する積極的な手段をもってはいない。もっとも完成されたミサ曲でも、聖変化というミサにおけるもっとも聖なるヌーメン的瞬間を表現する場合、それは音楽が鳴りやみ、しばらくそのまま静寂の状態が続いて、いわば沈黙それ自体が聞こえるという仕方でなされる。ミサの中でこのときほど、この『主のみまえに静けさを保つこと』がもっている強烈な敬虔さの印象を醸しだす瞬間はほかにない」
第12章「旧約聖書におけるヌミノーゼ」でも音楽の問題が取り上げられますが、著者はなんと孔子の名をあげ、以下のように述べます。
「今日われわれが孔子の音楽を聞くならば、それはたぶん奇妙な雑音の連続としか感じられないであろう。だが、その孔子がすでに当時、心情におよぼす音楽の力について、われわれの誰もがかなわないほどたくみに語っており、音楽体験による印象の諸要因を的確に捉えているのである。われわれもそういう要因があることに同意せざるを得ない」
続けて、著者は未開民族の音楽について言及します。
「これとの関連でもっとも注目を引くのは、多くの未開民族がわれわれの音楽を容易に理解するその才能、天分である。かれらはわれわれの音楽に接すると、歓喜してすぐにそれを理解し、練習し、そして楽しむ。この成熟した音楽にかれらが接した瞬間に、なんらかの相対成長、後成もしくはその他の奇跡が起こって、はじめてこの天分がかれらのなかに入りこんできたわけではない。この天分は自然の『素質』としてはじめから具わっていたもので、ある刺激を受けて内部から目覚めた、つまりすでに現存している素質から成長発達したものである。この天分は、原始的な音楽による『粗野な』表現形式のうちに動き始めていたものとまったく同一のものである。音楽のこの『粗野で原始的な』表現形式は、発達したわれわれの音楽趣向からすると、確かに実際の音楽としては、ほとんどあるいはまったく認識しえないことが多いが、それでもわれわれの音楽と同じ衝動、同じ魂の要因の表現にほかならない」
第14章「ルターにおけるヌミノーゼ」の冒頭では、著者はカトリックについて以下のように述べています。
「カトリックでは、その儀礼において、その秘蹟の象徴性において、奇跡信仰と俗信的民間伝承において、その教理の背理性と神秘性において、その思想形成におけるプラトン・プロティノス的特質およびディオニューシオス的特質において、教会堂およびその用いられ方の荘厳さにおいて、そしてとくにその信心と神秘主義との緊密な関係において、ヌーメン的感情がけたはずれに力強く生きている」
著者は、プラトンの思想についても以下のように述べます。
「そもそもプラトンの考え方でもっとも特徴的なのは、かれにとって、哲学と学問は人間的精神生活の全体を包括するには狭すぎるということである。本来、かれは宗教『哲学』なるものをもっていない。かれは宗教的なものを概念的な思考の手段とはまったく別の手段、すなわち熱狂主義、エロース、狂熱といった神話の表意文字的表現の手段で把握している。そして、かれは宗教的対象を学知〔epistēmē〕の対象、つまり理性の対象といっしょくたにして、1個の認識体系に入れこむことを放棄した。そのことにより、宗教的対象は、かれにとっては小さくなるどころかむしろ大きなものとなり、同時にこの対象のまったく非合理的なものを、かれはきわめていきいきと感じとっている。感じとっているだけではなく、表現してもいる。神がすべての理性を越えているということ、しかもたんに把握困難であるだけでなく、把握不可能なものであることを、この思想界の巨匠ほどはっきりと語った者はいない」
第15章「発展」では、「魔神的おそれ」というものについて、著者は以下のように述べています。
「原始的な宗教感情が最初に『魔神的おそれ』という仕方で捉えるもの、またそれがさらに展開し高められ洗練されていくときのそれは、まだ合理的なもの、倫理的なものではなく、まさしく非合理的なもので、この非合理的なものの体験のなかで、心情は既述のような特別な感情的反射作用をもって独自に反応する。この種の要因の体験は、初期の段階ですでに始まりつつある合理化と道徳化の経緯とは別に、それ自身のなかで固有の発展過程を踏んでいる。『魔神的おそれ』は、それ自体多くの段階を経て、『神々への畏れ』と『神への畏れ』の段階へと上昇する。魔神的なものは神的なのとなる。おそれは礼拝となる。あちこちに散漫し混乱し動揺する気持ちは、敬神となる。恐怖は聖なる畏怖となる。ヌーメンへの依存とヌーメンにおける至福という相対的な感情は、絶対的な感情となる。誤った類比と誤った結びつきは消えるか排除される。ヌーメンは神となり神性となる」
これに続く第2の発展として追跡すべきは、かの合理化と道徳化のプロセスでるとして、著者は以下のように述べます。
「これは、第1の発展とまったく同時にとはいかなくとも、ほとんど同時に、しかもヌミノーゼという土台の上で進行していく。このプロセスも、われわれは宗教史のさまざまな領域で段階的にたどることができる。ほとんどの場合、ヌミノーゼは義務、正義、善の社会的かつ個人的理想の諸観念を自らに引き寄せる。これらはヌーメンの『意志』となり、ヌーメン自体はこれら理想の諸観念の番人、調整人、発起人、その基礎・源泉となる。それらはしだいにヌーメンの本質自身のなかに入りこんでいき、その本質自身を道徳化する。『聖なるもの』は『善きもの』となり、『善』はまさしく『善きもの』であるがゆえに『聖』となり、『至聖』となり、このようにしてついにもはや解きがたい両要因の混合、そして聖なるものの完全に複合化された意味が生まれる。そこでは、聖なるものは善きものであるとともに至聖である」
第22章「今日のキリスト教における予覚」では、著者はキリスト教の宗教感情について以下のように述べています。
「キリスト教の宗教感情は『聖なるものの範疇』をもっとも活発に働かせ、かくして宗教史上に見出されるもののなかではもっとも深い宗教的直観を生みだした。
諸宗教を比較して、どの宗教がもっとも完璧なものかを確かめたければ、まさに以上の点を念頭に置くべきである。どれだけ文化に貢献したかとか、宗教以前に、また宗教を抜きにして設定しうると考えられている『理性の限界』や『人間性の限界』をどれだけ際立たせているかとか、またいかに宗教らしく見えるかとかいったことは、根本においては宗教の宗教たる価値を計る尺度とはなりえない。宗教の本来的な核心部分であるところのもの、つまり聖なるものの観念それ自体、および個々の宗教がこの観念をどれほど正当に評価しているか。これのみが、尺度たりうる」
第23章「宗教的アプリオリと歴史」では、宗教における歴史について、著者は以下のように述べます。
「宗教は、歴史のなかで成っていくものである。その生成はつぎのようなプロセスを踏む。まず、人間の精神が歴史的に発展する過程で、刺激と素質が相互に作用しあい、素質そのものがその相互作用によってかたちと方向性を与えられて現実態となる。第2に、〔現実態となった〕素質そのものによって、歴史のある特定部分が、聖なるものの現われとして予感のうちに認識される。この認識は、第1の要因〔つまり刺激〕の質や程度に応じて入り込んでくる。第3に、第1と第2の要因〔つまり刺激と素質〕が基礎となって、聖なるものとの交わりが認識、心情および意志のうちに生起する。
このように、歴史だけが聖なるものを認識するための素質を発展させる一方、自らも部分的に聖なるものの現われである限り、宗教はなるほどまったく歴史の所産である。歴史に依存する宗教とは異なる『自然的』宗教などといったものは存在しない。まして、生まれつきの宗教などというものは論外だ」
「解説」では、訳者の久松氏が本書の内容をまとめています。
「オットーは、宗教が始まる契機というのは、ある対象が『聖なるもの』だと認識されることだと主張する。だが、『聖』という範疇は、通常、倫理的な意味合いで理解されている。つまり、善いというのが『聖』の内容だと受け取られている。しかし、オットーによれば、この倫理的含蓄は、宗教の歴史が進展していくなかで、いわばつけ加わったものである。では、倫理的要因がつけ加わっていないもともとの『聖なるもの』とはなにか。これこそ本書のキーワードたる『ヌミノーゼ』にほかならない。これは、『神霊』を意味するラテン語の『ヌーメン』(numen)をドイツ語化したオットーの造語で、『ヌーメン(神霊)的なもの』という意味である。したがって、ある対象がヌーメン的なものとして、つまりヌミノーゼとして認識されるところで、はじめて宗教が生ずるということになる」
