- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2016.05.20
『神話と古代宗教』カール・ケレー二イ著、高橋英夫訳(ちくま学芸文庫)を読みました。古代ギリシア人、古代ローマ人のあいだで、宗教がいかなる意味を持ち、いかなる現われをしたかを研究した本で、この読書館で紹介した名著『古代都市』の内容を補完するような印象でした。著者は1897年にハンガリー・テメシュヴァール(現ルーマニア・ティミショアラ)に生まれた神話学者・宗教史学者で、ギリシア神話や古代宗教の研究に大きな足跡を残しました。この読書館で紹介した『神話と宗教』の著者である文献学者のヴィルター・フリードリヒ・オットーの知遇を受け、歴史学者ヨハン・ホイジンガ、民族学者レーオ・フロベーニウス、小説家トーマス・マンとも親交を結び、1973年に逝去しています。
本書のカバー裏には、以下のような内容紹介があります。
「神話は荒唐無稽な作り話などではなく、古代人の生(ビオス)であり、実存であった。碩学ケレーニイは、ギリシア・ローマ古代宗教の神話的位相を解明し、”ビオスとしての宗教”を提示する。その根幹から大いなる時間=祝祭を導き出し、学問・芸術・宗教などが根元的に一つの根から生じたことを明す。さらに、人間存在の裏側にある巨大な非存在の領城を探索し、存在は非存在によって支えられ、存在の意味を賦与されているという位相を照射する。人間存在にとって、今もなおこの上ない示唆を与えつづけている名著。図版多数」
本書の「目次」は、以下のようになっています。
「まえがき」
「序説」
第一章 ギリシア宗教の神話的特性
第二章 祝祭の本質
第三章 宗教的経験の二様式
第四章 ギリシアおよびローマの宗教的経験の頂点
一 〈観 テオーリア〉theoria
二 〈慎み レリギオー〉religio
第五章 ホメーロス、ヘーシオドスにおける人間と神
一 奉献のギリシア的観念
二 神々の笑いについて
第六章 ローマ的理解における人間と神
一 〈ユーピテル神官〉Flamen Dialisの生活
二 総括
結語 宗教的観念としての非存在
「原注」
「あとがき」
「文庫版あとがき」
「序説」で著者は、「神話、教養、祭式、制度、生活慣習、共同体、彫刻作品、建築物など、これらすべては1つの様式をあらわしている作品なのである」と述べます。その中でも、最も中核になるのが本書のタイトルにもある「神話」すなわち「ミュートス」です。ミュートスは荒唐無稽な作り話ではありません。それを生み出し、語り伝えてきた古代人たちの思惟や感性そのものの表現です。古代人はミュートスを生きていたのであり、その基盤にあるのは古代人の生としての「ビオス」でした。ミュートスは古代的リアリティであり、現実に生きられるものだったのです。ビオスは単に動物的な生命ではなく、現代風に言い換えれば「実存」です。
第一章「ギリシア宗教の神話的特性」の最後で、著者は「神話は生のなかで、遊びのように引用されることが許されていた。そうであることによって、ギリシア人の場合と同様、ローマ人においても〈ビオス〉は神話との正しい関係を保ちえていた」として、続いて以下のように述べています。
「ギリシア人の最大の、最もひろく行われていた生贄の祭りである牡牛の生贄でさえも〈神話的引用〉と見做すことを許されるだろう。この祭祀では、いわゆるプロメーテウスのごまかしの模倣が行われた。プロメーテウスは、生贄の捧げものの御馳走を、神々と人間のあいだで人間の方が得をするように、不公平に分配した。まるで〈引用〉のように、人間たちはすべての年齢の扮装をした。いわば遊びのように、アテナイの娘たちはブラウローンの小さな〈牝熊〉になって、9歳から結婚までのアルテミスを模倣した。アポロ―ンが青年たちによって模倣されたことを立証するのは、クーロス像とエウリピデースの悲劇『イオーン』である。こういう祭りは、つねにある特定の時を目標とした〈神話に含まれた生〉にほかならない。何よりもそのために存在していたのが祝祭である」
著者は、さまざまな祝祭の実例を挙げながら、以下のように述べます。
「純粋に人間的な努力とか、日常的な義務の遂行とかは祝祭とは言えないのだ。非祝祭的世界の立場では、祝祭を行うことも理解することもできないのだ。不断ならば不可能なことも可能になるような何ものかが、そこに付け加わらなければならない。祝祭において、人々はすべてが〈劫初の日のごとく〉輝かしく、新しく、〈最初〉となるような次元へと引き上げられる。そこにおいては、人々は神々と共にある。いや、彼ら自らが神々となる。そして創造の香が漂い、人々は創造に加わる。これが祝祭の本質である。しかしこのことは、祝祭の反復を排除するものではない。むしろその反対である。人間は、自然の兆候によって、あるいは伝承や習慣によって、祝祭を思い出されられるや否や、非日常的な存在と創造に自らも参加する能力を帯びる。時間と人間は祝祭的となる」
わたしはこれを読んで、すべてが〈劫初の日のごとく〉輝かしく、新しく、〈最初〉となるような次元へと引き上げられる祝祭とは、人間を「初期設定」させる文化装置そのものであると思いました。
著者は、祝祭的なものは芸術、学問、宗教、呪術の4つのものの中に同時に融けこんでゆくとし、さらに「遊び」という現象に注目して、述べます。
「遊びは、それ自体がすでに最大の強制であるが、それと同時に、最大の自由をも意味している。遊ぶ人は、心のリアリティとしての世界のある位相に己れをゆだねるが、その世界に拘束されたという点で、それは最大の強制を意味している。彼はその特殊な世界のなかで、魔法にかけられたわけである。兵隊ごっこをして遊んでいる少年は兵士の世界のなかに生きており、お人形を持って遊んでいる女の児は、母親の世界のなかに生きている。その代り彼らは、その世界の外側にあるいかなる目的観念からも解放されている。遊びとは目的から解放されたものである」
わたしは、『遊びの神話』(東急エージェンシー、PHP文庫)という本を書きましたが、「遊びとは、魂を自由にする営みである」と考えています。
著者は、「遊びの自由は学問以上に大である」と述べます。それは学問の自由がけっしてそうであることを許されていないもの、つまり自由自在 なのだとして、さらに以下のように述べます。
「遊んでいる人は全世界を彼自身の世界に作り変え、そのことによって世界の創造主、神になっている。このように遊びは強力なものである。そしてその点において、遊びは呪術と等しいが、それにもかかわらず1つの点で、すなわち目的観念からの自由の点で、遊びは呪術とは異なる。だから、遊びとは自らそれを拘束として選びとったものであるのに、遊びの自由はかくも完璧であり、かくも美的なのである。それゆえにまた遊びの生は、祝祭の生以上に軽やかで、より幸福で、より実体が希薄である」
このケレーニイの祝祭論は、ノーベル文学賞作家であるトーマス・マンに大きな感銘を与えたことで知られますが、「遊び」論の第一人者であるヨハン・ホイジンガにも大きな示唆を与えました。ホイジンガは名著『ホモ・ルーデンス』で以下のように述べています。
「祝祭と遊戯の間には、極めて親しい関係が成り立つ。日常生活を閉めだすこととか、必ずそうだとは言えないがだいたい陽気であるといえる催し事の情調、それから時間的、空間的に制限が加えられることとか、厳しい規定性と真の自由の融合、これらの要素はみな遊戯と祝祭に共通する最も主要な特徴である。・・・・・・祝祭を独立した文化概念として把えるケレーニイの思想は、これから後、さらに綿密な結論を描き出すことが期待されるが、その現在できあがっている粗描でさえも、すでに私のこの本がよって立つ基礎になるものを強化し、それをひろく押し拡げてる。・・・・・・」
ともに1938年に書かれた『ホモ・ルーデンス』も、本書『神話と古代宗教』も、訳者は高橋英夫氏です。高橋氏は「こうしてみれば、1938年という年は遊戯論と祝祭論がいわば相携えて、学問の世界に新たに根をおろしはじめた記念すべき年だったわけである」と本書の「あとがき」に書いています。
なお、高橋氏は本書の翻訳によって、1972年の「日本翻訳文化賞」を受賞しています。
著者は、古代宗教における祝祭性について、以下のように述べています。
「たとえわれわれがギリシア人・ローマ人の宗教の生成状態に出逢わなかったにしても、その現場にめぐりあうことがなかったにしても、彼らのすべての祭祀行事と神話素は、はげしい輝きを放つ観念のなかから流れ出てきた祝祭性に伴っていたのだ、ということである。この祝祭性そのものが古典古代の宗教はそういう観念の上に立つものであり、だからそれは祝祭的なものと同じように、われわれにも理解できるものになったのだということの証左であり、保証なのである」
さらには、古代ギリシア人における祝祭性について述べています。
「祝祭のために我が身を飾り、死すべき人間として、祝祭のときできうる限り美しくなること、それによって、人間が神々に似た存在となること、これが祝祭性の基本特性であるが、これは芸術にとってはおあつらえむきのものである。それは祝祭的なものと美との根源的類似であるが、それがギリシア人のように大きく前面に立ち現われ、祭祀を支配していた民族は、他になかった」
祝祭、祭儀、祭式、つまり儀式の背景には神話があります。
そのことを、著者は以下のように述べています。
「ある神を殺し、ナイフでその神の肉を切り裂くという神話がかつて存在していたのである。それが、〈牡牛の息子〉の神話と、牡牛の姿となってあらわれるディオニューソスの神話だった。これはまたしても、かなり初期のギリシア宗教のなかから頭を擡げている1つの岩のようなものである。たとえば、斧が罰せられるのではなくて、ナイフが罰せられるという事実がその証拠である。生贄とは、動物によって表現された神にほかならないということを示したこの行為は、聖でもあり、聖ならざるものでもあるが、この行為の記憶は、今日のわれわれには、こういう祭式は、まだギリシア様式を帯びるに至らなかった比較的初期のディオニューソス宗教に属していた」



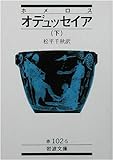
第四章「ギリシアおよびローマの宗教的経験の頂点」では、古代における詩と祝祭の関係が興味深く論じられます。まず、著者はホメーロスの作品について以下のように述べます。
「叙事詩『イーリアス』『オデュッセイア』における神々の出現は祭祀の一要素ではない。それは祭祀の雰囲気と同じくらいに、ある祝祭的雰囲気のなかで〈起る〉出来事なのである。すなわち詩は、真正、真実な芸術であるかぎりは、また真の創造の性格を有するかぎりは、おのずと祝祭的である。古代の詩をつねに取り巻いているのは祝祭的雰囲気であり、ギリシア詩の歴史は、せいぜいその幅が時によって変化を示すだけである。祝祭性がそこから完全に消失するということはけっしてない。もっとも時として、それは詩人が何かの社交的機会にとった一時的な祝祭的態度にすぎなくないことも、事実上ある。しかしホメーロスの場合はそうではない。彼はあくまでも祝祭的である。ギリシアの大いなる祝祭構想の時代―アルカイック期、および古典期における祝祭周期の創造と技巧的な行事の時代―は、詩をすぐれて祝祭的な現象と見做して、自らの祝祭的秩序のなかに受け入れていた」
さらに著者は、詩と祝祭について以下のように述べます。
「詩は、すでにホメーロスに描写された時代でさえも祝祭であって、人間の特殊な存在形式としての祝祭という特性的な表徴をすべて帯びていた。『イーリアス』のなかのアキレウスは、彼のまわりで日常たえまなく闘争が荒れすさんでいるあいだ、心に憂いを抱きつつ、より祝祭的な別世界である詩の雰囲気のなかへ赴くことによって、己れを救いあげている。この詩の世界にこそ、浄化され、無時間的な高みに引き上げられたもろもろの人物や出来事を〈観る〉立場に引き籠ることを、彼に可能ならしめた。『オデュッセイア』においては、まことに自然そのままである饗宴の祝祭性が―たとえそれ自体はまだ祝祭とはいえなくても、世界中のどこであれ饗宴は祝祭的ではあるが―吟唱詩人ペーミオス、デーモドコスの技芸によって、歌と踊りを伴う本物の祝祭の形を獲得している。ホメーロスの詩とそのなかで描写された世界との関係は、全体として、より祝祭的な世界とそれほど祝祭的ではない世界の関係として捉えることができる」
第五章「ホメーロス、ヘーシオドスにおける人間と神」では、著者は「奉献のギリシア的観念」として、祭祀の本質を述べます。祭祀とは、まず第一に現前化作用であり、第二に現前化されたものに関して神に対してなされる請願、神への奉献であるにすぎないといいます。古代ギリシアの祭祀行事における儀式は神々の物語を伝える神話的出来事の反覆であるとして、著者は以下のように述べます。
「それは祭儀的動作の形に圧縮されていたが、その儀式の劇的性格によって、単なる物語よりも強烈な現前となった。かくして祭祀は、現前化作用の強度においては神話を凌駕したが、それだけに止まらず、神話を忘れさせもした。儀式が事細かなものになればなるほど、最初の神話はますます透けて見えてきた」
ギリシアにおける祭祀の根本観念を、著者は次のように述べています。
「祝祭の饗宴において、人間と神とがお互いに対して現前の状態になっていること、すなわちギリシア的な意味でお互いに〈知っている〉こと、これがギリシアの祭祀の根本観念である。文学や碑銘にのこされたギリシア宗教の記念物は、神々への呼びかけ―神々の勧請と招待―に充ちているし、また、神々の到来を祝う勧請の歌や、到来の歌にも溢れている。生贄の食事以外にも、そこには賓客歓待のあらゆるシンボルによって執行される種々の饗応があった」
また古代宗教について、著者は次のようにも述べます。
「古代諸民族の宗教は、神々や神的な存在は、人間や神々がまだ直接に交わりあっていた始源の時に遡るものである、としばしば主張するが、この主張はまた彼らの祭祀行事を根拠づけるものでもある。この観念は、神話的宗教としてのギリシア宗教の基礎にも存在する。生贄といった宗教観念の閃めきのいわば具体化、時間化されたものである祝祭性は、流れ去ってゆく時間とは分離して、特殊なあり方の時間となったのである。すなわちこれが始源の時である。
ピンダロスにとって、祝祭競技のとき、勝利者の花冠を黄金の枝に変貌させた祝祭性に属した、特有の黄金の光輝こそが、始源の時を黄金時代たらしめるものだった。黄金時代については、物語の変種が種々存在していた。歴史時代に入って以後、祭祀のなかで実現しようとした観念のなかに人々が見ていたのは、彼らの黄金時代のさまざまな現実だった」
第六章「ローマ的理解における人間と神」の冒頭で、著者は述べています。
「ギリシア人の場合、神と人間の関係を特徴づけるには、彼らの高度な詩を基礎にすることができる。その時はギリシア英雄時代の大いなる生贄儀式についての描写、それも、その儀式が最初にとり行われたときの描写まで含んでいる。それは、彼らの聖なる行事の発祥について古代宗教が語る、一聯のよく似た神話の一部分としての物語である」
著者は古代ギリシアの宗教の根本は「観(テオーリア)」であるといいます。
ギリシア的な意味では、生とは、観ることそして観られることであり、より適切に云えば、知ることそして知られることであり、最も本質的な意味からすれば、存在することそして知られることなのです。実際、ギリシア語の「知る」は「観る」ことを意味しました。
一方、ギリシア人にとっての「観(テオーリア)」は、ローマ人の場合は「慎しみ(レリギオー)」でした。著者は以下のように述べています。
「ギリシア人の〈観(テオーリア)〉の能力が、神的なるものについて明晰なイメージを創り出すことを助けたように、ローマ人も彼らの〈慎しみ(レリギオー)〉のおかげで、行動と生活を通じて神的なるものを計画的に実現する能力を獲得した」
結語「宗教的観念としての非存在」の冒頭で、著者は述べています。
「古代宗教だけではなく、一般に宗教の深源を求めていったとき、あらわれる人間的経験は死であるが、それは次のような規定に達する。〈すべての信仰は彼岸信仰である。死後の霊魂の運命ということが、すべての宗教において宗教的思索の中心点を形づくっている〉と。」
また、著者は以下のようにも述べています。
「宗教的認識は哲学的認識よりも、はるかに直接的である。ハイデッガーが、哲学者の実存的分析を必要とするこの最も重要なものは、〈未開民族〉の死の把握、彼らの呪術や祭祀における死への独自な態度によって、根源的に、つまり直接的に解明され、照らし出される、と述べていたのは、正しい。最も純度の高い、前史時代の死の観念の1つ―一例だけあげれば、迷宮の図形のなかに表現されているような観念―が、われわれに示していることは、いかに神話的観念というものが、古代哲学的観念以上に、ゆたかな、複雑な、多くの意味を内包しているか、ということである」
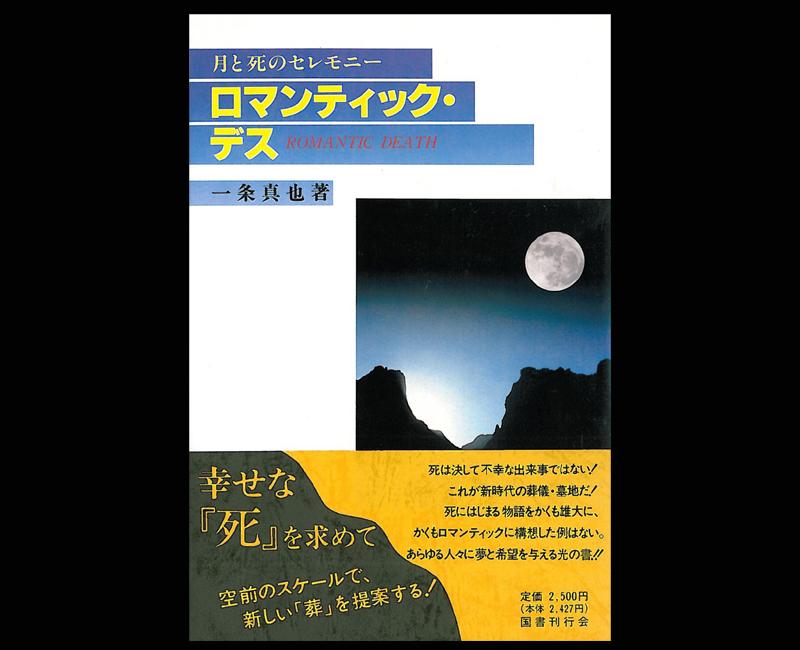 『ロマンティック・デス~月と死のセレモニー』(国書刊行会)
『ロマンティック・デス~月と死のセレモニー』(国書刊行会)
神話にとって「死の起源」は最大のテーマの1つですが、著者は述べます。
「死の起源についての神話の物語は、世界中いたるところで、人間の正常な生の成立を物語った神話の一部を成している、ということがある。死は生と一体であるのでも、生を排除するのでもなくて、生の本質的な成分として生に属しているのだ。それがいかなる死であっても、生―死―生という系列的継起のなかに組み入れられてゆく種族の無限の生命線の成分になったのは死である。はじまりでもあれば、次に新しいはじまりが続く滅びでもある生と死の共属性というこの観念は、さまざまな天体、特に月から読みとれるものだが、植物の生長や動物の増殖もそれである。それは、死でありながら、永遠でもある神々の姿のなかに、特に月の女神のなかに体験される共属性である」
この一文を読んだわたしは、かつて「死」と「月」の深い関係について書いた『ロマンティック・デス~月と死のセレモニー』(国書刊行会)を連想してしまいました。まさに、「月を見よ、死を想え!」といったところです。
結語「宗教的観念としての非存在」の最後、著者は述べています。
「古典古代の宗教は天上の神々と冥界の神々、すなわちオリュンポス神族とクトニオス神族とを崇拝していた。後世の汎神論的哲学の世界以上に、彼らの世界は1つの全体だった。非存在さえも、心にとって現実として存続し、人間にとって別の存在として存在していたのであり、その限りでは、存在と非存在とは、古代宗教にとって同じくらい強力なものであった。いわばそれは、輝きと意味をもって万有を取り囲み、万有に浸透していった神々の輪舞のうちにも、あらわれることができたのである」
「あとがき」では、訳者の高橋英夫氏が本書を解説していますが、「ホモ・サケル」という言葉について以下のように述べています。
「『ホモ・サケル』といえば、今日の理解では単純に『聖なる人』と受けとられかねないが、古代ローマにあっては『サケル』とは冥界に帰属していることを意味する言葉であり、犯罪をおかした人間、死に捧げられた人間、つまり不浄な、穢れた人間が『ホモ・サケル』だったのである。死は人間にとって不吉な禍いであり、穢れである。生からそういう死の領域に帰ることも『サケル』であり、死の領域に赴いたものに対して、生の側から『慎しみ』の態度をあらわすことも『サケル』であって、その全体が今日単純に『聖』と解されているものの古代的に重層化した意味にほかならない。こう見えてくれば、ケレーニイが『聖と俗』とか『晴と褻』という単なる反対概念として用いられている現代宗教学の『聖』概念に異議申立てを行なっているわけも、納得がゆくのではないだろうか」
ここで著者は、日本の折口信夫もケレーニイとほぼ同じ意味合いで古代的両義性の統一を探り当てていたのではないかと推測します。たとえば折口は、この読書館でも紹介した『古代研究2 祝詞の発生』での中の「古代に於ける言語伝承の推移」という論文で、つみ(罪)とつつしみ(慎しみ)の古代的関連を明らかにしました。
これを踏まえて、著者は以下のように述べています。
「慎しみと罪はほとんど本質において変りはないとする折口信夫は、ケレーニイが認めた『聖』の両義性と全く同じ本質を直観しているといえるようで、まことに興味ふかいのである。あるいは折口信夫がしばしば取り上げた遊行神人の問題はどうだろうか。物乞いをしながら祝福の言葉を授けて歩く『ほかひびと』『ものよし』の類が、神事に携わる存在でありながら非人であり、穢れと見做されていたことを、折口信夫は彼らの生活形態の面から解明してみせたが、この折口説もケレーニイ的解釈とどこかで吻合するものがありはしないか」
そして、高橋氏はこの驚くべき書物について、以下のように述べます。
「古代のギリシア人、ローマ人は、非存在、死をもリアリティとして経験していた。死を世界秩序のなかに組み入れ、死の位相がいかなるものであるかを、本質的に知っていた。そうであることによって、彼らは確実に生の観念をいっそう強化していた。―これがケレーニイの突きとめた古代人の生(ビオス)であるが、この認識はすでにケレーニイ自身にもある共振(レゾナンツ)を伝えているのを、われわれははっきりと読みとることができる。同時にわれわれにも、その共振(レゾナンツ)が伝わってくるのが感じられるようだ。」
続けて、著者は以下のように述べるのでした。
「生が死と統一され、存在と非存在の共通性が示されたことによって、ミュートスとビオスの関係が強化され、祝祭の位相が明確になり、テオーリアとレリギオーをはじめとするかずかずの衝撃的な発見と暗示がわれわれに開かれる、といえるからである。そして今、それらの認識は1つに寄り集り、非存在を通過したことによって高められた生というものを、確として指し示しているのが感じられる」
古代のギリシアやローマの宗教からケレーニイが見出したもの、それは存在と非存在を統一するこの「高められた生」という人間的リアリティでした。高橋氏は「学問にとって、人間にとって、これはこの上なく真実味を含んだ示唆であろう」と述べています。
