- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2016.06.12
『卒業式の歴史学』有本真紀著(講談社選書メチエ)を読みました。 わたしのブログ記事「客員研究員会議」で紹介した会合で、國學院大學副学長である石井研士先生から教えていただいた本です。日本独自のセレモニーとされる「涙の卒業式」をめぐる興味深い論考でした。 著者は、1958年鳥取県生まれ。東京藝術大学音楽学部卒業、同大学大学院音楽研究科音楽教育専攻修士課程修了。現在は立教大学文学部教授で、専門は音楽科教育、歴史社会学です。
本書のカバー裏表紙には、以下のような内容紹介があります。
「『最高の卒業式』を目指し、教師と生徒が努力を重ね、みんなでともに歌い、感動し、涙する『感情の共同体』が達成される―この、日本独特と言える『儀式と感情との接合』は、いついかにして生まれたか。涙の卒業式、この私たちにとって当たり前の光景の背景には、明治初期以来の学校制度構築の歴史が横たわっている。日本の近代と教育をめぐる、新たな視角」
本書の「目次」は、以下のような構成になっています。
序章
第一章 卒業式のはじまり
第二章 試験と証書授与―儀式につながる回路
第三章 小学校卒業式の誕生
第四章 標準化される式典―式次第の確立
第五章 涙との結合―儀式と感情教育
第六章 卒業式歌―「私たちの感情」へ捧げる歌
終章
「注」
「参考文献」
「あとがき」
「索引」
序章では、「涙の社会性・文化性」というものが論じられます。 学校においては涙が望ましいとされる状況があります。著者によれば「誰も理由を問うことのない涙」であり、それは個人が泣くのではなく複数の個々人が泣くにでもない「集団の涙」です。 そこでは、連帯の証となるような「共同化された涙」であることが重要な条件となるとして、著者は以下のように述べています。
「この『涙の共同化』は、努力や感動ときわめて親密な関係をもっている。たとえば、スポーツ競技や合唱コンクールなど『みんなでがんばった』結果が表れる場面の涙は、美しく道徳的なものとみなされる。『みんなで泣く』ことが、子どもたちの精神的成長の表れと解されることもある。その際教師も一緒に涙するならば、良好な教師・生徒関係が築かれているとして肯定的に受け止められることが多い」
実生活での卒業式も、感動や涙と強く結びついています。 「感動の卒業式」「涙、涙の卒業式」などの言い回しが、慣用句として流通してもいますが、著者は以下のように述べます。
「実際には涙のない卒業式があり、少なからぬ児童・生徒が『くだらない』『面倒くさい』と思いながら参加しているとしても、感動と涙を抜きにしては卒業式というものを観念することができないほどである。だからこそ、ネット上に『卒業式で泣けない私はおかしいのでしょうか』と不安が表明されたり、『特に感慨深いこともないのに、場の雰囲気にのまれて泣きそうです。どうしたら涙をこらえられますか』という質問に多くの回答が寄せられたりする。卒業式での涙が全く個々人の意に任されているものならば、涙に向けられる周囲の目がこれほど意識されることはないだろう。さらに、『卒業式=涙という方程式ができ上がり、何日も前から「卒業式、泣く?」とか、「いいなあ、○○ちゃんは泣けて」だとか、そんな会話をしているクラスメートたちへの反抗』という書き込みは、卒業式を控えたクラスの会話が『涙の方程式』を前提に展開されていることを象徴的に示している」
わたしは斉藤由貴の大ファンだったのですが、彼女のデビュー曲「卒業」には、「ああ、卒業式で泣かないと、冷たい人と言われそう♪」という歌詞が出てきます。そんなことを思い出しました。 意外にも、こうした卒業式のあり方や歌は、ほとんど日本に特有の学校文化であるといいます。義務教育段階の卒業にあたって特別なセレモニーなど存在しない国も多く、卒業式と感動や涙との結びつきは普遍的な現象ではないというのです。著者は述べます。
「ここから帰結されるのは、卒業式において感じられる感動と流される涙が純粋に個人のものではなく、一方で世界共通でもないことである。つまり、この感情と感情表出は、特定の範囲/広がりをもつ社会と文化において規則性を有する『方程式』なのである」
第一章「卒業式のはじまり」では、「日本最初の卒業式」について言及しています。それは、日本の近代化と深く関わっていました。著者は述べます。
「日本の近代化は何よりもまず、幕藩体制の下で細かな地域と階級に分断された武士たちの諸集団から、西洋的な訓練を施された身体の集合体である新政府=国家の軍隊へと、組織を新たにすることによって着手された。そして、軍隊を組織するとき、あるいはすでに組織された軍隊を堅固に保とうとするとき、訓練と同等またはそれ以上に意味をもつのが儀式である」
軍隊に限らず、公共的儀式の執行は、権力にとって重要です。なぜなら、人々が儀式に参加し、参集者が当該儀式にふさわしいふるまいをすること自体が権力を成立させ、追認させるからであると、著者は指摘します。 人類学者のD・I・カーツァーは、著書『儀式・政治・権力』において、政治儀式の普遍性を論じ、権力はその本質を儀式に負っていることを明らかにしました。カーツァーによれば、ある人物がもともと持っていなかった権威を獲得することは儀式執行を通して表現されるべきです。個人を役割と一体化し、権力を確立するために儀式が利用されるのです。
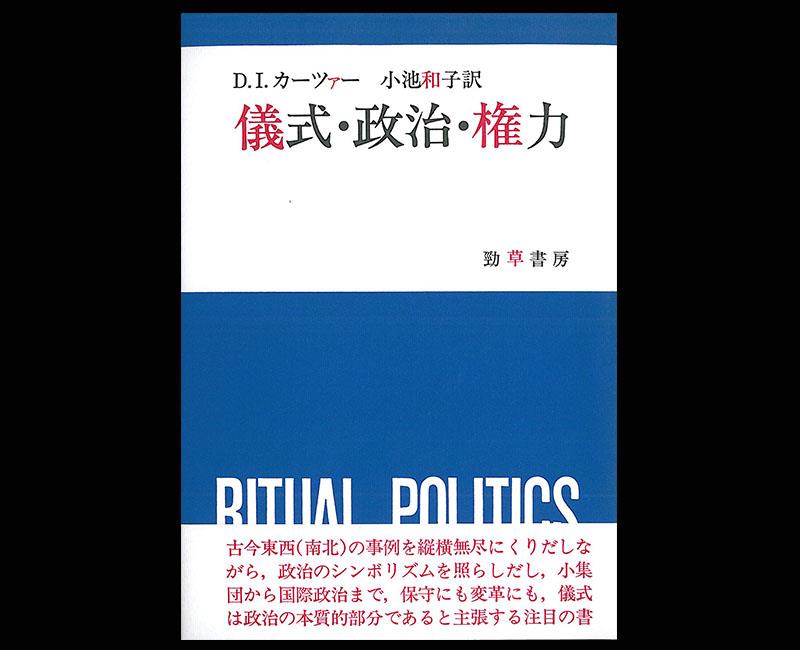 カーツァー著『儀式・政治・権力』
カーツァー著『儀式・政治・権力』
だからこそ、維新の推進者たちは明治天皇即位の礼(1868[慶応4]年8月27日=旧暦)を挙行したと、著者は言います。 この儀式が数々の新儀に彩られたのは、カーツァーの言葉を借りれば、「自分の治世を前任者のそれから分離したい統治者は、旧い儀式を代替する新しい儀式をつくりだす必要がある」からでした。 維新後の神祇官は、先帝祭、紀元節祭、神武天皇祭などの祭典を創出し、天長節という個人の誕生日を祝う西洋的な祝典を組み込みました。つまり、明治維新は儀式の「御一新」でもあったのです。著者は「そもそも、1868年4月(旧暦)に太政官制が敷かれると同時に神祇官が再興されたこと自体、祭儀や式典と権力との関係を象徴していよう」と述べています。
軍隊にやや遅れて日本の近代化を牽引しはじめたもう1つの組織は学校でした。卒業式という新しい風習をいち早く取り入れたのは軍学校で、最も古い卒業式の記録は、1876(明治9)年6月29日に陸軍戸山学校で行われた「生徒卒業式」だそうです。著者は以下のように述べています。
「卒業式としては戸山学校と陸軍士官学校で1880(明治13)年から、海軍兵学校ではその翌年から天皇臨御が恒例となり、後に陸軍大学と海軍大学も含め、これらの軍学校卒業式は原則として天覧となった。1880年12月24日の陸軍士官学校卒業式では、生徒の運動式、馬術、大砲打方などが天覧に供されている(読売新聞1880.12.25)のだが、天皇の前では運動も『式』として行われたことが興味深い」
第二章「試験と証書授与―儀式につながる回路」では、明治時代前半の小学校は現在のように同年齢の者が学んでいたわけではなく、族籍や性別や年齢といった条件を問わずに学力水準によって級を分ける制度が導入されていました。じつに10歳ほども年齢の隔たった子どもが同じ学級に並ぶことすらあったといいます。そこでは、さまざまな理由から中途退学も多く、その構成員は流動的であり、晴れて「卒業生徒」となる割合はきわめて低かったのでした。そして、卒業にあたっては試験が行われ、卒業組と落第組とに分けられました。
当時の小学校の卒業式の様子を、著者は以下のように紹介しています。
「『及落宣告』と証書および賞品の授与は、勝ち残った者、優等だった者を『受験生徒』の群から浮かび上がらせる。その及第者の中でも、成績に応じて何等かの賞が与えられた。太郎は一等だったが、二郎は落第した―試験はそのように徹底して個人を分類し差異化するのであり、集団としては扱わない。『卒業生徒』はあくまで個人を指すのであって、共に行為する集合体と見なされるような存在ではなかった。個別の口頭試問が重視され公開された当時の試験では、試験自体が重要なパフォーマンスであった。授与は成果をあげた個人の顕彰であり、『卒業生徒』は授与の場において個々の名前を呼ばれ、恭しく証書を受け取る以外の行為を行わなかったものと思われる。落第した生徒は、呆然とした、あるいは悲嘆に暮れる観客であったに過ぎない」
続けて、著者は以下のように述べています。
「学校は、この選別と差異化の全過程を公開することで正統性と権威を広報することができたのであり、そのためにも試験をある程度頻繁に行う必然性があった。各級の標準学修期間は半年であり、試験と授与は原則年2回のはずだが、定期試験以外に臨時試験も行われて、卒業証書授与の機会は年4回ほどあった。したがって、『卒業』は特定の年齢にも季節にも結びついたりしなかった。さらに重要なのは、『卒業』が別れとは結びついておらず、むしろ『卒業』によってその後の学校生活への連続性が担保されたことである。同級を連続して落第すると退校となったし、落第や成績不良のために学校を離れる者は跡を絶たなかった。学校生活を続けるには、各級の『卒業』を積み重ねることが不可欠だったのである」
第三章「小学校卒業式の誕生」では、明治20年前後に、地方教育会雑誌に師範附属以外の小学校卒業証書授与式が式手順を含めて掲載され始めていることが紹介されています。それ以前にも、師範附属小以外で「授与式」「卒業式」と呼んだ例は皆無ではありませんが、試験とは日を改め「式」と名づけて実施することと、全級合同で行う授与の形とは並行して普及しました。学校によっては、校長や来賓の告辞・演術および授与に応えて「生徒総代」が行う「祝文朗読」「答辞」などを取り入れ始め、教育雑誌や投稿雑誌にはその文例が掲載されるようになったといいます。 著者は、以下のように述べています。
「生徒が行う演目を式手順に含めるには、前もって人選し準備させる必要がある。それを可能にしたのは試験と授与の分離だった。こうして『生徒総代』が名指されることで、それに対する呼称として『生徒一同』が定着した。式場に臨んだ生徒全員をまとめて名指し、そのうちの特別な個を代表として名指す。『一同立礼』『生徒総代答辞』などのように、全体と特別な個、それぞれの行動を定めることで、生徒の群れは集団へと組織されていく」
また、師範学校附属以外の一部の小学校においても卒業式と唱歌が結びつき始めました。各地で教員を対象とした唱歌講習会が開かれ、受講した教員は自校へ戻って主に『小学唱歌集 初編』(1882)の数曲を指導し、さっそく卒業式で歌った例が見られます。明治20年代に入ると「君が代」を歌う例が目立つようになりますが、唱歌練習の成果を披露できるのはごく限られた小学校のみでした。著者によれば、式での唱歌公開は学校の格づけを対外的に誇示する好機であったといいます。さまざまな教育内容の公開を含んだ卒業式は、住民にとっても、学校にとっても重要なイベントだったのです。
娯楽と啓蒙の要素を備えた盛大な卒業式は、人びとが心待ちにするような行事でした。当時の学校はまさに文化発信と伝達の中心であり、とりわけ戸外でも行われる卒業証書授与式は、その絶好の機会として活用されていたのです。第三章の最後では、「『卒業生』の意味変容」として、著者は以下のように述べています。
「従来生徒は1つの学校で何度も『卒業』を経験したのだが、新しい意味の用法である『卒業生』は、1人の生徒にとって、それまで数年間を経た学校生活最後の日に初めて正式に名指される呼称となった。ここに、『卒業』は現代と同じ範囲へと用法が限定され、『終わり』や『別れ』との意味連関をもち始める。この後、小学校卒業式は『卒業生』という特別な名称と属性を付与された者たちが学校生活との離別を行う、年に一度の儀式として整えられていくのである」
第四章「標準化される式典―式次第の確立」では、1892年(明治25年)に学年度が統一され、小学校が全国的に4月1日始まりとなり、それによって卒業式も全国的に3月下旬特有の行事として定着していったことが説明されます。これを踏まえて、著者は以下のように述べます。
「特定の季節への固定は、儀式とその時候に特徴的な自然条件とを結びつける。年々同じ時期に繰り返されるうちに、卒業式は春の風物詩として認識されていく。そして、儀式は一定の時に反復されることで象徴的な意味を獲得する。春が子どもたちの巣立ちの季節として認識されるようになり、土地によって雪解けや桜の開花などと卒業式が人々の観念の中で結合していった。高等教育機関ではこの後も9月始まりの学年度が続いたが、学校教育を受ける者の中で圧倒的多数が尋常小学校だけしか教育経験をもたない時代にあって、小学校の学年度統一が春を特別な季節に変えたのである」
また、「学級編成」こそは卒業式に影響を与えた最も重要な背景であったとして、著者は以下のように述べています。
「『学級』は能力差、学力差、年齢差にかかわらず70名、学校によっては100名もの児童を1つの教室空間に押し込み、1人の教師に教えさせることを合理化するための方策であった。単級学校では従来通り生徒全員が1つの教室で1人の教師に教わる状況が続いたのだから、学級制の実施によってさほどの外形的変化が起きたとは見えないかもしれない。だが、複数の学年にまたがる年齢も学力も雑多な子どもの集まりを『学級』というユニットとみなすことで、日本の学校はそれまでと大きく性格を変えていくことになった。『学級』は、教師の意識に確かな変化をもたらし始めたのである」
さらに、明治20年代前半には、およそどの小学校でも卒業式は自校での単独開催となっていました。準備に時間をかけるようになった卒業式は、成績品展示や運動会などの催しと組み合わせて行われたのです。卒業式は宣告と褒賞の場から祝祭へ、それも卒業生を祝うだけでなく、住民にとっての娯楽や啓蒙を含む「村の祝祭」ともいえるような行事になっていたとして、著者は以下のように述べます。
「こうした『村の祝祭』に、もうひとつ別の祝祭が加わっていく。それは、『国家の祝祭』である。明治20年代に入ったころから、卒業式で歌われる唱歌の中に目立つようになったのが《君が代》である。もっとも、この《君が代》は、現在の国歌と同じものとは限らない。日本で初めての五線譜による唱歌教材集『小学唱歌集 初編』に掲載された、2番までの歌詞をもつ《君が代》であった可能性も高い。だが、どちらであったにせよ卒業式に《君が代》を歌うことは比較的短期間に広まっていった」
「君が代」や卒業式歌を全員で斉唱するという行為について、音楽教育の専門家である著者は「儀式におけるシンボルの使用、とりわけ斉唱という特殊な一斉行動によるそれは、個々人を集団へと束ねる卓越した方法である。卒業式の唱歌は、デュルケムのいう、個人意識が交霊し共通的感情へと溶解しうるための『合成力』の典型ともいうべきものである」と述べています。 著者は、デュルケムの「諸個人が連合していることを彼らに知らせ、また、彼らに自らの道徳的統一を意識させたのは、この合成力の出現である。彼らが一致し、また、一致していると感ずるのは、同じ叫びを発し、同じ言葉を発し、同じ対象について同じ所作をすることによってである」というデュルケムの言葉を引用しつつ、以下のように述べます。 「たとえ歌詞の意味理解やそれへの共感を抜きにしても、息を合わせ、『われら』の一員として『われら』全員と声を揃える行為自体が、その結果としての音響に包み込まれることが、集団に連帯の快をもたらすのである」
第五章「涙との結合―儀式と感情教育」では、これまで教育を受ける機会のなかった各地の子守の児童たちも小学校に入れられ、1903年からは子守の総代も答辞を読むことになったことが紹介されています。著者は、「卒業式において、子守児童の集団が他の集団と並ぶ位置を与えられたといってよいだろう。中等・高等教育を受けた者と、学齢期にあった子どもの一部だけが経験する儀式として始まった卒業式は、こうして多様な階層や境遇の児童にも共有される体験となった」と述べています。 カーツァーによれば、人々は儀式活動を通してグループへの社会的自己同一化と自己重要性の感覚を手に入れ、儀式の装備によって一体感と共感を育成されます。著者は「同じ境遇にある『不幸せの者』たちの代表が全校生徒の前で発言を許されることは、子守児童たちにとって他の成員から承認を受ける最大の機会となったことだろう」と指摘しています。
卒業式においては、式場の「体裁模様」や「生徒の挙止動作」が直接観察されていましたが、それらを通して読み取られ批評されていたのは「平素の訓練」でした。儀式における挙止動作というパフォーマンスを、身体に染みこんだ「習慣の記憶」として評価しているのだとして、著者は以下のように述べます。
「儀式の挙止動作から平素の訓練が推察されたのは、儀式のもつ力からすれば当然のなりゆきである。儀礼の効果は儀礼の場のみにとどまるものではなく、コミュニティの全生活に及ぶ浸透性を備えているからである」
社会集団がいかにして記憶を伝達するかを、「記念式典」と「身体の実践」に着目して読み解いた社会理論家のコナトンは、著書『社会はいかに記憶するか―個人と社会の関係』で次のように述べています。
「儀礼において示されるものはすべて、儀礼以外の行為や精神性にも浸透している。時間的、空間的には明確に境界が定められているが、儀礼にはいわゆる浸透性も備わっている。儀礼が有意味と考えられるのは、儀礼が儀礼以外の全行為、つまりあるコミュニティの全生活について重要性をもつからである。儀礼はそれを行う人々の生活に、価値と意味を与える機能をもつ」
このコナトンの言葉を受けて、著者は以下のように述べています。
「学校というコミュニティもまた、儀式を行うことで学校生活全体に対する価値と意味を確認し合い、浸透させていた。平素の訓練が重要であるゆえに儀式が重要なのであり、学校儀式が有意味であるのは学校生活に意味があるからなのである。とりわけ、学校生活の最終日となる卒業式は、試験当日に証書授与を行っていたころとは異なり、学校の成員たちが入学以来たどってきた学校生活のすべてに価値と意味を与える儀式として機能するようになっていた」
著者は「卒業式による感情教育」にも言及し、儀式において、唱歌は「よき感情」の醸成を担う要となるファクターであるとして、述べます。
「国家が指定した祝日大祭日儀式唱歌とは異なり、卒業式歌は続々と新曲が生み出されていた。明治期の卒業式歌に含まれる感情語には、『うれし』『楽し』が多いものの、明治期最後の10年間に発表された唱歌に限れば、『悲し』を含むものが目立つようになる。これも、感情教育の重視と連動してのことだろう。こうした変化は、学校制度や学校を取り巻くさまざまな条件の影響によるものでもあるだろうが、年々卒業式を重ねる間に感動が徴募されていったことも見逃してはならない」
人類学者のレヴィ=ストロースは、著書『今日のトーテミズム』において、「推進力および感動はつねになにものかに由来している」とし、「集会および儀式のさいにそこで現に感ずる感動が、儀礼を生み、あるいは存続せしめるのではなくて、儀礼活動が感動を挑発するのだ」と喝破しました。とすれば、試験後の証書授与が儀式となり、卒業式として繰り返されるうちに感動が挑発され、やがて事態は転倒して感情教育を目的として儀式を行うに至った面も看過できません。著者は、以下のように述べています。
「この変化の過程で、最も早く、そして最も効果的に儀式による感情教育を受けたのは、儀式を執り行う側の教師だったと言ってよい。擬人的に表現するなら、儀式はひとたび創られると、より高い価値を獲得しようとしてその執行者に働きかけ、魅力的に創り上げるための努力を強要する性質をもっている。挑発された感動が、その努力を最大限に引き出すのである」
著者はまた、「劇場作品としての卒業式」として、以下のように述べます。
「儀式というものは、往々にして決まりきった行為のパターンが型通りに構成され遂行されるものである。型通りに遂行されてこそ儀式は儀式たりえるのであり、型通りに反復されてこそ儀式はその地位を揺るぎないものとするからである。だが、儀式の形式が定まり、それが習慣として安定的に反復されるようになるのと時を隔てずになされるのが、形式的に陥ることへの警戒である」
第六章「卒業式歌―『私たちの感情』へ捧げる歌」では、卒業式で歌を斉唱することによって、同じ場にいる者が同時に、同じテンポ、同じリズム、同じピッチで、同一の発音を行うことの意味が説明されます。著者によれば、「日本語」の確立途上にあって、それまで地域や性別、属籍によって差異のある音声を発していた人たち、人前で口を開けて声を発するのは恥ずべきことと感じていた者たちが揃って同じ発音を行うのは、「声の近代化、ひいては声を介した心情の近代化」というべき事態であったのです。
著者は、「儀式は興奮させるだけでなく、教えもする。だがその教える力が、個々人を感じやすい心の枠組みにする儀式の力に、おおいに依存しているのである。リズミックなシュプレヒコールから様式化された踊りや行進まで、力強い歌から悲しい鐘の音まで、あらゆる種類の感覚装置が、その人の情緒状態に影響するよう利用される。もっとも効果的な儀式は、情緒的にひとを動かさずにおかない性質がある」というカーツァーの言葉を引用し、感覚装置である卒業式歌は、卒業式を最も効果的な儀式としての成功に導き、ひいては唱歌科の地位向上に貢献し、学校儀式の速やかな浸透にも貢献したことを指摘します。
終章では、「フィクションの中の卒業式」として、木下恵介監督によって1954年に製作された映画「二十四の瞳」が紹介されます。この映画では、子どもたちが涙ながらに「仰げば尊し」を歌う場面が登場し、観客に大きな感動を与えました。著者は述べます。
「小豆島を舞台に、高峰秀子扮する大石先生と12人の子どもたちが繰り広げるドラマは、今でも日本映画の名作に数えられる。《仰げば尊し》はこの映画のテーマ音楽であり、タイトルバックとエンディングロールには壮大な混声合唱とオーケストラによる演奏が流れるのだが、観客の心に残ったのは子どもたちの歌う《仰げば尊し》だろう」
しかし、実は原作に卒業式場面は存在しません。著者は述べます。
「木下監督は、歌の1番後半から3番の前半にかけて、眼をしばたかせたり、目頭に涙を光らせたり、頬を伝う涙を手でぬぐう子どもと大石先生の姿を、1人ずつゆっくりと映し出している。おそらく、これが封切られた当時に映画館で鑑賞していれば、スクリーンの涙と周囲の観客の涙とが重なり一層の感動を味わえたことだろう。監督は当然、卒業式場面を挿入すること、しかもこのようなカメラワークで《仰げば尊し》を歌う姿を映し出す効果を熟知していたはずである。映画全体が感動の物語だったとはいえ、この涙の卒業式場面は特に強く感動へと誘う演出だといえよう。卒業式と涙の結びつきは、こうしたフィクションによる感動を通しても流布されていく」
さらに、「フィクションの中の卒業式」として、著者は以下のように述べます。
「『儀式的』な卒業式ではなく心のこもった卒業式を、と望む教師と生徒にとって、ドラマの感動的な卒業式は格好の参照対象となる。たとえば校長が証書を授与する際に1人1人に短い励ましの言葉をかける場面、謝恩会で肩を組みながら先生を囲んで歌う場面などを見て、現実もそうであってほしいと願う人は少なくない。また、『金八先生』を通して教師にあこがれを抱き、その気持ちをあたためて教職に就いた人もいる。そうした先生が、子どもたちを感動の卒業式で送り出したい、涙の光る卒業式をみんなで作り上げたいという思いをもつのは当然だろう。こうしたあこがれや願望もまた、卒業式と涙の結びつきを強固なものとする」
しかし、現実はドラマのようにはいきません。著者は述べます。
「実際にはドラマのように美しく涙を流せる卒業式はなかなかないだろうが、卒業式と涙、卒業式歌と感動との結びつきは、こうしたフィクションによっても強化され増幅されてきた。より正確に言うなら、フィクションであるからこそ人々がすでにもっている観念に訴えるようにして構成され、現実では見られないほど純化した形で観念を表現しているのである。フィクションの中の卒業式が典型的な式次第を遵守し、しばしば歌いながら涙する子どもたちを映し出すのは、そのためである。そして、私たちがフィクションの中の卒業式を見て共感し涙するとき、それは単に個人の感情を表出しているのではなく、社会的な観念を強化し増幅する行為となる。数多くのフィクションが感動的な卒業式場面を表現し、それが受容されることで、現実の卒業式にもさらなる感動が求められてきたのである」
儀式は人々の感情への作用を通して集団の連帯を強めます。 デュルケムによれば、儀式は常に同じ機能を持っているにすぎず、「本質的なのは、個人たちが集まっていること、共通の感情が痛感され、かつまた、共通の行為によって表明されること」なのです。さらにカーツァーは、儀式が「社会グループの境界、個々人が忠誠を感じる人びとの集団の境界を定義」するのであって、儀式活動はグループの連帯を作り出す必要不可欠な方法であり、儀式の「シンボリックな行動にともに参加することによってのみ、集団の理念と感情を行きわたらせることができる」と述べました。これらを総括して、著者は、儀式、より明確にいえば、儀式において各人が参与する行為こそが集団とその感情を形づくる紐帯なのであると訴えます。これは儀礼論において繰り返し主張されてきた定説でもあります。
感情労働論で知られるアメリカの社会学者A・R・ホックシールドによれば、「結婚式の準備と儀式に参加することを通して、花嫁はある種の視野の歪みと歓喜を経験する権利と義務を獲得」するといいます。そして、「花嫁というものはどのように考え、感じ、見るべきかに関する一般的な規則を自分が了解していることを示しながら、花嫁は自分自身を作り上げる」と述べています。これを踏まえて、著者は以下のように述べています。
「彼女は花嫁としての権利と義務にしたがって感じ、そのように感じることで花嫁となるのである。主役たちがとりわけ入念な準備を重ねる卒業式も同様である。異なるのは、『卒業生』と『在校生』が『一同』となって、感情の共同体である『私たち』『みんな』というアイデンティティを引き受け、遂行することである」
そして、儀式の本質について、著者は以下のように述べるのでした。
「儀式の本質が集団の感情を喚起し行き渡らせることであるならば、卒業式は最も成功した儀式といってよいだろう。卒業式は学校行事の枠を超え、感情の慣行となって社会に分有され、さらに魅力的なパフォーマンスをめざして磨かれてきた。『みんなで泣いた』という記述が与えられるに至って、卒業式の成功はゆるぎないものとなったのである」
本書は、「卒業式」というユニークなテーマを扱いつつも、儀式の本質に鋭く迫った好著でした。それにしても、日本人は基本的に儀式好きであり、さらには儀式で感動し、涙を流すことを好む民族であることが確認できました。これは儀式産業に携わる者として、大きな示唆を得ました。 わたしは、冠婚葬祭業者として、ぜひ、日本人が感動できる結婚式や葬儀のお世話をさせていただきたいと思います。
