- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2016.08.12
12日は1985年の日航ジャンボ機墜落事故から31年目の日です。 犠牲者となられた方々の御冥福を心よりお祈りいたします。
『会社のカミ・ホトケ』中牧弘充著(講談社選書メチエ)を再読しました。 「経営と宗教の人類学」というサブタイトルがついており、著者は1947年長野県生まれの宗教人類学者です。2006年に刊行された本ですが、『儀式論』(弘文堂)を書くにあたり、参考文献として読み返したのです。同書の第十二章「社会と儀式」の中の「会社と儀式」の項で引用しています。
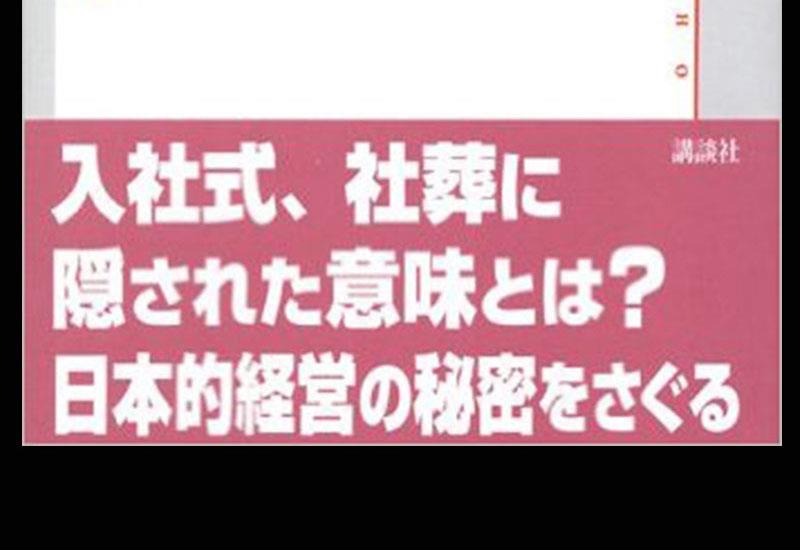 本書の帯
本書の帯
帯には「入社式、社葬に隠された意味とは? 日本的経営の秘密をさぐる」と書かれています。また、カバー裏には以下のような内容紹介があります。
「ビルの屋上に祠をかまえ、物故社員慰霊の法要を営む。日本の会社=社縁共同体はなぜ神仏をまつるのか? 入社式や社葬の知られざる意味とは?経営人類学の観点から日本的経営の本質を解き明かす一冊」
本書の「目次」は、以下のような構成になっています。
プロローグ「経営人類学と会社」
第一章 会社宗教とは何か
第二章 会社神社と社縁共同体
第三章 会社墓と日本的経営
第四章 会社への加入儀礼=入社式
第五章 会社の不滅と再生の儀式=社葬
第六章 会社の神聖化装置=企業博物館
第七章 経営者と宗教
エピローグ「宗教からみた経営」
「注」
「あとがき」
「索引」
プロローグ「経営人類学と会社」の冒頭を、著者は「経営人類学のくわだて」として、以下のように書き出しています。
「会社はいま岐路に立っている。会社とは何か、会社は誰のものか、会社はこれからどうなるのか、会社の社会的責任とはいかなるものか、企業文化はどうあるべきか、等々、会社の倒産やM&A(合併・買収)がめずらしくなくなった世相を反映して、会社の存在意義がさかんに問われている」
続けて、著者は以下のように述べています。
「そうした問いかけに、本書は、宗教をもって解答をあたえようとする試みである。宗教研究の実証的アプローチを活かして会社研究に取り組もうというわけだ。いうなれば、資本主義の説明原理ではなく、宗教のレトリックをもって理解しようとしているのである。無謀な挑戦とおもわれるかもしれないが、宗教研究にもそれなりに”武器”の調達ルートがあり、ひそやかな”戦法”もないわけではない。これはいわば、経済指標や原価計算の世界にひそむカミやホトケを顕在化し、経済合理主義の世界に異界や他界を発見するくわだてといってもよい。それは要するに、フィールドワークにもとづき会社文化を宗教で解こうとするところの人類学的研究である。つまり、宗教人類学の研究成果である。しかも、その文化は経営と密接にかかわる。その意味で経営人類学ともいえる」
また、著者は本書が書かれた背景について、以下のように述べます。
「経営人類学、とりわけ1993年以降における国立民族学博物館の共同研究を中心に展開した研究では、人類学と経営学の交錯領域に焦点が当てられてきた。そこでは企業博物館、社葬、会社儀礼、会社神話、グローバル化などが格好のテーマとしてとりあげられ、国内外の共同調査によって実証的なデータが蓄積されてきた。本書はそうした研究母胎から産み出されている。実際、日本の会社は神をまつり、物故社員を慰霊する法要を営んでいる。会社ビルの屋上には小祠があり、聖地の高野山や比叡山には会社墓がならんでいる。会社や商店の関係者は商売繁盛を願って酉の市や十日戎にくりだしていく。他方、創業者や社長が亡くなれば社葬をもって告別する。そうした行動は日本の会社にとってどういう意味があるのか」
さらに著者は、「岐路に立つ会社宗教」として以下のように述べます。
「アメリカのCSRのなかにはキリスト教倫理やスピリチュアリティ(霊性)に精神的な基礎を置こうとするものがある。それはプロテスタントにもカトリックにも、そしてユダヤ教やイスラームにもみられる。他方、日本の場合には経営者の個人的倫理観と同時に、特に問題とされなくてはならないのは「会社宗教」である。なぜなら、会社の宗教的施設や宗教的活動が経営倫理をおおきく方向づけてきたし、会社の社会的責任ともふかく関係してきたからである。さらに付言すれば、社縁のカミやホトケも一定の倫理基準や行動規範を要求してきた。また会社の経済的活動に魂を入れることの大切さを認識した経営者たちも、神仏をないがしろにすることはなかったのである。異界のカミや怨霊、他界のホトケや先祖の力をかりて、あるいはそれを鎮魂して、ひとつの共同体をまもり発展させることが経営者に課せられた責務でもあった」
第一章「会社宗教とは何か」の1「会社宗教のルーツ」では、「聖俗一致」として、著者は以下のように述べています。
「日本にはそれぞれのイエに家業繁盛や先祖祭祀を中心とする『イエの宗教』があるように、会社にも社業繁栄の祈願や創業者への尊崇を核とする宗教的・象徴的表現形態が存在する。会社といえば、経済的利益をうみだす装置で、宗教的な共同体とは異なるというのが現代の常識かもしれない。しかしながら、会社は世俗的なもので、宗教は神聖なものであるという聖俗二元論は、日本の会社にはかならずしも当てはまらない。 日本人は私立の会社や学園が宗教的祭祀をおこなうことにあまり疑問をいだかない。家で神仏や先祖をまつるのとおなじように、会社が神仏や社祖の加護を祈願するのはなんら不思議なことではないからであろう。社員も個人としての信仰や宗教的帰属は異なっていても、一部の例外をのぞけば、会社の祭祀に参加することにほとんどためらいはない」
また、「家永続の願い」として、著者は以下のように述べています。
「会社宗教を理解するための第一歩は、『イエの宗教』との比較である。イエは建物としての家屋を意味するとともに、家族のこともさし、家業と家産を継承し、先祖の祭祀をおこなう集団と考えられてきた。社会人類学的により厳密に定義すれば、イエは純粋な血縁集団ではなく、家族や親族以外にも奉公人などをふくむ社会的な基本単位である。しかも父系、母系にこだわらない双系的な集団であって、ひんぱんに養子縁組をとおしてイエの継承がはかられてきた。つまり、イエは血縁の連続性を犠牲にしても、家業によってうみだされた家産を代々ひきつぎ増大させるべき経済的単位でもあったのである。経済を優先するという意味で、日本のイエは血縁的紐帯のゲマインシャフトよりも利益を中心に編成されたゲゼルシャフトである、といった見解もある。この点、日本のイエは、漢人やコリアンにみられるような、初代の男系先祖からどこまでも枝分かれしていく父系血縁集団の編成原理とはおおきく異なっている」
続けて、著者は「家永続の願い」について以下のように述べます。
「家長にとってイエを引き継ぎ、それを次代に引き渡すことは、最大の責務と考えられていた。日本民俗学の父と称される柳田國男はそれを『家永続の願い』と表現した。先祖祭祀の役割はイエの永続のために、先祖をはじめとするイエの死者にたいする儀式を絶やさないでいくことである。逆にいえば、無縁の霊によるイエへのタタリをふせぐためにも祭祀は必要であった」
一方、会社宗教はどうか。「共同体としての会社」として、著者は述べます。
「会社宗教のほうはむしろ公的で、経営者や従業員たちの個人的信仰とも、かれらの『イエの宗教』とも異なる次元に属し、それと矛盾するとは考えられていない。イエに盆や正月や先祖の祭祀があるように、会社にも会社の祭祀が存在するだけのことである。ビジネスの世界にカミやホトケが介入するといっても、狂信的な信仰を会社ぐるみでいだいているというわけではない。また、ごく少数の例外をのぞいて、会社が特定の宗教的団体と密接不可分の関係にあるというわけでもない。実際に神仏はおおくの会社の社屋や敷地のなかにまつられているし、地域の祭に会社が組織として参加・協力することも日常茶飯事である」
続けて、著者は日本の会社宗教について以下のように述べます。
「日本の会社宗教においては特殊会社的な信念・象徴・儀礼がさまざまな機会に社内的に演出される。と同時に、社葬のような公的な場面で社外的に表出され、社内の連帯と会社の目標達成のために、社員に何らかの動機づけをおこなっていることもたしかである。では、そのルーツは何か。これまでの記述からも推察されるように、わたしは2つのルーツ、すなわち屋敷神と先祖祭祀がもっとも重要ではないかとにらんでいる。それらは『会社繁栄の願い』と『会社永続の願い』を保証してくれるよりどころでもある。日本の会社宗教は屋敷神や先祖祭祀を聖なる遺産としてかかえこみ、会社はひとつの共同体として、イエと似たような機能を果たしているのである」
2「カミと仏の不均等二分」では、「神仏の『棲み分け』」として、著者は以下のように述べています。
「カミとホトケは起源を異にし、中世に発展した神仏習合にもかかわらず、神道と仏教のちがいとして意識されている。とくに明治維新とよばれる政治革命のとき、新政府の神仏分離政策がカミとホトケの区別に拍車をかけ、封建時代の仏教優位の神仏二分法は神道優位のイデオロギーにとってかわられた。それまでふつう『寺社』とよばれていたものが、『社寺』にかわったことは象徴的である。それと同時に、神社や神道は現世にかかわり、仏教は死者祭祀をとおして来世に関係するという構図がますます明確化した。カミはこの世に関心をもち、ホトケは来世をつかさどるという職務分担ができあがったのである。それはいわば神仏の分業体制であり、今西錦司によって提唱された生態学的概念をもちいるとすれば、神仏の『棲み分け』にほかならない」
また著者は、神道や仏教の宗教の「メーカー」、イエや会社を「ユーザー」に見立て、以下のようなユニークな持論を展開します。
「視点をかえれば、宗教のメーカーとしての神道や仏教は独占の意図はもっているけれども、消費者ないしユーザーとしてのイエや会社は、カミとホトケを巧妙につかいわけているのである。したがって、会社宗教におけるカミとホトケの問題を考えるときには、その二分法的分業体制に注目しなければならない」
3「平等原理と不平等原理」では、「入社式というイニシエーション」として、著者は「入社式と社葬はかならずしも宗教的ではない。しかし会社宗教にとって重要なセレモニーであることにかわりはない」と述べています。著者によれば、日本では一般に会社は社縁の共同体と考えられており、地縁、血縁の次にならび称される縁の典型とみなされています。その共同体への加入と離脱を象徴化する演出が入社式と社葬にほかならないとして、著者は以下のように述べます。
「日本の会社ではふつう役所や学校とおなじように4月1日に一斉に新入社員をむかえる。かれらは同期とよばれ、出世競争のライバルでもあるが、時には助け合う仲間同士でもある。人類学的にみれば、入社式は年齢階梯制の新人に対する歓迎の儀礼の一種と規定できる。式の後は一定期間、新人研修が義務づけられている。そこではたんに会社の歴史や業務の概要を学ぶだけでなく、共同生活をとおして先輩後輩の関係や立ち居ふるまいを習得し、会社人としてふさわしい初歩的訓練を受ける。入社式と新人研修は、人類学の用語をふたたびつかえば、訓練や苦痛をともなうイニシエーションの会社版にほかならない」
いずれにしても、社会人になることは学生としての「死」と、会社人としての「再生」を意味しています。イニシエーションにおける「死と再生」のテーマが現代の会社においても働いているわけです。著者は、「『鎮めの文化』としての社葬」として、今度は社葬について以下のように述べます。
「一斉にイニシエーションを受けた人たちに対する平等の原理は、大村英昭の概念を借用すれば『煽る文化』として機能する。誰でも出世のチャンスはあるし、それは会社への貢献度によってはかられる。だが、平等原理は長つづきしない。組織の安定は実は不平等原理に秘密がある。日本の会社においても、熾烈な出世競争がくりひろげられ、重役の椅子までのぼりつめる社員は一握りしかいない。終身雇用といっても、定年まで皆つとめあげるわけではない。退社式も年度ごとに一斉におこなわれるわけではなく、個人の誕生日によって月ごとに実施されるケースが一般的である。もちろん途中で転職したり、関連会社に再就職したりする例もすくなくない。ましてや社葬の礼をもって社員から告別を受ける人は稀有である。入社式は全員が受けられるのに対し、社葬はごく少数のエリート(選ばれた人)だけが対象となる。ここでは不平等原理が優位に立っている」
このように入社式と社葬は、かたや平等原理にもとづく「煽る文化」、かたや不平等原理にもとづく「鎮めの文化」として位置づけられるとういうのです。著者によれば、「煽る文化」にはカミがふさわしく、「鎮めの文化」にはもっぱらホトケがかかわってきました。図式的にいうと、前途を祝福し競争を煽るのがカミの役割であり、過去を顕彰し魂を鎮めるのがホトケの任務となっているというわけです。これもユニークな見方ですね。
ここで著者は、企業博物館というものを取り上げます。
「ビジネスを神聖化する装置―歴史展示と事業展示」として、著者は企業博物館について以下のように述べます。 「わたしは企業博物館を会社の『神殿』とみなすことができると考えている。なぜならそれはビジネスを神聖化する装置にほかならないからである。ビジネスを世俗のこととして宗教から遠ざけたのは欧米の会社である。日本ではこれまで論じてきたように、会社には宗教的次元が陰に陽に組みこまれている。労働やビジネスに神聖な価値をみとめることに、労働者も会社もほとんど躊躇することはなかった。工事の開始にあたって地鎮祭をとりおこなうのは、たんに安全祈願のためだけではない。事業に神聖な価値を付与してもいるのである」
日本には企業博物館が多いそうですが、それはなぜでしょうか。 著者は、その理由について以下のように述べています。
「日本に企業博物館がおおい理由は、日本がたんに繁栄する企業国家になったということだけでなく、仕事や道具に敬意を表し、それを神聖化してきた伝統をもつからでもある。社業を人びとから尊敬に値するものとして認知してもらうこと、そこに企業博物館設立のかくれた意義がひそんでいる。企業博物館の展示はおおきく2つにわかれる。会社や創業者の歴史展示と、技術や製品にかかわる事業展示である。神殿論を媒介にしてそれを解読すると、日本の場合、やはりカミとホトケにいきつく。つまり、歴史展示は過去や死者を問題にするのでホトケの側に位置づけられる。他方、事業展示は商売繁盛を願う神社の側にたつ。寺院と神社が過去と現在で機能分化しているように、企業博物館の展示もホトケの心とカミの魂に分化しているのではないだろうか」
 TOTOミュージアムの前で
TOTOミュージアムの前で
 TOTOミュージアムのエントランス
TOTOミュージアムのエントランス
わたしのブログ記事「TOTOミュージアム訪問」で紹介したように、わたしは今年の1月22日に「TOTOミュージアム」を訪れました。これは、北九州市を代表する企業の1つであるTOTOさんが2017年に創業100周年を迎えることを記念してオープンした企業博物館です。この立派な施設を見学して、わたしは「たしかに企業博物館は神殿だ!」と思いました。北九州には、このTOTOミュージアムの他にも、安川電機さんの「ロボット村」、ゼンリンさんの「ゼンリン地図の資料館」といった素晴らしい企業博物館が存在します。わが社も、いつか「冠婚葬祭博物館」を作りたいものです。
4「カミとホトケの五行説」では、「社縁共同体の誕生」として、著者は以下のように述べています。
「ヨーロッパでは近代にはいり地縁や血縁に代わるあらたな社会関係が形成され、ゲゼルシャフトとかアソシエーションという概念が提出された。それに対し、日本では文化人類学の米山俊直によって社縁の概念が1960年代の初頭に提起された。米山は『会社縁』の意味でジャーナリスティックに使いはじめられていた『社縁』をより包括的な『結社縁』の意味で定義しなおした。地縁・血縁とならんで鼎立する関係概念として、また工業化・都市化にともないその重要性がいちじるしく増大した関係として、それを打ち出そうとした。その背景には、戦後、経済的に高度成長を遂げつつあった時代に、地縁集団、血縁集団とならんで社縁集団が台頭しつつあったことがあげられる。社縁概念は会社が発展した時代背景のもとに『生まれるべくして生まれた』概念だったのである」
続けて、著者は「社縁」のルーツについて述べています。
「社縁のルーツは江戸時代の組、講、連、社、流、派などにもとめることができる。また社縁が発達した要因としては、日本が中国・韓国とくらべて父系血縁原理のよわい国であり、むしろ家父長的なイエがそもそも社縁的な社会単位でもあった点にもとめることもできる。いずれにしろ、日本に特徴的な擬制的なオヤ―コ関係がイエから社縁への道をひらいたのである。そうして誕生した社縁は、現代社会においてもっとも発達した社会関係のひとつであることはまちがいない」
さらに続けて、著者は「社縁」について以下のように述べます。
「社縁はもともと加入・脱会の自由な第2次的集団をさす造語だが、日本ではバブル・エコノミーがはじけた1990年代にいたるまで、社縁の典型である会社縁をみてもあきらかなように、会社にいったん就職するとなかなか退社できないほど、その拘束性もつよかった。その社縁共同体には年中行事に比することのできる歳時記がある。また、秩序を保持するための独特のルールも存在する。社是・社訓あるいは家憲がその例である。そうしたシステムは会社の発展にともない充実し多様化してきた」
第二章「会社神社と社縁共同体」の1「会社神をまつる神社」では、「会社神のタイプ」として、著者は以下のように5つに分類しています。
(1)業者ないし創業家の信仰する神。創業者の出身地に鎮座する宗像大社の祭神をまつる出光興産、2代目当主の崇敬した琴平神社をまつるキッコーマンなどがその例である。
(2)会社や工場の立地する地元の神。 たとえば香取神社の祭神をまつる成田の日本航空、札幌神社の分霊をまつるサッポロビールなどがあげられる。
(3)業種に関係の深い祭神。これは商売繁盛を祈願する稲荷を筆頭に、酒の神の松尾大社など枚挙にいとまがない。
(4)国家の祭祀と結びついた神。典型としては伊勢神宮の祭神をあげることができる。とりわけ天照皇大神を祭神にくわえている会社がめだつ。
(5)人を神としてまつる場合。たとえば明治天皇の例があり、招魂社に創業の功労者や物故社員をまつるのも広義にはこの分類にあてはまる。
ここで、(1)は屋敷神をはじめとする「イエの神」が会社神のモデルとなっています。(2)は地元の「氏神」を会社に取り込んだもの。(3)はいわゆる「機能神」で、農業・漁業・商業など特定の分野をつかさどる神です。(4)は「国家神」で、(5)は「人神」です。 『神社新報』で「企業の神社」シリーズを担当した宇野正人氏は、会社神を「創業者、あるいはそれに類する人の信仰する神社が祀られる場合」、「その立地するところの産土、氏神の神社が祀られる場合」、そして「その業種に関連する神を奉祭する神社が祀られる場合」の3つのタイプに分類しました。著者の5分類は、この宇野説を修正したものです。
会社神に対しては、さまざまな儀礼が行われます。 これは会社にとって、どのような意味があるのでしょうか。 「社内に対する統制ツール」として、著者は以下のように述べます。
「会社神に対する儀礼は厳格な規律が要求される会社組織にとって重要な意味をもっている。大祭では社長以下の重役・幹部が序列にもとづいて参列し、祝詞とともに業務報告を神に奏上したり、会社の発展や操業の安全、さらに社員の健康などを祈願したりする。松下電器の洗濯機事業部でおこなわれた会社神社の大祭では出席予定者の人数分しか椅子が用意されておらず、欠席者がただちに判明するしかけを講じ、組織の引き締めをはかっていた。プロローグで引用した企業の社会的責任(CSR)に引きつけて言えば、儀礼は『社内に対する統制ツール』として機能しているのである」
続けて、著者は会社儀礼について以下のように述べています。
「大祭の日には記念行事やパーティーが開催されることもある。会社儀礼を担当するのはふつう総務部門であり、祭祀担当社員のいる松下電器のような例外をのぞき専属の神官をかかえることはない。入社式に神社参拝がおこなわれたり、社員研修に会社神の系列の有名神社への参拝をとりいれたりしているところもある。このように会社組織へのアイデンティティーと会社神への儀礼は密接につながりあっている。また、会社儀礼では、海の幸・山の幸とともに、松下電器の電気洗濯機のように、当該工場でつくられた製品を「初穂」の供物として奉納することがある」
第三章「会社墓と日本的経営」の1「高野山と比叡山」では、「資本とは別の論理」として、著者は以下のように述べています。
「会社神社がカミの側を代表する施設だとしたら、会社墓はホトケの側の最右翼に位置する。どういうわけか墓や供養塔をもっている会社は関西の企業におおく、高野山と比叡山に集中している。本章では、高野山と比叡山における会社墓の歴史とその祭祀の実態をしめし、現代日本人にとって会社とは何かを考える手立てとしたい。高野山には100をこえる会社供養塔がきそうように建立され、比叡山にも20以上の法人墓が存在する。こと会社墓に関するかぎり、高野山が日本最大のセンターであり、比叡山がそれに次ぐ」
また著者は、「学問仏教と庶民仏教」として、比叡山と高野山について、以下のように述べています。
「比叡山と高野山は日本を代表する仏教の中心地である。比叡山は最澄(伝教大師)、高野山は空海(弘法大師)によって開山され、それぞれ天台宗と真言宗の総本山であることは言うまでもない。比叡山と高野山を比較すると、前者が学問仏教の最高学府であったとすれば、後者は庶民仏教の最大聖地であった。そのため比叡山は『仏教の母山』とよばれ、高野山は『日本総菩提所』とうたわれる。そうした性格の相違は、墓地の形態にも如実にあらわれている。比叡山には伝教大師の廟や僧侶の墓はあっても、在家の墓地はなかった。これに対し、弘法大師廟のある高野山奥の院では、古代末期以来の納骨・納髪や塔婆供養の風習がいまでもさかんである。そればかりか奥の院につらなる旧参道の両脇には、大名供養塔(大名墓)をはじめとする無数の墓石群が鬱蒼とした木立のなかに林立している。現存する最古の墓石は平安末から鎌倉初期の五輪塔の残欠であり、墓石数は20万をこえるといわれる」
第四章「会社への加入儀礼=入社式」の1「同期の桜」では、著者は入社式について、「年齢階梯制」として以下のように述べています。
「一斉に入社した仲間は『同期の桜』として、またライバルとして、会社人生の苦楽を共にしていく。会社における年齢集団のきずなは4月の一斉入社に基礎をおいているのである。人類学的な視点からすると、そのような『同期の桜』はオセアニアの島々やアマゾンの密林に、あるいはアフリカの戦士集団として分布している年齢階梯集団のイニシエーション(加入礼)とダブってみえる」
第五章「会社の不滅と再生の儀式=社葬」の1「創業者の社葬」では、社葬について、「社葬とトップ・マネジメント」として述べます。
「社葬は会社に貢献のあったトップ経営者に対して、会社の名のもと、資金面でも動員力の点でも、会社が全面的に主催するところの葬儀である。日本で顕著な発展がみられたが、韓国などでも多少おこなわれている。社葬は故人にとって2度目の葬儀であり、遺族中心の『密葬』『仮葬』に対し、『本葬』と位置づけられている。ジェームズ・ボンド風に言えば『社長は2度死ぬ』のである。その準備のため、死亡してから数週間、時には2ヵ月も時間をかける。すでに近親者による密葬はすませてあり―会社が実質的に協力する場合もおおいが―、本葬といっても告別式が中心となる。最近は寺院や葬儀専門の施設ではなく、無宗教式でホテルを会場にえらぶところが増えてきた。 わたしが社葬に注目するのは、それがトップ・マネジメントとふかくかかわっているからであり、ひいては会社文化を象徴的に演出しようとしているからでもある。社葬は経済的には損金の対象としてしか計上されないかもしれないけれど、経営的には会社経営の継承と会社カラーの演出という、すぐれて社会的・文化的命題と直結しているのである」
続けて「不滅と再生」として、社葬の基本的性格について述べます。
「社葬の基本的性格はおよそ次のとおりである。第1にたんに故人の冥福をいのるだけでなく、会社として故人を顕彰し告別することに重点が置かれる。つまり会社組織によって告別の演出がなされるのである。そのため、第2の特徴としては、会社の威信が社葬にかかっていることが指摘できる。会社が多大の時間と労力を投入して実施する社葬は、落ち度があっては故人と会社の名をけがすことにつながりかねない。したがって、細心の注意をはらって準備がなされ、不測の事態にそなえて臨機応変の対応がはかられる。第3に、社葬は会社同士の互酬的なつきあいのなかで存続している習俗である。会社づきあいの儀礼的慣行のひとつであり、社外にひらかれた儀式の場でもある。そこでは故人の死にもかかわらず会社が存続することを内外に表明する機会となる。これが第4の特徴で、会社の不滅と再生が演出される。権力の継承が象徴的に演じられることもおおい。そして、最後に社葬の性格としてあげたい顕著な点は、不平等の演出がなされることである。社葬はトップ経営者に対象が限定される。入社式には新入社員全員が参加するが、トップにのぼりつめないと社葬の礼を受けることはできないのである」
また著者は、創業者の社葬について以下のように述べています。
「創業者の社葬はトップ経営者の社葬のなかでも突出した性格をもたされている。というのは、イエにたとえれば創業者は初代の先祖にあたるからである。先祖のDNAが子孫に継承されるように、創業者の精神も従業員に何らかの形で引き継がれていく。また家風と同様、社風も見えざる掟として伝承されていく。とはいえ、会社の顔であった創業者の死は会社に変化をもたらす機縁を提供している。DNAを組み替え、社風を変革する可能性も秘めている。したがって、創業者の社葬をどう演出するかによって、会社の方向がおおきく決定づけられることもありうるのである」
4「社葬の意義」では、「王殺し」として、著者は述べます。
「社葬は”王殺し”にとどめを刺す儀式である。とりわけ創業者の社葬は「神聖なる王の殺害」に類比することができる。J・フレーザーはその記念碑的な著作である『金枝篇』において、王権の定期的更新の際に王を殺害する儀式の痕跡がみとめられると主張した。王の肉体的な力が弱体化すると国土は疲弊し臣民も飢餓の苦難におちいるとされ、それを予防するために、後継者が生きたまま王を殺害することによって王権の活性化がはかられたと論じた。王の殺害は植物の死と再生を模倣したもので、前王は死して新王としてよみがえるとされた。これにたいし、数々の批判はあるものの、現代の創業社長にあてはめてみると、納得のいく要素もみいだされる。たしかに創業者は神格化され『神聖なる王』にちかづいていく。社長や会長からの退任は”王殺し”の第1歩、第2歩である。しかし、創業者が名誉会長・相談役などのかたちでとどまっているかぎり、社内には過激な変革は実行できないという雰囲気がただよいつづける。だが、社葬後はかなり自由な経営がゆるされるようになる。その意味で社葬は”王殺し”にとどめを刺す役割をになっている」
第六章「会社の神聖化装置=企業博物館」の1「会社の神殿としての企業博物館」では、著者は「神聖化装置」として以下のように述べます。
「企業博物館を何か別のものにたとえるとしたら、わたしは神殿がもっとも近いのではないかとおもう。その役割は神聖化である。つまり、企業博物館を会社の神聖化装置のひとつとみるわけである。企業理念も企業文化も神聖化がほどこされて展示されている。その場所が、企業の設立するミュージアムにほかならない。 ミュージアムをテンプル(神殿)としてみる見方はすでにダンカン・キャメロンによって提示されている。かれは重要で価値のあるものをまつるのがテンプルであり、ミュージアムは社会学的には学校よりも教会にちかいと指摘している。ただし、かれの議論はテンプルと対比されるフォーラムとしてのミュージアムであって、体験や討論が可能な場としての公的で開かれたフォーラムこそあたらしいミュージアムの形態としてのぞましいと論じている。テンプルとしてのミュージアムだけでは変革の障害となるとも」
また著者は、企業博物館について以下のように述べます。
「オリュンポスの神々の場合、主神ゼウスもミューズたちも家族・親族の系譜によって表象されているが、日本では企業博物館の神々は創業者を筆頭に代々継承される先祖祭祀のおもむきで表現されている。創業者は会社の先祖にほかならず、同族企業はことのほかその色彩がつよい。他方、企業博物館のミューズは、ヒット製品とみなすこともできようし、それぞれの展示コーナーにたとえることもできるだろう。そして現場の従業員たちは、ご先祖さまの薫陶よろしきをえて、製造・販売の活動にいそしんでいる」
 便器にも歴史あり!(TOTOミュージアム)
便器にも歴史あり!(TOTOミュージアム)
 先人の業績を展示(TOTOミュージアム)
先人の業績を展示(TOTOミュージアム)
2「展示にみるカミとホトケの相克」では、「会社の過去・現在・未来―社業展示」として、著者は以下のように述べます。
「社業展示は会社の値うちをひろく一般に知らしめるものである。製造業ならば、社業をとおして、会社が何を生産し、人びとの暮らしにいかに役立っているかを提示しようとするにちがいない。会社が人びとの尊敬をかちえるのは、やはり社業が基本である。ただし、社業は経済的価値が優先されるので、尊敬よりも経済的なニュアンスをもつ、信用とか信頼のほうがふさわしいかもしれない。 社業展示には大別するとふたつの類型がみられる。ひとつは歴史展示で、もうひとつは事業展示である。前者は創業以来の物的資料や文献資料を時系列的にならべるもので、後者は事業内容を構造的・機能的にしめすものである。歴史展示は過去にかかわり、事業展示は現在ないし未来に、より関心をはらっている」
また著者は、「歴史展示は寺院、事業展示は神社に相当する」として、以下のようなユニークな論を展開します。
「企業博物館=神殿論を日本にあてはめた場合、ゆきつくところは神社や寺院である。神社と寺院、あるいはカミとホトケは、日本宗教史におりこまれた縦糸と横糸の関係にある。神社と寺院は明治の神仏分離以降ますます役割を特化させ、神社はこの世、寺院はあの世をもっぱらあつかうエージェントとなった。事業展示が現在にかかわるのに対し、歴史展示は過去にこだわっている。事業展示がもっぱら商売繁盛をめざしているのに対し、歴史展示は過去の顕彰と鎮魂をおもな目的としている。それはちょうど神社や寺院のそれぞれの役割と平行的関係にある」
第七章「経営者と宗教」の1「経営者はなぜ宗教にひかれるのか」では、著者は「経営宗教」として以下のように述べています。
「会社経営者の経営思想はしばしば『経営哲学』とよびならわされる。それにならうならば、会社経営における経営者のいだく宗教観や宗教行動を『経営宗教』と称することはゆるされるだろう。会社宗教が組織としての会社にかかわる宗教的側面であるのに対し、経営宗教は経営者が個人としていだく思想や行動にかかわる。たとえば『和をもって尊しとなす』で有名な聖徳太子の十七条憲法の『和』を会社の経営理念として掲げる経営者はすくなくない。
儒教もまた近代の経営者に少なからぬ影響を与えています。近代日本の頂点に立つ実業家・渋沢栄一は『論語』の教えを重視し、「義にかなった利益の追求」(義利両全説)を唱えました。渋沢の影響を受けた経営者は数え切れないほどです。さらに経営宗教のスーパースターに安岡正篤がいます。儒教の中でも「安岡教学」とよばれる思想は戦中・戦後の経営者に精神的な支柱を提供しつづけてきました。著者は以下のように述べます。 「『安岡教学』とは漢学者・安岡正篤の思想と実践を指し、『歴代首相の知恵袋』として吉田茂をはじめとする政治家が信頼を寄せていたことでも有名である。『吉田学校』の系譜を引いた『宏池会』は彼の命名である。財界にも『安岡教学』の傾倒者は数知れず、その著作ならびに関連の書物は現在でも人気がたかい。かつては『師友会』という全国組織があり、いまでも『関西師友協会』が独自の活動を継続している」 経営者としてのわたしも、渋沢栄一と安岡正篤を深く敬愛しています。 彼らから学んだことについては、拙著『孔子とドラッカー 新装版』(三五館)に詳しく書きました。
『孔子とドラッカー 新装版』には、「経営の神様」と呼ばれた松下幸之助も何度も登場します。現在は「パナソニック」と社名変更した松下電器には龍神をまつる祠が各工場に存在しますが、2「松下幸之助の経営宗教」で著者は以下のように述べています。
「祭祀を担当するのは、関西では本社の総務部付の宗教家である。司祭とよばれ、現在は4代目であるが、初代の加藤大観は祭祀をつかさどるだけでなく松下幸之助の相談相手としても重宝がられていた。いまでも門真の本社にある大観堂にその名をのこす加藤大観は真言宗醍醐寺で修行を積んだ宗教家で、歴代の司祭も醍醐寺での修行を継承している。司祭は僧職にありながら神社祭祀もおこなう点でいかにも神仏混淆の醍醐派の面目躍如といえるが、主たる任務は毎日、多いときは3回も執行されている龍神のまつりである。関西地区以外の社屋や工場でも醍醐寺に縁のある地元の寺の住職が祭祀を依頼されている。このように松下電器は会社宗教としての独自の施設、儀礼、司祭を有している」
なお、松下電器の本社の中央広場にはエジソンを中心に、ファラデー、オーム、マルコーニ、アンペール、フィリップス、関孝和、平賀源内、佐久間象山、橋本曇斎、豊田佐吉の銅像群が立ち並んでいるそうです。いずれも松下幸之助に影響を与えた人物だそうですが、三度の飯より銅像が好きなわたしはぜひ訪問してみたいです。社名変更した今でも、銅像はそのままなのでしょうか?
 ぜひ訪れてみたい!
ぜひ訪れてみたい!
エピローグ「宗教からみた経営」では、「遊びとしての文化」として、著者は文化人類学者の山口昌男先生について以下のように述べています。
「国際化の時代に対応できるのは、『遊びとしての文化』をわすれない企業ではないか、と『両義的存在』のトリックスター研究や『中心と周縁』論で有名な文化人類学者の山口昌男はかんがえている。『経営者の精神史』で山口が取り上げた人物は近代日本の形成に良きにつけ悪しきにつけ一役買った破天荒な経営者たちであり、剣豪、茶人、写真家、喜劇作家、美術コレクター、古銭コレクター、野球導入の立役者などである。つまり、文明の中心に位置する企業を活性化できるのは周縁的な「遊びとしての文化」だというわけである。さらに、20数年前にある編集者から出版企画を打診され、経営人類学で本を書くとしたら『経営・狂気・破壊』というタイトルになるとまで言っている」
生前の山口先生には、わたしも大変お世話になりました。 わたしのブログ記事「山口昌男先生の思い出」で紹介したように、わたしは、2013年3月10日に逝去された山口先生に新宿の「火の子」という酒場で御馳走になったことがあります。『遊びの神話』が刊行された1989年当時、山口先生は「ニューアカの親分」として大変な威光でした。影響を受けた学者や文化人はかなりの数で、その強大な人脈を称して「山口組の組長」などとも呼ばれていました。山口先生は、『遊びの神話』を手にされて、「これ、読んだよ。面白いじゃないか、よく書けてる」と言って下さいました。まだ20代の若造だったわたしは、涙が出るほど感激しました。「ディズニーランドは現代の伊勢神宮である」という帯のコピーについても、いろいろと意見を交換させていただきました。その御縁で、山口先生とは『魂をデザインする~葬儀とは何か』(国書刊行会)本で対談させていただきました。日本を代表する大思想家と対談させていただいたことは、わが人生の宝です。
最後に、著者は「企業の持続可能性」として、以下のように述べています。
「投資業界で10年以上はたらき教職に転じたローレンス・ミッチェルは、エンロン事件を予測したかのように、株主利益の最大化に警鐘を鳴らしている。短期的に株主利益の最大化をはかることは長期的には破壊的な価値観をもつことであり、そうした経営は無責任のきわみであると主張する。アメリカ企業の法的・財務的構造が短期的経営につよい競争優位をあたえたことが問題であり、それが株主利益の最大化に収斂すると指摘する。しかし、企業はたんに生活のためにはたらく場ではなく、それを通じて意味と他者との絆を得る場でもあるとかんがえ、経済に対する文化の影響を重視する。ミッチェルは日本語版の序文では『アメリカ市場における日本の自動車産業の成功は、自らの方式を用いたことに加えて、働く人々のニーズと幸福に最大の配慮を惜しまなかったからにほかならない』と述べ、株主至上主義ではない経営文化に言及している」
わたしの本名ブログである「佐久間庸和の天下布礼日記」を読まれている方ならおわかりでしょうが、わが社は入社式などをはじめ、数多くの会社儀礼を積極的に行っています。これはナレッジ・マネジメントの一種としての「儀式マネジメント」という側面もありますが、なによりもわが社のビジネスそのものが儀式産業だからです。「礼」を重んじるのは当然であり、儀式を行うのも当然だからです。創業者である父はまだまだ元気いっぱいですが、いつの日か社葬も盛大に行うことでしょう。本書を読んで、「わが社の行き方は間違っていない」と思いました。
