- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2016.11.09
『経営は哲学なり』野中郁次郎編(ナカニシヤ出版)を再読しました。
2012年2月25日に刊行された本で、一橋大学名誉教授で日本を代表する経営学者である野中郁次郎氏が編者を務められています。 野中氏といえば、ドラッカーの日本への紹介者としても知られ、自身も米クレアモント大学ドラッカースクールの名誉スカラーでもあります。 サンレー創立50周年記念出版となる『ミッショナリー・カンパニー』(三五館)の参考文献として、本書を読み返しました。
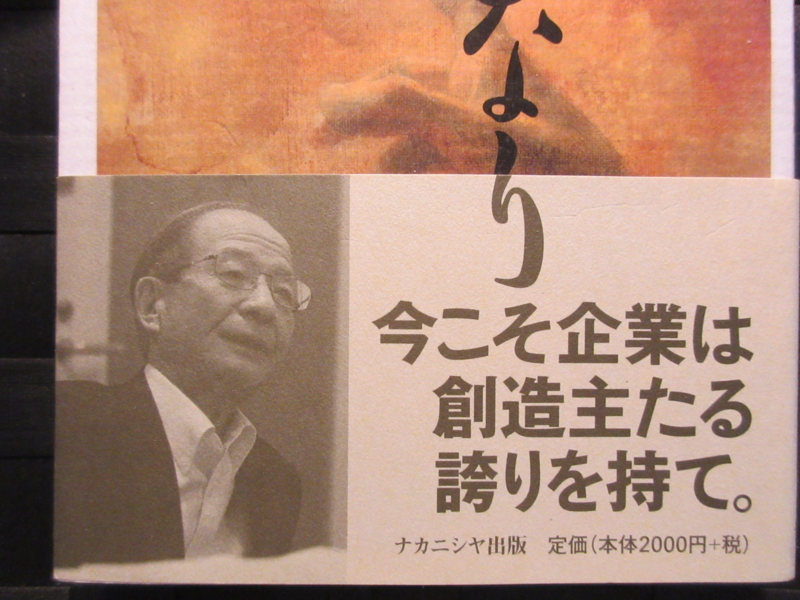 本書の帯
本書の帯
本書の帯には野中氏の写真とともに「今こそ企業は創造主たる誇りを持て。」と書かれています。また、帯の裏には以下の内容紹介があります。
「企業はいったい何を信じて経営すればよいのか。従来の日本型経営では戦えない。アメリカ型のグローバル・スタンダード経営では展望が開けない。新興国の台頭、低迷する日本経済、ユーロ危機、そして東日本大震災。経営環境が厳しいことが当たり前になるなか、日本企業が本来の輝きを取り戻すために必要なものは何か。経営は哲学なり。経営スキルの時代から、再び経営哲学が問われる時代へ。もう本当の変革は始まっている。企業、リーダー、文献。これらの豊富な事例のなかから答えとなる哲学を見出していく」
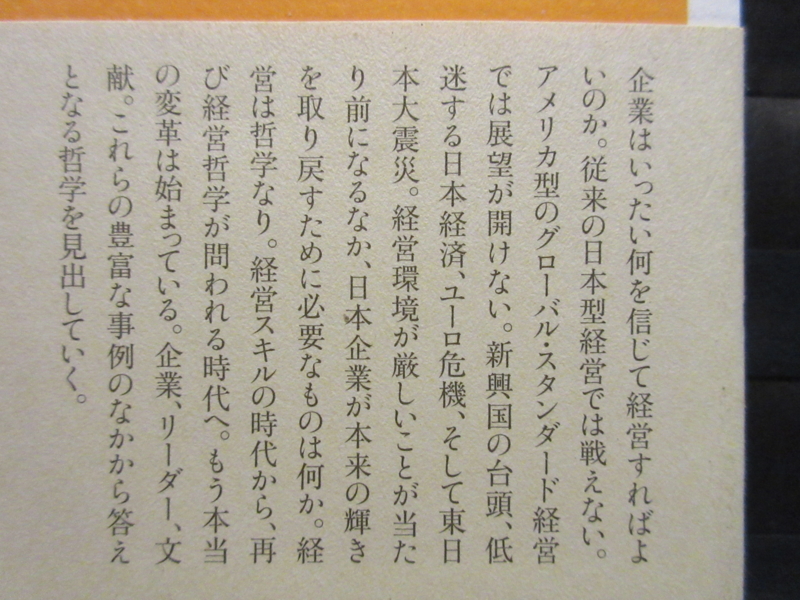 本書の帯の裏
本書の帯の裏
本書の「目次」というか章立ては、以下のようになっています。
「はじめに」(野中郁次郎)
序章 哲学の意義(平田透)
第1章 現場の哲学(成田康修)
第2章 変革の哲学(磯村和人)
第3章 創造の哲学(弦間一雄)
終章「未来へ」(野中郁次郎)
「はじめに」の冒頭を、野中氏は以下のように書き出しています。
「組織を構成する最小単位は、人である。しかし、個人と組織は、目的や行動原理が大きく異なる。そのため、人が組織に加わる動機はさまざまであり、複数の人が参加する組織を一体化して経営していくことは、なかなか難しいのが現実である。これまで、企業の経営は、さまざまな側面から論じられ研究されてきたが、そのもっとも基本となるのは経営者の思想、哲学である」
また、野中氏は「経営は哲学なり」という言葉は、具体的な財務数値などには換算できないといいます。それは無形資産である哲学に対する、執筆者の思いが込められているとして、「古今東西を問わず、すぐれた経営は、明確な哲学が基盤にあった。現在のように「明日は何がおこるかわからない」という不確実で流動性の高い時代において、企業の未来における『あるべき姿』を描き進むべき方向を定めるには、実践と結びついた哲学が求められる」と述べます。
さらに、野中氏は以下のように述べるのでした。
「混迷の時代において、何を手がかりに組織の意思決定を行い、何を基準に行動すべきなのか。それに対する答えが『哲学』であり、それをもつリーダーである。『経営は哲学なり』は、われわれの未来を切り拓くための不変の道標といってよい。以下、本書では、変化する現実に対応し、実践に活用するためのエッセンスとして哲学の意義とリーダーの役割を提言していこう」
序章「哲学の意義」では、金沢大学人間社会研究域経済学経営学系教授の平田透氏は、組織における哲学について、「経営の柱」として以下のように述べています。
「組織の成員が、社会的に正しいと思える企業哲学もしくは基本的価値観を共有し、そこから派生する理念を信じて働くときは、求心力やモチベーションが高まるだけではない。価値観は、行動するうえでの指針や判断基準のベースとして機能する。つまり、哲学は、組織のマネジメントにおける柱となるものなのである」
また、平田氏は「変化のなかで」として、プロセス哲学について述べます。
「経営においては『これを行えば絶対確実』という絶対的法則もしくは普遍的方法論は存在しない。なぜなら、企業を取り巻く環境は、複雑な因果関係と偶然性に満ちており未来は不確実だからである。事象の絶え間ない変化のなかでは、有効とされる既存の考え方や仕組み・方法論は陳腐化していく可能性をつねにもつ。過去の成功体験にとらわれすぎると、しばしば失敗するのはこのためである。『万物流転』といわれるように、環境におけるさまざまな事象は相互に有機的な関係性をもっており、それが時事刻々と変化するためまったく同じ状況は二度と発生しない。このように、世界は相互に関係するプロセスや出来事の連なりによって形成されている有機的な網であり、すべては生成消滅を繰り返す関係性のなかにあるという世界観は『プロセス哲学』と呼ばれている」
さらに平田氏は「限界を超えるのは」として、企業経営について以下のように述べています。
「企業経営においては、ある事実関係において確証が得られなくとも判断を下さなければならない状況に直面することも多い。不完全な情報のもとでは、厳密な客観的事実から論理的に結論を導くだけでは不十分であり、どのように判断すべきか(もしくはどうありたいか)という基準に照らして直観的に判断する『実践的推論』が有効である。そのときに、未来へ向けての方向を示し、行動するよりどころとなるのが経営哲学もしくは経営思想である」
平田氏によれば、経営の神様といわれた松下幸之助が卓越していたのは、企業を経営という狭い範囲で考えず、大きな世の中もしくは大宇宙の流れのなかでとらえようとし、プロセス哲学と同じような考え方をもっていた点にあります。平田氏は述べます。
「経営とは、人知を超えた自然の節理に従いつつ、そのなかで企業自らの存在意義や社会的価値といった本質を見極め、到達すべき正しい目標を明らかにすることであるという。何が正しい目標なのかは『天然自然の理』と『生成発展』の原則を踏まえて経営者が熟慮することにより見出される。その正しい目標へ向けて衆知を集め、どのような方法で実践していくのかを見極め、長期的な視点に立ってそれを推進していくことが幸之助の経営の要諦であった」
第1章「現場の哲学」の冒頭では、公益企業の社員である成田康修氏が、「現場は、われわれの哲学である」として、以下のように述べています。
「現場での経験を通じ、われわれは心のなかに哲学を生み出す。この哲学は、ものごとを理解するための枠組みとなる。哲学がなければ、日常の現象から意味を引き出せず、現場を理解できない。ゆえに、現場を理解するためには、われわれ自身の哲学を理解する必要がある」
また、成田氏はヨーロッパを例にあげ、「ヨーロッパには多様な哲学を尊重してきた歴史があり、それが社会発展の原動力のひとつでもあった。例をあげれば、ルネサンス期の芸術家はチームを組んで絵を描いていたが、彼らは素人画家の哲学をも尊重したという。多様な哲学を尊重する姿勢は、個性を認め、人間を尊重する出発点となる」と述べています。
そして、成田氏はローマ帝国の名をあげ、以下のように述べるのでした。
「哲学のあり方は現場だけでなく、国家の存亡をも左右する。ローマ帝国を支えていたリーダーは、自らが国を支えるという善き哲学をもっていた。だが、国難に際し、彼らは善き哲学を捨ててしまった。その結果、ローマ帝国は滅んでいった。哲学なき存在は無のような存在へと帰結するのである」
現代日本の経営者の大半は哲学を持っていません。 わたしが経営するサンレーの経営理念である「S2M 」の1つの「サポート・トゥー・モラル」に謳われている道徳や倫理というものは哲学の一部ですが、しっかりした道徳や倫理を持っている経営者は少ないと思います。ところが、この読書館でも紹介した『稲盛和夫の哲学』の著者である稲盛和夫氏は、経営における道徳・倫理というものを本気で考え、かつ実行している稀有な経営者であるといえます。
「人間は価値ある存在なのか」「この世に生を受け、生きていく意味とはどこにあるのか」・・・そのように「人間」というものに対して核心をつくような問いを受けたとき、稲盛氏は次のように答えるそうです。
「地球上・・・・・・いや全宇宙に存在するものすべてが、存在する必要性があって存在している。どんな微小なものであっても、不必要なものはない。人間はもちろんのこと、森羅万象、あらゆるものに存在する理由がある。たとえ道端に生えている雑草一本にしても、あるいは転がっている石ころ一つにしても、そこに存在する必然性があったから存在している。どんなに小さな存在であっても、その存在がなかりせば、この地球や宇宙も成り立たない。存在ということ自体に、そのくらい大きな意味がある」
 『ホスピタリティ・カンパニー』から『ミッショナリー・カンパニー』へ
『ホスピタリティ・カンパニー』から『ミッショナリー・カンパニー』へ
宇宙の中で「存在する」ということは、あるものが自立的に存在するのではなく、すべてが相対的な関係のなかで存在するということになります。さらに考えを進めていけば、他が存在しているから自分が存在するし、自分が存在するから他が存在するという、相対的なつながりにおいて存在というものが成り立っている、ということができます。 釈迦ことゴータマ・ブッダはこれを「縁があって存在する」というふうに表現しましたが、つまるところ哲学的思考とは、宇宙の中における人間の位置や、自然の秩序や人生の意味などについて深く考えをめぐらせることだといえます。わたしは、自分なりに経営哲学というものを考えていきたいと思い、『ハートフル・カンパニー』『ホスピタリティ・カンパニー』(ともに三五館)を上梓しました。そして、現時点でのわが経営哲学は『ミッショナリー・カンパニー』に記しました。
ご一読下されば幸いです。サンレー創立50周年まで、あと9日!

