- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.1417 心霊・スピリチュアル 『震災後の不思議な話』 宇田川敬介著(飛鳥新社)
2017.04.16
『震災後の不思議な話』宇田川敬介著(飛鳥新社)を読みました。
3・11後の被災地で語られた「幽霊」の噂を丹念に取材した本です。
著者は1969年東京都生まれのフリージャーナリスト、作家。94年中央大学法学部卒業、マイカルに入社。法務部にて企業交渉を担当。マイカル破綻後に国会新聞社に入社、編集次長を務めました。
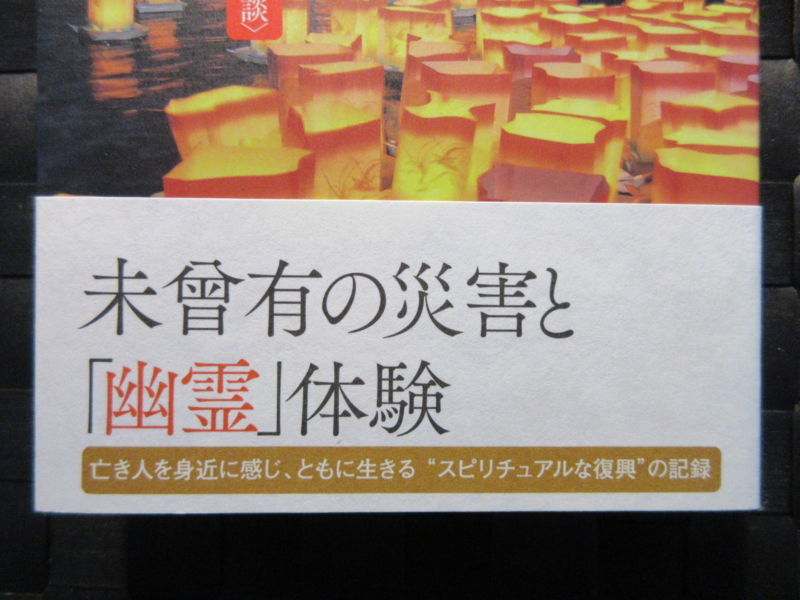 本書の帯
本書の帯
本書の表紙には、東日本大震災から5か月、福島県南相馬市で花火が上がる中、津波の犠牲者を悼み流される灯籠の写真が使われています。
帯には「未曾有の災害と『幽霊』体験」と大書され、続けて「亡き人を身近に感じ、ともに生きる “スピリチュアルな復興”の記録」と書かれています。
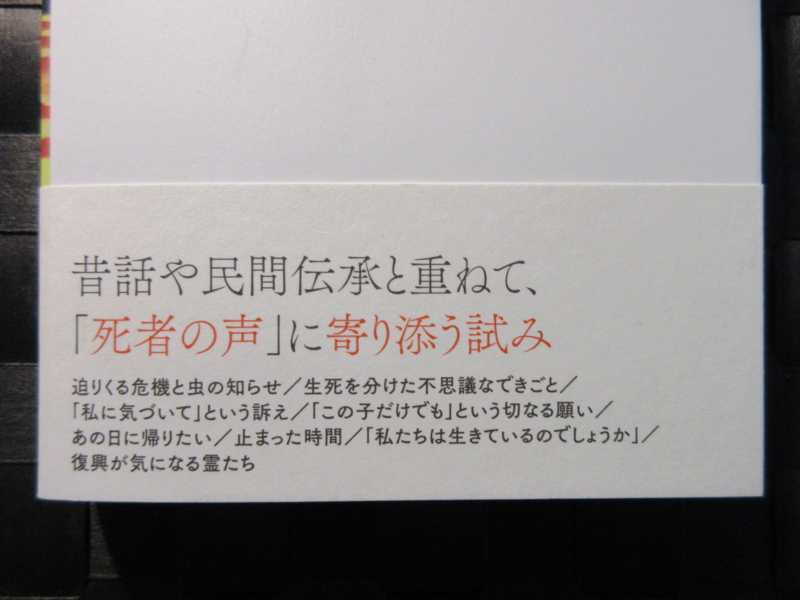 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、「昔話や民間伝承と重ねつつ『死者の声』に寄り添う試み」と大書され、続けて、「迫りくる危機と虫の知らせ/生死を分けた不思議なできごと/「私に気づいて」という訴え/「この子だけでも」という切なる願い/あの日に帰りたい/止まった時間/「私たちは生きているのでしょうか」/復興が気になる霊たち」という「目次」の内容が記されています。
本書の「目次」は、以下のような構成になっています。
第一幕 迫りくる危機と虫の知らせ
前 段 荒ぶる神々と予知能力
第一段 「虫の知らせ」とは
第二段 生死を分けた不思議なできごと
第二幕 「助けて」という願望
前 段 海の中の出来事
第一段 「私に気づいて」という訴え
第二段 「この子だけでも」という切なる願い
第三幕 あの日に帰りたい
第一段 帰るべき場所
第二段 止まった時間
第三段 生きている人を引き込む霊
第四幕 見守っています
第一段 死者を祀る
第二段 復興が気になる霊たち
「おわりに」
第一幕「迫りくる危機と虫の知らせ」の前段「荒ぶる神々と予知能力」では、「災害に対する先人たちの知恵」として、著者は以下のように述べます。
「昔の人のほうが、科学の力を借りなくても、自然と共存する暮らしをしていました。つまり自然からさまざまなことを教えてもらっていました。現在の科学ではわからない何かが、そこにはあったのかもしれません。震災や災害についても、自然から教わる状況があったように思います」
「科学がない時代、地震は神やナマズのような妖怪が起こすものとされました。自然災害は、普段は静かで、豊穣をもたらしてくれる神々が、何らかの理由で『荒ぶる神』になって、人々に何かを知らせようとしたり、反省を促すという理屈です」
著者いわく、災害を引き起こす「荒ぶる神」の怒りを鎮め、ほかの神々の力を借りて村落共同体を維持し、自然と共存するわけです。「荒ぶる神」については、以下のようにも述べています。
「荒ぶる神も怒りさえ鎮まれば、また元のように人間に豊穣をもたらします。日本の神は『破壊』もしますが、一方で、『創造』する力も持つのです。破壊と創造は反対のようですが、創造したものはいつか破壊され、また破壊された後には新たなものが創造されることになります」
神々に助けられる人の条件とは何か。著者は述べます。
「悪いことをしていない人、罰当たりなことをしていない人というだけではなく、『自然に近い生活をしている人』というカテゴリーがあるのではないでしょうか。日本では、森羅万象すべてに神々が宿ると考えられています。その神々に穢れがついてしまうと力がなくなり、穢れが溜まると怒り出して『荒ぶる神』に変化します。さらに穢れが固定化してしまうと、妖怪や物の怪に変化します。万物に神々が宿っていることを認識し、元来の役割の通りに、自然に扱えば秩序は保たれます。自然の定めに従うこと。日本人の場合、何か特別なことをしなくても、普通に生活していることが、自然に逆らわないという意味で、重要なのです」
第二段「生死を分けた不思議な出来事」では、「てんでんこ」について、著者は以下のように述べています。
「岩手県に『てんでんこ』という言葉があります。『津波の時はてんでんこ』というのだそうですが、これは、『津波が来たら、取るものもとりあえず、肉親にも構わずに、各自てんでんばらばらに1人で高台へと逃げろ』『自分の命は自分で守れ』という意味だと、1990年に開催された第1回「全国沿岸市町村津波サミット」で紹介された防災標語です。その際の説明によると、逆に『自分自身は助かって、他人を助けられなかったとしても、それを非難しない』という不文律であるとされますが、それは利己主義ではなく、互いを探して共倒れするのを防ぐという意味だと理解されています」
実際に東日本大震災で、この「てんでんこ」の教えを守った、岩手県釜石市内の小中学校では、全児童・生徒の約3000人が即座に避難しました。その結果、生存率99・8%という素晴らしい成果を挙げています。
「てんでんこ」の内容は悲しい話ではありますが、なんとか生存者を残して、家や地域の再生を図るべく生み出された民俗社会の「知恵」だと言えるでしょう。
第二幕「『助けて』という願望」の前段「海の中の出来事」では、「荒ぶる神々と津波」として、著者は「津波は、見えてから逃げ始めたのでは間に合いません。非常に速いスピードで押し寄せますから、地震が起きたらすぐ、高台に避難しなければならないのです」と述べています。
では、昔の人は津波のことをどのように考えていたのか。著者は述べます。
「もちろん、その固有名詞は昔からあったわけですから、海の異常事態として明確に認識されていました。しかし、その原因は『荒ぶる神』のしわざだと考えていたようです。海というものは、普段は人に恵みを与えてくれるありがたい場所ですが、他方で、神々を怒らせてしまうと、すぐに死につながる場所でもあります」
著者は「津波に関する民話」として、古来、津波は「海坊主」と形容されることがあったことを紹介し、さらに以下のように述べます。
「この海坊主が『津波』と結びつくのは、その出現が、嵐や天候不順、時化などとは関係なく、前触れもないまま突然現れるということと、黒い坊主頭で非常に大きいということから、『津波の化身』ではないかと考えられるからです。嵐や天候不順を伴うことなく、海上にいると突然、黒い大きな塊が襲ってくるというのは、今回の東日本大震災の津波の形態に似ていることにお気づきの方もいらっしゃるでしょう。東日本大震災の津波は、引き潮もなく、突然襲ってきたのでした。昔の人なら、妖怪が意思を持って動いているかのように、荒れ狂う黒い波が陸地を襲い、一面を海に変えていってしまうのを見て、荒ぶる神か妖怪の仕業でなければできないことと考えたでしょう」
第一段「『私に気づいて』という訴え」では、「自分はここにいます」として、著者は以下のように述べています。
「あまり良い言葉ではありませんが『いじめ』のなかに『しかと』という行為があります。語源を調べてみると、花札の10月の札が紅葉(楓)なのですが、その鹿の絵柄が完全に横を向いていて、こちらを無視しているように見えることからきているといわれます。元々は警察用語の隠語だったようで、1956年に出された『警察隠語類集』の中には、『しかとう とぼける。花札のモミヂの鹿は10であり、その鹿が横を向いているところから』と書いてあります。その『しかとう』が、『シカト』となり、一般でも使われるようになったということです。完全に無視されると『いじめ』になるくらい、無視されるのは悲しいことです。それは、人が死んだあとでも同じでしょう」
著者は、「バスの中から」という項で、震災後にバスの残骸から男の子の遺体が発見されたエピソードを紹介します。発見したのは神主さんだったそうですが、著者は以下のように述べています。
「埋葬されないご遺体や、行方不明者の近くでは幽霊が出るとされます。しかしたとえば、戦場で多くの死者が野ざらしになっていても、幽霊が出るとは限りません。先の大戦でも、激戦地での幽霊の目撃談はあとからたくさん出てきましたが、戦闘のさなかに怪談として語られることが少なかったのは、それだけ人の心に余裕がなかったからです。霊を慰め、供養するには、生きている側の人々が平常心に戻り、心に余裕がないといけない。こうした教訓がよく理解できる話ではないでしょうか。実際、この話を聞かせてくれたのは、被災した現地の人ではなく、仙台に住むボランティアの人でした。霊の声を聞きとることができたのは神主さんだったのも同じことです」
第二段「『この子だけでも』という切なる願い」では、「母と子の絆」として、著者は「絆」という言葉について以下のように述べます。
「『絆』とはもともと、犬・馬・鷹などの家畜を、通りがかりの立木につないでおくための綱のことを言います。そのことから呪縛、束縛の意味に使われていました。しかし、徐々にその意味が変化し、震災後のような、人と人との結びつき、支え合いや助け合いを指すようになったのです。もともとは『糸』が『半分』になっているのですから、大きなものを2つに分けるという意味で、糸がそれをつないでいる構造のために、『つなぐ』という意味に転じていったのではないかといわれます。もちろん諸説ありますが、近年の『絆』という字に込められた意味としては、ちょうどいい解釈です。
この『絆』、『日本人の人と人との結びつき、支え合いや助け合い』が最も試されたのが、東日本大震災ではなかったでしょうか。『死してなお子供や親、愛する人』を『思う気持ち』を感じさせるエピソードが、たくさん生まれました」
また、肉体のない霊魂について、著者は「身体がないんです」として以下のように述べています。
「人間は、強い思いを残した時に加えて、『自分が死んだということがわからないうちに死んでしまった場合』に、幽霊になることがあるといいます。本人は生きているつもりが、肉体がないということになるのです。この話の親子も『自分たちは死んでいない』と思っていたに違いありません。車に乗っていて、何が何だかわからないうちに津波に巻き込まれてしまったのではないでしょうか。津波も、建物の上のほうにいて、波が徐々に近づいてくるのを見ていれば、自分が巻き込まれると認識できますが、たとえば車に乗っていて、車体の後方から一気に襲われたら、津波であるかどうかも認識できないまま、一瞬のうちに亡くなってしまうこともあるかもしれません」
さらに、著者は「逃げる音」として、津波が押し寄せてきた時間になると、逃げる足音が聞こえるという怪談を紹介します。著者は、亡くなった人が、自分が亡くなった時の情景をそのまま、その場に再現することがあるとして、以下のように述べます。
「怪談で、飛び降り自殺をした人の姿が、何度も見えるというものがあります。よく聞いてみると、窓の外を飛び降りている姿が、途中まで見えるのですが、地面に着くまでに見えなくなるというのです。それは、飛び降りている途中で本人が意識を失ったために、そこで記憶が途切れているからだと解釈する人がいます。つまり、『亡くなった方の記憶』を客観的に見せられたり、あるいはその時の音を聞かされたりしているというのが、このパターンの怪談の特徴です。
第三幕「あの日に帰りたい」の第一段「帰るべき場所」では、「人間の帰巣・帰省本能と『神隠し』」として、著者は以下のように述べています。
「昔の田舎町には『神隠し』という現象がありました。突然、人がいなくなってしまうものです。電気のない時代ですから、すぐに暗くなってしまいますし、道路も整備されていないので、迷ったり事故に遭ったりしたことも多かったでしょう。まだ人身売買の習慣が残り、人さらいが来るような状況も少なくないので、誘拐に近いこともあったのではないかと思います。寒村では、食糧不足に苦しむあまり、『口減らし』といって、飢餓に陥らないよう子供を殺してしまう習慣があったところも存在します。そうした時、あからさまに『口減らしで殺した』とはいえないので『神隠しにあった』と、神の仕業にしてしまうことが、往々にしてあったのではないでしょうか」
また、「遠野物語『寒戸の婆様』からの考察」として、著者は「神隠し」について以下のように述べます。
「『神隠し』とは、人間がある日、忽然と消えうせる現象で、それが単なる人さらいや事故と区別されたのは、「神域」で起きるからだとされます。昔の日本の地域の中には必ず、神域とされる場所がありました。街の中にも『祠』や『注連縄をした古木』などがあったように、山深い村や神社の境内でなくても、街中に神域がいくつもあったのです。そうした『神域』は、地域の憩いの場でもありましたし、子供たちの遊び場でもあったのです。そこで神様や、あるいは神の使いとされる者に魅入られて、神の領域から出ることができなくなってしまう。そしてそのまま、人間の領域からは、見ることも会うことも話すこともできなくなってしまう。これが神隠しです」
さらに著者は、「神隠し」について以下のように述べるのでした。
「『神隠し』では、神に魅入られて連れて行かれると考えられていますが、その多くでは、神様そのものではなく、『神の使い』としての『天狗』や『妖怪』が、神隠しを実行するとされています。天狗とは神の使いで山の神の精霊であり、剣術の達人で武にもすぐれ、また正義漢であるとされています。そのため、剣豪などが天狗に弟子入りしたという伝説が残るわけです。天狗の世界に入り込んで、修行を積んで戻ってくれば、剣術の士としては、『箔がつく』ことになります。さらに東北には、『雨女』という妖怪がいて、神隠しを実行する主体であるとされます」
著者は、「先祖が帰ってくる『お盆』の起源」として、日本の死生観について以下のように述べています。
「日本の死生観では、『死者の世界』も『これから生まれてくる魂の世界』も、同じ神の領域で、古事記では『黄泉の国』と表現されています。古事記で、伊邪那岐命が黄泉の国まで追いかけてきた時、伊邪那美命は『あなたは、すぐにわたしを助けに来てくださいませんでしたので、黄泉の国の食べ物を食べてしまいました』といって、一緒に帰ることはできないと拒絶します。ここには、その土地の物を食べるとその国の住人となる、という日本人の思想があらわれています。今でも『水に慣れる』『水が合う』などという言い方をしますから、そういう感覚をわかっていただけるのではないでしょうか。伊邪那美命は、黄泉の国の食物を食べてしまったので『黄泉の国の住人になってしまった』、そのために地上の世界には帰れない、と言っているわけです」
日本最大の先祖供養儀礼である「お盆」についても、著者は述べています。
「お盆は『盂蘭盆会』という仏教儀式を日本流に習慣化したもので、仏教に多大な影響を与えた古代インドのサンスクリット語の『ウランバナ』という儀式が、現代まで残ったものです。サンスクリット語の『ウランバナ』は、現在の『ウド、ランブ』(ud-lamb)、つまり倒懸(さかさにかかる)という意味であるとか、または古代ペルシャ語の『ウルヴァン』(urvan)、つまり『霊魂』という意味が合わさってできた言葉が語源ではないかといわれます。古代ペルシャでは、精霊は人間の中にも宿っていて、人間が死ぬと魂の最も神聖な部分、これは古代ペルシャ語、そしてゾロアスター教で『フラワシ』という下級霊とされているのですが、そのフラワシになった祖先霊を迎え入れる儀式があり、それを『ウラバンナ』と呼んでいたようです」
第二段「止まった時間」では、「死んだことに気づかない」として、著者は以下のように述べています。
「怪異譚の中で死者が幽霊になる状況には、2つの代表的なパターンがあります。1つは、『人を恨む』『思いを残す』ということです。現世に執着が残っているため、自分が死んだことに気づいても、この世にとどまってしまう。人にとり憑いたり、祟りをなすような幽霊は、このパターンにあてはまります。もう1つは『死んだことに気づかない』または『死んだことに納得がいかない』場合に、自分は生きているつもりで、同じように姿を現してしまうというパターンです」
また、東日本大震災といえば被災地でのタクシー怪談が有名ですが、「タクシーの幽霊」として、著者は以下のように述べます。
「タクシーと幽霊の話は、その人が亡くなった場所から、出身地やゆかりのある土地へ、幽霊が『帰りたい』『行きたい』場所へ移動する交通手段として、タクシーを使うという特徴があります。幽霊ですから、幽体離脱のように飛んで行けばいいのでしょうが、本人はなぜか、生きている人と同じ手段で移動したいわけです。自分が死んだことを認めたくないのか、もっと違う動機があるのかはわかりません」
怪談の定番である「幽霊トンネル」についても、著者は述べます。
「『幽霊トンネル』について考えてみると、『異界』としてのトンネルの手前で乗るという特徴があります。バスや電車などの他の交通機関はないのでしょうか。はたして幽霊は電車やバスに乗るのか、疑問が湧いてきます。タクシーの場合、個室で、しかも密室ですから、走っている間にいなくなれば、すぐ気づきます。消えたと気づかれることが大事なので、タクシーが選ばれるのかもしれません。しかしバスや電車に乗って、気がつかれないうちに消えてしまっている幽霊もいるのかもしれません。もっと多くの幽霊が一般の人に混ざって一般の交通機関に乗って移動しているかもしれないと思うと、なんとなく痛快な感じがします」
そして、著者は「要は『自分が最後にいた場所』から『自分の帰るべき場所』まで、生きている時と同じように、公共交通機関を使って帰りたい、ということになります」と述べています。
著者は複数の霊たちが居酒屋で酒を飲み、タクシーに乗った話を紹介し、最後にその中の1人が「私たちは生きているのでしょうか」と尋ねた話を紹介します。そして、以下のように述べます。
「タクシーに特有の現象というよりも、霊魂が『帰るべき場所に帰りたい』と願った時、生きている時と同じように交通機関を使おうとしてしまうために、運転手たちと邂逅してしまうのかもしれません。しかし震災のような、あまりに想定外の出来事が起こると、自分は本当に死んでしまったのかわからず、疑問を抱きながら『帰りたい』と願いつつ、この世にとどまっているケースも少なくないのでしょう。そんな『人たち』は、生前と同じように行動し、さまざまな人に話しかけたり、食べたり飲んだりもする。こちらの世界の人間にはそれと判別できなくても、彼らは生きている時と同じ感覚なのです。
『タクシー』という『移動する密室』は、そうした状況で生者に問いかけたり、『自分自身を確認する場所』として、選ばれることがあるのかもしれません」
著者は、いわゆる地縛霊についての報告も紹介し、「時間の流れ」に注目して以下のように述べます。
「その魂にとって『時間の流れ』はどうなっているのでしょうか。自分が死んでしまったかどうかわからない、この世に心を残す霊にとって、時間はその場その時で『止まってしまった』ように感じるでしょう。時間が止まるということは、その場から移動できず、新しいことも起きないということです。『地縛霊』ともいわれますが、まさに『時間が止まっているから、その土地に縛り付けられて移動できないでいる』のではないでしょうか。『自分は死んだんだ』と自ら納得し、次のステージに行っていただければよいのですが、なかなか難しい事情もあるのでしょう」
さらに、著者は夏の風物詩である花火大会について述べます。
「日本で花火大会が夏に行われる理由をさかのぼると、お線香と同じで、死者が迷わずに天に昇れるように打ち上げるということが、庶民の間で民間信仰的に考えられていたようです。現代では花火を見る理由を『きれいだから』などと考えている人も多いかもしれませんが、隅田川の花火が毎年7月に行われるのも、お盆の行事の1つだからです」
第三段「生きている人を引き込む霊」では、人間が「怖い」と感じるのは「不安定」な状況であると説明されます。とりわけ、あの世とこの世の境界線上が最も不安定とされるわけですが、著者は「震災で『境界』が崩れた」として、以下のように述べます。
「不安定な境界は他にもあります。たとえば『墓場』は、この世とあの世をつなぐ場所ですし、『河原』も、向こう岸とこちらとを分ける境界線です。昔の日本人は、妊娠中の女性を境界の存在だと考えていました。今では男女差別になりますが、女性は、『子供を産む』ことができ、新たな命をつくりだすことができるからです」
続けて、著者は以下のように述べています。
「現在のように医学が発展していない時代ですから、生物学的に卵子が受精して、というようなことはわかりません。そこで、昔の人は女性の身体の中に、新たな生命を産む『黄泉の国』につながる道があると考えたのです。ですから女性のほうが霊力は強いとされ、勘も鋭いとされていました。また、老人も、境界の存在とされ、あの世と交信できるとされていました」
さらに、著者は以下のように述べるのでした。
「東日本大震災は、そうした不安定な場所や、不安定な精神状態をたくさん作りだした災害という一面を持っています。今までは『河原』や『墓場』としてはっきり区分されていた不安定な場所が、津波に襲われたことによって、『街のあらゆる場所』に拡散してしまいました。多くの人が犠牲になったことで、『霊』も数多く発生してしまいます」
著者は「戦闘ストレス」反応にも言及し、以下のように述べています。
「『戦闘ストレス反応』という心の病があります。戦争後遺症とか戦闘疲労とも言われ、あまりにも過酷な状況にさらされて心的外傷を受けると、その状況の記憶とその後の平穏な生活との間で心のバランスが崩れ、精神を病んでしまい、ひどい場合は自殺に至るケースもあります。『戦闘』『戦時』と名前がついているので、日本ではあまり関係がないように思われがちですが、実際に東日本大震災のような巨大災害の現場に立ち、『戦争と同じような破壊状態』で活躍した、自衛官や警察官、消防団員の中には、この心的外傷に悩まされている人がいると聞きます。被災地の復興に加えて、自衛官や警察官などの心のケアも大切なのではないでしょうか」
第四幕「見守っています」の第一段「死者を祀る」では、著者は「人が祀られる日本の神の系譜」として、以下のように述べています。
「『怨霊』でなくても、非業の死を遂げた人々を祀る風習もあります。そのもっとも象徴的な例が、靖国神社です。日本の場合、『無名戦士の墓』のように、墓として慰霊するだけでなく、靖国神社にお祀りすることによって、『戦争という死から守る』こと、すなわち『平和を守る神』として、靖国神社に参拝する習慣があるのです。世界にはあまり理解されていないかもしれませんが、靖国神社で戦勝を祈願することは、基本的に日本の『死者を神様として祀る』という考え方とは違うのかもしれません。坂本龍馬なども靖国神社に祀られていることを考えれば、日本という国の平和的持続のために参拝する、という解釈が可能です」
また、「『オシラサマ』伝説が残したもの」として、著者は「村八分」と「先祖供養」を結びつけたユニークな見方を以下のように示しています。
「日本人はかつて、共同体の中の最も厳しい制裁を『村八分』だとしました。(火事と葬式以外は)『無視されること』こそ、私たちにとって、一番つらく、こたえる仕打ちなのです。日本人は、そうやって制裁を与えることが、やがて許すことにつながるのを、自然と身に付けていったのではないでしょうか。
『先祖を粗末にすると祟られる』という考え方も、『霊の存在を無視する』のが、死者にとって最もつらく、悲しいことだと考えていたわけです。逆に、忘れることなく念入りに弔っていれば、自分たちに恩恵を与えるような存在に変わってくれる、と考えていたのです」
第二段「復興が気になる幽霊たち」の「がれき整理の手伝いをする幽霊」では、著者は以下のように述べています。
「幽霊が自分の大事なものを探しているという怪異譚は少なくありません。最も怖いパターンは、バラバラになってしまった自分の身体の一部を探している幽霊が出てくるものです。その場合、失った身体の一部を取り戻したいと探しているだけでなく、やがて生きている人の身体がほしい、よこせと言い出して、恐ろしい話に発展することがあります。たとえば右手がいつまでも見つからない霊が『貴方の右手をちょうだい』などと言ってくるパターンです。またほかにも、事故の廃墟などから、何か物を拾って持ってきてしまうと、それを幽霊が取りに来るというパターンもあります。たとえば指輪などを持ってきてしまうと、いきなり見ず知らずの人から電話がかかってきて、『返して』と言われてしまう、といった話です」
「おわりに」では、著者は「心の復興」という言葉に言及して述べます。
「がれきの山に囲まれ、避難所というプライバシーのない場所で大変な思いをしたこと。住み慣れた家や今までの隣近所のつきあいから切り離されて、プレハブの仮設住宅で慣れない生活をしていること。生と死の境界が混乱する被災地で、亡くなっていった人たちへの思いはどのようなものだったでしょうか。震災後の東北では『ロコミ』で、幽霊にまつわる不思議な話が語られていながら、同時期のマスコミが、被災地への配慮やオカルト批判を恐れ『自粛』の名のもとに、触れようとしなかったことは、日本人の精神世界、『スピリチュアル』な『霊性』という側面からみた心の復興に、問題を投げかけたのではないか。そのことを少しでも、感じていただけたらと思います」
そして、「あとがき」の最後に、著者は以下のように述べるのでした。
「犠牲になられた方々は、悲しいことですが、帰ってきません。それでも、生きている側はその現実を乗り越えなければならないのです。本書でとりあげた不思議な現象の登場人物や、今、被災地で頑張っている人たちの願いは、復興を果たし、この土地で暮らす人々や、これから生まれてくる次の世代の幸せの土台を築くことでしょう。これ以上、政治の迷走で復興が大幅に遅れるようなら、口コミで語られた不思議な現象の記憶は昇華されないまま、新たな怪異譚を生む土壌になってしまうかもしれません。『前よりも良くなった』と感じられるような町づくりを進めるのが、一番の解決策です」