- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.1547 論語・儒教 『あわいの時代の「論語」』 安田登著(春秋社)
2018.04.19
『あわいの時代の「論語」』安田登著(春秋社)を読みました。
「ヒューマン2.0」というサブタイトルがついています。
著者は能楽師ですが、『論語』についての造詣が深いことで知られ、この読書館でも紹介した『身体感覚で「論語」を読み直す』などの著書があります。
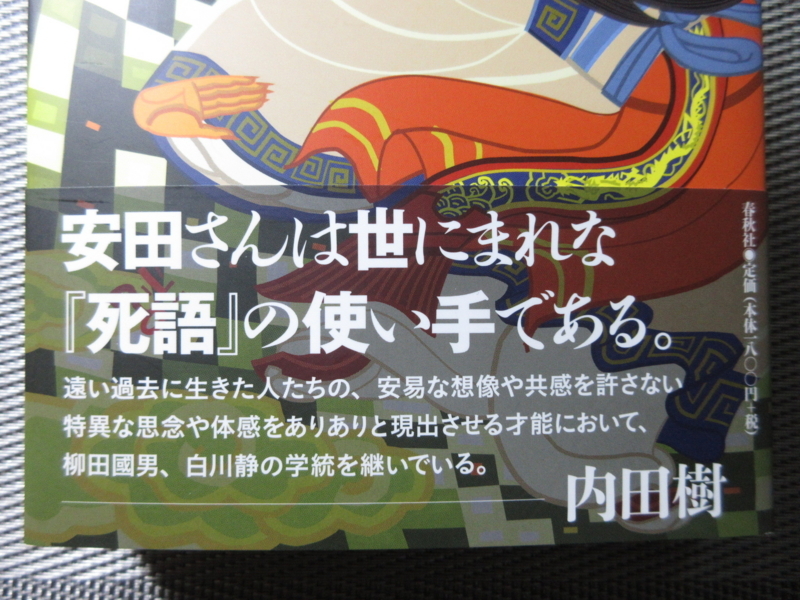 本書の帯
本書の帯
本書のカバーには京劇のようなPOPな孔子のイラストが使われ、帯には「安田さんは世にもまれな『死語』の使い手である。遠い過去に生きた人たちの、安易な想像や共感を許さない特異な思念や体感をありありと現出させる才能において、柳田國男、白川静の学統を継いでいる。―内田樹」とあります。
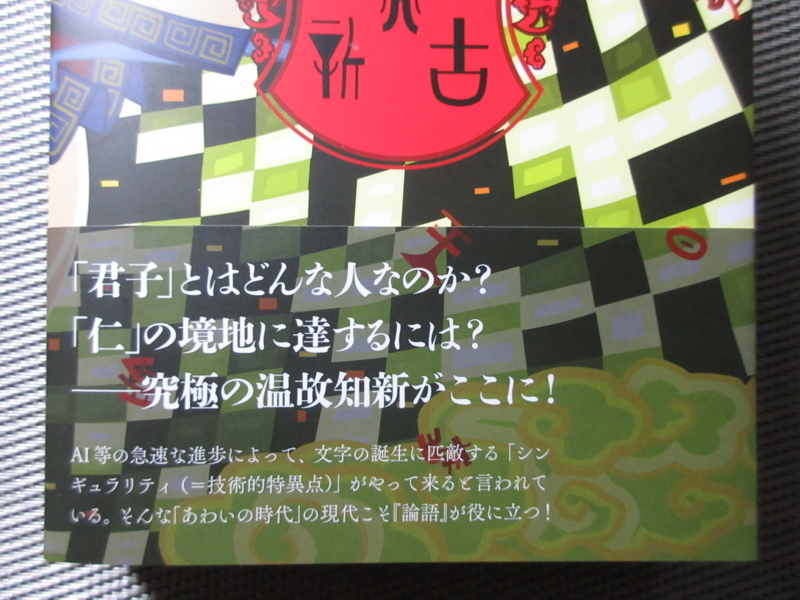 本書の帯の裏
本書の帯の裏
また帯の裏には、 「『君子』とはどんな人なのか? 『仁』の境地に達するには?―究極の温故知新がここに!」「AI等の急速な進歩によって、文字の誕生に匹敵する『シンギュラリティ(=技術的特異点)』がやって来ると言われている。そんな『あわいの時代』の現代こそ『論語』が役に立つ!」と書かれています。
本書の「目次」は、以下のような構成になっています。
「はじめに」
第1章 あわいの時代―シンギュラリティ
第2章 心―腹部に宿った「自由意志」
第3章 君子―「心」を使いこなす
第4章 礼と六芸―身体拡張装置としての「礼」
第5章 知―脳の外在化によって生まれた精神活動
第6章 仁―ヒューマン2.0
付録 『大盂鼎』を読む―論理の誕生
「おわりに」
「参考文献」
「はじめに」を著者は以下のように書きだしています。
「いまからおよそ3000年前(紀元前1300年頃)。古代の中国では文字が誕生しました。文字は『時間』を生み、『論理』を生み、そして『心』(という文字)も生みました。生まれたばかりの『心』の意味はいたってシンプル。すなわち、未来を変え、過去から学ぶ力、それが『心』でした」
また、著者は以下のようにも述べています。
「未来を変える力を、心の『作用』だとすれば、『不安』は心の『副作用』です。その副作用に対する処方箋を私たちに与えてくれたのがお釈迦様であり、イエスであり、そして孔子です。みな、2000年以上も前の方たちです。それなのに今に至るまで、このお三方を凌駕する人物が現れないのは、『心の時代』がまだ続いているからです。
しかし、近年の急激な時代の変化を肌で感じていると『ひょっとしたら、文字や心の誕生前夜もこうだったのではないか』と思います。文字が生まれたばかりの頃の資料を読んでいると、いま私たちが直面している不安や期待に似たものを感じるのです」
第1章「あわいの時代」では、『論語』全体を孔子の時代の文字に書き直してみると、孔子の時代にはなかった文字群があることを、著者は指摘します。それは「感」を含めた「心」を部首とする文字群でした。さらに漢字を追っていくと、「心」という文字自体が孔子の生まれた500年前(紀元前1000年頃)に誕生したことがわかりました。
自由意志としての「心」とほぼ同時に「時間」が生まれ、「論理」が生まれ、そして「(政治)組織」も生まれました。
このような「心」について、著者は紀元前1000年に発明された現代人類のOS(御ペレーティング・システム)であるとし、以下のように述べます。
「『文字』の発明と、その後300年後にやってきたOSとしての『心』の発現は、人間社会を劇的に変えた『シンギュラリティ』だといえます。このシンギュラリティ(以下、文字シンギュラリティ)によって、人々の思考の量や質は爆発的に増加し、人間社会は質的な飛躍を遂げることになったのです。文字シンギュラリティ以降、時代は『心の時代』に突入しました。『心』を中心にいろいろなことが回るようになったのです。これは中国だけに限ることではありません。人類最初の都市文明を生んだ古代メソポタミアでも、エジプトでも同じです」
孔子の儒教をはじめ、釈迦の仏教、イエスのキリスト教は、「心の時代」に生まれました。そのあたりは拙著『世界をつくった八大聖人』(PHP新書)に詳しく書かれています。各宗教は、その創始者だけでなく、それ以降も聖人や偉人を排出しました。たとえば仏教なら、空海。キリスト教なら、聖フランシスコやマザー・テレサ。儒教だって、幕末の吉田松陰などがいます。しかし、著者は以下のように述べるのです。
「不思議なことに空海は釈迦ほどではないし、聖フランシスコやマザー・テレサだってイエスには及ばない。吉田松陰だって孔子の方がずっとすごい。しかも、釈迦、孔子、イエスの三聖人はみんな2000年以上も前の人たちです。釈迦や孔子は紀元前500年ほどの人、イエスはちょうど紀元ごろの人。こんなすごい人たちがみんな今から2000年以上も前に生まれて、それ以降、これに代わる人がいない」
「これって変ですよね」と読者に問いかけてから、著者は以下のように述べます。
「科学も文明も、当時に比べれば現代の方が格段に発達しています。人類全体の知的水準だって上がっているはずです。それなのになぜ今まで彼ら以上の人が誕生しなかったのか。そして、この3人は、なぜ『あの時期』に生まれたのか。それは、この3人がみな『心の時代』になって数百年後に生まれた人たちで、そして『心の時代』のパイオニアだからです。『心』の副作用に対して、その共同体で初めての、そして強力な処方を施した人たちです」
本書の中でも、特に第4章「礼と六芸」が読み応えがありました。
古代中国で士以上の者が修めるべき六つの教科が六芸(礼、楽、射、御、書、数)です。これらの教科はいずれも「超越的なもの」と関わる技法であると言えますが、その最初に置かれているのが「礼」です。姿のない神霊という、通常ではコミュニケーションができない相手との交流をするという「礼」の機能は六芸すべてに通底するとして、著者は以下のように述べます。
「第一層の礼を社会的に行うのが通過儀礼です。五経の『礼』のひとつに『儀礼』という本があります。その中には、成人式(士冠礼)や結婚式(士昏礼)などの通過儀礼の式次第が載っています。私たちにもっとも身近な通過儀礼は卒業式でしょう。講堂の檀の下にいるときには『在校生』なのに、壇の上に登って卒業証書をもらい、反対側の階段から壇を下りると『卒業生』に変わり、学校からの縛りを一切受けることがなくなります。式の前とあとでは人格が変容する、それが通過儀礼です」
さらに通過儀礼について、著者は次のように述べています。
「人は、卒業や成人のようなさまざまな『通過』を人生の中で経験します。それがうまく機能しないと、それは『過ち』になります。『過ち』とは通過の『過』であり、過剰の『過』です。成人になっても大人になりきれなかったり、卒業をしても学校にいつまでも未練を持ち続けたりと、『通過』をうまくクリアできすに、前の時代の心身を持ち越してしまうことを孔子は『過ち』と呼びました。これは時間的な『過ち』もありますが、空間的な『過ち』もあります。風習の違う土地からやって来た人が、前の土地のままで生きようとすると、やはり『過ち』として現れます」
そして、それらは「過剰」という形で現れるとして、著者は以下のように述べます。
「大人になっても何かイヤなことがあると子どものような反応をしてしまったり、卒業をしてもしばしば学校に足を運んで『ウザい卒業生』と思われたりしてしまいます。それを避けるために通過儀礼があるのです。現代は、通過儀礼の力が弱まっているので、それがうまく機能しないことが多いようです。そうなったら孔子は『改めよ』といいます」
北九州のド派手成人式で馬鹿騒ぎをする新成人たちも、あのままでは大人に変容できないのではないかと心配してしまいます。ぜひ、「過ち」を「改め」てほしいものです。
「『文』と『質』」として、著者は以下のように述べています。
「孔子の学団で『礼』が、具体的にどのように学ばれていたかは想像するしかありません。貝塚茂樹氏は、礼のふたつの型式は『文』と『質』であるといいます。礼の学びは、この『儀礼(文)』と『実践(質)』でなされていたのではないでしょうか。装飾と訳される『文』は、礼の学びでいえば儀礼的身体の修養と儀礼的教養の獲得であり、素朴と訳される『質』は日常生活における徳目の実践です。孔子は初学者たちに『家においてはまず”孝”を、そして外に出たら”悌(弟)”を、そして言葉数を少なくして(謹)、言ったことは必ず実現するようにし(信)、多くの人に思いやりの気落ち(愛)を持ち、そして人(仁)に親しむ』ようにと勧め、そして、そのような行動を尽くして、さらに余力があったら『文』を学ぶといいだろうと言いました」
それでは、「孝」とは何か。著者によれば、「孝」はまさに孔子の儒教文化が完成させ、そして日本も含めた東アジアに大きく影響を与えた、世界的に見れば非常に特殊な徳目です。著者は、「親が子を養ったり、親が子のことを想ったりするのは本能であり自然なことです。しかし、子が親を思うのは本能ではありません。しかし、だからこそ子が親を養い、自分が親から思われた以上に強く親のことを思う、それが尊いのです。本能を超える力、それが『孝』です」と述べています。
「孝」と「老」の字の上が同じであることからもわかるように、「孝」の対象は自分の親に限らず、すべての老人となります。その人の能力や性格などとは関係なく、年上であるというわけで、また親というだけで尊敬しなければなりません。それが人間社会のすごさなのです。
孝に続く実践は「悌(弟)」です。目上の人を敬うという徳ですが、「なめし皮」という文字の原義から見ると「悌(弟)」には「柔らかな徳」という意味もあることがわかります。著者は、「決して大きな声でもないし、論理的に筋が通っているというわけでもない、それなのに、その人に柔らかくお願いされるとイヤといえない、そんな人がいます。そういう人が『悌(弟)』の徳を備えた人です。北風と太陽の、太陽の人です」と述べています。
第6章「仁」では、「上帝サテライトとしての『天』」として、儀式の問題が取り上げられます。著者は、殷の紂王が「衣」の儀式によって上帝と一体化していたのではないかと推測し、さらに以下のように述べています。
「日本で天皇が即位後最初に行う一世一度の新嘗祭である『大嘗祭』でも、衣は重要な意味を持ちます。即位式が地上の儀式だとすれば、大嘗祭は霊的な即位式だということができるでしょう。このときに天皇が伏す神座に設けた衾(ふすま)は、天孫降臨の時、高皇産霊尊が瓊瓊杵尊を覆って降ろしたという真床覆衾(まことおうふすま)(『日本書紀』)とも関係があるともいわれます。また、この真床覆衾に包まるということは天津神の直系であることを象徴するものとされています」
平安朝期の大嘗祭の形態を伝える『儀式 践祚大嘗祭儀』(思文閣出版)によると、大嘗祭当日の戌の刻に、天皇は廻立殿で湯浴をします。そのときにまず「天の羽衣」を着て背中を流されたあと、その衣を湯殿に置いたまま出て、別の衣に着替えます。「天の羽衣」は能の『羽衣』や『竹取物語』にも登場する衣で、これを着ると過去を忘れ、違う人格に変容するといいます。すなわち、人間としての天皇から現人神としての天皇に変容するための衣なのです。
最後に、「いのる」についての説明が興味深かったです。
日本語で「いのる」というのは、本来「い+宣(の)る」、すなわち神の名を唱えることでした。ですから平安時代までは「神にいのる」という用法はなく、「神をいのる(神の名を唱える)」という使い方をしていました。孔子はずっと「神を祷る」行為をしていました。しかし、弟子の子路がしようとしていたのは「神に祷る」でした。それは「祷り」ではなく「願い」だったのです。
そして著者は、以下のように述べるのでした。
「神霊は敬するだけでいい。願いのような祈りは必要ないと孔子は思っていました。神霊は遠ざけるもので、近づく必要はない。すべての人は、自分の中に神(帝・天)を持っていて、そして、ひとりひとりが別々の『神の刻印(天命)』を身に刻んで生まれて来ている、それに気づいたからです。すなわち孔子が長い間やってきたという祷りは、神に対する願いではなく、自分の中の神にアプローチする方法としての祷りだったのです」

わたしは、本書を読んで唸りました。著者の『論語』の読み方は深いです。
わたしのブログ記事「論語とマネジメント」で紹介したように、昨年の4月、わたしは「齋藤アカデミー」で特別講義をしました。社会起業大学・九州校が主催する、これからのリーダーを育成する私塾で、受講生のほとんどがMBAの取得者です。そこでわたしは「論語とマネジメント」を担当したのですが、著者の安田登氏も出講されており、「哲学・思想・宗教」を担当されていました。
ニアミスというか出講日が違ったために、わたしたちが出会うことはありませんでしたが、わたしは著者に拙著『儀式論』(弘文堂)を献本すべく事務局に預けました。安田氏にはぜひ一度お会いさせていただいて、『論語』について語り合いたいです。