- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.1576 神話・儀礼 『世界神話学入門』 後藤明著(講談社現代新書)
2018.07.25
『世界神話学入門』後藤明著(講談社現代新書)を読みました。
著者は1954年生まれ。東京大学文学部卒業。同大学大学院人文科学研究科修士課程、ハワイ大学人類学学部大学院博士課程修了。南山大学人文学部教授・同大学人類学研究所所長。専攻は海洋人類学および物質文化や言語文化の人類学的研究です。
 本書の帯
本書の帯
本書の大きな帯にはギュスターヴ・モローによる「オルフェウスの首を運ぶトラキアの娘」の絵画が使われ、「神話は人類の記憶の宝庫」「最新の神話研究とDNA研究のコラボが解明! ホモ・サピエンスの壮大なドラマ」と書かれています。
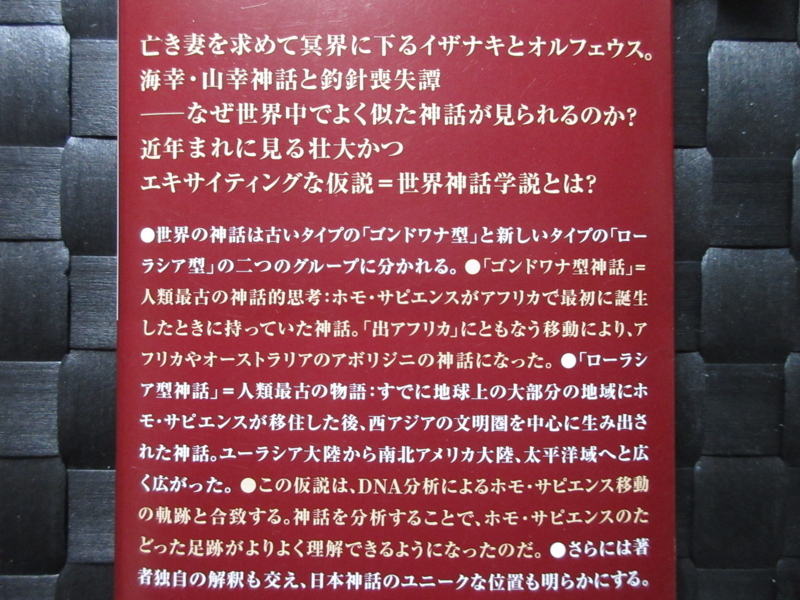 本書の帯の裏
本書の帯の裏
また帯の裏には、「亡き妻を求めて冥界に下るイザナキとオルフェウス。海幸・山幸神話と釣針喪失譚。―なぜ世界中でよく似た神話が見られるのか? 近年まれに見る壮大かつエキサイティングな仮説=世界神話学説とは?」と書かれています。
さらに、アマゾンの「内容紹介」には以下のように書かれています。
「日本神話では男神イザナギが、亡き女神イザナミを求めて冥界に下ります。一方ギリシア神話にも、オルフェウスが死んだ妻エウリュディケーを求めて冥界に下るという非常によく似たエピソードがあります。しかしこのパターンの神話は上記の二つに止まるものではなく、広く世界中に分布しています。では、なぜこのように、よく似た神話が世界中にあるのでしょうか?
2013年にハーヴァード大学のマイケル・ヴィツェルが、この謎を解くべく『世界神話の起源』という本を出版しました。この本によれば、世界の神話は古いタイプの『ゴンドワナ型』と新しいタイプの『ローラシア型』の二つのグループに大きく分かれるとされます。『ゴンドワナ型』はホモ・サピエンスがアフリカで最初に誕生したときに持っていた神話です。それが人類の『出アフリカ』にともなう初期の移動により、南インドからパプアニューギニア、オーストラリアに広がり、アフリカやオーストラリアのアボリジニの神話などになりました。一方『ローラシア型』は、すでに地球上の大部分の地域にホモ・サピエンスが移住した後に、西アジアの文明圏を中心として新たに生み出されたと考えられています。それがインド=ヨーロッパ語族やスキタイ系の騎馬民族の移動によってユーラシア大陸全域に、さらにはシベリアから新大陸への移動によって南北アメリカ大陸に、そしてオーストロネシア語族の移動によって太平洋域へと、広く広がっていきました。つまりこの説によれば、日本神話もギリシア神話もローラシア型に属する同じタイプの神話ということになります。両者が似ているのは、むしろ当然のことなのです。
近年、DNA分析や様々な考古学資料の解析によって、人類移動のシナリオが詳しく再現できるようになりました。するとその成果が上記の世界神話説にぴったりと合致することがわかってきました。すなわち神話を分析することで、人類のたどった足跡が再現できるようになったのです。本書は、近年まれに見る壮大かつエキサイティングな仮説であるこの世界神話学説をベースにして、著者独自の解釈も交えながら、ホモ・サピエンスがたどってきた長い歴史をたどるものです」
本書の「目次」は、以下のような構成になっています。
「はじめに―なぜ世界中に似たような神話があるのか」
第一章 遺伝子と神話
第二章 旧石器時代の文化
第三章 人類最古の神話的思考―ゴンドワナ型神話群の特徴
第四章 人類最古の物語―ローラシア型神話群
第五章 世界神話学の中の日本神話
第六章 日本列島最古の神話
「参考文献」
「おわりに」
「はじめに―なぜ世界中に似たような神話があるのか」の冒頭で、著者は「『古事記』とオルフェウス神話」として、以下のように書き出しています。
「世界の遠く離れたさまざまな場所によく似た筋立ての神話があることは、読者もお聞きになったことがあるだろう。
たとえば『古事記』における最初の男女、イザナキ・イザナミの話。この最初の男女神が天界から下界を眺め、何もない海をアマノヌホコという矛でかき混ぜると、滴がしたたり落ちてオノゴロ島になる。このかき混ぜる道具はじつは銛、つまり漁具であり、ポリネシアに広がる島釣り神話と同列ではないかという議論が早くからなされてきた。すなわちハワイやニュージーランドのマオリ族の間に伝わるマウイ神の島釣り神話との親近性である」
では、どうして世界の非常に離れた場所、あるいは世界中の広範な場所にこのように類似した神話モチーフが存在しているのでしょうか。著者は、以下のように、その理由を2つ述べています。
「1つには、人類は文化や環境が異なっていても似たような思考を持つことが考えられるだろう。たとえば太陽は全ての生命の成育に不可欠なものである。そのために太陽を神格化するような思考である。ただし太陽や月を神格化する思考は広く見られるにしても、どちらを男あるいは女とするかには一般性はない。もう1つの理由として、歴史的な要因、すなわち人類の移動や文化の伝播に起因する場合も考えられるだろう。これまでにも世界中の神話の類似点から、さまざまな文化の伝播や系統論が唱えられてきた。しかし近年、世界の神話の系統は大きく2つの流れに分けられるのではないかという学説が唱えられるようになった。それがこれから本書で見てゆく世界神話学説である」
「世界神話学説とは?」として、本書では神話の世界的な広がり、とくにアフリカとアジアやオセアニア、あるいはアメリカ大陸という予想外の地域間に見られる類似について、1つの仮説を提唱することを目的としていることが明かされます。著者は以下のように述べます。
「この仮説は20年ほど前に提唱されたが、そのまとまった書物がハーバード大学のマイケル・ヴィツェルによって近年公刊された『世界神話の起源』である。ヴィツェルは古代インドの神話や宗教を専門とする研究者である。日本人女性を妻とすることもあって日本をはじめ世界の神話に精通しているが、那智の火祭りを見た時、自らの専門であるインドの火の祭りとの類似に気がつき、この学説を構想するに至ったという」
一方、ロシアの学者ユーリ・ベリョーツキンもシベリアと北米を中心に神話モチーフの共通性を探ってきました。著者は述べます。
「シベリアと北米神話の共通性はクロード・レヴィ=ストロースやフランツ・ボアズといった人類学の巨人たちによってすでに指摘されていた。しかしベリョーツキンはパソコンを駆使して神話モチーフの分布を明示化し、さらに中南米、ユーラシアからアフリカ、そしてオセアニアにまで視野を広げ、比較神話学に大きく貢献した。ベリョーツキンはロシア人だが、自身の学説を英語でワールド・ミソロジー(world mythology)と呼んでいる。ヴィツェルの著作のタイトルも『世界神話の起源』なので、本書ではこの学説を『世界神話学』と呼ぶことにしよう」
また、著者はヴィツェルが近年唱えている世界神話学説を紹介します。それは、古層ゴンドワナ型神話と新層ローラシア型神話と、世界の神話が大きく2つのグループに分けられるという仮説です。そしてこの神話学説が、遺伝学、言語学あるいは考古学による人類進化と移動に関する近年の成果と大局的に一致するというのがヴィツェルの主な主張であるとして、著者は以下のように述べます。
「ゴンドワナ(Gondwama)は、インド中央東部にある、サンスクリット語起源の名前である。それは現在のアフリカ、南アメリカ、南極、オーストラリアなどの大陸および、インド亜大陸、アラビア半島、マダガスカル島を含んだ、大きな大陸であった。
一方ローラシア(Laurasia)大陸は、アメリカ大陸を意味するローレンシア(セントローレンス川に由来する語)大陸とユーラシア大陸からの造語である。南にあったゴンドワナ大陸に対し、北半球にあったローラシア大陸は、後にユーラシア大陸とローレンシア、つまり北アメリカ大陸に分離したと考えられている」
この語源は大陸移動説に由来するとして、著者は述べています。
「大陸移動説を唱えたアルフレート・ヴェーゲナーは、現在の諸大陸は分裂する前に1つであったという仮説を考え、この大陸をギリシャ語で『すべての陸地』を意味する『パンゲア(Pangaea)大陸』と呼んだ。この超大陸パンゲアが分裂し、ゴンドワナ大陸とローラシア大陸が生成されたわけである。
ゴンドワナ神話群はアフリカで誕生した現生人類のホモ・サピエンスが持っていた神話群で、初期の移動、すなわち『出アフリカ(アウト・オブ・アフリカ)』によって南インドそしてオーストラリアへと渡った集団が保持する古層の神話群と考えられる。具体的にはサハラ砂漠以南のアフリカ中南部の神話、インドのアーリア系以前の神話、東南アジアのネグリト系の神話、そしてパプアやアボリジニの神話群である」
一方、ローラシア型神話群にはエジプトやメソポタミア、ギリシャやインドのアーリア系神話、中国や日本神話の大半が含まれるとして、著者は「日本神話が周辺の中国や朝鮮半島の神話と類縁性があるのは当然としても、ユーラシア大陸の西端のゲルマンや北欧神話との類縁性、あるいはインド、またポリネシアなどの神話との関係がこれまでにもしばしば議論されてきた。だが世界神話学説によれば、これらはすべてローラシア型神話群に含まれるのだから、似ているのはむしろ当然になる」と述べています。
それでは、わたしたちの日本神話はどうなのでしょうか?
日本神話について、著者は以下のように述べています。
「私は日本神話は、大局的に見ればユーラシア大陸に広く分布するローラシア型神話群に属していると考えている。つまり日本神話とゲルマン、北アジア、朝鮮、インドの各神話などとの類似性は同じ根っこから来ているからだと理解している。ポリネシア神話との類似性も同様である。ただし日本列島は、人類が東南アジアから北方アジアあるいはアメリカ大陸へと移住するときの経路になっていたために、列島にはゴンドワナ型神話の痕跡も存在する。そのために、日本神話の複雑さあるいは多様性が生まれた、そう考えている」
第二章「旧石器時代の文化」では、「初期ホモ層の埋葬」として、ネアンデルダール人の段階になると、意図的な埋葬の証拠が増えてくるとして、著者は以下のように述べています。
「イラクのシャニダール洞穴で発見された人骨の周辺から花の花粉が発見されたことにより、この人骨は洞穴の奥に安置されて花が手向けられたのではないかということで有名になった。洞穴のこれほど奥まで花粉が飛ぶことはないから、この推測は確実だと言われた。しかし後に発掘隊のメンバーの2人が飾りのために体に花を付けていたことが分かり、この推測を疑問視する向きもある」
ネアンデルタール人といえば、著者は「新人の登場」として、以下のように述べています。
「ネアンデルタール人とホモ・サピエンスの間にはDNAの面でほとんど繋がりはないと言われてきた。しかし最近のゲノム分析では、ネアンデルタール人とホモ・サピエンスの間に若干の遺伝子の交換があったことがわかってきた。またネアンデルタール人の文化であったムスティエ文化が発展したシャテルペロン文化には、ホモ・サピエンスの文化とされるオーリニャック文化の影響を受けている可能性がある。この例に見られるように、DNAに共通性がなくても、文化的な影響を受けることがあるのは、人類には学習という能力があるからである」
また、「動物の王あるいはシャーマンと原母」として、著者は述べています。
「壁画研究者のD・ルイス=ウィリアムズはアボリジニやカラハリ・サン、あるいは北米の民族事例や壁画を比較した上で、旧石器時代の洞窟壁画は暗い場所で一種の幻覚を見ながら行う、シャーマン的儀礼の証拠であると考える。このような儀礼は神話的思考と密接に関わると考えていいだろう」
これに関しては、この読書館でも紹介した『洞窟のなかの心』で詳しく書かれています。
第三章「人類最古の神話的思考―ゴンドワナ型神話群の特徴」ではメラネシアの神話を例にして、ゴンドワナ神話群においては「海は最初から存在した」と語られることが多いとして、以下のように述べられています。
「世界の始まりは具体的な話題から説き起こされ、宇宙は空の人々が住む世界であり、一方、死者たちは生者と同じように暮らしている。死者の村は同じ村のブッシュ、あるいは沖の島という具合に具体的な場所として語られる。ときには最初の存在、いわば神が語られ、それが人間や天体や地形を造ったとされるが、それ以上の興味は持たれない。また神々と精霊と祖先の霊は明確に区別されておらず、最初の存在はしばしばトーテムとして今日まで畏敬されている。そして多くの地域で蛇が最初の存在とされるが、その蛇が殺されて人間の祖先になる。また死んだ蛇の体から最初の作物が起源する(死体化生型神話)」
第四章「人類最古の物語―ローラシア型神話群」では、「ローラシア神話群の層序」として、著者は以下のように述べています。
「ローラシア型神話群では無からの世界の出現(エマージェンス)、その進化(エボリューション)、あるいは至高神による創造(クリエーション)などから始まって、その後、神々の物語や神同士の闘争、最初の世界の破滅と再生などが語られる。そしてその延長上に今度は人間の誕生とその子孫たる王族の出現、またその一族である英雄の旅と戦い、この世の秩序化と混乱の平定などが続く。そのようにして、この神話群に属する神話の多くは支配者の正統性を主張して終わる」
また、著者は最古の神話テキストについて、以下のように述べます。
「現存する文字記録の神話テキストのなかで、各地域においてそれぞれもっとも古いものは、今から4000年ほど前のメソポタミアの『ギルガメッシュ』などの楔形文字文書、エジプトの絵文字(ヒエログリフ)文書、さらに2700年ほど前のギリシャの『神統記』、さらにインドのヴェーダ、中国では『楚辞』、『山海経』『淮南子』などであり、日本では『古事記』や『日本書紀』、アメリカ大陸ではマヤの『ポポル・ヴフ』などがあげられる」
「ローラシア型神話の基本シェーマ」では、以下のように述べられています。
「ローラシア型神話群は人類の最古の物語である。創造、成長、そして世界の破壊、そして神と人間の進化と退化、また誕生から死、さらには創造からその破壊に至るまで、宇宙と世界のサイクルは、人間の体、その誕生、成長、老化、そして死と対比して語られる。これは人類最古の世界観あるいはイデオロギーといえるだろう。もちろんすべての神話群がこのシェーマにきれいに当てはまるわけではなく、それぞれの地域の神話においてさまざまなモチーフの省略や統合も頻繁に行われる」
続けて、著者は以下のようにも述べています。
「日本の『古事記』や『日本書紀』がそうであるように、さまざまな系統の神話の複合体の場合や、稲の起源が2度語られる(『古事記』では女神オオゲツヒメノカミが、『日本書紀』ではウケモチカミが死んでその体から稲や五穀が出てきたという死体化生型神話が語られるその一方で、『日本書紀』で稲はもともと高天原でアマテラスが管理していたが、天孫降臨のさいに地上に降りる天孫に授けて地上に伝えたとされる。のみならず、天孫降臨以前から稲はすでに地上にあったと解釈できる記述も『日本書紀』や『風土記』には存在している)などの矛盾も存在する。だが総体的に見ると、神話群全体には基本的には共通のストーリーラインが見いだせる、そう世界神話学説は考える」
ローラシア型神話にとっての究極的な問いは、「世界と人間の起源はどのようなものだったのか?」です。この問いについて、著者は「原初の出現」として、以下のように述べています。
「世界の始まりは、ユダヤ系の神話などでは創造(クリエーション)とされる。至高神の力によって世界が生み出されるのである。しかし多くの神話では、むしろ無からの出現(エマージェンス)ともいうべき現象が見られる。何もないところから、あるいは無限の闇の中からひとりでに世界の芽が胎動してくる、という現象である。これを出現型神話と呼ぶ」
日本の『古事記』の冒頭の「天地初発之時」(あめつちのはじめのとき)もこちらに近いとして、著者は以下のように述べます。
「出現型神話では、原初の存在、あるいは元物質は、原初の無、あるいは混沌、水、潜水者(アースダイバー)と浮遊する大地、原初の巨人、牛、卵などとされる。無からの出現を語る神話の有名な事例がインドの『リグ・ヴェーダ』である」
「聖書を生み出したヘブライの創世神話では、神々による最初の天と地の創造の後に原初の闇が語られる。しかし聖書のさまざまな翻訳を比較すると、当初、大地が混沌から現れたとされていたものが、だんだんと神の創造というニュアンスが強くなっていったことが知られている」
興味深いのは、現世の前に3つの時代があったとする「四時代」の話が西アジアからギリシャにかけて顕著であり、印欧語族にもっとも広範囲に広がっていたというくだりです。このような四時代制はゾロアスター教神学に由来する可能性があるとして、著者は以下のように述べます。
「ゾロアスター教では世界は1万2000年続くとされる。最初の時代は善き宗教がゾロアスターによって啓示された黄金時代、次に彼の保護者である王が彼の宗教を受け入れた銀の時代、そしてササン朝ペルシャ期に相当する鋼の時代、さらには宗教画衰退する鉄の時代である。悪が敗北するのもこの時代である。善と悪の闘争は果てしなく続く。この後、世界は一度破滅するが、最後に流星群が天空に現れ、最終的には悪が滅び、魂と、肉体あるいは物質との完全な合一が果たされる。おそらくこのゾロアスター教における連続する世界の破壊と再生の思想も、中東からギリシャにかけての基本的な宗教観の一環であろう」
「神々の数世代、人間の誕生と堕落、世界の破局」として、著者は「『金枝篇』を書いたジェームズ・フレーザーは、太陽信仰は文明社会に多く見られると指摘しているが、社会が進化すると、太陽神の系譜は王族や貴族に限られてくる。ゴンドワナ型神話群にも表面的に似た天神の子孫の話はあるが、明確に太陽神とされるものはない。人間は最高神の直接の子孫というわけではなく、神かトーテムによって創造されるのが普通である」と述べています。さらにローラシア型神話では、人間の出現から土地のシャーマン、あるいはのちの貴族の出現へと続くのが一般的であるとし、著者は以下のように述べます。
「ここでは英雄やシャーマンあるいは妖精が出現し、火や食料、さまざまな技術や作物をもたらす。それに伴って儀礼の始まり、人間の拡散、貴族一族の誕生、地域史の始まりが語られる。すなわち神や人間のために最初の火を盗む話、シャーマンのような存在の出現、儀礼や供犠の起源、聖なる飲み物の起源、人間社会そのものの確立などだが、それには相互的な交換、同意、結婚の制度などが伴う」
そしてローラシア型神話は、最終的な世界の破滅を語る黙示録をしばしば伝えるとして、著者は以下のように述べています。
「破局の原因は氷河期、地下世界(暗黒)、洪水、火の雨などとされる。この世界の破滅のモチーフが4ないし5時代制神話に取り入れられると、破滅のたびに世界が作り直されることになる。ゾロアスター、インド、ゲルマン、エジプトなどでは破壊はローラシア型神話の最後の所行となっている。洪水による破壊はギリシャやメソポタミア、聖書、ポリネシアでは人間への罰として起こる。これに対して、何度も破滅が起こるのが中米や後期インド神話である。これは創造の試みが失敗したために起こる」
また、「ローラシア型神話の意義」として、著者は述べています。
「地上における誕生から成長、そして死にいたるというローラシア型神話のストーリーラインは人間の成長と死と対比的である。またそれは、人間の現状を説明する手段、すなわち『なぜわれわれはここにいるのか』に象徴的に答えようとするものである。これはゴーギャンの『われわれはどこから来たのか、われわれは何者か、われわれはどこへ行くのか?』という問い、あるいはカントの『私は何を知ることが出来るのか、私は何をなすべきか、私は何を望むべきか?』という問いに対する回答である。また死後の世界についてもポジティブな答えを表現するものである」
このあたりは、拙著『唯葬論』(サンガ文庫)の第五章「神話論」でも詳しく述べました。
さらに「ローラシア型神話とは」として、ローラシア型神話群は本来の意味における人類最古の「物語」であると著者は喝破し、こう述べます。
「ローラシア型神話の基本構造が繰り返し今日まで再生されるのは、その基本的なストーリーラインに今日でもわれわれに訴えるものがあるからである。不思議なことに、言語や文化あるいは経済形態を超えて現代を生きる人類の心に響くのは、何らかの意味において人類に内在的ななにものかにその源を発しているからだ。だからこそ悪用される危険性もあるのだ。
日本神話が戦前、軍国主義教育に利用されたことは周知の事実である。また朝鮮半島や南方の神話との類縁性が日本民族を中心とした同根説の証拠として大東亜共栄圏の根拠とされた。その反動で、日本では戦後、神話を研究することがタブーとなった不幸な時代があった。神話や民話研究はけっして政治と無関係でない。戦前、日本が中国大陸や朝鮮半島に侵略を画策していたとき、七福神の船に桃太郎と家来の動物たちが乗り込み、侵略の地へ鬼退治に出向く挿絵などが教育用に描かれたことがあることを忘れてはならない」
世界神話学説を提唱したヴィツェルは、「ナチスドイツやロシア革命のイデオロギーにもローラシア型のストーリーラインが見いだせる」と言いました。彼はそれ以上詳しく説明していませんが、著者は「おそらく最初は不遇であった英雄が苦難を堪え忍び、最後には過去の体制を打ち破って世界を再生させる、といった現体制の正当性を語る神話につながるということだろう」と推測しています。著者は石塚正英氏の書いた『「白雪姫」とフェティシュ信仰』を紹介し、以下のように述べます。
「『赤ずきん』や『白雪姫』が北欧の神話的要素やキリスト教民俗を取り込んだ童話であることはよく知られている。ワイマール共和国時代には、それまでは削除されていた、これらの童話の野蛮で残酷な部分が再度取り入れられて子供世代の教育に活用されたという」
続けて、著者は以下のように述べています。
「ヒトラー青年運動の指導者が編集した『若い民族』という児童向けのナチス文学書は闘争を理想化し、権力を賞賛し、向こうみずな勇気と神秘主義に力点を置く童話集だが、それは一面においてはこのようなグリム童話の側面を強調したものだったのだ。さらにドイツ文学者野村泫氏によると、ナチスはグリムの昔話を大いに利用し、赤ずきんの話に出てくる悪い狼はユダヤ人で、赤ずきんは哀れなドイツ国民、そして赤ずきんを救い出す猟師は国民を解放するヒトラーである、という」
第五章「世界神話学の中の日本神話」の冒頭では、「日本神話の系譜」として、著者は以下のように述べています。
「日本人の起源と相まって、日本神話の系譜には長い研究の歴史がある。思い切って単純化すると、島生み、作物起源、死の起源などに関する基層的な神話は中国南部、東南アジアあるいはオセアニアなどに類例を辿ることができる。一方、天孫降臨など支配階級に繋がる神話は朝鮮半島から中央アジアの方に連なる内容を持っている。また神話細部の要素ではなく、その骨組みあるいは構造を比較すると、ゲルマンを始め印欧語族の神話にも共通性が見つかることが神話学者の大林太良や吉田敦彦によって指摘されてきた」
「日本神話と世界神話」として、著者は、混沌の闇から次第に大地が固まってくる状況を語る記紀神話の冒頭は、古くから南島、ことにポリネシアの創世神話との類似性が注目を集めていたことを指摘し、さらに述べます。
「ポリネシアでも例えばマルケサスの創世神話がそうであるように、国土の成長を基礎や家屋や水波を意味する神名で象徴している。それによると最初に虚無があった。その中に隆起、沸騰、暗黒の波、渦、泡立ち、吸収が生じ、ついで大小長短、いろいろな形の柱と支柱が現れて、さらには基礎が出現する。続いて空間、光、山が現れた。これらの話もローラシア型の原始混沌からの出現神話の範疇に入るだろう」
ちなみに、イザナキ・イザナミがアマノヌホコという矛で原初の海をかきまわして、滴りが落ちた所にオノゴロ島ができた、という件りがポリネシア世界の島釣りモチーフの類縁であることは、多くの学者が指摘しています。
「死後の世界」として、著者は、オルフェウス型神話(死んだ親族を訪ねてあの世に行く神話)にはイザナキ・イザナミのように、2人の神がこの世とあの世の間で離縁を誓いあう「誓健(こととわたし)」モチーフがあると指摘し、さらには以下のように述べます。
「オセアニアでは、『誓健』はミクロネシアのカロリン諸島やメラネシアのフィジー諸島にも見られる。
さて、イザナキは黄泉の国から帰って来ると筑紫の日向で水の中でみそぎをし、次々に神を生んだ。目を洗ったとき左目からアマテラス、右目からツクヨミノミコトが生まれた。ミクロネシアにはリゴアププという神が木の窪みで水を飲んで女子を生む、そしてその目から男女一対の神が生まれ、人間の始祖になったという神話がある。
また生者と死者は食料あるいは調理の火を異にせねばならない。もし禁を犯したら永遠の離別になるという話がメラネシアなどにも見いだせる(後藤明『南島の神話』参照)」
日本神話の後は、中国神話としての『西遊記』が取り上げられます。「ローラシア型神話としての『西遊記』として、著者は以下のように述べています。
「『西遊記』のポイントは4つある。第1に観世音菩薩が女性、それも処女として現れる点である。第2に観世音菩薩は神通力を持つものの、最高の神格ではなく、その上に如来が存在する点である。『西遊記』は、如来という最高神格から与えられた試練の旅なのである。第3に天竺旅行は三蔵法師からみると帰還であり、この英雄の旅を女神が援助する形式と考えられる点である。第4にしばしば観音が乞食、老人、道人、美女など変幻自在、さまざまな人間に化身して登場する点である」
続けて、著者は以下のように述べます。
「同様の構造は古代ギリシャの叙事詩『オデュッセイア』にも見られる。第1に旅を助けるアテーナーは女神であり処女神である。第2にアテーナーを超える存在としてゼウスがいる。第3にオデュッセウスが故国に帰還する物語である点である。第4にアテーナーは身を隠して行動するが、ときにオデュッセウスのもとに姿を現す。しかし傍らの人々には見えないという不思議がある。同じことは古代ローマの叙事詩『アエネイス』でも指摘できる」
第六章「日本列島最古の神話」では、「ゴンドワナ型神話の意義」として、著者は以下のように述べています。
「人類が誕生すると知能の発達の結果として、社会の中の逸脱者、たとえば力ずくで資源を多く占めようとする者、あるいはズルをして労力をかけずに分け前にあずかるフリーライダーなどが発生した。しかし狩猟採集民の多くでは、これらを排除する力も働くようになった。このような輩がもし生存に有利であったとすれば、そのような遺伝子の方が選択され、人類の社会は争いの絶えない、あるいはズル優先の不道徳な社会となり、早晩滅びていただろう。一見不利になる、つまりコストが大きいと思われる利他主義者が多く残って形成したものが、人類最初の社会である狩猟採集民社会だったのだ」
文化人類学者であるクリストファー・ボームは、著書『モラルの起源』で、人類は脳の発達によって、乱暴やズルは最後には損をするという教訓を内面化したと指摘しました。これがモラルの誕生であるというボームの結論を紹介した著者は、以下のように述べます。
「私は、この説を知り、現世の狩猟採集民の多くが保っているとのような慣習こそゴンドワナ型神話の基盤をなしていたのではないかと考えるに至った。しかし鉄器が発達し武器の殺傷能力が高まり、また経済的な不平等が生じ、宗教が不平等を覆い隠すイデオロギーとして機能するようになると、力のある者、能力のある者が権力を握れる社会になっていった。ローラシア型神話がしきりと王や貴族などが誕生した理由を説明しようとするのは、その結果だったのではないだろうか」
さらに著者は、「行き詰まった現代社会にこそ必要とされる思想」として、以下のように述べています。
「解決の糸口が見えない、現代の人類社会。どんな思想も大宗教も解決策を提案できないでいる今日、よほどの革新的な思考の転換が必要だ、そう多くの人々が感じ始めているのではないだろうか。私にも答えはわからない。しかしこんなときにこそ、人類としての原点にもどってみるべきではないか、このところ私はそう考え始めている」
そして本書の最後で、著者は以下のように述べるのでした。
「ゴンドワナ型神話が教えるのは、対等の関係あるいは互酬性、すなわち調和と共存こそが世界の神秘、そして人類の、いや、地球上の生きとし生けるものたちの叡智だということだ。動物も、植物も、森もみなそう考えているからだ。結局のところは進化思想であり右肩上がりの思考であり、さらには自民族中心主義につながりかねない危険性を孕んだローラシア型神話とは違って、ゴンドワナ型神話は、われわれは自分たちだけの永遠の成長など求めてはならないことを教えてくれる。
人類最古の神話、あるいは日本列島最古の神話について考えるなど、浮世離れした作業に見えるかもしれない。しかしこのような試みにこそ案外、現代の行き詰まりを解決できるヒントがあるのではないか」
わたし自身は、人類が行き詰まったときは「最古」のものに帰るべきであると考えています。いわば「初期設定」をするわけです。人類にとって最古のものといえば、神話と儀式です。拙著『儀式論』(弘文堂)の第2章「神話と儀式」では、人類は神話と儀式を必要とし、両者は古代の祭儀において一致していたことを明らかにしました。本書を読んで神話に興味を持たれた方は、ぜひ、『儀式論』も一読していただきたいと願っています。