- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2020.03.17
『物語は人生を救うのか』千野帽子著(ちくまプリマリー新書)を読みました。一条真也の読書館『人はなぜ物語を求めるのか』で紹介した本の続編です。わたしたちの人生はままならないものであり、困難を乗り越えるためには物語が必要です。果たして、物語はわたしたちを救ってくれるのかを考える本です。著者はパリ第4大学博士課程修了の文筆家で、公開句会「東京マッハ」司会とのこと。
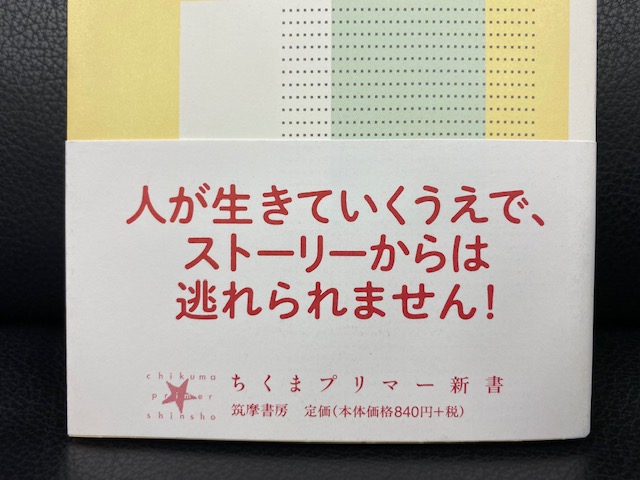 本書の帯
本書の帯
本書のカバー裏表紙には「世界を解釈し理解するためにストーリーがあった方が、人は幸福だったり、生きやすかったりします。実話とは? そして虚構とは? 偶然と必然って? 私たちの周りにあふれているストーリーとは何でしょう?」と書かれています。また、帯には「人が生きていくうえで、ストーリーからは逃れられません!」とあります。
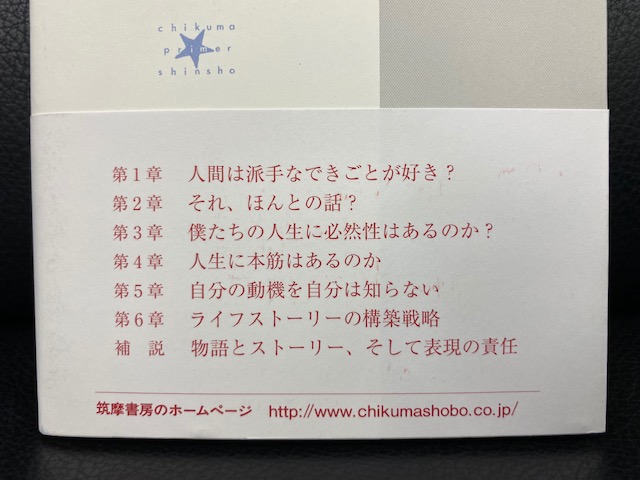 本書の帯の裏
本書の帯の裏
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
第1章 人間は派手なできごとが好き?
1 犬が人を噛むか、人が犬を噛むか?
2 珍しいできごとと、けしからぬできごと
第2章 それ、ほんとうの話?
1 ストーリーには、派手なできごとさえあればいいのか?
2 架空の人がピンチに陥っても、笑う気にはならない
3 事実は小説より奇なり?
4 フィクションとノンフィクションの違いは?
第3章 僕たちの人生に必然性はあるのか?
1 人は現実にも必然性を要求してしまうことがある
2 できごとの意味づけ・必然性・因果関係と報告価値
3 僕がこうしたら、まさにそのとき、世界がこうなった
第4章 人生に本筋はあるのか
1 人は話の「本題」「本筋」を自動的に決めている
2 さて、この本の要点は? あなたの人生の教訓は?
第5章 自分の動機を自分は知らない
1 実話における偶然
2 わかったときには、
「意味のあるストーリー」の形にしている
3 〈心の穴〉はいつできる?
第6章 ライフストーリーの構築戦略
1 脚本のレパートリーにないことが起こると、
人間はフリーズすることがある
2 ストーリーは、
特定の立場から見たストーリーにすぎない
3 人に罪悪感を抱かせようとするシステムからは
すぐに逃げろ
補説 物語とストーリー、そして表現の責任
「日本語で読める読書案内」
「あとがき」
「はじめに」で、著者は以下のように述べています。
「人間は不可避的にストーリーを合成してしまう」として、「人間は物語を必要としている、というのは、まるで人間が、自分の外にある日光や水や酸素と同じように、物語を外から摂取することが必要であるかのようなイメージですよね。僕はそれとは違うことを考えています。人間は生きていると、二酸化炭素を作ってしまいます。そして人間は生きていると、ストーリーを合成してしまいます。人間は物語を聞く・読む以上に、ストーリーを自分で不可避的に合成してしまう。そう思っているのです」
続いて、著者は以下のようにも述べています。
「生きていて、なにかを喜んだり楽しんだり、悲しんだり怒ったり、恨んだり羨んだりするのは、その『ストーリー』による意味づけのなせるわざです。『喜んだり楽しんだり』の部分だけを拾って生きることができればいいのですが、なかなかそうはいきません。『苦』とか『生きづらさ』とかを生み出しているのが、ほかでもない『喜んだり楽しんだり』の部分なのですから」
この発言は人間にとっての「ストーリー」の本質を見事に説明していると思います。ここでいう「ストーリー」とはもちろん小説や演劇や映画の筋ではなくて、人間が生きていくための内的な物語のことです。
物語は「宗教」と深い関係がありますが、「道徳」とはどうなのでしょうか。第1章「「人間は派手なできごとが好き?」の1「犬が人を噛むか、人が犬を噛むか?」では、「道徳規範、その他の規範からの逸脱」として、著者は以下のように述べています。
「道徳はあくまで感情という形で感じられるものです。理屈が先にあるのではありません。理屈はむしろ後づけです。言い換えると、道徳感情に、進化論でいう適応的な根拠(生物種の形や行動パターンが、周囲の環境下で生きていくのに向いたものになっていると判断できる根拠)がたまたまあったとしても、そういった偶発的事情から独立した『絶対的・客観的に正しい、合理的な』根拠というものは、おそらくありません。ヒトという生物は、道徳感情に反する事例が発生したら、群れでそれを情報としてシェアする必要を感じるようにできあがってきたのではないでしょうか」
たとえば、不倫がタブー視されるなどもそうです。共同体の中で他のメンバーの所有物(配偶者を含む)を脅かしたり、共同体内で望ましいとされている家族像から逸脱するような行動をするとスポイルされるのです。著者は、「思いっきり極論しちゃうと、僕らのご先祖は、自分が不利なあつかいを受ける可能性に敏感な(=心配性で僻みっぽい)人たちであったということ。呑気な人たちは子孫を残せず滅んじゃったのではないか。だから僕らのなかの動物的な部分は、心配性で僻みっぽくて、ほっとくと他人の瑕疵についつい気がついて大騒ぎしたがるのではないか。だから犯罪や著名人の醜聞がワイドショウの題材になるのではないか、と思うのです」と述べています。
第2章「それ、ほんとの話?」の4「フィクションとノンフィクションの違いは?」では、著者は「フィクションとは近代的な約定である」として、「現在、僕たちはフィクションをフィクションとして受容しています。少なくとも、身体の文化的な部分では、そのように自覚しています。しかしそもそも、作り話がみずから作り話であることを謳って流通するというフィクションの伝達状況が、人類初期からずっとあったとは思えません。神話とか伝説とかいったものは、いかにファンタジー小説に似ていても、当初は特殊で象徴的な『実話』の一種として流通していたと思われま」と述べます。。
著者いわく、作り話が演劇的パフォーマンス抜きで、みずから作り話であることを謳って流通するという伝達形態は、なんらかの条件を満たした社会・文化のもとにようやく成立するといいます。残された小説の古典から推測するに、1-2世紀のローマ帝国都市部、唐代都市部、アッバース朝のバグダード、平安京などはその要件を満たしていたと考えられるそうですが、政権交代などがあるとその要件は失われるとか。そして著者は、「現在の僕たちがフィクションをフィクションとして読んでいるのは、ルネサンス以後のヨーロッパの文化条件がグローバル規模に拡大した結果だと言えます」と述べています。
本書は、著者の前作『人はなぜ物語を求めるのか』の「あとがき」の内容をにさらに詳しく述べた印象です。書名の「救う」という単語からグリーフケアのヒントになる部分を期待しましたが、残念ながらそれは得られませんでした。
拙著『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)で、わたしは葬儀という儀式の役割について書きましたが、必然的に物語の本質にも言及しました。愛する人を亡くした人の心は不安定に揺れ動いています。しかし、そこに儀式というしっかりした「かたち」のあるものが押し当てられると、不安が癒されていきます。
親しい人間が死去する。その人が消えていくことによる、これからの不安。残された人は、このような不安を抱えて数日間を過ごさなければなりません。心が動揺していて矛盾を抱えているとき、この心に儀式のようなきちんとまとまった「かたち」を与えないと、人間の心にはいつまでたっても不安や執着が残るのです。この不安や執着は、残された人の精神を壊しかねない、非常に危険な力を持っています。この危険な時期を乗り越えるためには、動揺して不安を抱え込んでいる心に、ひとつの「かたち」を与えることが求められます。まさに、葬儀を行なう最大の意味はここにあります。
では、儀式という「かたち」はどのようにできているのか。それは、「ドラマ」や「演劇」にとても似ています。死別によって動揺している人間の心を安定させるためには、死者がこの世から離れていくことをくっきりとしたドラマにして見せなければなりません。ドラマによって「かたち」が与えられると、心はその「かたち」に収まっていきます。すると、どんな悲しいことでも乗り越えていけるのです。
それは、いわば「物語」の力だと言えるでしょう。わたしたちは、毎日のように受け入れがたい現実と向き合います。そのとき、物語の力を借りて、自分の心のかたちに合わせて現実を転換しているのかもしれません。つまり、物語というものがあれば、人間の心はある程度は安定するものなのです。逆に、どんな物語にも収まらないような不安を抱えていると、心はいつもぐらぐらと揺れ動いて、愛する人の死をいつまでも引きずっていかなければなりません。
仏教やキリスト教などの宗教は、大きな物語だと言えるでしょう。「人間が宗教に頼るのは、安心して死にたいからだ」と断言する人もいますが、たしかに強い信仰心の持ち主にとって、死の不安は小さいでしょう。なかには、宗教を迷信として嫌う人もいます。でも面白いのは、そういった人に限って、幽霊話などを信じるケースが多いことです。宗教が説く「あの世」は信じないけれども、幽霊の存在を信じるというのは、どういうことか。それは結局、人間の正体が肉体を超えた「たましい」であり、死後の世界があると信じることです。宗教とは無関係に、霊魂や死後の世界を信じたいのです。幽霊話にすがりつくとは、そういうことだと思います。
儀式の話に戻すと、死者が遠くに離れていくことをどうやって表現するかということが、葬儀の大切なポイントです。それをドラマ化して、物語とするために、葬儀というものはあるのです。たとえば、日本の葬儀の9割以上を占める仏式葬儀は、「成仏」という物語に支えられてきました。葬儀の癒しとは、物語の癒しなのです。人類が葬儀を発明しなかったら、おそらく人類は発狂して、とうの昔に絶滅していたのではないでしょうか。わたしは、本気でそう考えています。
あなたの愛する人が亡くなるということは、あなたの住むこの世界の一部が欠けるということです。欠けたままの不完全な世界に住み続けることは、かならず精神の崩壊を招きます。不完全な世界に身を置くことは、人間の心身にものすごいストレスを与えるわけです。まさに、葬儀とは儀式によって悲しみの時間を一時的に分断し、物語の癒しによって、不完全な世界を完全な状態に戻すことなのです。ですから、本書のタイトルである「物語は人生を救うのか」という問いに対して、わたしは「救える」と答えたいです。
