- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.1846 プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『2000年の桜庭和志』 柳澤健著(文藝春秋)
2020.03.20
『2000年の桜庭和志』柳澤健著(文藝春秋)を読みました。一条真也の読書館『1964年のジャイアント馬場』、『完本 1976年のアントニオ猪木』、『1984年のUWF』で紹介した一連のプロレス・ノンフィクションを書いた著者の最新作です。著者は1960年、東京都生まれ。慶應義塾大学法学部卒業後、メーカー勤務を経て、文藝春秋に入社。編集者として「スポーツ・グラフィックナンバー」などに在籍し、2003年にフリーライターとなりました。
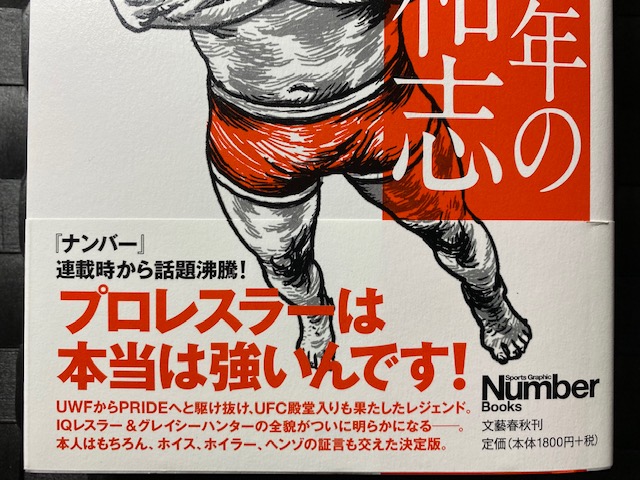 本書の帯
本書の帯
表紙カバーには桜庭和志の全身イラストが使われ、帯には「『ナンバー』連載時から話題沸騰!」「プロレスラーは本当は強いんです!」「UWFからPRIDEへと駆け抜けUFCの殿堂入りも果たした総合格闘技界のレジェンド桜庭和志。IQレスラー&グレイシーハンターの全貌がついに明らかになる――本人はもちろん、ホイス・ホイラー・ヘンゾの証言も交えた決定版」と書かれています。カバー前そでには、「サクラバは世界一のファイターだ。どんな相手だろうが、みんなをワクワクさせてくれる。すべてがクールなんだよ」というディナ・ホワイトの言葉が紹介されています。
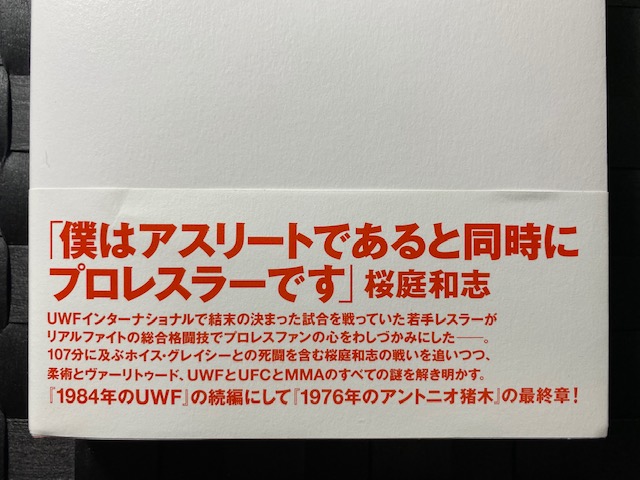 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には「僕はアスリートであると同時にプロレスラーです」という桜庭和志の言葉に続いて、「UWFインターナショナルで結末の決まった試合を戦っていた若手レスラーがリアルファイトの総合格闘技でプロレスファンの心をわしづかみにした――。107分に及ぶホイス・グレイシーとの死闘を含む桜庭和志の戦いを追いつつ、柔術とヴァーリトゥード、UWFとUFCとMMAのすべての謎を解き明かす」「『1984年のUWF』の続編にして『1976年のアントニオ猪木』の最終章!」と書かれています。
アマゾンの「内容紹介」には、こう書かれています。
「タイガーマスクに憧れプロレスを志した少年――。アマレスを学び、プロレスラーになった桜庭和志は、サブミッションレスリングに夢中になり、総合格闘技の世界へ。そしでPRIDEの主役となり、UFCのレジェンドであるホイス・グレイシーと107分の死闘の末、伝説となった。桜庭が、”リアルファイトのタイガーマスク”になったのである。桜庭の生き様を追いながら、グレイシー柔術とは何か、MMAとは何か、格闘技とは何か、UWFとは何か、プロレスとは何かに迫る。取材は、桜庭への幾度にも及ぶインタビューだけでなく、石井和義やホイラー・グレイシー、ホイス・グレイシーにも行った。著者は、自ら柔術教室にも通い、そのなんたるかを学んだ。まさに体当たりのこの作品は、著者の真骨頂でありひとつのシリーズの大きな締めくくりでもある」
本書の「目次」は、以下の通りです。
序章 ホール・オブ・フェイム
第1章 レスリング
第2章 最強の格闘技
第3章 UFC2
第4章 ヒクソン・グレイシー
第5章 道場破り
第6章 リアルファイト
第7章 PRIDE-1
第8章 キングダム
第9章 UFC JAPAN
第10章 新たなる舞台
第11章 PRIDE.4
第12章 DSE
第13章 悪役登場
第14章 柔術と異種格闘技戦
第15章 グレイシー柔術
第16章 ホイラー・グレイシー
第17章 対立する価値観
第18章 107分の死闘①
第19章 107分の死闘②
第20章 107分の死闘③
第21章 ヘンゾ・グレイシー
第22章 PRIDEからの離脱
第23章 HERO’S
第24章 DREAM
終章 クインテット
「あとがき」
序章「ホール・オブ・フェイム」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。
「2017年7月6日午後7時30分。桜庭和志はラスベガスのアリーナ『パークシアター』にいた。総合格闘技団体UFCのホール・オブ・フェイム、すなわち殿堂入り表彰を受けるためだ。UFCのホール・オブ・フェイムはモダン部門、パイオニア部門、コントリビューター(裏方)部門、ベストファイト部門の4つに分かれている。桜庭が受賞したのは草創期のMMA(Mixed Martial Arts=総合格闘技)で活躍したファイターを対象とするパイオニア部門だ」
続いて、著者は以下のように述べます。
「桜庭の主戦場は日本のPRIDEであり、のちにHERO’SやDREAMにも出場した。UFCへの出場は一度しかない(1997年12月21日に横浜アリーナで行われたUFC JAPAN)。UFC以外で活躍した選手であっても、圧倒的なパフォーマンスを観客に披露したファイターは顕彰すべきだ、というUFCの姿勢は素晴らしい。ちなみにプロレスのWWEも同じだ。アントニオ猪木、藤波辰爾、そして力道山がWWEの殿堂入りを果たしている。私たちの国はアメリカに学ぶ点がまだまだ多い」
1997年12月21日に横浜アリーナで行われたUFC JAPANで、ブラジルの柔術家マーカス・コナンを破り、優勝しました。それはPRIDE-1で髙田延彦がヒクソン・グレイシーに完敗した直後でした。著者は、「プロレスラーは弱く、柔術家は強い。プロレス最強の夢は雲散霧消した、と誰もが思った。ところが、髙田の敗戦からわずか2カ月後、誰もが予想しなかったことが起こる。桜庭和志が、UFCJAPANのヘビー級トーナメントに優勝したのだ。UWFインターナショナルでデビューした若手プロレスラーが、ブラジリアン柔術の黒帯からギブアップを奪い、優勝インタビューでは『プロレスラーは、本当は強いんです!』と発言したのだから、プロレスファンは狂喜乱舞した」と書いています。
1993年、「格闘技元年」と呼ばれ、K-1やパンクラスが生まれたこの年の11月12日、アメリカのコロラド州デンバーのマクニコルス・スポーツ・アリーナで「アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ」が開催されました。UFCです。反則は噛みつき、髪をつかむこと、目つぶし、急所攻撃のみで、あとはすべての攻撃が許される格闘技の大会です。馬乗りになって顔面にパンチを入れても、首を絞めても、後頭部に頭突きをしても、ヒジを落としてもいいという、まさにアルティメット(究極の)戦いでした。これを制したのは、ホイス・グレイシーという名の柔術家でした。ホイスはボクシングのアート・ジマーソン、プロレスのケン・シャムロック、そしてサバットのジェラルド・ゴルドーを次々に撃破し、見事に優勝を飾ったのです。
そのUFCには3つの衝撃があったとして、著者は「ほぼすべての攻撃が許されれば、これほど凄惨な戦いになるのか、という驚き。凄惨な戦いを、無傷で勝ち抜くことができる男がいるのか、という驚き。それを可能にする技術とは、日本から伝わった柔術なのか、という驚きである」と指摘しています。すべての攻撃が許されるヴァーリ・トゥードの技術を持っていたのは当時はブラジルの柔術家だけでしたが、その中でも無敵を誇るグレイシー柔術を代表するホイスの勝利は、多くの観客にとって魔法のように見えました。このUFCを企画したのは、ホイスの兄であるホリオン・グレイシーであり、その目的はグレイシー柔術を世界中に普及させることだったのです。
桜庭和志は、1992年7月、プロレス界に一大ブームを起こした新生UWFが崩壊した後に誕生したUWFインターナショナル(Uインター)へ入団しました。当初桜庭はプロフェッショナルレスリング藤原組の入団試験を受けるつもりだったそうです。髙田延彦をエースにいただくUインターではレスリング技術に加えて、打撃と関節技を習得する。1993年8月13日の日本武道館大会でスティーブ・ネルソンを相手にプロデビューします。Uインターはプロレス団体でしたが、ここで桜庭は先輩レスラーの田村潔司と2回、キックボクサーのレネ・ローゼと1回、リアルファイトを経験しています。
初期のUFCを席巻した柔術家の戦い方は、おおよそ「背筋を伸ばし、アゴを引いて、遠い間合いを保ちつつ、前蹴りを相手のヒザに向けて放つ。相手が足を引くと同時に一気に距離を詰め、そのまま組みついてテイクダウン。上をとると、蛇が獲物にからみつくように相手を制圧して、再度ポジション(横四方)やマウントポジション(馬乗り)の状態から絞め技や関節技で攻める」というものでした。しかし、次第にその戦法は知られるところとなり、柔術家は無敵ではなくなりました。代わりに脚光を浴びたのがレスリング出身の選手です。著者は、「レスラーが得意のテイクダウンで相手の上になり、下からの攻撃(三角絞めや腕十字など)を警戒しつつ殴るか頭突きで倒す。このような攻撃を”グラウンド&パウンド”と呼ぶ。このシンプルだが効果的な攻撃によって、UFCの主役は柔術家からレスラーに交代した。代表的な選手がドン・フライであり、マーク・コールマンであり、マーク・ケアーだ」と書いています。
そして、ドン・フライ、マーク・コールマン、マーク・ケアーと同様に、われらが桜庭和志もアマチュアレスリング出身の選手だったのです。しかし、アマレス出身であっても、桜庭の本職はプロレスラーでした。よって、MMA(総合格闘技)の舞台でも、つねに観客を意識しながら戦っていました。本書には、「僕たちの仕事は、お客さんが観に来てくれることで成り立っています。グラウンドでグチャグチャもつれあったまま、長時間膠着した末に引き分け。そんなつまらない試合ばかりを観せられれば、お客さんは二度と会場に足を運んでくれません。初めて格闘技を観る人でも、試合を楽しむことができて、次の試合もまた観にきてもらえる。僕たちはそんな試合をしなくてはいけないんです」という桜庭の言葉が紹介されています。
髙田延彦とヒクソン・グレイシーのリアルファイト実現のために誕生した格闘技イベント「PRIDE」が誕生しましたが、その主役はヒクソンに二度敗れた髙田ではなく、グレイシー一族を次々に撃破した桜庭でした。著者は、「桜庭和志は総合格闘技の伝道師だ。UWFのレスラーたちが使っていた関節技が、リアルファイトのMMAでも有効であることを伝え、一度関節技が極まってしまえば、バタバタ暴れてロープに逃げることなど絶対に不可能であることを示し、ストライカーとグラップラーの異種格闘技戦のだいご味を教え、打撃だけでも組み技だけでもMMAには勝てないことを明らかにした。かつて、マウントポジションとガードポジションの区別さえつかなかった日本の観客たちは、桜庭和志によって、リアルファイトのMMAの魅力を、ひとつひとつ学んでいったのだ」と述べています。
さらに、著者は桜庭について以下のように述べています。
「観客を楽しませつつ、リアルファイトの世界で結果を出す。そんな離れ業を可能とするのは天才だけだ。桜庭和志は、モハメッド・アリのような天才だった。ヴィトー・ベウフォートやエベンゼール・フォンテス・ブラガといった自分よりもはるかに重いクラスの選手と果敢に戦って勝利し、ホイラー、ホイスの両グレイシーをも撃破した桜庭和志を、90kg以下の世界最強ファイターとみなしたのは、日本人だけではなかった」髙田延彦や船木誠勝を破ったヒクソン・グレイシーは日本でビッグマネーを手にしましたが、世界中の格闘技ファンやファイターからの評価は桜庭のほうが比較にならないほど高いそうです。「ヒクソンは弱い相手とばかを選んでいる」「ヒクソンはサクラバから逃げている」といった批判の声が世界中で上がったのでした。むしろ、ヒクソンよりもホイスのほうが評価されていると言っていいでしょう。ヒクソンのことを「兄は私の10倍強い」と語ったホイスでしたが、勇気は弟のほうにありました。
2000年5月1日、「PRIDE GP2000決勝戦」で、桜庭和志はホイス・グレイシーと107分の激闘を演じ、ついに勝利を手にします。両雄の一戦を、日本の総合格闘技史上最高の試合と考えるファンは多いそうです。その理由は大きく分けて3つあるとして、著者は「ひとつめは、グレイシーサイドの要求を桜庭がすべて受け容れ、その結果、15分×6ラウンドの90分とインターバルを含めてトータル107分にも及ぶ常識を超えた長時間ファイトとなったこと。ふたつめは、その間、立ち技から寝技へ、寝技から立ち技へと何度も移行し、一瞬も目を離せないほどの緊張感に溢れる熱戦であったこと。3つめは、髙田延彦、安生洋二らUWFのプロレスラーが手も足も出なかったグレイシー柔術についにプロレスラーがリベンジを果たしたこと」と指摘しています。
あの伝説的な名勝負から、すでに20年という長い時間が経過しました。本書の最後に、著者は「1990年代末まで、リアルファイトのMMA=総合格闘技は危険で暴力的な上に、膠着ばかりでつまらないというのが日本の格闘技ファンの常識だった。その常識を完全にくつがえし、MMAを美しく芸術的で、意外性に溢れ、ユーモラスですらあるスペクテイタースポーツに変えてしまったのが2020年の桜庭和志だ」と書いています。さらに「あとがき」で、著者は「アントニオ猪木が生み出した『プロレスは最強の格闘技』という思想を、誰よりも真剣に受け止め、現実のものにしようと試みたのは元タイガーマスクの佐山聡であった。佐山聡がUWFという潰れかけたマイナープロレス団体でやろうとして失敗したことについては『1984年のUWF』で書いたつもりだ。本書『200年の桜庭和志』は『1984年のUWF』の続編であり、同時に『1976年のアントニオ猪木』の最終章でもある」と書くのでした。
本書に書かれていることは、わたしがほとんど知っていることでした。2000年当時、日本における総合格闘技熱は凄まじいもので、TVや雑誌などのメディアも桜庭和志についての情報を常に発信していました。ですから、本書を読んで新たに得た知識はあまりありません。もちろん著者の分析眼は相変わらず鋭いですが、正直言って、『1976年のアントニオ猪木』や『1984年のUWF』のような異様なまでの熱は感じませんでした。おそらく、猪木や佐山ほどには桜庭のことをリスペクトできていないのではないでしょうか。そのため、本書全体が「あっさり」した印象になってしまっています。
桜庭がPRIDEを離脱して高田延彦と絶縁するくだりはもっと踏み込んで書いてほしかったですし、『1984年のUWF』の「キャラメルクラッチ」のように基本的な誤植誤認が本書にも見られたことは残念です。しかしながら、本書を読むことによって、あの頃の日本の総合格闘技の盛り上がりぶりを思い出すことができました。2000年5月1日、わたしは「癒す人」こと「せたがや手技均整院」院長の鈴木登士彦君と一緒に東京ドームに出掛け、桜庭vsホイス戦をリアルタイムで観戦したのです。桜庭の勝利が決まったときの感動は今でもおぼえています。本当に、良い時代でした。