- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2011.11.23
『スティーブ・ジョブズ』Ⅰ・Ⅱ、ウォルター・アイザックソン著、井口耕二訳(講談社)を読みました。
今年の10月5日に逝去したジョブズは、大変な取材嫌いで有名でした。その彼が唯一全面協力した、本人公認の決定版評伝だそうで、全世界同時発売されるや、日本でもアマゾンの総合ランキング1・2位を独走している話題の書です。
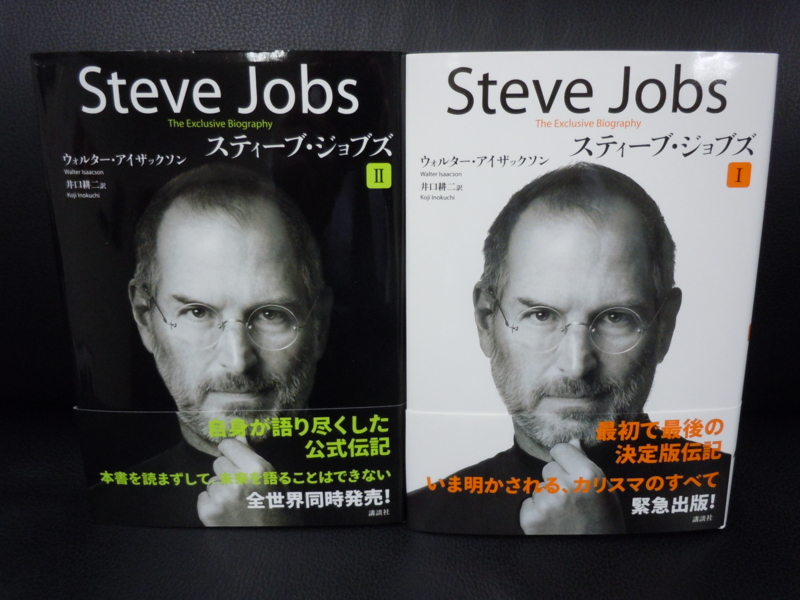
最初で最後の決定版伝記
本書の「目次」は、以下のようになっています。
『スティーブ・ジョブズ』Ⅰ
第1章 子ども時代 ~捨てられて、選ばれる
第2章 おかしなふたり ~ふたりのスティーブ
第3章 ドロップアウト ~ターンオン、チューンイン
第4章 アタリとインド ~禅とゲームデザインというアート
第5章 アップルⅠ ~ターンオン、ブートアップ、ジャックイン
第6章 アップルⅡ ~ニューエイジの夜明け
第7章 クリスアンとリサ ~捨てられた過去を持つ男
第8章 ゼロックスとリサ ~グラフィカルユーザインターフェース
第9章 株式公開 ~富と名声を手にする
第10章 マック誕生 ~革命を起こしたいと君は言う・・・・・・
第11章 現実歪曲フィールド ~自分のルールでプレイする
第12章 デザイン ~真のアーティストはシンプルに
第13章 マックの開発力 ~旅こそが報い
第14章 スカリー登場 ~ペプシチャレンジ
第15章 発売 ~宇宙に衝撃を与える
第16章 ゲイツとジョブズ ~軌道が絡み合うとき
第17章 イカロス ~のぼりつめれば墜ちるだけ
第18章 ネクスト ~プロメテウスの解放
第19章 ピクサー ~テクノロジー・ミーツ・アート
第20章 レギュラー・ガイ ~凡夫を取り巻く人間模様
第21章 『トイ・ストーリー』 ~バズとウッディの救出作戦
『スティーブ・ジョブズ』Ⅱ
第22章 再臨 ~野獣、ついに時機めぐり来たる
第23章 王政復古 ~今日の敗者も明日は勝者に転じるだろう
第24章 シンク・ディファレント ~iCEOのジョブズ
第25章 デザイン原理 ~ジョブズとアイブのスタジオ
第26章 iMac ~hello(again)
第27章 CEO ~経験を積んでもなおクレージー
第28章 アップルストア ~ジーニアスバーとイタリアの砂岩
第29章 デジタルハブ ~iTunesからiPod
第30章 iTunesストア ~ハーメルンの笛吹き
第31章 ミュージックマン ~人生のサウンドトラック
第32章 ピクサーの友人 ~・・・・・・そして敵
第33章 21世紀のマック ~アップルを際立たせる
第34章 第1ラウンド ~メメント・モリ 死を忘れるなかれ
第35章 iPhone ~三位一体の革命的製品
第36章 第2ラウンド ~がん再発
第37章 iPad ~ポストPCの時代に向けて
第38章 新たな戦い ~昔の戦いの余韻
第39章 無限の彼方へ さあ行くぞ! ~クラウド、宇宙船、そのまた先へ
第40章 第3ラウンド ~たそがれの苦闘
第41章 受け継がれてゆくもの ~輝く創造の天空
「はじめに」の冒頭で、2004年の夏に現代アメリカを代表するジャーナリストである著者のもとに、スティーブ・ジョブズから電話があったことが書かれています。2人は散歩をしながら語り合いますが、著者はジョブズから「僕の伝記を書いてくれ」と頼まれます。そのときのやり取りを、著者は次のように書いています。
「そのころ私はベンジャミン・フランクリンの伝記を出版し、アルベルト・アインシュタインの伝記を書きはじめたところだったので、一瞬、ジョブズが自分のことをそのふたりに連なるべき人物だと考えているのかなどと半ば冗談で思ったりした。ジョブズはキャリアの途中で、まだまだ上りも下りもたくさんあるはずだと思っていた私は、彼の依頼を断った。いまじゃない、10年後か20年後か、君が引退するころに書くよ、と」
ジョブズは、著者に「僕は子どものころ、自分は文系だと思っていたのに、エレクトロニクスが好きになってしまった。その後、『文系と理系の交差点に立てる人にこそ大きな価値がある』と、僕のヒーローのひとり、ポラロイド社のエドウィン・ランドが語った話を読んで、そういう人間になろうと思ったんだ」と打ち明けました。
それを聞いて、著者は「この伝記のテーマを提案されたのかと思った(少なくともこの場合、妥当なテーマだった)。文系と理系、つまり、人文科学と自然科学、両方の感覚を兼ねそなえた強烈なパーソナリティーから生まれる創造性こそ、フランクリンやアインシュタインの伝記で私が興味を引かれたトピックだったし、21世紀に革新的な経済を生みだす鍵になるものだとも思う」と考えたそうです。
なぜ、ジョブズは著者に伝記を書いてほしいと思ったのか。そのことを訊ねた著者に対して、ジョブズは「話を聞きだすのが上手だろうと思ったからさ」と答えます。そして、「23でガールフレンドを妊娠させ、それにどう対処したかなど、僕は、人様に誇れないこともたくさんしてきたよ。でも、”これだけは外に出せない秘密”なんてものはないんだ」と述べて、ありのままの自分の姿を書いてくれるように依頼したのでした。たしかに、著者は「話を聞きだすのが上手」でした。次のように書いています。
「ジョブズへの取材は40回ほどもおこなった。パロアルトの自宅の居間で本格的におこなったインタビューもあれば、えんえんと散歩しながら、あるいは車中、電話でおこなったものもある。彼のところへは18ヵ月ほど通ったが、その間、ジョブズはどんどん打ち解け、細かなところまで教えてくれるようになっていった。なお、アップルの昔の仲間が”現実歪曲フィールド”と呼ぶ、彼の特殊な性格を目の当たりにしたこともある。誰にでもある記憶違いのたぐいもあったが、自分にとっての現実を私と自分自身に語り続けたこともある。彼から聞いた話の裏取りや肉付けをおこなうため、合計100人を超える彼の友人、親族、競争相手、敵、仲間などからも話を聞いた」
本書は、どのような本なのか。いったい何が描かれているのか。著者は、次のように述べています。
「本書に描かれているのは、完璧を求める情熱とその猛烈な実行力とで、6つもの業界に革命を起こしたクリエイティブなアントレプレナー(起業家)の、ジェットコースターのような人生、そして、やけどをしそうなほど熱い個性である。6つの業界とはパーソナルコンピュータ、アニメーション映画、音楽、電話、タブレットコンピュータ、デジタルパブリッシングだが、これに小売店を加えて7つとする人もいるだろう」
そして、著者は本書をイノベーションの書としても読んでもらえるのではないかと期待しているとして、「イノベーション力を維持できる方法を米国が模索し、クリエイティブなデジタル時代の経済を構築しようと世界中でさまざまな努力がおこなわれているいま、ジョブズは、創意工夫、想像力、持続的イノベーションを象徴する究極の偶像となっている。21世紀という時代に価値を生み出す最良の方法は創造性と技術をつなぐことだとジョブズは理解していた。だから、想像力の飛躍にすばらしいエンジニアリングを結びつける会社を作ったのだ」と述べています。
こうして、この奇妙で偉大な人物の伝記は始まるのでした。
第1章「子ども時代 ~捨てられて、選ばれる」では、幼くして養子に出されたジョブズのトラウマが描かれています。スティーブ・ジョブズは、自分が養子だと小さいころから知っていました。「そのことについて、両親はとてもオープンだった」とジョブズは言ったそうです。
6歳か7歳のころ、向かいの女の子と芝生の庭で話していたとき、「じゃあ、本当のお父さんやお母さんは、あなたをいらないって思ったの?」と女の子から聞かれ、幼いジョブズは頭に電撃をくらったように感じました。ジョブズは、そのときのことを次のように振り返っています。
「あ~っ!って感じで。泣きながら家に駆け込んだのを覚えている。そしたら、両親に言われたんだ。『落ちついて、しっかり聞いて』って。ふたりとも真剣な顔で僕をまっすぐ見つめていた。『わたしたちは、あなたを選んだの』。ふたりとも、そう、ゆっくりと繰り返し語ってくれたよ。一語一語、しっかりとね」
この養子に出されたことから来る孤独感や疎外感は、彼の人生に大きな影響を与えたことは間違いないようです。
本書で、わたしが最も興味深く読んだのは、青年時代にジョブズが精神世界へ傾倒したくだりでした。第3章「ドロップアウト ~ターンオン、チューンイン」には、以下のように書かれています。
「ジョブズは精神世界や悟りに関するさまざまな本に感銘を受ける。とくに、サイケデリックドラッグ(幻覚剤)のすばらしい作用と瞑想についてババ・ラム・ダス(本名リチャード・アルパート)が書いたガイドブック、『ビー・ヒア・ナウ』の影響を強く受けた。
『あれは強烈で、僕はもちろん、友だちも多くが感化されたんだ』
そのような友だちのひとりが、やはりひげをちょぼちょぼとはやした1年生、ダニエル・コトケである。ジョブズがリードに来て1週間くらいのころにふたりは出会い、禅にディランにLSDと趣味が似ていて仲良くなった」
ジョブズは図書館に通い、コトケといっしょに禅の本をたくさん読むようになりました。一体どんな本を読んだのかというと、鈴木俊隆の『禅へのいざない』、パラマハンサ・ヨガナンダの『あるヨギの自叙伝』、リチャード・モーリス・バックの『宇宙意識』、チョギャム・トウルンパ・リンポチェの『タントラへの道―精神の物質主義を断ち切って』などだそうで、いずれもわたしも読んだことがある本ばかりです。彼が強い影響を受けたというラム・ダスの『ビー・ヒア・ナウ』も読みました。
ジョブズたちは、部屋の天井裏に瞑想室を作り、インドの絵に絨毯、ろうそく、香、座禅に使う座布団の坐蒲などを持ち込んだそうです。本書には、その頃の様子が以下のように書かれています。
「『天井の一部が開くようになっていて、そこから天井裏に入ると大きな空間があったのです。そこでサイケデリックドラッグを使ったこともありますが、だいたいは瞑想をしていました』
ジョブズにとって、禅宗を中心とする東洋思想に傾倒したのは一時の気の迷いでも若気のいたりでもなかった。いかにも彼らしい激しさで追究し、東洋思想を自分のなかに取り込んでいく。ふたたびコトケの証言―。
『スティーブは禅と深くかかわり、大きな影響を受けています。ぎりぎりまでそぎ落としてミニマリスト的な美を追究するのも、厳しく絞り込んでゆく集中力も、皆、禅から来るものなのです』
ジョブズはまた、直感や洞察を重視する仏教の教えにも強い影響を受け、『抽象的思考や論理的分析よりも直感的な理解や意識のほうが重要だと、このころに気づいたんだ』とのちに語っている。ただ気性が激しかったため、解脱して涅槃にいたることはできなかった。禅を追究したが、心の安寧も得られなかったし、他人に対する姿勢が和らぐこともなかったのだ」
もう1冊、大学1年のジョブズに大きな影響を与えた本がありました。フランシス・ムア・ラッペの『小さな惑星の緑の食卓―現代人のライフ・スタイルを変える新食物読本』という本です。わたしはこの本を読んでいませんが、菜食主義が個人にも地球にも大きなメリットをもたらすという内容だったとか。
この本を読んで以来、ジョブズは肉をほとんど口にしなくなっただけでなく、浄化や断食、あるいはにんじんやリンゴなど、1~2種類の食べ物のみで何週間も過ごすといった極端な食事をすることが増えていったそうです。
当時の精神世界への傾倒について、のちにジョブズは「僕はすばらしい時代に大人への階段をのぼったと思う。禅によって、また、LSDによって意識が高められたからね」と語っています。若い頃だけではありません。歳を取ってからも、意識改革の効果があったとサイケデリックドラッグを評価するジョブズは、「LSDはすごい体験だった。人生でトップクラスというほど重要な体験だった。LSDを使うとコインには裏側がある、物事には別の見方があるとわかる。効果が切れたとき、覚えてはいないんだけど、でもわかるんだ。おかげで、僕にとって重要なことが確認できた。金儲けではなくすごいものを作ること、自分にできるかぎり、いろいろなものを歴史という流れに戻すこと、人の意識という流れに戻すこと。そうわかったのはLSDのおかげだ」とはっきり述べています。
その後、ジョブズは強迫的といえるほど自我を求め、インドを放浪したり、ジョン・レノンも試したという「原初絶叫療法」を経験したりしました。原初絶叫療法とは、幼少期の抑圧された痛みが心理的問題の原因だとするフロイトの理論に基づくセラピーの一種です。その頃のジョブズは、自分が養子に出されたこと、また、生みの親を知らないことが心の痛みになっていると親しい友人に漏らしていたといいます。当時の友人も「スティーブは生みの親を知りたい、そうすることで自分を知りたいと強く願っていました」語っています。しかし、育ての親を傷つけたくなかったために、結局、生みの親を探すことはやめたそうです。
さて、ジョブズがのめり込んだ精神世界やLSDは、いわゆる「カウンターカルチャー」と呼ばれるジャンルです。カウンターカルチャー世界の住人とハッカーの協力を推進した人物にスチュアート・ブランドがいました。
ブランドは、長年にわたって楽しいことやさまざまなアイデアを生み出してきたいたずら好きの人物でした。60年代初頭には、パロアルトでLSDの研究を行っていましたが、そのうち、「ホールアース」と名付けたトラックストアでクールなツールや教材を移動販売するようになりました。そして販路を拡大するため、1968年にブランドは『ホールアースカタログ』の発行を開始します。
その創刊号の表紙には、宇宙から見た地球の有名な写真が使われていました。そこには「ツールへのアクセス」という副題が付いていましたが、その背景には「技術は人間の友となり得る」という考えがありました。『ホールアースカタログ』創刊号の最初のページに、ブランドは次のように書いています。
「自分だけの個人的な力の世界が生まれようとしている―個人が自らを教育する力、自らのインスピレーションを発見する力、自らの環境を形成する力、そして、興味を示してくれる人、誰とでも自らの冒険的体験を共有する力の世界だ。このプロセスに資するツールを探し、世の中に普及させる――それがホールアースカタログである」
この後ろには、「確実に動作する計器や機構に私は神を見る・・・・・・」ではじまるバックミンスター・フラーの言葉が続いていました。
よく知られていることですが、ジョブズは『ホールアースカタログ』が大好きでした。特に最終号が大のお気に入りだったようで、ハイスクールの生徒だった1971年に出たその号を大学でもオールワンファームでも持ち歩いていたそうです。ジョブズは、「最終号の裏表紙には早朝の田舎道の写真が使われていた。ヒッチハイクで旅でもしていそうな風景で、『ハングリーであれ。分別くさくなるな』の一言が添えられていた」と語っています。後にスタンフォード大学の伝説のスピーチに登場する「ハングリーであれ。分別くさくなるな」という言葉に、彼は『ホールアースカタログ』最終号で邂逅したのでした。
ちなみに、スチュアート・ブランドは、「ホールアースカタログが求め、世間に広めようとしたもの、渾然一体とした文化の化身としてもっとも純粋な存在なのがジョブズだ」と考えているそうです。ホールアースカタログがアメリカのIT業界に与えた影響をさらに詳しく知りたい方は、ブログ『ウェブ×ソーシャル×アメリカ』もお読み下さい。
本書には、ジョブズの魅力的な面ばかりが描かれているわけではありません。それどころか、じつに醜い一面もしっかり描写されています。
娘のリサの認知における往生際の悪さもそうですが、以下のような一文を読むと、「こういう人物とは関わり合いになりたくないな」と思ってしまいます。
「礼儀や敬意に欠ける面があるのはあいかわらずだった。ウエートレスはばかにするし、こんなものは『生ゴミ』だ、と出された料理を突っ返すことも多かった。1979年にアップルがはじめておこなったハロウィーンパーティーには、ローブをまとい、イエス・キリストのいでたちで出席。ちょっと皮肉な自己認識としてジョブズはおもしろいと思う扮装だったが、顔をしかめた人も多かった」
わたしは、ジョブズという人の本質を表現するには、本書に何度も登場する「現実歪曲フィールド」という言葉がぴったりだと思います。「現実歪曲フィールド」とは、そのままの現実を認めず、自ら現実を変えようとする生き方です。これはLSDによって得られた超現実体験の影響もあったかもしれませんが、ジョブズとはとにかく現実を認めず、自分の思うように変化させる意思の強い人でした。
もちろん、それには「思い込みの強さ」とか「自己中心的」といった負の側面もありますが、同時に「Think different」の精神そのものでもあったのです。人並み外れた「現実歪曲フィールド」ゆえに、ジョブズは数多くのイノベーションを実現したのでしょう。
たしかに非常識な側面が多々あったにせよ、ジョブズは間違いなく天才でした。部下や取引先から提案を受けると、最初は「くだらん!クズだ」と言いました。
しかし数日後には、「素晴らしいアイディアを思いついたぞ!」と言って、提案とまったく同じことを話し始めることもしばしばあったといいます。一種の人格破綻者のようにも思えますが、やはり彼は「天才」だったのでしょう。誰よりも、デジタル革命の次なる段階を予見し、推進したのはジョブズその人でした。その理由を著者は本書でいくつか列挙していますが、わたしが最も共感したのは次のような指摘でした。
「まず、彼が常に人間性と技術の交差点に立っていた点があげられる。音楽や写真、動画が大好きな上に、コンピュータも大好きだ。”デジタルハブ”とは要するに、創造的なアートの世界のモノを優れたエンジニアリングで結び付けることだ。のちにジョブズは、『リベラルアーツ』と『テクノロジー』の交差点を示す道路標識を、製品プレゼンテーションの最後に示すようになる。その交差点こそ彼が立つ場所であり、だからこそ、誰よりも早くデジタルハブを思いついたのだ」
また、著者は「ジョブズはシンプルを追求する」と指摘し、次のように述べています。
「シンプルさの極致といえるのは、iPodにオン・オフのスイッチをつけないというジョブズの決定だろう。これにはまわりも驚いた。
このあと作られるアップルの機器は大半がそうなっていく。
たしかに必要ないのだ。美的な意味でもあるべき形という意味でも不快なだけである。使うのをやめると休止状態となり、なにかキーに触れると使えるようになる。それで十分であり、クリックすれば、さよならとオフになるスイッチなど必要ないのだ。
こうしてすべてが収まるべきところへ収まった。
1000曲を記憶できる装置。その1000曲をナビゲーションできるインターフェースとスクロールホイール。1000曲を10分以内でダウンロードできるファイアワイヤー。そして、1000曲を再生できるだけのバッテリー。
『そう気づいたとき、僕らは顔を見合わせたよ。「すっごくクールなものができるぞ」ってね。クールなものになるのはよくわかっていた。みんな、自分も絶対にひとつ欲しいって思っていたからだ。コンセプトもすごくシンプルでよかった。「1000曲をポケットに」だよ』
名前は、コピーライターから『Pod』が提案された。iMacやiTunesを参考に、これを『iPod』としたのはジョブズ本人である」
まあ、個人的な意見を言わせてもらえば、オンとオフのスイッチがないために、バッグの中のわたしのiPodはいつも何かに触れて勝手に作動してしまい、気づくとバッテリーが切れかかっているのですが・・・・・(苦笑)。
下巻の最終章となる第41章「受け継がれてゆくもの ~輝く創造の天空」で、著者は「リーダーには、全体像をうまく把握してイノベーションを進めるタイプと、細かな点を追求して進めるタイプがいる」として、ジョブズは両方を過激なほどに追求するリーダーであると述べています。そのために、彼はさまざまな業界を根底から変える製品を30年にわたって次々と生み出すことができたといいます。そのジョブズの偉大な業績について、著者は以下のように列記しています。
●アップルⅡ~ウォズニアックの回路基板をベースに、マニア以外にも買えるはじめてのパーソナルコンピュータとした。
●マッキントッシュ~ホームコンピュータ革命を生み出し、グラフィカルユーザインターフェースを普及させた。
●『トイ・ストーリー』をはじめとするピクサーの人気映画~デジタル創作物という魔法を世界に広めた
●アップルストア~ブランディングにおける店舗の役割を一新した。
●iPod~音楽の消費方法を変えた。
●iTunesストア~音楽業界を生まれ変わらせた。
●iPhone~携帯電話を音楽や写真、動画、電子メール、ウェブが楽しめる機器に変えた。
●アップストア~新しいコンテンツ製作産業を生み出した。
●iPad~タブレットコンピューティングを普及させ、デジタル版の新聞、雑誌、書籍、ビデオのプラットフォームを提供した。
●iCloud~コンピュータをコンテンツ管理の中心的存在から外し、あらゆる機器をシームレスに同期可能とした。
●アップル~クリエイティブな形で想像力がはぐくまれ、応用され、実現される場所であり、世界一の価値を持つ会社となった。ジョブズ自身も最高・最大の作品と考えている。
そして、著者は最終章に次のように書いています。
「こうしてスティーブ・ジョブズは、まず間違いなく100年あとまで記憶に残る経営者となった。エジソンやフォードに並ぶ人物として歴史にその名が残るはずだ。詩心とプロセッサーのパワーを組み合わせ、ジョブズは誰よりも多く、まったく新しい製品を生み出した。職場に刺激と同じくらい動揺をもたらすほどの獰猛さで、ジョブズは世界一クリエイティブな会社を作り上げた。そのDNAに、デザイン感覚や完璧主義、想像力を組み込み、今後何十年にもわたり、芸術と技術の交差点で栄え続けるに違いない会社に仕立てたのである」
「最後にもうひとつ・・・・・」というのは、新製品を発表する際のジョブズの口癖でしたが、それにならって、著者は本書の「最後にもうひとつ・・・・・」として、数々のジョブズ語録を巻末で紹介しています。その中で、わたしの心に強く残った言葉は次の2つでした。
1つ目は、次のような言葉です。
「文系と理系の交差点、人文科学と自然科学の交差点という話をポラロイド社のエドウィン・ランドがしてるんだけど、この『交差点』が僕は好きだ。魔法のようなところがあるんだよね。イノベーションを生み出す人ならたくさんいるし、それが僕の仕事人生を象徴するものでもない。
アップルが世間の人たちと心を通わせられるのは、僕らのイノベーションはその底に人文科学が脈打っているからだ。すごいアーティストとすごいエンジニアはよく似ていると僕は思う。どちらも自分を表現したいという強い想いがある。たとえば初代マックを作った連中にも、詩人やミュージシャンとしても活動している人がいた。1970年代、そんな彼らが自分たちの創造性を表現する手段として選んだのが、コンピュータだったんだ。レオナルド・ダ・ビンチやミケランジェロなどはすごいアーティストであると同時に科学にも優れていた。ミケランジェロは彫刻のやり方だけでなく、石を切り出す方法にもとても詳しかったからね」
もう1つは、次のような言葉です。
僕がいろいろできるのは、同じ人類のメンバーがいろいろしてくれているからであり、すべて、先人の肩に乗せてもらっているからなんだ。そして、僕らの大半は、人類全体になにかをお返ししたい、人類全体の流れになにかを加えたいと思っているんだ。それはつまり、自分にやれる方法でなにかを表現するってことなんだ――だって、ボブ・ディランの歌やトム・ストッパードの戯曲なんて僕らには書けないからね。僕らは自分が持つ才能を使って心の奥底にある感情を表現しようとするんだ。僕らの先人が遺してくれたあらゆる成果に対する感謝を表現しようとするんだ。そして、その流れになにかを追加しようとするんだ。そう思って、僕は歩いてきた」
この2つの発言から感じるのは、ジョブズの持っていた「人類的視点」とでも呼ぶべきものです。自らの仕事について「宇宙に衝撃を与えている」と語ったジョブズですが、「人類的視点」を超えて、さらには「宇宙的視点」の持ち主だったのかもしれません。
そのような巨大なスケールの発想から、ジョブズはどのような死生観に至ったのでしょうか。その答えは、本書の最後に次のように書かれています。
「日の光がさんさんと降り注ぐとある午後、ジョブズは自宅の裏庭に座り、つらい体調に耐えながら死について考えていた。40年近くも前に行ったインドでの経験、仏教を学んだこと、輪廻や精神の超越性に対する考えなど、さまざまな話をしてくれた。
『神を信じるかと言われれば半々というところだね。僕は、目に見えるものだけが世界ではないはずだとずっと思ってきた』
死に直面し、来世があると信じたい気持ちが強くなっているのかもしれないともわかっている。
『死んだあともなにかが残るって考えたいんだ。こうしていろいろな体験を積んで、たぶん、少しは知恵もついたのに、それがふっと消えてしまうなんて、なんだかおかしな気がする。だから、なにかが残ると考えたい。もしかすれば自分の意識が存続するのかもしれないって』
長い沈黙が訪れた。
『でも、もしかしたら、オン・オフのスイッチみたいなものなのかもしれない。パチン!その瞬間にさっと消えてしまうんだ』
ゆっくりと薄い笑みが広がる。
『だからなのかもしれないね。アップルの製品にオン・オフのスイッチをつけたくないと思ったのは』」
正直言って、本書が優れた伝記であるかどうかは意見の分かれるところだと思います。スティーブ・ジョブズは死去したばかりですし、彼はあまりにも有名人でした。
本書に書かれている多くのエピソードも、ジョブズやアップルのファンなら誰でも知っていることばかりです。レアな人物の伝記を書くことの難しさを思い知らされますが、最後のくだりだけは間違いなく名文であると思いました。
本書には多くの写真が掲載されていますが、わたしが一番好きなのは、2010年にジョブズが来日したときに愛娘のエリンと京都の金閣寺で一緒に写っている写真でした。そこには、愛する娘の肩を抱いて微笑む1人の幸せそうな父親の顔がありました。その表情は、遠くに離れてしまったわが子をやっと見つけたニモの父親のようでした。
発想においては「different」であり続けたジョブズが、父親としては「same」だったことを知り、なんだか温かい気持ちになりました。
iPodが大好きでいつも手放せない上に、ピクサー映画(特に「ファインディング・ニモ」)をこよなく愛する長女にも、いつか本書を読んでほしいと思います。
