- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.1872 宗教・精神世界 | 心霊・スピリチュアル 『ポップ・スピリチュアリティ』 堀江宗正著(岩波書店)
2020.05.09
延長された「緊急事態宣言」を「読書宣言」と陽にとらえて、大いに本を読みましょう!
『ポップ・スピリチュアリティ』堀江宗正著(岩波書店)を読みました。「メディア化された宗教性」というサブタイトルがついています。著者は、1969年生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科附属死生学・応用倫理センター准教授。死生学、スピリチュアリティ研究。2000年、東京大学大学院人文社会系研究科宗教学宗教史学博士課程満期退学。博士(文学)。聖心女子大学文学部准教授を経て現職。著書に、一条真也の読書館『スピリチュアリティの行方』で紹介した本などがあります。
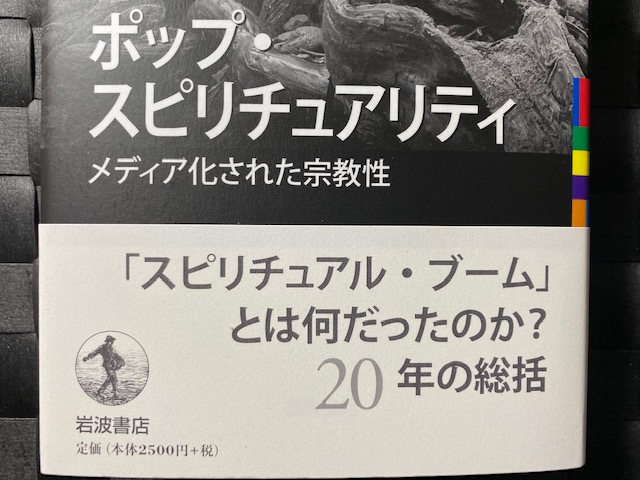 本書の帯
本書の帯
本書のカバー表紙には、パワースポットらしき注連縄が巻かれた大木の写真が使われ、帯には「『スピリチュアル・ブーム』とは何だったのか? 20年の総括」と書かれています。
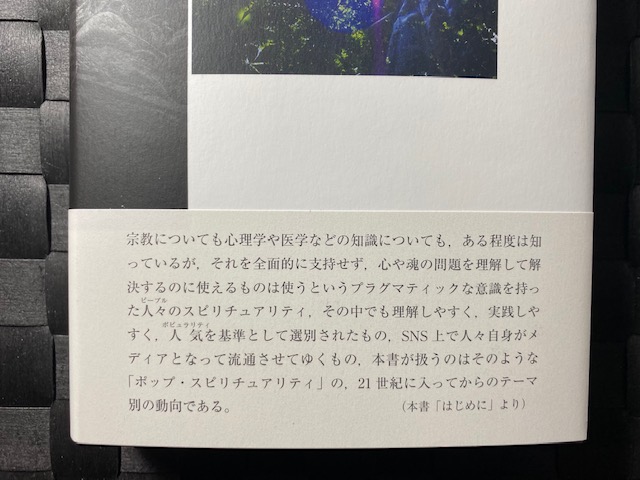 本書の帯の裏
本書の帯の裏
本書の帯の裏には、以下のように書かれています。
「宗教についても心理学や医学などの知識についても、ある程度は知っているが、それを全面的に支持せず、心や魂の問題を理解して解決するのに使えるものは使うというプラグマティックな意識を持った人々のスピリチュアリティ、その中でも理解しやすく、実践しやすく、人気(ポピュラリティ)を基準として選別されたもの、SNS上で人々自身がメディアとなって流通させてゆくもの、本書が扱うのはそのような『ポップ・スピリチュアリティ』の、21世紀に入ってからのテーマ別の動向である」
また、カバー前そでには、以下の内容紹介があります。
「アカデミックな『スピリチュアリティ』は定着せず、霊を信じる『スピリチュアル・ブーム』が起こったが、バッシングを受けて衰退した。このような見方に本書は再考を迫る。それはグローバルに同時多発するスピリチュアリティの日本的な現象にすぎない。『前世療法』の体験談から探る現代の輪廻観。『パワースポット』でパワーが体験される仕組み。ライトノベル、アニメ、SNSなど『サブカル』を操っている『魔術師』たち……。『ブーム』を超えて東日本大震災の後も拡散と深化を続ける、その各メディアでの展開を緻密に読み解く」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
第1章 スピリチュアリティとは何か
――概念とその定義
第2章 2000年以後の日本における
スピリチュアリティ言説
第3章 メディアのなかのスピリチュアル
――江原啓之ブームとは何だったのか
第4章 メディアのなかのカリスマ
――江原啓之とメディア環境
第5章 スピリチュアルとそのアンチ
――江原番組の受容をめぐって
第6章 現代の輪廻転生――輪廻する”私”の物語
第7章 パワースポット現象の歴史
――ニューエイジ的スピリチュアリティ
から神道的スピリチュアリティへ
第8章 パワースポット体験の現象学
――現世利益から心理利益へ
第9章 サブカルチャーの魔術師たち
――宗教学的知識の消費と共有
「参考文献」
「あとがき」
「はじめに」で、著者は以下のように述べています。
「日本では1970年代から『宗教』団体の外で個人主義的な宗教文化的資源の消費が始まる。それは、オカルト、精神世界、ニューエイジなどと呼ばれてきた。95年のオウム真理教地下鉄サリン事件を経て、下火になるかと思いきや、2000年代にはテレビ・書籍を中心に『スピリチュアル・ブーム』が起こる。そのピークはだいたい2007年あたりで、江原啓之がテレビ出演を中止した後に衰退したと思われている。しかし、実際にはテレビなどのマス・メディアを素通りしているだけである。出版やネット・ユーザーの動向を見る限り、東日本大震災以後にも関心の盛り上がりが見られる。インターネット、SNSなど、従来とは異なるメディアを通じて拡散と深化は続いている。それは、人々自身がメディアとなって情報を伝え合うという新しい状況に根ざしている。一方、インターネットは激しい論争が繰り広げられる場所でもある。『スピリチュアル』という言葉は『虚偽・詐欺・軽信』というイメージで批判されるようになり、当事者は『スピリチュアル』という言葉を使用するのを避けるようになっている」
著者によれば、「スピリチュアリティ」という言葉を比較宗教・比較文化的な分析概念として使用し、グローバルに起こっているスピリチュアリティをめぐる動きのなかで日本の状況をとらえてみようというのが本書の狙いであるといいます。著者は、「宗教はもともとメディアであり続けた。とくに近代以降の宗教は、書物を通じて同一の内容の教えを共有し、伝えるメディアになろうとした。また信者になることは、布教を通して自分自身がメディアになることであった。そのあとになっているのは、同一の意味内容を保持する書物というメディアのメタファーである。だが、キリスト教の聖書も仏教の経典も、元をたどれば口コミや伝承の世界に根ざしている。そこから立ち上がって、抽象的な概念や教義を作り上げてきたのが『宗教』である。それは、もっと大きな人類の歴史のなかでは極めて特殊なものである」と述べます。
また、著者は「『宗教』を相対化し、宗教ではないけれど、何か自分にとって大切な価値観を表明し、伝えようとする人々がいる。そのような人々が日々に更新し続けているポップ・スピリチュアリティの世界は、現代的な現象ではあるが、むしろ文字以前の、つまり『宗教』以前の人々の精神生活の有様に近いものであるかもしれない。そこには科学的に誤った信念や倫理的に不適切な行動が含まれているかもしれない。しかし、『宗教』に比べれば流動的であり、公的に議論することで正されると期待できる」とも述べています。
第1章「スピリチュアリティとは何か――概念とその定義」では、本書が現代日本におけるスピリチュアリティに関わる様々な文化現象を扱うことが示され、日本では、「オカルト」「精神世界」「ニューエイジ」「スピリチュアル(名詞的用法)」などと言葉が移り変わり、指示される現象の強調点も移り変わることを指摘して、著者は「こうした用語の乱立を踏まえ、これらを広く括るために島薗進は『新霊性運動』『新霊性文化』という分析概念を提唱し、やがてカタカナ語の『新しいスピリチュアリティ』を使用するようになる。筆者もこれにならい、当事者の自称とは別に比較宗教学的な分析概念として『スピリチュアリティ』を使うことにする」と述べています。一方、このスピリチュアリティ概念を使用するにあたっては、もともとのキリスト教的な文化的背景、英語圏での用法の歴史、学術的背景を踏まえる必要があるとして、「特に概念構築に貢献してきたのは心理学で、後に宗教社会学に取り入れられた」と指摘しています。
第2章「2000年以後の日本におけるスピリチュアリティ言説」では、6「マス・メディアにおける『スピリチュアル』」として、「スピリチュアル・カウンセラー」として一世を風靡した江原啓之を取り上げ、「江原のユニークさとは、片仮名語の使用による『ファッショナブル』な印象、トラウマ指向心理学の援用、伝統的な霊信仰への根づきと刷新、メディアを介した消費主義との結びつきとしてまとめられる。知識人の片仮名スピリチュアル/スピリチュアリティの使用は、伝統的な霊信仰からの決別を含意していたが、江原はよりポピュラーなレベルで根深い霊への関心を引きつけつつ、トラウマ心理学的な語彙を用いて、伝統的外観から離脱し、『癒し』と同等の成功を、ほぼ独力で成し遂げたのである」と述べています。
また、7「根強い『霊』への関心」として、著者は「確固たる霊信仰ではないとしても、霊への関心は、ポピュラーなレベルで、特に低年齢層を中心に根強く続いていた」と指摘し、「それは信仰というよりは、『学校の怪談』などの現代民話や都市伝説という物語の形をとって伝達されている。他方、オウム事件以後、知識人とマス・メディアは、霊的なものを宗教的なものとして遠ざけてきた。知識人は『霊』という言薬を取り除いた片仮名の『スピリチュアリティ』を好み、『無宗教』と自覚する末期患者(高齢者が多いと思われる)のスピリチュアル・ケアにも対応してきた。しかし、それではより若い大衆の霊への関心には十分に応えられない」と述べています。
続いて、著者は、近年の高齢者が「霊」を信じず、逆に若者の方が信じている傾向については、各種の世論調査でも確かめられているとして、「その間隙を埋めたのが、江原啓之の、『スピリチュアル』であった。江原はポップ・スピリチュアリティ領域における霊への関心に応えつつ、トラウマ指向の心理学の知見を積極的に取り入れ、霊信仰を片仮名語の『スピリチュアル』でイメージ・アップし、マス・メディアに載りやすいものへと作り替えた」と述べます。
さらに、8「日本人の無宗教の宗教性」として、著者は以下のように述べています。
「日本人の多くが無宗教となったのは、自然なことではなく、江戸幕府、明治政府以来の宗教政策によるところが大きい。そこでは、『宗教』は、政府によって管理・統制されるべきものとして社会的に位置づけられてきた。また、生業と結びついた年中行事や、イエと結びついた通過儀礼・葬送儀礼も、社会習俗として位置づけられたため、日本人の多くはそれを『宗教』と見なさない。だが、それらの儀礼や人々の信念のなかには、死者に対する敬慕の念、自然への恐れや感謝などが入り込んでいる。それは、死者の霊や自然に息づくエネルギーやパワーへの関心とさほど距離がない」
そして、9「スピリチュアリティのゆくえ」として、著者は「『無宗教の宗教心』を育んだ伝統行事・儀礼の基盤であった氏子や檀家の結束が薄れると同時に、有名社寺がますます人を集め、財力を蓄え、不特定の個人向けの行事を拡大する傾向は、2010年代に入るとパワースポット・ブームや御朱印集めの形を取って、ますます顕著となる。『伝統的』と認知された宗教的実践は、新しい宗教運動に警戒を抱く人々にも受け入れられやすい。特定の信仰を強制しない修行への自由な参加という形態は、スピリチュアリティに関心を持つ人々を広く引きつけるだろう」と述べるのでした。
第3章「メディアのなかのスピリチュアル――江原啓之ブームとは何だったのか」では、3「テレビ番組の相談事例から――スピリチュアル・カウンセリングの構造」として、著者は「江原のスピリチュアル・カウンセリングは、霊観念を介在させているにもかかわらず、通常の心理学的カウンセリングと多くの共通性を有することが分かった」と述べます。その構造をまとめると、(1)霊視(シッティング)により、相談者は江原に急速に信頼を寄せるようになる。(2)問題の遠因を過去の失敗や喪失や被害に求める。(3)問題を問題として感じている相談者の認知そのものを変え、本来的には善なる性質が逆説的に問題を悪化させ、固定化していることを指摘する。(4)その善なる性質を、守護霊の性質と結びつけることによって、相談者が孤独ではなく、問題解決能力を潜在的に持っているということを示す。そして著者は、これらの構造は「臨床心理学では順番に、ラポールの形成、トラウマ理論への依拠、リフレーミング、エンパワーメントなどと呼ばれるものに近い」と指摘します。
さらに、「筆者は、江原を決して特別視するつもりはなく、熟練の宗教家や評判の良い占い師は、その時代の心理療法的な技法に関心を持ったり、あるいは経験にもとづいて無自覚に実現したりしていることが多いと考える。とはいえ、宗教的治療者の多くは、宗教的な病因論や儀礼的な治療法を前面に押し出すことが多い。ところが、江原の場合は、総じて心理学的な病因論に依拠する比率が高く、時おり浄霊や除霊もおこなうが、最終的には相談者本人の自覚と決断に問題解決をゆだねることが多い」と述べ、江原が書籍では「ガイド役」、テレビでは「カウンセラー」というイメージを自ら演出していることは「呪術的実践による直接的援助より、霊的な世界観や価値観の伝達による自立的成長の間接的支援を重視していることを示唆する」と指摘しています。
4「江原の思想の特徴――霊的真理の八つの法則」では、著者は、江原と宗教との関係性について述べています。
「江原は、自らをスピリチュアリストとし、宗教と一緒にされたくないと考えているようだが、日本の新宗教にはもともと神霊との交流をおこなうシャーマニズム的な要素がある。その一つである大本教から別れた浅野和三郎が日本にスピリチュアリズムを紹介したという経緯もある。そして、それが再びGLAや幸福の科学などのより新しい新宗教(新新宗教と呼ばれることもある)に流れこんでゆく。こうした『霊界』観念を軸とする宗教思想の発展のなかに、江原の思想は位置づけられる。これらの教団の信者は、江原の教えにさほど違和感を抱かないだろう(実際、筆者は新宗教の男性幹部の妻が江原のファンとなって幹部が困惑する話はよくあると、複数の教団関係者が集まる場で聞いたことがある)」
7「ブームのゆくえ――スピリチュアリティ言説の状況から」では、人々と具体的に関わらずにメディアを介してのみ情報を伝達する「心理―霊」的なカリスマという「江原モデル」は、「カルトはバッシング、オカルトはブーム」という日本のメディア状況と、「霊を信じるが無宗教」という層に適合的であったと指摘し、著者は「この成功例により、今後も同様のカリスマが登場する可能性がある。反オカルト論者も巻き込んで、透明性と共通言語が本当に成立すれば、霊に関するビジネスには自浄作用が働き、社会的信頼が高まるかもしれない。だが、これはメディア主導のスピリチュアル・ビジネスが、『宗教』を圧殺し、新しい宗教とデなることの予兆かもしれない。そこで提供されるのは、最終的な真偽にこだわらず、役に立つかどうか、面白いかどうか、日常生活をおびやかさないかどうかという条件をクリアした情報のみである。若年層における都市伝説の流通、メディアにおける占いの定着、古くから存在するがますます高まりを見せるファンタジー人気、そして本章で取り上げた江原ブームなどは、その好例と言える」と述べます。
続けて、著者は以下のように述べています。
「ポストモダンとも呼ばれる価値観や信念の多様化・流動化・相対化した社会においては、このようなプラグマティズム的な信念、あるいは(社会性を欠く場合)コミットメントなき信念が主流となる。それが、欧米では『スピリチュアルだが宗教的ではない』個人、日本では『霊を信じるが無宗教』という一般的態度、これらを総称するなら理解しやすさ、実践しやすさ、人々の支持を特徴とするポップ・スピリチュアリティとして表面化していると言えるだろう。いずれもプラグマティズム的な信念のあり方である以上、宗教のような『最終的な解決』は期待できないし、人々もはじめから期待しない。ブームは作り出され、使い果たされてゆく。そのなかで、一部の人々は、一時的な現実逃避を繰り返すようになるかもしれない。江原自身の『霊的真理』を広めたいという真剣な意欲と、江原ブームの置かれている文脈とのギャップは著しい。しかし、彼自身、どこかでその半端さや矛盾や欺瞞を感じながら、それに乗っているのである」
第4章「メディアのなかのカリスマ――江原啓之とメディア環境」では、5「テレビ『天国からの手紙』――ミディアム・ヒーラーとして」で、著者は、年に2回ほどの特別番組として2004年からフジテレビ系列で放送された「江原啓之スペシャル 天国からの手紙」を取り上げ、江原は、霊視や霊言を介して、遺族にしか分からない事実を言い当て、死者の言葉として整合するようなメッセージを伝える。遺族は、驚きながらリアリティをもってそれらを受け止めている。また、『グリーフ・ケア』という用語が紹介されていることから、死別の悲嘆に関する心理学的知見を江原が意識していることがうかがえる。除霊や浄霊を常とする霊能者の呪術的・宗教的救済とは異なり、相談者本人が悲嘆から回復するのを助ける心理的な癒しが目指されている。自らの存在意義を見失ってしまった遺族が故人との絆を再確認することで生きる意味を取り戻すのを助けるという実践は、東日本大震災の被災者に対する宗教者によるスピリチュアル・ケアとも近い。しかし、遺族を癒すのが江原の伝える死者のメッセージそのものだという点は、グリーフ・ケアやスピリチュアル・ケアの域を超えている。遺族の自責の念は『誰も悪くない』という死者のメッセージによって癒され、死別後の孤独は、実は死者が語りかけていたという光景に置き換えられる。そうして、見えなくなっていた家族の絆がリアルに思い描かれる」と述べています。この著者の指摘は非常に的確かつ重要であると思います。
そして、第5章「スピリチュアルとそのアンチ――江原番組の受容をめぐって」の冒頭を、こう書きだしています。
「1970年代のオカルト・ブーム以来、超常現象や心霊現象を扱ったテレビ番組はある一定の視聴率を稼ぎ、テレビの世界でその存在価値を認められてきた。とはいえ、それは恒常的な地位を占めていたわけではない。むしろ、ブームと衰退を繰り返してきたと言ってよい。たとえばユリ・ゲラーや宜保愛子など、人々を引きつける存在が現れる。番組制作側は、彼らが視聴率を稼ぐことを確認すると、彼らを繰り返し出演させる。それに伴って知名度が上がると、懐疑派から批判が続出する。台頭してはバッシングを受け、衰退する。それがいわゆる『オカルト番組』、超常現象を扱う番組がたどる運命であった。それはまるでモグラ叩きのように、アンダーグラウンドにあったものが表に出ると一斉に叩かれるという図式である」
これは、わが国におけるオカルト・ブームの構図を見事に説明しているように思います。
第6章「現代の輪廻転生――輪廻する”私”の物語」では、「スピリチュアリティと死生観」として、「輪廻」の問題が取り上げられます。著者は「輪廻は、日本では仏教由来の伝統的死生観として考えられがちだが、実は葬式仏教の先祖祭祀とは矛盾する」としながらも、「輪廻と先祖祭祀の矛盾を処理する方法はいくつかある。1つは、分裂した信念体系を使い分け、矛盾を自覚しないというものである。もう一つは、死者はしばらく生まれ変わらないと考え、記憶のある近親者のみを追悼すること(メモリアリズム)である。しかし、祖霊の系列を真剣に祀る先祖祭祀からは離れる。先祖祭祀の立場から輪廻を統合するものとしては、先祖は仏になった死者である(浄土へ往生、あるいは追善供養を経て成仏)という観念がある。この場合、六道輪廻は成仏しない死者に限定される。仏教の教理を表面上は保持しているが、このような輪廻の局限化は、死んですぐに仏になって生まれ変わらないと考えるのであれば、実質的な無効化に等しい」と述べています。
著者は、論理的にもっとも整合的な融和策は民俗的輪廻観とでも言うべきものであるとして、「ラフカディオ・ハーンは、1896年の時点で、日本人には西洋流の薄くて透明で内側に宿っている個性ある『霊 ghost』の観念がないと書いている。西洋流の『自己』とは、仏教においては無数の前世 preexistenceの行為と思念との総計であるカルマ(業)が作る幻想 illusionsの一時的合成体であり、神道においても複数の死者の霊(=神、祖先)の集合体である。それを若い学生から教育のない最貧層の百姓までもが信じている、と記述している。このことから、ハーンの観察する当時の日本人は、自分が複数の前世ないし祖霊の集合体からの生まれ変わりであるという死生観を持っていたことが分かる。このような死生観であれば、先祖祭祀と輪廻の矛盾は解消されるだろう」と述べています。
さらに著者は、日本民俗学の創始者である柳田國男の死生観に言及し、以下のように述べています。
「時代を下って、柳田國男は六道輪廻の思想は日本にはなく、死者の霊が浄化されると大きな霊体、『神』と呼ばれるものと一体化して個性をなくし、以前の個性のままでは生まれ変わらないとした。その一方で、床下に小児の墓を設けて生まれ変わりを早めようとする事例、子どもと故人の類似性を取り上げて「この児は誰さんの生まれ替りだ」などと観念する事例から、『必ず同一の氏族に、また血筋の末にまた現われると思っていたのが、わが邦の生まれ替りだったかと』推測している。イエの先祖や氏神などと呼ばれる祖霊集団にいったん融合して、そこから生まれ変わるという、イエを基体とする輪廻観である。この輪廻観なら先祖祭祀と両立可能である」
著者は「もとより日本人の死生観を1つに代表させることはできない」として、「インド起源の輪廻の説話が文字通り信じられていたとは言えない。貴族の輪廻の観念がどの程度民衆に広まっていたか定かでない。輪廻を無効化した死後即成仏の観念や先祖祭祀も、寺請制度やイエ制度に適したものであり、日本史を一貫した普遍的なものとは言えない。民俗的輪廻観/祖霊観/他界観も、普遍化するには根拠が薄い。むしろ異なる死生観が多元的に並存し、時代・地域・階層によって強調点が移動するというのが、日本人の死生観の現実であろう」と総括しています。
また、「20世紀の輪廻転生観」として、著者は超能力者として知られたエドガー・ケイシーの思想などに触れた後で、「現代のスピリチュアリティの領域でもっとも影響力があり、頻繁に引用・参照されるのは、精神科医ブライアン・ワイスの『前世(退行)療法』だろう。これは、退行催眠によって前世を想起し、現世の問題を解決するという療法である。前世の状況、その死から光あふれる中間世への移行、『マスター Master』(現在は肉体のなかにいない高度に進化した霊)との出会い、現世への計画的な誕生の有り様が、催眠中のクライエントの口から語られる」と述べています。「マスター」という言葉については、「神智学その他を介して広くニューエイジで流通している言葉で、輪廻をやめて昇天(次元上昇)した霊を指すことが多いが、ワイスの本に出てくる『マスター』たちは、浄化されてはいるが完全に輪廻をやめた存在ではないようである」と説明します。
第7章「パワースポット現象の歴史――ニューエイジ的スピリチュアリティから神道的スピリチュアリティへ」では、1「1980年代のパワースポット――天河神社の登場」として、一条信也のハートフル・ブログ「天河大弁才天社」で紹介した神社が取り上げられます。そして、「バク転神道ソングライター」こと宗教哲学者の鎌田東二氏が登場します。著者は、天河の名を世に広めた宗教学者として鎌田氏を紹介し、「鎌田は、パワースポットとしての天河を見出し、積極的に評価し、その地位を固めた立役者と言っても過言ではない。また、鎌田は天河との関わりを通して、彼自身の宗教学的な聖地論を形成し、それによって天河を世界各地の聖地とつなげる視点を提示した」と述べています。
また著者は、「宇宙船の船長」こと天河神社の柿坂神酒之祐宮司にも言及しながら、「鎌田の宗教論は、神道に属する神社という日本固有のスピリチュアリティと関わりのある聖地の評価を含むが、他の国や地域の聖地をも同様に評価するため、必ずしも排他的なナショナリズムにならない。たとえば、鎌田は柿坂の『神社は宇宙船なり』という言葉を引き、またメイソンJ.W.T.Masonの『神ながらの道』を参照しながら、神社は『神霊の乗り物』であり、『自然の霊性・万物の霊性・宇宙の霊性と交通する回路』であり、『バリの聖地やアメリカ・インディアンの聖地やケルトの聖地とつながっている』という。したがって、鎌田にとって、神社とは地球上の数々の『聖地』の一形態でしかない」と述べています。
続けて、著者は鎌田氏の聖地論について、「それでは聖地とは何であるか。鎌田は、アメリカ・インディアンの聖地を精査した環境心理学者であるスワンJ.Swanを参照し、聖地とは『人間を[他の場所より]ずっと容易に霊的な意識状態へ導く力を持って』おり、『浄化・治癒・変容・洞察が生起するような場所』と規定する。また、ゲーテJ.W.GoetheやシュタイナーR.Steinerなど、ドイツのロマン主義と神秘主義の思想家を頻繁に参照し、山頂の岩は地球が生成する始原の光景を幻視できる場所であり、地球と直接つながる場所であり、それが神道においては奈良県の三輪山のように神の降りる岩座として特別視されると考える」と説明しています。
さらに、著者は鎌田氏の聖地論について、「そのような聖地に行くことを通して、人間は天と地の媒介となることができる。鎌田はそのことの例証として、モーセがホレブ山で神に『裸足になれ』と命じられたことを引用する。このように彼が天河神社をはじめとする日本の様々な神社を評価するのは、神道という宗教の施設だからではなく、宗教を超えた霊性との交流を可能とするチャンネルだからである。鎌田の天河論と聖地論には、神道的スピリチュアリティの再評価という面と、世界各地の聖地に地球と宇宙の神々を媒介する機能を見出そうとする同時期のニューエイジ的スピリチュアリティの反映という面の両方がある。それはこの時期のパワースポット論が神道には偏っていないということを示す」と述べるのでした。
 『開運! パワースポット「神社」へ行こう』
『開運! パワースポット「神社」へ行こう』
6「神道的スピリチュアリティとナショナリズム」として、著者は「日本ではパワースポットは仏教ではなく神道と強く関係づけられる。仏教は、欧米では宗教よりもスピリチュアリティに近いが、日本ではむしろ既成宗教の一つである。神道、とくに鎌田東二のような思想家たちが創造的に定式化した古神道が日本のニューエイジにおいて占める位置は、欧米におけるネオ・ペイガニズムや先住民のスピリチュアリティの位置に相当する。これらは世界宗教以前の古代のスピリチュアリティを表象するものと考えられている。実際、ヨークは日本の神道をその自然崇拝ゆえにペイガニズムの1つと見なしている。他方、神道は組織宗教であり、戦前においては権威主義的な教えと強力な天皇崇拝とともに、国民を戦争に導いてきた。それは権威主義的な宗教組織を嫌うニューエイジャーにとって受け入れがたいはずだ」とも述べています。ちなみに、わたしは『開運! パワースポット「神社」へ行こう』(PHP文庫)という本を監修しました。
本書の版元は岩波書店です。著者は「あとがき」で、岩波書店から出版された類書としては、著者自身の書である『スピリチュアリティのゆくえ』(2011)、島園進著『スピリチュアリティの興隆――新霊性文化とその周辺』(2007)、リゼット・ゲーパルト『現代日本のスピリチュアリティ――文学・思想に見る新霊性文化』(2013)などを紹介しています。島薗氏の著書には『現代宗教とスピリチュアリティ』(2012、弘文堂)もあります。
これらの先行研究を紹介した後で、著者は「本書は、内容も論調もこれらの系譜上に位置づけられる。まず宗教学の立場から書かれていること、宗教と関わりつつそれと距離をとろうとする『スピリチュアリティ』を扱っていること、日本を主な対象としているがグローバルな視野を持っていること、ポピュラー文化から政治的意味にわたる広い領域に目配りしていること、スピリチュアリティを賛美も非難をせず多角的にとらえようとしていることなどである。だが、これらの類書はどちらかと言えば、知的な言説の分析に傾きがちである。本書の特色は、よりポピュラーな次元でのスピリチュアリティをとらえ、インターネット時代のスピリチュアルな個人のあり方に迫ろうとする点にある」と述べています。
本書には、島薗進先生や鎌田東二先生といった、日頃からわたしが師事している方々も登場しており、興味深く読むことができました。一条信也の読書館『バラエティ化する宗教』、『オカルト番組はなぜ消えたのか』で紹介した本などのテーマとの共通性も観られましたが、本書の分析はさらに鋭いと感じました。特に、江原啓之についての考察が秀逸でした。本書は「スピリチュアリティ」について総合的に考える最適のテキストであると思います。