- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.1876 プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『永遠の最強王者 ジャンボ鶴田』 小佐野景浩著(ワニ・ブックス)
2020.05.15
5月13日は、ジャンボ鶴田の20回目の命日でした。その日に発売され、その日のうちに読了した『永遠の最強王者 ジャンボ鶴田』小佐野景浩著(ワニ・ブックス)をご紹介いたします。ソフトカバーながら592ページの大著ですが、一気に読みました。それにしても、命日に評伝本が出されるのは、故人にとって最高の供養ですね。
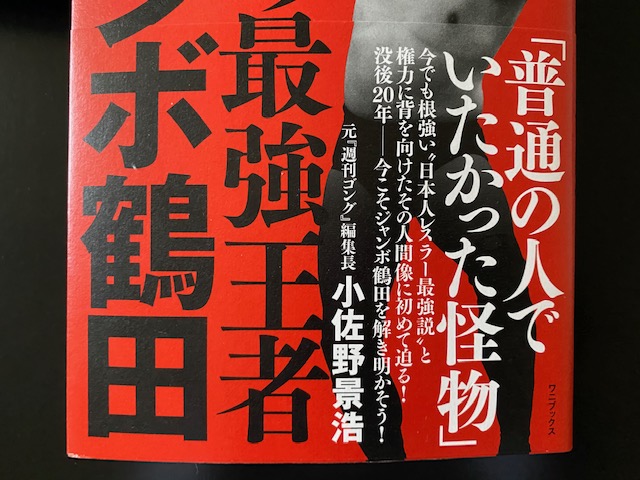 本書の帯
本書の帯
カバー表紙には、往年のジャンボ鶴田のリング上の雄姿の写真が使われ、帯には「普通の人でいたかった怪物」と大書され、「今でも根強い〝日本人レスラー最強説〟と、権力に背を向けたその人間像に迫る!没後20年――今こそジャンボ鶴田を解き明かそう!」「元『週刊ゴング』編集長 小佐野景浩」と書かれています。
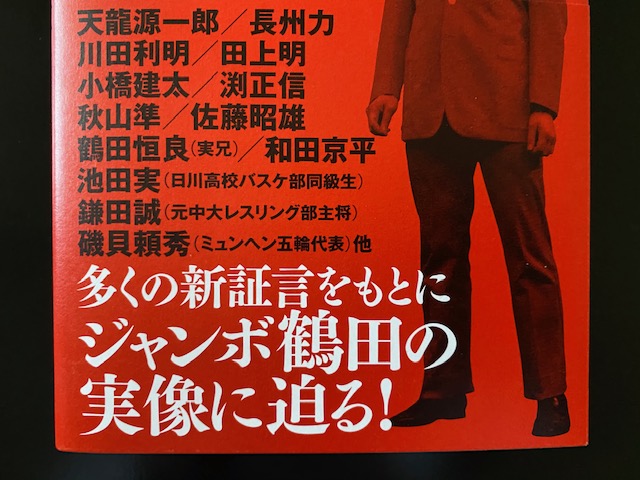 本書の帯の裏
本書の帯の裏
また、カバー前そでには「鶴田の何が凄かったのか、その強さはどこにあったのか、最強説にもかかわらず真のエースになれなかったのはなぜなのか、総合的に見てプロレスラーとしてどう評価すべきなのか――などが解き明かされたことはない。もう鶴田本人に話を聞くことはできないが、かつての取材の蓄積、さまざまな資料、関係者への取材、そして試合を改めて検証し、今こそ〝ジャンボ鶴田は何者だったのか?〟を解き明かしていこう――」という、著者よりのメッセージが記されています。
本書の「目次」は、以下の通りです。
「はじめに」
第1章 最強の原点
第2章 ミュンヘン五輪
第3章 エリート・レスラー
第4章 驚異の新人
第5章 馬場の後継者として
第6章 逆風
第7章 真のエースへの階段
第8章 覚醒
第9章 鶴龍対決
第10章 完全無欠の最強王者
第11章 そして伝説へ
「おわりに」
「はじめに」では、幼少の頃からプロレスファンだったという著者が「怖くて、強いという従来のプロレスラーのイメージとは違い、鶴田は爽やかで明るく、当時の日本の子どもが憧れていたアメリカの自由な空気感をまとっていた。デビュー早々に4種類のスープレックスを華麗に操り、196cmの長身を生かしたダイナミックなドロップキックは驚きだった。アントニオ猪木が好きだった私でも『若くてカッコいいな!』と理屈抜きに鶴田ファンになった」と述べています。
鶴田は豊かなポテンシャルを感じさせながらも、本気で怒らない、必死になる姿を見せないと批判も浴びてきました。しかし、著者は以下のように述べます。
「本人は『いやいや、そんなことはありませんよ』と否定するかもしれないが、天龍と相対した時、三沢光晴らの超世代軍と相対した時には明らかに本気で怒り、時にジェラシーの炎を燃やした。それが怪物的な強さを生んだ。そしていつしかジャンボ鶴田日本最強説が生まれた。だが、鶴田の何が凄かったのか、その強さはどこにあったのか、最強説が根強いにもかかわらず真のエースになれなかったのはなぜなのか、総合的に見てプロレスラーとしてどう評価すべきなのか――などが解き明かされたことはない」
それを解き明かすために、本書は書かれたのです。
本書の冒頭には、鶴田友美(後のジャンボ鶴田)の少年時代が描かれていますが、「朝日山部屋入門事件」というのは初めて知りました。1964年の夏、中学2年生だった鶴田少年は大相撲の朝日山部屋に入門させられたそうです。相撲好きの親戚に連れられて東京見物に行った際に体験入門させられ、自覚のないまま新弟子検査に合格したというのですが、本人の意思ではなかったために夏休みが終わると故郷に戻りました。しかし、地元の人々は「相撲の稽古が辛くて逃げ帰ってきたらしい」「身体は大きくても根性なしだ」と陰口を叩いたとか。それで鶴田少年は「オリンピックに出て、陰口を叩いていた人間を見返してやる!」と思ったとか。それが高校、大学でのバスケットボール、アマレス、最終的にはプロレスに到達することになるのでした。
日川高校に入学したとき、鶴田少年の身長はすでに192cmだったそうです。バスケットボール部に入部し、エースになりました。さぞかし女子にモテたのではないかと思いますが、思春期の少年にとって大きいことはコンプレックスだったようです。鶴田の同級生の池田実氏は「やっぱり大きすぎるという劣等感があったんですよ。ホントに嫌がってましたよ。そりゃあ、目立ちますよね。あれだけ目立てば注目の的ですよ。みんな好奇の目で見ますわ、あの頃は。常に人から見られていたらかなわないですよ。それから、ちょっと吃音があるというのもあったんですよ。なかなか上手くしゃべれなかったんですよね。仲良くなってしまえば大丈夫なんですけど、親しくなるまで、ちょっとナイーブというか」と述懐しています。ルー・テーズや大山倍達などが代表的ですが、格闘技の猛者には吃音がよく見られるようです。鶴田もそうだったとは知りませんでした。
中央大学法学部に入学した鶴田は、バスケットボール部に所属しながら、レスリング部にも出入りするようになります。団体競技であるバスケよりも個人競技の方がオリンピックに出場しやすいと考えたのですが、柔道やボクシングを含む選択肢の中から、最後に残ったのがレスリングでした。中大レスリング部が名門だったことも大きく影響しました。中大レスリング部は多くの五輪メダリストを輩出していますし、鶴田よりも後の世代ですが、桜庭和志や諏訪間もOBです。鶴田はミュンヘン五輪に出場し、グレコローマン100kg以上級に参加しましたが、12選手が参加した中で1勝もできませんでした。当時のレスリング重量級の世界の壁は途方もなく高かったのです。
同時代に活躍したレスリングの選手としては、同じ72年ミュンヘン五輪に韓国のフリー90kg級代表(3回戦失格)として出場した吉田光雄(長州力)、76年モントリオール五輪フリー90kg級代表(4回戦失格)、80年モスクワ五輪フリー100kg級代表(日本のボイコットにより不参加)の谷津嘉章がいます。その中で誰が一番強かったのかというテーマは興味深いですが、中大レスリング部主将でアマレス時代の長州に勝ったこともある鎌田誠は「鶴田、長州、谷津の3人を並べたら、谷津が一番強かったんじゃないかな。アマチュアのルールで試合をやったらね」と述べます。
また、ミュンヘン五輪フリー100kg級以上の代表選手だった磯貝頼秀は「時代が違うけど、やっぱり強かったのは谷津ですよね。鶴田は経験が2~3年だから比較したら可哀相だけど。谷津はスタミナもあったし、いい片足タックルも持っていたし、凄く強かった。長州に勝った鎌田さんとか、その時代の人にも勝ち抜いていますから、やっぱり谷津が強かったんじゃないですか?」と述べます。後にプロレス入りして、鶴田と五輪コンビを組む谷津ですが、さすがに「日本アマレス史上最強の男」と呼ばれただけのことはありますね。
鶴田は、五輪出場も就職のための学歴としてとらえていたといいます。大学卒業前の1972年10月31日赤坂プリンスホテルで全日本プロレス入団が発表されました。そのとき、鶴田は「プロレスは僕に最も適した就職だと思い、監督と相談の上、尊敬する馬場さんの会社を選びました」と挨拶しましたが、この発言は非常に有名になりました。著者は、「それまでのプロレス入りは『団体への入門』だったが、鶴田は『会社への就職』と言った。徒弟制度だった日本プロレス界に一石を投じる言葉で、当時のプロレス・マスコミを感心させる一方で、これがのちには『鶴田=サラリーマンレスラー』というマイナスイメージを生むことになってしまう」
全日本に入団した鶴田は、下積みを経験せずにアメリカに送られてデビュー。スタン・ハンセンと一緒に修行しながら、ドリー・ファンク・ジュニアのコーチを受けます。入団記者会見から1年後の73年10月には、馬場と組んでドリーとテリー・ファンクのファンクスが保持するインターナショナル・タッグ王座に挑戦しているのですから、いかに破格の黄金ルーキーだったかがわかりますね。
デビュー以来、鶴田はNWA世界王者をはじめとしたアメリカの強豪たちに胸を借りながら、順調にエリート・レスラーとしての道を歩みます。75年暮れ、全日本は一大イベントを開催します。力道山13回忌追悼&アメリカ建国200年&全日本プロレス創立3周年の記念と銘打った「全日本プロレス・オープン選手権」です。これは、前年74年から馬場に執拗に対戦をアピールし、日本選手権の開催を訴えていた新日本プロレスのアントニオ猪木に対して「門戸を開放するので、参加すれば、貴殿が望む馬場線実現の可能性もあり」という返答でした。
猪木は「馬場と戦うのは日本選手権であるべき。お祭りには参加できない」と拒絶しましたが、国際プロレスのラッシャー木村、グレート草津、マイティ井上をはじめ、大木金太郎、ヒロ・マツダが参加を表明、全日本からは馬場、鶴田、ザ・デストロイヤー、アントン・ヘーシンク、外国人勢はドリー・ファンク・ジュニア、アブドーラ・ザ・ブッチャー、ディック・マードック、ホースト・ホフマン、ドン・レオ・ジョナサン、パット・オコーナー、ハーリー・レイス、ダスティ・ローデス、バロン・フォン・ラシク、ミスター・レスリング、ケン・マンテルといった錚々たるメンバーが参加しました。これは猪木の参加を想定してのものでした。
この大会の発案者は、馬場のブレーンで、鶴田と天龍の全日本入りを手引きしたことでも知られる森岡理右でしたが、「あれが猪木を黙らせようとしてやったこと。『オープン』という名称にしたのは、〝対戦したがっている猪木さんに対してもオープンな姿勢ですよ″という意味だから。それでガチンコの強い連中を集めてね。僕と馬場、原章の3人で〝一番手はホフマン、次にマードック、そしてレイス、よしんば猪木が勝ち上がってきたとしたら、最後はデストロイヤーをあてて……″ってカードを全部考えていた。当時でもデストロイヤーは強かったからね。他にオコーナー、レスリング、ジョナサンといった錚々たる連中がいたわけだから、どうやったって猪木は勝てなかったよ」と語っています。この大会には「ファンが最も観たいカード」の応募企画がありましたが、1位は馬場vs鶴田の師弟対決でした。
若き日の鶴田にとって大きな収穫だったのは、〝人間風車″ビル・ロビンソンと遭遇したことです。鶴田とロビンソンの対決は〝夢のスープレックス対決″として注目されましたが、76年7月17日に北九州市小倉の三萩野体育館(!)で「ジャンボ鶴田・試練の10番勝負」の第4弾として待望の一騎打ちが行われたのです。三萩野体育館には冷房設備がなく、うだるような暑さでしたが、2人は計65分も戦って引き分けでした。著者は「ロビンソンと戦うようになってから、鶴田はダブルアーム・スープレックスをドリー式の『大きく、ゆっくり』から、徐々にロビンソン式の『速く、強く』に変えていった」と述べています。
また、馬場も鶴田に「ロビンソンからいろんな技を学んだらどうだ?」とアドバイスしたといいます。著者は、「実現できなかったが、馬場はのちの『世界最強タッグ決定リーグ戦』でロビンソン&カール・ゴッチの世界最強コンビを考えるなど、確かな技術を持ったレスラーが好きだったのだ。パット・オコーナー、ダニー・ホッジ、若かりし頃に指導を仰いだビル・ミラーも馬場が認めていた実力者である」と述べているのですが、ということは、じつはアントニオ猪木というプロレスラーは馬場好みだったのかもしれませんね。馬場は、鶴田を猪木のようなレスラーに育てたかったのではないでしょうか。若き日の鶴田について、馬場は「実力は十分にあるのだから、あとは猪木のような表現力を身につけてほしい」などと語っていたといいます。
ロビンソンに続いて、若き鶴田の好敵手となった外人レスラーは、〝仮面貴族″ミル・マスカラスです。77年8月25日、田園コロシアムにおいて、女性ファンを開拓した鶴田と、少年少女ファンを開拓したマスカラスのドリームマッチ3本勝負が実現しました。1本目はマスカラス、2本目は鶴田が取った後、決勝の3本目はコーナー最上段から場外の鶴田にスーパーダイブを敢行したマスカラスが雨で足を滑らせて客席に突っ込んでしまい、リングアウト負けになりました。著者は、「結末こそ残念だったが、内容はハイレベル。そして若いファンの応援合戦というプロレスの新風景を生んだこの一戦は、77年度のプロレス大賞年間最高試合賞を受賞した。鶴田にとっては、『プロレスは強さを追求する〝実力勝負の世界″と、芸術面を追求する〝観客を魅了する世界″のバランスが大切だ』ということを考えるきっかけになった試合だったという」と述べています。
マスカラスとのアイドルレスラー対決に続いて、鶴田のプロレス人生で待っていたのは「最初で最後の異種格闘技戦」でした。78年2月5日に後楽園ホールで行われた〝柔道王″アントン・ヘーシンクとのUNヘビー級防衛戦です。76年2月、アントニオ猪木はミュンヘン五輪の柔道無差別級および重量級の金メダリストであるウィリエム・ルスカと初めての異種格闘技戦を行いましたが、ヘーシンクは東京五輪の無差別級金メダリストです。東京五輪の直後からヘーシンク獲得に動いていた日本テレビの悲願が実って全日本プロレス入りしましたが、プロレスラーとしては大成しませんでした。鶴田との一騎打ちについて、著者は「結末を先に書いてしまえば、ヘーシンクがエプロンからリング内の鶴田に裸絞めを仕掛けて反則負けという不透明決着で『鶴田のUN防衛戦史上の大凡戦』とされているが、それはあくまでもプロレス的な見方からの評価。異種格闘技戦的な目で見ると、かなり興味深い攻防が展開されている」と述べています。結局、これがヘーシンクの全日本ラストマッチになりましたが、鶴田はヘーシンクのナチュラルな強さを認めていたそうです。
鶴田のライバルといえば、なんといっても天龍の名前が思い浮かびますが、天龍の前にキム・ドクことタイガー戸口がいました。入団した日本プロレス崩壊後、独力でアメリカ各地を渡り歩いてきた戸口は、エリート・コースを歩む鶴田に激しい対抗意識を抱き、72歳になった今も、「鶴田は作られた偽りのスターだ!」と激しい言葉を口にするそうです。その戸口と鶴田の試合では、日本のプロレスファンは〝韓国の龍神″ドクの193cmの長身から繰り出されるスケールの大きなアメリカン・プロレスに目を見張りました。ドクは鶴田と同じように、NWAのファンクス、ジャック・ブリスコ、レイス、マードック、AWAのバーン・ガニア、ロビンソンからもプロレスを学んでいたのです。著者は、「お株を奪うダブルアーム・スープレックスで鶴田を叩きつけ、さらにサイド・スープレックス、ショルダーバスター、ガニアとの構想から盗んだと思われるスリーパー・ホールドなど、大技で鶴田と互角に渡り合うドクに、当時のファンは『もうひとりの鶴田がいた!』という驚きの声を上げた」と書いています。
さて、当時の鶴田について、著者は「鶴田の試合は、相手のリードにしっかり対応して、そこからはみ出ることがなかった。よく言えば安心して観ていられるし、アベレージ以上の内容になるが、一手先がわからないハラハラ感や緊張感はなく、巧くこなしている感が出てしまっていた。その一方で垣間見えたのはプライドの高さだ。頭を掻きむしって『オーッ!』と怒りを表すパフォーマンス、頭を抱えながら痛がる姿、身体をヒクヒクと痙攣させてダメージを表現する姿は、『実はこんなに余裕があるんだよ』ということを暗にアピールしているように見えたのである。それではファンの心は掴めない」と述べていますが、まさに若大将時代のジャンボ鶴田の本質を衝いた分析だと思います。
鶴田は「善戦マン」などと呼ばれ、NWAやAWAといった世界タイトルにも何度か挑戦しますが、いつもあと一歩で王座奪取に失敗しました。そんな鶴田がついに日本人初のAWA世界王者に君臨したのが84年2月23日でした。蔵前国技館で行われたAWA世界王者ニック・ボックウィンクルとインターナショナル王者ジャンボ鶴田のダブル・タイトルマッチで、鶴田はニックにバックドロップ・ホールドを決め、特別レフェリーのテリー・ファンクはしっかりと3カウントを数えました。著者は、「鶴田の快挙は世界タイトルマッチは時間切れ、もしくは反則やリングアウト絡みで完全決着がつくことが少ないという全日本の悪しき伝統を断ち切って、ピンフォールでAWA世界王座奪取をやってのけただけではない。世界王者としてベルトを腰にアメリカに逆上陸して全米をサーキットしたことだ」と述べています。確かに、これは前代未聞の快挙でした。
続いて、著者は「馬場はジャック・ブリスコを1回、ハーリー・レイスを2回破り、NWA世界王座に3度も就いたが、いずれもシリーズ中に王座を奪回されているし、79年11月30日に徳島市立体育館でボブ・バックランドを下して日本人初のWWFヘビー級王者になったアントニオ猪木も、1週間後の再戦は無効試合になって王座を返上。同月17日のニューヨークMSGに王者として登場することはできなかった。しかし鶴田は、84年2月26日に大阪府立体育会館でニックのリターンマッチを退けて初防衛に成功し、3月3日にウィスコンシン州ミルウォーキーのメッカ・オーデトリアムに天龍とのコンビで出場して、『新AWA世界ヘビー級王者』と紹介された」と述べています。結果として、5月13日にリック・マーテルに敗れて王座を失うまで、鶴田は81日間に渡って世界王者として全米をサーキットしたのです。
1985年、全日本プロレスに激震が走ります。前年に新日本プロレスを離脱した〝革命戦士″長州力率いるジャパン・プロレス軍団が全日マットに登場したのです。全日本vsジャパンの頂上決戦が、同年11月4日に大阪城ホールで行われた鶴田と長州の一戦でした。伝説の60分の戦いは今も語り継がれていますが、「鶴田と長州の実力差があり過ぎた」とか「いや、長州が鶴田の強さを引き立てたのだ」とか、諸説が入り乱れています。当の長州ですが、2012年10月5日の髙田延彦とのトークショーで、伝説の一戦を振り返り、「鶴田先輩は本当に強い。もう、全然! やっぱり、鶴田さんのほうが凄かったですよ。僕はあの人のペースに合わせちゃうと、絶対駄目なんですよ。僕は常に動くタイプなんだけど、自分のペースには入れさすことができなかったですね。それで、しんどい思いにはなりましたよね。難しいです。あの人のペースでやっちゃうと、僕はもう完全に自分のキャラはないです。僕はもう2度とやりたくないですね。要するに、流れが絶対合わないというか。流れの奪い合いはやってるんだけど、やっぱりそれは崩せなかったですね」と語っています。著者はこの長州発言について「本音だった気がする」と述べていますが、わたしもそう思います。
長州との一戦で尋常ではないスタミナと強さをプロレスファンに見せつけた鶴田は、次第に「最強」のイメージを濃くしていきます。88年春には、インター王者の鶴田、UN王者の〝風雲昇り龍″こと天龍、PWF王者の〝不沈艦″スタン・ハンセンに、馬場の恩赦によって新日マットから戻ってきた〝超獣″ブルーザー・ブロディを加えた4選手による三冠統一闘争が勃発しました。まずは3月9日、横浜文化体育館でハンセンを首固めで撃破した天龍がUN&PWF二冠王者になりました。次に3月27日、日本武道館で天龍がハンセンを相手に二冠防衛に成功。続いて、鶴田とブロディのインター戦が行われましたが、大方の予想に反して、この大一番をブロディが制しました。キングコング・ニードロップで鶴田を破ったブロディは、号泣しながらリングサイドの観客と抱き合って喜びを爆発させました。こんなブロディの姿を見るのは、誰もが初めてでした。あのブロディが勝利して泣くほど、鶴田は怪物的に強くなっていたのです。
そして、怪物と化した鶴田に戦いを挑んだのが生涯最高のライバルであった天龍です。もともと「週刊ゴング」の天龍番の記者であった著者は「鶴龍対決がプロレスファンの心を掴み、熱狂させたのは、プロレスラーとしての技量、主張をぶつけ合うだけでなく、生き方、価値観、人間性……それこそお互いの存在すべてをぶつけ合う戦いだったからだ」と述べ、以下の天龍の発言を紹介しています。
「人生から価値観から、すべてが対極にいる人が反対側のコーナーにいたわけだから、これは面白かったよ。すべてが面白かったね。やってることすべてが……変な表現だけど、箸の上げ下げから気に食わないとか、やってることすべてがジャンボにつながるんだからさ。あの頃は毎日すべてがプロレスだったから。それはジャンボの言葉がどうであれ、ジャンボもそうだったと思うよ。余裕を持ちながらやっているっていうのが彼の美学だったからね。あのジャンボが真っ向から来てくれたのは俺の財産。俺はジャンボが〝天龍とやってもいいか″って立ち止まってくれたからこそ、その後の天龍源一郎があると思っているし、みんなにジャンボが怪物だって言わしめたのは〝俺が真っ向から行ったからだ!″っていう自負もあるよ」
さらに天龍は今、「鶴龍対決は俺にプロレスの楽しさを教えてくれたよ。それと〝一生懸命やっていたら、誰かが見ていてくれる″っていう天龍源一郎の存在感を生んでくれたよ。今思うとね、ボロボロにされたっていう印象だね。〝こんなにボロボロにされたのはジャンボ鶴田と真っ向から戦ったからだ″という誇りもあるけどね。長州との闘いとはまた違うんだよ。破壊力と、プロレスのスタイルが違った。長州は一応、テクニックで攻めるプロレスだけど、ジャンボはぶっ壊しにくるプロレスだったからね。本当に俺をぶっ潰そうという気概で攻めてきてくれたよ、そのあとの三沢たちとの試合も凄かったけどね。俺は、あれを堪え切れたから、60すぎになって若いあんちゃんと試合をやっても、〝ジャンボとやった俺がこんなあんちゃんに!″っていうのがやめるまでずっとありましたよ。いいプロレスの基礎と、いい思い出をジャンボによって与えられましたよ」と語ります。著者は、「懐古ではなく、鶴龍対決は今でも最高のプロレスだと私は思っている」と告白しています。
天龍が「三沢たちとの試合も凄かったけどね」と述べたように、三沢光晴をはじめとする超世代軍との戦いも、鶴田の怪物ぶりを強く印象づけました。渕正信によれば、「あの頃は三沢たちが突っ掛かっていって、鶴田さんがムッとした顔をしただけで〝ダメだよ、ジャンボを怒らせちゃ!″っていう空気になった」そうですが、鶴田は後輩である三沢らにナマの感情を引き出されて、かつて馬場に指摘された「技術的に凄いものを持っているのに表現力が駄目なんだ」を克服したのでした。また、和田京平レフェリーは、「三沢の凄さってスタミナなんだけど、そのスタミナを作ったのがジャンボ鶴田。敵わないからジャンボにやるだけやらせて、ジャンボが疲れたのを見極めてやっつけに行く三沢だったよね。ジャンボ鶴田を疲れさせるための受け身によって、あの時代の三沢は出来上がったんじゃないのかな。三沢は受けながら、自分のスタミナをコントロールできた。だから相手の技を全部吸収したよね、逃げることなく」と語っています。
三沢だけでなく、川田利明も鶴田に鍛えられました。著者が川田に「鶴田は怪物だったのか、最強だったのか」を聞いてみたところ、川田は「昔は体力面じゃないところで怪物をアピールするプロレスラーが多かったじゃない。たとえば〝肉をこれだけ食った″みたいな。人とは違った怪物ぶりをアピールして、名前を売っていた時代に比べると、鶴田さんは〝全日本プロレスに就職します″って言ったぐらいだから、入ってきた時からそういう意識はまったくなくて、プロレス界でお堅く生きていこうって思ったんじゃないかなと思うから、それまでの怪物とは全然違うよね。でも、最強かって聞かれれば……最強だと思いますよ。プロレスラーとして最強かどうかっていうのは、また別で、お客さんに喜んでもらえるとか、人を惹きつけるとかいう面では違うと思うけど、フィジカル的なものでは最強だと思う。ファンの人たちに共感されにくかったのは、強すぎるがゆえにというのがあったと思うよ。でも超世代軍とやっていた時に指示されたのは、鶴田さんが俺らみんなを余裕を持っていじめたからだよ。もう、みんなが鶴田さんの強さを理解しちゃっていたからね」と語るのでした。
最後に、気になるのは鶴田と馬場との関係です。
77年に起こった全日本プロレスのクーデター未遂事件から両者の間に不信感が芽生えたようにも思えますが、著者は「私は取材をしていて、鶴田は常に馬場と一定の距離を取っていることを感じていた。社長の馬場は、選手たちにとっては近寄りがたい存在だったのはたしかだが、鶴田の場合は、全日本の黎明期からの師弟関係にもかかわらず、何か他人行儀なのだ。馬場にして鶴田に一目置きつつも、明らかに天龍のほうを信頼して、大事なことは天龍に相談していたし、天龍もまた自然体で馬場に接していた」と述べています。また、「馬場は天龍、三沢にはピンフォールを許したが、鶴田にはついに一度も負けなかった」という事実も示しています。プロレス馬鹿に徹することができなかった鶴田に対して、馬場は最後まで物足りなさを感じていたのかもしれません。天龍が全日本プロレスを離脱してSWSへ行くとき、馬場は「お前を社長にするから」と慰留したそうです。
でも、いくら馬場が物足りなさを感じたとしても、それが鶴田の本質だったのでしょう。「おわりに」で、著者は「昔の真のトップレスラーの条件は、力道山に始まり、ジャイアント馬場、アントニオ猪木がそうであったように、自分で団体を起こして、なおかつトップレスラーに君臨することだった。しかし、鶴田はそうした権威、天下獲りに背を向けた。望んだのはリング上のトップだけで、リングを降りたらプロレスを忘れて、家族と人生を謳歌する普通の人でいたかったのだ」と述べています。しかし、「計画どおりにはいかないのが人生。図らずも波乱万丈になってしまった鶴田の後半の人生はドラマチックだ。結局、ジャンボ鶴田は『普通の人』にはなれなかった。その生き様は紛れもなくプロレスラーだった」と述べるのでした。
ジャイアント馬場の死後、1999年2月20日の引退記者会見に続いて、同年3月6日に日本武道館にて鶴田の引退セレモニーが行われました。その後、研究交流プロフェッサー制度によりスポーツ生理学の教授待遇として、オレゴン州ポートランド州立大学に客員研究員として赴任することになりました。 この前後より持病のB型肝炎は肝硬変を経て、肝臓癌へ転化かつ重篤な状態へ進行していました。第三者らの進言もあり肝臓移植を受けることを決断した鶴田でしたが、日本では親族間の生体肝移植しか認められておらず、親族で唯一血液型が合致した実兄がドナー候補となるも最終的に移植条件に合致しなかったため、日本での移植が不可能となり、海外での脳死肝移植に望みを賭けました。オーストラリアで臓器提供を待っていたところ、2000年春になりフィリピン・マニラでドナー出現の報を聞き、フィリピンに渡航。国立腎臓研究所にて手術が行われましたが、肝臓移植手術中に大量出血を起こしてショック症状に陥り、16時間にも渡る手術の甲斐なく同年5月13日17時(現地時間では16時)に49歳で死去。この日は、奇しくも1984年にリック・マーテルに敗れてAWA世界ヘビー級王座から陥落した日と同じでした。最後までプロレスラーらしかった鶴田の戒名は「空大勝院光岳常照居士」。
かつて、日本プロレス界のトップにいた馬場と猪木が衰えを見せはじめていた頃、ジャンボ鶴田、藤波辰爾、長州力、天龍源一郎の4人がニューリーダーとして注目されました。著者が編集長を務めた「週刊ゴング」では、4人の頭文字を集めた「鶴藤長天」というコピーを考案。「鶴藤長天」は「格闘頂点」を目指す男たちだったのです。現在、時代は令和です。4人がリング上で活躍した昭和は遠くなりました。しかし現在、天龍、藤波、長州らは「日本プロレス殿堂会」を設立して、さまざまな場で思い出を語り合っています。その場に鶴田がいないのは、やはり寂しいことです。鶴田が生きていれば、彼らとどのように語り合ったでしょうか。しかし、本書を読んで、鶴田の往年の雄姿がありありとわたしの脳裏に蘇ってきました。故人の20回目の命日に刊行された本書は、「永遠の最強王者」にとって最高の供養になったのではないでしょうか。ジャンボ鶴田こと鶴田友美氏の御冥福を心よりお祈りいたします。合掌。