- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2020.11.15
『人生の1冊の絵本』柳田邦男著(岩波新書)を読みました。著者は、1936年栃木県生まれ。ノンフィクション作家。現代における「生と死」「いのちと言葉」「こころの再生」をテーマに、災害、事故、病気、戦争などについての執筆を続けています。最近は、絵本の深い可能性に注目して、「絵本は人生に3度」「大人の気づき、子どものこころの発達」をキャッチ・フレーズにして、全国各地で絵本の普及活動に力を注いでいます。
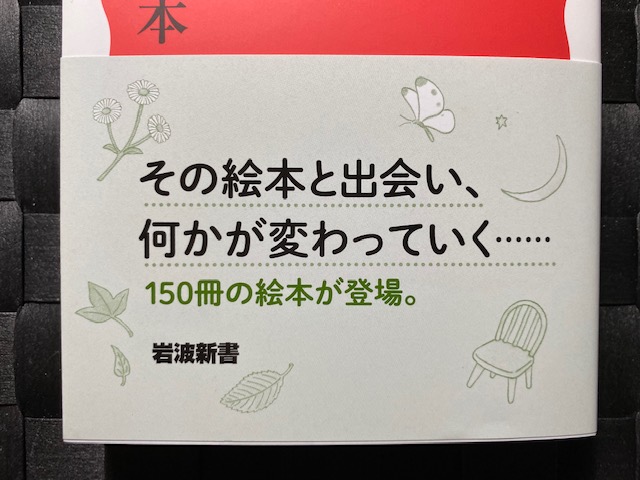 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、「その絵本と出会い、何かが変わっていく……150冊の絵本が登場」と書かれています。また、帯の裏には、「絵本は文章の理解力がまだ発達していない幼い子どものために絵でコトバを補っている本だと思いこんでいる人が多い。だが、違う。絵本は、子どもが読んで理解できるだけでなく、大人が自らの人生経験やこころにかかえている問題を重ねてじっくりと読むと、小説などとは違う独特の深い味わいがあることがわかってくる。(本書「あとがき」より)」と書かれています。
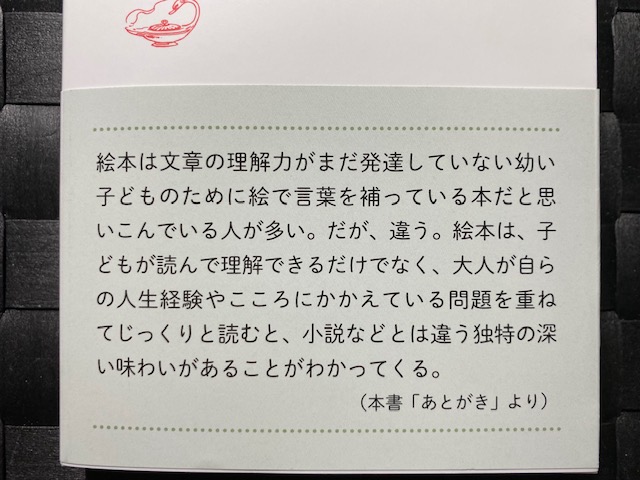 本書の帯の裏
本書の帯の裏
カバー前そでには、以下の内容紹介があります。
「絵本と出会い、何かが変わっていくかもしれない……。こころが何かを求めているとき、悲しみのなかにいるとき、絵本を開いてみたい。幼き日の感性の甦りが、こころのもち方の転換が、いのちの物語が、人を見つめる木々の記憶が、そして祈りの静寂が、そこにはある。150冊ほどの絵本を解説しながら、その魅力を綴る」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
1 こころの転機
2 こころのかたち
3 子どもの感性
4 無垢な時間
5 笑いも悲しみもあって
6 木は見ている
7 星よ月よ
8 祈りの灯
「あとがき」
「登場する絵本索引」
1「こころの転機」の「ゆびがなくても、おかあさんになれるんだ」の冒頭を、著者は「夜、静かなまちのなかをクルマを走らせていると、ふと思うことがある。家々は静まり返っている。どの家も屋根の下では、家族が何の問題もなく平穏に暮らしているように感じられるけれど、必ずしもそうではないだろうな。むしろ屋根の下では、誰かががんを患っていたり、認知症の親のケアに追われていたり、障害児の養育が大変だったりなど、何らかの問題をかかえている家が少なくないだろう。そんな思いが、頭の片隅を過るのだ」と書きだしています。
続けて、著者は「そんなことを思うのは、病気や障害や事件の取材に長年取り組んできて、様々な家族の内実をとらえてきたからだろう。だが、家庭内にそうした問題をかかえているからといって、その家族は不幸なのかというと、必ずしもそうではない。直面する問題としっかりと向き合い、たとえ病気や障害などの現実は変えられなくても、現実を真正面から受け止め、新しい生き方や人生観や価値観を見出して、こころの成熟した日々を過ごしている家族が少なくない」と述べます。そして、著者は『さっちゃんのまほうのて』たばたせいいち、先天性四肢障害児父母の会、のべあきこ、しざわさよこ共同制作(偕成社)を紹介するのでした。
また、「少女のこころの危機と絵の力」では、『きょうは、おおかみ』キョウ・マクレア(文)、イザベル・アーセノー(絵)、小島明子(訳)(きじとら出版)を紹介し、「小児精神医学の専門家によれば、女の子は少女期にどちらに転ぶかわからないような危ない精神状態になっていることが多いという。親はそのことに気づかずに、子どもを追いこんでしまいがちだ。だが多くは、親あるいは親代わりの人のまるごと受け入れて抱きしめてくれる愛や、きょうだいの支えなどによって、人格形成にゆがみを残さないで済んでしまう。この絵本は、そんなことを描いた作品と見ることができる」と解説します。さらには、「特にこころを病む場合がそうなのだが、精神世界におけるコミュニケーションにおいては、言葉が力を失っても、絵という表現手段の力は極めて大きいということだ。その意味でも、この絵本は多様な問題提起をしている作品だ」と述べるのでした。
「もうひとつのこころの動きが」では、著者は「人は誰でも、こころのなかに他者に知られたくない”ひみつ”を持っている。”ひみつ”と言うと、ちょっと大袈裟に響くかもしれない。たとえば、私が10歳のころだったか、いたずらごころで大きなアンズの木の枝に群がる小鳥たちに小石を投げたら、一羽に命中してしまった。小鳥は羽をバタつかせながら墜落し、すぐ横の田植えが済んだばかりの水田にじゃぼんと落ちてしまった。田んぼは水が張ってあるので、なかに入って助けてやることはできない。私はかわいそうなことをしてしまったと胸が痛んだが、そんなことをした自分が恥ずかしくて、家族にも友達にも話せなかった。今にして思えば、そのことをこころのなかに”ひみつ”としてしまいこんだのだ」と述べます。それから、主人公の少女「わたし」のこころの‟ひみつ”をテーマにした、こころの成長の物語である絵本『ひみつのビクビク』フランチェスカ・サンナ(作)、なかがわちひろ(訳)(廣済堂あかつき)を紹介します。
「自己否定が自己肯定に変わる瞬間」では、著者は「子どもたちの間では、名前の印象とか、言葉の訛りとか、洋服のちょっとした模様とか、些細なことがきっかけで、意地悪をしたり、いじめたりするトラブルが生じやすい。落ちこんだ子は、それがきっかけで、孤独になったり、引きこもったりしがちだ。そんなときに、親や教師や別の友達が、沈んだ表情の子の通常でない様子を察知して、その子が悲しみやつらさ、くやしさなどの感情を吐き出させるように、全身で包んであげるような対応の仕方が大事になってくる」と述べ、『ハコちゃん』かんのゆうこ(文)、江頭路子(絵)(講談社)を紹介します。
「障害のある子どもの限りない創造力」では、著者は「偏見と差別の問題は、人類の歴史とともに古くからあると言ってよい。人種差別、障害に対する差別、ハンセン病などの患者に対する差別などは代表的なものだ。そういうなかにあって、近現代になると、欧米などで、障害者や特定の病気の患者に対する偏見と差別をなくそうとする人々が現れ、教育界も少しずつ変わってきた。こうした変化とともに、絵本のジャンルでも、障害のある子どもや重い病気の子どもたちに対する理解を深めようというねらいで作られた絵本が、まだ少ないながら刊行されるようになってきた」と述べ、『がらくた学級の奇跡』パトリシア・ポラッコ(作)、入江真佐子(訳)(小峰書店)、『みんなからみえないブライアン』トルーディ・ラドウィック(作)、パトリス・バートン(絵)、さくまゆみこ(訳)(くもん出版)を紹介します。
「何をすることが、いちばんだいじか」では、著者は「”災害ユートピア”という言葉がある。1995年の阪神・淡路大震災のときも、2011年の東日本大震災のときも、家を失った何十万人という被災者たちが大きな公共スポーツセンターや学校の体育館などで長期にわたる避難生活を余儀なくされた。一家族あたりのスペースは狭く、プライバシーなどないかたちで寝起きする日々を過ごす。食事も粗末なものだ。そんななかで、家族以外の避難者たちと食べ物を分け合ったり、ほかの家族の高齢者や幼い子どもを世話してあげたりなど、支え合う日常が生まれる。見ず知らずの人々が職業や社会的地位や財産の有無に関係なく、同じ人間同士として連帯感を持って一日一日を乗り越えていく。そういう非日常のなかで生まれた共同体を、いつ誰が名づけたのか、”災害ユートピア”と呼ぶようになった」と述べています。
しかし、”災害ユートピア”は、長続きするものではありません。著者は、「いずれ貯えのある人、仕事や収入基盤のある人は、避難所から出ていって新しい生活に入る。どこかに移住先を見つける人もいる。遺された人々は、やがて仮設住宅などに移る。”災害ユートピア”は消えていくのだ。しかし、”災害ユートピア”で体験した支え合いや人とのつながり、あるいは困っている他者への思いやりといったものは、多くの人々のこころに刻まれ、その後の人生観に影響を与えることが少なくない」と述べます。
続けて、著者は「つまり、本当のユートピアはつくれなくても、そういうこころの持ち方こそ、人間が人間らしく生きるうえで、日常的にも非日常的な状況下でも、ささやかながらいちばん大きな支えとなるものであろう。しかも自然体で実行できるものだ。自分は人間としていかに生きるべきかという問題を頭のなかだけで考えていると、答えを見出せずに迷路に入ってしまいがちだが、なんらかの社会的な活動をして動いていると、案外答えは身近なところにあることに気づかされるものだ。”災害ユートピア”が教えてくれたものは、そういうことなのだと思う」と述べ、『3つのなぞ』ジョン・J・ミュース(作)、三木卓(訳)(フレーベル館)を紹介するのでした。
2「こころのかたち」の「人はなぜ学び、なぜ働き、なぜ祈るのか」では、著者は『いのる』長倉洋海(写真・文)(アリス館)を取り上げ、「世界各地における多様な祈りの情景と人間の表情が、頁をめくるごとに紹介されていくが、この写真絵本のなかほどのところで、長倉さんがたどり着いた死生観が、綴られている。
〈ぼくが小学生のとき、おばあちゃんが死んだ。焼いた煙が高い空にのぼっていくのを見たとき、すべてが無になってしまったような気がして、悲しかった。でも、さまざまな死に出会う中で、やっと気づいた。ただ死を恐れるのではなく、生きている、この時間、この瞬間を、もっともっとしんけんに生きることが大切なんだ、と〉
 長倉洋海氏の著書たち
長倉洋海氏の著書たち
著者は、「ドキュメンタリーの気配を漂わせるこの写真絵本の終わり近くで、長倉さんはこう記す。
〈いのることで、昔の人たち、宇宙、未来とも つながることができる。 そうすることで、わたしたちは「永遠」というものに 近づくことができるのかもしれない〉
長倉さんの結びの言葉は――。
〈今日も世界各地で、いのりは続いている。 そして、これからも続いていく。人が生きているかぎり。 希望を捨てないかぎり。 人が人と生きていくかぎり〉
この写真絵本『いのる』は、私の終生の伴侶というべき大切な本たちの1冊になるだろう」との書いています。『いのる』の他にも、長倉氏は『働く』『まなぶ』『つなぐ』『さがす』といったシリーズ続編を世に問うています。これらに強く心惹かれたわたしは、早速、アマゾンですべてを注文し、一気にすべてを読みました。躍動する子どもたち、真摯な子どもたちの姿に感動しました。これから何度も読み返したいと思います。
「ファンタジーはグリーフワークの神髄」では、著者は「絵本の物語に、おばあちゃんやおじいちゃんがお母さんやお父さんに負けないくらい登場し、タイトルにも書きこまれるのは、なぜだろうか。答えは簡単だ。おばあちゃん、おじいちゃんは、育児に親ほど責任を負うわけではないし、時間的にもゆとりがあるので、遊び相手や散歩の相手になって、楽しい時間を過ごしていればいい。孫はかわいいねえと言って、楽しんでいればいい。子どもにしてみれば、おばあちゃんもおじいちゃんも『大好き』ということになる」と述べ、『おじいちゃんの ゆめの しま』ベンジー・デイヴィス(作)、小川仁央(訳)(評論社)を紹介しています。また、「子どもが旅立ったおじいちゃんの”向こうの世界”にまで行って、どのような日常なのかを見届け、励ましの言葉をもらって帰ることで、大好きな人はこころのなかでいつも一緒なのだという安心感を得ている。子どもならではの想像力の豊かさを、グリーフワークに生かしていると言えるだろう」と述べています。
 『死を乗り越える読書ガイド』(現代書林)
『死を乗り越える読書ガイド』(現代書林)
続けて、著者は「しかし、よく考えてみれば、大人でもそうした想像力を活性化することで、魂レベルでの《あの人は今も私のこころのなかで生きている》という思いを強く抱けるようになるのではなかろうか。そうした想像力を持つことは、精神的いのちの永遠性への気づきをもたらすものであって、グリーフワークの神髄と言えよう。最近は、ファンタジーの物語によって、そうした課題に応える絵本が創作される時代になっているのだ」と述べていますが、まったく同感です。拙著『死を乗り越える読書ガイド』(現代書林)でも、ファンタジーの本をたくさん紹介しましたし、わが社のグリーフケア・サロンにはいつも多くの絵本が常備されています。
「ファンタジーの世界で遊ぼうよ」では、著者は『みんなうまれる』きくちちき(作)(アリス館)を紹介し、「きくちちきさんの『みんなうまれる』は、太陽の光によって、草木が芽を出し、虫たちも生まれ、いろいろな色も生まれ、そしてぼくも赤ちゃんとして生まれるという、新しい生命の誕生の数々を、自作の簡潔な詩のような短文でつないでいくという内容になっている。絵は水彩の爽やかな色づかいによって、モダンアート風だがそれほど突っ張らないで、形より色のイメージを前面に出す感じで描いていて、なかなかにユニークな絵本にしている。言葉と色のカノンと言おうか。いろいろな生命の誕生の姿を、読み手の1人ひとりが想像力を発揮して思い描くのをうながすような絵本だ。ゆっくりと頁をめくり、最後の頁を閉じると、何だかほわんとした温もりのなかにいる気分になるだろう。忙しいときこそファンタジーの世界で遊ぼう!」と述べています。
「50歳からの6歳児感性の再生法」では、『さびしがりやのクニット』トーベ・ヤンソン(作)、渡部翠(訳)(講談社)、『プー あそびをはつめいする』A・A・ミルン(文)、E・H・シェパード(絵)、石井桃子(訳)(岩波書店)を紹介し、ムーミン童話やプーさん童話は、子どもと大人の領域を超えた世界児童文学の傑作として、これから100年後も200年後も読み継がれていくだろうとして、著者は「優れた児童文学の数々を読んでいつも感心するのは、6歳児くらいまでの幼いこころの動きを、みごとと言えるほど鋭くとらえている点だ。それはとりもなおさず作家が6歳児くらいまでの感性をそのまま失わずに持ち続けていることを示している」と述べています。鋭い指摘であると思います。
では、6歳児くらいまでの感性とは、どういうものなのか。それは、小学校に入って受ける教育のなかで身につけていく知識や理屈などが前頭葉で支配的になる前のこころの動きであるとして、著者は「たとえば、未知のものへの好奇心、何かを自分でやろうとするひたむきなこころ、自分が生きるのを守ってくれる人に対する真っすぐな信頼感、言葉に対する敏感な反応などだ。ヤンソンにしてもシェパードにしても、そういう幼児期の子どもの心理を、物語のなかの会話の言葉でも、挿し絵や絵本の絵のなかでも、みごとに表現している」と指摘しています。
そして、著者はこう述べるのでした。
「絵本や童話を読んでいつも思うことがある。人は人生のなかで青年期から中年期にかけては、ガツガツと仕事仕事の日々を過ごすのはやむを得ないにしても、50歳を過ぎたら、忙しくても、毎日20分は絵本や童話を読むライフスタイルを身につけるように心掛けてはどうか、と。その日常を積み重ねていくなら、いつしか幼いころの無垢な感性を取り戻し、還暦を迎えるころには、周囲から『あなた、変わったね』と言われるようになっているだろう」
3「子どもの感性」の「夢のなかで遊ぶ子どもの世界」では、著者は「インドネシアのある島では、子どものころから、見た夢をその日のうちにお年寄りに話すという日常生活の文化があるという。かなり前だが、臨床心理学者で夢分析の専門家でもあった故・河合隼雄先生がご健在だったころに聞いた話だ。その島では、こころの病気になる人が1人もいないというので心理学者や精神医学者が関心を持っているとのこと」と述べています。
夢を見たら人に話すことは、傾聴ボランティアの人が、ホスピスや老人ホームや在宅医療において、死を間近にした人が人生を振り返ってじっくりと語るのを支持的にひたすら聴くことによって、語る人がこころの安らぎを保てるのと似ているように思うとして、著者は「つまり夢を語る文化は、抑圧感情などを引きずらずに解放し、自己肯定感を獲得することにつながっていくのだろうと私は解釈している。このようなことを考えると、夢のなかのファンタジーを描いた絵本を幼い子に読み聞かせするのは、夢のなかで自由に遊ぶ機会をつくる意味を持ち、ひいてはこころをのびやかにし、感情を豊かにする役割を果たすのではないかと思えてくる」と述べ、『はんなちゃんがめを覚ましたら』酒井駒子(作)(偕成社)を紹介しています。
「子ども時代を生きるとは」では、著者は「子どもが母親の温もりを求め、母親の愛を強く求めるとき、大人が気づかなければならないのは、幼くても母親の微妙な心模様を鋭く読み取る感性が育っているということだ。幼い子は言葉では表さなくても、母親が喜んでいるか悲しんでいるか、ヒステリックになっているかどうか、落ちこんでうつの状態に陥っているかどうかなど、母親の心理状態を直観的に感じ取り、その母親の心理状態に応じた振るまいなり身の処し方をする。特に重要なのは、母親がパニック状態だったり、うつ状態だったりすると、子どもは母親に迷惑をかけまいとして、自分の感情を抑えこむ、いわゆる抑圧反応を起こすという点だ。自身のこころを貝殻のなかに封じこめて表に出さず、縮こまった状態になるのだ。そういう抑圧状態が続くと、こころの発達が止まってしまう」と述べ、『かあさんは どこ?』クロード・K・デュボア(作)、落合恵子(訳)(ブロンズ新社)を紹介します。
「おさな子が『お兄ちゃん』になるとき」では、『ねぇ、しってる?』かさいしんぺい(作)、いせひでこ(絵)(岩崎書店)を紹介し、著者は「子どもがほんとうに幼いころには、現実の世界とファンタジーあるいはイマジネーションの世界との間に境界線がない。ペットやぬいぐるみとお話をしたり、何かわからないことをつぶやきながら芝居がかったことをして、物語を創ったりしているとき、その営みは、ほんとうの人間との間で経験することとほとんど同じ意味を持つ。言い換えるなら、幼い子の感性と想像力はものすごく豊かなのだ。ところが4~6歳になると、現実と想像の世界に境界線ができて、両者は別のものなのだということがわかってくる。そして、覚えた知識や他者との関係の持ち方などで、自分の行動を判断していくようになる」と述べています。
5「笑いも悲しみもあって」の「不条理な悲しみの深い意味」では、著者は「人がこの世に生まれてからあの世に旅立つまでの長い歳月のなかでは、『ああすればよかった』『こうすればよかった』と悔やまれることや、『なんで私が』とか、『そんなつもりじゃなかったのに』と無念の思いや悲しみに駆られて落ちこんでしまうことが少なくない。もともと人生というものは、『こうすればこうなる』というぐあいに、思い通りにはならないことが多いと考えたほうがよいのだと、私は思っている。そのことを学んでいくのが人生というものだろう。そういう学びは、実は子ども時代から始まるのだということを、絵本や童話を読む子どもたちの反応を見ているとよくわかる」と述べ、『ごんぎつね』新美南吉(文)、箕田源二郎(絵)(ポプラ社)を紹介します。
7「星よ月よ」の「まるい月に目を輝かせる赤ちゃん」の冒頭を、著者は「昼下がりの乗客の少ない時間に電車に乗ると、私には異様としか思えない光景が目の前に広がっている。窓を背にした長椅子の人々も私の両脇の人々も、ほとんどがスマホかタブレットの操作に熱中しているのだ。たまに1人くらい、文庫本を読んでいる人を見かけるが、そういう人は珍しい。窓の外の街の風景とか空の雲を眺めている人は、ほとんどいないのだ。特に愕然となるのは、子どもを間に座らせている親子3人が、会話をするでもなく、それぞれにスマホに集中している姿だ。窓から見える空に美しい巻雲が流れていようと、遠くにスカイツリーが見えようと、もうそういう風景にはまるで関心を向けないし、互いに会話もしない」と書きだしています。
続けて著者は、「夜、駅を出て家路を急ぐ勤め帰りの人々も、スマホを離さない。まるで国中の人々がスマホ中毒に陥っているのかと思うほどだ。子どものころからそんなスマホ中毒になっていたら、自分の育った街や村の風景に愛着を抱くようにはならないだろうし、樹木や草花の季節の変化を感じる感性も育たないだろう。これは人生の大事な時間の喪失であり、感性を豊かにする機会の喪失だと思う。そういう時代だからこそ、テレビを消し、スマホなどを切って(せめてマナーモードにして)、親が子どもに絵本や童話を読み聞かせしたり、逆に子どもが親に読み聞かせしたりして、絵本や童話の楽しい世界をこころに刻むことがとても大事な意味を持つようになっていると言いたい」と述べます。
 わが家の絵本コレクションの一部
わが家の絵本コレクションの一部
そして、著者は『きょうはそらにまるいつき』荒井良二(作)(偕成社)、『よるのかえりみち』みやこしあきこ(作)(偕成社)を紹介しています。じつは、わが家では、「うさぎ」と「月」に関する絵本はすべてコレクションしています。2人の娘たちも「うさぎ」と「月」の絵本を読みながら、育ってきました。わが家には、『きょうはそらにまるいつき』はありましたが、『よるのかえりみち』は初めて知ったので(うさぎが登場しますが、未読でした)、早速、アマゾンで注文しました。幻想的で素晴らしい絵本です。
「強烈な色がひらく異界」では、著者は「画家が色にこだわりを持つのは当然のことだが、絵本の分野でも、作品のなかで特定の色をテーマに結びつけて強く打ち出す作家がいる。2016年から次々に邦訳され、新しい作風で注目されているフランスのイザベル・シムレールさんは、まさに色自体をテーマにからめて強烈なインパクトをもたらす絵本を制作している新進の絵本作家だ」と述べ、シムレールの『あおのじかん』『はくぶつかんのよる』『シルクロードの あかい空』石津ちひろ(訳)(岩波書店)を紹介します。そして、著者は「シムレールさんの絵本を読み通した後に私が感じたのは、どの絵本のどの頁を開いても、そこだけを切り離しても楽しめる絵と文になっており、どの1冊も、それぞれに大人が深く味わえる、絵本を超えたしい詩画集になっているということだった」と述べるのでした。
 「朝日新聞」2018年11月27日朝刊
「朝日新聞」2018年11月27日朝刊
8「祈りの灯」の「亡き人の実存感がこころにストンと」では、著者は「グリーフケアあるいはグリーフワークという用語が、この国においてもかなり一般的に使われるようになってきた。大切な人、愛する人を喪った悲しみを癒し、生きる力を取り戻すのを支えるのがグリーフケアであり、自分自身で再生への道を歩むのがグリーフワークだ。ここで言うグリーフ(grief)とは、生きているのがつらいと思うほどの喪失や挫折によってもたらされる深い悲嘆のことだ」と述べています。わたしは、現在、グリーフケアの研究と実践に取り組んでいます。
また、著者は「人は、なぜ重い病気になると闘病記を書いたり、俳句や短歌を詠んだりするのか。人は、わが子や伴侶や親を亡くすと、なぜ追悼記を書くのか。私は、そうした問いに対する答えを求めて、この40年ほどの間に数百人の闘病記や追悼記を読んできた。そうした手記に見られる共通点は、自分あるいは愛する人がこの世に生きた証を残したいという思いだ。そして、書くことによって、その人のこころに何がもたらされるかというと、それはこころの癒しであり、生き直す力だ。自分の体験や状況を見つめ、それらに文脈をつけて書くという行為は、ショックや悲嘆や不安によって渾沌としていたこころのなかを整理する作業にほかならないからだ」とも述べ、『いつまでもいっしょだよーー日航ジャンボ機御巣鷹山墜落事故で逝った健ちゃんへ』みやじまくにこ(作)、(扶桑社)を紹介します。
日航ジャンボ機事故で40歳の夫・谷口正勝さんを亡くした真知子さんが、絵本『パパの柿の木』を刊行したのは、事故から31年経った2016年夏でした。そのきっかけは、30年を過ぎた2015年秋、事故当時は小学生だった次男の誠さん一家と御巣鷹の尾根に慰霊登山をしたときのこと。5歳の孫・結菜ちゃんが「生きているパパのパパに会いたかった」とつぶやいたことでした。著者は、「真知子さんは、このつぶやきを聞いて、事故によって家族に何が起きたかを、しっかり孫たちにも伝えなければと思ったのだという。夫は事故の5年前に、『家で作った果物を子どもたちに食べさせたい』と、柿の苗木を買ってきて植えた。その柿の木の成長と小学生だった2人の男の子の成長を重ね合わせ、さらに真知子さんのこころの遍歴も忍ばせている絵本の構成は、とても感銘深い。事故の後、夫が機内で記した「子供達の事をよろしくたのむ」という遺書を見ては、泣いていた真知子さん。パパの代わりになろうとがんばるお兄ちゃん。いつもパパのシャツを抱いて涙して寝る弟。はじめて実った柿を涙ながらにほおばる家族……。やがて、子どもたちは成長し、家族を持ち、孫が5人にもなる」と述べています。絵本の最後の言葉は、〈パパ、いつも僕たちを見守ってくれて、ありがとう〉でした。
そして、著者は、2000年の暮れに起きた東京の世田谷一家四人殺人事件の被害者家族の姉で隣に住んでいた入江杏さんが描いた『ずっと つながっているよ――こぐまのミシュカのおはなし』(くもん出版)を紹介し、「喪失体験者にとっての癒しとは、亡き人の精神的いのち(それは魂と言ってよいだろう)は、決して消えることなく、人生を共有した遺された人のこころのなかに(全身に染みこんで、と言ったほうがよいかもしれない)、いつまでも生き続けていることに気づくことなのだと言えよう。しかも、亡き人の魂は残された人たちの人生を、人間性の豊かなものに膨らませてくれるのだ。こころのなかにあふれんばかりにこみあげてくる悲しみを、絵本というかたちで表現する行為は、喪失体験者自身のこころを癒すだけでなく、その絵本を読む悲しみに暮れる人のグリーフケアの役割をも果たすに違いない」と述べるのでした。
 『涙は世界で一番小さな海』(三五館)
『涙は世界で一番小さな海』(三五館)
わたしは、「死」を説明するものとして、「医学」「哲学」「宗教」とともに「物語」に注目していました。そして、その中でも「ファンタジー」の持つ力に注目し、アンデルセン、メーテルリンク、宮沢賢治、サン=テグジュペリの4人の作品を死を乗り越えることのできる「ハートフル・ファンタジー」としてとらえ、『涙は世界で一番小さな海』(三五館)を書きました。本書を読んで、「物語」とともに「絵」の持つ力に改めて気づきました。「あとがき」で、著者は「今、絵本の世界が新しいルネッサンス期を迎えている。21世紀になってはや20年。この新しい時代に、絵本という表現ジャンルが、実に多様な人生の課題について、絶妙な解答例と言える作品を次々に生み出しているのだ」と述べていますが、グリーフケアの世界においても絵本の持つ力は無限大であると言えるでしょう。本書を読んで、読みたい絵本がたくさんできました。いろいろと購入しましたので、わが社のグリーフケアサロンにも置きたいと思います。
 たくさん購入しました!
たくさん購入しました!
