- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2021.03.10
『命の経済』ジャック・アタリ著、林昌忠&坪子理美訳(プレジデント社)を読みました。「パンデミック後、新しい世界が始まる」というサブタイトルがついています。「緊急事態宣言」あるいは「GoToキャンペーン」などが語られる際に、つねに「命が大事か、経済が大事か」といった議論がなされますが、まったくナンセンスな話です。重要なのは、本書のように「命の経済」について考えることです。
著者は、1943年アルジェリア生まれ。フランス国立行政学院 (ENA)卒業、81年フランソワ・ミッテラン大統領顧問、91年欧州復興開発銀行の初代総裁などの要職を歴任。政治・経済・文化に精通することから、ソ連の崩壊、金融危機の勃発やテロの脅威などを 予測し、2016年の米大統領選挙におけるトランプ の勝利など的中させました。著書多数。
 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、著者アタリの顔写真とともに、「欧州最高峰の知性が、来るべき未来を予測!」「政治/経済/歴史/文化/社会/科学/テクノロジー」「ニューノーマル時代になすべきことがわかる」と書かれています。
カバー前そでには「欧州最高峰の知性が訴えるのは、事実から目を背けずに向き合い、真実を語ることの重要性である」「歴史を紐解き、現状を分析し、未来を見通す。傍観者でも、隷属者でもなく、自ら主体的に生きる存在となるために」「博覧強記のアタリ氏がロックダウン下のフランスで書き上げ、日本語版刊行を前に、最新のデータに基づく加筆を行った渾身の一冊」と書かれています。
アマゾン「出版社からのコメント」には、「欧州最高峰の知性が、歴史、政治、経済、文化、科学の観点から、新型コロナウイルスを分析します。さらにパンデミック後に広がる新しい世界を、『命の経済』の切り口から提示し、私たちに生きる勇気と希望を与える提言書です」と書かれています。さらに、「アタリ氏は、これまで数々のパンデミックに関する予測を的中させています」として、以下の過去の書籍の言葉を紹介しています。
「疫病の予期せぬ蔓延により、世界は集団隔離を余儀なくされ、ノマディズムと民主主義に再考が促される」(『21世紀事典』、1998年)。
「今後10年で、破滅的なパンデミックが発生する恐れがある。パンデミックは、多くの個人・企業・国家のサバイバルにとって非常に大きな脅威である」(『危機とサバイバル』、2009年)。
「これまでにないタイプのインフルエンザが明日にでも流行する兆しがある。だが、そのための準備はまったくできていない」(『二〇三〇年 ジャック・アタリの未来予測』2016年)。
そして、「この本に新たに書かれている、2020年以降の新たな『予測』を是非、読み解いてみてください」と書かれています。
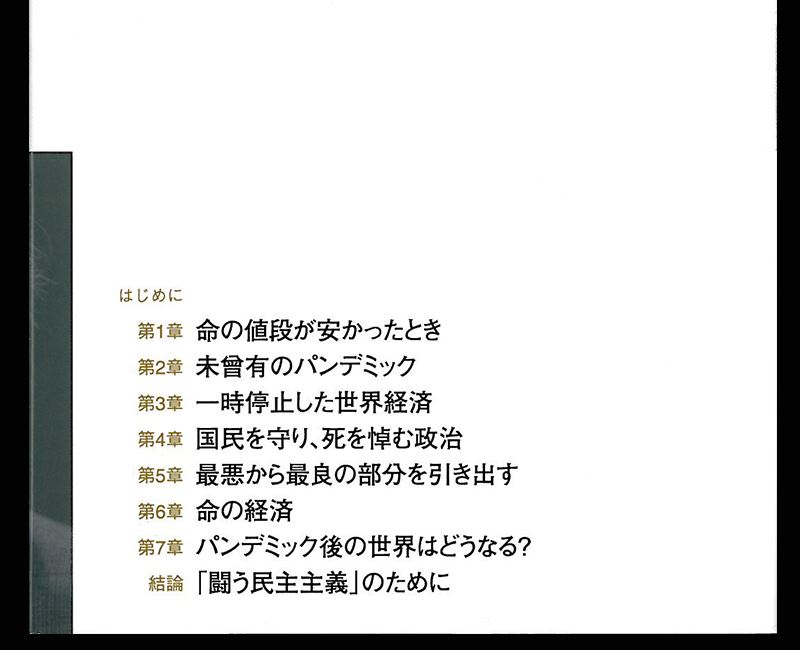 本書の帯の裏
本書の帯の裏
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
第1章 命の値段が安かったとき
第2章 未曾有のパンデミック
第3章 一時停止した世界経済
第4章 国民を守り、死を悼む政治
第5章 最悪から最良の部分を引き出す
第6章 命の経済
第7章 パンデミック後の世界はどうなる?
結論 「闘う民主主義」のために
「謝辞」
「訳者あとがき」
「付属資料」
「原注」
「はじめに」では、「聞くべき声に耳を傾ける」として、著者は「本書の総括は、専門家を自称する者たちの論争、恐怖を煽る輩の罵言、事態を直視せずに自分たちのユートピアを繰り返し説く人々の妄想とはまったく異なる。そして今後の展望では、来るべき未来に備えるためになすべきことを明確に語る。私は、これまでとは異なる暮らし方を今、試みようとする幾多の人々に本書を捧げる。執筆に際しては、世界各地から得た確固たる知識だけを用いることを心がけた。20ヵ国以上の医師、疫学者、歴史家、経済学者、社会学者、哲学者、小説家、経営者、研究者、労働組合活動家、非政府組織(NGO)の代表者、与党と野党の政治家、文筆家、ジャーナリストの見解を参考にした」と述べています。
そして真理が宿っているのにもかかわらず無視されることの多い、市井の人々の意見にも耳を傾けたとして、著者は「自分たちの知識と懸念を私に惜しみなく語ってくれた彼らに感謝申し上げる。彼らの言葉は、この特殊な状況においていっそう価値をもつ。私はSF小説のような突拍子もない仮説をはなから排除しないようにも気を配った。現実の世界はSFを超えてしまったのではないか」と述べています。
また、「死から目を背けることなかれ」として、著者は「なぜ、われわれは死と向き合う必要があるのか。それは何より、死がやがてわれわれの元に訪れるものだからだ。現代人は、死を完全に回避可能な事故のようなのとして捉える傾向があまりに強い。われわれは死を忘れ、否定する。個人に代わって、あらゆる社会、宗教、イデオロギーが死を引き受けようとする。目前の出来事に意義を付し、生き生きと暮らしたいと願うなら、これらの疑問に回答を見出すことこそが必要だ。これまで以上に快活に、真の意味で生きるために」と述べます。
また、「私の怒り」として、著者は「人類は悪夢を乗り越えようとしているようだ。そして、ただ一つの願望、野望、悲痛な願いを抱いているようだ。それは、悪夢が終わり、危機が発生する以前の世界に戻ることだ。私は、そうした無分別な態度に怒りを覚える。というのは、たとえこのパンデミックが自然に、あるいは治療薬やワクチンのおかげで魔法のように急速に終息したとしても、われわれがパンデミック以前の世界に戻ることはあり得ないからだ」と述べます。
さらに、「パンデミックとの戦いは『戦争』である」として、著者は「パンデミックでは戦争と同様、人々の基本的自由は制限されることになる。多くの人々が命を落とすことになる。多くの指導者が失脚することになる。それまでの世界に戻ろうと願う者たちと、そのようなことは、社会、政治、経済、エコロジーの観点から不可能だと理解する者たちとの間で、激しい論争が起こるだろう。戦時中と同様、すべては死との関係において展開する。個人でなく集団の死であり、私的な出来事としての死でなく、可視化された死である。死は巷に溢れ返り、独自性を失う。こうして各人の命の独自性も失われる」と述べています。
そして、「危機をチャンスに変える『命の経済』」として、「すべては時間との関係において展開する。なぜなら、パンデミックにおいては時間だけが重要な価値をもつからだ(戦争もまた、同様のことを人々に再認識させる)。この危機をチャンスに変える者たちだけでなく、あらゆる人々の時間が、いかなる事態に陥ろうとも価値をもつ。戦時中と同様、最初に勇気を振り絞って武器を手にした者たちが勝者になるだろう。そのためには、斬新な計画を滞りなく遂行しなければならない。私はこの計画を『命の経済』と命名する」と述べるのでした。
第1章「命の値段が安かったとき」では、どの時代においても、人類は、恐怖、病気、苦悩、死に直面してきており、文明を定義するのはいつも死との関係に他ならないとして、著者は「死に意味を付与することに成功すると、その文明は繁栄する。逆に、死に意味を見出すことができないと、その文明は消滅する。だからこそ、感染症は文明にとってきわめて重要な出来事なのだ。この感染症流行の渦中において、人類は苦悩、病気、死と向き合う。感染症のもつ意味合いは、これまでにないほど強烈になっている」と述べています。
続けて、著者は「人類はもはや個人でなく、社会一丸となってこの事態に立ち向かう。文明にとっての審判の時である。指導者のなかには、人々を保護する最良の戦略を選択できた者もいた。反対に、指導者が間違った戦略を選択したり、他者や自分たちの死に意味を付与できなくなったりすると、パンデミックはすでに進行中の変化を加速させ、それまで存在しなかったイデオロギーや合法権力を生み出し、新たな指導者の登場を促し、地政学を一変させる」と述べます。
「帝国を守るという信念」では、「古代文明と感染症」として、諸説はあるけれども、疫病に関する最初期の記述は約3000年前のメソポタミアと中国の文書にみられると指摘し、著者は「これらの文書には、神々が人間を弄ぶため、あるいは罰するために地上に疫病という災いを広めるのだという当時の人々の不平が記されている。このようにして、疫病は過ちを犯した人間を罰するために神々がもたらしたものだという考えが生まれた。疫病が発生すると、権力者、宗教者、軍人、政治家は、自分たちの責任を転嫁するために、人々に罪悪感を植え付けよう、あるいはスケープゴートを見つけ出そうと躍起になった。こうした工作がいつも成功したとは限らない。疫病は、家族、都市、人民を破壊し、個人の命と死の尊さを否定し、王朝、宗教、帝国の消滅を加速させた〕と述べています。
また、「世俗化の始まり」として、ヨーロッパでは、疫病を退治するのは宗教だと信じる者たちが相変わらず存在したと指摘し、著者は「1350年〔ローマ教皇クレメンス6世が、ローマ巡礼を促す「聖年」と定めた〕、100万人ほどの信者がローマを目指した。しかし、これらの巡礼者の大半は道半ばにして息絶えた。そこで犯人探しが始まり、井戸に毒を入れたとしてユダヤ人が糾弾された」と述べます。疫病の勢いが衰えないため、宗教は存在意義を失いました。14世紀中頃、フランスのアヴィニンの医師ギー・ド・ショーリアックは、「〔人々は]召使に看取られることなく死んだ。埋葬の際に司祭はいなかった。父親が息子を見舞うことも、息子が父親を見舞うこともなかった。慈愛の精神は失われ、希望は打ち砕かれた」と記しています。
ドイツの画家ハンス・ホルバインは、木版画シリーズ『死の舞踏』において、社会的な地位に関係なく疫病による死者が続発する様子を描きました。地主は不動産収入が途絶えたために没落しました。著者は、「このパンデミックと戦うため、人々は何らかの対策を試みようとした。そこで彼らは、過去にハンセン病患者に対してとられた扱いを参考に、感染者や感染が疑われる者を閉じ込めた。旧約聖書に登場する隔離である。期間も旧約聖書と同様、40日間だった」と述べています。
「感染症管理体制の確立」では、「猛威を振るうインフルエンザ」として、著者は「1889年、(オルトミクソウイルス科のウイルスが引き起こす感染症である)インフルエンザが初めて大規模な世界的流行を見せた。ロシアで始まったこの大流行は、モスクワ、フィンランド、ポーランドで流行し、その翌年には北アメリカとアフリカを襲った。1890年代末に36万人を死亡させたこのインフルエンザは、その後しばらくの間、息を潜めた」と書いています。しかし、1918年に再び猛威を振るいました。まずは中国、次にアメリカとヨーロッパを襲いましたが、アメリカとヨーロッパは、軍事作戦〔第1次世界大戦]を停止させるわけにはいきませんでした。
著者は、「完全な報道規制が敷かれていたが、中立国だったスペインがこのインフルエンザによる被害を報道した(こうしてこの疫病は「スペイン風邪」と呼ばれるようになった)。パリの日刊紙『アントランシジャン』紙は、この風邪を『まったく危険性のない病気』と論じた。各国の指導者である老人たちは、戦争と疫病の地に若者たちを送り込み、彼らを犠牲にした」と書いています。また、このパンデミックで覚えておくべき二つの教訓として、「感染症の流行に直面しながら、早い段階で戦いに勝利したと考えるのは幻想である。そして、疫病対策への財政出動を早々に打ち切るのは拙速である。幻想と拙速はいずれも、われわれを惨憺たる結果へと導く」と書いています。
第2章「未曾有のパンデミック」では、ほとんどのパンデミックは、アジア、とくに中国で始まり、続いて、ヨーロッパ、アメリカ、アフリカの諸国を揺るがし、ときに、文化、社会、政治、地政学に甚大な影響をもたらすとして、著者は「一般的に、貧困層より富裕層のほうがはるかに危機を切り抜けやすいのは明らかだ。だが、権力者が効果的な対応を講じないと、パンデミックは国の指導者層に一撃を与える。政治体制がすでに脆弱だと、この一撃はしばしば致命傷になる」と述べます。また、疫病という敵に対して、治安当局の指導、保健衛生の向上、ワクチンや治療薬の開発など、具体的な対策が講じられるようになったことを指摘し、「その際、経済活動を停止させるようなことはなかった。病死する危険があっても、生きる糧を得るには働く必要があったのだ。そして信仰心を失った者でさえ、死を特別なことだとは考えていなかったので、人々は自分が何歳であっても、訪れる死を甘受した」と述べます。
「容認できない死」では、今日ではついに、われわれは命を守るためなら、経済活動が制限されることもやむなしと考えるようになったとして、著者は「なぜだろうか。近年のデジタル経済の発展によってテレワークが可能になり、以前よりも身を守れるようになったからだと、短絡的な見方をしたがる者もいるが、それは副次的な理由に過ぎない。真の理由はまたしても、人々と死の関係性にある。先進国の一部では戦争の影が視界から消えた現在、人々にとって死とは、先進国がなお関与する少数の紛争での死、事故やテロ行為などによって引き起こされる死に他ならない。自然死は、もはや有名人の死を除き話題に上らない。路上での暴力や違法薬物の乱用などによる死も、めったに語られることはない」と述べます。
著者によれば、今後、哀悼の意が表されるのは、特殊な状況で発生した死と、有名人や政治指導者の死だけだそうです。彼らの死は公的討論の議題になり、追悼の対象になるといいます。また、死の捉え方に関する教訓は次の通りだとして、著者は「予見可能でひっそりと死ぬことができる状況での死は容認される。一方、死が巷に溢れ、誰もがいつ何時死ぬかもしれないという状況での死は耐え難い。パンデミックでは、まさに後者の死が跋扈する。ひっそりと死ぬことができる機会は奪われ、誰もが予期せぬ死に怯えるのだ」と述べます。
3月11日、WHOは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行は「パンデミック」になったと宣言しました。これは最初の感染者が確認されてから3ヶ月以上後のことでした。「起こるべきして起こった流行」では、人々はパンデミックを封じ込め不能なものにし、制御不能にさせるような行動パターンをとるようになっていたことが指摘されます。また、「感染爆発を許した背景」として、著者は5つのポイントを挙げます。
第1に、世界各地では医療制度が長い時間をかけて脆弱化されてきたこと。その原因は、療制度を国の財産ではなく負荷だと見なすイデオロギーにありました。第2に、世界はこれまで以上に開放的になり、相互依存が進んでいたこと。第3に、自己満足し、自らを過信した人類は、「悲劇は起こり得る」という感覚を失っていたこと。第4に、すでに20年以上にわたり、利己主義、偏狭な視点、他人の考えを受け入れない態度が幅を利かすようになっていたこと。世界は、軽薄、利己主義、不誠実、不安定で溢れ返っていました。第5に、おそらく最も重要であり、これまで列挙したすべてを物語る点として、世界から見捨てられた層の存在が挙げられます。世界人口の45%以上は満足のいく衛生設備を利用できません。著者は、「ようするに、すべてが非持続的であり、もはや許容しがたい状態にあると誰もが無意識のうちに感じていたところに、今回のパンデミックが発生したのだ」と述べます。
第3章「一時停止した世界経済」では、新型コロナウイルス感染症による医療面の津波を押しとどめるための解決策は、われわれが知る通り、ワクチンと治療薬の開発であるとして、著者は「その間、大規模な都市封鎖を避けるには、マスクの着用、検査の実施、感染経路の追跡調査、感染が疑われる者の隔離を行うことになる。一方、経済危機という津波をどうやって押しとどめればよいのかは、よくわかっていない。というのは、これは人類が自己決定により招いた危機であり、過去の経済危機とは性質がまったく異なるからだ。つまり、これは金融経済ではなく実体経済の危機なのだ。その大きさは計り知れない。いまだにほとんどの人がこの危機のあまりの深刻さと多面性について把握できていない」と述べています。
「現実否認:孤立経済」では、パンデミック下の各国においては、以下の社会の機能を維持するのに必須の立場の人々しか就労できなかったとして、「医療、軍、警察、警備業、道路管理業、運送業、食料品販売業、農業、食肉処理業、食品加工業、漁業、エネルギー産業、衛生管理業、水事業、テレコミュニケーション事業、IT事業、宅配業、そして、最低限の公共交通機関と公共事業だ(職人のように、少人数で働く職業も就労を続けられたかもしれない)。これらの職業部門では、国によって就業者の30%から40%ほどが働いている。だが、社会は彼らの働きに対して充分な感謝の念を示していない」と具体的な職業名を列記しています。わたしは、それに葬祭業を加えるべきだと思いますが。
また、先述以外の業種の工場、作業場、工事現場、商店は閉鎖されたとして、著者は「学校、大学、レストラン、美容室、バー、ホテル、画廊、映画館、劇場、コンサート会場、スタジアム、会議場、航空機、クルーズ船、スポーツクラブも閉鎖された。これらの業界で直接的および間接的に働く人々は失業を強いられる。ガソリンスタンドのように顧客の足が遠のくことによって閉鎖に追い込まれる場合もある」と述べます。残念ながら、結婚式場はこちらのグループに近いと思います。
「奈落の底」では、「副次的な影響」として、企業では、顧客だけでなく、事業を維持するための運転資金や資本が不足し、倒産が続発する恐れがあることを指摘し、著者は「たとえば、旅行会社、航空会社、クルーズ船の運営会社、ホテル、レストラン、舞台芸術や興行会社が代表的だが、さらには、自動車会社、繊維会社、航空機製造業者、水上レジャー産業の会社、化粧品会社、ぜいたく品の会社など、他にも多くの企業が影響を受けるだろう。反対に、危機に乗じて売り上げが増えた製品、雇用を増やした産業、業績を伸ばした産業がある。たとえば、一部の治療薬、医療機器、衛生用品、基本的な食料品、宅配業、物流業、視聴覚メディア、オンラインの娯楽、インターネット通販、オンラインチャット、出会い系サイト、オンライン会議用アプリ、家庭用品の修理業、中古品販売業などだ」と述べます。
第4章「国民を守り、死を悼む政治」の「政治の重要な役割:国民を守る」では、今回のパンデミックにおいて、政治は機能しなくなり、その役割を果たせなくなったとして、著者は「死を悼む儀式は、親愛なる人とのつながりを確固たるものにし、人生と離別に意義を付す。この儀式は、太古からきわめて重要だったが、われわれはこれが解体されるのを目にしてきた」と述べています。大いに同意したい一文です。また、「死を悼む」として、著者は「この陰鬱な時期にもよいニュースがあった。世界中で、これまで以上に多くの人々が覚醒したのだ。孤立社会はもはや持続的でないのではないか。パンデミックを口実に全体主義の社会へ、そしてこれまで以上に不当な扱いへと国民を導くのはおかしいのではないか。政治指導者の選出や政策決定の過程は完全に時代遅れなのではないか」と述べます。
死を語ることもできず、また語ろうともしない政治指導者に対する国民の怒りは煮えたぎっていたという著者は、「いつの時代においても権力の源泉は、安全の追求に次いで、死に対する恐怖にあるからだ。政治と国民の関係の基盤、あるいはその根底にあるのは、死を悼む儀式だ。〔犠牲者の急増、二次感染への不安、犠牲者や家族への偏見などにより〕その儀式が維持できなくなったのだ。この危機が発生して以来、政治討論の場で国民の死が語られることはないとしても、非常に多くの国において政治不信を招いたのは、こうした政治家の態度が原因だと私は睨んでいる。だからこそ、ますます多くの人々がよき人生のあり方を新たに形づくるために己の死を自分自身で管理しようとしているのだ」と述べます。
第5章「最悪から最良の部分を引き出す」の「死を覆い隠す:気を紛らわせて生きる」では、自宅待機令発動中に起きている言語道断の出来事の1つは、近親者の臨終に立ち会えないことであるとして、著者は「この状況は今も続いている。一部の国では葬儀にさえ列席できない。このような事態が再び起きないように全力を尽くそうと誰もが心に誓っている。人間関係においてきわめて重要な瞬間である死に際が覆い隠されてしまわないように。しかしながら、臨終に蓋をするこうした行為は、突発的な出来事、いわば人類史における挿話ではなく、眩暈を催す不可避の変容へと向かう一歩なのだ。将来、この変化は甚大な影響をもたらすだろう」と述べます。
また、「日常生活から締め出される死」として、死に意味を与えること、あるいは課すことができなければ、どんな社会構造も不適切であり持続不可能だと訴える著者は、「これまで順に、宗教的、軍事的、社会的、医学的、科学的な意味が死に付与されてきた。だが今日、こうした説明は不充分になった。死の正体は生と同様、不可知の謎だと判明したのである。また、死に意味を付すことの難しさ、そして死が意味をもたないと認めることのさらなる難しさを前に、われわれの社会はこっそりと少しずつ死を隠蔽するようになった」と述べます。
自宅で息を引き取ることはなくなり、人々は死者についても死についても語ることがなくなったとして、著者は「自身や他者の死について考えないために、死に際の光景を見ないために、高齢者施設で暮らす年長者の存在を忘れ去るために、ありとあらゆることが行われている。すべては、暮らしのなかでつねに気を紛らわせ、ほんのわずかな瞬間であっても、独りで思索に耽ることがないようにするためだ。よって、自宅待機中に起きた出来事は、それまでの平和な暮らしを破壊する破廉恥な変ではなく、以前から定着していた、死者と瀕死の者に蓋をするという行為の発展型なのだ」と述べます。
さらに、「ヴァーチャルに徘徊する死者」として、著者は「近親者の死に蓋をすることによって死を断固否定しながらも、彼らの生前の姿を残しておきたい人々を対象に、新たな市場が生まれるだろう(すでに出現しつつある)。亡き者のヴァーチャルな姿を生者に売りつけるのだ。死者との会話、写真、ビデオ、手紙のやりとりなどに蓄積されているデータを、今後さらに高性能になる人工知能(AI)が分析することによって、死者がメールに返信し、ソーシャルネットワークにメッセージを発信し続けることができるようになる。近い将来、亡き者はホログラムとなってヴァーチャルな暮らしを送るようにさえなって、生者の暮らしに加わることだろう。その実現は遠くない。初期のうちは生き写しとまではいかないかもしれないが、いずれ本物と見紛う人物として生者の日常生活に登場するようになる」と述べています。
こうした技術に投資するのは、近親者の存在を残しておきたいと願う生者、あるいは死者たち自身かもしれないとして、著者は「後者の場合、自身のヴァーチャルな分身を死後に維持することだけが使命の財団に、遺産の大部分を寄贈する。死後の管理業務は独自の大市場を形成するようになるだろう。亡き者の存在は商売のタネの1つになる。死後の世界を準備するためだけにこの世を過ごす者も現れる。彼らは自身のデータをホログラムに移し、エネルギーを浪費するだろう」と述べるのでした。
「マスクの起源」では、すべての日用品には、歴史、系譜、存在理由があり、これらを探ることはこの上ない知的刺激に満ち溢れているとして、著者は「目立たない釘、やかましいトンカチ、巧みに書かれた本、忠実に仕事をこなす洗濯機、馬力のある自動車、魔法のような力でわれわれを魅了するコンピュータなどの歴史、系譜、存在理由は、多くの哲学者、歴史家、経済学者、社会学者よりも、われわれの社会について多くのことを物語る」と述べています。
非常に古くからある日用品で、現在、再び脚光を浴びているのがマスクです。著者は、「今日のマスクの存在意義を理解するには、他のモノの場合と同様、歴史を紐解く必要がある。歴史を振り返ると、マスクは、死、そして不死の探求を意味するモノの一例であり、典型だとわかる。人間は互いを愛さないからこそ、新たな存在をつくり上げるため、自己を超越するため、他者になりすますためにマスクを着ける。他人を愛していないからこそ、存在する権利をもつ者、あるいは不死身となる権利をもつ者だけがマスクを着ける。マスクが存在するのは、人間としての顔があるときだけだ」と述べます。
また、「歴史上に存在した数々のマスク(仮面)」として、著者は「人類初のマスクは、エジプトのミイラの仮面だ。ミイラは仮面によって永遠への道のりを歩み始める。次に登場するのは、アフリカの儀式で使われる仮面だ。このマスクの役割もまた、あの世とのつながりを生むことだ。だが、エジプトのミイラと異なり、アフリカの儀式で仮面を着けるのは死者でなく生者だ。マスクを着ける生者は、神や半神など、いずれも超人的な風貌を得て、多くの場合、踊る。太古の時代から長きにわたり、踊りに興じるのはマスクを被る者たちだけだった」と説明します。
さらに、儀式が影響力を失うと、マスクは古代ギリシアの劇場や日本の能など、演劇の場で用いられるようになるとして、著者は「こうして、普遍的な人物の特徴を偉大に見せ、ゆがめ、称揚するようになり、仮面を着ける人物の特徴は消え去る。フランス語の「人物(personnage)」や「人(personne)」という単語の語源は、古代ギリシア語で顔や仮面を意味する「プロソーポン(prosōpon)」だ。次に、儀式におけるマスクの役割は、謝肉祭とともにさらに低下する。謝肉祭のつかの間、人々は人格を変え、別人になって自身の境遇や死の状況から逃れることができる。その後、個人はさらなる自由、自立、率直さを得るようになった。そして、自身の偶像に命を残そうとする最後の試みであるデスマスクが登場する」と述べます。
マスクは、帽子、かつら、化粧、そして美容整形へと姿を変えました。これらもマスクと同様に死の否定を意味します。「没個性の医療用マスク」として、著者は「17世紀末以降のパンデミックの際に着用を課されたマスク〔「瘴気」を防ぐために薬草を詰めたくちばし状のマスクは〕、他の時代のどのマスクよりも死と密接なつながりをもつ。このマスクの目的も死期を遅らせることだ。このマスク名儀式を重んじる。それは司祭に代わって死とのつながりを司る新たな統率者である、医師が課す儀式だ。医師は率先してこのマスクを着用するようになった」と述べています。
「未来の企業像」では、「過小評価されている職業:看護師、清掃員、レジ係、教員」として、著者は「今回の危機により、一部の職業の重要性が、多くの人の間で認識されるようになるのではないか。たとえば、これまで注意を向けられてこなかった看護師、清掃員、レジ係などの職業だ。そして多くの親たちがようやく、学校の教師は苦労の絶えない職業だと気づくようになるのではないか」と述べます。わたしは、これに葬儀のサポートをする葬祭スタッフを加えるべきであると思います。彼らの社会的役割はきわめて大きいと言えるでしょう。
続けて、著者は「人々がこうした認識をもち続けられるようにするには、称賛したり感謝の念を示したりするだけでなく、これらの職業の賃金を上げ、労働の手段や環境を整備し、雇用を増やす必要があるだろう。こうした業務に従事しているのが公務員なら、さらなる税金を投入すべきだ。それは税金の使い道として申し分ない。民間の枠組みで運営されているのなら、これらの職業はすばらしい大市場をつくり出すだろう。これは企業と民間資本の双方にとって利益と成長の源泉になるはずだ」と述べています。また、「企業の新たな評価基準」として、著者は「企業が優秀な人材を保持するには、社員の仕事に意義を付与することが何よりも重要だ」と述べますが、まったく同感です。わたしは、まったく同じ考えで、わが社を経営してきました。
「企業は居心地のよいホテル」では、企業もホテルのような存在でなければならなくなるという考えが示され、その理由として、著者は「企業の組織形態は、パンデミックによるテレワークの推進によって一変した。企業の組織形態が過去の状態に戻ることはないだろう。1つめの理由は、パンデミックが終息とは程遠い状態にあるからだ。完全な都市封鎖の決断が新たに下されることはないとしても、多くの従業員はデスクがびっしりと並ぶ職場に戻って働くリスクをとりたがらないはずだ。2つめの理由は、パンデミックにより、複合型経済(サービス部門がGDPの70%にまで達することもある)では大半の業務はテレワークでこなせることが明らかになったからだ。2035年には少なくとも10億人がテレワークで働くという見通しさえある」と述べています。
また、「テレワークの弊害」として、著者は「テレワークがあまりに広く浸透して一般化したり、オフィス外でのフルタイム就業が長期化したりするようになると、われわれは、それが企業と従業員の双方にとってよくないことだと気づくだろう(企業にとっては、従業員は自己愛に満ちた不誠実な傭兵のような人物だけになってしまい、力を合わせて働く協力者がいなくなってしまう。従業員にとっては、外出したり、同僚と意見を交換したりする機会が失われる。そして、従業員はテレワークで孤立しているので解雇されやすいと思い、企業の価値観に違和感を覚えるようになる)。結果として、社内のあらゆる階層でテレワークを導入しすぎる企業は、社員で共有すべき企業精神、事業計画、固持すべき価値観を維持できなくなり、消滅するだろう」と推測します。
続けて、「観光業のノウハウを活かす」として、企業を守るには次の2つのことをなすべきだとして、「1つめは、従業員が企業への帰属意識を感じられるようにする方法を探すこと」と述べます。そのためには、共通の価値観を練り上げ、従業員が誇りをもって取り組める、短くとも10年単位での計画を打ち立てることが必要です。そして、「2つめは、職場、とくに本社を、従業員が働きやすい雰囲気にすること」と述べます。より具体的に言うと、従業員に出社したいと思わせるためには、社内のレストラン、会議室、作業場は、居心地のよいホテルのような雰囲気にすべきだといいます。
これはパンデミックで壊滅的な被害を受けた観光業にとって新たな市場になるだろうとして、著者は「観光業には企業の本社やサービス産業の職場を改装および新設するためのノウハウがある。同様に、観光業は、患者とその家族を丁重に迎える快適な環境を提供するなど、病院のサービス向上にも貢献できるだろう。また、ホテル業のノウハウは高齢者施設の開発にも適用できる。高齢者施設が実際のホテル業界のノウハウから得られるものは多岐にわたり、さらには、供給過剰のホテルを高齢者施設に転用することも考えられる」と述べるのでした。
「時間の新たな利用法:自ら行動する」では、結局のところ、この危機の最中にわれわれが真っ先に悟るのは、大切に扱うべき唯一のものは時間だということではないかとして、著者は「時間、それも心地よい時間こそが、本当に稀少かつ価値をもつということだ。日々の時間は、不安や浅はかなことに費やすべきではない。個人の時間は、健康のために投じる資源を増やすことによって引き延ばすべきだ。学んだり自分自身を見出したりするためにより多くの時間を割くこと、つまり、『自己になる』姿勢を模索することによって、個人の時間はこれまで以上に豊かになる。働く時間は、単に稼ぐためでなく、創造的であるべきだ。そして文明の時間は、自分以外の全人類、現在および将来を生きる人々に対し、まったく新たな姿勢で臨むことによってしか保全できないだろう」と述べています。
第6章「命の経済」では、われわれは、組織構造、消費、生産の形態を抜本的に見直す必要があるとして、著者は「われわれの社会は、経済活動を新たな方向へと誘導しなければならない。すなわち、生産がこれまで著しく不足していたが、生活に必要不可欠だと判明した部門へと経済を導く必要があるのだ。1つめは、パンデミックとの戦いに勝利するために必要な部門だ。2つめは、パンデミックによって必要性が明らかになった部門だ。これらはともに、この先発展させていくべき経済活動を構成する。本書において私はこれらの部門を『命の経済』と命名する」と述べています。
「『命の経済』への転向」では、「命の経済」以外の部門で活動する企業を転換させることも必要だとして、著者は「企業は現在、自分たちの市場が過去の活況を取り戻すのを待っているが、それは幻想だろう。自動車、航空機、工作機械、ファッション、化学、プラスチック、化石燃料、ぜいたく品、観光などの部門で活動する企業が過去の市場を取り戻すことはないだろう。たとえワクチンと治療薬が今すぐに見つかったとしても、あるいはパンデミックが自然消滅したとしても、あらゆる物事が均衡を取り戻すには少なくとも2年はかかる。そのときまでに、これらの企業の多くは死に絶えるだろう。そして消費者は別のモノを欲しがるようになる」と述べるのでした。
第7章「パンデミック後の世界はどうなる?」では、「サイエンス・フィクションから学ぶ」として、パンデミックのような出来事を予測して阻止するには、単なる見通しを超えて、あらゆる想像力を駆使しなければならないことを指摘し、著者は「過去から教訓を見出して同じ出来事の再来に備えるだけでなく、予期せぬ未知の出来事への備えも必要だろう。そうした準備には通常の数値分析よりも、突拍子もない分析のほうがはるかに役立つ。つまり、経済学の入門書よりもサイエンス・フィクション(SF)のほうが有益かもしれないのだ」と述べています。まったく同感です。
サイエンス・フィクションの多くの書籍や映画は、昔から人類にとっての脅威を語り、われわれに未来を占う手段を提供してきたとして、著者は「サイエンス・フィクションを通じて、私は枠にとらわれずに考えることを学んだ。意外なところに光ある道筋と闇の道筋を探すことを学んだ。また、私はサイエンス・フィクションを通じて、最悪の事態を避ける最良の方法は備えること、そして愛することだと気づいた」とも述べています。
そして、「未来へ向けて:儚くもすばらしい命を生きる」では、死の恐怖ではなく、生きる喜びのなかでこれらのことを考えるとして、著者は「1つ1つの瞬間を快活に生きる。われわれは全員が死を宣告された存在である。その顔には死刑囚の笑みが浮かぶ。その心は、未来を可能にする人々への感謝に包まれ、惨事に対して充分な備えのある世界をつくろうとする大志に満たされる。間違いなく不可避であるこれらの惨事に対し、準備が万全であるがゆえに、事前の不安も、渦中での心配も必要がなくなる世界をつくるのだ。われわれ自身、われわれの子供たち、われわれの孫たち、そしてその孫たちのために」と述べるのでした。
本書は、欧州を代表する知性が語っただけあって、非常に読みごたえがありました。博覧強記の著者の発言は勉強になるだけでなく、とても面白いです。特に、予期せぬ未知の出来事への対応は、経済学の入門書よりもサイエンス・フィクション(SF)のほうが有益であるという指摘はまったく同感で、嬉しくなりました。
