- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2021.04.13
『この1冊、ここまで読むか!』鹿島茂著(祥伝社)を読みました。「超 深堀読書のススメ」というサブタイトルがついています。カバー表紙には著者である鹿島氏の対談相手(ゲスト)の名前と取り上げた本の書名が記されています。フランス文学者で、ALL REVIEWS主宰者の鹿島氏と各章のゲストが、ときにははみだし、ときには関連書籍を出しながら、深掘りの読みを展開しています。
 本書の帯
本書の帯
帯には、「書評サイト『ALL REVIEWS』限定公開の対談書評 待望の書籍化!」「知の巨人たちが選んだ”今読むべき”ノンフィクション」「関連図書も紹介」と書かれています。著者は、です。
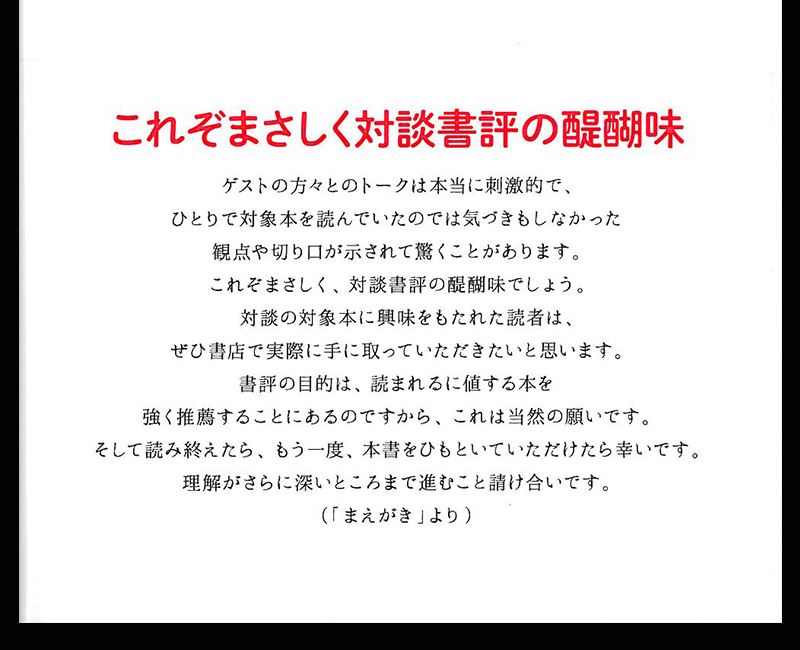 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、「これぞまさしく対談書評の醍醐味」として、「ゲストの方々とのトークは本当に刺激的で、ひとりで対象本を読んでいたのでは気づきもしなかった観点や切り口が示されて驚くことがあります。これぞまさしく、対談書評の醍醐味でしょう。対談の対象本に興味をもたれた読者は、ぜひ書店で実際に手に取っていただきたいと思います。書評の目的は、読まれるに値する本を強く推薦することにあるのですから、これは当然の願いです。そして読み終えたら、もう一度、本書をひもといていただけたら幸いです。理解がさらに深いところまで進むこと請け合いです。(「まえがき」より)」と書かれています。
カバー前そでには、以下のように書かれています。
「これを読んでいると、ある企業の戦略や競争上の強みというのは、成功した現在の姿だけを見ていてもわからないということをつくづく感じますね」――楠木建(第1章『NETFLIX コンテンツ帝国の野望』)
「人間は100メートル走ではほかの動物より遅いけど、それより長距離歩けることが生き残る上で大きかったんだ」――成毛眞(第2章『絶滅の人類史』)
「孔子のいう『礼』は鹿島さんがおっしゃるとおりで、平たくいえば、差別化戦略です」
――出口治明(第3章『論語』)
「ノンフィクション・ライターとしてのマルクスの手腕は天才的」――内田樹(第4章『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』)
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「まえがき」鹿島茂
第1章 楠木健×鹿島茂
『NETFLIX コンテンツ帝国の野望』
――戦略のヒントが詰まった1冊
第2章 成毛眞×鹿島茂
『絶望の人類史』――なぜ人類は生き延びたのか?
第3章 出口治明×鹿島茂
『論語』――世界史から読む
第4章 内田樹×鹿島茂
『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』
――ジャーナリスト、マルクスの最高傑作
第5章 磯田道史×鹿島茂
『日本を襲ったスペイン・インフルエンザ』
――記録は命を守る
第6章 高橋源一郎×鹿島茂
『9条入門』――憲法と戦後史を改めて考える
「まえがき」の冒頭を、鹿島氏はこう書きだしています。
「私は2017年の7月から、新聞、週刊誌、月刊誌などの活字メディアに発表された書評を再録するインターネット無料書評閲覧サイト『ALL REVIEWS』を運営しています。創設の動機の1つは、遠い将来、紙の本というものが一切、出版されなくなり、古本として残された本も廃棄される運命にあるのではないかと強く危惧したことにあります。これまでに出版された本は無限にありますから、デジタル情報として残すべき価値のある本と、それ以外の本をトリアージ(命の選別)にかけなければならない日がくることは目に見えています」
そのトリアージの際、デジタル情報として、ある本の書評が残っていれば、その本は保存すべき価値のあるものと認められて救われることになるそうです。しかし、反対に書評がいっさいなければ(あるいは書評が書かれていても、それが発見できなければ)、その本は価値を認められずに永遠に忘却の淵に沈んでしまうに違いないとして、鹿島氏は「実際、文学賞や学芸賞の一次選考では、書評のあるなしがふるい落としの基準になっているのです」と述べています。この一文には、非常に感銘を受けました。ここには、書評の意義というものが示されています。125万部の発行部数を誇る「サンデー新聞」に連載中の「ハートフル・ブックス」で、150冊を超える本の書評を書き、書評サイト「一条真也の読書館」では2000冊以上の本のレビューを書いたわたしのハートにヒットする内容でした。そして、いま、本書の書評も書いているわけです。
第1章では、一橋ビジネススクール教授の楠木健氏が取り上げた『NETFLIX コンテンツ帝国の野望』ジーナ・キーティング著、牧野洋訳(新潮社)をめぐって対談が行われます。楠木氏は、「1つの作品に何百ものタグを『人力』でつける」では、「ネットフリックスが何を見ているかというと、いまの人々が、ストリーミングになって以降、どういう作品を選び、それをいつ、1回あたりどれぐらいの長さで見ているかといったことです。しかも、どこでポーズをしてどこで巻き戻して、その次にどこで視聴を止めるかといったことまで、すべて日常的にデータ収集しているわけですよね。それによって、いわば二重の意味で後出しジャンケンをしているわけですよ」と語ります。
そういうデータを集めると、ある俳優にものすごく食いつきのいい固定ファンがいるとわかるだけではなく、その俳優の作品が出たら何人ぐらいが見るのかも予測できるとして、楠木氏は「そうやって何から何まで分析すれば、主演も監督も物語のタイプも最初から売れるように組み立てて映画を制作できるわけです。昔から映画は典型的な興行世界で、山師みたいな人の勘に頼って『当たるか当たらないか』とやってきましたが、ネットフリックスのやり方だと後出しジャンケンができる。もう1つの後出しじゃんけんは、その映画ができたときに、きっと見てくれるだろうと思われる人に向けてピンポイントでガンガン推していけるということですね。これが、リスクを抱えていた従来の映画興行とまったく違うところです」と語ります。
ネットフリックスのアルゴリズム戦略について、鹿島氏が「たとえばアマゾンで本を買うと、すぐに『これもどうですか』とレコメンデーションしてきますけど、なんか違うんだよなぁと思うことが多いですよね(笑)、全然こっちの趣味を読み取ってくれていない。それをちゃんと読み取れる方法を考えることができたのは、やっぱり創業者の根がオタクだったからでしょうね」と言えば、楠木は「これはもう、アルゴリズムで回すデータの量が多ければ多いほど精度が上がりますからね。アマゾンとの違いは、ネットフリックスはすべて映像コンテンツなので、『♯後半に山場あり』とか『♯いきなりハラハラドキドキ』とか無限にタグがつけられるので、やりやすいですよね」と語ります。
また、楠木氏は「本ではなかなかそうはいかないと思いますし、洋服のような商品で、も難しいので、やはり映画コンテンツという商品のジャンルと経営手法がうまくフィットしたのが大きいと思います」とも述べます。そして、鹿島氏は「いまはハリウッドの映画製作自体がアルゴリズムになってますね。ありとあらゆる過去の映画をタグ付けみたいな形で分析して、演出や撮影方法も非常にアルゴリズム的になっている」と語るのでした。この対談を読むと、ネットフリックス大成功の秘密がより深く理解できます。
第2章では、書評サイト「HONZ」代表の成毛眞氏が取り上げた一条真也の読書館『絶滅の人類史』で紹介した分子古生物学者の更科功氏の著書をめぐって対談が行われます。「辺境ほど古いものが残る」では、成毛氏が「これはユヴァル・ノア・ハラリの説ですが、ホモ・サピエンスは複数の大集団がネットワークを作るのに対して、ネアンデルタールはそれぞれが孤立した集団で生きていた。それが槍投げの機械を含めた決定的なテクノロジーの差になるんですね。ネットワークがあれば、一人が弓を見つければすぐに1万人に広まるでしょう。しかしネアンデルタール人は、自分の集団にいる30人ぐらいにしか伝わらない。だとすれば、これは決定的な差を生む可能性があります」と述べます。
すると、それに対して、鹿島氏は「そうですね。人類は何かを発明すると、あっという間に全員が持つようになる。言葉や文字もそうです。このことは逆に言うと、いろいろな辺境の文明が崩壊したというジャレド・ダイアモンドの最近の研究ともかなりクロスしてきます。たとえばイースター島の文明がなぜ滅びたか。いろいろな影響があったけれども、孤立していたのが大きいわけです。孤立している集団は絶滅しやすい」と語っています。
「役に立たない基礎科学こそ実は役に立つ」では、成毛氏が「地学や人類学、物理学などは基礎科学じゃないですか。目の前の現実社会では全然役に立たないんですよ、こんなものは。しかし、この役に立たない基礎科学こそが人類にとってもっとも大事だったことは、ギリシャ文明以来3000年の歴史が証明しているわけです。政治学や経済学みたいな学問は、役に立つようでいながら、そのじつ社会の足を引っ張ることもある。マルクス経済学などそのよい例です。ところが基礎科学は、たとえば100年前に量子力学と相対性理論が生まれなかったら、スマホが生まれていないんです。量子力学がなければ、この中に入ってる半導体は存在しません。リチウムバッテリーもない。相対性理論がなかったら、GPSもうまく稼働しないんですよ」と語ります。
続けて、成毛氏は「100年前に量子力学ができたときは『こんなもん何の役に立つんだ』といわれたでしょう。相対性理論も、当初は東大の先生が『世界で4人しか理解できない』と紹介したらしい。そのぐらい役に立たないと思われていたのに、いまやこれがなければ社会は19世紀のままだった。そういう基礎科学の分野の本を一般読者が読むようになったのはいいことです。一般的な興味が高まれば、政府からも民間からもそういう研究にお金が行き渡るようになって、結果的に100年後の人類がより良くなるという気がしますね」と語っていますが、非常に示唆に富んだ発言であると思います。
第3章では、立命館アジア太平洋大学(APU)学長の出口治明氏が取り上げた『論語』をめぐって対談が行われています。現在、NHK大河ドラマの「青天を衝け」が放映中ですが、主人公の渋沢栄一は「論語と算盤」で有名な人です。フランス文化を研究する鹿島氏がパリ万国博覧会について調べているうちに、1867年万博のところで渋沢栄一の名前を見つけたそうです。鹿島氏は、「万博に日本からはるばるやってきた徳川昭武一行に、彼が会計係として入っていたんです。そこで僕は、日本の資本主義が明治に成功したのは、もしかしたらサン=シモン主義の影響が渋沢栄一を経由して日本に入ったからではないかという仮説を立てました」と述べています。
その仮説の証明をするために『渋沢栄一』という本を書いた鹿島氏は、「渋沢栄一という人物は、サン=シモン主義だけでは理解できません。彼の中にもう一つあったのが『論語』です。『論語』のエートスや倫理観を理解できなければ、渋沢の資本主義も理解できないというわけです。そこで『論語』を読み返してみたというのが、今日、『論語』を取り上げることになった一つのきっかけです。僕なりに理解すると、渋沢栄一は、お金儲けを卑しいものとする朱子学の考え方をぶち壊したかったということです。朱子学的価値観では資本主義は発展しない。自分の利益のみを追求しないかぎり、お金儲け自体は卑しむべきことではない、それどころか社会に貢献することであると証明したかったんです」と述べています。
続けて、鹿島氏は「そのために、彼(渋沢栄一)は『論語』を読み直しました。二松學舍大学の創設者でもある三島中洲さんという偉い論語学者について、一から勉強したんですよ。そして最終的には、利益を求めるときには、その利益が自分の与えたサービスとちゃんと釣り合っているかどうかがいちばんの問題だと理解しました。要するに、暴利じゃなければ、お金儲けをしてよい。孔子先生は、それがなければ国は成り立っていかないと言っている。これが、渋沢による資本主義のための『論語』解釈なんですね」と述べます。
これは、実のところサン=シモン主義とかなり近いと指摘し、鹿島氏は「僕なりに解釈すると、ちょっと資本主義に傾いた社会民主主義がサン=シモン主義ではないかと思うんです。ですから、『暴利を貪ってもOK』という英米型の資本主義とは違う。渋沢の求めていた資本主義も暴利を否定しますから、親和性があるんです。渋沢がサン=シモン主義を知っていたわけではないのですが、渋沢は、第二帝政とパリ万博で現実化されたサン=シモン主義をモノとして、あるいはシステムとして目撃したことで、これと似た資本主義を模索するために『論語』を援用したわけです」と述べるのでした。
これに対して、出口氏は開口一番、「荒っぽくいえば、渋沢はルターのような人だったと思います」と言った後、「ローマ教皇に疑問を抱いたルターが聖書に立ち返ったように、明治政府が天皇制とイエ制度をセットにネーションステートを創ったときに朱子学を大いに活用したわけですが、渋沢は孔子に立ち戻って『論語』を読んだ。原点に立ち返ることで商売の大事さを再発見したと考えればわかりやすいんじゃないですか」と語ります。
「中国社会はなぜ流動性が高いのか」では、出口氏が「ヨーロッパよりも広い中国をエリート官僚がコントロールするのは容易ではありませんが、それができたのは漢字と紙があったからですね。たとえば伝言ゲームでは5人ぐらい後になると中身がめちゃくちゃに変わってしまいますが、紙と漢字があればきちんと伝えられます。『始皇帝はこう指示した』と紙に書けば、全国津々浦々まで広めることができる。中国は漢字と紙のおかげで、文書行政による統技術がめちゃ早くに確立したのです」と語ります。
しかも「法家」という流派がいて、法治国家の概念を作り上げたから、イデオロギーだけでなく法律によって「一君万民」の体制を実施できるようになったことを指摘し、出口氏は「そのあたりが世界の中で中国は群を抜いて早い。『出鱈目もいい加減にせい、紙は紀元105年ぐらいに蔡倫が発明したんやないか』というツッコミが入りそうですが、蔡倫は紙を完成させたのであって、発明したわけではありません。始皇帝の時代にも、紙の祖形が豊富にあったのです」と述べています。
さらに、中国の場合、流動性の高い社会に一君万民の体制ができてしまったので、封建領主のような中間的な指導層がいないとして、出口氏は「中間層のリーダーがいれば、ひょっとしたら優しい殿様が村民を可愛がってくれるかもしれません。あるいは、ギルドのようなものが強ければ人々を守ってくれることもあるでしょう。ところが中国は殿様もいなければ、ギルドの力も弱いので、市民を守る仕組みが何もないんですよ。中間的な自治体制がないから、中国の人々は人間関係で自らの身を守るのです。いちばんわかりやすいのが一族や秘密結社ですよね。そういう点で、中国社会は国を治めるロジックも民のロジックも、ヨーロッパやその他の地域とはかなり違う、とても変わった地域なんです」と述べるのでした。
「中国社会に孔子が登場した背景」では、出口氏は「そういう社会で、なぜ孔子のような人が生まれたのか。これには2つの説明があります。1つは、ヤスパースが『枢軸の時代』と呼んだ紀元前500年前後にプラトン、アリストテレス、孔子、ブッダといった賢い人たちが世界中で生まれています。昔は『なんでこの時期に一斉に天才が現れたんや!』と不思議に思われていましたが、いまの歴史学では『地球が暖かくなったから』というわかりやすい説明がなされています。ちょうど鉄器が普及したのと同じ時期ですね。気候が温暖になって、鉄器が普及したので農業の生産性が急上昇した。すると食糧の備蓄ができるので、『賢い人は農作業しないで勉強しとったらええわ』という余裕が出てくる。だから天才が能力を発揮できたというわけです」と述べます。拙著『世界をつくった八大聖人』(PHP新書)で、わたしは「枢軸の時代」について詳しく書きましたが、「地球が暖かくなったから」聖人たちが輩出したというのは一理あると思いました。
紀元前771年に周(西周)が滅びました。出口氏は、「それまで金文職人は高給を約束される代わりに『よそに行ったらアカンで』と囲い込まれていたのですが、雇い主が滅んだら別のところで雇ってもらわなければなりません。そこで、周から青銅器をもらってありがたがっていた地方の王様のところに行って、『青銅器が作れます』『字の読み書きもできます』と売り込むと、雇ってもらえるわけです。そうやって、周に囲われていたインテリゲンチャたちが各地に散らばりました」と述べています。
戦国時代になるとさらに世の中が豊かになったので、このインテリゲンチャは2つに分かれたとして、出口氏は「1つは、役人になる人たち。『戦国の七雄』という王様に仕えて文書を書いたり、下っ端のほうは県庁に行ってその文書を受け取ったりするわけですね。その一方で、社会が豊かになったのだから、インテリとして格好いい言説を弄すれば養ってくれる人がきっといるだろう、ということで野に出ていく人もいるわけですね。この人たちが、諸子百家になった。孔子もその中から登場したわけです」と説明しています。
「『マナースクールの校長先生』としての孔子」では、「礼」の問題が取り上げられます。鹿島氏は、「『論語』を虚心坦懐に読んでも、やたらとしつこく言われる『礼』というものをどう考えたらいいのか、なかなかわからない。僕なりに『礼』を解釈すると、これは宮廷儀礼のこと。たとえば王様の次に偉い人は右に座るべきか左に座るべきかとか、本当ならどうでもいいことなんですが、それを格付けして『王様の左に座る人が偉い』といったことを決めるのが宮廷儀礼です。もともと、孔子先生はその指導者でした。礼儀作法を教える塾の塾長なんですね。僕の通勤ルートの途中にブライダルの専門学校がありまして、生徒たちがずらりと並んで『腰は何十度傾ける!』などと言われながらお辞儀の練習をさせられています。別のところにはセレモニーホールがあって、お葬式のやり方を教えたりしているわけですが、まあ、孔子先生もそういうブライダル兼セレモニー学校の校長先生だったと考えていいんじゃないかと思います」と述べています。わたしも、冠婚葬祭業者こそは孔子の精神的末裔であると考えているので、この発言には納得する部分がありました。
また、鹿島氏は以下のようにも述べています。
「ただ孔子先生は、どうもシャーマン系の占いや宗教みたいなものが大嫌いだったらしく、それを『淫祠邪教』などと蔑んでいるんですね。自分がやっているのはそういうものとは違う哲学的な意味があると考えていたのでしょう。それこそ「礼」にしても、単に知識として『左に座るほうが偉い』と教えるのではなく、哲学的な理由付けをした。『いまは形骸化しているから左右どちらが偉いか覚えればいいんだけど、もともとは左が偉い理由があったのだから、なぜそうなのか考えてみようじゃないか』といったことを、弟子たちに盛んに言うわけです。『論語』の最初のほうにも、『学んで思わざれば則ち罔し。思うて学ばざれば則ち殆し』という言葉がありますよね。知識を得たら、そこから理由なり、原因なり、わからないことを自分で考えてみよう、というのが孔子先生がやったことなんじゃないかと思います」
「『血統』と『礼儀』が社会を安定させる」では、出口氏が一般に「おばあちゃん仮説」といわれているものを紹介し、「本来、人間は動物なので、次の子孫をつくったらもう大人に用はないので、死んでいくはずなんですよ。ところが実際には、もう子孫を残せない年齢になっても長生きしています。昔は歯医者もありませんから、歯がボロボロになった高齢者に食事をすり潰して与えるのはすごくコストがかかるんですが、どういうわけか人間の寿命は長い。なんでそんなことになったのかというと、高齢者の経験(知恵)を活用することによって群れ全体が賢くなって、生き残る確率が高まるからです。そのために、生殖能力がなくなっても、ホモサピエンスは高齢者を長生きさせたというのが『おばあちゃん仮説』です。そういう面では動物とホモサピエンスは違うんですね。孔子のいう『礼』は鹿島さんがおっしゃるとおりで、平たくいえば、差別化戦略です」と述べています。
また、出口氏は「日本の古代の天皇制も、中世からやたらに有職故実が詳しくなりますよね。これに対して『そんな面倒臭いことはやってられん』と最初に抵抗した実力者が、平清盛でした。京都にいると儀式にばかり呼び出されるので、『これでは政治なんかできへん』ということで、福原に引っ込んだ」と述べます。一方、足利義満は儀式に対する考え方が清盛とは正反対であったとして、「彼は勉強が好きだったので、『面倒臭いけれど、いっぺん覚えてしまえばこちらの勝ちだ』と考えたんですね。『ガンガン礼儀を勉強しておれのほうが詳しくなったら、朝廷もいうことを聞くやろ』というわけです。日本の歴史の中では、儀式に対してこの2つのパターンがありました。清盛も義満も傑出した人物で、武家で太政大臣になったのは近世以前ではこの2人しかいません」と述べています。
さらに、出口氏は、「礼」といわれるもののかなりの部分は孔子が創ったと推測し、「彼が理想としたのは周公旦という周の大宰相で、孔子は、何度も『周公旦の夢を見た』と述べています。孔子が生まれた魯という国は周公旦の子孫が治めていたので、『自分の国の先祖はきっとこういう礼儀作法で諸侯を仕切っていたにちがいない』と考えたのでしょう。全部が創作だとは思いませんが、夢で見たものを自分なりに再構成したのが、孔子の『礼』だと思います。そのノウハウを諸侯に売ることで、自分の教団が食べていけるようにした。さまざまな諸子百家がお互いに差別化戦略を練る中で、孔子はそういう形で生き残ろうとしたのではないかと思います」と述べます。
「文献学者であると同時に哲学者になった孔子」では、直系家族についての特徴について、鹿島氏が「それは土地私有と結びついていることです。当たり前ですが、農地が私有でなければ、それを大切に子どもに伝えようなんて誰も思いません」と述べ、直系家族と土地私有が結びついて代々やっていくと、先祖崇拝、原始シャーマンが生まれるとして、鹿島氏は「孔子さんも、当初は半分ぐらい原始シャーマンでした。それが途中から変わったんです。直系家族的もしくは先祖崇拝的な狭い共同体のルール、一族が大きくなると『宗族』と呼ばれるもの――これは中国にまだありますけれども、孔子はたぶんそういうものが嫌だったので、そこからフィロソフィーに転換したんです。つまり、血統的な直系家族的なものに普遍性や一般原理を求めた。単に『じいさんのそのまたじいさん』という個々の話からドーンと飛躍して、殷や周、その前の夏という王朝にお偉い人がいたんだぞ、と。そうやって遠い先祖に飛んだのが、彼なりの一般化だったんですね」と述べます。
さらに、孔子がやったのは、ドイツ的な意味での文献学あるいは系譜学であると指摘し、鹿島氏は「文献学(系譜学)とは、単に昔の文献を調べるだけではありません。たとえばニーチェは『道徳の系譜』というすごく面白い本の中で、聖書の記述に混在している古い内容と新しい内容を見分けてるんですが、それがまさに文献学的な方法です。孔子のやった文献学もそれと同じようなものです。『詩経』や『易経』などに含まれている古いものと新しいものを見分けた。その意味で、孔子は文献学の元祖ともいえます」と述べています。
一方、出口氏は「自分は周の礼節を発見した」「太古のルールをすべて知っている」と売り込むためには、自分で昔の文献を集めなければいけないし、みんなにその内容の正しさを整合性のある形で説得できるようにしなければいけないと指摘し、「孔子は、それを広く売りに行けるよう、古いものや新しいものを整理し、どこの国でも通用する儀礼マニュアルを作って、弟子に教えていた感じですよね。孔子は、どこかの国の大臣になって、給与をもらおうとしていた節があります。そこに自分の弟子を連れていって、政治をやろうとした」と述べています。
しかし、どこの国でも、「たしかに立派な教えだが、うちの国ではイマイチやな」という話になってしまって、お払い箱になるとして、出口氏は「とりあえず話は聞いてくれるけど、みんな『こんなグループを雇ったら、えらい出費やな』などと思うんでしょうね。それで最後は孔子も大臣になるのは無理だと諦めるんですよ。その代わり、自分が勉強してきたことを体系化し、普遍化して、それを弟子に教えた。それを各国へ売りに行った弟子の中から、ひょっとしたらいつか大臣が出るかもしれないという思いもあったのでしょうね」と推測します。
そして、出口氏は「これは、意外にもプラトンと似ているんですよ」と言います。現実の政治は、海千山千の相手との駆け引きがあるとして、「時にはいうことを聞かない相手を脅したり、逆に頭を撫でたりもしなければいけません。それがプラトンにはできなかったので、最後はアカデメイアという学園を創って、そこで一所懸命教えることにした。そういう面では孔子とプラトンはよく似ています」と述べるのでした。孔子もプラトンも基本的に哲学者でしたが、彼らの哲学が後世の多くの政治家に大きな影響を与えたことは紛れもない事実です。
第4章では、「凱風館」主宰者で、思想家・武道家・神戸女学院大学名誉教授でもある内田樹氏が取り上げた『ルイ・ボナパルトのブリューメル18日』をめぐって対談が行われます。「ヨーロッパからアメリカに亡命した『四八年世代』」では、マルクスの書く政治ドキュメンタリーは非常に面白く、中でも『ブリューメル18日』は「ジャーナリスト」マルクスの最高傑作であると絶賛する内田氏は「リンカーンとマルクスが同時代人だったことに世界史の教科書を読んでいるだけでは気がつきません。でも、リンカーンの大統領再選のときに、第一インターナショナルを代表して祝電を送ったのはマルクスなんです。そして、リンカーンはそれに対して在英アメリカ大使を通じてマルクスに感謝の言葉を返している。アメリカとマルクスのあいだには深い因縁があるんです。南北戦争は人間社会はいかにあるべきかをめぐる思想的な戦いでもあるわけですけれど、北軍の思想の基盤形成にマルクスは深く与っています。いまのアメリカ人たちは、自分たちの国の歴史的転換点にカール・マルクスがいたという事実を絶対に認めないでしょうけれども」と語ります。
「ナポレオン3世がいなければ第二帝政はわかりやすかった」では、マルクスの盟友エンゲルスが『空想から科学へ』の中で空想的社会主義者としてロバート・オーエン、シャルル・フーリエ、サン=シモンの3人を取り上げたことを紹介し、内田氏は「その中のフーリエの弟子だったヴィクトル・コンシデランは、二月革命に『フーリエ派』としてかなりコミットしているんですね。そのコンシデランも、のちにテキサスに行きます。フーリエの理想郷であるファランステールを建設するために、集団で出かけたんです。それに対してサン=シモン主義のほうは、ナポレオン3世自身もサンシモニストでしたが、頭目のアンファンタンが同志を集めてアメリカではなくエジプトに行ったんです。そこでスエズ運河を通そうと言い出してね。サン=シモン主義は、ヒトとモノと金とアイデアを循環させることが富を生むという考えですから、東洋と西洋が分離しているのはよくない、東洋と西洋でヒトとモノと金とアイデアを循環させるには、スエズ運河を通してしまえばいいんだ、という話です」と述べています。基本的にマルクスは読まないわたしですが、彼の本がいかに面白いかを興奮気味に語る内田氏の発言を読んでいると、「そんなに面白いのなら、読んでみようかな」という気になりました。
第5章では、国際日本文化研究センター准教授の磯田道史氏が取り上げた『日本を襲ったスペイン・インフルエンザ』速水融著(藤原書店)をめぐって対談が行われます。著者の速水融は磯田氏の師ですが、歴史人口学の創始者でありながら感染症の本を書きました。「専門分野を超えたジェネラリストの多様な視点」では、磯田氏が「日本は『専門は何ですか』と聞く人が多くて、専門外のことを語ると批判する人もいますが、それは逆に面白がるべきです。『あなたは何が専門ですか』と問われたら、『いや、人間が専門です。私は人間としてやっているんです』というのが正しい姿。人を1つの専門分野に押し込めて、それに関する発言だけを求めるのは、豊かな社会のあり方じゃありません。それをやっていると脆弱になると思います」と述べています。
それに対して、鹿島氏が「そうですね。たとえば日文研(国際日本文化研究センター)を作った梅原猛さんは、本当にジェネラリストですよ。専門ばっかりやっていたら、梅原先生のような学者は出てきません。京都大学から多くのジェネラリストが生まれるのは、自由の学風のおかげなんでしょうか。あまりに効率ばかり追い求めて専門への特化を促すと、本当の意味での学問が生まれなくなります」と言えば、磯田氏は「実は速水先生のお父さんは京都大学の哲学科なんです。西田哲学とか和辻哲郎とか、京都学派の人たちには、分野を超えて、あらゆる知識を世界中から、あるいは時代を超えて収集してやるという姿勢があったと思います」と述べるのでした。
「博覧会と百科事典」では、鹿島氏が「あるとき、神田神保町の田村書店でパリ万国博覧会総目録が売られていたんです。すごく高くて、大学の研究室のお金ではとても買えない。そこで図書館の特別予算を使おうとしたら、主任の先生が『こんな本を買ってどうするんです? フランス文学の研究には何の役にも立たない。こんなものを買うなんて問題だな』と言うんです。そうしたら、その会話を横で聞いていた河盛好蔵さんが『面白いじゃないですかこれ。ぜひ買いなさい』とおっしゃってくれました。それで買ったんです。そこから僕の万国博覧会研究が始まり、第二帝政研究につながり、さらに渋沢栄一にまで来たわけです。資料との出会いとはそういうもので、何の役に立つかわからなくても、面白いと思ったら買う。こういう資料との出会いはとても重要ですね」と語っています。良い話ですね。
 百科事典を集めた実家の書庫
百科事典を集めた実家の書庫
また、鹿島氏は「博覧会には、すべてがある。これは百科事典もそうなんです。古い百科事典は誰も買わないので神保町でいちばん最初に捨てられちゃう本なんですが、これは百科事典というものを知らない人の態度です。というのも新しい百科事典を作るときには新しい知識を入れるから、その分、古い項目は削除されてしまうのです。古いことを調べるには古い百科事典じゃないとダメなんですね。たとえば渋沢栄一の実家は藍玉製造を仕事にしていたんですが、藍玉製造の方法のことはいまの百科事典には何にも出てこないですよ。だけど昔の、平凡社が最初に出した頃の百科事典にはちゃんと出ているんです。藍玉の製法とかね」と述べます。わたしも、百科事典をこよなく愛しており、古今東西の百科事典をコレクションし、一条真也のハートフル・ブログ「実家の書庫」に書いたプライベート・ライブラリーである「気楽亭」に収めています。
 実家の書庫に並ぶ『古事類苑』
実家の書庫に並ぶ『古事類苑』
いま、実家の書庫には『ブリタニカ』や『ラルース』の初版をはじめ、『ブロックハウス』『チェンバース』『アメリカーナ』など世界中の百科事典が集められています。
特に、日本のものは『和漢三才図絵』『嬉遊笑覧』『厚生新編』『日本社会事彙』から『古事類苑』『廣文庫』、そして現代のものまでほとんど揃っています。平凡社の『世界大百科事典』などは、初版以来のあらゆる版を神保町で揃えました。平凡社以外の百科事典もたいていは揃えていますが、中でもお気に入りは、小学館の『万有百科大事典』です。各巻が「日本歴史」「哲学」「文学」といったふうに専門事典として編集されているので、使いやすい。この事典には非常にお世話になりました。専門事典では、他に、吉田東伍の『大日本地名辞書』とか、諸橋徹次の『大漢和辞典』とか、吉川弘文館の『国史大事典』、小学館の『日本国語大辞典』、角川の『日本地名大辞典』など、全部で数十巻に及ぶものもカバーしていました。それらの事典類をながめながら、少年時代は「古今東西の全知識を自分のものにしたい!」という大それた、というより罰当たりな妄想を抱いていました。
「真の意味での『撲滅』は難しい」では、スペイン・インフルエンザから100年後のパンデミックである新型コロナウイルス感染症について語られます。磯田氏は、「新型コロナへの対処では、トータルでの超過死亡を減らすことを考えるのも重要です。その方法に、あらゆる知恵と能力と資源を使わないといけない。新型コロナウイルス本体での死者以外にも、たとえば経済的に追い込まれた人々が自殺するといったことも起きかねません。もちろん、一方で外出の自粛によって、交通事故死など一時的に減少するものもあると思います。また、みんながマスク着用や手洗いを励行したことで、インフルエンザによる死者は劇的に減るかもしれません。しかしその反面、新型コロナが流行っているせいで、病院に行くのを見合わせる人もいます。その結果、症状を悪化させたり、中には手遅れになるといった形での関連死が生じるわけです。そういう死者を減らすことも含めて、政策担当者は総合的に考えなければいけません」と述べるのでした。
第6章では、作家で明治学院大学名誉教授の高橋源一郎氏が取り上げた『9条入門』加藤典洋著(創元社)をめぐって対談が行われます。「ヴィシー政権と日本国憲法はどちらも『二重人格』だった」では、鹿島氏は「日本やドイツは明らかにあの戦争の敗戦国ですが、フランスは、勝ったのか負けたのか、被害者なのか加害者なのか、実はよくわからないんですね。戦争中に北半分をドイツに占領されて、南にそのヴィシー政権ができた。実際にはドイツの意向を忖度しているので、ユダヤ人虐待にも手を貸しているんですね。それを、とりあえずなかったことにしたんですよね」と述べています。
それに対し、高橋氏は「映画では、対独協力者を摘発して女性の髪の毛を剃るシーンなどがよく描かれます。それで、当時のフランス人はレジスタンスで戦ったという神話ができた。共産党もド・ゴールも戦った。ヴィシー? そんなのいたっけ? という感じで語ってきたわけです。要するに、記憶の捏造なんですね。フランスはレジスタンスによって勝った国だと思い込んでいるけれど、実は抵抗せずに対独協力したという暗部がある。それをごまかすことでフランスの戦後を作ってきたんだけれど、とくにアルジェリア戦争以降はそれが保てなくなってきた」と述べます。
「日本人の記憶の書き換え」では、高橋氏は「たとえば原爆についても、日本人は記憶の書き換えを行ないました。戦争中は日本も東大や京大で原爆の研究をしていましたし、極秘でもなかった。実は庶民も知っていたそうです。巨大新型爆弾を製造してアメリカに落とす、という小説が、1944年には何冊か出ていました。でも戦後は、広島・長崎の原爆について自分たちは無垢の犠牲者だと思いたいがために、原爆を研究して敵地に落そうとしていた記憶はなかったことになっている。本当は、ドイツも日本も研究していたけれども、残念ながらアメリカに先んじられたんです。被害者の顔をしているけれど、単に遅かっただけ。これも典型的な記憶の書き換えですよね」と語ります。
「『選び直し』か『書き直し』か」では、吉本隆明の『共同幻想論』を読み直すという連載をやっているという高橋氏が、「吉本さんが天皇制を正面から論じた本があるですが、そこで彼は、天皇制自体が日本人のメンタリティを規定してはいるけれども、その淵源とマッカーサーの受け入れは同じではないかと、すごいことを言っています。彼は、天皇制の始まりよりも前に遡った『源日本人』というものを想定するんですね。そして源日本人は、上から接ぎ木のように体制が生まれたときに、それがまあまあ良い支配をする体制なら『OKよ』と受け入れるような人々なのではないかと考える。だから、大昔に天皇制を受け入れたのと同じレベルで、マッカーサーを受け入れたのではないかというわけです」と述べるのでした。
本書には6人のゲストが薦める「関連図書」のコーナーもあり、わたしの読んでいない本、知らなかった本も多く、大いに興味を惹かれました。ネット全盛で読書人口は減る一方かと思いますが、本書に紹介されているような深堀り読書から得られる学びはネット記事から得られるそれの比ではありません。コロナによってさらに混迷を極めているこの世界を生きていくためにも、わたしはこれからも読書を続けていきたいと思います。
